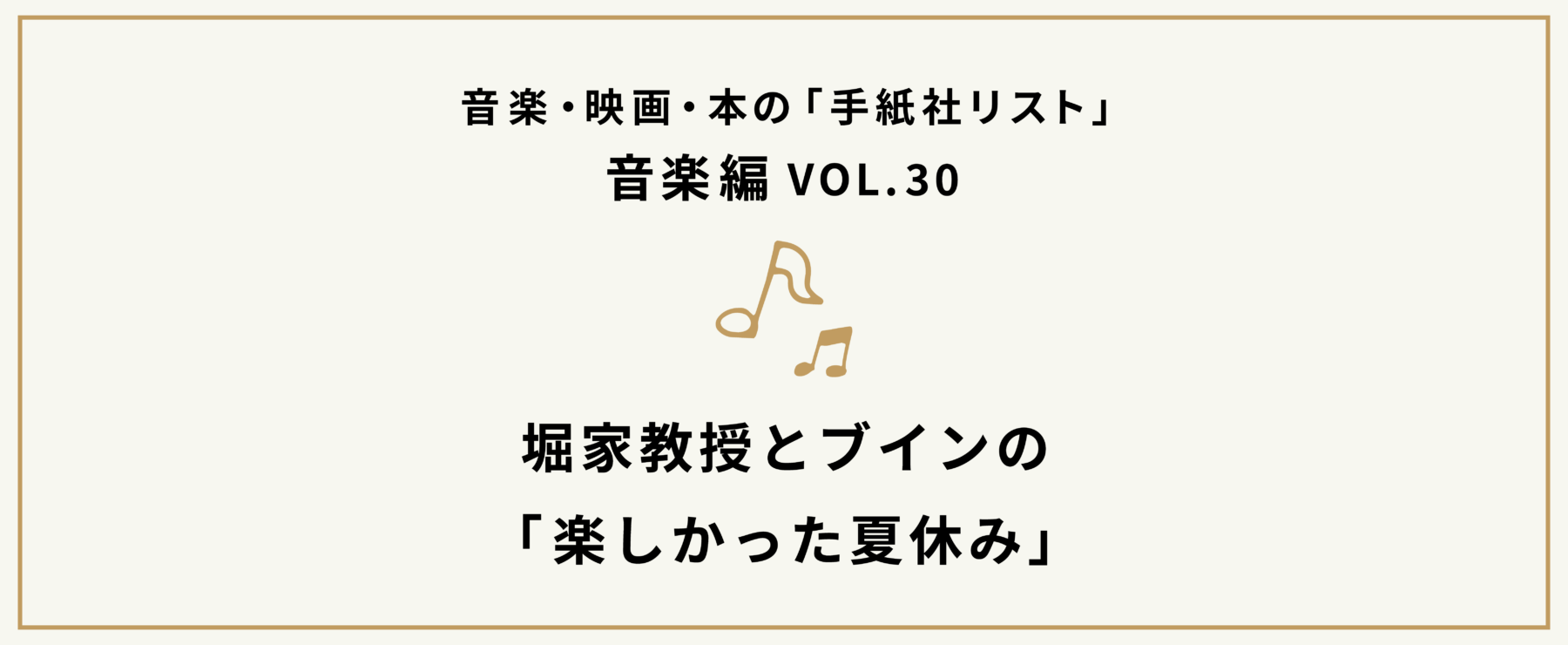
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。30回目となる音楽編は、「楽しかった夏休み」というテーマでお届けします! 夏をテーマにした歌は古今東西たくさんありますが、「夏を待ち望む歌」ではなく「夏を惜しむ歌」の方が圧倒的に多いようない気がしませんか? 夏とは、楽しむ対象として、そして、惜しむ対象としてあるのかもしれませんね。さあ、夏を惜しみ、愛おしむ歌の数々、堀家教授と手紙社のブインのみなさんと、一緒に味わっていきましょう!
この後、まずは手紙社の部員さんが選んだ5曲を紹介し、続いて堀家教授のコラム、その後に堀家教授が選んだ5曲を紹介します!
手紙社部員の「楽しかった夏休み」5選リスト
1.〈夏休み〉吉田拓郎(1971)
作詞・作曲/吉田拓郎,編曲/吉田拓郎、石川鷹彦
この歌はシンプルな言葉の繰り返しでありながら、日本の夏が良く表現されてると思います。それぞれの夏の光景が目に浮かび、思い出が蘇ります。余計な言葉がないおかげで、聴く人それぞれの夏を歌っているようにも思えます。私が思い浮かべる「田んぼ」はカエルどころか跡形もなく宅地になってしまいました。中学時代、吉田拓郎大好きな友だちから借りたLPレコードに入っていて後に拙いギターの練習曲となりました。この曲を聴くと、そーそー、こんなだった、昔々の夏は良かったなぁ、と懐かしむとともに、ひと言で夏を感じさせる言葉がたくさんある日本語を誇らしく思います。
(3103)
2.〈さよなら夏の日〉山下達郎(1991)
作詞・作曲・編曲/山下達郎
人生にこの曲があってよかった。「このまま時が止まればいいのに」と思ったあの瞬間、帰りたい"あの日"を想いながら聴きたい曲です。後半になればなるほど胸がふるえます。
(あっこ)
3.〈いつまでも変わらぬ愛を〉織田哲郎(1992)
作詞・作曲・編曲/織田哲郎
1992年リリース。32年前になるのですね。32年前の夏もそれなりに暑かったと思いますが、今ほどの暑さではなかった。この<いつまでも変わらぬ愛を>はギラギラとした夏というより、さらりとした夏。それもそのはずで、清涼飲料水のコマーシャルソングでした。1990年代音楽業界はビーイングのアーティストが売れに売れまくっていて、タイアップ曲も多数。私もビーイングのアーティスト、音楽にハマりました。織田哲郎さんはビーイングに関与していたとのことで、多くのヒット曲を生み出しています。心地よいメロディーに日常の飾らない言葉を乗せて、やわらかい声。今年の夏も終わりが見えてきて、この曲を聴くと気持ちが和らぎ、ほっとします。何回繰り返して聴いても飽きない、素敵な曲です。
(あさ)
4.〈Sunny Day Sunday〉センチメンタル・バス(1999)
作詞/赤羽奈津代,作曲/鈴木秋則,編曲/センチメンタル・バス、ホッピー神山
暑い日には必ずと言っていいほど『39度のとろけそうな日』のサビが頭に流れてくる、私の夏の定番曲です! 可愛いボーカルの声ですが、ギターのフレーズがとてもかっこいい! CMの印象も強く、この曲を聴くと海に飛び込みたくなります笑 昔は39度、というと日本では考えられないなぁと常夏の島に思いを馳せていましたが、今となってはよく聞く気温に…でもその分身近な曲となり、『今日はあの曲と同じ、39度のとろけそうな日だ…』なんて考えながら歩くと、うんざりする暑さの中でもちょっと楽しい気分になります♪
(しまえなが)
5.〈夏の終わり〉森山直太朗(2003)
作詞/森山直太朗・御徒町凧,作曲/森山直太朗,編曲/中村タイチ
同じく森山直太朗の「さくら」と並び、私の中では”その季節になると聴きたくなる歌”のひとつです。ある夏、奥多摩へキャンプに行きました。夕暮れ時に心地よい風を感じながら山の木々を眺めていたら、ヒグラシの鳴く声が聞こえてきて…その時この曲が浮かんできました。夏が終わると思うと、何故少し寂しくなるのか。その寂しさと、会いたいけど会えない人への想いがリンクした歌です。二胡のように聴こえるファルセットと美しいビブラートが聴きどころ。じんわりと心に沁み込んでくる歌詞とメロディーに浸ってみるのはいかがでしょうか。
(アン)
歌謡曲も夏休み
子どもたちの特権
夏休みとは、いうまでもなく、幼児から児童、生徒、学生に至るまで、大人たちの庇護のもと扶養される子どもたちに与えられた特権です。幼稚園、小学校、中学校、高等学校、そして大学や短期大学、高等専門学校といった教育機関にかよう彼ら彼女らが、そこでの活動や勉学を困難にさせる真夏の暑さを回避するために、当時の文部省が設けたことに端を発するそれは、ただし“夏季休暇”ではなく、あくまでも“夏季休業”として担保された期間です。
それら教育機関において、特に授業に代表される教育業務の提供が停止される夏季の一定の期間については、そのかわりこれら教育機関における通常の授業では提供しえないなにがしかの体験を積むことが期待されています。このような体験を“教育”とみなすことの是非はともかく、夏休みとは単に授業などが休業する期間なのであって、子どもたちには休んでいる暇などありません。
夏休みと、働く大人たちに許された夏季休暇やお盆休みとの違いは、まさしくここにあります。
この期間、子どもたちは、外遊びに、プールに、ゲームに、昼寝に、部活に、塾に、お手伝いに、旅行に、親の帰省の追従に、たまった宿題の追い込みに、なんなら園や学校の休業のあいだの暇をつぶすことに大忙しです。
彼ら彼女らを庇護する大人たちにとって、そんな子どもたちの無邪気な忙しなさは、もはや自分のものではありえません。すべてはすでに喪失され、新しい夏が訪れるたびに郷愁と悔悛をもって羨望するよりほかないような、あまりにも甘美な賜物なのです。
就学を終えるまで夏休みとともに繰り返されたあの気怠さも、憂鬱も、暑気も、晴天の霹靂と雷光も、焼けたアスファルトに跳ねる夕立ちの雫が孕んだ塵芥の匂いも、ページを開くことさえなく机の片隅に積まれた宿題も、汗まみれの午睡から醒めない白日夢も、孤独も、視界の消失点に湧きのぼる入道雲の隆盛な立体感も、石垣にしがみついたまま乾ききった蝉の抜け殻の枯れ葉のような軽さと脆さも、秋の気配をにわかに招いて蚊帳を揺らした夜風にそよぐ蚊取り線香の白い煙の筋も、そして所在ない暇さえも。
事実、〈夏休み〉(1972)の吉田拓郎は、「麦わら帽子」も「たんぼの蛙」も「もうきえた」と歌っています。「絵日記つけてた」、「花火を買ってた」、「西瓜を食べてた」、「水まきしたっけ」などと、「夏休み」の体験を過去形で列挙しつつ、「姉さん先生」も「もういない」あの不可能な「夏休み」、かつては「指折り待ってた」それを、いまなお彼は「それでも待ってる」のです。
したがって、「あの時逃がしてあげた」まま「どこ行った」とも知れない「畑のとんぼ」とは、すなわち「夏休み」そのものの謂でしょう。あの「とんぼ」を、「ひまわり」を、「夕立」を、「せみの声」を、これら喪失された体験の索引としての「夏休み」を、彼は「それでも待って」います。 もちろん、「とんぼ」も「ひまわり」も、「夕立」だって「せみの声」だって、依然として大人たちの夏を相応に彩ってくれます。でもそれらは、「あの時」の「とんぼ」や「ひまわり」、「あの時」の「夕立」や「せみの声」と同じものではけっしてありえません。あの「夏休み」は、もう私たちのもとには戻ってこないのです。
モラトリアムの罠
瞬間ごとに絶えず更新され、その都度、はじめて直面する現実と対峙せずにはいられないはずの私たちは、にもかかわらず、そうした現実のうち似たものを概念で囲い、言葉で括りながら、生活にとって肝心な要素を重視し、そうでない詳細や些事を捨象しています。そうすることで、私たち大人は、変化しつづける現在を、あたかも型どおりに繰り返される一般的な日常として秩序づけ、そのぶん効率的に、計画的に、日々の営みを送ります。
就学とは、大人になるために必要なさまざまな型を子どもたちに習得させるべく準備されたモラトリアムであり、科目や教科書、授業時間や時間割、公式や規則など、教育機関はあらゆる局面で彼ら彼女らを型枠に嵌め、子どもたちに紋切り型の対応を促します。あるいはむしろ、そうした枠の介在に疑念を抱くことなく感覚や認識を型に馴致され、毎日を、毎月を、毎年を定型どおり繰り返して社会秩序を維持し、定型の堆積を人生として消費できる主体、それが大人なのかもしれません。
子どもたちの一日が長く、忙しないとすれば、おそらくそれは、複雑にして不断に変化する現在を捕捉するための定型の形成が途上ないし未然であって、大人がそれをとおして捨象している細部のいちいちを感覚し、認識しないことには日が暮れないからです。園や学校が管理する空間と時間の範疇にあっては提供できない体験を期待する自律的な“教育”の名のもとに、こうした型枠のたがが緩み、そこから浸透してくる現実の細部が胸をざわつかせる夏休みとは、それゆえに、子どもから大人への直線的な道程に、波風の立たない凪のような成長の過程に世界の側からしかけられた、ある種の罠として機能します。
戻らない過去として夏休みを懐かしむのではなく、現実の細部にあふれて倦むことのない現在に向けて、もしくはいまそこにある世界のすべてに対して、知覚の諸点が収斂する中心としての身体を投げだすこと。はっぴいえんどの〈夏なんです〉(1971)において松本隆が綴ってみせたのは、そうしてかろうじて実現されえた夏のかたちにちがいありません。
ここで松本は、吉田拓郎による〈夏休み〉の場合とは異なり、「風が立ち止まる」だの「ビー玉はじいてる」だの、あるいは「太陽なんです」だの「蝉の声です」だの「入道雲です」だの、あくまでも現在形でそのかたちを把握しようと試みています。とりわけ彼は、「ギンギンギラギラ」や「ホーシツクツク」、「モンモンモコモコ」といったオノマトペでどうにかこれをなぞろうとしますが、けれど言葉という型枠を援用している限りにおいて、そのように夏の輪郭として描かれるかたちとは、結局のところ夏の名残り、夏の抜け殻にすぎないでしょう。
松本隆の言葉をもってしても、型に秩序づけられたかたちから夏の本当が剥落することは不可避です。事実、チューリップに提供した〈夏色のおもいで〉(1973)の歌詞にあっては彼自身もまた、「夏はいつのまにか」言葉の彼岸で「翼をたたんだ」ことを悲嘆するばかりです。
それでもなお、〈夏なんです〉をめぐってこれら漏れ、零れる細部の生々しさをすくいとるもの、それこそが、はっぴいえんどの演奏と、わけても細野晴臣による歌唱であることは論をまちません。
彼らのなかでももっとも大人びていたはずの細野晴臣による低音の歌声をもって歌唱されるやいなや、〈夏なんです〉が呈する事態は一変します。細野の不器用にして雑味ある、寛容にして不作為の歌唱は、まさしくそれゆえに、演奏もろとも変化しつつある現在、型枠のすきまから浸透してくる現実それ自体として、私たちの鼓膜を動揺させる響きとなります。逃げ水のように茫洋とした彼の朴訥な歌声は、夏のかたちの正調性から逸れ、その本当を出来させるのです。
避暑地の恋
鋳型に嵌められ、整えられたかたちには、いまだ分節化されない夏の本当を期待することは困難です。加えて、そのような鋳型にも流行り廃りがあって、去年の夏には確かに正調だったひとつのかたちも、今年の夏となればとうに古びていない保証はどこにもないはずです。
たとえば、〈恋する夏の日〉(1973)の天地真理は、「今年の夏」を「心にひめいつまでも」けっして「忘れない」と歌います。なるほどそれは、「美し」さの定型のもといつまでも彼女の「心の中」に「残るでしょう」。他方で、この「二人の夏」に対して、彼女は「どうかずっと」このまま「消えないでね」と請願してもいます。
要するに、「二人の夏」そのものは、もっぱら「美し」さや「幸せ」の印象だけを彼女の「心の中」に「残」して、瞬間ごとに明滅しながら絶えず変化しているのです。
とはいえ、ここで古びる型とは、なにもそうした個人的な心象に限りません。なるほど、彼女の「心の中」に「残」された「美し」さや「幸せ」の印象も、いずれ褪せ、衰えてしまうのでしょう。しかしながら、〈恋する夏の日〉は、より単純かつ直裁に、当時の「今」として一定の夏のかたちを表現していた古い型を、すなわちすでに廃ってしまったかつての流行の様式を証言しています。
それは、高原での避暑をめぐる夏のありようです。
明治期には外国人宣教師らの保養地として、その後は結核患者の療養地として、とりわけ夏季に清涼な澄んだ空気を供給してきた高原の気候風土については、なにより1957年の軽井沢が昭和期の皇太子と美智子妃とのテニスコートでの出会いを演出したことで、にわかに市井の関心を集めます。
誰もがほとんど裸も同然の風体で徘徊することを許容する海辺が、いわば夏の暑さを下世話な仕方で堪能するための舞台装置であるとすれば、高原は、夏の暑さを避けてスポーツに勤しみ、あるいはカフェでくつろぐなど、上品な仕方で余暇をすごすための舞台装置です。
この型枠が醸す上流階級風の秩序の薫りに憧れた一般市民は、高度経済成長の達成と国土の整備にもとづく高地への観光旅行の簡便化による大衆化とともに、社会的な高揚もしくは熱狂もろとも、夏ともなれば高原の避暑地へと赴くようになりました。わけても軽井沢については、ジョン・レノンとオノ・ヨーコ夫妻の滞在がお墨つきとなり、そこでの休暇に箔を与えています。
〈恋する夏の日〉の「私」が「あなたを待つ」のは、まさしく「テニスコート」です。それを囲む「木立ちの中」には「白い朝もや」が「のこ」り、ここが高地であることをほのめかします。「夏」であるにもかかわらず「涼しい風」が「吹いてくる」こともまた、高原の証左といえます。
高原での体験を夏の記憶と明確に関連づける歌謡曲の情緒に先鞭をつけたのは、おそらく、1949年に江間章子が作詞し、中田喜直が作曲した〈夏の思い出〉でしょう。「夏がく」るたびに「はるかな尾瀬」を「思い出」させるこの楽曲は、1954年には藤山一郎の歌声をもって音源化されています。
単に高原を謳った歌謡曲としては、小畑実が歌唱した〈高原の駅よ、さようなら〉(1951)、岡本敦郎の〈高原列車は行く〉(1954)、林伊佐緒による〈高原の宿〉(1955)なども発表されていました。
とはいえ、避暑地のテニスコートでの1957年の出来事より以降は、たとえば舟木一夫の〈高原のお嬢さん〉(1965)の場合のように、さらには「軽井沢」を「天国」と形容したブレッド&バターの〈傷だらけの軽井沢〉(1969)もそうだったように、避暑地たる夏の高原での体験は、もっぱらその空間と時間に行方を委ねられた刹那の恋愛模様に彩られていきます。
村田和人が竹内まりやを迎えて二重唱で吹き込んだ〈SUMMER VACATION〉(1984)も、この延長線上にあります。前年に川島なお美の歌唱によるシングル盤のB面として提供された件の楽曲について、そこに「海辺のカフェテラス」や「夕暮れマリーナ」を設えていた安藤芳彦の歌詞は、ここでは「テニスコートの出会い」や「白いポーチのホテル」で「避暑地の恋」を叶えるのです。
夏が終わる
それでもなお、〈SUMMER VACATION〉が叶えた「避暑地の恋」は、「枯葉舞うテラス」での「一足早い秋」の気配に、もはや「帰らぬ夏の夢」たらざるをえません。いまだ海辺の夏が謳歌されるころ、高原の樹々をそよがせる風は性急にも次の季節の秩序を漂わせています。
なるほど、田原俊彦の〈ハッとして!Good〉(1980)に夏の符号は認められないものの、「きらめく高原」において「君と触れ」ることを正当化する「ハッと」するような「Sweet Situation」として、「僕」のために「グレーのテニスコート」を準備してくれます。けれど「私」が「高原のテラスで手紙」を「したためてい」る松田聖子の〈風立ちぬ〉(1981)の場合、この「夏から秋への不思議な旅」にあって、「色づく草原」を「振り向」いた彼女は、とおりすぎた「風」が「あなた」との「夏」を「想い出」に変え、確かに「今は秋」となったことを知るのです。
おニャン子クラブの渡辺美奈代が〈瞳に約束〉(1984)で単独デビューしたとき、彼女たちの集団が放課後のクラブ活動の名目で夕方のテレビを賑わしていたこともあり、秋元康が描く「星のカーテン」の「下」りた「夏の終わりの高原」の光景は、合宿をともなういわゆる林間学校を想起させるものでした。そしてここにも、「風の香り」が浸透してきています。
終業式の午後、途轍もなく長く思われた夏休みも、林間学校を終え、お盆の帰省から戻ったころには、机の片隅に山と積まれた宿題だけを残してあとわずかです。
井上陽水と安全地帯の合作となる〈夏の終りのハーモニー〉(1986)では、「お別れ」の「ハーモニー」すなわち「最後の二人の歌」は、「夜空をたださまよ」い、「星屑のあいだをゆれながら」、「真夏の夢」や「あこがれ」を、彼らの饗宴を「想い出」とすべく、「夏の夜を飾」ります。
〈夏の思い出〉から「水芭蕉」を借用した〈夏の終わり〉(2003)の森山直太朗は、「時」の「徒に過ぎ」るばかりでもう「夏の日は帰らない」ことを、この「夏の終わり」に「吹き抜け」ていく「いつかと同じ風」のうちに覚悟しています。
かつてそうした「夏の日」を「永遠より長い」ものとみなしたのは、〈いとしのテラ〉(1984)の杉真理でした。ただし「永遠より長い」はずのそれら「夏の日」も、「今」の「二人」にはとうに「過した」昔日であって、その喪失感は、ここでの修辞をもっていっそう「遠く離れた」さまが強調されます。「永遠より長い」ものとして消費されたあの時間は、「今はどこへ行った」とももはや知れません。
どの夏も、どの季節も、どの年も、どの月も、もちろんどの一日も、いずれ終わってしまいます。
山下達郎の〈さよなら夏の日〉(1991)にあっても、「夏の日」に「さよなら」と告げて「僕等は大人になって行」きます。
そこでは、たとえ「君」が「時が止まればいい」と「つぶや」いてみたところで、「巡る全てのもの」、けっして停滞することのない現在は、「急ぎ足で」瞬時に推移し、「変わって行」きます。そこに留まっていてはくれない現実は、夏の秩序、夏らしさの型枠からにじみ、漏れ、抜け、流れ、ついに消失してしまおうとしています。あの「一番素敵な季節」が、こうして「もうすぐ終わ」ろうとしているのです。
つまるところ、再び訪れることのけっしてないあの「一番素敵な季節」たる「夏の日」に「さよなら」と告げること、それは、とりもなおさず子どもの自分に「さよなら」を告げ、「大人にな」ることに相違ありません。
幼児から児童、生徒、学生に至るまで、学年におうじて夏休みが終わるその都度、私たちは、そのぶん子どもであることを放棄し、私たちの現在を、自らの時間を、私たち自身を、大人らしさの型枠に適合させてきました。そしておそらく、そこで重ねてきた諦念こそが、園や学校の休業のあいだの暇をつぶすことに忙しなかったかつての自分の記憶を、いかにも大人らしく郷愁と悔悛の型のもと羨望するよりほかないような、あまりにも甘美な賜物とするのです。
私の「歌謡曲も夏休み」5選リスト
1.〈夏なんです〉はっぴいえんど(1971)
作詞/松本隆,作曲/細野晴臣,編曲/はっぴいえんど
歴史的な名盤《風街ろまん》に収録。ニ長調ともト長調ともつかず浮遊する調性の曖昧な感覚は、この楽曲が終止することなく無限に持続し、永遠に鳴り響いていそうな、きわめて散文的な展開を可能にしている。頻出するmaj7も、そうした調性の不安定さに拍車をかける肝要な因子だろう。松本隆によるオノマトペの多用は、このように巧みに練られた編曲と演奏が支える朴訥な細野晴臣の歌唱を介してこそ、暑く気怠い夏の光景を音響として実現する。
2.〈恋する夏の日〉天地真理(1973)
作詞/山上路夫,作曲/森田公一,編曲/馬飼野俊一
1957年の軽井沢での出来事が、ほかでもないこの時期に〈恋する夏の日〉の世界観に反映され、聴衆もまたその事実にほとんど疑念を抱くことなく素直に受容できたとすれば、おそらくそれは、高度経済成長が終わった停滞期の日本において、電通が「ディスカバー・ジャパン」と銘打って当時の日本国有鉄道をとおしてしかけたキャンペーンと無縁ではないだろう。「美しい日本と私」として標榜された戦後日本の“自分探し”の旅は、全国の小京都のみならず高原の避暑地にも観光客を、とりわけ若い女性たちを呼び込み、併せてこの楽曲などは、そこでのひと夏の恋を彼女たちに夢みさせる。天地のほか、このころあいついで登場したアグネス・チャン、浅田美代子、山口百恵ら女性アイドルたちの、必ずしも安定していたわけではない歌唱力は、これに眉をひそめた大人たちによる狭量な評価とは逆に、歌手と同世代の聴衆たちにとっては、むしろ楽曲に描かれた世界観に対する親近感を担保し、自分ごととして共有させたにちがいない。
3.〈いとしのテラ〉杉真理(1984)
作詞・作曲・編曲/杉真理
歌謡界屈指のメロディ・メイカーとして知られる杉真理の、本人の歌唱曲としてもっとも世間に流通した代表作のひとつであり、本人には山下達郎からも電話口で賛辞を示されたというこの楽曲は、飲料のCMへの採用が前提であったことから、とりわけ商品名が織り込まれたサビの旋律のキャッチーさにその能力が存分に発揮されている。他方で、歌詞における「永遠より長い 夏の日を過した」の文言は、秩序の回復と引き換えに喪失され、すでにとりかえしのつかない不可能な瞬間へと手向けられた情緒を謳うものとして、彼の言葉の感覚の非凡さを物語るきわめて秀逸な表現であるように思う。
4.〈SUMMER VACATION〉村田和人(1984)
作詞/安藤芳彦,作曲・編曲/村田和人
川島なお美に提供された楽曲の、作曲者によるセルフ・カヴァー。海辺を舞台としたオリジナル版に対して、作詞者は同じまま、こちらのカヴァー版では舞台は高原に設定され、しかも竹内まりやとのデュエットのかたちで《MY CREW》に収録されている。そのうえで、川島の場合はシティ・ポップス風の趣きが強かったものを、村田の場合には竹内の歌声とともにオールディーズ調の機微が前景化する。
5.〈瞳に約束〉渡辺美奈代(1986)
作詞/秋元康,作曲・編曲/後藤次利
編曲家やベースの演奏家として貢献が多い後藤次利の、歌謡曲の作曲家としての一世一代の傑作。この楽曲でデビューする歌い手を女性アイドル歌手の正統として提示すべく、歌謡曲におけるいわゆるカノン進行となるⅠ-Ⅲm7-Ⅵm7-Ⅲm7のコードの展開を援用した後藤は、それぞれのパートが8小節からなるA-A’-B-C-C’の構成の最後に、カノン進行から抜きだしたⅢm7-Ⅵm7-Ⅲm7を繰り返す4小節からなるDパートを加え、王道の安定感にわずかながら動揺をもたらす。いうまでもなくこれは、「叶」いつつある「素敵な夢」に「少し」だけその「肩先」を「震」わせる主人公の、さらにはデビュー曲を歌唱するさなかにある当の歌い手の、大きな喜びのうちにも隠しきれない戸惑いと不安を表現するシークェンスである。
番外_1.〈夏色のおもいで〉チューリップ(1973)
作詞/松本隆,作曲/財津和夫,編曲/川口真,チューリップ
職業作曲家としての松本隆の、実質的なデビュー作にして最初のヒット作。この歌詞を筒美京平が評価したことが、のちの彼らの協働につながる。前曲〈心の旅〉につづいてThe Beatlesによる〈Hello, Goodbye〉への憧憬を引きずりつつ、その直接的な影響下にあったThe Iveys、のちのBadfingerによる〈Maybe Tommorow〉の芳香も組み込まれた曲調に、こうして松本の傑作のひとつとなる言葉が綴られるとき、筒美ならずともそこにヒット曲たる必然を聴くことは難しくないだろう。ただし、「ビートルズを探せ!ヤァ!ヤァ!ヤァ!」(2022年4月号)のテーマのもとすでに「手紙社リスト」入りしているため、ここでは番外とした。
番外_2.〈星くず〉久保田麻琴と夕焼け楽団(1977)
作詞・作曲/藤田洋麻
発表後すでに半世紀にならんとしているにもかかわらず、いまなお微塵も古さを感じさせない音像の肌理。久保田と細野晴臣とが共同プロデュースし、ハワイのホノルルで録音された。浮かれた気分や気怠い感覚など、夏の期間をとおしてあらゆる状況で聴きたくなるうえに、どのような状況のもといつ聴いてもまったく齟齬がない。にもかかわらず、歌詞のうちに夏を仄めかす記号的な言葉が提示されていないため、ここでは番外とした。
番外_3.〈百合コレクション〉あがた森魚(2007)
作詞・作曲/あがた森魚,編曲/久保田麻琴
初出はヴァージンVS名義のもと《RADIO CITY FANTASY》に収録された版。そこでは鈴木慶一が編曲を担当しているが、あがた森魚がソロで発表した《Taruphology》のためにセルフ・カヴァーのかたちであらためて吹き込まれ、久保田麻琴が編曲を任せられたこちらの版を推す。ただ、いずれの版にしても、稲垣足穂的な語彙の集った世界観が、当時の最新の音楽事情を反映させた音響に奇妙に合致している。描写される「高原」の「星」の「夜」のさまが夏から秋への季節の推移を感じさせるものの、明確に「秋空」を謳っているため、ここでは番外とした。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





