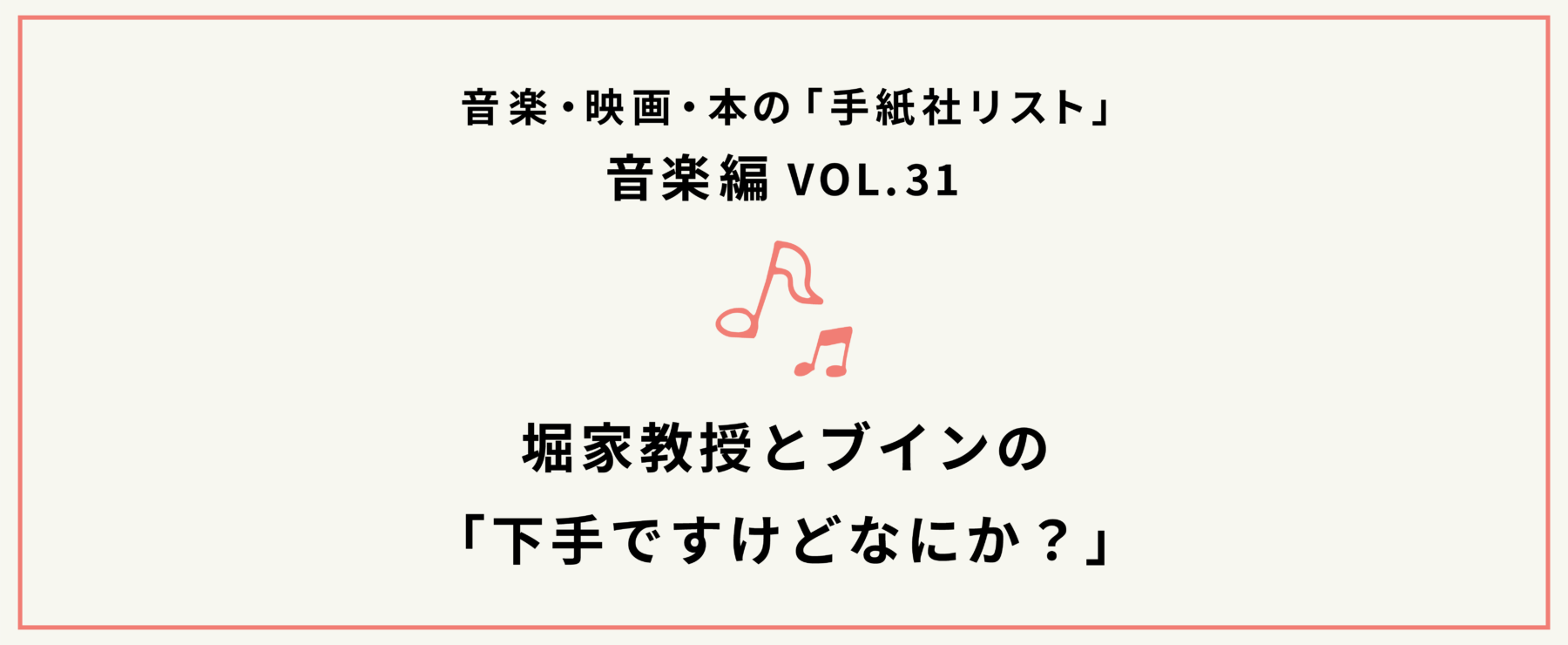
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。31回目となる音楽編のテーマは、「下手ですけどなにか?」。なんという挑戦的な(?)テーマ! 一般的には”へた”と言われているけれど、心に響く歌、胸に迫る歌、感動する歌を、堀家教授と手紙社のブインのみなさんと、味わっていきましょう!
この後、まずは手紙社の部員さんが選んだ5曲を紹介し、続いて堀家教授のコラム、その後に堀家教授が選んだ5曲を紹介します!
手紙社部員の「下手ですけどなにか?」5選リスト
1.〈赤い風船〉浅田美代子(1973)
作詞/安井かずみ,作曲・編曲/筒美京平
好きで毎週観ていたドラマ「時間ですよ」の挿入歌。 毎回終わる頃、屋根の上で、健ちゃん(堺正章)とミヨちゃん(浅田美代子)が歌います。 ハートウォーミングなところも、 コミカルなところもある、とても面白いドラマです。 特に樹木希林さん、(その頃は悠木千帆さん)演じる浜さんと堺正章さん演じる健ちゃんとミヨちゃんの掛け合いはとても楽しかったです。 新人のものすごくかわいいミヨちゃんがそれはまた可愛らしく歌うんですが、 初めて聞いた時のズッコケ感、その後は、今日はどうかな?の期待感、そして「あーやっぱり」の残念感と何故かの安心感、などとても楽しみにしていました。 ミヨちゃんが素晴らしくかわいいので、下手だなんてこと、どうでもよかったです。 きっと観ていたみんなが「がんばれ〜」って思いながら聞いて、暖かい拍手を送ってたと思います。
(3103)
2.〈かけめぐる青春〉ビューティ・ペア(1976)
作詞/石原信一,作曲・編曲/あかのたちお
ビューティ・ペアとは、かつての全日本女子プロレスのタッグチーム。最近ではNetflixのドラマ「極悪女王」でも取り上げられているようですね(私はまだ見ることができていません)。 1970年代、芸能活動もする女子プロレスラーが現れます。その先駆けとしてこの2人の登場はインパクトがありました。美人だし、背が高くてかっこいいのですが、びっくりするくらい下手な歌唱力。楽曲そのものも、出だしとサビが「ビューティ・ペア」と自分たちのグループ名を連呼するという謎の構成。さらに「野に咲く白い花が好き」というジェンダーバイアスバリバリの歌詞。ダンスとはいいがたいボックスステップの振り付け。それでも当時は熱狂的な女子中高生が、会場を埋め尽くしたのだとか…。 それはやはり、「かけめぐる青春」という刹那を、このユニットが日々体現していたからではないでしょうか?おそらく、歌唱指導もダンスの指導もなく、一流の歌手と一緒に歌番組や映画に出演しながらも、リングのうえでは、飛んだり投げたりの力技。(たぶん)八百長はなくガチの試合をほぼ毎日させられていた。 そんな彼女たちの末路についてはドラマでも取り上げられているそうです。その内容を知ると、歌の下手さはそのまま、この歌とユニットの切なさに、より一層転換されていきます。
(手芸愛好家)
3.〈風の谷のナウシカ〉安田成美(1984)
作詞/松本隆,作曲/細野晴臣,編曲/萩田光雄
「風の谷のナウシカ」は、世界の巨匠である宮崎駿監督率いるスタジオジブリの記念すべき第1作映画です。 テレビのベストテンを見る日は、いつもより遅く寝ることを許されていた小学生のころ。 目のクリッとした細身の可愛らしい女の子が華々しく紹介されてからの・・・ 「風の谷のぉぉぉナウゥゥシカァァ」 あまりのはずしっぷりに、かなりの衝撃を受け、完全に私の記憶に刷り込まれました。 それから40年近くたちますが、「下手ですけど何か?」な歌謡曲に自信を持って推薦できる1曲です。 今になって調べてみましたが、作詞は松本隆・作曲は細野晴臣… え!名曲やん・・・・まぁ、ある意味メイキョクですけど、ナニカ?
(あん)
4.〈フレンズ〉REBECCA(1985)
作詞/NOKKO,作曲/土橋安騎夫,編曲/REBECCA
今年2月。あるアーティストの東京ドームライブにゲスト出演したNOKKOさん。二人でREBECCAの代表曲〈フレンズ〉〈RASPBERRY DREAM〉〈Maybe Tomorrow〉を熱唱。私にとって初めて生で聴くNOKKOさん。小柄ながらパンチのある歌唱、唯一無二の声。感動ものでした。そのライブのテレビ放送があって観ていたのですが…あれ?こんなだった?音が外れている??もちろんライブでのパフォーマンスは最高でした。80年代当時のレコーディングでの歌唱も、ていねいに録っているからそれはそれでいいですし。下手というわけではないけれど、ライブ!という臨場感、熱量がメロディーを超えてしまうのかな。昨年還暦を迎えたNOKKOさん。年を重ねていくと体力、声などの維持は大変で、それでもあれだけのパワー、パフォーマンスはすごい!キュートなNOKKOさん、素敵でした。
(あさ)
5.〈君は1000%〉1986オメガトライブ(1986)
作詞/有川正沙子,作曲/和泉常寛,編曲/新川博
極々最近のことでした。この曲がカーレディオから不意に流れて来て。。。カルロストシキさんの歌声って最高やん!と、感じた自分に驚きと興奮が走りました。それと同時に、過去の自分をしみじみ振り返えったのです。 私がまだ、歌の上手も下手も良くわかっていなかった子供の頃(今もようわからんけど😅)、杉山清貴&オメガトライブ解散後の1986オメガトライブ、そしてカルロストシキ&オメガトライブ。突き抜けるほど透き通った歌声の杉山さんとは対照的な、あの耳慣れないこもった歌声と独特な動きに「えーっ🤨」って思ったんです。 しかし今になってようやく、カルロストシキさんは✨透き通った鼻声✨なんだと。その良さにわたくし51歳にしてやっと追いついたのです😅 〈君は1000%〉の歌詞とメロディ、そして唯一無二な歌声。なんだかんだと聴く人の記憶に強く刻まれる要素満載に、感動すら覚える一曲です。
(大分の共子)
下手ですけど、なにか?
素人/玄人
日本の大衆音楽が録音技術を前提とした産業体系として成立した当時、レコードに歌唱を吹き込むことを専業とする歌手は存在しませんでした。いわゆるレコード歌手という概念は、レコード産業の確立をもってはじめて形成されたわけで、その時点でレコード歌手たりえた誰もが単なる素人にすぎませんでした。生まれたてのレコード産業においては、素人でないものなどただのひとりもいなかったのです。
このようなレコード産業の草創期に、流行歌を吹き込む即戦力として歌声をあてにされたのは、浅草オペラといった演劇の舞台で人気を博した二村定一や榎本健一らヴォードヴィリアンたち、お座敷で三味線にあわせて長唄を朗じていた小唄勝太郎や江戸小唄市丸ら芸妓たちなど、すでに自らの歌唱を技芸として客前で披露することが生業だった芸達者の面々でした。
他方で、ラジオ放送の開始や映画のトーキー化といった音声メディアの多様化とも歩調をあわせ、いよいよレコード産業が活性化してくるにつれ、大衆音楽の聞き手の数も飛躍的に増大していきます。
日本のどこかの街角でひとりの聞き手の耳に届き、その嗜好にかなうことのできた歌は、やはり日本のいたるところで同じように匿名の誰かの耳に届き、そうした彼や彼女の心に響いているはずです。このような歌には、やがて映画が、ラジオが、さらにはレコードが、こぞって繰り返し再生の機会を提供し、日本の街角にいっそう露出することになります。
流行歌の誕生です。
しかもそれが一定の資本のもと産業化された流通網をとおして配達される、いくらでも複製可能な商品である限りにおいて、特定の歌への聞き手からの支持の集中は、巨大な利益を生産者側に還元します。歌い手の需要はいよいよ増加し、レコード会社は歌唱の技量の確かな新人たちの発掘に余念がありません。畢竟、レコード業界の鵜の目鷹の目は、音楽を学び、わけても声楽を専攻する音楽学校の学生に対して注がれるようになります。
〈波浮の港〉(1928)を日本の最初期の流行歌としてヒットさせた佐藤千夜子がその嚆矢でしょう。東京音楽学校、すなわちいまの東京藝術大学で西洋式の声楽の学徒だった彼女は、中退したのち吹き込んだ〈波浮の港〉の翌年には〈東京行進曲〉(1929)を発表し、これを〈波浮の港〉以上のヒット曲に仕立てています。
古賀政男の作曲による〈酒は涙か溜息か〉(1931)や〈丘を越えて〉(1931)、さらに〈東京ラプソディ〉(1936)の歌唱で知られる藤山一郎もまた、東京音楽学校で声楽を学ぶとともに、すでに在学中から身分を隠してレコード歌手として活躍していたことから、一時はこれを契機に退学の危機を迎えますが、最終的には首席で卒業しています。
服部良一が提供した〈別れのブルース〉(1937)や〈雨のブルース〉(1938)を歌唱した淡谷のり子は、東洋音楽学校、すなわちいまの東京音楽大学に入学後にピアノ科から声楽科に転籍し、やはり主席で卒業しています。
つまるところ、佐藤や藤山、淡谷らは、レコード歌手としては素人ながら、それ以前にすでに歌唱の玄人たらんとしていたわけです。
古典音楽/大衆音楽
芸術としての西洋音楽を人声で歌うために、自己の身体を楽器として西洋音楽を奏でる声楽家となるために、しかるべき教育機関においてしかるべき教授法で専門教育を施された佐藤千夜子や藤山一郎、淡谷のり子らの歌唱は、それゆえに、西洋の旧大陸で培われた長い伝統を東洋の島国で継承する資格を有しています。その身体器官が実現する歌声の差配には、芸術の名のもと権威づけられた表現技巧の正統が担保されているのです。
けれどこのことは、専属契約か一時雇用かといった就労の形態をめぐる如何を問わず、レコード産業の草創期に最初の職業歌手となった彼ら彼女らにとって、ある種のうしろめたさを感じさせる背景ともなりました。
芸術の名のもと権威づけられた玄人の歌唱は、高尚で上品な古典音楽のために精神を賭して奉仕すべきものであって、大衆音楽などという低俗にして下卑な、幼稚にして粗野な戯れごとごときにこれを浪費することは、まさに悪徳まがいの愚行にほかならないものとされました。流行歌をレコードに吹き込む行為に芸術の折り紙つきの歌声を貸すことは、西洋式の古典音楽のためだけに洗練されてきたはずの身体器官の無駄遣いとみなされたわけです。
彼ら彼女らへのこのような批難のうちには、西洋の芸術的な古典音楽に対して、大衆音楽を、流行歌を差別的に処遇する貴賤のヒエラルキーが率直に反映されています。そればかりか、その姿勢になんら悪びれるところがないさまが、佐藤や藤山、淡谷らの苦境をいっそう不遇としたはずです。
音楽としての表現の形式や内容にみられる貧しさや稚拙さはもちろん、金銭的な成功のためとあらば大衆への迎合を厭わず、そうした表現の形式や内容さえがいともたやすく犠牲にされるような、いわば経済原理に支配された堕落的な娯楽など、それこそ舞台役者や映画俳優、芸妓や大道芸人といった、歌唱については素人にすぎない芸達者たちの領分だということでしょう。
これを芸能人と換言してもかまいません。実際、島村抱月による演出を拠りどころに新劇の舞台に立っていた松井須磨子による〈復活唱歌〉(1915)の歌声は、いまなおこうした観点についていかにも雄弁です。正統の音楽から疎まれ、軽蔑された徒花。
結局のところ、大衆音楽とは、たとえ古典音楽の素養ある上手の歌声をもって歌唱されたとしても、生来的にそれ自身が下手だったのです。流行歌のある一定の歌い手の歌唱について、聞き手の側がその巧さや旨さを、上手さをあれこれもてはやし、あるいは歌い手の側がこれを誇示することとは、だからそもそも倒錯かつ不毛なのであって、大衆音楽は、流行歌は、歌謡曲とは、いってみればそれ自体が生まれながらに下手なのです。
洋楽/邦楽
歌謡曲は、日本のレコード産業がそうであったように、当初からアメリカ合衆国における大衆音楽の影響を強く被り、これを吸収し、消化しながら、古典的な西洋音楽とは別のなにかへと自らを展開していきます。歴史の浅い新大陸にあって、民主主義と資本主義を根幹としつつ、由緒ある旧大陸の権威的な芸術とは異なる自由な価値観を体現しえたアメリカ合衆国のありようが、長い歴史をいったん棚あげにした日本の近代化と親和的であったことも、おそらくそれと無縁ではないはずです。
アメリカ合衆国の文化的な価値観は、映画やレコードをはじめとした複製技術およびその電化をとおして、日本のみならず世界中を侵略していきます。生演奏において本領が発揮されるよう鍛錬されてきた旧大陸式の古典音楽の真髄とは本質的に異なるばかりか、まさに低俗にして下卑、堕落的にして退廃的であるがゆえの欲動的にして扇情的な魅惑が、いまや高尚かつ上品を旨とする禁欲的な価値観を機能不全に陥らせようとしています。
物量と率直さに頼んだ新大陸式の快楽主義的な流儀は、旧大陸の芸術様式を上手としてきた従来のヒエラルキーを宙吊りし、もしくは脱臼させるような、新世紀にふさわしい新しい上手を出来させました。その勢いに憧れ、歌謡曲もこれに範をとります。ジャズにはじまり、ラテン音楽からハワイアン音楽、戦後にはカヴァー・ポップスから和製ポップスにいたるまで、歌謡曲は自分なりの仕方でその魅惑の秘訣に触れようと試みてきました。
しかしながら、アメリカ合衆国の大衆音楽の枠組みを輸入し、範としたがゆえに、今度はこれを上手とするヒエラルキーの下手に歌謡曲が抑圧されることはもはや自明です。
とりわけ歌唱については、歌詞においてどうしても日本語の使用を考慮せざるをえない特殊な事情が足枷となって、表現の観点から律動や音響にきわめて不都合な制約を被ることは不可避です。欲動と扇情に率直な快楽主義の魅惑に対して、それへの無批判的な熱狂を諌め、冷静を勧奨するかのように母音が音節を均等に分割する日本語の等時拍とは、輸入元の大衆音楽では肝要だったスウィング感やグルーヴ感の昂揚に対して、輸入先となった東洋の島国で言語が穿つ吃りにちがいありません。
歌謡曲は、音楽的な構成要素や演奏様式それ以前に、あらかじめ英語という言語それ自体のうちに孕まれたスウィング感やグルーヴ感を禁じられました。それでもなお、新大陸の大衆音楽の本質を無媒介的に享受し、味わうことのこの不可能性こそが、歌謡曲にあってはむしろ創造的に機能し、その影響の甚大さにもかかわらず、これを固有の音楽へと駆動していく因子ともなります。
本来から下手だった大衆音楽のうち、わけても下手たらざるをえない歌謡曲の歌い手たちによる歌唱の技法や技巧の工夫は、いったん輸入品を換骨奪胎しつつ、これを次第に自分たちの文化風土にそって血肉化していきました。
上手/下手
そうしたなか、たとえば弘田三枝子が吹き込んだ〈ヴァケーション〉(1962) や〈砂に消えた涙〉(1964)における歌唱などは、原曲との比較にもとづく上手さと下手さの二項対立的な関係性を転倒し、または無効化するほどの独自性を謳歌します。
古典音楽の素人として、これを上手とするヒエラルキーにあっては下手となり、また新大陸の大衆音楽の素人として、これを上手とするヒエラルキーにあっても下手となった日本の大衆音楽のレコード歌手は、いま、まぎれもなく歌謡曲の玄人として存在します。そうした彼ら彼女らの歌唱を、旧来の諸ヒエラルキーを前提とした二項対立的な尺度で測ってみたところで、状況を正確に評価することはできないはずです。
加えて、とりわけビートルズの登場がそれを標榜して以降、若者たちの、若者たちによる、若者たち自身のための音楽が、フォークやロックを象って世界の市場を席巻します。日本も例外ではありません。グループ・サウンズに端を発する一連の潮流は、1970年代をまるごと費やしながら、人生の素人としての若者たちを歌謡曲の主流のうちに組み込んでいきます。
要するに、それは職業としての素人の音楽であり、素人の玄人たらんとする音楽を意味します。このころ、それまで銀幕のスターを生産してきた映画からブラウン管のタレントを重宝するテレビへと、視覚メディアの基軸が移行したことも、その背景で誘因となったにちがいありません。
ブラウン管のタレントとは、すなわち芸能人です。お茶の間で寝転んで音と映像を受容できるテレビの気やすさ、気軽さは、ブラウン管の番組を家族で共有し、家庭の出来事として親しむことを許容します。目鼻立ちの整った手の届かないスターが暗い映画館のなかで銀幕を輝かせるアウラの眩さに、ただただ夢に惚けたように圧倒されるよりほかなかったかつての観客は、ここでテレビの視聴者として、芸能人を隣人のごとく扱います。
TBS系列で放送された『時間ですよ』で“隣のマリちゃん”や“隣のミヨちゃん”としてお披露目され、のちにレコード歌手としてデビューする天地真理や浅田美代子といったアイドルの事例がその典型でしょう。
そのとき、視聴者には、おそらく誰でもかまわなかっただろうひとりの隣人の娘が愛らしく成長するさまを優しいまなざしで見守り、ともに生活することが求められています。仮にこれが、当人でなければそのアウラを発しえない銀幕のスターのように、直視することも憚られる完成された美人であっては、テレビを迎えたお茶の間の側の、蛍光灯に青白く照らされた貧相さばかりがきわだってしまうわけです。
もはや歌唱は、ただの歌声、彼ら彼女らがテレビを介して話し、語り、囁く声の延長でしかありません。歌唱のために技巧を研鑽することは、むしろブラウン管とお茶の間のあいだで曖昧に横たわる境界を鮮明に屹立させ、テレビのなかの出来事を虚しく隔離することは必然です。
聞こえる/聴かせない
歌が、歌唱が下手であること。
音程については、そもそも音程を正確にとれないいわゆる音痴をはじめ、正確な音程の位置に声帯を維持できないことによる音程の揺れもあるでしょう。グリッサンドで音程を探ったり、ビブラートで音程をごまかしたり、下手と聴かせない工夫も一種の技巧といえるかもしれません。
音域の狭さや肺活量の少なさ、音価の感覚に鈍いリズム音痴も歌唱の下手さに関与しますが、よりいっそう歌唱における下手さの印象を左右する要素として、やはり声質そのものの貢献は重大です。まさに身体的な個性というほかない発声や発音の具合い、呼気の強弱に抑揚を欠いた声の平坦さ、輪郭の不明瞭にこもった抜けの悪いモコモコの声、もしくは極端な周波帯域における成分の尖ったキンキンの声。
逆にいえば、多少は音域が狭かろうが音程が怪しかろうが、声質次第でその歌唱は実力にも増して良好な聞こえかたをするものです。栗田ひろみによる〈太陽のくちづけ〉(1973)や川田あつ子による〈哀しみよ今日は〉(1982)など、そうした事例はまれではありません。
歌唱を隠蔽して下手さを聴かせないために、あるいは少なくともそれをまろやかに聴かせるために、音源の制作者たちは、さまざまに手練手管を駆使してきました。
コーラスやハモりの声を必要以上に大きく調整し、そこにレコード歌手の歌声を埋没させる試みは、その最たる対処法でしょう。大村雅朗が編曲した能勢慶子の〈海の妹〉(1979)や〈新しい予感〉(1979)をはじめ、ビューティ・ペアの〈真赤な青春〉(1977)やひかる一平の〈青空オンリー・ユー〉(1981)がその効用を響かせています。もちろん、楽器群の演奏音をもって同様の効果を期待する場合もあります。
レコード歌手による歌唱にそって楽器が主旋律を奏でること、より正確には、楽器が奏でる主旋律をたどるようにレコード歌手が歌唱することも、編曲家が考慮する対策のひとつです。これを露骨に示せばカラオケまがいの駄曲となるところを、田原俊彦が発表した〈さらば‥夏〉(1983)では主旋律の要所のみいくつかの楽器に分散して奏でられ、それと意識させることはほとんどありません。ここでは、歌唱における不安定かつ不正確な音程に楽器の正確な演奏音をあてて、これらをひとつの音塊の成分のごとく響かせる魂胆もあったはずです。
究極的には、歌唱をもって再現すべき音程をなくしてしまうこと、すなわち、歌詞のかわりに台詞として語りを採用することも選択肢となります。栗田ひろみによる〈愛の奏鳴曲〉(1974)や伊藤つかさによる〈もう一度逢えますか〉(1982)、田原俊彦による〈ジュリエットへの手紙〉(1981)や近藤真彦による〈ブルージーンズメモリー〉(1981)などにあっては、おそらくそれは、歌手としての歌唱のみならず俳優としての演技もこなすタレント性を逃げ口上とする彼ら彼女らの、ある種の免罪符の機能を遂行します。
聞く耳/聴く心
なるほど、財津和夫は、たとえば〈チェリーブラッサム〉(1981)の松田聖子に対してそうだったように、〈秘密のオルゴール〉(1982)の川田あつ子にも、歌唱する当人の声域からすれば無理があるような高低の幅で音程を旋律に配分しています。おそらくこれは、チューリップを率いて自作自演で活動してきた彼にとって、作曲家としての挑発というよりはむしろレコード歌手としての矜持がそうさせたように思われます。
編曲のみならず作曲者としても大場久美子の楽曲に多く関与した萩田光雄は、彼女たちアイドル歌手においては、歌唱はもちろん、ルックスも含めて存在性のまるごとが魅力であることを指摘し、ここから歌唱の上手い下手のみを故意に抽出して問うことの不毛さを喝破しています。
〈あこがれ〉(1977)であれ〈大人になれば〉(1978)であれ、大場久美子にとっては、単に音盤のうちにパッケージ化された歌唱ばかりが商品なのではありません。きっとそれは、ひとりの娘の愛らしさを謳うことによって、持続する全体としての彼女の存在性との邂逅を叶える旅券となるような魔法の呪文、その響きだったにちがいなく、もっぱらこれが楽曲や歌唱の体裁で世界に預けられたにすぎないのです。
ただし、萩田のこうした見解は、レコード盤やブラウン管の裏側でアイドルたちの無防備な私性に一瞬ではあれ接し、その人柄を知りえた制作者たちの、聞き手に対する優越的な立場をもって担保されるものです。これに触れる機会がせいぜいのところコンサートや握手会といった程度でしか保証されない一般の受け手の側が、その存在性の評価にはあくまでも大衆メディアを介して一定の制約を被らずにはいないこと、にもかかわらず、まぎれもなくそれが受け手の側にとってのアイドルたちの存在性の全体であること、この事実については留意されるべきでしょう。
だからこそ、大場久美子なり浅田美代子なり、アイドルそのひとが親しみやすい普通の女の子であることと、たとえばメディアを介して表現された“隣のマリちゃん”や“隣のミヨちゃん”の親しみやすさとは、けっして等価ではありえません。
近藤真彦と田原俊彦のどちらにも楽曲を提供しながら、近藤よりも田原にこそ、筒美京平は難曲をあてがっています。これは、近藤の歌唱力をめぐって、歌いこなせるか否かの境界線を画すことの可能な、いわば相対的な巧さ/拙さが彼の存在性を差配しうるのに対して、田原の場合には、技術的に歌唱の容易な楽曲であれ困難な楽曲であれ、結局のところ同じように聞こえるがゆえに、自らの歌唱をそうした二項対立から逸脱させてしまいます。
このことは、彼の歌唱が、上手が下手であり下手が上手でもあるような状態、もしくは上手と下手とが歌唱を契機として分化するより以前の根源的な状態のまま、ある存在性に本質的な絶対の位相にあることを示唆します。
巧拙をめぐる難易が意味をなさず、さらにいえば歌の本当はそれら巧拙を超えて伝わるものであることを、おそらく筒美は明確に理解していたのであり、こうした認識が、この作曲家を一世一代の歌謡曲の天才たらしめたのかもしれません。そしてそれだからこそ、筒美京平は、小林麻美には〈初恋のメロディー〉(1972)を、浅田美代子には〈赤い風船〉(1973)を、太田裕美には〈木綿のハンカチーフ〉(1975)を、斉藤由貴には〈卒業〉(1985)を、内田有紀には〈明日は明日の風が吹く〉(1995)を、驚くほど端正にして適切なかたちで提供しえたわけです。
これらの楽曲は、彼女たちの歌唱の巧みさをもって聞くものを感心させるわけではまったくありません。そこにあるのは、歌唱の巧拙をめぐる評価ではなく、まさに彼女たちによる歌唱そのもの、この歌唱それ自身の存在性なのです。ここでのそれらのありようは、演奏音もろとも楽曲をその都度の肌理に織り込み、音響的な持続となって聴くものの胸を刺し、琴線を共鳴させ、こうしてひとつの全体のうちに組み込まれた心は、なすすべもなくこれに動揺するばかりです。
耳で聞くこと、それは、心で聴くための門を開けることにほかなりません。ところが、歌唱の巧拙に惑わされ、いったんこの門を閉ざして聞くことを放棄すれば、その瞬間に、心で聴く機会もまた手放されてしまうのでしょう。
みなさんは歌が上手ですか?
私の「下手ですけど、なにか?」5選リスト
1.〈初恋のメロディー〉小林麻美(1972)
作詞/橋本淳,作曲・編曲/筒美京平
〈渚のうわさ〉にはじまり、筒美京平が弘田三枝子に提供した〈枯葉のうわさ〉から〈涙のドライヴ〉を経て〈渚の天使〉に至る一連の楽曲群の系列は、それぞれの題名が順列組み合わせの陳腐さをまとう一方で、曲調の多彩さをもって彼女の歌唱の万能さを誇示し、この歌い手の圧倒的な才覚のあまり筒美をしてさえ焦点を絞りきれていないかのような印象を与える。そして、漣健児の訳詞による弘田の傑作〈砂に消えた涙〉を踏まえ、それゆえもっとも弘田三枝子に似つかわしい〈渚のうわさ〉を除く以降の3曲について、筒美は、〈枯葉のうわさ〉を〈ブルー・ライト・ヨコハマ〉に展開していしだあゆみに、〈涙のドライヴ〉を〈初恋のメロディー〉に展開して小林麻美に、そして〈渚の天使〉は〈真夏の出来事〉に展開して平山三紀に、各々の曲調にかなう歌唱を提示する3人の歌い手にひとつずつ配分するかたちで後継させている。とりわけ〈涙のドライヴ〉の曲調は、弘田が口先で囁くように歌ってなお、線が太く力強い彼女の歌唱にとってはどれほどか繊細にすぎるように感じられる。他方で、筒美京平は、小林麻美のような女性アイドル歌手の歌唱をえて、むしろこの路線の曲調を彼のひとつの商標的な様式にまで昇華させていく。その情緒にふさわしい言葉を綴る作詞家となれば、やはりそれは橋本淳よりも松本隆ということになるだろう。
2.〈ハッとして!Good〉田原俊彦(1980)
作詞・作曲/宮下智,編曲/船山基紀
これだけの難曲を、デビュー曲〈哀愁でいと〉の大ヒットの次にシングル盤として発表できたのは、なんといってもジャニーズ事務所のアイドルとしての田原が背負っていた当時の気運に対する制作者たちの確信によるものだろう。ロック調に歪んだエレキギターがイントロでソロを奏でた短調のデビュー曲のものとは異なり、ビッグ・バンド編成のジャズ風の、どこか大人びた船山基紀の編曲の洗練も、むしろ〈哀愁でいと〉の曲調を継承した近藤真彦の〈スニーカーぶる〜す〉の若々しい勢いを、いまではずいぶん幼稚に感じさせてしまう。いきなり“ラ-ソ#-ラ-シ♭-ラ”と半音が連なる歌いだしでは裏打ちのリズムでアクセントが置かれていた旋律が、「高原の Telephone Box」の箇所でにわかに表打ちに変わり、しかも“ko-o-ge”と“no-te-re”が同じ音程を繰り返すなか「Box」の響きが字余り的に嵌め込まれるなど、一聴しただけでは覚えきれない癖のある抑揚と進行を、田原のフニャフニャな歌唱はやんわり受け流し、けっして正面からこれを受け止めようとはしない。聴くものを宙吊りにしたまま、足を着ける地面を掠めとっていく彼の歌唱の浮遊感もまた、歌謡曲の醍醐味であり、この味わいを安易に論難することを諌めるその深みを示している。
3.〈マイ・ボーイフレンド〉北原佐和子(1982)
作詞/堀川マリ,作曲・編曲/梅垣達志
“花の’82年組”でありながら、あるいはむしろそうであったがゆえに、制作者側の期待に比して大きくブレイクすることはできなかったものの、しかしこのデビュー曲が稀有の傑作であることは疑いない。好き嫌いは別にして、誰がみてもかわいらしく整ったその顔立ちについては、たとえばいまの時代に当時のままデビューしたとしても、おそらく受け手に同様の印象を与えることだろう。“花の’82年組”にあっては、中森明菜、川田あつ子、そしてこの北原佐和子が、群雄割拠の女性アイドル陣のなかでもとりわけそうしたルックスに恵まれていた。にもかかわらず、川田も北原も不遇のままアイドル活動を終えたほか、中森明菜さえがデビュー直後はさほど話題となっていなかった事実は、アイドル歌手が必ずしもルックスだけで評価される存在ではないことを示唆する。
4.〈秘密のオルゴール〉川田あつ子(1982)
作詞/松本隆,作曲/財津和夫,編曲/萩田光雄
アイドル歌手としてはシングル盤を2枚、そのA面とB曲のそれぞれをあわせて正確に4曲しか発表していない川田あつ子は、それでもなお、この4曲すべてが名曲であるがゆえに、これらの楽曲を耳にするその都度、歌謡曲にとって歌唱とはなにか、歌唱にとって上手/下手とはなにか、そう聴き手は自問せずにいられない。声域の狭い川田に対して明らかに低く、そして高い音が使われ、わけても最高音はサビの最後に全音として声を張る局面で登場する。かつて〈白いパラソル〉で同様の試練で松田聖子に挑んだ財津和夫だが、このときの作詞家も松本隆だったことは、彼女たちに共通するなにごとかを感知したCBSソニーによる川田への期待の証左かもしれない。
5.〈話しかけたかった〉南野陽子(1987)
作詞/戸沢暢美,作曲/岸正之,編曲/萩田光雄
松任谷由実の〈DESTINY〉および荒井由実名義の彼女が三木聖子に提供した〈まちぶせ〉を足して割ったような歌詞の世界観。たとえば〈DESTINY〉の松任谷による「安いサンダル」は、ここでは「はねた髪」であるだろう。加えて、その「はねた」感覚は、楽曲の全体をとおしてシャッフルのリズムとして維持される。歌謡曲らしくBパートが加えられているものの、イントロをはじめ曲調の下敷きとして、ほぼ確実にThe Monkeesの〈Daydream Believer〉が念頭に置かれている。
番外_1.〈太陽のくちづけ〉栗田ひろみ(1973)
作詞/山口あかり,作曲/森田公一,編曲/馬飼野俊一プ
抜けがよく澄んだ、しかしわずかに舌足らず気味の歌声は、旋律を構成する正確な音程から少々ずれてみても、この歌い手に対する好感を削ぐものではない。とはいえ、この恵まれた声質が逆に音程の所在を明瞭化することにも貢献するわけで、彼女の歌唱における音程の不安定さが、その声質をもっていっそう顕在化し、強調される傾向をともなったとすれば、それは栗田にとって幸運だったのか、それとも不幸だったのか。
番外_2.〈鳥の詩〉杉田かおる(1981)
作詞/阿久悠,作曲・編曲/坂田晃一
西田敏行が歌唱した〈もしもピアノが弾けたなら〉を主題歌に日本テレビ系列で放送された『池中玄太80キロ』の挿入歌として、西田の長女役で出演していた杉田かおるによる佳曲。主題歌と同じ阿久悠と坂田晃一のコンビの提供曲であるうえに、ともに俳優を本業とする西田と杉田の歌唱でもあること、さらにこの楽曲の最初の披露がドラマのなかでの西田による歌唱だったとされることからも、両曲の密接さは疑いようがない。なお、杉田の歌唱で吹き込まれたレコード盤の発売は、同世代の若手アイドル女優だった伊藤つかさのデビュー曲〈少女人形〉や薬師丸ひろ子のデビュー曲〈セーラー服と機関銃〉の発売よりも早い。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





