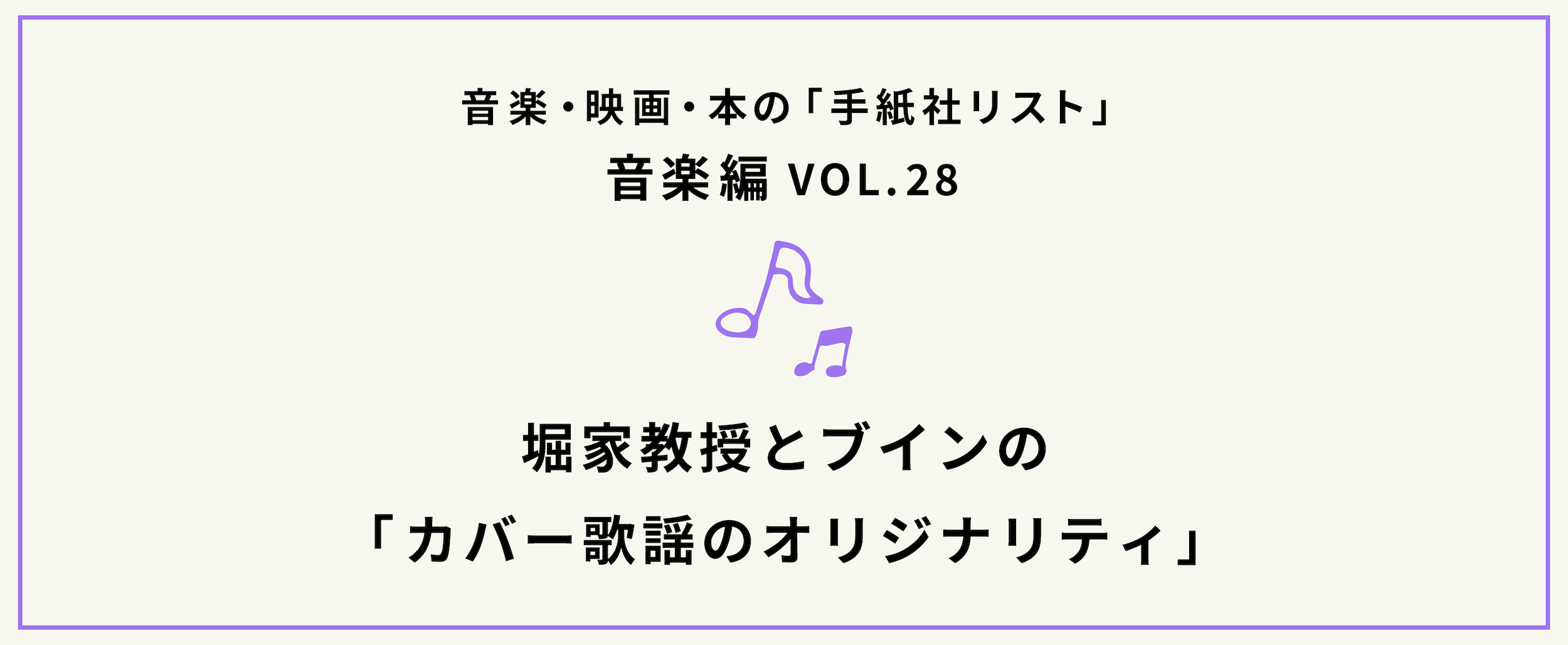
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。28回目となる音楽編は、「カバー歌謡のオリジナリティ」というテーマでお届けします! まずは手紙社の部員さんが選んだ10曲、そして堀家教授のコラム、その後に堀家教授が選んだ10曲と続きます。
手紙社部員の「再びの歌謡曲」10選リスト
1.〈なんとなくなんとなく〉つじあやの(2004.05/原曲:ザ・スパイダース 1966.12)
作詞・作曲/釜萢 弘,編曲/(林 一)
それこそ「なんとなく」気楽に聞いて長年楽しんでる曲です。この曲がカバーだと知ったのはムッシュかまやつさんが亡くなられたニュースでだったと思います。原曲の好きな女性への愛しさあふれる雰囲気にびっくり。とてつもない発見をした気分でした。つじあやのさんカバーは、広い意味でのあらゆる好きが詰まっている感じがとても気に入っています。わたしも、好きな人・物・ことに囲まれてじんわり幸せを感じる人生でありたいです。
(さっぽん)
2.〈悲しくてやりきれない〉コトリンゴ(2010.09/原曲:ザ・フォーク・クルセダーズ 1968.03)
作詞/サトウ ハチロー,作曲/加藤 和彦,編曲/(ありた あきら)
オリジナルは1968年にザ・フォーク・クルセダーズがリリースした楽曲です。一見、自然の風景を眺めてただ嘆きを綴っただけの歌詞ですが、作詞を手がけたサトウハチローさんは、広島の原爆で弟さんを亡くされ、当時晴れ渡る青空の下で亡骸どころか遺品ひとつ見つけられなかった、なんともやるせなく悲しい体験をされています。
広島の街・呉に1人お嫁にやってきたすずさんが戦火の足音が徐々に忍び寄り困難に直面する中、それでも続く毎日を生きていく姿を描いた、2016年公開の劇場アニメーション「この世界の片隅に」。〈悲しくてやりきれない〉を以前リリースしたアルバムでコトリンゴさんが歌っていたことから、前作の映画でご縁のあった片渕須直監督がこの映画のオープニングテーマとして採用し、そのまま劇伴や主題歌も彼女が手がけることとなりました。
元々こうの史代さんの原作を何度も何度も読んでいて、映画の予告編を見た時、唯一のカバー曲でありながら1番しっくりきた曲だったのです。自分の力ではどうにもならない、やりきれなさ、苦しみ、悲しみ、モヤモヤ…人からしたら瑣末な出来事かもしれませんが、年を重ねて幾度となく経験しました。どうしようもなく悲しみに覆われてしまって…
それでも自然は眩しすぎるほど綺麗で、それでも毎日は過ぎて行く。この歌の中では、悲しみは癒されません。優しく包むような歌声やメロディーは、むなしさが救われる術を、教えてくれるわけでもありません。答えも出口もありません。ただただ、しみじみと嘆く。それでいいのだと、思わせてくれました。風に吹かれ、澄み切った空を眺め、木漏れ日の中で、言い知れぬ悲しみを抱えながらもそれでも日々を、生きていく。私という人間の生きる道と、あの日の広島に生きたすべての人々にそっと寄り添ってくれたこの曲に、心からの感謝を。
(ひよこちゃん)
3.〈結婚しようよ〉ハンバートハンバート(2016.06/原曲:吉田 拓郎 1972.01)
作詞・作曲/吉田 拓郎,編曲/(加藤 和彦)
私がハンバートハンバートを好きになった頃、たまたまこの曲を家族とのドライブ中に流したところ、一緒に車に乗ってた両親が急に「ふふんふーん」と揃って鼻歌を唄ってきました。原曲を知っていた両親、ハンバートハンバートで知った私。なんだかほっこりしたドライブになり、更にこの曲が好きになりました。ふふんふーん♪
(なかざわ)
4.〈また一人〉九重祐三子(1972/原曲:Gilbert O’Sullivan 1972)
作詞・作曲/Gilbert O’Sullivan,日本語詞/なかにし 礼,編曲/横内 章次
コメットさん。60年代生まれの夫だと九重佑三子。70年代生まれの私だと大場久美子。そんな60年代コメットさんの歌う、70年代ポップスの日本語カバー曲、歌詞はあの、なかにし礼です。原曲は、軽くて聞きやすいメロディに対して、男性が婚約者や家族の愛や死に対して歌う、ちょっとヘビーな内容です。
対してこちらは女性が失恋を繰り返す内容。メロディの軽さに訳詞を合わせたようで、原曲のヘビーさはなし。しかしながら「また一人」という端的な表現が、〈Alone Again〉という言葉の解像度をむしろ上げていると思い、今回推薦しました。あとこの曲は出だしが「私としたことが」という歌詞で、それがオモロイとメディアで話題になった時期があったようです。恋多き女性とか商売をしている女性とか解釈は様々あるようですが、私としては、この女性は幼少期から孤独で、一人で生きていくと自覚していたのに、うっかり愛にハマってしまって「私としたことが」と不覚だった心境、と解釈しています。
(手芸愛好家)
5.〈まちぶせ〉石川ひとみ(1981.04/原曲:荒井由美 1976.06)
作詞・作曲/荒井 由実,編曲/松任谷 正隆(松任谷 正隆)
石川ひとみさんのヒット曲〈まちぶせ〉。こちらをオリジナルだと思っている方も多いと思います。幼い頃、テレビ番組でポニーテールのとてもきれいな方を見た記憶があります。その方は、三木聖子さん。その三木聖子さんが当時歌っていたのがこの〈まちぶせ〉です。記憶がうっすらなので、歌唱していたシーンを覚えていません。ですが、石川ひとみさんがこの曲を出された時に『あぁ、三木聖子さんのカバーだなぁ』とすぐにわかりました。石川ひとみさんのかわいらしい声、ていねいに歌い上げていますが、歌の中の主人公のしたたかな、今でいうとあざとい、心の内側を描いています。
作詩作曲はユーミンこと荒井由実さん。ユーミンがほかの方の提供した、例えば麗美さんの「青春のリグレット」なども主人公のそういう心の内側を描いていて、時代を超えて聴いてみても、ユーミンってすごいなぁ、と思います。カバーといっても、この『まちぶせ』はオリジナルよりずっとヒットしていますし、オリジナルが埋もれてしまうところをこうして多くの人に届いて、歌い継がれていくのもカバーのいいところかも知れません。
(あさ)
6.〈タイム・トラベル〉 スピッツ(2012.02/原曲:原田真二 1978.04)
作詞/松本 隆,作曲/原田 真二,編曲/SPITZ,亀田 誠治(原田 真二)
スピッツの新曲、と言われても分からないくらい、歌詞の世界観や草野さんの歌声がしっくりきているこちらの曲。新曲と思い込んでウキウキ気分で聴いてる私の横で、「えー!すごい懐かしい!」と、原田真二さんの大ファンだった母が私より嬉しそうに聴いていたのが印象的でした。原曲そのままの曲調ですがスピッツの色があちらこちらにあり、聴き比べると「ここはこんな風にカバーしてる!」と新しい発見があります。そして、この曲をきっかけに原田真二さんを聴いたら甘い歌声にすっかりハマってしまうという、親子で似た趣味なことが判明した一曲です笑
(しまえなが)
7.〈セクシー・ユー〉郷ひろみ(1980.01/原曲:南佳孝 1979.04)
作詞/来生 えつこ,作曲/南 佳孝,編曲/萩田 光雄(坂本 龍一)
郷ひろみさんの〈セクシー・ユー〉ってカバーだったんですね。オリジナルはあの南佳孝さんの〈モンロー・ウォーク〉。実は今回初めて聴きました。手放しで陽気になれるヒロミゴーの軽いノリが好きなのですが、オリジナルの方が断然セクシーユー。歌詞は2番以降は新たに書き下ろしされているとか、郷のファン層はモンロー・ウォークの語源を知らないだろうからということでレコード会社がタイトルも変更したとか、、、カバーにもいろいろあることを知りました。南さんの原曲はプライベートビーチを連想させる大人の雰囲気。郷さんのカバーはスティールパンの音も加わった事で一気にプライベート感は薄れ、大衆リゾート的ギラギラが増し、聴く人の脳裏にグッと身近な雰囲気が広がった感もヒットの要因なのかなと思いました。
(大分の共子)
8.〈異邦人〉EGO-WRAPPIN’(2013.04/原曲:久保田早紀 1979.10)
作詞・作曲/久保田 早紀,編曲/(萩田 光雄)
数年前久し振りにEGO-WRAPPIN’を聴くことがあり、いくつかの楽曲を聴いた後このカバー曲に辿り着きました。EGO-WRAPPIN’によって作られる他にはない独特なサウンドが、違和感なく原曲に浸透して、原曲とはまた違う、気だるげな中に品が含まれた雰囲気が魅力だと思います。〈異邦人〉はどのアーティストもカバーしていますが、原曲が際立ちカバーする歌手をかすめてしまう曲だと感じます。カラオケでもどうやって自分の物にして歌い切ろうか毎回悩みます。
(アラさん)
9.〈フライデイチャイナタウン〉BENI(2022.08/原曲:泰葉 1981.09)
作詞/荒木 とよひさ,作曲/海老名 泰葉,編曲/(井上 鑑)
この曲の思い出は、一昨年、あるSNSで知って、なんていう歌だろうって思い、Shazamっていうアプリで検索して知り、お気に入りに登録して、時々、聴いています˖*♬೨̣̥
(里央)
10.〈今夜はANGEL〉椎名恵(1986.01/原曲:Fire Inc. 1984.05)
作詞/Jim Steinman,日本語詞/椎名 恵,三浦 徳子,作曲/Jim Steinman,編曲/戸塚 修
「ヤヌスの鏡」と言うドラマの主題歌。「ストリートオブファイヤー」という映画の作中歌〈Tonight Is What It Means to Be Young〉のカバーだそうです。この映画は観てないなぁ、やっぱり観ないとだよねえ。曲のはじまりの「ジャーーン!」のところがカッコいい! 「涙隠す瞳に勇気がみなぎるまで」という歌詞がカッコいい、椎名さんの歌声がカッコいい✨ ちなみに「ヤヌスの鏡」は中学生の夏休みにテレビで再放送されてたのを見ました。おばあさま、怖い!!
(ゆうこスティーブ)
カヴァー歌謡のオリジナリティ
オリジナル
大衆音楽の歴史において、ある楽曲にオリジナル/カヴァーの区分を設けることは、すなわち誰がそれを歌唱ないし演奏しているのかを問うことにちがいありません。そして当該の楽曲を最初に発表した歌唱者ないし演奏者、それがオリジナルの主体となるわけです。
ただしここでの発表とは、おおむねレコードやCDなど、音響的な再現を可能にする記録媒体をもって、原理的にはいつでも誰でもそれを聴くことのできる状態で公表されることを意味します。より厳密には、ラジオやテレビでの放送や舞台での上演をとおして、記録媒体を介することなく生で披露される歌唱や演奏、さらには映画の上映をとおして観客の耳にさらされた挿入歌などの事例は考慮しえます。
たとえば、西條八十と服部良一の詞曲による傑作〈蘇州夜曲〉(1940)について、霧島昇と渡邊はま子の歌唱をもって最初に発表されたレコード盤は、これに先行して映画作品『支那の夜』(1940)の主演の李香蘭が劇中で同曲を歌唱しているシークェンスをオリジナルと措定し、それを吹き込みなおしたカヴァー版として扱われることがもっぱらです。
それでもなお、仮に蓄音機以前に大衆音楽が可能だったとして、歌唱や演奏そのものを記録するすべがない以上、歌唱や演奏ではなく、そのもとにある、もしくはそこから採録された楽譜こそが楽曲でありそのオリジナルだったはずです。ここでオリジナルの身分を主張できる権利者とは、あくまでも作詞家や作曲家、およびこれを最初に楽譜として発表した出版社のみでしょう。極論すれば、そこでは歌唱者や演奏者は譜面の音符を実際の音声へと変換する任意の再生者であり、いわばレコード・プレイヤーのような再現装置の座に位置するにすぎません。
ある楽曲におけるオリジナル/カヴァーの区分は、歌唱や演奏を保存し、音響的な持続として再現できる媒体の登場をもって成立します。印刷物としての楽譜の位相には、複製や模倣、剽窃といった概念は適用できますが、カヴァーの概念は成立しえないのです。
蓄音機の功績、それは、作詞者や作曲者がインクの染みとして紙面に記すよりほか遺しようのなかった楽曲を、歌唱者や演奏者による音声と密着させ、音楽を音響的な持続そのままに大衆化してみせたことにあります。
こうしていったん楽曲と密着した最初の音声とその主体、それがオリジナルの歌唱者ないし演奏者であり、その音声をもって発表されたレコードやCDがオリジナル盤となります。こののち、その楽曲に密着していた特定の音声とは異なる音声の主体による歌唱や演奏をもって響くとき、私たちはそれをカヴァー曲とみなすでしょう。
大衆音楽の流通が多様な音声メディアをもって実現されるなか、それが生演奏か記録の再生かはさておき、いまや楽曲は、およそ音響的な持続として直接的に聴かれています。そのような響きそれ自体が楽曲と等価といって過言ではないこんにち、ある楽曲といったん密着した特定の音声をこの楽曲から剥がすことは容易ではありません。
多くの聴衆の鼓膜を馴致したいわゆるヒット曲の場合、歌唱や演奏の音声は楽曲の表面に固着しているどころか、むしろその屹立を支持し、構造を差配する当のものでさえあるだけに、ひとたびこれを刷新しようとするならば、その組成から丁寧にほぐしていかなければならず、困難はなおさらです。
カヴァー
にもかかわらず、これまで多くの楽曲がカヴァーされてきたのはもちろん、いまなおけっして少なくない数のカヴァー曲が発表されつづけています。
とりわけ日本においては、歌謡曲の歴史はカヴァーの歴史と無縁ではいられません。というのも、歌謡曲の歴史とは、維新を契機に明治政府が採用した欧化政策の一翼を担って導入された西洋の音楽体系の、新しい日本社会における消化と普及の過程にほかならないからです。
にわかに直面した西洋の音楽体系を導入するにあたって試みられた施策、それは、なによりもまずそれをカヴァーすることでした。
新しい音楽体系の導入にあたって日本政府から西洋に派遣された役人たちは、現地で音楽教育を授かるとともに、もっぱら西洋の歌曲や民謡、讃美歌の類いを、楽譜の収集をもって母国に紹介しました。
なるほど、楽譜に対してカヴァーの概念はそぐいません。しかしながら、ここではたとえば〈Auld Lang Syne〉を歌い継いできたスコットランドをはじめ西洋の人びとの音声一般、その歌唱一般をオリジナルとして、当時の日本人の音声ないし歌唱一般は、稲垣千穎によるさほど忠実ではない日本語の翻訳詞をもって、これを〈蛍の光〉の名のもとカヴァーしたわけです
まして音声の保存や拡大伝播の技術が確立し、蓄音機やラジオ放送、トーキー映画をとおしてジャズのリズムが世界を賑わせるころともなれば、日本で最初にヒットしたジャズ・ソングとされる〈あほ空〉(1928)が、ジャズの本場で大ヒットしていた〈My Blue Heaven〉(1927)の音盤の、堀内敬三の訳詞をえた二村定一と天野喜久代の歌唱によるカヴァー版であったとしても、もはやなんの不思議もありません。オリジナルの精神に近づき、その真髄に触れるためのもっとも原初的にしてもっとも有効な手段、それがカヴァーなのです。
こうした傾向は、低俗で浮薄で扇情的な敵性文化としてジャズを中心に西洋式の大衆音楽を攻撃した太平洋戦争の抑圧から解放され、文化的支配の観点から著作権の適用を弛緩させたGHQの方針による後援もあって、1950年代の後半から1960年代の前半にかけて日本の歌謡界における“翻訳ポップス”の流行のうちにきわまります。
“カバーポップス”とも称され、小坂一也から平尾昌晃、ミッキー・カーチス、山下敬二郎、あるいは坂本九や中尾ミエ、伊東ゆかりらの歌声に、そして漣健児の奔放な日本語詞に彩られるこの時期の一連の歌謡曲は、まさしく日本語で書きなおされ、日本語で詠み換えられた、最良のアメリカ文化の安価な翻訳、そのミニチュア的模像であり、どこか卑屈に矮小化されたそのカヴァー版でした。
戦後の困難な状況にあって、そもそもオリジナルを創作する担い手が不足していたことも一因ではあれ、オリジナル性への希求がいかにも脆弱すぎたことへの杞憂は、中村八大の成功を準備します。西洋の音楽体系を基本としながらも、単なる西洋の模倣ではなく日本の風土や情緒にかなった固有の大衆音楽をかたちづくることをめざし、高度経済成長と歩調をそろえて“和製ポップス”を牽引した彼の功績については、なにより坂本九に提供された〈上を向いて歩こう〉(1961)が雄弁です。
オリジナル性
加えて、著作権の適用が次第に厳格さを増していくなか、“翻訳ポップス”の衰退は不可避でした。にもかかわらず、ただひとり〈ヴァケーション〉(1962)の弘田三枝子の歌唱だけは、そうした枠組みを突き抜けて響く強度を維持していました。カヴァー曲でありながらオリジナル曲を凌駕するほどのオリジナル性を力強く訴える彼女の歌唱は、中村八大にも比肩する貢献を歌謡曲に提供します。
とりわけ、イタリアでミーナが発表した〈Un Bucco Nella Sabbia〉(1964)をオリジナルに、めざとくも漣健児が日本語詞をあてがって吹き込まれたカヴァー版〈砂に消えた涙〉(1964)は、のちにこの版をめぐって麻丘めぐみ、安西マリア、小林麻美、北原佐和子、竹内まりやらがカヴァー盤を発表しているほか、矢沢永吉や桑田佳祐もコンサートで歌唱するなど、以降の歌謡曲のありようを方向づける決定的な楽曲となりました。桑田にあっては、その前奏を自作曲〈鎌倉物語〉(1985)に借用してさえいます。
もはやオリジナル歌手とは、単に当該の楽曲をはじめてレコード盤に吹き込んだ先着の存在にすぎません。音盤として表現された楽曲における真の意味でのオリジナル性は、オリジナル版とコピー版のあいだでそれらを区別するものとしてではなく、オリジナル版であれコピー版であれ、これら楽曲の音響それ自体のうちに所在しています。
〈渚のうわさ〉(1967)は、筒美京平が弘田三枝子に提供したオリジナル曲でありながら、いわば筒美一流の仕方で〈砂に消えた涙〉の精髄をカヴァーしてみせた、ある種の本歌取りのような楽曲です。
この精髄は、一方では平山三紀の〈真夏の出来事〉(1971)から都倉俊一によるピンク・レディーの〈渚のシンドバッド〉(1977)や佐々木勉による榊原郁恵の〈夏のお嬢さん〉(1978)、網倉一也による太田裕美の〈南風〉(1980)や小田裕一郎による松田聖子の〈青い珊瑚礁〉(1980)、馬飼野康二による小泉今日子の〈渚のはいから人魚〉(1984)や林哲司による堀ちえみの〈稲妻パラダイス〉(1984)、筒美本人の作でいえば早見優の〈夏色のナンシー〉(1983)など、盛夏の渚に躍動する生命感の行方にどれほどかの寂寞を翳らせた楽曲の系譜を描き、歌謡曲の本流を形成していきます。
うしろゆびさされ組の〈渚の『•••••』〉(1986)やPuffyの〈渚にまつわるエトセトラ〉(1997)、AKBの〈ラブラドール・レトリバー〉(2014)などもその延長線上に位置するかもしれません。
他方ではそれは、小林麻美の〈初恋のメロディー〉(1972)から太田裕美の〈木綿のハンカチーフ〉(1975)を経て、斉藤由貴の〈卒業〉(1985)や〈海の絵葉書〉(1985)、真璃子の〈恋、みーつけた〉(1986)や小泉今日子の〈夜明けのMEW〉(1986)へと、さらには内田有紀の〈明日は明日の風が吹く〉(1995)にまで連なりながら、季節も場所も問うことなく痛む切なさの感傷となって歌謡曲に浸透していきます。
筒美作品に限らず、松田聖子に〈白いパラソル〉(1981)を、川田あつ子に〈秘密のオルゴール〉(1982)を、芳本美代子に〈雨のハイスクール〉(1985)を提供した財津和夫や、菊池桃子に〈青春のいじわる〉(1984)を、児島未散に〈セプテンバー物語〉(1985)を提供した林哲司、また渡辺美奈代に〈瞳に約束〉(1986)を提供した後藤次利らが、こうした側面から歌謡曲を擁護するのです。
カヴァー性
“翻訳ポップス”から“和製ポップス”への移行につづく中村八大から筒美京平への歌謡曲の王道の禅譲は、アメリカ合衆国のヒット・チャートを基軸とした西洋の大衆音楽の精神を、その真髄を、いまや楽曲のカヴァーという形式的な反芻に頼ることなく自在にカヴァーし、そればかりかこれをもって固有性を、要するに自らのオリジナル性を担保するまでに歌謡曲が成熟したことを意味します。
そうした段階に到達した歌謡曲がカヴァーするもの、それは、西洋の大衆音楽よりはむしろ歌謡曲そのものとなるはずです。
筒美京平ら少数の若き才能に依存するだけでは十分な楽曲の質と量を供給できなかった時代には、女性アイドルのアルバム盤が曲数をかせぐためにその片面をまるごと外国曲のカヴァー曲で占めていた事例など、けっして珍しいものではありません。
歌謡曲の作り手が充実してからは、歌い手がおのれの歌唱力を誇示するために、もしくはレコードを生産する企業における収益上の観点から、大きな枚数を売り上げた高名な歌謡曲を選んでカヴァーする事例も増えました。これらの場合、当該の楽曲がカヴァーされる理由は、すなわちそれがすでに広く知られているという前提に収斂し、そこにオリジナルへの畏怖を感じる機会はほとんどありません
それとは逆に、大瀧詠一率いるNIAGARA FALLIN’ STARSによる〈河原の石川五右衛門〉(1981)の諧謔性は、これが原曲の作詞家の狭量な神経をさかなでしたにもかかわらず、ピンク・レディーの〈渚のシンドバッド〉(1977)への敬意と愛情を漲らせています。
さほど売れなかった楽曲、あまり知られていない既存曲、とうに忘れられた旧曲が、ことさらカヴァー曲と謳われることなくカヴァーされ、とりわけシングル盤として発表されるとき、もちろん商売上の視点は否定しがたく介在するにせよ、埋もれた佳曲を発掘し、発信しようと試みる歌い手や製作者らの音楽人としての矜持と、先達の業績に対する尊重がここにはうかがえます。
柏原よしえの〈ハロー・グッバイ〉(1981)や〈あの場所から〉(1982)、小泉今日子の〈私の16才〉(1982)や〈素敵なラブリーボーイ〉(1982)、北原佐和子の〈夢で逢えたら〉(1984)や〈砂に消えた涙〉(1984)、森尾由美の〈初恋のメロディー〉(1984)や松本伊代の〈悲しくてやりきれない〉(1989)などは、このようなカヴァー盤とみなせるでしょう。
最初の地層として堆積した音声がいったん削ぎ落とされた楽曲の表面を、新たな歌唱や演奏があらためてなぞり、その起伏を覆うこと。そうしてオリジナル版とともにいくつものカヴァー版を傾聴しながら、楽曲とそれら音声との組み合わせの妙を、違和感や意外性を味わいつつ、やがて私たちの鼓膜は本来の楽曲のかたちを、その普遍性を象ります。
真正のスタンダードとは、このような洗練に耐ええた楽曲のことにほかなりません。〈あほ空〉からおよそ一世紀にわたり流れてきた歌謡曲の、けっして短いわけではない歴史においてもようやく、いくつかの楽曲が、もはや誰のものでもない音声一般として、それゆえ誰の音声とも問わない楽曲そのものとして響きはじめています。
私の「カヴァー歌謡」10選リスト
1.〈洒落男〉榎本健一(1966/1928, Frank Crumit)
作詞/Lou Klein,訳詞/坂井透,作曲/Frank Crumit,編曲/川上義彦
〈私の青空〉にせよこの楽曲にせよ、榎本健一の歌唱がオリジナルのジャズ・ソングに添加する悲哀と郷愁の、聴くものの胸をなんと切なく締めつけにやってくることか。この切なさ、この哀愁の響きこそは、まさしく歌謡曲の普遍的な存在意義となって、そのオリジナリティを毅然と謳う当のものである。《エノケン大いに唄う》所収。
2.〈よろしく哀愁〉吉田拓郎(1977/1974, 郷ひろみ)
作詞/安井かずみ,作曲/筒美京平,編曲/吉田拓郎(森岡賢一郎)
小室等、井上陽水、泉谷しげると共同設立したレコード会社の窮地を救うべく、社長に収まっていた吉田拓郎の思いつきのもと吹き込みから発売まで突貫で遂行された《ぷらいべえと》に収録。時間的な猶予がないという悪条件が、彼が他の歌手に提供した自作品も含め、アルバム盤一枚をまるごと出来合いの既成曲だけで構成するカヴァー集を実現した。そうした事情のなか、歌謡曲の王道にいた筒美京平による楽曲をフォークの王道で並走していた吉田が歌唱した〈よろしく哀愁〉では、それゆえ大きな衝撃とともに、あまり練られたものとも思われない演奏の荒さが、歌い手としての彼の癖ある歌唱を魅力的に伝える。さらにこのアルバム盤では、吉田がキャンディーズに提供した〈やさしい悪魔〉もまた、これとは対照的に作曲家としての器用な才気を再確認させ、カヴァー作品の味わいに富む。
3.〈しらけちまうぜ〉東京スカパラダイスオーケストラ feat. 小沢健二(1995/1975, 小坂忠)
作詞/松本隆,作曲/細野晴臣,編曲/東京スカパラダイスオーケストラ(細野晴臣,矢野誠)
カヴァー曲を聴くことの興味は、基本的には“what”ではなく“how”に対して注がれる。そこで歌われている楽曲がどのようなものであるのかについてはおおむね既知の領域にあり、それがどのようにカヴァーされているのか、その次第こそが未知の領域に存しているからだ。小坂忠が歌唱した名曲〈しらけちまうぜ〉をめぐる小沢健二による“how”への返答が、いかにも軽妙かつ浅薄に聴こえるとすれば、これはそのまま小坂忠の歌唱の卓越した技量と懐の深さを証言するにちがいない。とはいえ、小沢の版は小沢なりの「僕ら」のありよう、その「情」のなさを的確に表現しており、造形のもっともらしさの謂においてオリジナル性を十全に発揮してもいる。《GRAND PRIX》に収録。
4.〈蜃気楼の街〉一十三十一(2009/1975, Sugar Babe)
作詞・作曲/大貫妙子,編曲/曽我部恵一(山下達郎)
一十三十一は、たとえば曽我部恵一のプロデュースによるカヴァー集《Letters》の発表にあたって、大瀧詠一による松田聖子の楽曲や、山下達郎、荒井由実、尾崎亜美らの楽曲が並ぶなか、こと大貫妙子に限っては不均衡をものともせず、〈春の手紙〉 とこの楽曲を併せて都合2作品を吹き込み、そうした事実をもって大貫への崇敬の念をいささかも隠そうとしない。ただしここでは、清廉に研ぎ澄まされ、厳粛に張りつめた若き大貫の、いかにも希望に満ちた歌唱によるオリジナル版とは対照的に、ハービー・ハンコックの〈Maiden Voyage〉におけるジョージ・コールマンのサックスをかすかに想起させなくもない前奏から、スティール・ギターが滑走をはじめ、一十三の歌唱が聴かれるころには、あたりはすっかり和やかに寛いだ雰囲気で満たされる。リズムを刻むためのドラムスのセットが準備されていないことも、彼女の歌声の、脱力した、かといってけっして「気怠い」わけではなく、気負わず肩肘を張らない自然体の輪郭を丁寧に描くための、いかにも適切な方便であろう。
5.〈失恋レストラン〉敏いとうとハッピー&ブルー(1977/1976, 清水健太郎)
作詞・作曲/つのだひろ,編曲/馬飼野俊一(つのだひろ)
収録曲の大半をカヴァー曲が占める《星降る街角》のなかでも特に異色な原曲のファンキーさ、それをどうにか忠実に再現しようと試みる節度ある姿勢のあまり、結局はそれを希釈した模造品の域を越えない脆弱なカヴァー版に終始するかに思えたAパートから、Bパートへと移行するやいなや、主旋律の背景でにわかに重層化したいわゆる“ウー”のハモりの上昇が、ここで長調に転じた調性をほどよく湿らせる。そのさまは、これぞムード歌謡”のコーラス・グループによる、まぎれもなく本領の発揮された瞬間である。こうした挑戦的な瞬間の露呈との邂逅もまた、カヴァー歌謡の味わいのひとつであることは疑いない。
6.〈グッド・ラック〉坂本慎太郎(2014/1978, 野口五郎)
作詞/山川啓介,作曲/筒美京平,編曲/坂本慎太郎(高田弘)
ここでのスティール・ギターは、一十三十一の場合とは異なり、どこまでも呪術的である。深いリヴァーブに沈み込むもの、モデュレーション系の効果に揺れたゆたうもの、諸ギター群のそうした音の粒子を貫通し、これらのあいだで通奏低音のごとく坂本慎太郎の歌声をも慰撫するそれは、聴衆の精神を避けがたく怠惰のうちに耽溺させずにはいないような、ある種の麻痺的にして幻覚的な魔性の響きとなる。筒美京平による野口五郎の“シティ・ポップ(ス)”の傑作でありながら、あまり言及される機会に恵まれないこの楽曲をめぐって、とりわけそこに戯画的に提示される都会の光景の欺瞞をそれは呪詛してみせる。
7.〈探偵物語〉安藤裕子(2018/1983, 薬師丸ひろ子)
作詞/松本隆,作曲/大瀧詠一,編曲/(井上鑑)
大瀧詠一が薬師丸ひろ子に提供した原曲に対する敬意は、ここでは編曲の位相にうかがえる。これをそのまま援用するのではなく、ストリングスの旋律やピチカート奏法は生かしながら、しかし間奏で鈴木茂が実現していたソロのフレーズなどは、エレクトリック・ギターではなくエレクトリック・ピアノの音色をもって丹念に置換される。そのうえで、平坦で面白みに欠ける薬師丸の歌唱法のせいで、オリジナル版では等時拍音的な音符の均質な並びがいかにも単調に響いたサビの旋律は、安藤裕子の声質の表情や歌唱の表現のおかげで、鼓膜にまといつくように立体的に屹立する。それでいて、ハモりの旋律は薬師丸を真似てか裏声で平板に歌われ、主旋律の展開を妨げることがない。同じく薬師丸ひろ子の原曲をカヴァーした〈Woman〜Wの悲劇より〜〉も必聴。
8.〈ガラスの林檎〉アン・サリー(2010/1983, 松田聖子)
作詞/松本隆,作曲/細野晴臣,編曲/(細野晴臣,大村雅朗)
《Fo:rest》に収録。〈蘇州夜曲〉や〈胸の振子〉のような服部良一作品や〈黄昏のビギン〉のような中村八大作品、あるいは〈星影の小径〉といった演目を自家薬籠中のものとしてきたアン・サリーのように、いかにも気の利いた歌唱者の歌声をもってその旋律がなぞられるとき、細野晴臣によるこの楽曲は、たとえば松田聖子の本来の音盤を片面で共有した〈Sweet Memories〉よりもなおいっそう、日本の大衆音楽のスタンダードとして歌い継がれていく資格があるように思われる。主旋律の裏道をたどるフレンチ・ホルンの丸みを帯びた柔らかい音色とその旋律が、ここではその証左ともなる。当初の松田聖子の歌唱においてあまり好意的な受容の仕方を聴衆によって示されなかった不幸は、いまやむしろ幸いへと転じるかもしれない。
9.〈Tシャツに口紅〉CRAZY KEN BAND(2002/1983, ラッツ&スター)
作詞/松本隆,作曲/大瀧詠一,編曲/Crazy Ken Band(井上鑑)
この音源の魅力は、ラッツ&スターにおける鈴木雅之の歌唱の粘着質を拭い、「つきあって長い」恋人たちの「別れ」の光景を、歯切れよく軽やかに、そのぶん鮮やかで清々しく響かせていることにある。濁りのないエレクトリック・ギターとエレクトリック・ピアノの音色が大仰さを抑えたボサノバ調でまとめるこのカヴァー版は、本家のドゥワップ式のコーラス・ワークからも解き放たれ、かわりにフリューゲル・ホルンやフルートといった管楽器のまろやかな起伏が横山剣の歌声に呼応する。これに限らずどの楽曲をカヴァーするにあたってもおよそそつなく歌いあげる横山の凄みは、歌謡曲の歴史と意義をよく踏まえ、その知見に裏打ちされた自負と矜持がなすわざである。大瀧詠一作品のカヴァー集《ナイアガラで恋をして》は、このほか前川清の歌唱による〈幸せな結末〉なども聴きどころ。
10.〈雨のリグレット〉佐藤竹善(2022/1981, 稲垣潤一)
作詞/湯川れい子,作曲/松尾一彦,編曲/藤田千章(井上鑑)
“シティ・ポップ(ス)”の隆盛に遅れ、もっぱらバブル経済における豊かさのイメージを持ち前の清涼感で潤すことばかりに浪費するよう請われた佐藤竹善の歌声は、しかし本来ならばまさしく“シティ・ポップ(ス)”のために、あるいはむしろ和製A.O.R.のために奏でられるべきものであって、彼の蹉跌はこの一点に尽きるだろう。その意味において、オフコースの松尾一彦が書きおろした稲垣潤一のデビュー曲〈雨のリグレット〉を《radio JAOR〜Cornerstones8〜》の佐藤がカヴァーしてみせたことは、いわば必然である。“シティ・ポップ(ス)”のなかでも、これほどまでに和製A.O.R.と形容するにふさわしい楽曲はほかにないからである。事実、素直で抜けのいい佐藤竹善の歌声は、発声や母音の伸びに癖のある稲垣の歌唱に勝るとも劣らずこの楽曲に合致する。このことは、スタジオで録音された当該のカヴァー版よりも、公式に公開されているステージでの実演版のほうでいっそう確信が持てる。
番外_1.桑田佳祐
たとえば一時期、「ひとり紅白歌合戦」と称して日本の歌謡史における歴代の名曲群を単独で歌いきるステージの開催を恒例としていた桑田佳祐は、CRAZY KEN BANDの横山剣より以上に露骨に歌謡曲への愛着を表明し、いまとなってはそこから被った影響を微塵も隠そうとしない。しかも、彼が選定するすべての楽曲について、その歌唱はことごとく冴える。換言すれば、日本の歌謡史における歴代の名曲をめぐって、いたずらに我流で崩すことなく丁寧に歌い継ぐ彼の姿勢と行為は、日本の大衆音楽史が誇る稀代の歌唱者としての彼の才能を、それを耳にした誰に対してであれ必ず納得させるものである。なかでももっとも説得力のある歌唱とは、林哲司が上田正樹に提供した〈悲しい色やね〉を採用した場合であるにちがいない。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





