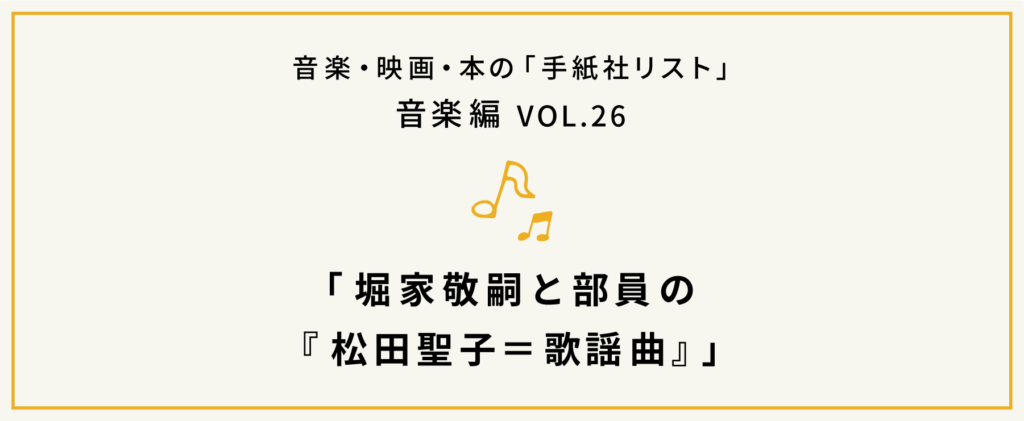
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。26回目となる音楽編は、『松田聖子=歌謡曲』というテーマでお届けします! まずは手紙社の部員さんが選んだ10曲、そして堀家教授のコラム、その後に堀家教授が選んだ10曲と続きます。松田聖子は歌謡曲と共にあったのか? それとも、歌謡曲が松田聖子と共にあったのか? 稀代のアイドルについて、堀家教授が何を語るのか? そして、部員さんと堀家教授が選んだ、“聖子ちゃん”の名曲は!?
手紙社部員の「松田聖子=歌謡曲」10選リスト
1.〈裸足の季節〉松田聖子(1980)
作詞/三浦徳子,作曲/小田裕一郎,編曲/信田かずお
洗顔フォームのCMソングに起用されたデビュー曲。サビの部分の伸びやかな声とCMにつられて洗顔フォームを買ってもらった思い出があります。その後ヒット曲を連発し、スター街道を駆け上がっていくとはこの当時予想していませんでした。中学生のとき、明菜ちゃん派の友達と互いにどっちがいいかをノートの表紙に殴り書きしあったのも思い出です。確か岸谷(旧姓奥居)香さんがオーディションで歌ったのがこの曲で、オーディションによって選ばれたメンバーで赤坂小町(のちのプリンセス・プリンセス)結成となった話にはもっと驚きでした。
(れでぃけっと)
2.〈白いパラソル〉松田聖子(1981)
作詞/松本隆,作曲/財津和夫,編曲/大村雅朗
明菜派だった私としては、聖子ちゃんの選曲は難しかったのですが、最近YouTubeで明菜ちゃんが聖子ちゃんの曲を歌う動画を見つけました。その時の曲がこれです。古舘伊知郎の司会の番組の動画でしたが、当時の聖子と明菜は東西の冷戦状態のような、アメリカvsソ連のような関係。周りはいつも二人を離して配置していたと。その中で、明菜ちゃんは「私・・・彼女のレコードほとんど持っています」と言い、聖子ちゃんのモノマネでこの曲を歌います。二人は不仲ではなかったという説もありますが、ライバルにリスペクトをもって聴いてもらっていたという点でも、やはり聖子ちゃんは偉大。そして聖子&明菜の陰陽の関係性があったからこそ、80年代の歌謡曲は面白かったのだと思います。
(手芸部部長)
3.〈赤いスイートピー〉松田聖子(1982)
作詞/松本隆,作曲/呉田軽穂,編曲/松任谷正隆
“松田聖子=歌謡曲”なのに、“=アイドル”として考えてしまいましたが、“歌謡曲=アイドル”の部分で考えると、やはり“松田聖子”なのでよしとして、、、🤫“アイドル=ハツラツかわいい”から“=かわいい可憐”に更に昇華させているのが、「赤いスイートピー」だと思います。柔らかい、可憐なスイートピー。並のかわいいなら、ピンクのヒラヒラを持ってくるところを、あえての赤いちょっと目立つ、でもバラではなくてスイートピーな所が松田聖子の儚さ、可憐さなのではないでしょうか。単なるかわいいじゃなく、唄の上手さありきの聖子ちゃんならではの花が「赤いスイートピー」な気がします。
(ぬりえ)
4.〈真冬の恋人たち〉松田聖子(1982)
作詞/松本隆,作曲・編曲/大村雅朗
《Candy》所収。恋人たちの甘いショートムービーを観ているような気持にさせてくれる「真冬の恋人たち」。聴いている方が恥ずかしくなるくらい表現がストレート。だからこそ最小限の歌詞とシンプルだけどピアノを中心にキラキラした曲といい感じに甘い男声のバックコーラス。そして聖子ちゃんが歌うから世界が完璧に表現されて聞こえてくるのだと思います。私を含め皆なの理想、憧れ、思い描いた世界が昇華されていくような、聖子ちゃんの歌の一つがこの「真冬の恋人たち」に感じられ、私は凄いと思いながら聴いてしまうのです。では、これらを作った作詞作曲家は誰なのか、バックコーラスは誰なのかとついつい調べたくなってしまいます。すると作詞は松本隆さん作曲は大村雅朗さんでコーラスは杉真理さん。そして永遠のアイドル聖子ちゃんが歌うのだから完璧なのも納得です。しまいにはピアノの響きや曲全体の雰囲気が「SWEET MEMORIES」と重なって聞こえ出してきました。そんな気付きが出来たのも堀家教授の歌謡曲の向こう側をここで覗かせていただいたお陰です。第一回目の講座で、除湿された音楽・シティーミュージックに湿気を加えたのが歌謡曲とおっしゃっていてとても勉強になりました。かつてシティーミュージック側だった才能があり徹底して自分の美学を貫いた人たちが集まって出来ている歌に松田聖子の完璧なまでの可愛い仕草+太く力強い声+甘い声が混在する湿潤さが加われば「表現者“松田聖子”=歌謡曲」と言うタイトルの意味がこの曲から段々見えてきたのですが。。。上手く表現できないし違ったら恥ずかしい~でもこれで出しちゃう。
(大分の共子)
5.〈天国のキッス〉松田聖子(1983)
作詞/松本隆,作曲・編曲/細野晴臣
この歌の可愛らしさがよーく理解出来たのはずいぶん歳を重ねてからでした。「誘惑されるポーズの裏で誘惑してるちょっと悪い子」のくせに「抱きしめられて気が遠くなる」んですよ。「愛してるって言わせたいから瞳をジッとみつめたり」するのに「抱きしめられて気が遠くなる」んですよ。背伸びして大人ぶってみても可愛らしい純情なところが出てしまう、なんとも微笑ましくて、なんて可愛らしいんでしょう。この歌が大好きです。いい歳になってからもカラオケでの定番の一曲で、恥ずかしげもなく思いっきりぶりっ子で歌います。そーいう曲なんです。
(3103)
6.〈セイシェルの夕陽〉 松田聖子(1983)
作詞/松本隆,作曲・編曲/大村雅朗
《ユートピア》所収。イントロからおやおや? っと引っ張られ、甘くかすれた歌声に、情景が浮き上がる歌詞。「セイシェルの夕陽」。夕焼けじゃなくて夕陽、涙が滲んで見てられない感じしますねー。カラオケでこれは歌います、フォークじゃないけど。歌詞、いいんだよなぁ
(あお)
7.〈ガラスの林檎〉松田聖子(1983)
作詞/松本隆,作曲/細野晴臣,編曲/細野晴臣・大村雅朗
名曲ばかりの聖子ちゃんの曲の中でスペシャルなお気に入りの中の1曲。作詞松本隆氏・作曲細野晴臣氏。まず特徴的な前奏。今回作曲が細野氏というのを初めて認識しなるほど!と納得。宙を舞うような幻想的なメロディで始まり歌い出しからの”蒼ざめた月が…”というこちらも幻想的な風景を連想させ、まるでおとぎ話を読んでいるような美しい歌詞が続きます。そしてこのメロディは間奏でも流れ、この間奏から大サビへの転調の一連の流れ…。そして大サビ!”愛しているのよ…指を噛んだ”までの歌詞が大好き!ガラスのように透明な清純な2人が禁断の林檎を食べてしまい大人な2人に変わって行ったのかな…?って自分も大人になって改めて聞いてから思いました。両A面の「SWEET MEMORIES」と合わせ超傑作な1枚と言っても過言ではないのではないでしょうか。
(kyon)
8.〈SWEET MEMORIES〉松田聖子(1983)
作詞/松本隆,作曲・編曲/大村雅朗
1980年代前半、サントリー缶ビールのTVCMに出ていたペンギンのキャラクターたちを登場人物とした劇場版アニメーション「ペンギンズ・メモリー 幸福物語」。歌手を目指す少女ジルが劇中で歌っていたのが「SWEET MEMORIES」です。この作品は可愛らしいペンギンたちとは裏腹に、戦争をテーマにした大人向けの内容で、初めて観たときまだ幼かった私の印象に残ったのは、冒頭のショッキングな戦闘シーンと、セピア色の風景の中でベルがしっとりと歌い上げるシーンとの対比でした。ストーリーはよくわからずとも、子ども心に何か切なく感じた思い出とともに忘れられず、今でも口ずさむ曲です。
(Annie)
9.〈天使のウィンク〉松田聖子(1985)
作詞・作曲/尾崎亜美,編曲/大村雅朗
アイドルという枠からアイドルを超えていった聖子ちゃん。恋愛、結婚、出産…と歩む姿を見せてくれたアイドルは、当時は存在していなかったと思います。“愛のもとへと 運んでく~れ~る~♪”と長く伸ばすのがあざとさのちょっと手前、かわいらしさを感じます。尾崎亜美さんは、この曲を約3時間で作り上げたという話には驚きです。この曲を歌い上げる透明感のある声、安定している歌唱力は素晴らしく、アイドルというよりみんなを魅了するシンガーですね。
(あさ)
10.〈瑠璃色の地球〉松田聖子(1986)
作詞/松本隆,作曲/平井夏美,編曲/武部聡志
《SUPREME》所収。私の中のベストオブ聖子さんソングです。なんとも美しい絶妙な色と光の情景が目の前にすーっと広がります。当時、瑠璃色ってどんな色かしらと調べて、綺麗な色とうっとりしたのを覚えています。朝日が水平線から光の矢を放ち二人が包まれる、空と海、銀河と地球、美しく壮大なスケールの歌詞に優しいメロディと聖子さんのあの声が、、、何にもないんだけれど気づいたら涙がでてるそんな不思議な名曲です。心から癒される私にとってのパワーソング。大切な一曲です。
(HAPPY弥生)
松田聖子=歌謡曲
松田聖子=アイドル
松田聖子が発表した最初のアルバム盤は《SQUALL》(1980)です。収録されている楽曲すべての作詞を三浦徳子が、作曲を小田裕一郎が担当し、やはりこの両名の協働のもとそれまでに発表されてきた彼女のシングル曲〈裸足の季節〉(1980)と〈青い珊瑚礁〉(1980)も、ともに盤面に刻まれています。
その1曲目に位置づけられた〈〜南太平洋〜サンバの香り〉からは、デビューしてほどない松田聖子の魅力があふれてきます。それが彼女の歌声における高音部の伸びにあることはしば指摘されるところですが、とりわけここでは、「サンバに浮かれ」たり「ボンゴのリズムに揺られ」たりなど、「夕暮れの海」での「カーニバル」の「にぎわ」いに心身を委ねた開放感からか、そうした側面をきわめて顕著に聴くことができます。
実際、そこでの彼女の歌唱は、単に高音部において伸びやかであるどころか、暴力的とでもいうべき荒さと粗さを示します。伸びやかさのあまり、ひとたび音程を逸脱しても調整や修正の叶わないそれは、音の行方は声に訊けとでもいわんばかりに、はずれた音がそのままはずれた方向へとどこまでも伸びていってしまう危うさを備えているのです。
歌声の持ち主である松田聖子本人にも決着の地点を見定めることができず、適切に管理し尽くせないこの伸びは、したがって、彼女の歌唱をどこかぶっきらぼうな、野蛮なものとして印象づけます。抑えが効かず暴走する歌声、それは、ただし、初期の松田聖子のためにその製作陣が着想し、事実このアルバムの随所に確認できる“南太平洋”だの“トロピカル”だのといった鍵概念が担保する粗野な奔放さを、みごとなまでに体現する当のものでした。
ましてアイドル歌手の歌唱には、音程の正確さよりも優先されるなにごとかがあって、彼女の場合、それはやはりこの粗野にして奔放な高音部の伸びだったにちがいありません。そしてそこで期待された陽気さの質は、同じレコード会社の女性アイドルとして彼女に道を譲るように引退した山口百恵の歌唱やその存在性に認められる陰気さの質と対照的です。
けれどアイドル歌手の宿命たる声帯の酷使ゆえに、ほどなく彼女の歌声はかすれ、その喉が高音を伸びやかに奏でることは困難となります。
勢いに任せて全速力で疾駆してきた彼女の歌唱は、そのもっとも魅力的な要素を欠落させることになったわけです。アイドル歌手として登場し、活躍するなか、なにより大事だったものの喪失。もはやけっして回復しえない欠如を贖うために、自身の意向の如何にかかわらず彼女は変容する必要がありました。
松田聖子=歌手
〈チェリーブラッサム〉(1981)からは作曲に財津和夫を起用し、〈夏の扉〉(1981)を経てついに〈白いパラソル〉(1981)では、三浦徳子が担ってきた作詞者の役目も松本隆に委託されます。この楽曲における松田聖子の歌声には、以前のような艶もないうえに、演奏する楽器の音数のまばらさによる音響的な余白の多さが、あの伸びやかだった高音部の喪失感をひときわ強調せずにはいません。
まさしくそれは、誰もいない「渚」にひとり残された「白いパラソル」のごとき寂寞です。
それでもなお、かつては自ら管理しきれなかった粗野にして奔放な自身の歌唱が、こうして否応なく落ち着く破目に至ったからには、逆にこれを契機として、彼女はしたたかにもアイドルから歌手へと態度の比重を推移させていきます。
ひとりの歌手としての松田聖子の歌唱の洗練は、彼女が歌唱する楽曲の洗練にともなって実現します。松本隆の提案で大瀧詠一が作曲に迎えられた〈風立ちぬ〉(1981)、さらには彼らとはっぴいえんどで共闘していた鈴木茂を編曲者として大瀧に並置したアルバム盤《風立ちぬ》(1981)が、単に彼女のみならず歌謡史上の傑作であるとすれば、おそらくそれは、彼女のそうした態度と無縁ではないでしょう。
大瀧が提供した〈ガラスの入江〉、ここでは鈴木の唯一の作曲でもある〈黄昏はオレンジ・ライム〉、杉真理による〈雨のリゾート〉、そして財津和夫の〈December Morning〉。アルバムの着想に先行して発表されたシングル曲ながら、にもかかわらずB面で鈴木作品と杉作品のあいだに配置された〈白いパラソル〉も含め、もしくはそれこそがもっとも象徴的に集約するように、陽気だったはずの彼女の寂寞、にぎやかだった渚の、浜辺のいまの寂寥は、それゆえ生命力の喪失を、普遍的な状態としての過去一般を、虚無を、つまるところ死のイメージを孕んでいます。
なるほど、恐れ知らずの若さへの執着を断ち切り、かつての自身の存在性との決別を宣言するかのように、彼女は髪を短く切ってしまいました。“聖子ちゃんカット”と称されたあの髪型を揚棄してのぞんだ楽曲、それが〈赤いスイートピー〉(1982)です。それは、松田聖子の歌唱と楽曲における洗練がいよいよ最高潮に到達しつつあることの予感となります。
松任谷由美からのシングル曲の提供は、呉田軽穂の名義をもって、以降も〈渚のバルコニー〉(1982)、〈小麦色のマーメイド〉(1982)、さらにいったん財津作品〈野ばらのエチュード〉(1982)をはさんで〈秘密の花園〉(1983)までつづきます。
松田聖子=スター
細野晴臣を作曲者に配し、松田聖子の業績の頂点となる〈天国のキッス〉(1983)と〈ガラスの林檎〉(1983)が発表されたのち、再び呉田軽穂の名義により提供されたシングル曲が〈瞳はダイアモンド〉(1983)から〈Rock’n Rouge〉(1984)、〈時間の国アリス〉(1984)へとつながるころには、そうした気運も希薄化してしまいます。
結局のところ、歌手としての松田聖子の洗練と音楽性は、作詞における松本隆と作曲における松任谷由実の貢献を基軸に、彼らの人脈を頼った作曲者、編曲者、演奏者たちが総力で仕立てたものとみて過言ではありません。
そうしたなか、デビューほどない〈青い珊瑚礁〉から松田聖子を支えてきた大村雅朗は、単に編曲のみならず、〈真冬の恋人たち〉(1982)や〈セイシェルの夕陽〉(1983)といったアルバム収録曲の作曲者としても活躍してきました。そしてなにより、彼の〈SWEET MEMORIES〉(1984)は、洗練から表現へと彼女の歌唱の可能性を拡張したうえで、いまや日本の大衆音楽におけるスタンダード曲として扱われつつあります。
しかしこの時期あたりから、松田聖子の周辺は、その私生活をめぐる興味で喧しくなります。アイドルから歌手へと態度の比重を推移させた彼女がこうして射止めたもの、それは、芸能界きってのスターの座でした。そこでは歌声ばかりか存在性そのものが消費のための商品であって、松田聖子と蒲池法子のあいだの棲みわけはほとんど機能しようもありません。
松本隆の歌詞にあてがわれた言葉が屹立させる女性像も、もはや松田聖子の存在性を一定の側面から補強する材料にすぎず、これを倦んでかアルバム《Tinker Bell》(1984)では松本は、彼女を大人への成長を拒絶して永遠に歳をとらないおとぎ話の登場人物に見立てて、どれほどか幼稚な空想の世界の非現実性に囲み込もうとしています。
それでもなお、松田聖子のしたたかさは、私生活の醜聞さえもその存在性のうちに吸収してしまいます。交際していた芸能人との別離を悲劇的に演出したかと思えば、舌の根も乾かないうちに別の芸能人との婚約が報道され、結婚と妊娠のために芸能活動はいったん休止となるのです。
ただし妊娠していた期間にもアルバムの録音は実施され、《SUPREME》(1986)として発売されます。盤面の最後には、「私たち」の「誰もが」ともに「地球という名の船」に乗る「旅人」であり、「ひとつしかない」この「地球」、この「私たちの星を守りたい」と壮大に謳われる〈瑠璃色の地球〉が収録されています。
松田聖子=母
かつて大人に成長することを拒絶し、永遠に歳をとらないおとぎ話の登場人物を装っていた松田聖子が、ほかでもない「私たち」のために「ひとつしかない」この「星を守りたい」との意志を表明する歌声、まぎれもなくそれは、我が子の「争って傷つ」くことのない安寧の未来を願う母の祈りとして響きます。
それからほどなく、無事に長女を出産した彼女は、芸能活動に本格的に復帰するも、海外進出を視野に入れて事務所から独立し、また配偶者を変えるなど、歌唱すること以外の騒動をもって芸能界をにぎわします。自作自演の楽曲を発表するといった相応の模索はつづきますが、それは聴き手が彼女に求めるものではありませんでした。
ところが、やがて世紀が更新されようとするころ、あの松田聖子が、〈哀しみのボート〉(1999)を携えて平然とした顔で帰還します。作詞を担当したのは、シングル盤〈Marrakech~マラケッシュ~〉(1988)以来となる松本隆です。
成長した長女も、SAYAKAの名義で〈ever since〉(2002)をもって歌手となり、ほどなく松田聖子のコンサートが催されていた大きな会場の舞台を踏んで、母娘のはじめての共演が果たされます。
週ごとのランキングで出演の次第が決定される歌番組に招かれる常連だった母にとって、ひとたび歌手としてデビューした以上、たとえ娘であれ立派な競合相手です。緊張した面持ちでデビュー曲を歌唱する娘の様子に幾度となくうなずきながら涙する母の顔、それを自身の観客に甘んじて曝すことは、だからそれきりとなるはずでした。
それからちょうど20年後。あのとき冒頭の8小節のみを先導してのち娘に託した〈ever since〉の旋律を、あのときと同じ大きな会場で再び松田聖子は歌唱することになります。
深くお辞儀をしながら舞台にせりあがってきた彼女は、足もとも隠す黒いロングのドレスをまとっています。旋律からひとつたりとも正確な音程を逃すまいと一音ごとに宙の五線譜をなぞって左の掌を上下させるよりほか、強拍にあからさまに身体の揺れを合致させるでもなく、ほとんど直立の姿勢のまま彼女は歌唱をつづけます。
舞台には彼女ひとりのみ、歌唱を託すべきSAYAKAの姿はありません。
驚くほど慎重に、丁寧に、確実にこの楽曲の最後まで歌いとおし、最終音の発声にビブラートをかけながらゆっくりと、わずかに天を仰いだ瞬間、ついに堪えきれずあの泣き顔になった彼女は、掲げていた左の掌でそれを覆わずにはいられません。
松田聖子=松田聖子
早逝した娘にたむけられた弔いの歌唱を、けっして昂ることも悲嘆に耽ることもなく厳粛に遂行した彼女は、ここであらためて松田聖子という「運命」を選択したのです。
地方都市で生まれ、芸能界に憧れたひとりの少女が、アイドルになり、歌手になり、スターとなり、妻となり、母として娘が自身の歩みを反復するさまを喜びとともに承認し、これらの都度、彼女はそこから新しい自身の行方を定めなおし、そうした立場で自身を真摯に演じてきました。
松田聖子は、自分が思い描いた夢のかたちをほとんどそのまま実現しえた、もっとも恵まれた存在のひとりかもしれません。にもかかわらず、このことは必ずしも彼女の幸福を保証するものではないでしょう。
闘病に生命を削がれて昭和とともに去った美空ひばりをはじめ、中森明菜、岡田有希子、安室奈美恵、堀ちえみ…。これらの事例は、どれほどの名声と栄誉に輝くアイドルであれスターであれ、結局のところ彼女たちもひとりの人間にすぎないことを示唆します。それどころか、アイドルでありスターであるからこそ排除できない苦難をも、彼女たちは引き受けなければならなかったわけです。
それに耐えられず疲弊し、逃走し、平凡な幸福に焦がれて解散し、引退し、普通のひととなった山口百恵や、けれどまたしても脚光のもとに復帰することを選んだキャンディーズの面々、都はるみ…。
これまで世間が、社会が彼女に押しつけてきたさまざまな役柄をこなしながら、躓きや蹉跌、批判や誹謗中傷までも、巧妙に存在性を輝かせる光源として利用してきた松田聖子が、いま、その人生においてほとんどはじめて、どうにも克服しようのない翳りをまとっています。
松田聖子が松田聖子たらんとしても、どうしても埋めきれない亀裂、どのようにも癒しきれない傷跡。20年ぶりの〈ever since〉の歌唱を完遂して天を仰ごうとした彼女が不意に顔を歪め、これを左の掌で覆い伏せるとき、そこに露呈するものがこれです。
それでもなお、彼女が母の顔を観客に甘んじて曝したのはこれきりでした。やはり彼女は、松田聖子でありつづけることを、あるいはむしろ、あらためて松田聖子になることを選択したのです。
もちろん、娘を亡くしたからといって、彼女が神田沙也加の母であることを辞めたわけでも、辞められたわけでもありません。自分の生命が尽きてなお、彼女は神田沙也加の母でありつづけるはずです。そしてそのためにこそ、彼女には、またしても松田聖子たらんとすることの不自由さを生きはじめる必要があるのです。
松田聖子=歌謡曲
かつて「小さな入江」で「砂に褪せた小舟」に「座」り、「呼び戻」された「過ぎた時」のために「ほんの少しだけ」ではあれ「涙を流し」てみせた〈ガラスの入江〉の松田聖子は、〈哀しみのボート〉では、「時間の岸辺で抱きあったまま」に「哀しみのボートで」そっと「涙に漕ぎ出そう」とします。これは、「オールさえも失くしたまま」で、けれどそれが「運命」というのなら、たとえ「不幸の渦へと巻き込まれ」ようとも「今更後戻り」も「出来ない」ことは承知のうえでの選択です。
「運命」と対峙し、抗うことなくこれに「流され」ることを諦念をもって能動的に選択すること。いったん漂着した岸辺から、幾度も「小舟」で、「ボート」で「運命」の「流」れに向かって「漕ぎ出す」こと。いつもそこから、そのときから「時間」の「流」れに身を委ねなおすこと。
そうした彼女の姿勢には、「渚」に残された「白いパラソル」の寂寞、にぎやかだった渚の、浜辺の寂寥、普遍的な状態としての過去一般、虚無、つまるところ死のイメージに対する、生命力を介した抵抗ではなく、むしろ人生の、「運命」や「時間」への一定の句読法として、いずれそこに収斂すべくその都度そこから歩みなおす覚悟が反映されています。
最愛の娘への、と同時に松田聖子への鎮魂歌として松田聖子が歌唱した〈ever since〉。そこに綴られた娘の言葉に背中を押され、あらためて彼女が示した松田聖子になることへの覚悟にとって、「運命」や「時間」とは、いまや“歌謡曲”とおよそ同義にちがいありません。それだからこそ、私たちは、松田聖子を聴くとともに、まさに私たち自身の声をもって松田聖子を歌わずにはいられないのです。そしてこのとき、私たちもまた松田聖子となり、誰もが松田聖子であることを知るのでしょう。これが歌謡曲の、すなわち松田聖子の凄みです。
私の「松田聖子=歌謡曲」10選リスト
1.〈風立ちぬ〉松田聖子(1981)
作詞/松本隆,作曲/大瀧詠一,編曲/多羅尾伴内
前作〈白いパラソル〉から作詞を担当した松本隆が、かつてはっぴいえんどで共闘した大瀧詠一を次作の作曲者として提案し、松田聖子の音楽に本格的に関与しはじめる契機となった決定的なシングル曲。音の密度が粗いかわりに粒立っていた前作から一転、ここでは細かく配置されたきわめて密度の濃い音の粒子群が有機的に結合し、融解した塊となって、記譜された音符からその都度横溢する。さながらそれは音響の瀑布である。
2.〈ガラスの入江〉松田聖子(1981)
作詞/松本隆,作曲/大瀧詠一,編曲/多羅尾伴内
A面全曲の作曲と編曲を大瀧詠一が、先行のシングル曲として収録された〈白いパラソル〉以外のB面全曲を鈴木茂が担当し、それらすべてを松本隆が作詞することで、はっぴいえんどの試行が10年を経てついに日本の大衆音楽の中枢に浸透したことを印象づけた傑作アルバム盤、《風立ちぬ》に所収。「濡れた岩」の部分では、おそらく松田聖子の声域の最下限と思しき〈チェリーブラッサム〉の旋律の最初の音符よりわずかに半音だけ高いソ#から、1オクターブ上のソ#へと1拍で飛んだあと、すぐさま下のラ#へとほぼ1オクターブ戻ったのち、またしても1オクターブ近く上のソに跳ねてラ#まで上昇するなど、いかにも不自然で技巧的な旋律の動きが歌唱を難儀にさせるが、ほどなく「過ぎた時」の部分ではこの音階がまるごと長二度ぶん高く転調し、いっそうの困難をもたらす。彼女の歌声は、その一音ごとに、ことさら慎重にここでの音程を刻む。《Candy》に収録された〈四月のラブレター〉も大瀧詠一による佳曲。
3.〈雨のリゾート〉松田聖子(1981)
作詞/松本隆,作曲/杉真理,編曲/鈴木茂
《風立ちぬ》のB面で、財津和夫の提供した〈白いパラソル〉と〈December Morning〉とのあいだに配置されたこの楽曲は、夏から冬への急激な変転の緩衝として機能する。季節間の推移の感覚ならば、〈白いパラソル〉に前置された〈黄昏はオレンジ・ライム〉のほうがよほど秋の寂漠を印象づけようものを、ここではそうした特定の季節感を援用することなく、まさに「雨のカーテン」のようにきわめて滑らかに場面を転換する。杉真理による、自身以外の歌い手への300曲を超えるという提供曲のなかでも、メロディ・メイカーとしての彼の能力を存分に示す最高傑作のうちのひとつ。
4.〈小麦色のマーメイド〉松田聖子(1982)
作詞/松本隆,作曲/呉田軽穂,編曲/松任谷正隆
これほど地味で憂鬱な夏の午後のありようは、それまで歌謡曲においてシングル盤として発表されたことのない類いのものだった。ピンク・レディーの〈渚のシンドバッド〉や榊原郁恵の〈夏のお嬢さん〉、あるいは早見優の〈夏色のナンシー〉に代表されるように、女性アイドルにあてがわれる夏のシングル曲といえば、肌の過剰な露出を上昇する気温のせいにし、色気を元気さで糊塗する定型的な表現がほとんどで、〈青い珊瑚礁〉の松田聖子自身でさえこの範疇にあった。そうした傾向に追従する体裁で次の夏に発表された〈白いパラソル〉の彼女は、しかしどこか寂しげで、これが来たるべき夏の性質を準備していたのかもしれない。事実、〈小麦色のマーメイド〉は、もはや海辺の、渚や砂浜の、太陽のぎらつきや波のきらめきはない。もっぱらそこには、長い休暇のために人影の消えた都市の夏、残されたもののみが味わうことのできる贅沢な気怠さに満たされている。いわばそれは、限られたもののみに許された「小麦色の夢」、すなわち都市の「まどろみ」である。
5.〈Private School〉松田聖子(1983)
作詞/松本隆,作曲/林哲司,編曲/井上鑑
アルバム盤《Canary》に収録。いまのところ林哲司の提供による松田聖子のシングル曲は実現していないが、彼女のアルバム群にはその作曲作品がいくつか存在する。なかでもこの楽曲は、構成やサビのキャッチーさなど、いかにも林らしくまとまった良作だが、そのぶんこうした典型的な彼の仕事は、松田聖子のシングル曲とするにはわかりやすさが仇となるのだろう。
6.〈Rock’n Rouge〉松田聖子(1984)
作詞/松本隆,作曲/呉田軽穂,編曲/松任谷正隆
Cが基調となる8小節のAパートと、その短3度上に転調してE♭が基調となる8小節のBパートが、さらにA’およびB’となって繰り返されたのち、サビへの架橋として挿入される「ちょっとブルーに眼を伏せた」の4小節が秀逸。なにより、ディミニッシュ・コードの響きにあわせて1小節のあいだ演奏が止み、待ちきれないドラムスだけが2拍ぶん前のめりに残りの空白をスネアの連打で埋め、次の小節からの演奏を他の楽器に促すとき、そこにはまぎれもなく「ちょっとブルー」な瞬間の聴覚的な実現が招来される。
7.〈ピンクのモーツァルト〉松田聖子(1984)
作詞/松本隆,作曲/細野晴臣,編曲/細野晴臣,松任谷正隆
〈天国のキッス〉といい〈ガラスの林檎〉といい、細野晴臣が松田聖子に提供した楽曲に凡作はありえない。もちろん中森明菜の場合にも、最高傑作〈禁句〉は彼の作曲である。そうした細野の仕事のなかでは比較的に軽やかな〈ピンクのモーツァルト〉では、「モーツァルト」の響きを共感覚的に「ピンク」と表現した松本隆の言葉の斬新さもさることながら、やはりこの楽曲を彩るのは音響そのものである。サビでの「ピンクのモーツァルト」のフレーズを聴いてただちに鳴らされるティンパニーの音は、モーツァルト作品における実際の使用法の如何はさておき、なるほど華やかにして艶やかなクラシックの響きをここにもたらす。とともに、かつて〈制服〉がそうだったように、弦楽器にはシルヴィ・ヴァルタンの〈あなたのとりこ〉の余韻も芳しいとすれば、松任谷正隆の貢献もけっして少なくはない。
8.〈ハートのイアリング〉松田聖子(1984)
作詞/松本隆,作曲/Holland Rose,編曲/大村雅朗
Holland Roseこと佐野元春の作曲。編曲は、彼のデビュー曲となった〈アンジェリーナ〉やのちの〈SOMEDAY〉など、初期の代表作において協働した大村雅朗。松田聖子を触媒にはっぴいえんどが再集結したように、ここでついに大瀧詠一と杉真理に佐野が加わってNIAGARA TRIANGLE VOL.2も反芻され、彼らの音楽が1980年代前半の歌謡曲の中心にあることを確実とする。すでに佐野は作曲家の名のもとに沢田研二に〈Vanity Factory〉を提供するなどしていたものの、女性アイドルからの依頼にあたっては、曲想として自演の可能性が排除されるためか、あらかじめ筆名を騙ってみせる。同じく松田聖子が歌唱した〈今夜はソフィストケート〉のほか、Holland Rose名義としてはこれらに先んじて〈ストロベリー・フィールド〉を伊藤つかさに提供。
9.〈マリオネットの涙〉松田聖子(1986)
作詞/松本隆,作曲/久保田洋司,編曲/戸田誠司
THE 東南西北の久保田洋司が作曲、のちにYOUを誘ってFAIRCHILDを結成するSHI-SHONENの戸田誠司が編曲。尾崎亜美が作詞も担当した〈天使のウィンク〉以降、アルバム盤も含め松田聖子の楽曲から1年半にわたり距離を置いていた松本隆を再び全曲の作詞に迎えた《SUPREME》に収録。他方で、松本隆が松田聖子に関与する以前から、〈青い珊瑚礁〉などの編曲者として、さらには〈SWEET MEMORIES〉などの作曲者として彼女の業績に貢献してきた大村雅朗の名前はそこにはない。バンド活動で自作自演する若手たちを制作者に招いてかたちづくられた音像は、かつての彼女の音楽にはない中低音の厚い響きをもって、この歌い手の新しい地平の模索を実感させる。作曲の久保田も、ほどなく自身のバンドでカヴァーしている。
10.〈哀しみのボート〉松田聖子(1999)
作詞/松本隆,作曲/大久保薫,編曲/岡本更輝
バブル経済の狂乱とその後の混乱の時期を経て、ついに松田聖子は帰還する。ここで松本隆は、かつて〈Woman “Wの悲劇”〉でいったん薬師丸ひろ子に預託した、「オールはない」まま「流されて」いく「時の河を渡る船」のイメージを、まさに松田聖子のために、「流され」ることも「運命」と覚悟のうえで「時間の岸辺」から「涙に漕ぎ出」す「哀しみのボート」へとあらためて仕立てなおす。あの時期、とりわけ私生活における騒乱をも、まるでアイドルからスターへの飛躍に資する通過儀礼とでもいうかのように露悪的に昇華してきた彼女が、この楽曲と邂逅し、なにごともなかったかのように平然とそれを歌いあげることの奇跡。そしてあれからすでに四半世紀。松田聖子の次の帰還はいつになるのか。編曲の岡本更輝は、これまで松田聖子の領域を迂回するように山口百恵から中森明菜へと活躍の舞台を転じ、両者の音楽を系列化してみせた萩田光雄の別名。
番外_1.〈ever since〉松田聖子,SAYAKA(2002)
作詞/SAYAKA,作曲/奥田俊作,編曲/松岡モトキ
https://youtu.be/NXkfRhbl3ao
母娘の初共演となった、さいたまスーパーアリーナにおける松田聖子のコンサートでの歌唱。嬉しげな、恥ずかしげな、それでいて誇らしげな、安堵に包まれた涙と笑顔。《Seiko Matsuda Concert Tour 2002 Jewel》に収録。
番外_2.〈ever since〉松田聖子(2022)
作詞/SAYAKA,作曲/奥田俊作,編曲/松岡モトキ
母娘の初共演からちょうど20年後、同じさいたまスーパーアリーナにおける松田聖子のコンサートでの歌唱。悲壮で、厳粛で、それでいて強靭な、弔いにたむけられた歌声と涙。《Seiko Matsuda Concert Tour 2022 “My Favorite Singles & Best Songs” at Saitama Super Arena》に収録。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





