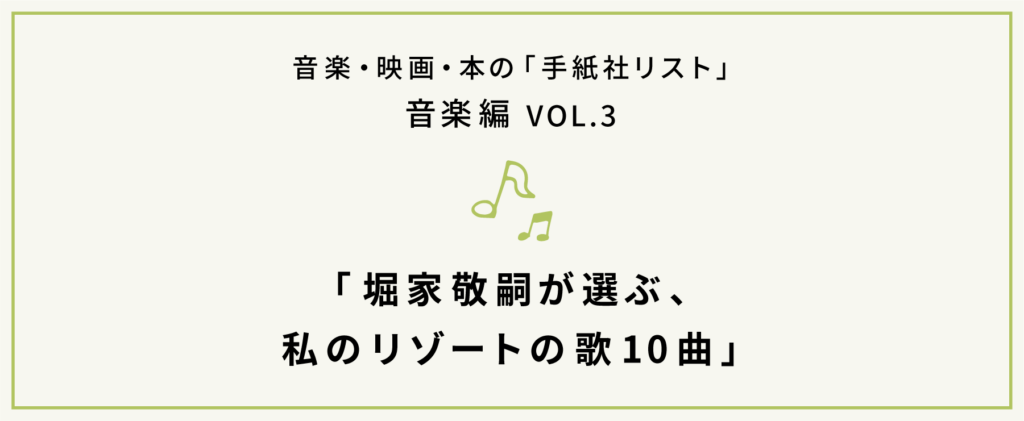
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。7月号の音楽部門のテーマは、「リゾート」。“聴くべき10曲”を選ぶのは、手紙社の部員たちに向けて毎月「歌謡曲の向こう側」という講義を行ってくれている、山口大学教授の堀家敬嗣さんです。自身もかつてバンドマンとして活動し、幅広いジャンルの音楽に精通する堀家教授の講義、さあ始まります!
歌謡曲の避暑地
リゾート
日本の大衆音楽史における記念碑的なアルバム《A LONG VACATION》(1981)は、その発表以来、夏に聴かれるべき日本の大衆音楽のありかたの理想型として機能しつづけてきました。40年を経たいまもなお、大滝詠一によるこの偉業を更新する音楽はまだ聞こえてきません。だからこそ、このアルバムは、彼を“シティ・ポップス”の担い手とすることに大きな躊躇を感じさせます。むしろそれは“リゾート・ポップス”とでもされるべき性質のものであり、仮に彼が“シティ・ポップス”に関与しているとすれば、それは[リゾート]が[都市]を前提に成立する概念である限りにおいてのことです。
勤労を基軸とする乾き荒んだ関係性が編み込まれた都市での生活は、そこで暮らす人びとにさまざまな摩擦を強いるものです。リゾートとは、こうした都市生活者の疲弊した心身を休養させ、彼らが再び都市での日常に復帰できる程度にまでその精神や身体の枯渇を潤わせるような、しばしの非日常性を意味します。もともとこれは、明治期の西洋化の過程で人為的に日本に導入された概念であり、そこにはやはり、性急な近代化のための勤勉さが反面として前提となっているわけです。
それ以前の日本でも、各地の温泉浴のほか海水に浸って疾病を癒す潮湯治がありました。しかしこれは、汲んだ海水を浴びたり、海中に挿した竹竿にしがみついて身体を波に晒すといった体裁のものだったとされ、今日的な海水浴が流通するのは、新鮮な空気と寒暖差の少ない気候、安定した湿度と潮風などが、リウマチや脚気、皮膚の疾患、とりわけ肺病すなわち結核の治癒に有効とする西欧式の医学を明治政府がドイツから導入して以降のことです。
幕末から維新のころにかけて、横浜に居留を制限された外国人にも移動が許されていた近辺の富岡や江ノ島での彼らの海水浴の記録が残っていますが、本格的なものとしてはたとえば1885年に大磯に海水浴場が開設されています。つづいて鎌倉や須磨、さらには平塚や茅ヶ崎などに海浜療養所が設立されます。つまり日本におけるリゾートとは、なによりもまず病んだ人びとが療養するための長期の滞在を意味したわけです(*1)。
加えて、その多くが、敷衍されつつあった東海道線における鉄道駅の設置を前提に、東京近郊のいわゆる“湘南”地域に集中していたことは重要です。南に、太平洋に開かれた海辺の陽射しと潮風に、勤労の場としての首都は癒しの機能を期待し、分担させたのです。
その後、疾病の治癒の舞台はより空気の清澄な高原へと移行して都市から隔離され、“湘南”の海浜は、病んだ人びとの療養の地から富んだ人びとの避暑や避寒を含む保養の地へと、機能の焦点をずらしていきます。事実、療養所だった鎌倉の海浜院は、東海道線の一部として1889年に横須賀線が開通し、鎌倉に鉄道駅が設置されるころには、外国人の逗留も可能なホテルとしての営業を開始します(*2)。
さらに天皇家の別荘となる御用邸が鎌倉に、そして葉山にあいついで建設され、これを機に、特に葉山には当時の政治家や政商らが競うように別荘を建築します(*3)。なお、横須賀線により首都から軍都の横須賀へとつながったことから、鉄道駅のない葉山に隣接する逗子には高級軍人が居住することになります。
“ハワイアン”
こうして日本でも、余暇の愉しみをリゾートに求める生活が富裕層のあいだで定着していきます。しかしそれは、あくまでも西洋から輸入された文化であり、だから日本に限らず世界各地には無数のリゾート地が存在します。そうしたなか、いまなお私たちにとってもっとも親しみある海外のリゾート地とは、おそらくハワイでしょう。
大磯に海水浴場が開設された1885年、日本政府の斡旋により日本からハワイへの最初の移民が海を渡っていきますが、むしろ彼らは現地で不足する人口を補う労働力として請われ、勤労の場をそこに移した人びとでした。
ハワイは、1898年にはアメリカ合衆国の準州となります。やがてハワイの音楽家のなかには、成功を夢みて小さな島を発ち、広大なアメリカ大陸に渡る演奏家のほか、日本に活躍の環境を求める事例も現われました。アメリカの大衆音楽をまともに実演できる楽器奏者が日本にはまだ少なく、彼らの成功の余地がアメリカ本土よりもはるかに大きかったことに加え、明治期以降、労働力として日本からの移民を多く受け入れてきたハワイでは、日本は実際の距離よりもよほど近しい関係にあったところと推察できます。
その嚆矢がアーネスト・カアイです。ウクレレやスティール・ギターをはじめ複数の楽器演奏をこなした彼は、1927年の来日の翌年には、二村定一の歌唱で吹き込まれた〈ウクレル ベビー〉などの演奏を自らのバンドで担当しています。7年ほどの滞在期間中に彼が日本の大衆音楽にもたらした貢献は、単に“ハワイアン”の範疇に収まるものではありません。たとえば[サビ]の語も彼の周辺から生まれたといいます(*4)。
日本語による翻訳詞で吹き込まれ、最初にヒットしたジャズの楽曲とされる〈あほ空〉と〈アラビヤの唄〉のカップリング盤が、二村定一と天野喜久代の歌唱により発売されたのも1928年のことです。だからこの年は、いわば洋楽が歌謡曲として日本の聴衆に広く受容された記念すべき年となります。
ラグタイムから派生したアメリカの大衆音楽がはじめて[ジャズ]の語を冠したのは1917年、ここから10年ほどかけて、たとえば1927年に世界最初のトーキー映画として発表された作品がほかならない『ジャズ・シンガー(Jazz Singer)』であったように、ジャズはアメリカ文化に深く浸透していきます。そしてこのころ、ついにそれは日本語の響きをまとったのです。
しかしながら、当時の日本にはまだ、職業人としてのジャズの演奏家のみならず、その歌い手もほとんど満足にいませんでした。〈あほ空〉を〈私の青空〉としてカヴァーした榎本健一は、浅草オペラの歌劇団出身の喜劇俳優であり、彼などはレヴューの劇場や映画館などでこれを歌い踊ってみせることで、そうした楽曲を紹介するきっかけとしました。演奏家については、大学生が中心のアマチュア・バンドがレコーディングに雇われることも多かったようです(*5)。
トロピカルな夜
日本の音楽産業の黎明期に来日したアーネスト・カアイは、“ハワイアン”のみならず本場のジャズにも通じた演奏家として重宝され、それゆえスティール・ギターがジャズ盤の編曲に用いられるようになっていきます。逆にいえば、ダンスのための音楽として輸入される洋楽に対して、この時期の日本の大衆音楽は、“ブルース”であれ“ハワイアン”であれ、ジャズの名のもとこれらを明確に区別しない寛容な態度で接していたものと考えられます。実際、服部良一も彼を名手と紹介しています(*6)。
アーネスト・カアイにつづいたのは、ハワイに移民した日本人の子息たち、すなわち日系二世の音楽家でした。灰田晴彦は、日本で“ハワイアン”を専門に演奏するバンドを1929年に結成し、ここに弟の灰田勝彦が歌い手として迎えられます。1936年には、晴彦が作曲し、勝彦の実質的なデビュー曲となった〈ハワイのセレナーデ〉が発売されています。
バッキー白片も、そうした日系二世のひとりです。灰田晴彦を頼った半年の日本滞在ののち、地元の大学を卒業して1937年には日本に帰化した彼は、特にスティール・ギターの卓越した演奏家として知られています。
神戸の大学生のころに音楽活動を本格化させ、バッキーの薫陶を受けた村上一徳は、“ハワイアン”の体裁のバンドのなかでスティール・ギターによるビバップ的なアドリブをこなし、その自作曲〈熱風〉(1943)での演奏などは戦前の日本のジャズの最高峰との評価もあります(*7)。
スティール・ギターの奏者として知られる大橋節夫は、戦後の日本における“ハワイアン”の流行を牽引した、もっとも成功した“ハワイアン”の歌い手のひとりとみなせますが、彼も村上の演奏に魅せられ、奏法の参考にしています(*8)。
ところで、“ハワイアン”の楽曲として日本でスタンダード化しているもののひとつに〈南国の夜〉があります。バッキー白片や大橋節夫の定番の演目としてレコードに吹き込まれているほか、石原裕次郎をはじめさまざまな歌い手が歌唱してきました。
これは、1938年に公開されたミュージカル映画『セニョリタ(Tropic Holiday)』のなかで、ドロシー・ラムーアによって歌われ、普及した楽曲〈On a Tropic Night〉に日本語詞をかぶせたものでしたが、原曲はメキシコ人のアグスティン・ララが作曲した〈Noche Criolla〉(1933)で、原詞ではこの熱帯の夜がメキシコ湾に面したヴェラクルスのものであることが謳われています。映画の物語も、これに準じてメキシコを舞台としています。
つまり本来はラテン系のリズムで作られた大衆音楽が、日本では“ハワイアン”のスタンダードとして聴かれているわけです。
ラテンのリズム
“ハワイアン”を特徴づける楽器や奏法はいくつかありますが、ウクレレはその代表的なものでしょう。最初のウクレレは、1879年にハワイに移住したポルトガル移民がハワイ固有の木材コアで故郷の楽器ブラギーニャを再現したものとされています(*9)。スラック・キー・ギターも、牛飼いの雇われメキシコ人が持ち込み、ハワイに置き去りにしたギターを用いて、調弦の段階から現地で模索され、あみだされた奏法だといいます(*10)。
要するに、音響的な観点から“ハワイアン”らしさを支える主要な楽器それ自体が、もとはラテン文化圏から派生してきたものであり、その音楽と“ハワイアン”とはそもそも親和性が高かったのです。
ただし、分節点から互いが進化するなかでそれらが独自の発展を遂げるのは当然です。これらを紹介し、消化する日本の大衆音楽の現場でも、世界的なタンゴのブームなどを背景にラテン系の要素の本格的な採用が叶うにつれ、ジャンルにおけるリズムの複雑さや楽団における楽器の編成の違いから、演奏者は専門化していきます。それにともない、聴衆の耳もまた、その違いを味わうことができるようになります。そしてこれは、歌謡曲が次の局面に移行したことを意味します。
事実、淡谷のり子の歌唱によって同時期に吹き込まれた〈アマポラ(けしの花)〉(1937)と〈バンドネオンに寄せて〉(1938)とを、発売元の日本コロムビアはいずれも「ジャズ・ソング」のラベルで分類していますが、服部良一の編曲による「ルムバ」の前者はコロムビア・ジャズ・バンド、仁木他喜雄の編曲による「タンゴ」の後者はコロムビア・タンゴ・バンドの演奏によります。
〈アマポラ(けしの花)〉では、拍子木によって2-3のソン・クラーヴェのリズムが明確に刻まれています。しかし淡谷の出番がないままハ長調で1コーラス分の演奏が終わり、さらに淡谷の歌唱を導く助走に入るまでの6小節にあっては、いかにも〈蘇州夜曲〉(1940)の服部らしく大陸風のヘ長調のペンタトニック・スケールに橋渡しさせたのち、にわかに流行歌的なハ短調の間奏へと旋律は下降していきます。
ジャズの素養を基底としたこうした大胆な異国趣味の結合と異国情緒の融合こそは、まぎれもなく服部の真骨頂であり、のちの歌謡曲のありようを示唆するものですが、それも実力において当代随一とされたコロムビア・ジャズ・バンドの演奏があってのことでしょう(*11)。
その自由奔放な展開を待ってようやく「アマポラ」と歌いだした淡谷の声は、スペイン語で書かれた原詞にはない「南の野辺」の語句をもって、そこに眩い陽射しを加えることになります。
南方へ
日本において、[リゾート]とは、なによりもまず南に、太平洋に開かれた海辺の陽射しと潮風のことでした。
けれどほどなく日本は太平洋戦争に突入し、ジャズや“ハワイアン”は敵性音楽としてただちに演奏を禁じられます。その一方で、西欧列強による植民地支配からのアジアの解放を大義名分に謳ったこの戦争は、ほかならないハワイ真珠湾への攻撃により開戦して以降、その戦線をひたすら南下させます。
そしてその過程で、アメリカニズムの横溢する敵性音楽ではなく、あくまでも南方との協調を唱える音楽の意匠のもと、ジャズや“ハワイアン”はかろうじて難局を生きながらえました。たとえば服部良一の場合、笠置シズ子に提供した〈アイレ可愛や〉(1943)などがその事例となります。
また、灰田晴彦は「モアナ・グリー・クラブ」から「南の楽団」にバンド名を変更し、弟の勝彦の歌唱で自作曲〈南国の夜〉(1943)などを発表しますが、同年の〈憧れの南〉にはもはや“ハワイアン”の名残りはほとんど認められません。他方で勝彦といえば、大谷洌子とのデュエットで〈ジャバのマンゴ売り〉(1942)を、歌上艶子とのデュエットで〈マニラの街かどで〉(1942)を、さらに〈バタビヤの夜は更けて〉(1943)や〈ジャワの夕月〉(1943)を吹き込み、南方への志向を明確にしたうえで、映画俳優としての成功もあいまって流行歌の歌い手の地位を確実にしていきます。
間奏にスティール・ギターの独奏パートを設けた霧島昇の〈カヌーに乗って〉(1943)は、そうした時局からすれば相当に“ハワイアン”調です。しかし村上一徳を迎えてまもなく「カルア・カマアイナス」から改称した、ヴィブラフォンの朝吹英一が率いる「南海楽友」の〈南の風〉(1943)は、“ハワイアン”であることを超えて日本の歌謡曲の歴史におけるこの時期の傑作のひとつというべきでしょう。
メンバーの芝幸二が歌唱するなか、Ⅱm7−Ⅴ7−Ⅰ−Ⅵmのコード進行に乗ってたどられる「われを待つ花園瞳に浮かぶ」のパートは、そのメロディがまったく褪色していないばかりか、後半部分の2拍3連の符割りには、〈君は天然色〉(1981)の「別れの気配を」のパートや松田聖子の〈風立ちぬ〉(1981)のイントロなどで大瀧詠一が仕掛けた、複合リズム的な感触を今日の聴衆にもたらします。
戦時期の抑圧のなか、南方のイメージを参照し、これを口実とすることでかろうじて演奏される機会をえていたかつての敵性音楽は、終戦後、今度は日本に進駐してきた占領軍の耳を慰撫すべく重宝されるものとなります。まずはNHKのラジオが日本人によるジャズ演奏の放送を解禁します。これにつづいて、クラブやバーなど占領軍の娯楽施設でアメリカ人のためにその芸能を提供するよう、GHQからの要請が届きます(*12)。
逗子と石原裕次郎
こうして“ハワイアン”の響きが醸成してきた南洋のリゾートの雰囲気は、首都たる東京にとってのリゾート機能を担った“湘南”の地に投影されることになります。
[湘南]の語句の使用は中国の湘南地域にちなんだものとされます。[湘]は湘江を、この場合の[南]は水辺の北側を意味します。つまり南側を湘江の水面に開いて陽射しを遮るもののない流域の、日向の土地がらのことです。鎌倉時代に輸入された禅宗の影響から、まずは鎌倉が湘南にたえられたことが日本における“湘南”の発祥と考えられますが、すでにここで、南に、太平洋に開かれた海辺の陽射しこそが“湘南”を“湘南”たらしめていたわけです(*13)。
ただし本来の湘南の水面は淡水です。“湘南”に潮風が吹くのは、開港された横浜を経由して西洋式のリゾートの概念が輸入されるまで待つ必要がありました。つまり現在の“湘南”とは、アジアの辺境に位置する島嶼である日本の地勢学的な必然として、中国文化や西洋文化から輸入された文物を咀嚼し、消化したすえの結実、その独自の産物にほかなりません。
したがって、本来の文化のありさまが歪曲される次第やその程度は問題ではありません。それがどのように消化され、かたちを変え、日本の風土に適合していったのか、その機微に鼓膜を揺さぶられることこそが、たとえば歌謡曲を味わうひとつの仕方なのです。
日本で“ハワイアン”が奏でられはじめたころ、夏の“湘南”の海水浴場のスピーカーから流れてきた音楽はディック・ミネの歌声ばかりだったといいます(*14)。ブルーズ色の濃厚なイントロのスライド・ギターと最後のトランペットのアドリブが印象的な〈ダイナー〉(1934)や、彼の歌唱とのユニゾンで主旋律をたどるヴァイオリンの音色が哀愁を煽る〈恋人よ我に帰れ〉(1935)などは、いずれも訳詞でカヴァーされたアメリカの楽曲です。
なお、ディック・ミネが三根徳一の名義で訳詞と編曲も担当した後者については、のちにY.M.O.が中本マリを歌唱に迎えたテクノ版が『ミュージック・フェア’82』で放送されています。
戦後の“湘南”は、まさしく“ハワイアン”で埋め尽くされました。その中心には太陽族映画がありました。石原慎太郎の通俗小説を原作とする1956年の『太陽の季節』の大ヒットは、“湘南”の鎌倉や逗子、葉山に暮らした富裕層の不良子息たちの享楽主義に耽る反道徳的な行状を描くことで、日活の再生を実現します。
ここでもわずかにダンスの場面の演目として“ハワイアン”が流れる機会はありますが、音楽を担当した佐藤勝は、次作『狂った果実』では武満徹との協働のもと、その全編をとおして“ハワイアン”の要素を採用しています。とりわけ、葉山のホテルの場面でフレーム外の音楽として流れてくる“ハワイアン”の演奏は、映画の公開後に原作者による歌詞をあてがわれ、バッキー白片のスティール・ギターを編曲の軸にすえた〈狂った果実〉(1956)として、はじめての主役をこの映画作品で演じた石原裕次郎のデビュー曲に迎えられます。
仮に“湘南サウンド”なるものがあるとすれば、その起源は太陽族映画における石原裕次郎がそれだろうと説く大瀧詠一の見解は、特定の音楽がそこではじめて“湘南”に直接的に関連づけられたことを指摘する観点の提示として的を射たものといえます(*15)。
茅ヶ崎と加山雄三
この年、アメリカではエルヴィス・プレスリーが〈Heartbreak Hotel〉で一躍スターとなり、これが日本では太陽族になぞらえて紹介されています(*16)。その後、プレスリーは、かつてビング・クロスビーが歌った〈Blue Hawaii〉(1937)の“ハワイアン”の調子をロッカ・バラードのリズムで希釈し、彼の〈Blue Hawaii〉(1961)として主演映画『ブルー・ハワイ(Blue Hawaii)』で歌唱します。その活躍も、ロカビリーの流行の一方でなお“ハワイアン”が日本で愛聴されつづけた理由のひとつと考えられます。
生まれたころからジャズや“ハワイアン”を聴かされていたという加山雄三も、プレスリーに影響を受け、すでに大学時代には彼の楽曲を演奏するバンドを結成しています。このほか、デビュー前の彼は、シンガー=ソングライターの先駆者でもある大橋節夫の楽曲などを、在住していた茅ヶ崎の浜辺にギターを持ちだして愛唱していたようです(*17)。のちに大橋が彼の〈お嫁においで〉(1966)の編曲を担当したのも、おそらくそうした縁によるものでしょう。
俳優となった加山の“若大将”シリーズ4作目、『ハワイの若大将』(1963)では、ついに彼自身もハワイへ撮影に赴きます。しかし滞在期間の制約から、ホノルルの浜辺と設定された場面でも、加山と星由里子の寄りのショットなどは茅ヶ崎の海岸で撮影され、事実、加山をみつめる星の表情のクロース=アップでは彼女の背後に烏帽子岩が映り込んでいます(*18)。波の荒さはいかにも茅ヶ崎のものですが、それでも“アメリカの夜”の効果もあって、ホノルルで撮影されたショット群と深刻な違和感なしにつながり、ここに私たちは、まさに“湘南”にハワイが投影された瞬間を目撃します。
このときウクレレを抱えて星のために加山が歌った自作曲は、岩谷時子が英語詞を日本語詞に書きかえ、弾厚作の名義を使用した最初の発表作品として、次作『海の若大将』(1965)の主題歌〈恋は紅いバラ〉となってレコード化されます。
さらに加山雄三は、これにつづく『エレキの若大将』(1965)において、ザ・ベンチャーズやアストロノウツらの“サーフ・ミュージック”を継承した演奏を披露し、日本におけるエレキ旋風を牽引します。このときの主題歌が、コード進行もメロディの符割りも〈恋は紅いバラ〉に酷似する〈君といつまでも〉でした。
ここで加山がしたがえたザ・ランチャーズの中心メンバーである喜多嶋瑛と修の兄弟は、加山のいとこにして茅ヶ崎の出身であり、また〈想い出の渚〉(1966)をヒットさせるザ・ワイルド・ワンズの加瀬邦彦も、茅ヶ崎に居住していた高校時代に、加山の自宅に押しかけてギターの手ほどきを受けています。ただし「あの渚」とは、実際には茅ヶ崎ではなく葉山のものだったといいます(*19)。
茅ヶ崎からは、筒美京平の作曲による〈傷だらけの軽井沢〉(1969)でブレッド&バターもデビューしますが、歌詞の内容はタイトルのとおり海岸ではなく高原の恋を取材したものです。
彼らと交流のある荒井由実の〈天気雨〉(1976)では、「茅ヶ崎」が歌詞の舞台に設定されていますが、そこではリゾート地としてではなく、あくまでも地方の海辺の町として茅ヶ崎を扱っています。彼女のこうした姿勢は、「相模線」や「ゴッデス」といった固有名詞に反映されるところです。つまり荒井由実は、居住する郊外の町である八王子から茅ヶ崎へ、東京の都心を経由することなく「相模線」でやってきたわけで、ここでは歌謡曲が[都市]の視座から“湘南”を[リゾート]と位置づける遠近法はまだ成立していません。
「江ノ島が見えてきた」
茅ヶ崎を“湘南サウンド”の発信地として全国に認知させたサザン・オールスターズの圧倒的な貢献について、誰も否定することはできないでしょう。歌詞に「茅ヶ崎」「湘南」「江ノ島」の語を組み込んだ〈勝手にシンドバッド〉(1978)の衝撃とは、なんといっても、メロディが追いつかないほどの音韻数をダミ声でまくしたてる桑田佳祐のあの歌唱法でした。しかもこれが、テレビの歌番組で学生あがりの彼らのラフないでたちとともに放送され、それまで存在しなかった非凡な奇抜さとして、歌謡界の常識を視覚的にも聴覚的にも揺さぶったわけです。
とはいえ、もちろんそこでは、「砂まじりの茅ヶ崎」は依然としてローカルのものであって、けっしてリゾートを謳うものではありませんでした。 歌謡曲において、[リゾート]を[都市]との関係のなかで明確に定義してみせたのは、まぎれもなく《SURF & SNOW》(1980)の松任谷由実です。夏であれ冬であれ、「悩みごと」はひとまず「都会に置き去」って「自然」に触れるとき、これを「レビュー」とさえ感じる「Highな気分」が「につまる恋」をどうにかしてくれるものと期待する〈サーフ天国、スキー天国〉では、リゾート地とはまさに「天国」です。
そしてこうした着想を具現化するように、1978年から葉山マリーナではじめたコンサートを、1980年からは冬は苗場のスキー場で、1983年からは夏は逗子のプールでも、『SURF & SNOW』のタイトルで彼女が長らく開催してきたことは、「都会」のかたわらに「天国」を求めるその聴衆たちを“湘南”までリゾートに赴かせる契機ともなりました。
しかしこのアルバムにおいて、このような観点からもっとも重要な楽曲とは、おそらく〈まぶしい草野球〉でしょう。なぜなら、そこでは「草野球」を「はじめて見」ている「外野席」までがリゾート地として作用するからです。
サーフィンやスキーどころか、週末の草野球でさえが、日常の暮らしの型枠どおりの惰性からほんのわずかばかりはみだし、些細なすきまを、余白を穿ちます。そこに「まぶしい」もの、「光る」もの、そうした精神の昂揚を招く一回きりのオーラが導かれ、それがリゾートの意味となり効用となります。そしてここに「しばらく地球は止ま」り、瞬間のうちに永遠が訪れるのです。
自然に触れることとともに、そこではスポーツにおける身体感覚がオーラの現出と大きくかかわっています。サーカスやシンクロナイズド・スイミングとの協働によるレヴューを組織した松任谷正隆は、彼女のステージの演出についても照明の重要性を説いています(*20)。逗子のプールで、苗場のスキー場で、あるいは草野球の外野席で、この永遠をかいまみた精神は、都会に残してきた生活のなかでいずれ再び新鮮な呼吸をはじめます。
こうしたさなか、大滝詠一の《A LONG VACATION》は発売されました。直接的には“湘南”を参照するところのないこのアルバムについても、たとえば〈雨のウェンズデイ〉で「菫色」の「雨」が「降る」あの「海」などは、葉山の一色海岸のことだといいます(*21)。それでもやはり、任意の一般性に向けてここから揮発していく海のイメージは、荒井由実の〈天気雨〉における「茅ヶ崎」のように局所的な輪郭の具体性をすでに曖昧にしています。
洋行
GHQが退去してなおアメリカ合衆国の管理のもとにあった沖縄が日本に返還されたのは、泥沼化したベトナム戦線からのアメリカ軍の撤退を翌年に控えた1972年でした。地元では1969年に発表されていた喜納昌吉の〈ハイサイおじさん〉がシングル盤というかたちで発売されるのも、この年のことです。占領下の沖縄で生まれ育った喜納は、のちに平和思想と反戦主義を掲げて〈すべての人の心に花を〉(1980)を作りますが、この録音にはスライド・ギターなどでライ・クーダーが参加しています。
その編曲に関与した久保田麻琴は、夕焼け楽団を率いてハワイ録音を試みた《HAWAII CHAMPROO》(1975)のなかで〈ハイサイおじさん〉をカヴァーするとともに、日本の大衆音楽の航路を再び南洋へと開きます。沖縄やハワイなど、太平洋に浮かぶ島が多様な文化の融合する坩堝であること、つまりそれらの“チャンプルー”の状態は、そもそも日本もこうした島嶼にほかならず、日本文化がそうした異国文化の結節点のひとつでありうることを体感し、彼はここに大衆音楽の可能性を看取します。
このアルバムをとおして客演のドラムを叩いているのはTin pan alleyの細野晴臣です。すでに久保田から〈ハイサイおじさん〉を紹介されていた細野は、このアルバムをプロデュースするとともに自身のソロ活動の方向性について示唆を獲得し、タイタニック号で唯一の日本人乗客を祖父に持つ出自もあってか、音楽による世界横断の航海に舵を切ります(*22)。《TROPICAL DANDY》(1975)、《泰安洋行》(1976)、および《はらいそ》(1978)は、西洋化を急いた日本の歌謡曲に中国やインドを含め東洋や南洋の要素を浸透させ、日本の歌謡曲をもって極楽へと遡行するための船出となりました。
これらの50年前に堀内敬三の訳詞により二村定一が歌唱した〈あほ空〉の盤のB面には、〈アラビヤの唄〉が収録されていました。絹の道を海路で廻った細野がめざしたのはここだったのかもしれません。というのも、はっぴいえんどの盟友だった大瀧詠一の死後に発掘された生前の吹き込みのなかには、〈私の天竺〉と訳した〈あほ空〉の大瀧ヴァージョンが遺されていたからです。
つまり細野と大瀧とは、歌謡曲の可能性をめぐる旅路の果てに、結局のところあのレコード盤の裏表に漂着したわけです。
西洋の近代を輸入し、これを消化することで築かれてきた歌謡曲の歴史は、その歪曲と矮小化の歴史であったともいえます。つまりそれはひとつの擬態であり、キッチュであり、西洋の大衆音楽のパロディでした。この歪曲をどのように補正し、どこまで本場に近づくことができるのか、そうした観点から音楽性のもっともらしさを競う傾向は、いまなお日本の大衆音楽の現場から完全に払拭されたわけではありません。
それでもなお、元来、日本文化の新しさ、その独自性は、むしろ擬態でありキッチュであることの行方に存しています。そして細野晴臣の航海は、今度は翻って西洋からの異国趣味の視線で日本を省みるY.M.O.の音楽へとつながっていきます。
「南太平洋裸足の旅」
細野の音楽による航海と並行するように、このころ日本の大衆音楽の周縁で南洋に向けたある奇妙なツアーが催されています。1977年8月に、資生堂とワコールが資金提供して実施されたこのツアーは、「南太平洋裸足の旅」と題されました。参加したのは、作詞家の阿久悠や音楽プロデューサーの酒井政利、写真家の浅井慎平や版画家で小説家の池田満寿夫らでした。
電通の藤岡和賀夫が企画したこのツアーは、当時の日本のクリエイターたちを招いて特に明確な代償を求めないイメージ創造のためだけの体験旅行を提供し、この経験が彼らのその後の活動に自発的に反映されることで、キャンペーンの布陣が前面に露呈しない柔らかなブームを操作することを意図したものとされます。
彼らがめざしたのは南太平洋のいくつかの島でした。タヒチやイースター島、フィジー、ハワイ、なかでもとりわけ西サモアのサラムムという村は、旅先を調整した藤岡によれば、地上に最後に残された村にして地上に最初に生まれた村であり、究極の村、すなわち浄土とでも形容すべき、文明を拒む自然の光と空気にあふれた場所だったといいます(*23)。
そうした無垢の島での経験が、たとえば矢沢永吉の〈時間よ止まれ〉(1978)の背景となりました。無償のツアーとはいえ、現地では参加したクリエイターたちが交代で順に夜のサロンを設け、そこでの会話を電通側の参加者が録音することで、相応の実りは収穫しようとしていたものと思われます。ここで記録された、時間が止まったように文明から遮断された村での感慨を、帰国後に藤岡から資生堂のCMタイアップ曲への助力を打診された酒井政利が、矢沢永吉の新曲のうちに反映させ、〈時間よ止まれ〉が制作されました。
これ以降、山口百恵の新曲に国鉄のキャンペーンが追従する体裁で相乗効果を狙った〈いい日旅立ち〉(1978)や、池田満寿夫の小説『エーゲ海に捧ぐ』(1979)の映画化と同期し、ワコールのCMタイアップ曲となったジュディ・オングの〈魅せられて〉(1979)、三洋電機のCMタイアップ曲に採用されデビューした久保田早紀の〈異邦人〉(1979)などが大ヒットします。酒井と藤岡との協働はこのツアーの成果とするに充分な内容であり、そのいずれもが、日本の外側から、さらには内側からも、異邦人の視線をもって相対化された日本のありようを謳う楽曲となりました(*24)。
なお、このツアーに参加していた美術家の横尾忠則は、帰国からほどなく、初対面の細野晴臣を今度はインド旅行に誘い、やがて彼との共同名義で《COCHIN MOON》(1978)を制作します。Y.M.O.のための習作のようなこのアルバムを経て、細野からの打診により当初は横尾もY.M.O.のメンバーとして活動する予定でしたが、結成発表の記者会見の当日に他の仕事に追われてこれを欠席し、Y.M.O.は3名となりました(*25)。
日本航空と全日空が沖縄旅行に誘うキャンペーンを展開したのもこのころからです。1979年、日本航空のCMに山下達郎の〈夢を描いて Let’s Kiss the Sun.〉が使用されたのを皮切りに、石川優子とチャゲの〈ふたりの愛ランド〉(1984)や桑田佳祐の〈いつか何処かで〉(1988)、米米CLUBの〈浪漫飛行〉(1990)など、1982年からは全日空でも山下達郎の〈高気圧ガール〉(1983)や南佳孝の〈スタンダード・ナンバー〉(1984)、またしても山下の〈踊ろよ、フィッシュ〉(1987)など、多くのヒット曲が生まれました(*26)。
松田聖子のトロピカル
高音の抜けのよさと伸びのよさに特徴的な松田聖子の煌びやかな歌声は、やはり、汗をにじませる太陽の輝きとわずかに涼やかな潮風、穏やかに繰り返される波音にしたがって足の裏で透いた水に浚われる白い砂によく似合います。
デビュー曲〈裸足の季節〉(1980)が資生堂のCMタイアップ曲となり、これを収録したはじめてのアルバム《SQUALL》(1980)の最初の楽曲が〈〜南太平洋〜サンバの香り〉であったこと、さらに酒井政利のもとCBSソニーからデビューしたことを考慮すれば、松田聖子というアイドルの存在性そのものを「南太平洋裸足の旅」の産物とみなすことも可能かもしれません(*27)。
松本隆が松田聖子の楽曲の作詞家として迎えられたのは〈白いパラソル〉(1981)からです。すでに彼女は、ブルック・シールズが主演した『青い珊瑚礁』(1980)から着想されたものと思しき〈青い珊瑚礁〉をもって、山口百恵と交代するように女性アイドルの先頭を走っていました。
松本隆が「渚」をめぐる歌から松田聖子との協働を開始したことは当然です。大瀧詠一を作曲に招いたつづくシングル盤は、高原のリゾートへの秋の訪れに愁う〈風立ちぬ〉(1981)となっていったん海辺から離れますが、呉田軽穂の名義による松任谷由実を作曲に起用した〈赤いスイートピー〉(1982)で、春先には早くも海に戻ってきます。後続の〈渚のバルコニー〉(1982)は、まさしく松任谷由実が提案した海辺のリゾートの感覚を松田聖子のイメージに敷衍するものです。
〈白いパラソル〉を「お願いよ」と歌いはじめたことに象徴的なように、松本隆は、〈風立ちぬ〉では「心配はしないでほしい」、〈赤いスイートピー〉では「春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ」、〈渚のバルコニー〉では「渚のバルコニーで待ってて」、などと、いずれも「あなた」に態度や行動をねだる女性の人格を松田聖子に託しています。
呉田軽穂が提供した両シングル曲を含む《Pineapple》(1982)の夏は、来生たかおを作曲に起用した〈SUNSET BEACH〉における「渚の果て」の語句で閉じられます。そしていくぶん気怠い〈小麦色のマーメイド〉(1982)を経験してから次の夏、細野晴臣による音楽の航海の成果を手にすることで、彼女のトロピカルなリゾート性はついにその完成形に達します。「天国に手が届きそうな青い椰子の島」にあってなお「もっと遠くに」「連れていって」とねだるそのシングル曲〈天国のキッス〉(1983)とともに、〈マイアミ午前5時〉や〈セイシェルの夕陽〉を収録したアルバムは、まさに自らを極楽ならぬ《ユートピア》(1983)とするものでした。
ところで、たとえば松田聖子がその果てまで到達し、もっと遠くをめざすとき、そうした[渚]は、日本の大衆音楽の歴史において“翻訳ポップス”から“和製ポップス”へと継承された、女性の歌い手が叶えるある世界観を表象しているように思われます。
[渚]
漣健児の訳詞による〈渚のデイト〉(1963)や〈砂に消えた涙〉(1964)の弘田三枝子が、筒美京平の作曲をもって提起した〈渚のうわさ〉(1967)や〈涙のドライブ〉(1968)、〈渚の天使〉(1968)の主題は、〈真夏の出来事〉(1971)の平山三紀において凝縮され、端的に要約されます。
さらに〈17才〉(1971)の南沙織の率直な若さや〈初恋のメロディー〉(1972)の小林麻美の拗ねた甘えをもその変奏としてまといながら、〈暑中お見舞い申し上げます〉(1977)、〈渚のシンドバッド〉(1977)、〈夏のお嬢さん〉(1978)などとつづく[渚]の系譜の正統に、まちがいなく〈裸足の季節〉(1980)や〈青い珊瑚礁〉の松田聖子は所在していたはずです。事実、彼女の次のシングル盤の片面は、平尾昌晃が提供した〈Eighteen〉(1980)でした。
明るく爽やかで、けれどわずかばかり切なく淋しい、リゾートの季節に置き去られた渚。砂と波、大地と海洋とが、互いに稜線をせめぎあい、融合する現場にほかならない渚の潮騒は、死の影を孕んで弱まる太陽の陽射しに濾過された、瞬間ごとの生の謳歌です。彼女たちの歌声は潮風となって私たちの頬をかすめ、忘れかけた渚の感傷を預けてくれます。
松田聖子を雛型として、そこからの偏差に自らの存在性を探りつついっせいにデビューした1982年の少女たち、堀ちえみの〈潮風の少女〉や川田あつ子の〈秘密のオルゴール〉、中森明菜の〈スローモーション〉、石川秀美の〈ゆ・れ・て湘南〉ももちろん、このような渚の変奏です。
そうしたなか、〈白いパラソル〉における翳りの印象はただごとではありません。高音の抜けのよさと伸びのよさに特徴的だった松田聖子の煌びやかな歌声が、酷使のあまりかすれ、変質してしまったこともその一因でしょう。しかし、この印象は、ここではむしろ演奏の側に由来するものです。
まず、使用される楽器の種類が限定的です。これらが奏でる音数もまばらで、譜面において縦軸としても横軸としても密接していません。また、それぞれの楽器が担当する音域もそれぞれの音の帯域も狭く、総体としてここには貧しい音場が、しかも無機的に組成されるわけです。この貧しさは、とりわけ厚みのない低音部、特にシンセ・ベースの扱いに象徴的に現われています。
当初、〈白いパラソル〉は、前曲〈夏の扉〉(1981)の延長線上で夏のはなやいだ雰囲気を表現する別ヴァージョンが、シングル盤として発表されたものと同じ大村雅朗による編曲で録音されていました。たとえばステージでは、こちらの派手な演奏をしたがえて歌唱されることもあったようです(*28)。つまり、シングル盤として発表された現行のヴァージョンがもたらす渚の貧しさが、編曲や音響の設計も含め制作者によって確信犯的に企図されたものであることは、およそ疑いようのないところです。
ただし、〈赤いスイートピー〉(1982)にはじまる呉田軽穂の作品群を編曲した松任谷正隆は、担当ディレクターがかなり厚い音を好み、このため楽器をたくさん重ねたことを述懐しています(*29)。
いずれにしても、松本隆の介入を契機として松田聖子の渚に一度きりもたらされたこの翳りは、聴くものの鼓膜を毛羽だてながら撫でてきます。冷めたその肌理に、儚く脆い季節への郷愁を感じ、まるで死の淵をのぞいてしまったかのような畏怖を覚えるとすれば、おそらくそれは、「涙を糸でつなげ」る仕方で配置されたこれら音の粒が、海辺で喪失された時間の白い耀いをそこに結晶化させているからにちがいありません。
*1 畔柳昭雄,『海水浴と日本人 』, 中央公論新社, 2010, pp.51-83.
*2 福田眞人,『結核の文化史 近代日本における病のイメージ 』, 名古屋大学出版会, 1995, pp.254-255.
*3 澤村修治,『天皇のリゾート 御用邸をめぐる近代史 』, 図書新聞, 2014, pp.145-146, p.218.
*4 早津敏彦,『日本ハワイ音楽・舞踊史 アロハ! メレ・ハワイ[復刻版] 』, 長崎出版, 2007, pp.51-61.
*5 瀬川昌久+大谷能生,『日本のジャズの誕生』, 青土社, 2009, pp.38-58.
*6 服部良一,『僕の音楽人生』, 中央文芸社, 1982, p.85.
*7 瀬川+大谷, 前掲書, pp.171-175.
*8 早津, 前掲書, p.185.
*9 小林正巳,『ウクレレ快読本』, 日本評論社, 2007, pp.3-4.
*10 中村とうよう,「ハワイとその音楽」, 『ハワイ音楽パラダイス』所収, 山内雄喜+サンディー, 北沢図書出版, 1997, pp.19-20.
*11 服部, 前掲書, p.161.
*12 三井徹,『戦後洋楽ポピュラー史 1945-1975』, NTT出版, 2018, pp.21-28.
*13 堀家敬嗣,「“湘南”論 孔を喰む:零度_1」『山口大学教育学部研究論叢』第70巻所収, 山口大学教育学部, 2021, pp.51-59.
*14 瀬川+大谷, 前掲書, pp.83-84.
*15 大瀧詠一,『大瀧詠一 Writing & Talking』, 白夜書房, 2015, p.418.
*16 三井, 前掲書, pp.102-105.
*17 「湘南スタイル」Vol.14, 枻出版社, 2003, p.105.
*18 加山雄三,『湘南讃歌』, 神奈川新聞社, 2007, pp.60-63.
*19 「湘南スタイル」, p.104.
*20 松任谷正隆,『僕の音楽キャリア全部話します』, 新潮社, 2016, pp.112-114.
*21 「Pen 大滝詠一に恋をして」4/1号, CCCメディアハウス, 2021, p.25.
*22 長谷川博一,『追憶の泰安洋行』, ミュージック・マガジン, 2020, pp.54-59.
*23 藤岡和賀夫,『あっプロデューサー 風の仕事30年』, 求龍堂, 2000, pp.142-150.
*24 酒井政利,『誰も書かなかった昭和スターの素顔』, 宝島社(宝島SUGOI文庫), 2018, pp.172-200.
*25 横尾忠則+細野晴臣+糸井重里,「3人が集まった日。第2回 横尾さんは、YMOになりそこねた。」(https://www.1101.com/artmusicword/2016-11-28.html), 『ほぼ日刊イトイ新聞』所収, ほぼ日, 2016.
*26 速水健朗,『タイアップの歌謡史』, 洋泉社, 2007, pp.127-134.
*27 同書, p.116.
*28 若松宗雄,「【松田聖子ストーリー】「白いパラソル」その2」
(https://www.youtube.com/watch?v=JlE-GPpkgiw&t=319s), 若松宗雄チャンネル, 2020.
*29 松任谷, 前掲書, p.116.
堀家教授の「リゾートの歌」10選
1.〈恋人よ我に帰れ〉ディック・ミネ(1935)
作詞/オスカー・ハンマースタインⅡ世,作曲/ジグマンド・ロンバーグ,日本語詞・編曲/三根徳一
1930年には映画化もされたオペレッタ『The New Moon』の挿入歌〈Lover, Come Back to Me〉が原曲。ビリー・ホリデイやナット・キング・コール、パティ・ペイジ、アレサ・フランクリン、ブライアン・フェリーらが歌唱したほか、ルイ・アームストロングやチャーリー・パーカー、オスカー・ピーターソン、スタン・ゲッツなど、錚々たるミュージシャンが演奏している。日本ではフランク永井がこの曲でデビューし、美空ひばりも吹き込んでいるが、ザ・ピーナッツが『Ed Sullivan Show』に出演した際にはこの曲を演目として披露した。さまざまなヴァージョンのなかでも、ディック・ミネの盤はもっとも感傷的なものであろう。それには、演奏のテンポや彼自身による日本語詞と歌唱はもちろん、これをユニゾンでなぞる、ジンタを思わせるヴァイオリンの効果が大きい。最後の「待ち侘びて毎日私は泣いているのよ」のフレーズでは、ある母音が持続するなかで別の母音へとその響きを変化させていったり、ひとつの音符に「毎」の語のふたつの音韻を充て、「my」とみたてて歌うなど、ジャズのリズムに乗せて日本語を英語的に響かせる歌唱の工夫が聴かれる。
2.〈南の風〉柴幸二+南海楽友(1943)
作詞/野村俊夫,作曲/東郷安正,編曲/朝吹英一
時局からカルア・カマアイナスを南海楽友に転じた学生“ハワイアン”バンドによる傑作。「ジャズ・ソング」や「ハワイアン」のラベルも使用できず「歌謡曲」として発売されているが、イントロから堪能できる朝吹英一のヴィブラフォンと村上一徳のスティール・ギターの競演は、まさに揺らぎの風となる。これに息吹を委ねたメロディの起伏は、色の褪せないどころか、むしろ今日のもっとも好ましい歌謡曲に通底する。
3.〈砂に消えた涙〉弘田三枝子(1964)
作詞/ピエロ・ソフィッチ,作曲/アルベルト・テスタ,日本語詞/漣健児,編曲/山屋清
ミーナが歌唱し、イタリアでリリースされた〈Un Buco Nella Sabia〉を原曲とし、漣健児が日本語詞を充てた“翻訳ポップス”の名曲。多くの歌い手がカヴァーし、矢沢永吉や竹内まりやも愛唱しているが、弘田三枝子では相手が悪い。1960年代後半にはGSブームの裏で“和製ポップス”へと機軸を移行させるにあたり、弘田は若き筒美京平を作曲に起用し、〈砂に消えた涙〉の趣向をふまえつつ〈渚のうわさ〉から〈可愛い嘘〉までタイプの異なる楽曲を提供される。彼女も歌唱法を変えるなどして応え、いずれも良作となったにもかかわらず、ヒットにはつながらなかった。しかしここでの実践が、平山三紀や南沙織、小林麻美を経由して斉藤由貴まで、以降の筒美京平がもっとも得意とする曲風として系列化していく。その源泉に〈砂に消えた涙〉がある。
4.〈初夏の香り〉久保田麻琴と夕焼け楽団(1975)
作詞・作曲/久保田麻琴,編曲/細野晴臣
ハワイ録音の《HAWAII CHAMPROO》所収。駒沢裕城のスティール・ギターが全面的に浸透し、日本の大衆音楽における新しい“ハワイアン”のかたちが提示される。かつてジャズとの深いつながりのもと日本に輸入された“ハワイアン”は、ここではフォークやロックの衝撃を経由し、それらの潜在性をもさらに汲んだ歌謡曲の可能態として、“リゾート・ポップス”の嚆矢のひとつとなる。彼らによる“シティ・ミュージック”の秀作〈星くず〉をあわせて参照すれば、その位置づけはより明確となるだろう。なお、〈初夏の香り〉は、すでに同年、久保田麻琴の単独名義でシングル盤〈バイ・バイ・ベイビー〉のB面曲として発表されていたが、やはりスティール・ギターが滑るとはいえ、ややテンポの速いそのヴァージョンはボサ・ノヴァのリズムを基調とし、その意味で歌謡曲の猥雑さをより強く感じさせる。
5.〈ソバカスのある少女〉Tin pan alley(1975)
作詞/松本隆,作曲・編曲/鈴木茂
メンバーが2曲ずつ持ちよるかたちで録音されたアルバム《キャラメル・ママ》に収録。こうした制作の方針も、このバンドが明確なコンセプトを共有しないまま結成された演奏巧者の集団にすぎなかったとする松任谷正隆の印象を補強する要素ではあろう。彼はまた、メイン・ヴォーカリストが不在だったこともこのバンドの方向性を散漫なものとさせた原因のひとつに挙げるが、実際、この楽曲で作曲者の鈴木茂とともにデュエットのヴォーカルをとったのは、ゲストの南佳孝である。なるほど、たとえばこの時期の鈴木のソロ・アルバム《BAND WAGON》や《LAGOON》にこれが収録されていたとしても、ほとんど違和感はない。とはいえ、彼らがここで共演したことは、この後に“シティ・ミュージック”が“リゾート・ポップス”へと展開されるための、きわめて重要な契機となる。ボサ・ノヴァ調のギターに多様な楽器が絡みあい、複雑な音場を生むが、鈴木のヴォーカルのパートでは鈴木の曲となり、南のヴォーカルのパートでは南の曲に聴こえてくるあたりにも、演奏巧者の集団が実現した不思議な魅力がある。
6.〈時間よ止まれ〉矢沢永吉(1978)
作詞/山川啓介,作曲・編曲/矢沢永吉
キャロルの解散後、思うようにヒットに恵まれなかった矢沢永吉は、資生堂のCMとのタイアップを受け入れたこの楽曲でついにブレイクする。編曲者としてのクレジットは矢沢本人だが、実際には、彼の脳裏にある曖昧な音像を伝えるための言葉を、キーボードの坂本龍一が中心となって読み解き、具体的に音に置き換えることで実現された録音だったという。同時期に細野晴臣が試行していた音楽による航海のかたわらで、坂本がドラムの高橋幸宏と合流して「南太平洋裸足の旅」の成果に関与していたことは意義深い。その電気ピアノとともにまろやかで穏やかなスカのリズムを刻むアコースティック・ギターと、これと対になって副旋律を持続させるスライド・ギターは、のちにNOBODYとしてデビューする木原敏雄と相沢行夫が担当。
7.〈海と君と愛の唄〉南こうせつ(1980)
作詞/阿木燿子,作曲/南こうせつ,編曲/水谷公生
谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』にでも感化されたかのような、〈神田川〉に代表される四畳半フォークや、〈夢一夜〉のごとく和様の情緒に依拠する楽曲で知られる南こうせつは、しかし〈夏の少女〉を歌い、また細野晴臣の〈絹街道〉にコーラスで参加するなど、陽にして洋の側面も備えている。かぐや姫の解散後、盟友の伊勢正三の音楽が“シティ・ポップス”化し、あわせて空疎なリゾートの形骸にはまっていく一方で、南のこの楽曲は、彼が親しんだ加山雄三の音楽を、この時代に彼なりの仕方で咀嚼したものだといえる。それよりスケールは小さいがはるかに機微に満ちたこの楽曲を聴いた近田春夫は、夏のこうせつのほうが圧倒的に好きだとかつて書いたが、都会の片隅を縫うように流れる冬の神田川でさえ、その行方には夏の海が、ただしいくぶんかの「影」とともに佇む。リゾートとはそうしたものである。水谷公生の編曲は、ほとんど前景化することのないピアノがストリングスと連携するときなど、メロディとの対話のなかで楽曲の抑揚に深みを与える。
8.〈SUNSET BEACH〉松田聖子(1982)
作詞/松本隆,作曲/来生たかお,編曲/大村雅朗
アルバム《Pineapple》の最後に収録された劇的な構成のバラードであり、その曲調は歌詞にも反映される。「夕陽が海に溶ける」この「黄昏どき」は、「死」と「生」とが同居する空間的な此岸としての「渚の果て」を、また時間的な此岸としての「世界の終わり」を表現する。『地獄の一季節』のランボーならばここに永遠をみつけるだろう瞬間の詩趣を、松田聖子の堂々たる歌唱は的確に捕捉し、また終盤でフェイド・アウトしていく松原正樹ならではのギターのソロの音色も存分にこれに応える。この楽曲と並べて聴かれるべきは、他の彼女のどの曲よりも、このアルバムと同時期に、けれどわずかに早くリリースされた中森明菜のデビュー曲〈スローモーション〉だろう。やはり来生たかおの作曲によるそこでの中森の歌声は、のちの彼女のこれ見よがしの大仰な歌唱ぶりとは異なり、どこか所在なさげで、脆そうで、しかし軽やかだ。
9.〈ハニーな昼下がり〉早見優(1982)
作詞/伊達歩,作曲/和泉常寛,編曲/馬飼野康二
熱海に生まれハワイで育ったことで、デビュー当初からトロピカルなイメージをまとうことになった早見優だが、映像としてはすでにペンタックスのCMで先行的に露出していた。〈あの日に帰りたい〉が流れるなか、プールサイドで肩で呼吸する水着姿の彼女の悔いに満ちた表情は、むしろ夏の水辺の憂いを感じさせるものであった。〈ハニーな昼下がり〉は、彼女のこうした側面をもっともよく描写し、さらにこの季節の暑気と湿気による気怠さをも表現する佳曲である。それこそ〈あの日に帰りたい〉が援用したボサ・ノヴァのリズムに適切な主題であるはずが、ここではパーカッションにラテンの要素を認めるばかりで、あくまでも“シティ・ポップス”的な洗練のうちにまとまる。1stアルバム《AND I LOVE YOU》所収。作曲の和泉常寛は、こうした文脈の延長線上で、のちに〈君は1000%〉や〈アクアマリンのままでいて〉を杉山清貴の脱退以後のオメガトライブに提供。
10.〈Mirage〉JINTANA & EMERALDS(2016)
作詞/detroit baby,Jintana Emeralds,作曲/Kashif Emeralds,Jintana Emeralds,XTAL Emeralds,Chao Emeralds
一十三十一がメイン・ヴォーカルをとる、スティール・ギターのJINTANA率いるプロジェクトのはじめての日本語詞による楽曲。いわゆるオールディーズの今日的な解釈として、サイケデリックな音場のなかスティール・ギターの音色と一十三十一の歌声が鼓膜を麻痺させる彼らの音楽は、単なる懐古主義に陥らない日本の“リゾート・ポップス”の総合とも評価できる。そのもくろみがもっとも顕著に露呈するのはデビュー作の〈Honey〉や〈Runaway〉、あるいは〈Oh! Southern Wind〉だろうが、いずれも英語詞で歌われるため、ここではこの楽曲を提示しておく。なお、一十三十一のソロによるカヴァー盤《LETTERS》に収録の〈蜃気楼の街〉でもスライド・ギターが採用され、「あての無い街から届いた手紙」は海辺からの誘いとなる。Sugar Babe時代の大貫妙子が歌った原曲との対比は、日本の大衆音楽における都市とリゾートの関係性をあざやかに照射するものである。
番外_1.《A LONG VACATION》大滝詠一(1981)
屋外でLPレコードを回したまま聞き流そうと、また狭い部屋でどの収録曲を選んで傾聴しようと、いまなおリゾートをめぐるこれ以上の名盤は日本では発表されていない。より厳密には、これが発表されて以降の日本でのリゾート音楽のありかたをこのアルバムが規定し、それによってリゾートそのもののありかたさえ再定義されたのだから、これを聴かずにリゾートに耽ることはもはや誰にもできない。
番外_2.《TROPICAL DANDY》/《泰安洋行》/《はらいそ》細野晴臣(1975/1976/1978)
細野晴臣による、いわゆるトロピカル3部作。日本の大衆音楽史をふまえつつ、来たるべきワールド・ミュージックの流行の先駆となるような、音楽による航海の軌跡。これらを、たとえばトム・ウェイツによる3部作、《Swordfishtrombones》《RAIN DOGS》《FRANKS WILD YEARS》の無ジャンル性や無国籍性と並べてみれば、その先見的な意義を容易に評価できる。月下の大地の土埃に塗れたトム・ウェイツの名盤群に対して、細野のものはあくまでも陽光のもと大海の飛沫を浴びている。
番外_3. 山下達郎
彼の楽曲でリゾートにそぐわないものがあるだろうか。もはや存在そのものがトロピカル・リゾート。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





