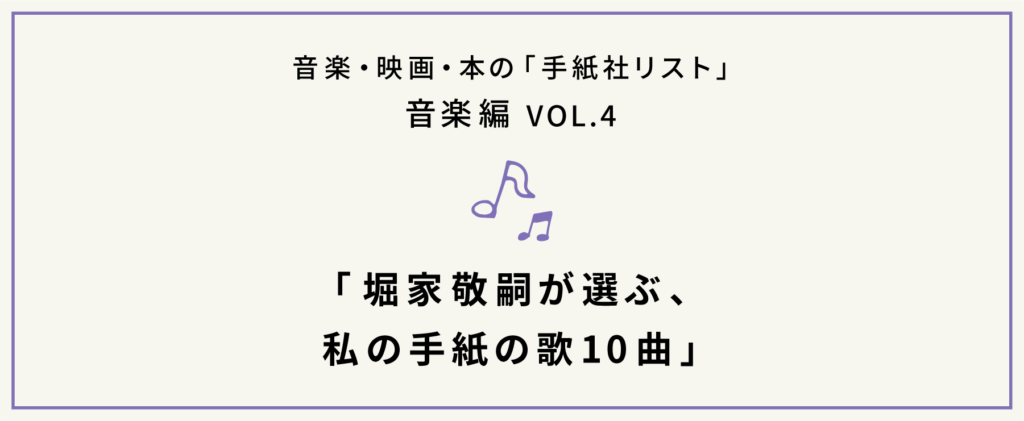
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。8月号の音楽部門のテーマは、「手紙」。“聴くべき10曲”を選ぶのは、手紙社の部員たちに向けて毎月「歌謡曲の向こう側」という講義を行ってくれている、山口大学教授の堀家敬嗣さんです。自身もかつてバンドマンとして活動し、幅広いジャンルの音楽に精通する堀家教授の講義、さあ始まります!
歌謡曲からの手紙
「ふたり」と「二人」
1971年のレコード大賞を受賞したのは、尾崎紀世彦が歌った〈また逢う日まで〉でした。ズー・ニー・ヴーが前年に吹き込んで発表された〈ひとりの悲しみ〉を、筒美京平による曲はそのままに阿久悠があらためて歌詞を書きなおしてのぞんだ、いわばそのリメイク版です。
ここで歌詞の言葉の語り手は、「あなた」と「別れ」るそのときに、あくまでも「あなた」と「ふたりでドアをしめ」、「ふたりで名前消」そうとします。作詞家はそこに、「別れ」の瞬間まで「ふたりで」ともに歩む新しい時代の男女の力学を展望しています。その歌詞は、男と女が「ふたりで」構築した関係性について、その責任を個人と個人のあいだで対等かつ均衡に按分することを理想に謳うものでした(*1)。
しかしこの作詞家による沢田研二の〈勝手にしやがれ〉(1978)では、「お前」が「想い出かき集め」て「鞄につめこむ気配」を「背中できいている」歌詞の言葉の語り手は、部屋から「出て行く」彼女を「寝たふりして」送りだします。このまま彼女が「行ったきり」でも「戻る気にな」ってもどちらでもかまわないとする、いわば主体的な選択も行動もできない自らの優柔不断さを、強がる男の「カッコつ」かない弱さの美学へとすりかえたこの歌詞の政治性をもって、阿久悠はまたしてもレコード大賞受賞曲の作詞者となります(*2)。
たとえば仮に、〈ひとりの悲しみ〉から〈また逢う日まで〉への改作にあたって、彼が新しい詞へのなんらかの着想をえていたかもしれない既成の楽曲があるとすれば、おそらくそれは、なかにし礼が作詞し、川口真が作曲した、由紀さおりの〈手紙〉(1970)のことにちがいありません(*3)。〈手紙〉もやはり、「二人で育てた小鳥をにがし」、「二人で書いたこの絵燃やし」、「二人で飾ったレースをはずし」、「二人で開けた窓に鍵をかけ」ているからです。
ただし、こうした「別れ」の局面にあって、「ふたりでドアをしめ」る〈また逢う日まで〉の場合とは異なり、おそらく〈手紙〉の「私」はただひとりきりでそれら「二人」の生活の痕跡を精算しています。「私」はひとり「小鳥をにがし」、「この絵燃やし」、「レースをはずし」、「鍵をかけ」ているのです。
というのも、このとき彼女は、「お別れの手紙」を「涙で綴りかけ」ており、ほどなくそれは「涙で綴り終え」られるからです。「二人」の生活の痕跡をひとり精算した「私」は、この「手紙」だけを置いてその部屋から去っていこうとします。そこに「あなた」の気配は感じられません。
A-B-A-Cという構造で1コーラスが成立しているこの楽曲にあって、ひとり「私」が生活の痕跡を精算する様子はBパートで描写されています。これを前後ではさんで重なるAパートの歌詞については、「別れ」の理由をめぐって「あなた」に語りかける文体であることから、ともに「手紙」の文面の体裁で「綴」られつつある言葉と理解していいでしょう。
そしてこのことを注釈するように、Cパートでは、「手紙」に没入していた「私」の視点はにわかに文面を客体視するものとなり、これを「涙で綴りかけ」ている、そしていずれ「涙で綴り終え」られた「お別れの手紙」として物質化します。短調を基調とする編曲のなか、このパートばかりが長調的にふるまい、7thを多用して展開されます。とりわけその2小節目は、他のパートになく洒脱なⅲ△7→ⅵ△7のコード進行を響かせ、これをⅠ△7→Ⅳ△7として聴かせることも、「私」の視点が超越的な位相にあるところと端正に印象づけます。
残すことの女性性
ここで歌詞の言葉の語り手は、いわば「手紙」の言葉の書き手から〈手紙〉の言葉の歌い手へとその身分を移行させるわけです。このとき、由紀さおりの歌声は、「私」が「綴」る文字の輪郭をなぞることをやめて、ようやく彼女自身のものとなります。
〈また逢う日まで〉では、歌詞の言葉の語り手は「別れのそのわけは話したくない」うえに、「ふたりで名前消して」もなお、ようやく「心」で「何かを話す」にすぎません。それどころか、「あなた」が「何処にいて何をしてる」かも彼は「ききたくない」とまで思っています。
こうした姿勢は、歌詞の言葉の語り手が「寝たふりし」ながら「背中できいている」だけの〈勝手にしやがれ〉についてもたがうところがありません。「さよなら」はもちろん、「あばよ」とさえ口にするものかおおいに疑わしい彼が聴くのは、「お前」からの別れの言葉、その最後の声ではなく、あくまでも「派手なレコード」に記録された音楽です。
おそらくは部屋の前に掲げられた表札の「名前」が「消」され、またなにを「話したく」も「ききたく」もないそこでは、言葉は、文字として記されることも、また音声として発されることも忌避されているわけです。ここで歌詞の世界から徹底的に放逐され、排除されたはずの言葉は、しかしその外部においては尾崎紀世彦や沢田研二といった歌い手の声を借りて、もっぱら楽曲の聴衆に対してむしろ積極的に、その「心」の「何か」を告白します。
こうしたことは、由紀さおりの〈手紙〉の「私」が「お別れの手紙」を「綴」っていたことと明確な対照をなすところであり、それゆえこれらはみごとなまでに相互補完的です。
〈手紙〉における歌詞の言葉の語り手である「私」は、「死んで」までも「あなた」に「つとめ」ることを願っているものの、にもかかわらず「明日の私」よりも「あなたの未来」を優先させて慮るなか「別れ」を決意した、いわば男性に従属的で犠牲的な古風の女性です。
〈また逢う日まで〉は、この不均等な男女の力学を脱してその関係性の責任を平衡させ、これを「ふたり」がともに応分に負担する新しい時代の進歩的な思想を謳いました。〈勝手にしやがれ〉では、さらにこの力学は更新され、今度は男の側が捨てられる自分の不甲斐なさを甘受します。
このように、一見したところ進行する時代に歩調をあわせて、あの〈手紙〉における男女の古風な力学を更新していったかに思える阿久悠の歌詞の世界観は、けれど実際には、言葉に対する不変の姿勢をもって、旧態依然とした価値観のなかに鈍重に収まりつづけています。というのも、そこでは文字としてであれ音声によってであれ、男性が言葉を残すことを厭う一方で、たとえば女性は「想い出かき集め」、これを「鞄につめこ」んでいるからです。
〈勝手にしやがれ〉における「お前」のこの行為は、いうまでもなく、〈手紙〉の「私」が「お別れの手紙」を「涙で綴りかけ」ているさまと同義です。要するに、黙して語らない性を男らしさとして囲い、過去の痕跡を残すことに拘泥した性を女らしさと捉える性差の枠組みが、そこではなんら訝しまれることなく存続しているのです(*4)。
この限りにおいて、都はるみによる〈北の宿から〉(1975)で「寒さこらえて編」まれた「着てはもらえぬセーター」とは、読んでもらえないとはわかっていても「女ごころの未練」としてしたためずにはいられない、毛糸で綴られた手紙なのです。
文面としての歌詞
歌謡曲においては、歌詞が手紙の文面を装い、あるいは文面それ自体として扱われることもあります。これは、手紙と歌詞とがともに言葉という共通のメディアをもって綴られているからです。
ただし、言葉には、片面を文字言語、もう片面を音声言語とする二側面があります。つまりそこには、書記された言葉と発声された言葉との区分があるわけです。手紙は文字によって記される一方で、歌詞は音声によって歌われるものです。それでもなお、歌詞の言葉が手紙の文面を模するとき、それは、作詞家がこれを音声の持続というよりはむしろ文字の連続として着想していることを意味します。
たとえば坂本真綾の〈おきてがみ〉(2003)は、楽曲の最初で「3月16日午前5時30分」、最後には「3月16日サウスウィッシュボーン3番地」と歌っています。これは、〈おきてがみ〉と注釈された文面が書かれたのだろう時間と場所とを記録したものと理解できます。
しかし歌詞の言葉が手紙の文面を装う仕方としてもっとも明瞭なその表明とは、手紙の文面を構成する定型的な挨拶の語句や文句がそこに援用される場合でしょう。
加川良は、彼が作詞して吉田拓郎に提供した〈加川良の手紙〉(1972)が、まさしく手紙の文面にメロディをつけ、そのまま歌詞として詠ずる試みであったことを述懐しています(*5)。実際、「拝啓」ではじまるこの歌詞は、「ごきげんよう」で文面を終えるその契機として、「紙が残り少なくな」ったことを口実とします。ここでは言葉は、あくまでも「紙」のうえに書き込まれる文字であることが、ただし音声によって謳われているわけです。
メロディの起伏やそこへの言葉の乗せかた、さらには歌唱法など、まさに吉田拓郎を思わせる真心ブラザーズの〈拝啓、ジョン・レノン〉(1996)の歌詞も、やはり「拝啓」の語から綴られていますが、ここではさらに、その文面の送付される行方が「ジョン・レノン」であることが示され、手紙の体裁を強調します。
「拝啓」とあらたまったうえで、人称代名詞ではなく固有名詞に宛てられた言葉は、平常なら軽々には口にできない敬意や重みを意味内容に付帯させ、相手に届けます。
音声とは、なんらかの音源から発せられた振動の波が、空気などを媒介としてその振幅を衰微させつつ、とにもかくにも鼓膜へと到達する範囲でのみ、それとして聞こえるものです。したがって、音声が語る情報を耳で直接的に聴取するためには、その受け手は、所在すべき位置を“いま・ここ”に限定され、時間的にも空間的にも制約されます。端的にいって、情報の受け手は、その音声が発生した瞬間に、その音声が到達できる場所にいないことには、この情報を獲得する権利さえないわけです。
こうした制約が解除されるには、音声の振動の記録、つまり録音技術が確立されて時間的な延長を実現し、もしくは音声を電波として送信する放送技術が確立されて空間的な拡張を実現するまで待たなければなりませんでした。
手紙を含め、書簡は、少なくとも意味内容の伝達について、この制約を別の仕方で克服するものとして、古来より機能してきました。まずそれは、音声をもって語られた雑駁な情報を、文字という別の媒体への置換のプロセスを介在させることで要約します。このうえで、文字による紙面への記録は、そこに記載された情報が空間と時間を超えて広がりをもつことを可能にします。
文語
実際、〈拝啓、ジョン・レノン〉は、手紙の体裁を採用することで私たちが存在する此岸さえ超え、すでに鬼籍にある彼岸のジョン・レノンに歌詞の言葉を宛てています。加えてこの歌詞の場合には、「拝啓、ジョン・レノン」の歌いだしを追って「あなた」と呼びかけ、ここからしばらくは語尾をいわゆる“です・ます”調で閉じた文章を綴ることで、いよいよ手紙の文面を擬態する精度を高めていきます。
ところが、メロディアスなこのAパートから調子を一転させ、歌唱がラップとも台詞の語りともつかなくなるBパートでは、「ジョン・レノン」を「あの」と指示することで二人称的な立場から逸脱させ、手紙をめぐる送り手と受け手の関係性はここでにわかに脱臼してしまいます。
それ以降、歌詞の言葉は、とたんにその語り手のこころのなかへと内向し、あとは「僕」の心境やら感慨やらが吐露されるばかりとなります。語尾を“です・ます”調で閉じることさえ放棄したそれは、もはや手紙であるよりも、むしろ日記として綴られた文章のようです。
この限りにおいて、書簡における定型的な挨拶の語句や文句の使用とともに、[あなた]に語りかけた文章の語尾を敬体すなわち“です・ます”調で閉じることは、単なる語りかけ以上によりあらたまった態度のもと、これを歌詞による手紙の文面の偽装を請け負う一助とするものと考えられます。
かつて日本では、書簡も書籍も文語体をもって記されていました。情報としての音声が直接的に届かない空間や時間にまでその要点を伝達する書簡や書籍の流通は、漢字や漢文の輸入がこれを可能にしたところであり、文語体とは、まずは漢字や漢文の様式を応用して情報を紙面に登録するための、固有の記載法にほかなりません。
この記載法の採用にあたって、音声や会話における肌理や機微といった具体性のいちいちは、そこでは損なわれるのが当然です。というのも、そうした肌理や機微とはいわば私的な個別性だからです。これらは、そもそも紙面に登録してまで空間的にも時間的にも隔たった誰かに伝達すべき要点でも、また文字によって忠実に再現できるその等価的な要素でもない、ある種の情報の余剰、無駄、すなわち雑音なのです。
漢文訓読体をはじめ、音声言語として日常的に話される言葉とは異質の文語体を操作する能力、つまり文字言語を読み書きする運用能力とは、社会にとって必要な情報を抽出し、適切に扱うためのひとつの公的な教養であり、その意味で特権的な技量だったわけです。
けれど明治維新による近代化は、とりわけ言葉による表現者のうちに個人の意識の芽生えをうながします。そして、書簡や書籍のなかでそれまでは等閑視されてきた私的な言語の肌理や機微によってのみ、ようやく表現できるなにごとかについて、彼らは思いをめぐらせます。あるいはむしろ、こうした肌理や機微こそが、彼らの新しい時代に表現すべき真正の価値だったのかもしれません。
言文一致体
なにかに記録されることを前提としないまま発された瞬間に消えていく音声のみを頼りに、日本語の言葉の体系はすでに成立していたはずです。ここに、まったく異質の記号体系として、新しい概念とともに漢字や漢文が輸入されます。このとき、言葉は、音声をとおして表現された意味内容を、さらにはその音韻を、文字の機能を借りて一定程度の再現精度のもと保存することを着想します。
日本語の歴史とは、音声から文字への、文字から音声への、その変換と圧縮、保存と解凍の効率をめぐる洗練の歴史でもあるわけです。このことは、いまや言葉のわかちがたい二側面として表裏に密着し、ひとつの言語として統合されているかに思える音声と文字とが、本来はまったく別の位相に所在する異質の記号体系であることを示唆します。
外山正一らの『新体詩抄』(1882)や二葉亭四迷の『浮雲』(1887)の模索を嚆矢とし、『文学論』(1907)が夏目漱石の苦悶をうかがわせつつ、詩や小説といった文字言語における表現の舞台で展開され、普及していく言文一致体は、音声と文字との本質的な乖離を可能な限り解消し、隔絶を埋め、齟齬をすりあわせる試みです。
さまざまな文面が話し言葉としての口語に近似するとき、そこではいわば書き言葉の民主化が謳われることになります。もはや特権的ではなく、誰もが口から発するように手で記すことのできる言葉。
実際、語尾を“です・ます”調で統一する敬体はもちろん、現代の文章表現においては公的で硬直的な、それゆえいくぶん高圧的な印象を与えもする“だ・である”調で統一された常体でさえ、近代化それ以前の文語体のあれこれと比較すれば、私たちの話し言葉とはるかに親しいものとなりました。
ただし、口語体とは、常体であれ敬体であれ、あくまでも文字によって書かれた文章における言葉の今日的なありようを規定するものであって、話し言葉そのものではありえません。話し言葉とは、そもそも音声による言語体系なのだから、文字それ自体が固有の音声をもって私たちに話しかけてくるわけではない以上、私たちは私たち自身の声でそれを読むよりほかないでしょう。
それでもなお、たとえば小説において、常体で書かれた地の文章に対して、文章の語尾が敬体で閉じられる文章を鉤括弧でくくるとき、読者はこれを登場人物の声として聞いたような気になることも事実です。
敬体とは、その読み手に敬意を示す表現です。あらためて[あなた]と呼びかけずとも、敬体の使用のみをもってすでにその文章は、そこにいる読み手に対して言外で[あなた]と語りかけているのです。
書簡、とりわけそれが私信の文面ならばなおさらです。この場合の多くは受取人が差出人の声を聞いたことがあるうえに、そもそもそれは受取人に宛てて私的に書かれたものだからです。ここでの文面の目読は、まさしく黙読であるがゆえに、鼓膜が記憶している差出人の声による[私]のための音読を錯覚させるかもしれません。手紙を手紙たらしめるもの、それは、音声になろうとする文字の潜勢力なのです。
詩と詞
現代において、文字で記された詩と音声で唱えられる詞との相違を指摘し、その混同を懸念したのは松本隆でした。これとともに、彼は、詞が詩に劣ったものと位置づけられる現状を憂います。彼のいう詞とはまさに歌詞の言葉ですが、これが音響と融合した楽曲となってはじめて一単位である限りにおいて、歌詞の言葉はせいぜいがその半身なのだとする観点について、ここで彼は悲嘆しているのです(*6)。
歌詞の言葉とは、詞先の場合であれ曲先の場合であれ、はじめから音声によって歌われることを前提に書かれるものです。自作詞の歌い手ならば自身の声で、松本のような職業作詞家においては依頼もとの歌い手がその声で、これらの言葉を歌唱してはじめて、ようやくそれは歌詞となって届けられます。換言すれば、なんらかの音声によって歌われないことには、それは歌詞にはなりえません。
松本隆によるはっぴいえんどの〈風をあつめて〉(1971)について考えてみましょう。彼の自伝的な要素が幻覚的な光景をまとったここは、「街のはずれ」であり「昧爽どき」であり、なんら「人気のない」そこでは、語としてさえ「ぼく」よりほか誰の気配も認められません。
にもかかわらず、松本は歌詞の言葉に敬体を使用しています。ではいったい、ここで「ぼく」は誰に対して「見えたんです」「翔けたいんです」などと語りかけ、その敬意を預けているのでしょうか。
もちろん、一義的にはそれは、この楽曲の聴衆に向けられたものにはちがいありません。しかしながら、ここではやはり、ただそのためだけに言葉が選択されているようには思えません。
基本的に松本隆の詞先で制作されたはっぴいえんどの楽曲において、彼らのなかでその方向性の検討やイメージの共有といった作業は介在せず、また松本も、メロディや音響について考慮することなく綴った言葉を、彼からの指名で細野晴臣や大瀧詠一に委ね、作曲を依頼していたとされます(*7)。このとき、細野や大瀧には、まずは紙面の文字として松本から歌詞が手渡されていたわけで、まさにそれは作詞者から作曲者への手紙だったことになります。
そのうえで、〈風をあつめて〉の「ぼく」に幻視された“風街”の光景が、松本隆の声ではなく細野晴臣のそれをとおして出来していることはきわめて重要です。
松本は、自分が文字として綴った歌詞の言葉を歌唱している細野の声を、自らの分身のものとして、だがけっして自身と一致することのない隔たりの違和のうちに聴いています。それは彼に固有の経験や記憶、あるいは主観的な光景や幻覚的な感触といったその内面の自明性を、本人の声とは異なる響きをもって相対化し、彼の身体から分離させます。
このころ細野は、自身の声や歌唱について苦悩し、そのありかたを模索していました(*8)。楽曲のできばえを、それを歌唱する自身の音域や声量といった身体性をふまえないまま優先させていたといいます(*9)。つまり細野も、彼の理想とは異質の響きをそこに聴き、これをいまだ自分のものにできずにいたわけです。かつての彼の歌唱については、声をただマイクに乗せるだけで歌を聴衆に届ける意識が希薄だったとする印象を矢野顕子が述べています(*10)。
要するに、いまここで松本の耳は、細野の声ではあっても細野のものではない匿名の響きを借りて、もはや自明ではない脳裏のイメージから語りかけられ、これと対話し、そのかたちと邂逅しているのです。内面に抱え、その身体とともに久しく自分自身として馴致してきたはずのものを、瞬間ごとに生きなおす現在の自分に宛てて、外部としてあらためてこれに向きあうこと。
この意味では、〈風をあつめて〉の歌詞の言葉は、それを文字に綴った松本隆が聴衆たる彼に宛てた、ただし「ぼく」よりほか誰ひとりそのように聴くことを許されていない手紙にちがいありません。
手紙としての歌謡曲
事実、〈風をあつめて〉は、最初のアルバム《はっぴいえんど》のために録音されながら、細野の意向により唯一ここに収録されなかった〈手紙〉の歌詞をもとに、「風をあつめて」の語句を生かして松本があらためて作詞したものです(*11)。
かつてはラジオから流れていた歌謡曲が、消費経済の進行にともなってレコード盤とその廉価な再生装置が流通し、誰でも容易にこれを購入できるようになった時代、それは、必要とあらば聞き手が繰り返しこれを再現して傾聴できる時代の訪れでした。回転する盤面に落とされた針が、そこに渦巻き状に刻まれた一本の溝線の凹凸をなぞるとき、吹き込まれた音声はそのたび蘇生し、本来ならば発された瞬間に消失することを運命づけられている音声に、紙面の文字の性質を担保します。
ヴァレンタイン・ブルーがはっぴいえんどに改名した1970年ごろからの音楽産業のこうした側面をふまえるならば、流行したのは手紙についての歌謡曲というよりはむしろ、手紙としての歌謡曲だとする見解もあります(*12)。単に〈加川良の手紙〉のような場合に限らず、宛てられた手紙の文字を、その文面を読むような仕方で歌謡曲は聴かれたのです。
音声になろうとする文字の潜勢力が手紙を手紙たらしめたように、そうした歌詞を歌詞たらしめるのは、文字になろうとする音声の潜勢力です。それでもなお、そこでは詞が詩になろうとしているわけではありません。詞はもっぱら詞のままに響きつつも、ときに私たちが求めるその分節化が、これをたちどころに吃らせるのです。歌詞を採録した文字列とは、まさしくこうした吃音の残響にほかなりません。
阿久悠が作詞したあべ静江の〈みずいろの手紙〉(1973)にも、歌詞の言葉が手紙の文面として綴られているくだりがあります。しかしその言葉は、歌いだしに先んじて台詞として語られています。そして後続する歌唱の本篇では、おそらくは「あなたへの手紙」に文字化できなかった「私」の「泣きそうな心」のうちが告白されます。
このとき、手紙の文字が台詞を語る声をもって表象される一方で、文字になれなかった「心」の余剰、無駄、その雑音は、メロディにそって歌唱する声のもとようやく吐露されます。ここでは文字を介することで「心」がその顕在性と潜在性とに峻別され、語る声の抑揚と歌う声の起伏とをもってその身分の差異を明瞭に区別されているわけです。
この楽曲もやはり、歌謡曲が手紙のように聴かれた時代のものです。とすれば、むしろそこでは、文字にされた「手紙」を読む声と「手紙」になれなかった「心」を歌う声とが聴かれるとするよりも、表の「手紙」を読む声と裏の「手紙」を歌う声とが聴かれるものと考えるべきでしょう。
「私」の「泣きそうな心」は、文字になれないまま「あなたへの手紙」における「便箋」の「涙いろ」に「たく」されます。「あなた」に「書い」た「手紙」を読む声の裏側で、彼女の「なおさらつのる恋心」を歌う声が「便箋」を「涙いろ」に染めるのです。
この「涙いろ」の「便箋」こそは、裏の「手紙」以外のなにものでもありません。あべによる歌声の音色とは、すなわち台詞の語りとして実現される「手紙」の文字を支える潜在性、要するに「便箋」という紙の肌理なのです。
書く行為としての歌唱
〈みずいろの手紙〉は、その翌年にデビューした木之内みどりの最初のアルバム《あした天気になあれ》でカヴァーされています。彼女のデビュー曲〈めざめ〉の作詞と作曲は、〈みずいろの手紙〉と同じ阿久悠と三木たかしによるものであり、それを収録したアルバムのA面をすべてこのコンビの楽曲で埋めるなかで採用されたのでしょう。
ところで、木之内みどりの盤では、冒頭の台詞による語りは吹き込まれていません。このことは、〈みずいろの手紙〉から文字が、文面が、表の「手紙」が消失してしまったことを意味する一方で、裏の「手紙」、要するに「涙いろ」の「便箋」それ自体の前景化を承認します。
そうしてにわかに前景化してきたこの「便箋」に、では文字は記されなかったのでしょうか。おそらくそうではありません。なぜなら、「なおさらつのる恋心」を、その「泣きそうな心」を「たくし」ながら、いま「私」は「あなたへの手紙を書いてい」るさなかにあるからです。その文面が紹介されることのないまま、「手紙」の文字はあの「便箋」に記されつつあります。
木之内みどりの歌声が淀みなくその響きを更新しているとき、それは、「私」によって「手紙を書」く行為が遂行されつつある瞬間そのものです。そうして「書」かれつつある言葉は、彼女の歌声が通過するやいなや、たちまちそこから消失してしまうことは不可避です。その歌声が私たちの鼓膜の表面に固着することがけっしてないように、この言葉もまた、「便箋」のうえで「書き」終えられることはありません。
ここでもやはり、歌詞の言葉は、文字への転生を叶えられない音声の潜勢力として響いてきます。文面を「読」まれることはおろか、おそらくは「あなた」のもとへ届くことすらないこの「便箋」は、だから「涙いろ」なのです。
「青い便箋が悲しいでしょう?!」と尋ねたのは〈心もよう〉(1973)の井上陽水でした。ここでも「手紙」は、いままさに「したため」られつつあります。しかし「私の気持は書け」ないまま、「さみしさだけ」を「つめ」た「手紙」が「あなたに送」られるとき、「文字」は「埋もれてしま」い、「青い便箋」にはただ「きれい」な「黒いインク」の染みばかりが残されます。
松田聖子の〈風立ちぬ〉(1981)の「私」もやはり、「高原のテラス」で「手紙」を「したためてい」るただなかにいます。ここで彼女が「SAYONARA」の語を綴ったのは、透明な「風のインク」によってでした。深呼吸した身体からその外側へと吐かれる空気をもって声帯を振動させ、この振幅をたどって聴かれる彼女の歌声とは、それこそ「風のインク」でなくていったいなにでしょうか。
アンジェラ・アキの自作曲〈手紙〜拝啓 十五の君へ〜〉(2008)では、基本的には歌詞の全体が手紙の文面を模しています。その1コーラス目では、「十五の僕」から「未来の自分」に宛てて「悩み」を「打ち明け」る言葉が投じられます。2コーラス目は、これに対する返信として、「十五のあなた」への励ましの言葉で「大人の僕」が応じます。
ここで注目すべきは、「誰の言葉を信じ歩けばいいの」かわからない「十五の僕」に向けて、「大人の僕」が「自分の声を信じ歩けばいい」と忠告していることです。これがまさしく「拝啓」の語から綴られはじめた「手紙」であるにもかかわらず、彼は、そこに記された「大人の僕」の文字ではなく、あくまでもこれを読む「自分の声」を「信じ」るように説いています。
手紙から遠く離れて
書き残された文字には証拠能力があります。けれど発された瞬間に消えてしまう音声には、その内容の真偽を問うこと自体、ほとんど意味をなしません。
「言葉交わすのが苦手な君」が「この海辺に残」すのは「いつも置き手紙」ばかりと嘆く宇多田ヒカルの〈Letters〉(2002)の「私」が、たとえ「夢の中」であれ「電話越し」であれその「声を聞きたいよ」と願う場合、だからそこでは、音声による言質の確保がなんら模索されているわけではありません。この言葉の話し手がその音声とともにここにいること、言葉が更新する時間をその行為の主体とともに生きること、「私」にとっての真実とはそうしたものであり、音声が語ることの信憑性もまたそこに求められるわけです。
仮に「言葉交わすのが苦手なら」ば「置き手紙」の類いはもう「何もいらない」とさえ言明する「私」には、完了してしまった言表のうちにではなく、遂行されつつある言表行為そのものにこそ意味があるのです。
手紙とは、ときに空間的な、ときに時間的な、ときに精神的な隔たりを埋めるための手段です。この限りにおいて、そこに隔たりがあること、およびこれを埋めようとする意思があることが前提とされています。しかし手紙はまた、これを実現する枠組みのなかで機能する文化的な産物でもあるため、こうした文化の外部にある異種の文化との交流は、手紙以前もしくは手紙以後の、あるいは手紙以外の手段でなされるよりほかないでしょう。
この観点からすれば、文字言語を習得する以前の幼児にのみ異星との交信が可能だと示唆する、赤い公園による〈交信〉(2013)のプロモーション・ヴィデオは秀逸です。とはいえ、いま私たちは、単なる異星ではなくむしろ異次元へと、身体から解かれた精神の所在する次元へと、あらかじめこの楽曲が宛てられていたものと訝りはじめてもいます。紙やペンやインクはおろか文字すらない世界では、音声が響く保証もないはずで、逆にそうした世界からの手紙は、文字や音声に依存した私たちの覚醒しないうちに、私たちの思いもよらない仕方ですでにこの世界のそこここに浸透しているのかもしれません。
実際、たとえば100sの〈光は光〉(2005)にあっては、「星の光」が「過去から幾光年分の手紙」として収受されています。換言すれば、この世界で視野に映るものすべては「手紙」なのです。
100sの中村一義が個人の名義で発表した《100s》は、その全曲をのちの100sの演奏で吹き込み、100sが結成されるきっかけとなったアルバムです。そこに収録された中村と池田貴史との共作〈Yes〉(2002)の歌詞では、これが「親愛なラブソング」に宛てて「書」かれた「ラブレター」であることが謳われます。ここで「ラブレター」は、さらに「君」と呼ばれて擬人化され、「僕」の「心」への「ノック」をうながされます。要するに、ここでは「ラブソング」への「ラブレター」が「ラブソング」として歌われているのです。
音声になりたい、けれどなれない文字と、文字になりたくて、それでもなれない音声。手紙と歌謡曲の歌詞とは、互いに焦がれる言葉のふたつの相貌がもっとも錯綜する現場であり、もっとも混濁した出来事にちがいありません。
したがって、由紀さおりの〈手紙〉において、「私」が「涙で綴りかけた」あの「手紙」、彼女がようやく「涙で綴り終えた」あの「お別れの手紙」は、「涙」ながらに書いた「手紙」であると同時に、透明な「涙」によって「綴」られた、それゆえ最初から音声のように、由紀の歌声とともに消失することを運命づけられた「手紙」だったのです。
*1 阿久悠,『阿久悠 命の詩〜『月刊you』とその時代〜』,講談社, 2007, pp.110-111.およびp.216.
*2 同書,p.212.
*3 同書,p.187.
*4 舌津智之,『どうにもとまらない歌謡曲―七十年代のジェンダー』, 晶文社, 2002, pp.188-200.
*5 『吉田拓郎読本』, 音楽出版社, 2008, pp.44-45.
*6 松本隆,『風街詩人』, 新潮社(新潮文庫), 1986, pp.10-16.
*7 門間雄介,『細野晴臣と彼らの時代』, 文藝春秋, 2020, pp.138-143.
*8 同書, p.135.
*9 同書, p.453.
*10 同書, p.246.
*11 同書, pp.121-122.およびp.146.
*12 舌津,前掲書, p.204.
堀家教授による「私の手紙」10選
1.〈手紙〉由紀さおり(1970)
作詞/なかにし礼,作曲・編曲/川口真
一聴したところ、歌詞の言葉の古めかしさにふさわしく前時代的な短調の歌謡曲であるかに思えて、Cパートでその印象を慎ましく覆し、これをもってAパートやBパートの効用を逆照射してみせる川口真の傑作。そのパートの1小節目のⅳm7→ⅶ7は、これを受ける2小節目に軽やかで洒脱なⅲ△7→ⅵ△7の響きを配され、これをもって長調におけるいわゆるツー・ファイヴのⅡm7→Ⅴ7としてふるまうものの、3小節目ではルート音を段階的に下降させて短調のツー・ファイヴとなるⅱm7♭5→ⅴ7に展開し、ひとまず4小節目にはⅰmへと回収される。しかし2コーラス目においては、4小節目のⅰmも2拍ごとに分割されてⅰ7へと移行し、ⅳm7を導いてコード進行を循環させながら、由紀の歌声とともにフェード・アウトしていくことになる。川口の才覚は、旧来の歌謡曲ならばⅴm→ⅰmとしよう2小節目にⅲ△7→ⅳ△7の進行を選択し、これをⅠ△7→Ⅳ△7として機能させたところにある。
2.〈さらば恋人〉堺正章(1971)
作詞/北山修,作曲・編曲/筒美京平
1971年の日本レコード大賞を尾崎紀世彦の〈また逢う日まで〉と競った候補曲のうちのひとつが、同じ筒美京平の作曲によるこの作品だった。しばしばアルバート・ハモンドの〈カリフォルニアの青い空〉との類似を指摘されるが、発表は〈さらば恋人〉のほうが早い。北山修による「僕」は、「さよならと書いた手紙」を「テーブル」に「置い」て、「君」に「黙っ」たまま「一人」で「外へ飛びだ」してしまう。この別離の風景は、〈また逢う日まで〉の阿久悠が、「別れ」る男女に「ふたりでドアをしめ」させたり「ふたりで名前消」させるなどして提示した「別れ」の新しい様式に対して、いかにも褪色の気配を禁じえないことが、堺の楽曲が大賞を失した理由のひとつにはあるかもしれない。なお、たとえば「サヨナラだけの手紙」は、久保田早紀による〈異邦人〉の「私」が「迷い続けて書」いたところでもある。
3.〈みずいろの手紙〉木之内みどり(1974)
作詞/阿久悠,作曲・編曲/三木たかし
https://www.youtube.com/watch?v=CRcRpl1zI4c
前年にあべ静江が歌唱した楽曲のカヴァーだが、原曲ではイントロにかぶせて語られていた「手紙」の文面と思しき台詞は、ここでは完全に排除されている。このことは、「君にあて」て「書いた」という「とても素敵な長い手紙」について、「なにを書いたかはナイショ」だとする小沢健二の〈僕らが旅に出る理由〉などとともに、歌謡曲における言葉のありようをめぐる問題意識を照射する。つまりそこでは、「書」かれた言葉は誰に対して「ナイショ」とされたのか。あるいはむしろ、ここで「あなた」や「君」以外の誰に対して歌詞の言葉は綴られているのか。高音側に抜ける澄んだ声で「みずいろ」を「涙」の透明さへと希釈するあべの礼儀正しく模範的な歌唱法に対して、甘く鼻にかけた声で伸ばした母音をしゃくりあげる木之内の歌唱法は、いくぶん声質は異なるものの、のちの松本伊代の歌唱法と通底する新しさをもって、あべの歌声をとたんに古びさせる。歌唱を規範に従属させるのではなく個人的な肌理に委ねる仕方は、「手紙」の本来的に私的な性質ときわめて親和性が高い私的な歌唱法といえる。このヴァージョンを推す理由である。ここで「手紙」を記すのは、発声の明確さや音程の正確さといった歌唱力ではなく、あくまでも歌い手の声質とその歌唱法なのである。1stアルバム《あした悪魔になあれ》所収。
4.〈カナダからの手紙〉平尾昌晃 畑中葉子(1978)
作詞/橋本淳,作曲/平尾昌晃,編曲/森岡賢一郎
平尾昌晃が、自身が主催する音楽スクールの生徒から抜擢した畑中葉子とともにデュエットで歌唱し、〈時間よ止まれ〉以来の歌謡曲による世界旅行ブームに加担することとなった一曲。男女デュエットであるからには混声パートのほか男声パートと女声パートが準備されているが、にもかかわらず歌詞は男性の立場と女性の立場で描きわけられていない。その結果、平尾と畑中とは、ときに顔を見あわせ、瞳を交わしながら、なぜか「あなたの居ないひとり旅」について同一の視点からデュエットしてみせる。おそらくは女性と思しき「私」が綴る歌詞の言葉は、したがって平尾が歌唱するパートではクロス・ジェンダー化し、にわかにムード歌謡の様相を呈する。とはいえ、メロディのキャッチーさは抜群で、またイントロやオブリガードにおける松原正樹のリード・ギターもこれによく応えて印象に強く残る。
5.〈アメリカン・フィーリング〉サーカス(1979)
作詞/竜真知子,作曲/小田裕一郎,編曲/坂本龍一
イントロのアルペジオのほか、参加する楽器の数が少ないAパートでは生ギターにまぎれるように見え隠れしている電子音の成分が、この編曲が坂本龍一によることのわずかな手がかりである。サビへのブリッジから派手に参入してくるブラスの按配が心地いい。しかしなにより、この楽曲でもっとも胸に刺さるのは、1コーラス目から2コーラス目への間奏において、ここにのみ適用されるⅣ→Ⅴon Ⅳ→Ⅲm7→Ⅵmのコード進行に乗るストリングスの旋律である。この旋律は、あらかじめ小田裕一郎が準備したものか、それとも坂本があつらえたものか、いずれにしてもこれとほとんど同じコード進行のもと、きわめて類似した旋律が、谷山浩子の〈カントリー・ガール〉のエンディングでもやはりストリングスによって演奏される。1小節あまりのほんの短いフレーズであるからには偶然のことだろうが、さらにいえば、これらは〈みずいろの手紙〉のイントロにおける5小節目から6小節目の持続の組み込みとして響く。
6.〈カントリーガール〉谷山浩子(1980)
作詞・作曲/谷山浩子,編曲/山川恵津子
「好・き・だ・よ」の語句に集約されるサビの歌詞の言葉は、1コーラス目には「きみ」の様子を観察する語り手のものとして、2コーラス目には「若い男」が「きみ」に「手わたし」た「手紙」に「書かれてい」た「セリフ」として、3コーラス目には「捨て」られた「きみ」が「鏡に映」る「自分」に対して「つぶや」く「あいつがくれたいくつかの言葉」として、その都度ステイタスを変化させ、歌唱される。ただし、ここまでしか歌唱されないシングル盤では、レコードの盤面サイズの都合により本来の楽曲から4コーラス目が削除されていた。のちに発表されたヴァージョンでは全篇が収録され、それにともなって事態も急変する。そこには突如として「はじめから終わりまできみを見ていた」という「ぼく」が登場するばかりか、「あの手紙の言葉」は「ぼくが書いた」とさえ告げるのである。「あいつ」の友人の「ぼく」が彼の「手紙」を代筆していたのだろうか。しかしここではやはり、超越的な視座にある1コーラス目のあの語り手が、そのままこの歌詞の言葉の書き手でありながら、登場人物である「きみ」に語りかける資格を獲得すべく自らを「ぼく」と称して歌詞の言葉のなかに人格を投入し、「ぼくが書いた」登場人物のありようを、「ぼくが書いた」あの「言葉」で慈しんだものと理解すべきかもしれない。
7.〈渚のラブレター〉沢田研二(1981)
作詞/三浦徳子,作曲/沢田研二,編曲/伊藤銀次
〈ス・ト・リ・ッ・パ・ー〉とともに、沢田研二のメロディ・メイカーとしての可能性を存分に感じさせる秀作。ここでは「口笛」の音が「ラブレター」となる。ロッカ・バラードだが、リードはもちろん2拍と4拍のコード・カッティングにもディストーションの効いたギターを採用し、単なるオールディーズ調の懐古ではなくその今日的な解釈を試みている。 GSでのキャリアは言うまでもなく、ソロ活動を開始してからも、通俗的にではあれたとえばグラム・ロックの雰囲気を歌謡界に紹介するなど、すでに沢田の貢献は無視できるものではなかった。阿久悠の関与においてこの作詞家のダンディズムを投影され、その理想を体現する役目を期待されることで窮屈そうだったジュリーも、このころにはそうした束縛から解かれ、かなり自由に音楽と関わる余地が生じたのだろう。とりわけこの楽曲では、編曲の伊藤銀次の存在が重要であり、ニュー・ウェイヴ的な要素をジュリーにまとわせ、また彼と佐野元春との邂逅を媒介するなど、新たな魅力の開拓に尽力している。
8.〈ファンレター〉岡本舞子(1985)
作詞/阿久悠,作曲・編曲/山川恵津子
リヴァーブの深い、スペクター的な“音の壁”風の音作りだが、しかしその輪郭は明瞭で、特にイントロにおけるスネアの4つ打ちをはじめ、ドラムスの音が女性アイドルのシングル盤にしてはきわだっている。これは、声量や音程の安定性に定評のあった岡本舞子の歌唱が可能にした設定と思われるが、それでもなお切れのいい清涼感と清潔感に満ちた佳曲である。ここでは「想い」を伝える媒体ではなく、むしろ「想い」そのものが「ファンレター」とみなされている。それが「届」き、これを「開」き、「読んだらすぐに」ここまで「翔んできて」と請うあたり、「手紙読んだら少しでいいから私のもとへ来て下さい」と願った〈みずいろの手紙〉に比しても、いくぶん率直とはいえ根本的な発想の転換はなく、作詞家の言葉に旬があることは否めない。
9.〈夢の中で会えるでしょう〉ザ・キング・トーンズ(1995)
作詞・作曲/高野寛,編曲/村松邦男
和製R&Bを知った最初がザ・キング・トーンズの〈グッド・ナイト・ベイビー〉だという高野寛が、内田正人の声を想定して作ったこの曲は、もともとザ・キング・トーンズへの提供曲だったSUGAR BABEの〈DOWN TOWN〉のイントロでのコード進行を引用し、またAパートの歌いだしにはまさに〈グッド・ナイト・ベイビー〉の歌いだしのメロディが組み込まれている。タイトルはもちろん大瀧詠一の〈夢で逢えたら〉を参照させるものである。しかし、ドゥワップ式のスローなロッカ・バラードを基調とする〈グッド・ナイト・ベイビー〉に対して、この楽曲はむしろマーヴィン・ゲイ的なグルーヴ感のクールさに内田の歌唱を委ねている。編曲はSUGAR BABEのギタリストだった村松邦男が担当。当時は実現しなかったザ・キング・トーンズによる〈DOWN TOWN〉の吹き込みは、この楽曲とともに《SOUL MATES》に収録されることとなった。
10.〈手紙〉フジファブリック(2018)
作詞・作曲/山内総一郎,編曲/フジファブリック
フジファブリックがこうした歌詞の楽曲を〈手紙〉として発表するとき、彼らの活動を知る聴衆の多くが、彼らの本旨にかかわらずその宛て先として志村正彦を想起してしまうことは、どうにも無理からぬところだろう。作詞した山内総一郎をはじめ彼らもまた、それを理解のうえで発表したはずだから、この楽曲がそのように聴かれること自体には是も非もない。あらかじめ孕まずをえないそうした意味をオブラートに包むように、ポップ・ロック調のアレンジのなか、エレキ・ギターとほとんど同じ資格で緩衝材のようなストリングスが響く。しかしこの楽曲の、あるいはむしろこの歌の本質は、山内が自身のアコースティック・ギターのみを頼りに弾き語るときに聴かれる粗野なかたちのなかにある。
番外_1.〈オレンジ色の絵葉書〉冨田靖子(1983)
作詞/長谷川千津,康珍化,作曲/柴矢俊彦,編曲/大谷和夫
手紙でなく「絵葉書」であるため番外とした。来生えつこと加藤和彦による武田久美子の〈噂になってもいい〉や売野雅勇と来生たかおによる伊藤麻衣子の〈微熱かナ〉など、1983年の女性アイドルのデビュー曲にはこれに類似した曲調が採用される傾向にあったが、どれも忘れるには惜しい良曲である。冨田の場合を含め、それらの歌い手のいずれも、すでに女優であったかのちに女優になる人びとであり、この流れは1981年の伊藤つかさや薬師丸ひろ子の歌手デビュー、さらには杉田かおるの成功を傍目ににらんだものであったかもしれない。とすれば、杉田の〈鳥の詩〉や伊藤の〈もう一度逢えますか〉は、こうした系譜の先駆ともなるだろう。
番外_2.〈光は光〉100s(2005)
作詞/中村一義,作曲/中村一義,池田貴史
このバンドの1stアルバム《OZ》所収。「星の光」を「過去から幾光年分の手紙」として収受するとき、いまや地球上を網羅する電子網が伝播させるあらゆる光はそのまま「手紙」の謂いとなるだろう。電子の時代には、もはや「手紙」は染みとその支持体を必要とするものではない。メールはもちろん、音声も画像も動画も、デジタル化された光の明滅は、そのことごとくが「手紙」である。電子の時代の「手紙」の可能性は、物質の時代を生きた手紙の制度的な機能不全を通告するとともに、失調した手紙が翻ってむしろ物質それ自体として存在しはじめることを示唆する。
番外_3.〈交信〉赤い公園(2013)
作詞・作曲/津野米咲
サビのメロディをこのような展開でつむぐことのできる作曲家の才能に疑うところは微塵もないが、実のところその真価は、Aメロとこのサビを接合する「開かなくなったかい」の部分、わずか2小節あまりのそのブリッジに存しているように思われる。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





