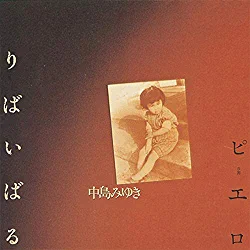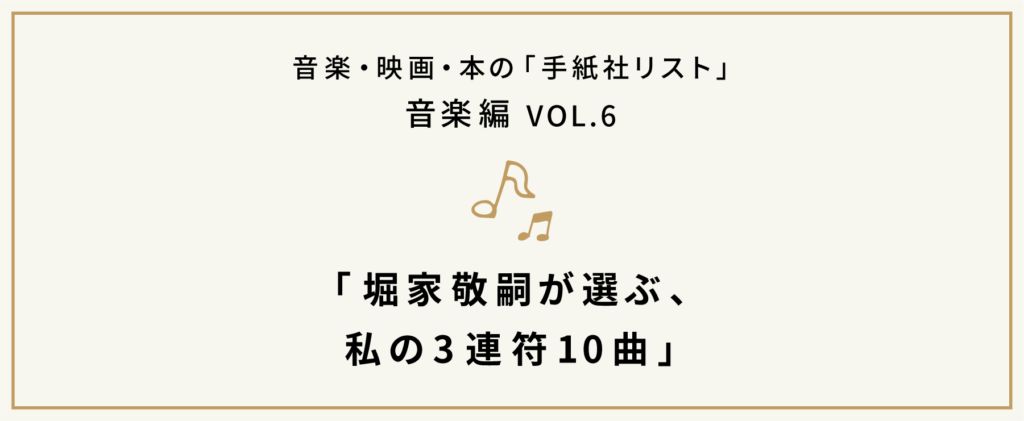
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。10月号の音楽編のテーマは、「私の3連符」。“聴くべき10曲”を選ぶのは、手紙社の部員たちに向けて毎月「歌謡曲の向こう側」という講義を行ってくれている、山口大学教授の堀家敬嗣さんです。自身もかつてバンドマンとして活動し、幅広いジャンルの音楽に精通する堀家教授の講義、さあ始まります!
三つ数えろ、歌謡曲
3連符
五線記譜法において、4分の4拍子とは、ひとつの小節の長さを4等分して楽曲の脈拍を記述することです。脈拍の定期的な律動が拍子であり、4分の4拍子の場合には、4等分された拍子を表現するために音符が等間隔で四つ並びます。この音符が4分音符です。
ひとつの小節のなかで4分音符ふたつ分に相当する倍の長さを表現するためには2分音符が、この2分音符ふたつ分に相当し、ひとつの小節のあいだ持続する長さを表現するためには全音符が使用されます。
逆に、4分音符の半分の長さを表現するのが8分音符で、これを八つ並べて小節を埋めれば小節の持続は8等分されることになります。さらにその半分の長さが16分音符です。
ひとつの小節を4分音符で等分することを基本に刻まれるリズムが4ビート、それを8分音符で刻むことを基本とするのが8ビート、そしてこれが16分音符の場合には16ビートとなります。
音符が表現する音の長さのことを音価といいます。4分の4拍子においては、ある小節を構成するすべての音符について、それぞれの音価は任意の音価に対して2の倍数の関係性のなかで相対的に位置づけられます。しかし、実際には音楽は動的な持続です。記譜法とは、あくまでも生きた音楽を固有の仕方でインクの染みに変換して紙面に記録し、一定の精度での保証する手段にすぎません。
デジタル技術の発達により、16等分であれ32等分であれ、いまや文字どおり機械的に、ひとつの小節の長さを完全に均等に分割した出音が可能になりました。これを演奏と呼ぶかどうかはともかく、指定された音が譜面にしたがって完璧な時機で再現され、その精度は狂うべくもないでしょう。
仮に、人間による楽器の演奏についてそれが可能であるものとして、そうして等間隔に配分された音符をその都度正確に出音していったところで、おそらくそこにグルーヴ感を創出することは困難なはずです。絡みあうすべての楽器において、出音の時機や音価、音量、音質などにみる波のような揺らぎが編む響きの持続こそがグルーヴ感であり、したがってジャズにおける“スウィング”の概念とそれは密接に関わるものです(*1)。
ところで、4分の4拍子の場合には、4等分された拍子を表現するために音符が等間隔で四つ並びます。これが4分音符でした。この4分音符の音価をさらに2等分したものが8分音符ですが、ではこれを3等分するとき、五線記譜法はどのように対応するのでしょうか。
その場合、4分音符の音価に相当する1拍につき、8分音符を通常のふたつではなく三つ並べたうえで、これが1拍を2等分する8分音符ではなくそれを3等分するものであることを明示するために、三つを連結してひとつの単位とみなす「3」の数字を音符の上部に記入します。
こうして表記される音符を3連音符、もしくは単に3連符といいます。そしてこのように1拍が等間隔の連続する三つの音符で分割されるときには、そのリズムを1拍3連と表現します。ここではひとつの小節につき3連符が四つ直列しえます。結果的にはそれは、ひとつの小節につき8分音符で12連拍することと同義のため、このリズムについて8分の12拍子と理解することもできます。
この1拍3連のリズムが、ジャズにおける“スウィング”の概念をよく説明します。
ひとつの小節を等分するふたつの8分音符について、その長さを1:1ではなく、たとえば2:1の比率で演奏するとき、そこではある種の跳ねの律動が招来されます。右足と左足を均等な歩幅で交互に踏み込む規則正しい行進に対して、それは、いわば軽やかなスキップの跳ねる足どりにみられるリズムです。
このリズムは、わらべうたや音頭にもみられ、もともと日本にも土着のものとも指摘されています(*2)。〈蛙の夜廻り〉(1929)で野口雨情が歌詞に充てたオノマトペに由来する“ピョンコ節”の名のもと、同じ中山晋平の作曲による〈兎のダンス〉(1924)など、幼児や児童に対する音楽教育のなかで近代的な童謡に頻出します。促音や撥音、拗音を招いて身体によくなじみ、律動的な所作や遊戯を誘いやすいのかもしれません(*3)。
“ロッカ・バラード”
ジャズにあっては、そうした跳ねの意識は、記譜に頼るまでもなく演奏者による“スウィング”の感覚をもって実現されました。しかしいまや一般にシャッフルと形容されるこのリズムは、1拍3連における第1音符および第2音符をタイでつないで統合し、第3音符はそのままに1拍3連を2:1の長さに還元したふたつの音符として記譜することができます。
服部良一が作曲した〈蘇州夜曲〉(1940)なども、そうして1拍3連の符割りを内在させた楽曲との解釈が可能です。もちろん、1拍の長さを単純に三つに等分した記譜に律儀にしたがったところで、そこにグルーヴ感は創出されないでしょう。あくまでもそれは、演奏者らの感覚をもって実演の現場で瞬時に織りなされる相互作用によるべきものだからです。
ロバート・ジョンソンのスライド・ギターが〈Cross Road Blues〉(1937)の冒頭ですでに奏でてもいる1拍3連のリズムは、しばしば“ロッカ・バラード”と関連づけられますが、“ロッカ・バラード”とは単にポップス寄りで甘めの、バラード調のロックン・ロールを意味する曖昧な概念であり、1拍3連の楽曲すべてが“ロッカ・バラード”というわけではないのはもちろん、“ロッカ・バラード”がすべて1拍3連なわけでもありません。 とはいえ、“ロッカ・バラード”の基盤にしばしば1拍3連の律動が援用されたことも確かです。
事実、ポール・アンカの〈You Are My Destiny〉(1957)では、1拍3連を刻む和音弾きのピアノの打鍵を大仰なストリングスの奥に聴くことができます。そのデビューとなった〈Diana〉(1957)は、日本でも山下敬二郎による〈ダイアナ〉(1958)をはじめいくつかのカヴァー版が存在します。そこに1拍3連の符割りを維持する楽器の演奏は聞こえてきませんが、しかしその拍子のいちいちに3連の鼓動を感じることはできます。
仮にここに1拍3連の符割りを強調するなんらかの出音をかぶせるならば、たとえばザ・ビートルズの《With the Beatles》(1963)における〈All My Loving〉のように、忙しなくも過激な楽曲となっていたことでしょう。
仮にここに1拍3連の符割りを強調するなんらかの出音をかぶせるならば、たとえばザ・ビートルズの《With the Beatles》(1963)における〈All My Loving〉のように、忙しなくも過激な楽曲となっていたことでしょう。
1拍3連の符割りで楽器の出音が認められる印象的な事例となるのは、やはりよりテンポの遅い楽曲であり、ザ・プラターズによる〈Only You〉(1955)などは、1拍3連の“ロッカ・バラード”の典型的な音盤です。
ドラムスもろとも聞こえる楽器の出音すべてが同期して3連の符割りを刻む前奏にあって、第1小節の3拍目までギターとピアノがそろって9連打したB♭の和音は、3連の符割りを保持しつつ4拍目のみ構成音をそのまま半音下げてAの和音で3連打されたのち、第2小節の冒頭でB♭に戻って4分音符の音価で1拍を埋めてからいったん消音されます。
伴奏が止んだ無音状態のなか、3拍目と4拍目のそれぞれにまたしても4分音符で「on-ly」のふたつの音節を今度はヴォーカルに割り当て、第3小節の冒頭で「you」の語の歌唱にあわせて再開された演奏では、すでに3連の符割りを負担しているのはE♭の和音を打鍵するピアノのみとなります。
前奏においてこれほどまでに強烈に1拍3連のリズムが刻印されるならば、あとはヴォーカルやコーラス・ワークの邪魔にならないようピアノだけにそれを委ねたところで、律動の印象は十分に管理できるところと確信した編曲であるように思われます。
フィル・フィリップスの〈Sea of Love〉(1957)やエルヴィス・プレスリーによる〈Can’t Help Falling in Love〉(1961)の伴奏では、ドラムスのハイハットとピアノの分散和音とが3連の符割りに乗って鳴らされます。
〈Blue Velvet〉(1963)、〈Mr. Lonely〉(1964)、〈Coming Home Soldier〉(1966)等、ボビー・ヴィントンには1拍3連を採用したヒット曲が多く、その貢献を認めないわけにはいかないでしょう。〈Blue Velvet〉(1963)のリズムはむしろシャッフルと形容されるべきですが、〈Mr. Lonely〉(1964)では、〈Sea of Love〉や〈Can’t Help Falling in Love〉と同様にハイハットとピアノの分散和音とが3連の符割りに配当されています。
ザ・ライチャス・ブラザーズが歌唱した〈Unchained Melody〉(1965)は、映画の劇中歌として1955年にトッド・ダンカンによる吹き込みで発表された当初は、まだ1拍3連のリズムに嵌め込まれていませんでした。
“リズム&ブルース”周辺
ハイハットによる切断面をオルガンの持続音が貫通するパーシー・スレッジの〈When a Man Loves a Woman〉(1966)もまた、このリズムにもとづく傑作のひとつです。ザ・プラターズやパーシー・スレッジは、いわゆるR&Bの系譜に位置づけられます。
日本における“リズム&ブルース”の先駆といえば、やはりザ・キング・トーンズでしょう。《Lover’s Nocturne》(1969)では〈Only You〉もカヴァーした彼らは、その代表曲〈グッド・ナイト・ベイビー〉(1968)のAパートを緩やかな1拍3連のリズムに費やします。雨音のように転がるピアノの分散和音が刻むそのリズムは、しかしサビが小節単位の体感速度をにわかに倍化させるなか、いったん放棄されずにはいません。
デビュー曲となるシングル盤のジャケットで、まさしく「リズム&ブルースの女王がうたう我国で初めてのR&Bのオリジナル」と謳ったのは、和田アキ子の〈星空の孤独〉(1968)でした。日本流の「リズム&ブルース」を本場の「R&B」と区別したうえで、ついに模倣や歪曲を排した真正性の獲得を本邦で最初に達成したところと誇るこの楽曲にも、やはり1拍3連が採用されています。
村井邦彦が編曲を担当し、サビの最後の節回しでは〈Unchained Melody〉を想起させるこの楽曲のほか、和田は、たとえば〈笑って許して〉(1970)などでもこのリズムに執着し、あたかもそこにR&Bの本質を見透かしているかのようです。ここでは、GmにはじまりCmへと移行し、再びGmへともどるAパートの冒頭の8小節のあいだ、1拍3連の符割りにしたがって刻まれつづけるピアノの金属的な高いG音が鋭く鼓膜に刺さります。
小坂忠の最初のアルバム《ありがとう》(1971)に収録された〈機関車〉には、のどかなカントリー調の編曲が施されていました。しかしR&Bに傾斜した《HORO》(1975)のための吹き込みでは、この楽曲は、リズムによる主張に禁欲的なため“ブルース”の側面を前景化させています。それでもやはり、ここに内在された1拍3連の律動は、2コーラス目の歌いだしのG#音へ向けて、間奏の最後の小節で3拍目から4拍目をよぎるように、8分休符を合図にC#音から半音刻みで五つの8分音符が6連符となって下降していくピアノのフレーズに、わずかながら露呈する機会を実現します。
RCサクセションによる〈スローバラード〉(1976)は、アコースティック・ギターとピアノとがそれぞれの仕方で和音を分散させるAパートなど、1拍3連の符割りを継続的に意識させるバラードです。ただし表題どおりのそのスローさゆえに、ここでひとつの小節を1拍3連の4拍分の長さで区切って8分の12拍子と捉えることも、もしくはその半分の2拍分ごとに区切って8分の6拍子として捉えることもできるでしょう。それはあくまでも記譜における便宜の問題となります。
ところで、《Abbey Road》(1969)におけるザ・ビートルズの〈Oh! Darling〉では、ピアノが刻む和音の連打が、ハイハットより以上に堅固に1拍3連のリズムを維持し、さらにサビにあってはここにエレクトリック・ギターの単音弾きがかぶさります。〈This Boy〉(1963)をみても、ロックン・ロールやR&Bなど古きよきアメリカの大衆音楽からの影響を表明する一種の賛辞として、彼らがこのリズムを引用していることは明白です。
日本においても、キャロルを解散した矢沢永吉の個人名義によるデビュー曲〈アイ・ラブ・ユー, OK〉(1975)などは、そうした趣旨をうかがわせながら、なお〈Oh! Darling〉からの反響までも届けてきます。南佳孝の〈スローなブギにしてくれ(I want you)〉(1981)もまた、〈Oh! Darling〉を参照するところのけっして寡少とはいえない楽曲でしょう。
〈胸が痛い〉(1989)の憂歌団がもっとも歌謡曲に接近していたとすれば、それは、ほどなく田原俊彦に〈ジャングルJungle〉(1990)を提供することになる羽田一郎を作曲に迎えたことよりもむしろ、2拍目と4拍目とに強烈なアクセントを配する明確な1拍3連のリズムを採用したことによるものと考えられます。
安室奈美恵が歌唱した〈Don’t wanna cry〉(1996)や〈SWEET 19 BLUES〉(1996)では、1拍を刻む音符の数はもはや8分音符の3連ではなく、このそれぞれが16分音符に分割され、6連に倍増します(*4)。
アイドル周辺
古きよきアメリカの大衆音楽への賛意は、それがほとんど時間差なく輸入され、日本語の歌詞をつけて紹介されていた高度経済成長期の日本の歌謡曲に対する郷愁とも不可分です。
アン・ルイスの〈グッド・バイ・マイ・ラブ〉(1974)を作曲した平尾昌晃は、こうした時代に日本におけるロカビリーの先駆的な体現者として、平尾昌章の名義でミッキー・カーチスや山下敬二郎らとともに人気を博しました。歌い手として活躍するなかで、“ロッカ・バラード”、とりわけ1拍3連のリズムと歌謡曲との相性のよさを彼は実感していたにちがいありません。
アン・ルイスについては、この楽曲の自己模倣といっていい〈Linda〉(1980)もまた佳曲です。つまりそこでは、古きよきアメリカの大衆音楽とともに、高度経済成長期の日本の歌謡曲を、さらにはかつての自身の楽曲を参照しながら、反復される差異のうちに郷愁を共鳴させているわけです。
ここで詞曲を担当したのは竹内まりやであり、これは彼女が作家として他の歌い手に楽曲を提供した最初のものです。いかにもそれらしいコーラスの響く編曲には山下達郎も名を連ねています。その後も彼女は、たとえば河合奈保子のシングル盤にこのリズムで〈けんかをやめて〉(1982)を提供します。アイドル歌手のイメージの生成のために“ロッカ・バラード”を巧みに換骨奪胎し、洋楽の消化と吸収の次第が良質の歌謡曲のそれと認めたからか、この楽曲は筒美京平にも褒められたといいます(*5)。
伊藤つかさの《さよなら こんにちは》(1982)収録の〈パジャマ・パーティー〉は、〈Linda〉と〈けんかをやめて〉のあいだをつなぐように発表されました。これを介するとき、それらに通底するこのリズムが竹内まりやのなかでいかに加湿され、古きよきアメリカの香りを日本の聴衆の鼓膜に適合するものへと脱臭していったのか、その過程がよく把握できます。〈本気でオンリーユー〉(1984)や〈恋の嵐〉(1986)など、彼女の音楽の核心には1拍3連の脈動があります。
ところで、歌い手としての彼女の代表曲となった〈不思議なピーチパイ〉(1980)も、響きとしてはスネアのフィル・インなどに限定的に活用されるばかりとはいえ、やはり1拍3連の符割りに基礎づけられていました。これを提供した加藤和彦の跳ねる律動は、さらに伊藤つかさの〈夕暮れ物語〉(1981)へと移植されます。
なお、竹内まりやの作曲による〈パジャマ・パーティー〉および〈けんかをやめて〉、加藤和彦の作曲による〈不思議なピーチパイ〉および〈夕暮れ物語〉では、いずれも編曲を清水信之が担当しています。
松田聖子の声質が“ロッカ・バラード”によく共振することは、1拍3連の符割りに頼るまでもなく、たとえばキャシー・リンデンの〈Heartaches at Sweet Sixteen〉(1959)を下敷きに平尾昌晃が書いた〈Eighteen〉(1980)の歌唱において予見されえたものでした。だからこそ、ジャズの揺れも意識しつつバラードの側に軸足を置いた〈SWEET MEMORIES〉(1983)は、1拍3連の符割りに単なる甘い記憶の回顧だけではない洗練された新しさをもまとわせて、作曲と編曲を担当した大村雅朗の傑作となります(*6)。
1980年代前半は、古きよきアメリカの大衆音楽に親しみつつ高度経済成長期に生まれ育った世代が、その蓄積のもとこうして作り手の立場から歌謡曲の中枢に浸透した時代でした。
初期のチェッカーズに楽曲を供給していた芹澤廣明も、おそらくそうしたひとりです。それらの楽曲の趣旨は、チェッカーズの名称や彼らのチェック柄の衣装が示唆するように、英国を経由して再解釈されたロカビリーを歌謡曲に転写することにあり、その髪型を含めきわめて厳密に設計されたものでした。〈星屑のステージ〉(1984)は、こうした試行において1拍3連を刻む偉業のひとつにほかなりません。
芹澤による〈少女A〉(1982)を成功への糸口とした中森明菜は、〈飾りじゃないのよ涙は〉(1984)の詞曲のために井上陽水を招きます。ここではAパートの5小節目から8小節目にわたり、エレクトリック・ピアノと思しき音が、1拍3連の符割りにのっとってF#音とD音のあいだで半音ごとに下降と上昇を繰り返します。4音トリルとでも形容すべき疾走感にあふれる高域でのこの装飾は萩田光雄の編曲によるものであり、彼女の歌唱を歯切れよく加速させるきわめて挑発的な誘因となります。
〈飾りじゃないのよ涙は〉の作家である井上陽水が、その発売の直前に発表した〈いっそセレナーデ〉(1984)には、なるほど3連符が響く機会こそないものの、この心悸に聴き手の側が1拍3連の律動を同調させることは可能かもしれません。
後藤次利が作曲し、工藤静香が歌唱した〈抱いてくれたらいいのに〉(1988)では、再解釈の対象がロカビリーよりはむしろR&Bに傾斜して設定され、この後の安室奈美恵の登場を予告するものとなります。問題意識を〈星屑のステージ〉とどれほどか共有しつつも、歌謡曲の度合いをいっそう重く深化させる湿潤への耽溺は、やはり後藤の作曲による渡辺美奈代の〈雪の帰り道〉(1986)においてさらさらと雪の軽やかに舞うさまと比較するとき、いよいよ詳らかとなるはずです。
ポップス周辺
《SYMPHONY #!0》(1985)に収録された杉真理の〈僕のシェリーと少し〉は、ザ・キング・トーンズがめざした“ドゥー・ワップ”の体裁のもと、彼らへの敬意を1拍3連の符割りに忍ばせた良曲です。事実、地声と裏声のあいだでスタッカート気味に高音部の音程をたどるここでの彼の歌唱は、内田正人の仕方を想起させずにいません。のちに杉真理は、そのリズムによる〈夕焼けレッドで帰りましょう〉(1998)をザ・キング・トーンズに提供しています。
すでに〈ブルー・シャトウ〉(1967)の作曲者として知られ、シャネルズを〈ランナウェイ〉(1980)でデビューさせた井上忠夫は、この“ドゥー・ワップ”をより歌謡曲に適合させることに貢献した功労者です。井上大輔に改名したのち、彼は〈涙のスウィート・チェリー〉(1981)でシャネルズに1拍3連の律動を託しています。
ところで、3連符の“ロッカ・バラード”を配置できるように画策しながらサザンオールスターズのアルバムを制作してきたことを、桑田佳祐が証言しています(*7)。たとえば《ステレオ太陽族》(1981)からシングル盤として切りだされた〈栞のテーマ〉は、この形式を積極的に敷衍した楽曲として、彼らの演目のなかでもよく聴かれているところでしょう。
とりわけここでは、その符割りにしたがってピアノが刻む和音の進行がいかにも“ロッカ・バラード”的に響きます。実際に、Aパートにおける歌いだしのⅠ−Ⅲm−Ⅳ−Ⅴ7の展開は、ボビー・ヴィントンが歌唱した〈Mr. Lonely〉とまったく同一です。
3連符を主役として扱い、もっとも効果的に使用した楽曲のひとつに、大滝詠一の〈君は天然色〉(1981)があります。前奏から複数のアコースティック・ギターとピアノが総力で刻む1拍3連のリズムでは、同時録音に起因するそれぞれの楽器からの出音のずれや変化が絡んで音像にうねりや広がりが担保され、その音響空間の奥行きを深めます。
しかしそればかりではありません。この前奏が準備した8小節のAパートののち、「別れの気配をポケットに隠していたから」と歌唱される8小節のBパートにおける前半の4小節のみ、4分音符ではなく2分音符の音価が3等分され、ベースが中心となって2拍につき4分音符の3連となる2拍3連のリズムを強調するように演奏されます。4分の4拍子を基調としつつ、その4分音符に3拍子を組み込むものだった3連の符割りは、ここでにわかに2分音符に組み込まれ、複合リズムの様相を呈してきます。
荒木一郎が自らの詞曲のもといったん発表した〈空に星があるように〉(1966)については、海老原啓一郎による“カレッジ・ポップス”を予見する編曲を施されたその音盤が、拍を裏打ちするアコースティック・ギターのストローク等に耳触りのいい佳品であったことは疑いありません。それでもなお、この楽曲の潜在性を確実に実現してみせたのは、なんといっても神保正明に編曲を任せた1976年の再収録盤のほうでしょう。
3連符の気配をまったく感じさせない当初の音源に対して、エレクトリック・ピアノの独演による前奏からはじまる再収録盤でもまた、その律動を刻む楽器の出音が聞こえてくるわけではありません。アコースティック・ギターによる分散和音も、ひとつの小節を均等に8分割したうえで単音で弾かれます。
にもかかわらず、そこには確実に1拍3連のリズムを認識することができます。というのも、ここでは荒木の歌声が、1拍3連の符割りに依拠して歌詞の言葉を旋律に乗せているからです。「浜辺」や「心」、「東」や「流れ」、「小雨」や「枯葉」、そして「季節」といった三つの音節からなる語句の歌唱にとりわけそれは表現されており、当初の音源の場合と比較すればこのことは明瞭です。
和音の変化に乏しいAパートにクリシェを導入するなど当初から洗練のみられた音楽性も、エレクトリック・ピアノとフルートの響きのもとさらに詞曲を粒立たせ、この再収録盤をもって、彼の〈空に星があるように〉は歌謡曲の歴史が誇るまぎれもない傑作へと浮揚します。
荒木一郎とともに日本のシンガー=ソングライターの嚆矢となった加山雄三の〈君といつまでも〉(1965)も、“ロッカ・バラード”を援用した典型的な事例です。
坂本九の〈見上げてごらん夜の星を〉(1963)は、もともとは永六輔といずみたくが関与したミュージカル舞台の劇中歌として用意された楽曲でした。より大仰な主題を扱ってはいますが、ストリングスのありようをはじめ〈君といつまでも〉に通底するところがあります。“ロッカ・バラード”にジャズの名残りを委ねるあたり、〈SWEET MEMORIES〉の原型といえるかもしれません。
フォーク周辺
〈Can’t Help Falling in Love〉(1961)の作家陣のひとりであるジョージ・デヴィッド・ワイスは、ルイ・アームストロングの吹き込みによる〈What a Wodnderful World〉(1967)の制作にも参加し、ここでも1拍3連に頼ります。ただしそこでこの符割りを聴覚的に実現するもの、それは、もはやハイハットでピアノでもなく、アコースティック・ギターによる分散和音です。
フォーク系の音楽が3連符のリズムを援用する場合には、そこで中心的に扱われる楽器の性質に多くを負っているものと考えられます。つまり、フォーク系の自作自演の歌い手が奏でるアコースティック・ギターという楽器のありようが、彼らの楽曲に3連符の符割りを先験的に要請しているのです。
ギターには6本の弦が張られています。このうち、3本の太い弦は和音における根音、すなわちベース音を提示し、そのどれかの弦を鳴らすことで1オクターヴの音の幅が担保されます。要するに、これら3本の低音側の弦のうちどれか1本のみ、ある指定された和音に応じて根音を奏でるために弾かれるわけです。他方で、高音側の細い3本の弦は、その根音から3度や5度の関係で積まれる構成音をそれぞれ負担するため、ここでの音の重なりかたがその和音の響きや機能を決定づけることになります。
アコースティック・ギターを指で鳴らすことが多いフォーク系の音楽の場合、左手の指で和音を構成する各弦の音程を押さえ、右手の指が弦を爪弾いて出音します。特に、和音の構成音を単音ずつ順に出音していく分散和音の奏法においては、親指が低音側の3弦すべてを担当します。高音側の3弦については、そのそれぞれを人差し指、中指、薬指が1本ずつ担当します。換言すれば、ここで出音される和音は、低音側の1音と高音側の3音とで構成されるわけです。
だから、あるリズムにそって低音側から高音側へと、親指から薬指へと順に弦を弾いていくときには、右手の運指として一方通行のまま、四つの音の発生を等間隔でずらしながら和音を奏でることになり、親→人→中→薬が分散させた四つの音でひとつのまとまりが成立します。
ここで同じリズムにそったまま、右手の運指を、低音側から高音側への一方通行でなく、薬指が最高音の第1弦を弾いたあとで高音側から低音側へと順に回帰させ、いわば循環的に往来させてみましょう。すると、今度は中指が、そして人差し指が、より低い第2弦を、そして第3弦を順に弾いて戻ります。ここでは親指が担当する最低音と薬指が担当する最高音とは一度きり出音され、その往来のなかで人差し指と中指とは再度の出音の機会が訪れることになります。
ここでは親→人→中→薬→中→人によるのべ六つの音の発生の機会をもって、ひとつの演奏の単位が成立するのです。
これを4分の4拍子におけるひとつの小節にまるごと充当させるならば、4拍6連、すなわち2拍3連となります。そして2拍にこの六つの音の発生の機会を圧縮した場合に、2拍6連、すなわち1拍3連となるわけです。
このように、1拍3連を基本的な単位とする演奏は、指先でアコースティック・ギターの弦を爪弾くフォーク系の音楽にとって、運指としてきわめて滑らかで合理的なリズムの刻みかたであるといえます。それだからこそ、親→人→中→薬→中→人による分散和音を採用した演奏のもと、いくつもの楽曲が実現されたものと推察できます。
その最たる事例に、さだまさしが結成していたグレープの〈精霊流し〉(1974)があります。アコースティック・ギターによる1拍3連の分散和音が2小節にわたって独奏され、その最後の拍からようやくヴァイオリンの旋律が開始されるその前奏を一聴すれば、この奏法がいかに件の楽曲の根本を支える肝要であるかがわかります。
彼が詞曲を提供したクラフトの〈僕にまかせてください〉(1975)もそうした楽曲のひとつです。
中島みゆきの代表作である〈時代〉(1975)もまた、彼女が使用する楽器とその奏法が実現を促した楽曲にちがいありません。松山千春の〈かざぐるま〉(1977)におけるアコースティック・ギターの運指もやはり、これを変奏するものです。
ビリー・バンバンによる〈白いブランコ〉(1969)の編曲は、〈君といつまでも〉を実現した森岡賢一郎が担当し、この奏法に“カレッジ・フォーク”式の意匠を施しています。
筒美京平が作曲したブレッド&バターの〈白いハイウェイ〉(1969)では、1拍3連のリズムに被さる前奏のストリングスがパーシー・フェイス楽団による〈The Theme from “A Summer Place”〉(1959)を思わせる筒美自身の編曲のもと、この奏法も旋律を単調なフォークとして彩ることを拒みます。時代の潮流への安易な迎合に抗う洒脱さは、以降のブレッド&バターの行方を占う羅針盤となったはずです。
あみんの〈待つわ〉(1982)を編曲した萩田光雄は、1拍3連の符割りを前奏に印象的に落とし込んでいます。尾崎豊による〈卒業〉(1985)なども、フォークの周辺でこのリズムを採用した事例といえるかもしれません。
“ムード歌謡”周辺
中島みゆきにおいても、たとえば〈りばいばる〉(1979)となるといくぶん事情は異なってきます。〈りばいばる〉における戸塚修の編曲は、楽曲の全体をとおしてみれば、基本的にはハイハットとアコースティック・ギターの分散和音とで1拍3連の符割りを維持していきます。けれど前奏でこの楽曲の性質を印象づけるもの、それは、“ムード歌謡”的な世界観を模したブラスとエレクトリック・ギターの音色およびその旋律でしょう。
柔らかく歪んだエレクトリック・ギターの最後の長音に機をあわせ、それが徐々に減衰していくなか音量をあげられたアコースティック・ギターは、他の楽器による出音を待つことなく、ここからAパートにおける8小節のあいだ、1拍3連の律動に和音を分散した単音をもって中島みゆきの歌唱に同伴します。
こうした編曲の次第とともに、彼女の歌唱とその歌詞の意味内容とが、いよいよこの楽曲に“ムード歌謡”の機微をまとわせます。前奏ばかりでなく楽曲の随所で聴かれるブラスとエレクトリック・ギターの用途をたどれば、それらはあえてこの楽曲を“ムード歌謡”調に仕立てようとしているかのように、いかにも的確に機能しています。
明瞭に1拍3連のリズムが刻まれる“ムード歌謡”調の早期の楽曲として、たとえば水原弘による〈黒い花びら〉(1959)があります。第1回の日本レコード大賞を受賞したこの音盤では、フランク・永井の名義のもと吹き込まれた〈有楽町で逢いましょう〉(1957)における吉田正の曲調を前提に、中村八大なりの“ロッカ・バラード”が展開されます。ピアノの和音を打鍵する1拍3連の律動は、間奏で独奏されるサキソフォンを含めたブラスの扱いとともに、歌謡曲がロックン・ロールを消化するひとつの様式として、その行方に先鞭をつけました(*8)。
城卓也が歌唱した〈骨まで愛して〉(1966)あたりでは、歌唱の主体における性別と歌詞の主語における性別とが交差し、前奏から咽び泣くサキソフォンとともにいよいよ“ムード歌謡”の調子は高まります。しかしここでは1拍3連のリズムはほとんどハイハットのみが担当し、ミュートされたエレクトリック・ギターの音がごく部分的にそこに嵌め込まれます。
とはいえ、この楽曲については、そうした“ムード歌謡”の調子と並存しつつ、編曲に重用されるエレクトリック・ギターの奏法や音響処理にザ・ベンチャーズ風の味つけが施され、ときに城の歌唱にまで深いリヴァーヴが効いていることに留意すべきでしょう(*9)。
布施明の猛々しい絶唱が響くことで“ムード歌謡”の調子といくぶん距離を置くものの、それでもなお「霧」や「湖」、「水」や「涙」といった水溶性をたたえることは忘れない〈霧の摩周湖〉(1966)は、作曲家に転身した平尾昌晃の出世作となりました。1拍3連のリズムを維持するエレクトリック・ギターによる細かい和音のカッティングを埋没させないための配慮なのか、それとも“ムード歌謡”から漂う湿気に錆びてしまったのか、ここではブラスの音にあまり艶が認められません。
前奏ばかりか間奏や後奏、オブリガートにまでサキソフォンが咽び泣く〈夜霧よ今夜も有難う〉(1967)での浜口庫之助は、いくぶんかの時代の錯誤を承知のうえで、“ロッカ・バラード”よりはむしろ吉田正への共感に石原裕次郎の歌唱を預けています。
その旋律を参照しつつ、サキソフォンとコーラスの応酬からはじまる内山田洋とクール・ファイブの〈長崎は今日も雨だった〉(1969)は、あらゆる観点から“ムード歌謡”の度合いのきわめて強い楽曲ですが、1拍を3連符に分割しているのはライド・シンバルと和音を打鍵するピアノです。
〈バス・ストップ〉(1972)が“ムード歌謡”の傑作であることは論をまちません。ただし平浩二の個人名義による音盤のためわずかにその濃度は薄まります。加えて、基本的にはハイハットが1拍3連の律動を負担するここでは、編成された諸楽器における演奏と休止、出音と消音の時機を厳密に管理することで2拍目と4拍目とが強調され、単なる模倣ではない和製“ロッカ・バラード”の成熟を印象づけます。
たとえば川口真のもとフォークに感化されてこれが新沼謙治の〈嫁に来ないか〉(1976)となり、また三木たかしの手で演歌に浸ったそれが石川さゆりの〈津軽海峡冬景色〉(1977)となるのも、歌謡曲のそうした蓄積と寛容によるところにちがいないのです。
*1 油井正一/編,『モダン・ジャズ入門』, 荒地出版, 1970, pp.11-12.
*2 矢向正人,「ポピュラー音楽のリズムの研究―その方法論をめぐって」,『ポピュラー音楽へのまなざし―売る・読む・楽しむ』所収, 東谷護/編, 勁草書房, 2003, p.172.
*3 嶋田由美+奥村正子+一色伸夫,「子どもの歌のリズム変容を考える」, 『子ども学』第17号所収, 甲南女子大学国際子ども教育センター, 2015, pp.57-81.
*4 矢向,前掲書, pp.174-178.
*5 竹内まりや, 「クリス松村と紐解く「Mariya’s Songbook」」
(https://natalie.mu/music/pp/takeuchimariya02), 『音楽ナタリー』11/28配信, ナターシャ, 2013.
*6 堀家敬嗣,「松田聖子試論―歌謡曲の色彩―(1983年8月)」, 『成城文藝』第240号 (成城学園創立100周年記念号), 成城大学文芸学部, 2017, pp.306-286(pp.187-207).
*7 桑田佳祐,「セルフライナーノーツ」, 『葡萄白書』所収, タイシタレーベル, 2015, p.29.
*8 高護,『歌謡曲―時代を彩った歌たち』, 岩波書店(岩波新書), 2011, pp.23-24.
*9 同書, pp.86-90.
堀家教授による「私の3連符」10選
1.〈黒い花びら〉水原弘(1959)
作詞/永六輔,作曲・編曲/中村八大
吉田正とフランク永井の協働によって確立された“ムード歌謡”は、ジャズのリズムに基礎づけられていた。ジャズを奏でるピアニストとしてもっとも評価されたひとりである中村八大は、しかしジャズの人気の衰退とともに歌謡曲の作曲家へと転身し、その最初の楽曲のひとつである〈黒い花びら〉にロカビリーの要素を組み込んだ。ピアノの和音を打鍵する1拍3連の律動などがその象徴である。日本歌謡史上における金字塔となる〈上を向いて歩こう〉をまもなく坂本九に提供する永六輔と中村八大の、最初の共作でもある。第1回日本レコード大賞を受賞するにあたり、服部良一と古賀政男がこれを支持したとされる。
2.〈長崎は今日も雨だった〉内山田洋とクール・ファイブ(1969)
作詞/永田貴子,作曲/彩木雅夫,編曲/森岡賢一郎
彼らのデビュー曲となったこのシングル盤のジャケットでは、「ムード・コーラス艶歌」の文言が踊るとともに、「内山田洋とクール・ファイブ」の名義に加えてあえて「唄・前川清」の補足が印字されている。写真には、白い支持体に腰をおろした短髪の男を囲うように立ち並ぶ5人の男たち。まぎれもなく「内山田洋」と「クールファイブ」の面々である。内山田を囲んだ右端に佇む男は、他のメンバーよりも露骨に手前に位置し、もともと大柄なのだろう身長をより背高に提示している。こうした配慮は彼が「前川清」であることを明示するものである。にもかかわらず、ひとり髪型をリーゼント気味の横分けにした彼だけが身体の前で左手を右手で押さえるように組み、どこかぎこちなく所在なさげなそのさまは、「ムード・コーラス艶歌」の文言とここに収録された楽曲のあいだの、さらにはこの文言そのもののうちの齟齬を示唆する。しかしそうした齟齬もまた、歌謡曲の魅惑であるにちがいない。なお、〈そして、神戸〉のジャケット写真では、内山田と前川の立場は完全に入れ替わり、前川が大きな籐椅子に脚を組んで座する一方で、笑顔だった内山田はここではメンバーの右端で仏頂面のまま腕を組む。ふたりの革靴の爪先がかろうじて同じ線に揃っていることだけがここでの内山田の矜持か。
3.〈白いハイウェイ〉ブレッド&バター(1969)
作詞/橋本淳,作曲・編曲/筒美京平
ブレッド&バターのデビュー盤〈傷だらけの軽井沢〉のB面に収録。リズムを基軸に、ほとんどの楽器の出音が互いの演奏のすきまを埋めるオブリガートの応酬として奏でられていた〈ブルー・ライト・ヨコハマ〉からわずか1年も経たないうちに、ここで筒美京平は、とりわけイントロのストリングスがパーシー・フェイス楽団による〈The Theme from “A Summer Place”〉を思わせる編曲の有機的な組成を、いまなおなんら古さを感じさせない水準で達成する。マックス・スタイナーが作曲したその楽曲を筒美が参照していたとすれば、それは、これが映画作品『避暑地の出来事』のテーマ音楽としてこのシングル盤のコンセプトと合致したからか。のちに多くの女性アイドルに提供されることになる系列のメロディが岩沢幸矢の中性的な声質を活かす、筒美京平の最初期の傑作。
4.〈バス・ストップ〉平浩二(1972)
作詞/千家和也,作曲・編曲/葵まさひこ
ザ・プラターズの〈Only You〉を歌謡曲が消化し吸収した成果として誇るべき名曲。それは歌いだしのメロディやコード進行の類似にも明らかだろう。ただし、〈Only You〉ではⅠ−Ⅰ−Ⅲ7−Ⅲ7−Ⅵm−Ⅵm−Ⅰ7−Ⅰ7であるのに対して、〈バス・ストップ〉ではこの行程を半分の4小節に圧縮し、Ⅰ−Ⅲ7−Ⅵm−Ⅲmとなる。〈バス・ストップ〉の歌謡曲性は、〈Only You〉の7・8小節目に相当する4小節目のⅢmに表現されている。〈Only You〉のメロディは7小節目の冒頭でⅠ7の響きのもとⅦ♭音まで下降するが、これはミクソリディアン・スケールにそったものであるのに対して、〈バス・ストップ〉のメロディは4小節目の冒頭でイオニアン・スケールのままⅦ音に下降する。ルート音から1音下か半音下かの相違が、ここで歌謡曲としての性質を担保するのである。平浩二は、基地の街である佐世保の小・中学校で前川清と同級生であり、彼らがアメリカのポップスに早くから親しめる環境にあったことは想像に難くない。
5.〈機関車〉小坂忠(1975)
作詞・作曲/小坂忠,編曲/細野晴臣
のどかなカントリー調の編曲が施された《ありがとう》でのヴァージョンは、細野晴臣の全面的な関与のもとドラムスを松本隆が叩いている。元ザ・スパイダースの大野克夫もスティール・ギターで参加。一転してR&Bに傾斜したこの《HORO》のヴァージョンでは、やはり細野晴臣を中心としたティン・パン・アレーが演奏で支え、特にコーラスの吉田美奈子の存在感は圧倒的である。この楽曲については、鈴木晶子の名義で《HORO》に参加していた矢野顕子や、浜田真理子などによるカヴァーがあるが、どういった経緯によるものか田端義夫がシングル盤に吹き込んでいる。こちらもテイストはカントリー調。
6.〈空に星があるように〉荒木一郎(1976)
作詞・作曲/荒木一郎,編曲/神保正明
“グループ・サウンズ”と“カレッジ・フォーク”の融合による“カレッジ・ポップス”の登場を予告するものではあれ、海老原啓一郎の編曲のもとシングル盤で最初に発表された〈空に星があるように〉のかたちのままでいたなら、この楽曲は単なる佳作の域で充足してしまったことだろう。換言すれば、それは着脱の可能なさしあたっての意匠だったのであり、この詞曲と不可分なまでに溶解し、有機的に結合したものではなかったわけである。したがって、この楽曲の潜在性を確実に汲みあげてみせた再収録盤における神保正明の編曲の次第こそが、上質な音楽性といった位相を超え、音の肌理としてその都度の手触りを私たちの鼓膜とともに粒立てる当のものであり、その貢献のもと〈空に星があるように〉は歌謡曲で屈指の名曲となる。
7.〈りばいばる〉中島みゆき(1979)
作詞・作曲/中島みゆき,編曲/戸塚修
地方の場末のスピーカーから割れた音で流れてくるような“ムード歌謡”の哀愁を装うこの楽曲は、しかしたとえば《生きていてもいいですか》に収録され、後藤次利の編曲によってシャンソンの体裁を繕う〈エレーン〉と同じ精神で歌われる。角田ヒロのドラムスと後藤のベースに加えて鈴木茂がエレキギターを、石川鷹彦が生ギターを弾く〈エレーン〉の完成度は、〈りばいばる〉を経ることなく獲得されることはなかったのではないか。〈ファイト!〉や〈糸〉のように希望を騙る中島みゆきと、〈りばいばる〉や〈エレーン〉のように絶望を語る中島みゆきとでは、やはり表現者としての凄みが段違いであるように思う。
8.〈不思議なピーチパイ〉竹内まりや(1980)
作詞/安井かずみ,作曲/加藤和彦,編曲/清水信之
ゆったりした1拍3連の静かな導入部における第2小節の4拍目に突如として1拍6連の符割りで叩かれたはずのスネアのフィル・インは、これをきっかけにベースとドラムスが刻みはじめるリズムによって、翻って1拍3連の律動へと変換される。これが本編の真正のリズムとなるとき、静かな導入部についてもまた、1拍3連による2小節の記譜から2拍3連による4小節の記譜へと書き換えざるをえない。だからといって、このリズムを継続的に刻む楽器はここにはなく、さまざまな出音が絡むグルーヴ感のなかでそれは編まれていく。そしてこの2拍3連は、終盤での移調の際に再び導入されることになる。渡辺真知子の〈唇よ、熱く君を語れ〉とともに、なんら濁りのないポップさで歌謡曲が人生を肯定的に謳歌する姿勢は、CMソングがもっとも輝いたこの時期に特有のものであるかもしれず、実際、そうした時代はこれ以降まだ訪れていない。加藤和彦は竹内まりやのデビュー曲も作曲しているが、これは提供を希望する作曲者として彼女自身が指定したリストにもとづくものであり、そこには他に細野晴臣、山下達郎、杉真理、センチメンタル・シティ・ロマンスの名があったという。なお、翌年に発表された伊藤つかさの〈夕暮れ物語〉は、作詞、作曲、編曲のいずれにもこの楽曲と同じ人物を起用している。このことは、竹内の楽曲でプロデュースを担当した牧村憲一と、伊藤の所属したジャパン・レコードの創立者である三浦光紀との連携を邪推させる。
9.〈星屑のステージ〉チェッカーズ(1984)
作詞/売野雅勇,作曲・編曲/芹澤廣明
中森明菜の〈少女A〉を成功させた作詞家と作曲家のコンビは、その後、チェッカーズの制作チームとして彼らを支えることになる。とりわけチェッカーズのプロジェクトについては、芹澤による古きよきアメリカの大衆音楽への郷愁が、同時代のイギリスの大衆音楽を経由して歌謡曲として再構築され、深いリヴァーブのなかミュート気味のエレクトリック・ギターの硬い低音弦とサキソフォンが新鮮な懐かしさを奏でる。特にその低音弦の歯切れのよさは、粘りつくような藤井郁弥の歌唱にリズムが埋没することを回避させる効果が顕著である。サビの最高音あたりの節回しは布施明の〈霧の摩周湖〉と紙一重。
10.〈抱いてくれたらいいのに〉工藤静香(1988)
作詞/松井五郎,作曲・編曲/後藤次利
平浩二の〈バス・ストップ〉で一定の達成をみた“ロッカ・バラード”と“ムード歌謡”との調合は、ゴスペル的なコーラス・ワークとリズムのタメの導入をもって、この楽曲でR&Bにより接近したかたちで更新される。ただし、もはやここでは歌唱の主体と歌詞の主体における性別の交差といった問題系は捨象されている。このリズムのもと、打ち込みによる機械的な管理がテンポを倍化させることによって、のちに安室奈美恵が同じ系譜に位置づけられることになる。いずれにしても、ここでこの楽曲を歌謡曲の側に係留するもの、おそらくそれは、工藤静香のこれみよがしの歌唱であろう。1拍3連の“ロッカ・バラード”を作曲の後藤次利に提案したのは、当時の工藤のプロデューサーで堀ちえみや岡田有希子も担当した渡辺有三であり、この楽曲の成功が自身の作曲家としての突破口になったとも後藤は述懐している。
番外_1.〈スローなブギにしてくれ(I want you)〉南佳孝(1981) 作詞/松本隆,作曲/南佳孝,編曲/後藤次利
片岡義男の小説を原作に、浅野温子が主演し、藤田敏八が監督した映画作品『スローなブギにしてくれ』の主題歌として制作された。文字どおりスローなブギ、すなわち遅いシャッフルのリズムを基本とするこの楽曲は、いまや日本における1拍3連の“ロッカ・バラード”のスタンダードであり、番外とした。
番外_2.〈栞のテーマ〉サザンオールスターズ(1981)
作詞・作曲/桑田佳祐,編曲/サザンオールスターズ
桑田佳祐の企画と音楽監督による映画作品『モーニングムーンは粗雑に』の挿入歌。いまや日本における1拍3連の“ロッカ・バラード”のスタンダードであり、番外とした。
番外_3.〈SWEET MEMORIES〉松田聖子(1983)
作詞/松本隆,作曲・編曲/大村雅朗
サントリーの生ビール「CAN」のCMソング。シングル盤〈ガラスの林檎〉のB面に収録されたが、のちに両A面扱いへと刷新される。いまや日本における1拍3連の“ロッカ・バラード”のスタンダードであり、番外とした。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店