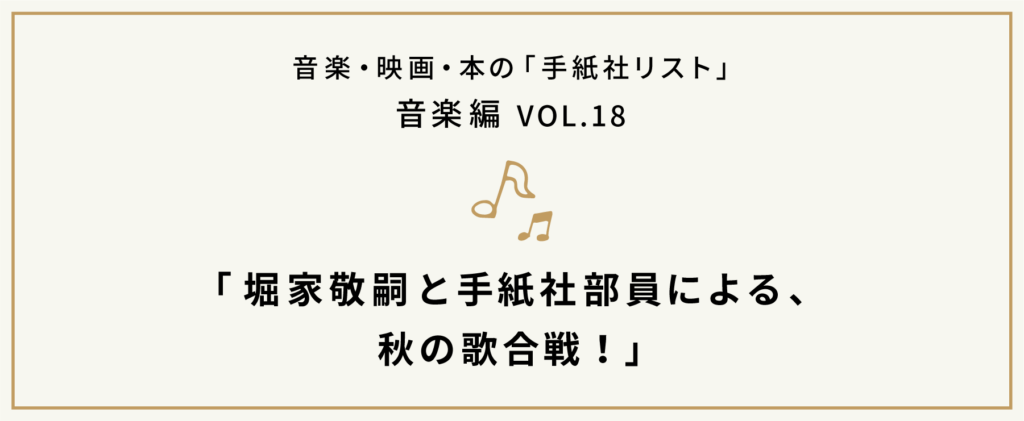
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。18回目となる音楽編は特別バージョン。「秋の歌合戦!」と題して、山口大学教授の堀家敬嗣さんが選ぶ10曲と、手紙社の部員が選ぶ10曲を紹介します。ということで、今回はいつもと趣向を変えて、最初に部員さんが選ぶ10曲を紹介しましす。その後、いつものように堀家教授のテキスト、堀家教授が選ぶ10曲と続きます。あなたが好きなリストは、どっち?
手紙舎部員の「秋」10選リスト
1.〈誰もいない海〉トワ・エ・モア(1970)
作詞/山口洋子,作曲/内藤法美,編曲/森岡賢一郎
私には、トワ・エ・モアのフォークソングとしてのイメージが強く、「今はもう秋…」とささやくように始まり静かな海の情景が浮かぶ美しい曲、でも歌詞はとても悲しい曲だと、子供なりに感じていました。タイトルと、秋、海というワードで歌の世界に引き込まれます。そして越路吹雪が抒情豊かに歌うと、見事にシャンソンに! 作曲者は越路吹雪のご主人でした。
(選者・コメント:はたの<館長>)
2.〈雨の街を〉荒井由実(1973)
作詞・作曲/荒井由実,編曲/松任谷正隆
秋の訪れとともに聴きたくなる大好きな一曲です。この曲が秋の曲だなと思うのは「庭に咲いてるコスモス」「夜明けの雨はミルク色」「夜明けの空は葡萄色」という歌詞。ミルク色、葡萄色だなんて、ユーミンはやっぱり天才だなぁと思います。雨の日は空を見て思わず口ずさんでしまいます。そして、特に好きなのは「〜たら、どこまでも遠いところに歩いていけそう……」という一節。閉塞感、無力感を感じていた10代の頃、自分の中にもきっと小さな可能性が眠っていて、いつかきっと遠いところまで歩いていけるような気がする。この曲を聴きながら、そんな風に感じていたことを、思い出します。これからも大切に聴いていきたい一曲です。
(選者・コメント:hidemi)
3.〈秋の気配〉オフコース(1977)
作詞・作曲/小田和正,編曲/オフコース
秋の風を感じるとこの曲が。意味深な詩ですが大好きです。
(選者・コメント:とも)
4.〈秋桜〉山口百恵(1977)
作詞・作曲/さだまさし,編曲/萩田光雄
この曲に特に思い入れはありません(笑)。それでも秋になるとどうしても聴きたくなる、秋の空気のような曲。「秋桜」をコスモスと読むのも、この曲からの当て字と聞いたことがあります。そこも含めて秋=この曲という「日本人の共通認識」かと。また縁側、秋の結婚、(紙の)アルバム等、すでに失われつつある、昭和の情景が、秋という少し切ない季節感と重なり、「秋桜」という「季語」が一層心に染みるのだと思います。
(選者・コメント:手芸部 長谷部)
5.〈すみれ September Love〉一風堂(1982)
作詞/竜真知子,作曲・編曲/土屋昌巳
この曲を色々なビジュアル系バンドがコピーしているようですが、元の一風堂のバージョンは、ぐっと大人なイメージです。ちょっと涼しくなってきたかな、いや、まだ暑いかな、9月の夜のちょっとロマンチックな都会の大人の感じなんですね。
(選者・コメント:ぬりえ)
6.〈夏のクラクション〉稲垣潤一(1983)
作詞/売野雅勇,作曲/筒美京平,編曲/井上鑑
周りから変な奴扱いされていて屈折していた高校時代を過ごしていた私にとって、この時代は放送部に所属してお昼の番組用にネタ探しをしたり、ラジオを聴くことが多かったりと黒歴史の中の唯一の救いだったので、80年代〜90年代の邦楽は今でも好きでよく聴きます。稲垣潤一さんは〈1ダースの言い訳〉がCDラジカセのCMソングに起用されたのを聴いて突如ハマり出し、アルバムが発売されれば買いに行ったり、昔のアルバムはレンタルしていました。コンサートに行くようになったのは社会人になってからです。〈夏のクラクション〉は自分の夢をつかまえるため、夏の終わりに別れた女性を時を経ても思い、悪いのは僕だよ優しすぎる人に甘えていたと歌っています。別れた女性を思い、自分に非があるという歌詞が多いのは稲垣さんの失恋ソングの特徴と言えるでしょう。そういえば大瀧詠一さんが〈Bachelor Girl〉をレコーディングしたものの違和感があり、代わりに歌ってくれる人を探して稲垣さんが抜擢されたのは歌詞の内容が合うと判断されたのですかね? 今となっては謎でしかないですが。
(選者・コメント:れでぃけっと)
7.〈木枯らしに抱かれて〉小泉今日子(1986)
作詞・作曲/高見沢俊彦,編曲/井上鑑
木枯らしなので、秋もずいぶん深まった頃でしょうね。歌詞に「寒い冬がやってくる」とあるので、まだ冬になっていないと思うんですが、バグパイプやチェンバロのような楽器の音は、確かに寒いイギリスやスコットランドのイメージですね。
(選者・コメント:ぬりえ)
8.〈楓〉スピッツ(1998)
作詞・作曲/草野正宗,編曲/スピッツ・棚谷祐一
19歳だった僕は西武新宿線沿いにある武蔵関の社員寮にいました。右も左もわからない東京での生活は得体の知れない不安の日々。お腹がすいたのでコンビニへ行こうとするも近所の道すらうろ覚え。秋の冷たい夜風が何もかも頼りない自分を貫くのでした。ようやく辿りついたコンビニに入ると、流れているのはスピッツの〈楓〉。「僕のままでどこまで届くだろう」という歌詞が妙に沁みたあの日を思い出します。あの頃僕は若かった。
(選者・コメント:なっち)
9.〈茜さす 帰路照らされど…〉椎名林檎(1999)
作詞・作曲/椎名林檎,編曲/亀田誠治
秋に感じるのは、淋しさや不安。終わりの暗示。それを振り払うようにヘッドフォンを耳に宛てる茜色の雑踏。「アイルランドの少女」「ファズの効いたベース」というリアルな記号が切なさをより鮮明にします。季節、情景、音楽。その立体的な関係性の真ん中にただどうしようもなく立っている自分という存在。いつ聴いても秋が沁みるのです。そしてファーストアルバムを聴いた時の衝撃、思い出します!
(選者・コメント:田澤専務)
10.〈金木犀の夜〉きのこ帝国(2018)
作詞・作曲/佐藤千亜妃
秋の夜長の帰り道、聴き終わるとなんだかちょっと前向きな気分になれる大好きな1曲。イントロに始まり、曲中で繰り返される星が瞬くようなキラキラっとした音が印象的です。後ろでときどき聞こえてくるフォーンっと鳴る音が、通りかかった時にふわっと香る金木犀の香りを想像させますね。ヴォーカルの佐藤千亜妃さんの透明感のある歌声やノスタルジックな言葉選びにもぜひ耳を傾けてみてください♪
(選者・コメント:ひーちゃん)
秋の歌謡曲について私が知っている二、三の事柄
季節は変わる
思いつくまま秋をめぐる歌謡曲を繰ってみると、いくつかのことに気づきます。たとえば他の季節と比較してみると、秋を謳った楽曲はさほど多くないことに思い至ります。
もちろん、夏から秋へと、もしくは秋から冬へと推移するいわゆる季節の変わり目に取材した楽曲はたくさんあります。とりわけ、騒がしかった渚が清涼な潮風とともににわかに人影のまばらとなるような晩夏から初秋にかけての一時期は、ことによると歌謡曲がもっとも頻繁に利用してきた期間であるかもしれません。
そうした歌謡曲については、加山雄三が歌唱した〈湘南ひき潮〉(1978)や大貫妙子が歌唱した〈海と少年〉(1978)のほか、石川秀美の〈ゆ・れ・て湘南〉(1982)や稲垣潤一の〈夏のクラクション〉(1983)、石野陽子の〈グッバイ・ブルーサーファー〉(1986)や井上陽水の〈少年時代〉(1990)、森山直太朗の〈夏の終わり〉(2003)など、枚挙に暇がないでしょう。
とはいうものの、日本の歌謡曲において季節感そのものが重視されはじめたのは、実際にはそれほど昔のことではないようです。これについて、大瀧詠一は、若者のあいだで夏が特別な意味を持ち、このため夏向きの歌が必要となってきたころに、その需要を叶えるかたちでちょうどザ・ワイルド・ワンズの〈想い出の渚〉(1966)が登場したことを指摘しています(*1)。それまでの歌謡曲は、特定の季節に偏ることなく年中をとおして通用するような、普遍的というよりはむしろ明確な時節柄を設定しない一般的な汎用性を前提としていたわけです。
しかも、どちらかというと歌謡曲には夜を謳うものが多く、これが太陽の光のもとに引っぱりだされてきたのも、おそらくは大瀧が指摘する事情と無関係ではないはずです。
いずれにせよ、夏から秋へと推移する、いわゆる季節の変わり目に取材した楽曲がたくさんあるなか、なぜ盛秋を謳う歌謡曲が希少であるかといえば、おそらくそれは、楽曲の世界を設定する時間的な舞台としてこれが魅力的でないから、あるいは聴き手に訴えるところが些少であるからだと考えられます。要するに、夏から秋へと、もしくは秋から冬へと推移する季節の変わり目にあっては、空間の移動を介さないまま、日々の生活においてさえ劇的な世界の変化が感じられ、聴き手の情緒を揺さぶる一方で、季節の最中にはこの変化が鈍化して感覚することが難しくなるのです。
加えて、収穫の秋には、こと聴覚的な刺激に限らず、視覚や触覚、味覚や嗅覚といった他の知覚に訴え、それゆえ私たちの身体と精神を昂らせるさまざまな魅惑的な事象が、大衆文化としての歌謡曲の存在意義を相対的に低下させてしまうにちがいありません。つまり秋は多様な仕方で私たちのもとを訪れ、しかもこれがいかにも豊潤な実りとなって誘惑してくるため、これに煽られ、感覚を総動員して忙しなく気を散らせがちな私たちは、ひとりの聴き手としてその音に集中できないのです。
アイドルは商う
それでもなお、秋を謳わずにはいられなかった歌謡曲の歌い手たちが一定程度います。おおむねそれは、商品としての楽曲の流通に関わる商業上の戦略にもとづくものです。
1970年代半ばから1980年代半ばにかけて、アイドル歌手は、年間に4枚、したがって3ヶ月に1枚の頻度でシングル曲を発表することを旨としてきました。彼ら彼女らの新曲がレコード盤で発売されるやいなや、これを待ち侘びたその熱狂的な支持者は競ってそれを購入し、結果的に発売日からの数日がもっとも高い売り上げ枚数を記録しますが、以降、その消費は急速に減衰していきます。
それに応じて、テレビやラジオなどの媒体にその楽曲やこれを歌唱する彼ら彼女らの存在性が露出する機会もたちまち減少してしまい、いずれこれが聴かれなくなるころに、あらためて次の新曲が発表されることになります。いってみれば、彼ら彼女らのアイドルとしての存在性に賞味期限がある以上、そのシングル曲にも当然ながら賞味期限があるはずで、こうした供給と消費のプロセスを年間で4回循環させることが、アイドルビジネスにとってもっとも効率化された適正なモデルということなのでしょう。いわばそれは、アイドル歌手に課されたノルマでありタスクなわけです。
年間で4回にわたり繰り返されるこのプロセスが、年間で4回にわたり切り替わっていく季節のありようときわめて親和性が高いことは、もはや想像にかたくありません。そのうえ、アイドル歌手については、歳末に設定されたいわゆる賞レースへの参画をあらかじめ見込んでそのプロモーション方針が戦略化されることから、春先にデビューさせたうえで初夏に次のシングル盤を発売し、さらに秋口に発表される楽曲が新人賞獲得のための最後の機会となるのです。
たとえば、デビューした年に3枚目のシングル盤として〈風は秋色〉(1980)を発表した松田聖子は、つづく2年目の秋には大瀧詠一の作曲による〈風立ちぬ〉(1981)を、その翌年には財津和夫を作曲に戻して〈野ばらのエチュード〉(1982)を発表していますが、これらはいずれも10月のことです。
ただし、ここまでにすでに歌謡界の中心に自身を位置づけることに成功した彼女は、もはや単なるアイドル歌手ではありませんでした。〈裸足の季節〉(1980)でデビューした4月を起点に、その後はきわめて律儀に、7月/10月/1月/4月の発表スケジュールを循環させてきた松田聖子の新曲は、〈野ばらのエチュード〉を受けて本来は1月のところ2月の発売にずれ込んだ〈秘密の花園〉(1983)以降、この定期性を放棄し、真夏のための〈天国のキッス〉(1983)として4月に、初秋のための〈ガラスの林檎〉(1983)として8月に発売されることになります。
律儀に維持されていた方針の変更が凶とでたのか、いくぶんか季節を先喰いしすぎた〈ガラスの林檎〉の不調は、けれどそれを補うように、当初はそのB面曲だった〈SWEET MEMORIES〉の評判がこのレコード盤を両A面として再定義することで息をつぎ、どうにか〈瞳はダイアモンド〉(1983)は10月にまにあいました。
女性は愁う
しかしながら、男性アイドルに秋の風は似合いません。というのも、この季節の憂い、あるいはむしろ愁いは、男性アイドルに期待される存在性にはけっしてそぐわないものだからです。
なるほど、郷ひろみの〈よろしく哀愁〉(1974)や田原俊彦の〈哀愁でいと〉(1980)、もしくは単にアイドルのみならず桑名正博の〈哀愁トゥナイト〉(1977)や T.C.R.横浜銀蝿R.S.の〈哀愁のワインディング・ロード〉(1983)など、哀愁を謳ってみせた男声による楽曲は相応に聴かれています。
けれどこれらのいずれにも、特定の季節をうかがわせる記号はその歌詞のうちに嵌め込まれていません。かろうじて松本隆が桑名に「身体はなせば 心寒々冷えるだけ」と歌わせたのみですが、この寒冷ささえ季節のものと限られたところではありません。そればかりか、T.C.R.横浜銀蝿R.S.などは「哀愁」に「わかれ」とルビを振り、そのルビにしたがって発音しているため、そこでの愁いはいかにも文語的で形式的な、それゆえ実感のともなわない空疎な記号にすぎません。
ところが女性の歌唱による歌謡曲の場合、この空疎さを満たすように女声が浸透していきます。なにが愁いとも、なにを愁うともつかないまま、彼女たちの歌声はもっぱら愁いそれ自身に耽溺します。
岩崎宏美による〈思秋期〉(1977)は、この季節を「心ゆれる秋」であり「あれこれ 思う秋」と認識するものです。
なによりもまず、「過ぎてから気がつく」ような「忘れもの」として「青春」を捕捉する阿久悠の歌詞は、いわばそれを現在進行形ではなく過去完了形でのみ実現可能な、したがってあらかじめ失われたものとして措定しています。「青春」とは、すなわち「行き過ぎ」てしまった「季節」だの、「通り過ぎ」た「誰も彼も」だのであって、もはやないこれらは、ここではもはやないことそれ自体をもって「青春」たりえます。そしてもはやないがゆえに、けっして感覚的ではなく、情緒的にして感傷的な思慕の対象としてそれらを実現する当のもの、それが、「涙もろい私」にとっての「秋」なのです。
いまや彼女の「秋」は、知覚の季節でも、行動の季節でもありません。ここではそれは、記憶のなかにあれこれ想い出として所在するイメージを思慕すること、内省すること、さらにはそこに「青春」のかたちを象ること、そのためにこそ訪れる季節です。「秋」とはそういう季節なのです。こうして阿久悠が女声に投影する女性性としての、ある種の女々しい情緒や感傷は、たとえば彼が歌謡曲に付託して男々しさを装う男性性にそぐわないことは自明です。
この限りにおいて、歌謡曲にとっての秋とは、女性アイドルの存在性がもっとも反映されやすい季節にちがいありません。堀ちえみの〈夕暮れ気分〉(1983)に謳われる気分とは、おそらくそうしたもののことでしょう。
なるほど、諸星冬子によるこの歌詞には、秋を直接的に参照する記号的な語句はなにひとつ使用されていません。それでもなお、ここには秋が存在しています。浅田美代子の〈赤い風船〉(1973)が、伊藤つかさの〈夕暮れ物語〉(1981)がそうだったように、これは歌い手の存在性をも包摂した楽曲の全体をもって、まぎれもない秋の表現となるのです。
*1 大瀧詠一,『大瀧詠一 Writing & Talking』, 白夜書房, 2015, p.361.
堀家教授による、私の「秋の歌」10選リスト
1.〈つるべ糸〉小坂忠(1975)
作詞・作曲/鈴木晶子,編曲/細野晴臣・矢野誠
エイプリル・フール時代の盟友だった細野晴臣をプロデューサーに迎えて制作された記念碑的なアルバム《HORO》に所収。「秋の日は」と歌い出されるこの楽曲は、疑いようもなく秋のものである。その秋に「指がかじかむ」ほどの「東風」の吹くことも、ここで詞曲を提供した鈴木晶子が幼少期を青森ですごしている事実をもって十分に納得のいくところだろう。この楽曲が発表された当時、細野晴臣とともに編曲に関わった矢野誠と彼女とはすでに結婚しており、のちに矢野顕子の名義でソロ歌手としてデビューすることになる。彼女自身も、〈やませ(東風)〉としてこの楽曲をカヴァー。
2.〈冬が来る前に〉紙ふうせん(1977)
作詞/後藤悦次郎,作曲/浦野直,編曲/梅垣達志
赤い鳥の解散によりhi-fi setの3人と別れて後藤悦次郎と平山泰代が夫妻で結成した紙ふうせんの、名曲といっていいその代表曲。フォーク調の旋律に歌謡曲調の編曲が施されているが、ドラムスとともにここに介入してくる歪んだエレキギターの低音のリフが、この楽曲自体が予定調和的な聴き心地に安住することを拒絶する。ことによると、この歪みがより鋭さを増したうえで、そのリフの側を基調に全篇を再編成してみれば、ハード・ロックとして十分に聴くに足る作品となるかもしれない。「秋の風が吹」くことによって、ここでの秋のありようは直接的に言及される。
3.〈9月には帰らない〉松任谷由実(1978)
作詞・作曲/松任谷由実,編曲/松任谷正隆
荒井由実が結婚して松任谷由実の名義のもと最初に発表したアルバム盤となった《紅雀》に収録。その意味で、ボッサ・ノーヴァやサンバなどラテン音楽の要素を積極的に摂取したきわめて挑戦的で充実したアルバムであるはずが、この野心的な気負いのもと歌謡曲的なキャッチーさに欠けたせいか、売り上げは不調に終わる。それゆえに、その反省を生かすかたちでこれ以降により顕著となっていく松任谷由実と松任谷正隆の、単なる音楽を超えた広告代理店的な仕掛けの声高な押しつけがましさは、ここでは徹底して希薄であり、そのぶん好ましく響く。実際、小品ながら佳曲が多いなかでも、とりわけこの楽曲は、〈白い朝まで〉とともに松任谷由実による秀作のひとつである。どうやらここでは、「夏のはかなさ」は「9月」のものであって、この地点までもう「帰らない」ことを決意したとき、すでに秋は訪れている。
4.〈海と少年〉大貫妙子(1978)
作詞・作曲/大貫妙子,編曲/坂本龍一
<pドラムスを高橋ユキヒロ、ベースを細野晴臣、キーボードを坂本龍一が担当し、結成されてまもないY.M.O.が顔を揃えたこの楽曲の収録には、さらにギターとして鈴木茂と松原正樹が参加するなどいかにも豪華な布陣で、制作側の相応の意気込みが認められる。“シティ・ポップス”の名盤となる《Grey Skies》および《SUNSHOWER》につづく《Mignonne》に収録。その最後を括る名曲〈あこがれ〉の「寒い部屋」に向かって、その前曲となるこの楽曲は季節を進めていく。こののち、大貫の音楽は、Sugar Babe時代の延長線上にあった新大陸式のものから旧大陸式のものへとにわかに変調する。「夏の日の終り」に「秋の気配かんじてる」この楽曲は、その数ヶ月前に加山雄三が発表した〈湘南ひき潮〉へのアンサー・ソングのごとく奏でられる。これにも矢野顕子によるカヴァー版が存在。
5.〈お元気ですか〉川田あつ子(1982)
作詞・作曲/鈴井みのり,編曲/戸塚修
〈秘密のオルゴール〉と〈おやすみなさい〉のシングル盤2枚のみを発表して歌手活動から引退し、したがってそれぞれのA面とB面の都合4曲のほか歌唱した楽曲の発表されていない川田あつ子による、2枚目のシングル盤のB面に収録。しばしばその音程の不安定さや音域の狭さ、声量のなさといった指標をもって、いわゆる歌唱の下手なアイドル歌手の典型として例示されもする彼女だが、そうした指標と、レコード盤に録音された楽曲の味わいとがほとんど無縁であることは、舌足らず気味の発音だが素直で抜けのいい声質に支えられたこれら4曲すべてがいまだ忘れがたい秀作であることをみても明らかだ。充実した’82年組のなかで十分には存在性を確立しえないまま、歌唱の不評を理由としてか、この楽曲を最後にアルバム盤を吹き込むこともなく引退した事実は、残された4曲を聴くにつけ、かえすがえすも惜しむべきことである。なお、川田はその後、北野武監督の『3-4x 10月』に主演した柳ユーレイと結婚している。「夏が過ぎ」て「秋になる」あたりの表現が秋の指標となろう。
6.〈Ya Ya あの時代を忘れない。〉サザンオールスターズ(1982)
作詞・作曲/桑田佳祐,編曲/サザンオールスターズ,弦管編曲/新田一郎
やはり青山学院大学の「つたのからまるチャペル」を舞台としてペギー葉山が歌唱した〈学生時代〉を踏まえながら、「恋を切なくす」る「秋」に「涙のチャペル」を懐かしむこの楽曲において、季節とはまさしく失われた時間そのものである。
7.〈ガラスの林檎〉松田聖子(1983)
作詞/松本隆,作曲/細野晴臣,編曲/細野晴臣・大村雅朗
作曲に細野晴臣を迎えたシングル曲〈天国のキッス〉で名実ともに最高潮に到達した松田聖子が、これに後続するシングル盤として同じく細野の作曲により発表した楽曲。芸能界の頂点に君臨する女性アイドル歌手が、そのキャリアの極北で発表する新曲としては、あまりにも地味な楽曲とも思われたが、換言すれば、そうした状況だからこそ、制作者の側にこれをシングル盤として吹き込む意欲が生じたのであろうことは容易に推察できる。はたして、市場は彼らの意気込みや楽曲それ自体の達成を裏切り、派手さにかけるとの懸念のとおり売り上げを伸ばすことができなかった。市場そのものは、依然としてこの林檎ほどは成熟していなかったわけである。かわりに、B面に収録された〈SWEET MEMORIES〉がCMソングに採用され好評を博したことから、両A面のかたちで抱き合わせて売り上げを確保している。とはいえ、この楽曲が松田聖子の歌唱したシングル盤史上、屈指の名曲であることに疑いはない。秋の記号として、ここでは「コスモスが揺れてる」。
8.〈リ・ボ・ン〉堀ちえみ(1985)
作詞/三浦徳子,作曲/松田良,編曲/萩田光雄
ストレイ・キャッツに代表されるネオ・ロカビリーのブームに便乗するかたちで、たとえばチェッカーズやSALLYといったバンドが登場し、懐古趣味の波は歌謡曲の歴史をなぞるように“エレキ歌謡”にも脚光を浴びせる。ジューシィ・フルーツの沖山優司が発表した〈東京キケン野郎〉を皮切りに、ザ・ナンバーワン・バンドの〈六本木のベンちゃん〉や高田みずえが歌唱した〈そんなヒロシに騙されて〉やT.C.S.横浜銀蝿R.S.による〈哀愁のワインディング・ロード〉が、そしてこの楽曲のあとには石野陽子が〈グッバイ・ブルーサーファー〉で、“エレキ歌謡”の体裁を採用している。〈リ・ボ・ン〉を含めキャニオンで堀ちえみの音楽を方向づけた渡辺有三は、加山雄三の演奏も務めた喜多嶋修のザ・ランチャーズでベースを担当しており、かつてこうしたジャンルを彩ったひとりでもある。「少し冷たい風」に「枯れ葉が舞い散る」さまは、これを秋の景色とみなして異存ないだろう。
9.〈もう逢えないかもしれない〉菊池桃子(1985)
作詞/康珍化,作曲・編曲/林哲司
林哲司による一連の菊池桃子のシングル曲群は、いずれもが互いを模倣しながら、そのわかりやすい構成とメロディのキャッチーさをもって、ある御しがたい魅力の塊となる。菊池の歌唱の特性は、浅田美代子や伊藤つかさの系列に連なりつつ、どれほどか川田あつ子にも似て声質そのものの肌理をもって存在性を聴き手の鼓膜に刻む。当初は秋元康が作詞を担当していたが、この楽曲からその言葉を逃れて新しい世界へと踏みだし、まずは康珍化が唯一その歌詞を綴ったここで、「秋は旅人」となって、「日差しがひとつ弱まるたびに」推移していく季節に「ふたりの心」のありさまが重ねられる。
10.〈イロトリドリノセカイ〉JUDY AND MARY(1998) 作詞・作曲/TAKUYA,編曲/JUDY AND MARY
「涙」に分光された「七色」が、したがってなにもかもが「初秋の風」に晒される。清澄な秋の空気のごとき、濁りない歌唱の透明感。このバンドのまごうかたなき最高傑作。
番外.〈湘南ひき潮〉加山雄三(1978)
作詞/松本隆,作曲/弾厚作,編曲/瀬尾一三
2,000曲を超える松本隆の作詞作品において、タイトルに“湘南”の語を謳う楽曲はわずかに3曲しかない。そのうちの1曲であるこの楽曲は、彼が加山の自邸や船に招かれてほとんど密着的に取材したときのメモをもとに詞作され、なかでも“湘南”の度合いがきわめて濃厚である。加山によれば、茅ヶ崎の秋の訪れはすでに8月、灼熱の浜辺の砂が裸足の足裏で不意に冷めていることに気づいてそれと理解される。とはいえ、温暖化のこんにちでは、もはや事情を異にするところかもしれず、ゆえに番外とした。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





