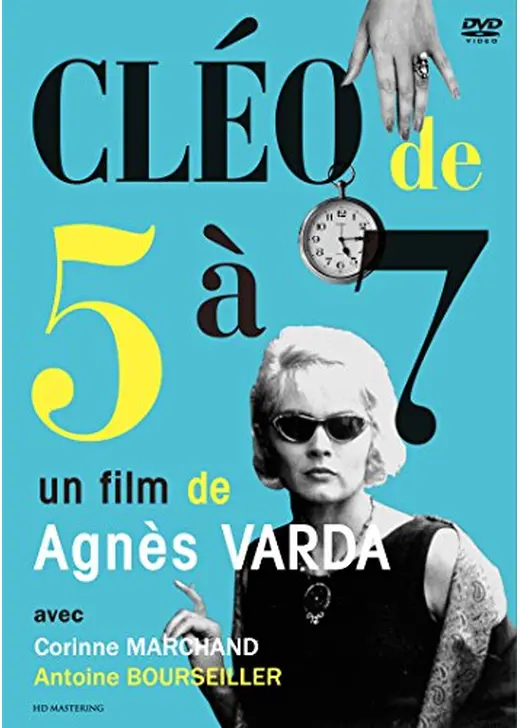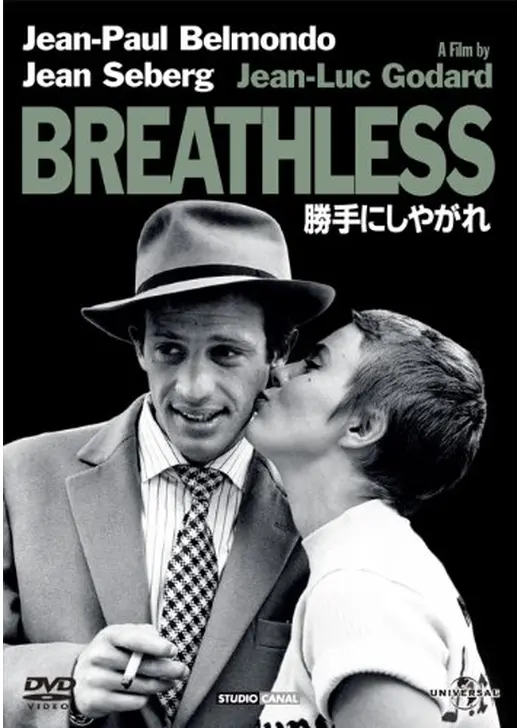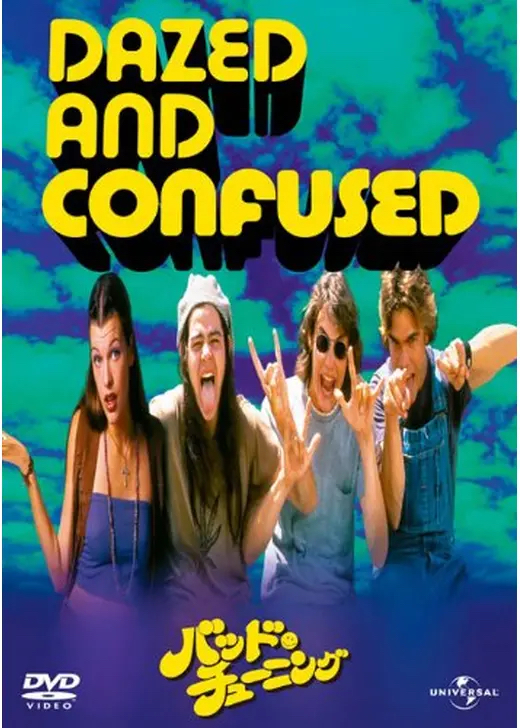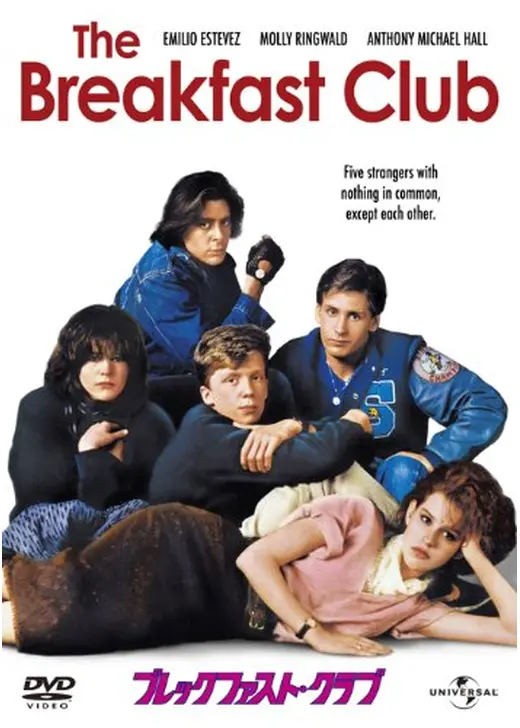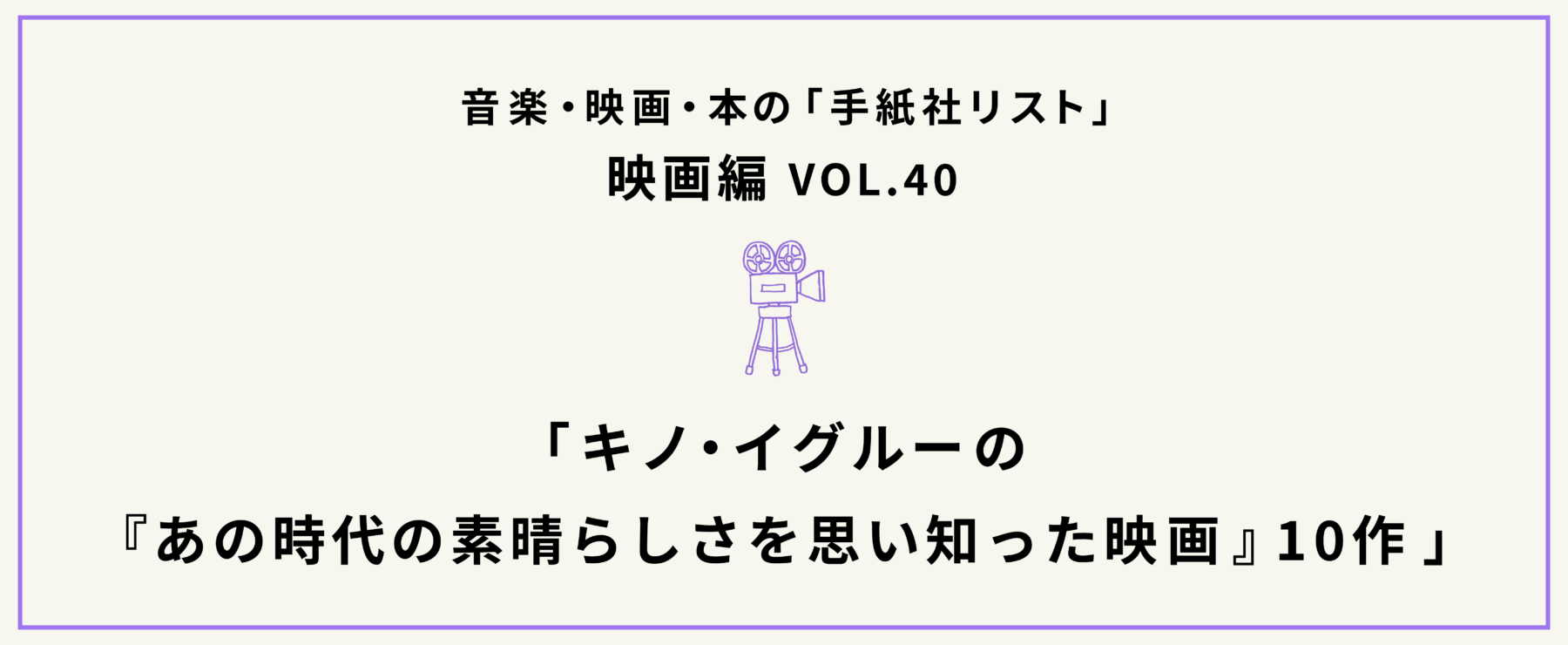
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。映画部門の今季1年間のテーマは、「○○の素晴らしさを思い知った映画」。今回は、「あの時代の素晴らしさを思い知った映画」です。その“観るべき10本”を選ぶのは、マニアじゃなくても「映画ってなんて素晴らしいんだ!」な世界に導いてくれるキノ・イグルーの有坂塁さん(以下・有坂)と渡辺順也さん(以下・渡辺)。今月も、お互い何を選んだか内緒にしたまま、5本ずつ交互に発表しました! 相手がどんな作品を選んでくるのかお互いに予想しつつ、相手の選んだ映画を受けて紹介する作品を変えたりと、ライブ感も見どころのひとつです。
──
お時間の許す方は、ぜひ、このYouTubeから今回の10選を発表したキノ・イグルーのライブ「ニューシネマ・ワンダーランド」をご視聴ください! このページは本編の内容から書き起こしています。
──
−−−なんと今回は、順也さんがスタート時間に間に合わないというハプニングもありましたが、どうなったのでしょうか? それでは、クラフトビールを片手に、大好きな映画について語り合う、幸せな1時間のスタートです。
──
有坂:みなさんこんばんは、なんと、まだ順也が到着していません。この会場に向かっているということなんですけど、まだ到着せず、間に合っていないので、早速僕一人で始めたいと思います。初めてのパターンですね。一回オンラインでつないでやったことはあるんですけど、まだ本人不在というのは初めてのパターンで、こういうライブ感いいですね。僕は大好きです! 来てくれるといいんですけど、来なかったらどうしよう(笑)。全然どうなるかわかりませんが、1時間弱お付き合いいただければと思います。今月のテーマは、「あの時代の素晴らしさを思い知った映画」ということで、時代にフォーカスして映画を5本ずつ選ぶというのが今月のテーマとなっています。ちなみに、今回のテーマの「時代」、「あの時代」というところなんですけど、実は、僕、個人的に時代っていうものにすごく関心があって、例えば映画史にも120、130年の中でいろんな時代がある。例えば、カルチャー、映画の枠を飛び越えて、音楽とかアートとかそういうシーンを見ても、いろんな時代があるわけですね。僕が、そのキノ・イグルーを始めたときに、やっぱりある時代に対してのあこがれがすごくあって、そんな時代のアーティストたちみたいに、何か一つの場所に、本当にその時代を象徴するような人たちが偶然集まって、一時代を築いていくっていうことって振り返ると歴史上やっぱり結構あって。例えば、ブラジル音楽のボサノヴァが誕生したときにも、そのある時代に、才能あるミュージシャン、まだ無名時代の才能あるミュージシャンがある場所に集って、そこでみんな若者でまだ暇だからといって、ダラダラしながらギターを弾いていたら、新しいコードを発見して、それがボサノヴァに変わっていったと言われています。そのある場所っていうのは、ナラ・レオンの住んでいたマンション。サロンを舞台にしている……おっ!! 到着しました。来ました。いらっしゃいませ。みなさん、順也が到着です!
渡辺:失礼いたしました(笑)
有坂:僕の今の話は、ナラ・レオンのサロンに集まっていた若者の中に、その後、時代をつくっていくボサノヴァのミュージシャンも多数いたと、時代の空気みたいなものがある場所に才能が引き寄せられるみたいな。そういう現象がもともと大好きで、時代にはすごく関心があるタイプなので、今回はすごくいいテーマだなと思っております。では、順也は、心の準備はできましたか。
渡辺:大丈夫です。じゃあ、僕から発表していきたいと思います。
──
渡辺セレクト1.『5時から7時までのクレオ』
監督/アニエス・ヴァルダ,1961年,フランス,90分
有坂:うんうんうん。
渡辺:別の切り口だった回で紹介した気はするんですけど。この作品は、ストーリー的にはクレオという主人公の女性が、がんの検診を受けて、その結果が出る夕方まで、5時から7時の間、パリの街をうろうろさまようという、それだけのお話なんですけど。でも、クレオ自体はすごい不安なんですよね。もしかしたら病気かもしれないというのがある不安の中で、パリの街をさまよっているという話なんですけど。これはやっぱりすごいのが、当時の撮影がゲリラ撮影なんですよね。ヌーベルバーグの本当にこの時代の映画って、今までセットで映画を撮っていたのを、カメラを持ち出して街に行って、ゲリラ撮影で、ロケで映画をつくるというのがやり始めの時期というのもあって、なので、そういう整備とかルールみたいなものがないので、今だったらSNSに載せる写真でも顔にモザイクを入れるとか、そのぐらいやっていたりしていますけど、この当時は、街にカメラ持ち出して全部無許可で、許可を取るという概念も多分なかったと思うんですけど、映り放題というところだったので、本当に生の当時のパリの様子が記録されている。そういう意味でも、すごい貴重な作品ではあるんでね。なので、この60年代のヌーベルバーグとか言われていた時代のパリっていうのが、そのまんま映し出されている。マーケットとかね、いろんなところをクレオが練り歩くので、そういう場所、場所だったり、あと本当にすれ違う人たちの表情だったりとか、服装だったりとか、そういったものも全部その当時のものなので。そういうのをひっくるめてあの時代のパリみたいなところに、思いを馳せたいときにこの作品を見ると、「本当にこういう感じなんだな」って、物語と現実がリンクしている状態なので、そういうのが楽しめる作品だなと思います。
有坂:ヌーベルバーグから来ました。僕も1本目はヌーベルバーグを用意しているので、やっぱり僕たちにとって、この時代のフランス映画というのはとても重要な意味があるということだね。あっ、順也先生、カレーが来ました!
渡辺:ありがとうございます。
有坂:今日、カレー食べながらやります。
渡辺:まさか、出していただけるとは。ありがとうございます! じゃあ、遠慮なく。
有坂:自分のパートで、喋りながら食べちゃダメだよ(笑)。
渡辺:わかりました。
有坂:じゃあ、食べていてください。僕の1本目にいきたいと思います。同じヌーベルバーグの、これはもう本当に歴史を変えた1本。1959年に撮影された映画です。
有坂セレクト1.『勝手にしやがれ』
監督/ジャン=リュック・ゴダール,1960年,フランス,95分
渡辺:うーん。おおー。
有坂:これはもう言わずと知れたジャン=リュック・ゴダールの長編デビュー作であり、フランス映画史のみならず、世界の映画史を劇的に変えた、革命的な一作と言ってもいいんじゃないかなと思います。今、順也が言ってくれたものとちょっと重複するところがあるんですけど、この時代というのは、自分たちの親世代とか、おじいちゃんおばあちゃんの世代が観てきた、つくってきた映画を否定するところから、映画づくりを始めているんですね。要は、「親父たちのフランス映画がダセーよ」みたいな。若い子たちが、アメリカンカルチャーを、音楽とか、映画も含めて浴びるように観ているからこそ、新しい時代のものをつくりたいという、創作意欲みたいなものがあふれている世代で、そんな彼らがちょうど街に出て映画を撮り始めた。それはちゃんと理由があって、手持ちカメラというものが開発されたんですね。なので、そういうハード面でも、街に出て映画が撮れるという状況が奇跡的にリンクして、街に出て映画を撮ってみたら、やっぱりそこに映り込む風景とか、人とか、空気とか、そういったものがこれまでのフランス映画というか、映画史の中では観たことがないようなみずみずしさがあったんですよね。なので、世界の若者たちが、みんな同時代的に熱狂したという、そのきっかけになった一本がこの『勝手にしやがれ 』です。
この『勝手にしやがれ 』のちょっと前に、実は盟友、フランソワ・トリュフォーが『大人は判ってくれない』という映画をつくって、それがカンヌで賞を獲ったというものが、実はもう土台にはなっていて、その流れでゴダールが決定打を放ったということで、本当に映画が好きな人にとっては貴重な一作。貴重なというか、これぞ映画史を変えた、というような一作でもあります。話的にはここにも書いてますけど、本当にチンピラみたいなミシェルという若者が、アメリカのパトリシアという女の子に恋をしつつ、でも、警察からも追いかけられてみたいな、ちょっとした軽犯罪劇みたいな物語なんですけど、物語が面白い面白くないを超えて、映画という表現でこんな可能性があるんだ、と。あと出ている、ジャン=ポール・ベルモンドとジーン・セバーグがかっこいいんですよ。今、観てもかっこいいし。僕もこの前、インスタで、ジーン・セバーグのサマーニットを上げたばっかりなんですけど、本当に今の時代で同じようなモチーフでTシャツをつくっている人がいたり、パーカーをつくっている人もいるので、そういった意味でもファッションとか、音楽とか、写真とかが好きな人にも、ぜひ観てもらいたいなと思う一本です。ぜひ、こういう時代のフランス映画を観たことがない人にとっては、なんかわかんないけどすごい、みたいな。その感動が最初にあったよね。
渡辺:そうだね。あと、パリのアパートが狭いんだけどね、窓を開けると大通りがあってとか、なんかああいう感じの建物だったりとか、あと大通りを新聞を読み歩いたりとかね。
有坂:「ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン」ね。
渡辺:あと、あの当時の車とか。
有坂:レトロなものが好きな人も、きっと満足できるポイントがあるんじゃないかなと思います。
渡辺:なるほど、近い作品だね。
有坂:このキノ・イグルーが始まったときって、移動映画館ではなくて、最初シネクラブとして始めたんですけど、そのシネクラブの原点っていうのは、このゴダールとかトリフォーとか、このヌーベルバーグの時代の監督たちが若かりしころに通っていた、そういうシネクラブという文化に僕らはあこがれがあった。なので、その時代の本とかも読んで、自分たちもシネクラブやってみたいと思ってキノ・イグルーを立ち上げたので、なので、お互い一本目に自然とヌーベルバーグが出てくるというぐらい、重要な時代かなと思います。
渡辺:なるほど。じゃあ、2本目はちょっとガラリと変えていきたいと思います。
有坂:カレーこんなに食べたの。早っ!
渡辺:それはもう、飲んでますから(笑)。
有坂:ちゃんと、噛んでください!
渡辺:僕の2本目は、2018年の日本映画です。
渡辺セレクト2.『止められるか、俺たちを』
監督/白石和彌,2018年,日本,119分
有坂:うんうんうんうん。
渡辺:これは日本映画なんですけど、舞台となるのは同じく60年代ですね。ただ、60年代の日本っていうのはまたちょっと違っていて、まさに学生運動の時代なんですね。その学生運動の時代に若者を集めて映画を撮っていたのが、若松孝二という監督で、『実録・連合赤軍』とかそういう学生運動を象徴するような映画を撮っていた人ですけど、その若松孝二を中心とした人たちを主人公とした映画になっています。この作品の主人公は、その中で女性スタッフとして働いていた人を門脇麦が演じていて、監督の若松孝二を井浦新が演じているという作品なんですけど、この60年代のなんていうのかな、めちゃくちゃなエネルギーみたいな、そういうもう何でもありみたいな。今のちょっと価値観とは違う、もうイケイケなエネルギーにあふれた映画づくりをしている人たちの作品なので、歌舞伎町とかがすごい出てくるんですよね。みんな歌舞伎町で安酒を飲んで、そこで映画議論を交わして、ああだここだとか、喧嘩とかして、そのまま「撮影行くぞ」みたいな感じで、今考えるとむちゃくちゃなスタイルでやっているんですけど、それが成立していた時代なんですよね。歌舞伎町とか、新宿とかはよく見ると、現代のまま実は撮影しているんですけど、でも、なんかちょっとモノクロにしたりとか、昔っぽい演出はしているんですけど、よく見ると現代の歌舞伎町だったりして、それはあえてそういうふうに撮影したらしいんですけど。でも、やっぱりそういうふうに映し出されると、もう60年代の新宿歌舞伎町に見えてくる。そういうちょっと不思議さもある作品です。これ、監督は白石和彌ですね。『孤狼の血』とか、いろいろゴリゴリのヤクザ映画を撮っていたりするんですけど、現代を代表する監督だったりするので、その人による、これは青春物語だと思うんですけど、そういう形で60年代の新宿を切り取ったという作品です。これ、作品自体は続編もつくられていて、『青春ジャック 止められるか、俺たちを2』。井浦新さんが、いいんですよね。ちょっと東北なまりの監督を、なんだろう、熱演というか、本当に自然とやっているという感じで、雰囲気のある監督というのをすごい演じています。
有坂:これはあれだよね。監督の白石さんも、若松孝二と直接関係があった人。
渡辺:そうだっけ。
有坂:そう、若松プロに関わっている人たちが、若松監督をやっぱり後世に伝えたいというところから始まっているから、その気合が違うんですよ。井浦新さんも若松孝二のリスペクトが強いから、最初は断っていたらしいんだけど、もうやるって腹を決めたら、あんなに乗り移ったかのような、モノマネしているように見えるぐらいキャラクターを変えているけど、観ていると本当に自然なんですよね。ちょっと不思議な魅力で若松孝二を演じて、こういうものをきっかけに、自分が全く興味のなかった70年代の日本映画とかね、観る入り口になるからすごくいいよね。
渡辺:「2」の方も、若松孝二監督が名古屋に映画館をつくるんですけど、そのときの話で、そのときに巻き込まれて、館長することになったのが、東出さんが役としては演じているんですけど、それが今も支配人として名古屋の「シネマスコーレ」という映画館でやっていたりするので、そこで井浦新が一日館長をやっていたり、プロモーションでしていたりするので、そういうところも面白い作品ですね。
有坂:続編の方が、もうちょっと軽いタッチで、また違った魅力があってね。
渡辺:そうですね。
有坂:ぜひ、二本立てで観るのもいいかもしれないですね。
渡辺:あっ、キネマ ミュージアムでやってた。新さんが舞台挨拶で出てね。
有坂:そうだそうだ。じゃあ、僕の2本目は、ちょっと視点を変えて、映画は1961年の日本映画。で、あの時代の「時代」っていうのは、90年代の東京、渋谷ですね。そういうところでちょっと紹介したいと思います。
有坂セレクト2.『黒い十人の女』
監督/市川崑,1961年,日本,103分
渡辺:なるほど。
有坂:この『黒い十人の女』というのは名匠・市川崑が、奥さんでもある和田夏十のオリジナル脚本で監督を務めた、いわゆるブラックコメディ要素のあるサスペンス映画になっています。テレビが一番元気があった時代のテレビ業界の話なんですけど、絵に描いたようなプレイボーイのプロデューサーがいて、その男に思いを馳せる10人の女、その10人の女から恨まれ、みたいな。このビジュアルが象徴していますけど、この女性たちが、主人公の男は船越英二が演じているんですけど、岸恵子さんとか、山本富士子さん、宮城まり子さん、中村珠緒さん、岸田今日子さんっていう、もう本当に個性派ぞろい、名優ぞろい、そんな彼女たちが、もうダメな男を何とかしてやろうみたいなことを企んだりするわけです。このモノクロ映画で、60年代の日本映画なんですけど、なんでここで紹介することになったかというと、これが日本でリアルタイムではない60年代以降に公開されたのが、実は90年代です。97年の渋谷のシネセゾンという劇場で、これはリバイバル上映されて、これだけ多くの人に知られることになったんですね。それを届けたのが、元ピチカート・ファイヴの小西康陽さんです。小西さんはミュージシャンで、あれだけ今でも現役でDJやって、めちゃくちゃ音楽詳しいですけど、同じぐらい、実は映画にも詳しくて、90年代っていうのは60年代の映画のリバイバルっていうのが、すごい流行って。それはさっき紹介したゴダールとか、ゲンズブールとか、割とヨーロッパとか、アメリカとか、ヨーロッパかな。60年代のちょっとビジュアル的におしゃれなものが、もう軒並みリバイバル上映されていた時代だったんです。いよいよ、もう『ナック』も上映したし、アントニオーニもやったし、もう掘り下げるものないかな。もう一回落ち着いたかなっていうタイミングで、小西さんが、ピチカート・ファイヴプレゼンツで『黒い十人の女』を出してきたんです。この当時って、やっぱりまだ海外へのあこがれがすごく強い時代で、日本の音楽でも和物、今は和物っていうと、シティポップで山下達郎とかになるのかもしれないですけど、その前の時代の和物って、もうちょっと昭和歌謡みたいなものをよく聞いていくと、クラブDJがかけられる曲いっぱいあるよねってことで、和物をすごく感覚のいいDJは、早くからいっぱい掘っていた。それをクラブイベントでかけて、感度の高いリスナーを熱狂させていた、みたいな時代があったんですよね。だから、知る人ぞ知る日本の昔のものを、もうみんながうすうす、かっこいいのがあるらしいっていうときに、どーんと大きく分かりやすく打ち出してきたのが、ピチカート・ファイヴプレゼンツのこの『黒い十人の女』でした。なので、海外だけではなくて、自分たちの生まれ育った日本にもかっこいいものがいっぱいあるっていうことで、60年代の日本映画を改めて掘り下げるっていう流れにもつながった、本当に決定的な一本です。これは、リバイバル上映のときにつくられた予告編がめちゃくちゃかっこよくて、岸田今日子さんがナレーションで、「もう死んでしまえばいいのよ。あんな男」っていう。すごいクールなナレーションに、ピチカート・ファイヴのトラックが載っているっていう予告が、もしかしたらYouTubeで観られるかな。ぜひ、機会があったら、本編もAmazonプライムで観られるので、ぜひ。本当にかっこいい日本映画です。
渡辺:これは、衝撃的だったよね。
有坂:パンフレットもかっこよかったし。
渡辺:やっぱり、当時日本映画=ダサいみたいな流れの中で、昔のモノクロの日本映画がかっこいいなんて想像もしていない角度からやってきたっていうね。
有坂:そう。女優さん、こんな綺麗だったんだみたいな。
渡辺:「岸田今日子って、あの岸田今日子でしょ?」って(笑)。
有坂:そうそう。「中村珠緒って、勝新の」みたいな。でも、そうやって、温故知新じゃないけど、同じ国の昔の文化をつないでいくっていうことは本当に大事だし、それをあの時代の感覚で届けてくれたっていう意味で、90年代を象徴する映画文化の一つかなと思います。
渡辺:本当に、あの時代にあの洗礼を受けといてよかったなと。
有坂:本当だね。素直に楽しんできてよかったね。ハスに構えないでよかったよ。
渡辺:渋谷系って言われる文化、現象だったからね。だから、どうなんだろう? 東京以外の人ってああいうのはあったのかな?
有坂:でも、リバイバルは、大阪とかでもたまにやっていたりするぐらいで、やっぱり、もうあくまでメインは東京だったと言われているからね。
渡辺:渋谷だったよね。
有坂:まあ、渋谷がね、本当に元気な時代だったよね。
渡辺:なるほど。そういう角度だね。じゃあ、僕の3本目は、90年代のアメリカ映画。1993年のアメリカ映画です。
渡辺セレクト3.『バッド・チューニング』
監督/リチャード・リンクレイター,1993年,アメリカ,110分
有坂:うんうんうん。
渡辺:この映画は、舞台は70年代です。『バッド・チューニング』っていう作品は、監督はリチャード・リンクレイターですね。かなり初期の頃に撮ったやつだと思うんですけど、話的には学園ものというか、学生たちの話なんですけど、「今日から夏休みだ」っていうときに、早速「お酒飲んでパーティーしようぜ」っていう若者たちの話になります。この主人公のグループの子たちは、早速そういうふうにお酒買おうぜって言うんですけど、バレちゃって、お酒を買えなくなっちゃって、「じゃあパーティーできないじゃんみたい」になったところから、バーに行ったりとか、その夜をさまよって、いろんな人に会って、いろんな流れに遭ってっていう一夜を描いた作品なんですけど。結構アメリカ映画って、こういうのが多くて。向こうって、夏に学年が変わるので、夏休みになるっていうのがその学年の終わりで、また次の学年の始まりで、高校から大学とか、そういう切り替わりも夏だったりするんですね。なので、そういう始まりと終わりみたいなタイミングが夏だったりするんですけど、そういう一夏の学園ものみたいなものは、結構アメリカ映画で多かったりするんです。その中で、こういう止めどなく将来への不安とか、何も考えていなくて「今を生きようぜ」みたいな生き方だったりとか、そういうのを酔っ払ってみんながちょっと語って、その時代の生き方みたいなのが見え隠れする、そういうタイプの青春映画になります。そういう映画、結構多かったりはするんですけど、その中でも個人的にはすごい好きな作品がこの『バッド・チューニング』です。それで、マシュー・マコノヒーが、若きマシュー・マコノヒーが出てくるんですけど、マシュー・マコノヒーが、高校をドロップアウトして今はバーだったっけな、酒屋で働いているみたいな、クセ者の役なんですけど、マシュー・マコノヒーってこんな若いときから、クセ者やっていたんだっていうですね、そういうのがめちゃくちゃ似合うんですけど、マシュー・マコノヒーに会うことで、酒が調達できるみたいになって、そこでまた話が転がっていくっていうきっかけの役ですけど。
有坂:大事な役だよね。
渡辺:また彼が変なやつなんですけど、ぽろっといいこと言ったりとか、そういう学生たちのセリフ回しみたいなものも、リンクレイターがうまく映し出した、すごい青春映画として面白い作品になってます。
有坂:ミラ・ジョヴォヴィッチも。
渡辺:そうなんだよね、当時まだ無名だったんですよね。たまにね、前も紹介した『スーパーバッド 童貞ウォーズ』に、エマ・ストーンが出ていたりとか。
有坂:そうなんですよ。青春映画を観る面白さの一つってやっぱりね、ネクストブレイクスターがいるんですよ。で、日本でも『桐島、部活やめるってよ』とかね。松岡茉優が出ていたり、東出くんが出ていたりとか、だからもうスターになってから振り返るのも楽しいんですけど、リアルタイムで公開されている青春映画を観ると、「もしかしてこの子、ブレイクするんじゃない?」って勝手にスカウトみたいな気分で、推しを見つけて、そこから追いかけていくっていうのも、青春映画を観る楽しみの一つかなって。
渡辺:そうだね。これ、舞台70年代のテキサスなんですけど、でも、なんか最近の映画を観ても、なんかアメリカの学生って同じようなことやっているなって、そういう面白さがあったりとか、あとオープニングの前半の方で、飲酒禁止に学校の先生がサインしろって、生徒にやるんですけど、まあ今ならそんなの当たり前じゃないかとは思うんですけど、ひたすらサインを拒み続ける生徒が主人公の一人だったりとか。なんか、そういうアメリカもだんだんやっぱり厳しくなっていって、最後の自由というか、70年代ってまだヒッピーとかの流れから自由なアメリカみたいなのがあったんですけど、それがまたちょっとだんだん規制されてきてっていう、本当に最後の自由みたいなところを切り取った作品でもあって、そういう意味でもすごい面白い作品になります。
有坂:はい。じゃあ、僕は続けて、70年代のアメリカ映画を紹介しようと思います。
有坂セレクト3.『さらば冬のカモメ』
監督/ハル・アシュビー,1973年,アメリカ,104分
渡辺:おおー。
有坂:1973年の映画で、ジャック・ニコルソンが主演した作品です。これは、学園ものとかではなくて、主人公は大人で、海軍の将校のジャック・ニコルソン。ベテランで、結構おじさんですよね。その相方の二人が、40ドルを盗んだ若い兵士を別の刑務所に移送する。その移送する役割を与えられた二人と、その移送される若い兵士、3人のロードムービーですね。この移送する側のジャック・ニコルソンたちは、めんどくせえなと思いつつも、でも、普段の職場を離れて旅ができるわけで、じゃあ、もう休暇気分で行くかみたいな感じで、もうとっととこの若い子を送り届けて、もう残りの時間でバカンスしようみたいな気分で旅に出たものの、何か話をしていくと、どうやら、その若い子はそもそも軽犯罪で40ドルを盗んだことで、なんでここまでのことになっているんだろう、というのを聞いていくと、どうやら、刑務所の中で福祉活動に熱心な署長夫人がいて、その署長夫人が福祉活動とか、なんとかクリーンな形に変えようと思ったところに泥を塗ったみたいな、だから絶対に許さないみたいな形で、いわゆる見せしめみたいな形になったんですよね。そうなるとジャック・ニコルソンたちも、それはちょっと不条理じゃないかみたいになってきて、だんだんその3人の中に連帯感が生まれてくるんですよ。もっと話を聞いていくと、その若い兵士は未成年で未来もいっぱいある。だけど、家庭環境にめちゃくちゃ問題がある子で、情緒不安定で、ということで、だんだんジャック・ニコルソンを演じるベテラン海軍の兵士が彼に対して親心みたいなのを持ち始めて、「何かじゃあお前、女の人も知らないんだろう」とか、だんだん自分の業務以外のこともいろいろと世話してあげるようになってきて、でも相方はどっちかというとモラルを大事にする人で、「それはやりすぎですよ」みたいになってくるっていう。この3人のバランスも面白いんですけど、でも、後半にかけてやっぱりもちろんルールとかモラルって大事なんだけど、もっと大事なことって、人間生きてく上であるんじゃないっていう、わりと大きいメッセージにつながっていく、本当に人間ドラマとしても観ごたえのある作品です。今ってね、コンプラとか、なんとかハラスメントとかよくわからないものに、みんなががんじがめになって、それを気にするあまり、表現ものびのびできないとか、上司も部下と向き合うときに、そのハラスメントのことばっかり考えて言葉を選んでしゃべっていたら、やっぱり心と心のつながりって生まれにくいと思うんですよね。だから、もちろん大事なことでもあるけど、これぐらいでもいいんじゃないみたいな。そのある意味ゆるさというか、人間の大らかさみたいなのが、実は、この70年代のアメリカ映画、ジャンルでいうとアメリカンニューシネマって言うんですけど、その時代の主人公たちには詰まっているので、こんな時代だからこそ、あらためてアメリカンニューシネマを観るっていうのは大事かなと思って、『さらば冬のかもめ』を紹介しました。
渡辺:なるほど。これあれだったよね、今年の『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリデイ』のベースになった一つの作品。あれも3人のバランスでやる作品ですよね。若者が一人いてね。
有坂:あれも同じようなメッセージがある。映画の中に、世の中の厳しさとはまた違う、人間の温かさとか、これがいいよねっていう人間が映画の世界にはいっぱいいるよね。そういう人が主人公の映画がいっぱいあるので、ぜひ観てください。
渡辺:なるほど。アメリカンニューシネマを。激しいものも多いですからね。じゃあ、僕の4本目は、激しさはない作品にしたいと思います。1990年のフランス映画です。
渡辺セレクト4.『プロヴァンス物語 マルセルの夏』
監督/イヴ・ロベール,1990年,フランス,111分
有坂:うんうんうん。うん。
渡辺:これは、舞台はすごい昔ですね。19世紀末のフランスになりますので、全然現代劇ではない作品なんですけど、もう絵本みたいな世界の話なんですね。この作品に、もうこの時代のフランス映画なので、服装とかももうみんなシャツにパンツで、サスペンダーで、帽子かぶってみたいな、そういう世界観ですね。お母さんも腰をキュッと絞って、下が広がるようなスカートを履いているスタイルなんですね。この一家がお父さんが先生なんですけど、地方で、教師の役があって、昇進になったとかで転勤しますって言って、引っ越すことになって、その中で夏にバカンスに行こうというので、別荘を借りて一夏を過ごすんですけど。やっぱりフランスのバカンスもの、けっこう好きなんですけど、さらに昔になればなるほど海外に出てくるようなスタイルでバカンスしているので、そういう雰囲気がすごい切り取られた、きれいな作品になっています。もう携帯とかもちろんないですし、電子機器みたいなのものも一切ない時代で、馬車で移動するみたいなところだったりも含めて、雰囲気のいい作品なんですけど。そこで別荘で過ごす、なんていうのかな、庭先にテーブル並べて、そこでみんなで食事とかワインとか飲んで、自然を楽しみながら家族でご飯を食べるみたいな、そういうのが自然にきれいに描かれている作品なので。こういう時代にちょっとタイムスリップしてみたいなと思わせてくれる、そんなきれいな絵本のような作品なのかなと思っています。
有坂:古き良き時代だよね。
渡辺:本当にそう。それなりの不便はあるんだろうけど、ちょっと今の時代からするとあこがれてしまうくらい、きれいな時代ですね。
有坂:これは続編もあるので、この夏の間に観るにはぴったりだね。あっ、U-NEXTがありますね。じゃあ、僕の4本目は、60年代のニューヨークを描いた作品です。
有坂セレクト4.『ライフ・オブ・ウォーホル』
監督/ジョナス・メカス,1990年,アメリカ,36分
渡辺:おー。
有坂:アンディ・ウォーホルのドキュメンタリーです。これ、映画自体は1990年につくられた作品で、ジョナス・メカスという世界を代表するドキュメンタリー監督の作品となっています。メカスは、もともとリトアニアの人で、リトアニアから亡命して、ニューヨークに単身行って、最初は詩人だったのかな。映像も撮っていたんだ。8ミリカメラを持って、自分の日常、自分の周辺にいる面白い人を記録し続けるという、記録することに取り憑かれた人なんです。それを、いわゆる日記映画というジャンルで作品にまとめていたんですけど、『ライフ・オブ・ウォーホル』は、ウォーホルの追悼で、美術館で大規模な展示をやったときに、過去のウォーホルの映像を集めてドキュメンタリーをつくりますということで、90年にこれは映画化されたものになっています。やっぱり、この伝説のアーティストの日常を記録しているというのは、とてもとても価値のあることで、なんでもないような日常が映っているほど、作品としては価値が上がっていく。で、本当に記録魔だった、ジョナス・メカスだからこそ記録できたものだし、その映像を、セリフとか音声は入っていないんですよ。映像もなんて説明したらいいんだろうな、けっこう難しいんですけど、ゆっくり観せてくれるというよりも、もう次々いろんな映像が目まぐるしく展開されていくという、なんだったんだみたいな。考える余白を与えないぐらいの情報量の日記映画だったりするんですけど、そこに音楽を載せている。でも、映像に映っている中の音というのは、一切映画の中では表現されないというタイプの記録映画です。このアンディ・ウォーホルの時代のニューヨークって好きで、僕、個人的に好きで。ウォーホルがやっていたファクトリーという場所。これはもうスタジオ兼サロンとして機能していた場所で、そこに時代を代表するアーティストとかスターが集まってきているんですよね。で、夜な夜なパーティーやったり、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドがライブやったりとか、本当に夢のような、この時代から見ると、夢のような場所がファクトリーでした。ジョン・レノンとかオノ・ヨーコとか、アレン・ギンズバーグとか、ミック・ジャガーとか、もうあげたらキリがないぐらいのスターたちが集まってきては、もうその風景をひたすら記録していたのがこのジョナス・メカスになっています。今から振り返ってみると、例えば、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドというバンドの伝説といわれているようなライブとか、あと、ウォーホルのすごいセンセーションを巻き起こした展覧会とか、そういうものが全部この36分の中にギュッと詰め込まれています。ナレーションとかでの説明も一切ないので、観ながら考えるしかないんですけど、ただその時代の記録としては、本当にこれは貴重な一本なので、60年代以降のアンディ・ウォーホルとか、ニューヨークのアートシーンに興味がある人は、絶対に観てほしいといいつつ、配信では取り扱いがないので、ぜひDVDとか探してみてほしい。
渡辺:俺も観てないんだよな、これ。
有坂:本当に、でも、メカスの特集上映とか、たまに劇場でやっているので、ぜひ。観られる機会はあると思う。ぜひ観てください。
渡辺:なるほど。じゃあ、僕の最後、5本目ですよね。80年代の作品にしたいと思います。1985年のアメリカ映画です。
渡辺セレクト5.『ブレックファスト・クラブ』
監督/ジョン・ヒューズ,1985年,アメリカ,97分
有坂:ふふふふふ。
渡辺:これは80年代を代表する作品で、監督はジョン・ヒューズという人で、けっこうこの時代の学園モノとかを撮らせたら、もう右に出るものがいないという名匠なんですけども。この『ブレックファスト・クラブ』という作品は、どういう作品かというと、これも高校のお話なんですけど、補修で、このジャケットに写っている5人が集められるんですけど、その5人っていうのが、もうそれぞれみんなバラバラのヒエラルキーのグループの、体育会系のやつとか、あとはすごいオタクとか、ガリベンみたいなのとか、お嬢様とか、そういうそれぞれ別のグループ属しているような人たちばっかりが集まって、補修を受けるという、そういう1日を描いた作品なんです。この中で、最初全然接点のない彼らが、この補修を通して自分とは何かみたいな課題を与えられて、それをやっていくうちにそれぞれお互いを認め出すというか、お互いの存在にしっかり向き合うようになっていって、友情が芽生え出していくっていう作品なんですけど。この学園モノで、それぞれスクールカーストとか、ヒエラルキーみたいなのがあるみたいなことを、多分映画で最初に描いたのが、この作品なんですよね。さっき、『桐島、部活やめるってよ』っていう話も出ましたけど、そういうベースになっているような作品なんですよね。その後、結構こういう学園モノで、それぞれグループの違うところの人たちが交流し出すみたいなのが生まれてきたりとか、っていうのがあるんですけど、これが結構その走りと言われているところで、ジョン・ヒューズ監督は、けっこうこういう作品を他にも80年代、いくつか出しているんですけど、それが全部面白いので、80年代ブームみたいなのがまた来たら、間違いなく取り上げられていく作品かなと思います。ジョン・ヒューズは、確か『ホーム・アローン』とかも。
有坂:そう、脚本を。
渡辺:やっていたりするので、その後もしっかり活躍している監督です。
有坂:いわゆるジョン・ヒューズ・チルドレンが、2000年代以降、活躍するようになって、また青春映画とか、学園モノのリバイバルみたいな形でやっぱり時代がつながっていっている。それぐらいの影響力を持った人だね。
渡辺:80年代は、ちょっと年代として出したいなと思っていて、最初は、少年が自転車に乗って並んで。
有坂:BMXに乗ってね。
渡辺:でも、なんか『グーニーズ』も、『スタンド・バイ・ミー』とかも、なんかすでに言っているよなと思って、その辺が出したかったけど、出せなかった。あの辺の80年代の子どものやつが、ちょっと、じゃない切り口で言ったら、こっちかなと。
有坂:でも、これも名作だよね。これも夏に観てほしい。じゃあ、僕の最後5本目は、2015年の日本映画です。
有坂セレクト5.『ハッピーアワー』
監督/濱口竜介,2015年,日本,317分
渡辺:おお!
有坂:これはもうみんな大好き。濱口竜介監督の5時間17分にも及ぶ大長編映画となっています。これを、なんで紹介するかというと、そもそも物語は4人の女性が主人公で、みんな30代後半を迎えて何でも話せる親友同士と思いきや、一人が秘密を、自分の抱えている秘密を話して、その4人のバランスが崩れていくっていう、いわゆる人間ドラマになっているんですけど。なので、この内容は別に時代とは関係ありません。僕がここで紹介したいなと思ったのが、この『ハッピーアワー』が公開されたときの現象。これ、東京では、渋谷のシアター・イメージフォーラムで上映されていたんですけど、映画が長いので3回に分けて、これ全部観ようと思うと、チケット代3本分払わないと観られない。そんな強気なことは、普通できないじゃん。だけど、もう連日満員だったんですよ。朝一でこのハッピーアワーの1を観たら、そりゃ、2も3も観るじゃん。だから、3回チケットをみんな買い直しているっていうか、全部買っているんだけど、そこにいるメンバー、ほとんど変わらないんだよね。5時間何分、運命共同体みたいな感じで、夕方ぐらいまでこの『ハッピーアワー』の物語に没入する。それを没入したいと思う人が、こんなにいるんだなっていうことに感動したんだよね。若い子が、圧倒的に多かった。20代の映画ファンとか。あと、5時間何分の映画体験っていうものをしてみたいとか、新しい映画の流れが生まれそうな雰囲気があったんですね。
渡辺:2015年。
有坂:そう、2015年。これって濱口監督のキャリアでいうと、この後に『寝ても覚めても』で商業映画デビューするんです。その商業映画デビュー前の『ハッピーアワー』の公開前ぐらいに、濱口監督のレトロスペクティブが開催されたんです。僕の知る限り、商業映画デビューする前の人が、レトロスペクティブを開催されているなんて聞いたことない。
渡辺:確かにね(笑)。
有坂:はっきり言って「どういうこと?」。でも、僕、濱口監督って大学のときにつくっている、東京藝大のときの映画からずっと好きで、ベスト1に選んでいたんですよ。『親密さ』っていう映画とか、この『ハッピーアワー』もベスト1に選んでいるんですけど、観た人は「圧倒的な才能ってこれだな」って、この今のあらすじだけ読んでも、これで5時間何分とか無理でしょうって思うけど、観始めたらあっという間なんですよ。何が面白いのかなぁ?
渡辺:これは普通にドラマとして面白くて、テレビドラマの1時間ものの一気見みたいな。5話一気見みたいな、そういう感じなんですよね。そのぐらいの面白さ。なので、すごい続きが気になるし、商業映画としても全然やっていけるんじゃないかってぐらい。これは、このとき観れなくて、遅れて観たんですけど、「こんなに面白かったんだ!」って、ちょっとびっくりしました。もっとアート系の作品だと思っていたんで、全然面白いじゃんって。
有坂:なんか、会話がとにかく上手いじゃん。濱口監督って、言葉選びとかも巧みだし、この人がそんな本音を抱えていたんだみたいな。その本音を出すまでの流れの組み方とか、そういうところを丁寧に丁寧に積み重ねていくだけで、こういう4人の女性の物語を300分超えても面白いものとしてつくれる。それは、世界的に見てもそんな才能の人って、そうそういないんですよ。「やべえよ、濱口竜介」って言っていたら、『ドライブ・マイ・カー』で、まさかのカンヌとオスカー両方獲るっていう。さすがにそこまで行くとは誰も思ってなかったですけど、やっぱり圧倒的な才能を感じられる一本。この映画がすごいのは、もともとなんでこの企画が立ち上がったかっていうと、これは神戸の市民参加型のワークショップなんですよ。そのワークショップに参加している一般の人が役者としてキャスティングされて、“濱口メソッド”をたたき込まれて演じてみたら、本当に一流の女優さんと、本当に遜色ない演技を披露して、結果的にその今年のロカルノ国際映画祭で、4人そろって最優秀女優賞というのをもらったんですね。だから、やっぱり映画の演技って、演技が上手いだけじゃなくて、監督がつくり出す世界の中にはまっていないと、いいも悪いもまずないわけです。濱口監督は、そこがもう絶対的な才能で、これは劇場じゃないと観られないと思うんですけど、DVDは確か出てるんですけど、劇場でぜひ観てほしいので、やっぱりこの『ハッピーアワー』の熱が、その後『寝ても覚めても』につながり、『ドライブ・マイ・カー』になり、『偶然と想像』で渋谷Bunkamuraル・シネマが、初めて日本映画を上映するというところにもつながっていった。そのきっかけが、2010年代のこの『ハッピーアワー』かなと思います。
渡辺:なるほど、『悪は存在しない』もね、最新作やっていますからね。あれもすごい映画ですからね。
有坂:あのラスト。絶対言えないけど、あのラスト、語りたくてしょうがない。
渡辺:あれは、ちょっと観てもらいたいですね。
──
有坂:ということで、僕はわりと映画の中で描かれている時代だけじゃなくて、公開された時の東京とかの時代の空気みたいなものも、含めて選んでみました。順也は、学園ものが2つあったね
渡辺:そうだね、時代、時代のものをそれぞれ選んでみました。
有坂:他にも紹介したいものは山ほどあったんですが、『ディス・イズ・ボサノヴァ』とかもいいんですよ。ボサノヴァのドキュメンタリー。最初に順也が来る前に話した、ナラ・レオンのエピソード、ボサノヴァが誕生していく流れがまとめられたドキュメンタリーなんかもおすすめです。じゃあ、最後にお知らせがあれば。
渡辺:僕は、フィルマークスのリバイバル上映企画なんですけど、今ちょうど『きみに読む物語』のリバイバル上映をやっています。これも20年くらい前の作品なんですけど、ライアン・ゴズリングとレイチェル・マクアダムスのストーリーなんですけど、これもかなりいい作品で、なかなか劇場で観られる機会はないので、ぜひ観てみてください。あと、ちょうど今週末からですね、『サマーウォーズ』15周年っていうのを、全国の映画館でやります。『サマーウォーズ』15周年なのでスタジオ地図も一緒にやっているんですけど、いろんな気合い入って、いろんな企画をやっていたりするんですけど、一つは入場者プレゼントで、劇中で花札をやるんですけど、あの花札のサマーウォーズバージョンをもらえるっていうのをやっているので、初日から配ってなくなったら終了ですので、ぜひ早めにもらってください。
有坂:それはファンが殺到しそうだね。
渡辺:殺到してくれたらいいなと思っています。
有坂:じゃあ、僕からは、8月のちょっと先なんですけど、8月31日、9月1日の土日に、毎年恒例の横須賀美術館の野外上映会が、今年も開催されます。今年の上映作品は、『ディリリとパリの時間旅行』という2018年のアニメーションです。フランスのアニメ、ミッシェル・オスロという、今の時代を代表するアニメーターが、もうパリ、『ミッドナイト・イン・パリ』が好きな人は絶対に観たほうがいい。これを美術館の野外シネマで観られる。しかも、あそこの環境って、スクリーンの向こう側が海で、空は広いし、大自然の中で、ぜひこの映画のラストシーンを観てほしいんです。なので、ぜひお時間ある方は、来てください。
もうすぐ、いよいよ、パリ・オリンピックが始まりますので、8月の終わりは、たぶんみなさん、パリづいていると思うので、そんなタイミングも含めてこの映画を選んでいます。予約も必要なく無料で観れますので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。
──
有坂:ということで、ちょっとイレギュラーな形で始まった、今日のニューシネマワンダーランド、いかがだったでしょうか?
渡辺:間に合ってよかったです(笑)。
有坂:間に合ってない(笑)。
渡辺:ギリギリセーフで良かったです(笑)。
有坂:ということで、今月のニューシネマワンダーランドは以上です。遅い時間までみなさん、どうもありがとうございました!
渡辺:ありがとうございました! おやすみなさい!!
──

選者:キノ・イグルー(Kino Iglu)
体験としての映画の楽しさを伝え続けている、有坂塁さんと渡辺順也さんによるユニット。東京を拠点に、もみじ市での「テントえいがかん」をはじめ全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館など様々な空間で、世界各国の映画を上映。その活動で、新しい“映画”と“人”との出会いを量産中。
Instagram
キノ・イグルーイベント(@kinoiglu2003)
有坂 塁(@kinoiglu)/渡辺順也(@kinoiglu_junyawatanabe)

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店