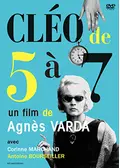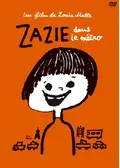あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。今月の映画部門のテーマは、「パリ(Paris)」です。その“観るべき10本”を選ぶのは、マニアじゃなくても「映画ってなんて素晴らしいんだ!」な世界に導いてくれるキノ・イグルーの有坂塁さん(以下・有坂)と渡辺順也さん(以下・渡辺)。今月も、お互い何を選んだか内緒にしたまま、5本ずつ交互に発表しました! 相手がどんな作品を選んでくるのかお互いに予想しつつ、それぞれテーマを持って作品を選んでくれたり、相手の選んだ映画を受けて紹介する作品を変えたりと、ライブ感も見どころのひとつです。
──
お時間の許す方は、ぜひ、このYouTubeから今回の10選を発表したキノ・イグルーのライブ「ニューシネマ・ワンダーランド」をご視聴ください! このページは本編の内容から書き起こしています。
──
−−−乾杯のあと、恒例のジャンケンで先攻・後攻が決定。今月も渡辺さんが勝利し、先攻を選択。それでは、クラフトビールを片手に、大好きな映画について語り合う、幸せな1時間のスタートです。
──
渡辺セレクト1.『ミッドナイト・イン・パリ』
監督/ウディ・アレン,2011年,スペイン・アメリカ,94分
有坂:うんうん。
渡辺:まず、ちょっと王道というか。まあ、2011年なので新しめの作品なんですけど。これはウディ・アレンの作品で、けっこう観たことがある方も多いんじゃないかなと思います。でもね、もう冒頭から、ほんとにパリのプロモーションビデオなんじゃないかっていうぐらい、名所、名所のきれいなところの映像のオープニングから始まるという、素敵な作品です。
有坂:そうだね。大好き。
渡辺:これですね、(ビジュアルの)セーヌ川がまたね。それで、これは話も面白くて、主人公がアメリカ人なんですけど、旅行でパリを訪れていて、ひょんなことから夜な夜なベル・エポックというね、昔の黄金期のパリに、タイムスリップしてしまうと。そして、そのベル・エポック期の偉人たちと酒を組み交わすみたいな、そういう不思議な、夜を過ごす主人公の話です。主人公は物書きなので、昔のヘミングウェイだったり、そういう人が好きなんですけど、その昔の時代のパリっていうのは、ヘミングウェイだったり、ピカソだったり、ダリだったり、世界中のアーティストが集まっていた時代なので、みんなね、そういう主人公からすると憧れの人たちが酒を組み交わしている。その中に自分も混ざって、一緒にお酒を飲むっていう夢のような時を過ごすという話で、朝になるともう家に帰るんですけど、それはまた現実に戻るんですね。でも、現実はなんか、ちょっとギスギスしていたりする中で、また夜になると、街に繰り出すと迎えが来て、またベル・エポックの夜へと行くみたいな、そういう不思議な話なんですけど。やっぱりね、あの時代のなんていうんでしょう、画家だったりとかアーティストだったりとか、そういうのが好きな方からしたら、もうたまらない。こんな世界に自分も行ってみたいと思わせるような、日々が続くっていう作品で、これはほんとに映画としてもすごく面白いし、なんかアートとかカルチャーとかが好きな人には、もうど真ん中な作品だなと思います。はい、ということで、僕の1本目は、『ミッドナイト・イン・パリ』でした。
有坂:これはもう、早い者勝ちの1本だね。僕も、もちろん用意していた作品ですけど、これは、ウディ・アレンがアカデミー賞でも、脚本賞を受賞して、久々に作品賞、監督賞にもノミネートされた。それも15年ぶりぐらいな。そういった意味でも、彼の長いキャリアの中でも、また新たな傑作って呼ばれるような一本。もう、ほんとにパリに行きたくなるよね。
渡辺:いや本当に、そう、パリのいいところをちゃんとね、いい感じに映してくれているっていう。
有坂:やっぱりウディ・アレン自身が、パリへの憧れがすごい強い人で、その憧れがベースにあるので、映る風景から何からね、ほんとにパリ好きの人にはたまらないようなシーンが目白押し、流れる音楽も含めてね。……まあ、そうだよね。出るよね。もうじゃんけんに負けた時点で、これは諦めました(笑)。はい、ということで、僕の1本目にいきたいと思います。僕もアメリカ映画です。
有坂セレクト1.『ビフォア・サンセット』
監督/リチャード・リンクレイター,2004年,アメリカ,81分
渡辺:ああ! そうだよね。そうなりますよね。
有坂:これは、イーサン・ホークとジュリー・デルピーが共演した、今のところ全3作ある中の第2作にあたる作品です。で、この映画のストーリーというのは、そもそもですね。第1作の『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』っていう映画の続きなので、『ビフォア・サンライズ』の話をまずすると、まあ旅行先で、男女が出会うんですね。イーサン・ホークとジュリー・デルピー。お互いに電車の中で、ユーロスターかな、そこで出会って意気投合して、このまま離れるのは寂しいっていうことで「ウィーンの駅でよかったら降りないか?」っていうことをイーサン・ホークがジュリー・デルピーに声をかけて、で、その朝までの時間を2人で共に過ごす。そのウィーンの街を二人で歩きながらいろんな話をしていく。その一夜の物語が、第1作目の『ビフォア・サンライズ』です。公開当時はね、『恋人までの距離(ディスタンス)』というタイトルだったんですけど。
渡辺:ね。
有坂:その9年後に、第2作の『ビフォア・サンセット』が公開されました。で、このプロジェクトが面白いのは、その、主人公の役者も変わらないんですね、イーサン・ホークとジュリー・デルピー。3作目もまたこの二人。その彼らのリアルなところであった年数。この映画でいうと9年、1作目から2作目まで9年かかってます。で、劇中も9年後の話なんですよ。なので、一応物語のあるフィクション映画なんですけど、彼らの例えば、その肉体的な変化だったり、そういったこう嘘がつけないドキュメント的な要素も込められているっていう、すごく野心的なプロジェクトだなと思います。で、これは3人でね、ああだこうだと、監督と主演二人がいろんなアイデアを出しながら脚本をつくっていくっていう、本当に他に類を見ないようなタイプの映画です。この『ビフォア・サンセット』は、前作で「半年後に待ち合わせをしましょう」って約束した二人なんですけど、結果的にいろいろあって、そこでは二人は再会せず、その9年後、パリの街、舞台は「シェイクスピア・アンド・カンパニー」という本屋さんで、偶然出会うんです。で、そのイーサン・ホークは、作家になっていて、彼の新書の発売記念という形で来ていたところに、ジュリー・デルピーがふっと来て、思わぬ再開を果たすという、本当に「映画か!」って言いたくなるような、まあ映画なんですけど(笑)
渡辺:(笑)
有坂:——というすごいロマンチックな設定になってます。
で、ただ前回は一晩の物語だったんですけど、この2作目は、もうね帰りの飛行機までの時間というタイムリミットが決まってるんですね。で、このタイムリミットが、わずか80分。だけど、半年後に会おうって約束したのに会えなかった。さらに、そこから9年経っている。話したいことがいっぱいあるのに、時間は80分しかないんです。で、この80分の間に二人がいろんな会話を交わしていく姿を追ったラブストーリーになってます。で、この会話を2人が交わすのも1か所にとどまって話すんじゃなくて、この映画はね、パリの街のいろんなところを歩いたり、あとは素敵なカフェでコーヒーを飲みながら喋ったり、もうそのパリの街もある意味、ひとつの映画の主人公といってもいいような魅力にあふれた作品となっております。
渡辺:ねぇー、僕もね、もちろん観ましたよ。三部作で “ビフォア” シリーズなんだよね。3作目が『ビフォア・ミッドナイト』。
有坂:うん、そうそう。
渡辺:まあ、リンクレイターらしいというか、リアルタイムでちゃんとその年月が経った。
有坂:そうだね。映画なんだけど、まあ映画って基本ね、大きな嘘をつく。物語をつくって、役者がそういう役を演じるっていう意味では大きな嘘っていわれてるんですけど、その中にどれだけこうリアルなね、要素を入れられるかっていうことでつくられた作品で、なんか、この映画は、パリのいろんなね場所が舞台になっていて、シェイクスピア・アンド・カンパニーから始まって、その後、パリ11区にあるカフェに行くんですけど、その間の道、なんか、パリの裏の小道とか、そういうところ——風景が、まあもちろん、そのルートっていうのも3人できっちり考えて、ロケーションされてる場所なので、もうそのパリの風景も、なんだろう、セーヌ川での遊覧船に乗って、そこから見るノートルダム大聖堂とか、そういうなんかいかにもな風景もあるんですけど、何気ないパリの風景もすごく魅力的なので、ぜひパリ好きで、まだ観ていないという方は、すぐに観てください! 1作目から観てください。
渡辺:そうだね、うん。
有坂:はい、という1作目でした。
渡辺:そうきましたか。
有坂:よかった。
渡辺:もうね、ほんとに早いもん勝ち状態だと思いますけど、じゃあ早速、僕の2本目にいきたいと思います。僕の2本目は、ちょっと昔の映画にしてみます。
渡辺セレクト2.『5時から7時までのクレオ』
監督/アニエス・ヴァルダ,1961年,フランス,90分
有坂:うわっ出た!
渡辺:これは、1961年の作品で、モノクロの作品です。で、いわゆるヌーヴェル・ヴァーグの時代のわりと代表的な作品のひとつになっています。監督は、アニエス・ヴァルダという女性監督なんですけど。これはどういう話かというと、クレオという主人公がいます。女性なんですけど、若くて美しい女性がいて、その女性が病院で検査を受けるんですね。がんの検査を受けてその結果が出るまでの2時間、5時から7時まで、パリの街を不安いっぱいでさまようっていうお話です。で、これ面白いのが、その検査を受ける前に占い師に見てもらっていて、「あなた、今日最悪ですよ」って言われながら検査を受けるので、もうクレオは不安でいっぱいっていうですね。その不安な気持ちでパリをさまようという話なんですけど、当時のこのヌーヴェル・ヴァーグのひとつの特徴としては、セットで映画を撮らない、街にカメラを持って飛び出して、ロケで撮影するっていうのをやり始めたときなんですよね。それで、当時なので当然ゲリラ撮影で、あのすごい、クレオ以外の人たちっていうのは、ほんとにパリの生の人たち。リアルな当時のパリっていうのが、この『クレオ』を観るとわかるんですよね。で、いろんなね、大通りを歩いてみたりとか、ちょっとお店に入ってみたりとか、商店街っていうのかな、こう市場的なところを歩いてみたりとか、その活気あふれるパリの風景っていうのが、すごく映し出されてるんですよね。なので、これはお話としても面白いんですけど、そういう目で、当時のリアルなパリ、演出されていないパリを観るっていう意味でも、すごい価値ある1本だと思いますので、なかなかこういう昔の作品って観る機会ってあまりないと思うんですけど、なんかね、入門編としてもね、すごくいい映画だし、オススメなので。はい、とういうことで、『5時から7時までのクレオ』が僕の2本目でした。
有坂:ある意味ドキュメントでもあるんですね、というコメントが。
渡辺:おお、そうなんですよ。
有坂:そうだね。でも、そういうゲリラ撮影の面白いところはね、よく観ると、カメラを見ちゃっている。当たり前なんですけど、普通に通行人がカメラをぱって見た瞬間も映っているので、ほんとに、なんかそこに嘘はないなって感じるよね。その着てるファッションだったりとか、そういうものも、60年代のファッションがそのまま映っているわけで、パリ好きには必須だね、これはね。で、なんかさっきの僕が紹介した『ビフォア・サンセット』と、ちょっとつながっているなと思うのが、2作ともパリの街をさまよい歩く話じゃない? 歩きながらパリの風景がどんどん、移り変わっていく。僕の中で、これどっちを紹介しようかなと悩んだ。
渡辺:そうだよね、その流れで紹介してみました!
有坂:はい、ということですね。じゃあ、それを受けて僕の第2作は、1976年の映画です。
有坂セレクト2.『ランデヴー』
監督/クロード・ルルーシュ,1976年,フランス,9分
渡辺:おお!
有坂:なんと上映時間9分の作品です。これは監督が『男と女』というね。カンヌ国際映画祭もアカデミー賞もとった、『男と女』のクロード・ルルーシュ監督がつくった短編映画。これはもうね、伝説的短編映画といってもいい、ぜひとも! 観てほしい、なんとかして! 観てほしい1本です。で、これ9分なんですけど、どういう内容かっていうと、これね映画の冒頭。このビジュアルのとおりなんですけど、映画の始まりが、なんかね暗い画面から始まるんですけど、すごいエンジン音が聞こえてきて、真っ暗なところからパッと車の音なんですね。で、車の運転席から見た目線のカメラなんですよ。なので、ずっとパリの中を車がこう疾走してるところから、どんどんどんどん、こうパリの中をものすごいスピードで駆け巡る姿だけをですね、記録した9分間の短編映画となっています。もう、ほんとにノンストップで疾走するその車が、車の運転席にいながら観ている人たちも巻き込まれたような、臨場感のある作品です。それで、なんでこの車はパリの街を疾走してるのかっていう説明とかね、一切ない。当然その、会話もないんですよ。なので、グイーンっていうエンジン音の中、風景がどんどん移り変わっていく映像をひたすら9分間観る。でも、その移り変わる風景の中には凱旋門が出てきたり、コンコルド広場とかオペラ座とかが、どんどんどんどんね。しかも、ワンカット長回しで撮っているので、ほんとにそのパリの街をどんどん知っている風景が、バスに乗って移動しているような風景が楽しめます。
渡辺:ね。 有坂:で、途中、信号が赤になる瞬間とかがあるんですけど、信号を無視するんですよ。で、これもさっきの映画と一緒でゲリラ撮影なので、これ多分、止まっちゃいけないというルールのもと撮影が始まっていて、なので、赤でも行っちゃう。で、向こうから車が来たら1回逆走するシーンとかもあったりして、結構ね、観ていてハラハラドキドキするような作品になっています。
これ、最後の方にぐんぐん北に上がっていって、モンマルトルの丘を登っていったところで9分間の映画が終わるんですけど、最後はね、ちょっと絶妙な落ちが、ずっこけるような落ちがあるんだよね。
渡辺:みんなが突っ込むっていうね(笑)。
有坂:でも、それも含めて本当によくできた1本。ほんとうに緩急のつけ方というか、そんな1本です。で、ちょっと最後に1つだけ、これ、クロード・ルルーシュっていう監督は、さっき順也が紹介したフランスのヌーヴェル・ヴァーグっていう映画運動、既成概念を壊して新しい映画をつくるぞっていう、音楽でいうパンクみたいなムーブメント。そのヌーヴェル・ヴァーグと同じ時代を、クロード・ルルーシュも生きてるんですけど、ルルーシュはどっちかというと、こう王道のフランス映画をもうちょっと自分なりに解釈したような、洗練された映画を撮る人なので、そのヌーヴェル・ヴァーグの監督たちからは、けっこう揶揄されていた。あんまりいい印象を持たれていない。「俺たちが硬派なら、あいつはちょっと、ちょっと女々しい映画をつくる」みたいなことをいわれていたんですよ、当時。だけど、このランデヴーを見たら、そのヌーヴェルヴァーグの誰よりも、最も過激な映画をつくっていたのはルルーシュだったって、ほんと最高の結果が待ってます。
渡辺:これ、バレたら逮捕されちゃうっていうね。
有坂:そう、そうなんですよ。信号無視も逆走もしてるので。ただ、それでも彼はこの映画を撮りたかったっていうモチベーションがあったわけですね。なので、その覚悟みたいなものが、やっぱり映画から伝わってくる1本でもあるので、9分間があっという間だと思いますけど、YouTubeとかでも、もしかしたら観られると思うので、気になる方は探して観てみてください。
渡辺:なるほど、そこ来ましたか。
有坂:はい。あっ、そうそうごめん、最後になんで、これを2本目に挙げたかというと、1本目の僕の『ビフォア・サンセット』と、順也が、そのあと『クレア』を挙げたけど、最初の1本っていうのは、歩行者から見たパリの風景。
渡辺:うんうん。
有坂:だから、映る映像っていうのはすごくゆっくり流れていて、この『ランデヴー』は、車に乗ってる人、しかも爆走している、車の目線から見たパリの風景っていうことで、同じ移りゆく風景でも、結構こう感じる印象というのが違うので、ちょっとそこのコントラストをつけたいなということで、2本目に紹介しました。
渡辺:なるほど。なかなか観る機会がない作品だからね。
有坂:この前ね、『男と女』のリバイバル上映の時に、併映されていたよね。
渡辺:そうだそうだ。これ映画館で観たらすごいだろうね。なるほどね。じゃあ、続けて僕の3本目。そしたら、今度は王道で。
渡辺セレクト3.『アメリ』
監督/ジャン=ピエール・ジュネ,2001年,フランス,120分
有坂:ふんふん。
渡辺:今のちょっと塁のやつを聞きながらだったんですけど、最後、えっとモンマルトルの丘を登ってサクレ・クール寺院のとろに行くんですけど、あそこっていったら、『アメリ』かなと思って、
有坂:うんうんうん。
渡辺:『アメリ』を3本目に持ってきました。これは、ほんとうに有名なので、結構観ている方、多いと思いますが……。どんな話かというと、ほんと不思議な女の子が、他人の幸せをサポートしようみたいな形で、お節介をし出すっていうお話なんですけど、それでこう、いろんな形に話が転がっていって、もうほんとうになんて言うんでしょう、「パリといえば」みたいな感じで、当時はもう本当に大ヒットも大ヒットして。キノ・イグルーでも昔、カフェで上映会をやるっていうのが、すごい多かったんですけど、もうカフェのスタッフの子たちが観てる率、ほぼ100%っていうね。それはすごいやっぱり印象に残っていて、特に女子の観てる率はもう100%だったもんね。
有坂:100%超えてたね! 超えてました。
渡辺:(笑)。これは本当にすごいなと思って、で、僕も昔パリに行ったときに、アメリの実際のお店に行ったんですよね。
有坂:カフェのね。
渡辺:そう、ここほんとに残っていて、もうザ・観光地みたいな感じになっていて、観光客ばっかりなんですけど。でも、やっぱり世界中からこんなにアメリ好きな人が連日訪れていると。で、多分、アジア人は僕らだけだったので、結構その、いろんな国で愛されている作品なんだなっていうのは、すごい思いました。で、この『アメリ』もほんとにパリのいろんな駅だったりとか、モンマルトルの丘とか、いろんなところを出歩いたりして、なんか、いたずらしたりとかしていくんですけど、そういうパリのいいところだったりとか、あとけっこう部屋の中が映るので、パリのアパルトマンの様子だったりとか、そういったところも楽しめる作品となっています。まあね、結構、これは観たことある人が多いんじゃないかなとは思いますけど。
有坂:「私も観ました。クレーム・ブリュレの憧れはここから」というコメントが。
渡辺:そうね。パリパリのところををね、スプーンで。あれは衝撃だったよね、当時ね。こういうところもなんかこうカフェ女子のね、全員のハートを射抜くみたいな、そういうパンチ力のある。
有坂:やったでしょ?
渡辺:やったよ、やるでしょう。
有坂:俺もやりました。写真は撮らなかった? スプーンをこうやってする。
渡辺:やってないけど、これはやりたくなるよね。
有坂:アメリの面白いなと思うところって、その今いったように、モンマルトルの丘だったり、実在する「カフェ・デ・ドゥー・ムーラン」とかが舞台なんですけど、全然リアリティがないんだよね。多分、そこのバランスが絶妙で、すごいノスタルジックなつくり方。
渡辺:そうだよね。おとぎ話みたいなね。
有坂:色味だったりとか、ヤン・ティルセンのアコーディオンの音だったりとか、ちょっとおとぎ話っぽいつくりにしているんだけど、実在するっていう、この絶妙なバランス感が多分良かった。で、僕もそのカフェにパリに行ったときに行ったんですけど、もうその観光地化してるっていうのを聞いてたので、朝一で行こうと思って、6時か7時かちょっと忘れちゃったんですけど、ほんとに早起きして行ったら、観光客ゼロで。
渡辺:お、そうなんだ!?
有坂:そう、ほんとに、地元のスーツ着たサラリーマン、これから仕事に行くみたいな人とか、工事現場のおじさん、そういった格好をした人とかが、カウンターでコーヒー飲んで、そこに若いお母さんが、子どもをなんか抱っこ紐で連れてきたら、その周りの人たちがこう声をかけて、すごい自然なコミュニケーションが生まれているのを、後ろの席から一人でみていた。
渡辺:(笑)
有坂:あれ、ほんとに感動で、だから、そのおとぎ話みたいな世界なんだけど、そのほんとにアメリの中の、あのカフェの空気感がね、その明け方のあのカフェにはあったので、もし、行かれる予定がある方は、朝一をおすすめします。
渡辺:行っているね、ミーハーだね。
有坂:ミーハーですよ。そりゃ、そうだよ。もう全力で楽しんできました。
渡辺:(笑)。はい、という3本目でした。
有坂:はい、じゃあ、僕もですね、もういいたいものをどんどんいわれてるので、ちょっと変えて、僕の3本目は、1961年の映画です。
有坂セレクト3.『女は女である』
監督/ジャン=リュック・ゴダール(ハンス・リュカス),1961年,フランス・イタリア,84分
渡辺:おおー!
有坂:はい、さっき順也が紹介した『クレオ』と同じ年に公開された映画で、監督はジャン=リュック・ゴダールです。ゴダールの映画って、なんかこう難しくって難解で分かりづらい。1本観たんだけど、なんかすごい苦手意識がありますって人も多いと思うんですけど、そんな人は、ぜひ、まず『女は女である』を観ていただいて、これがダメだったらもうしょうがないと思うんですけど。苦手な人ほどこの映画を観たらね、けっこう腰を抜かす、こんなキュートな映画が撮れるんだっていうぐらい、主演のアンナ・カリーナの魅力全開なミュージカルコメディとなっています。で、これはあの女1人、男2人の三角関係のほんとに他愛もないような、ボーイミーツガールの話になっています。そういうありふれた物語を、映画としてどういうふうに面白くするかっていうことに、あの多分ゴダールは気持ちを入れてつくったんじゃないかなと思います。まあ、ミュージカルコメディーってさっき言ったんですけど、「登場人物が歌わないミュージカルコメディー」というコンセプトだったそうです。そういうなんかひねくれ具合がね、ゴダールのいやらしさで、ただ、これに関しては、ゴダールのそういうクリエイティブに対するすごい欲求みたいなものが、全部いい方向に繋がったっていう奇跡的な1本です。
渡辺:うんうんうん。
有坂:このときって、主演のアンナ・カリーナとゴダールって付き合っていて、この映画が終わった後に結婚するんですよ。なので、ゴダールにとっては、幸せの絶頂。で、大好きなアンナ・カリーナの魅力は、彼はもうよく知っているわけですよ。なので、自分にしか見えないようなアンナ・カリーナの魅力を、フィルムに残したいっていうことで、とにかくね、もうアンナ・カリーナの表情もそうだし、彼女が着ているファッション——赤いカーディガンとか、その色味も含めて、ほんとにもう彼女の魅力がマックスで出たなっていう1本だとも思います。
渡辺:そうだね。
有坂:で、この映画の舞台はパリのサン・ドニ街っていう地域が舞台で、街中を歩くシーンっていうのは、そんなに多くはないんですけど、合間、合間で出てくる風景? アンナ・カリーナはもうね、見るからに女優っていうファッションで、オーラで、そのゲリラ撮影している、リアルなパリの中を歩くと、なんかね、その不思議なコントラストが生まれるんですよね。そういう面白さもあるかなと思います。で、この映画って、ゴダールにとっては初めてつくったカラー映画なので、さっき赤っていう色を言いましたけど、やっぱりね、ゴダールは色を使えるっていう、喜びに満ちあふれているなと。
渡辺:うんうんうん。
有坂:で、なんかテーマカラーを決めて、画面の色彩設計っていうのをつくっていったらしいんだけど、赤、白、青、フランスの国旗、トリコロールがテーマで画面をつくっていったらしいんですね。なので、ほんとに画面の中に出てくるメインの色っていうのは、そのトリコロールの3色のどれかだったりします。わかりやすいぐらいその色をふんだんに使っていて、でも、そのポップな色だったり、アンナ・カリーナの可愛らしさだったり、あとはその演技している女優さんが、カメラに向かって急に話しかけてきたり、そういうなんか、こう遊び心のある演出も含めて、ほんとになんかね、こうふわっと軽やかさのある、楽しいミュージカルコメディになっています。
渡辺:うんうん。
有坂:ちょっとなんかマニアックな話なんだけど、その『女は女である』って、アパルトマンの部屋とかもすごく魅力的じゃない? 部屋の中を自転車で走ったりするんですよ。パリの一人暮らしって、こんな広い部屋に住めるんだって思ったんですけど、そういう部屋の美術とかを手がけたのが、後に『シェルブールの雨傘』で美術を担当するベルナール・エヴァンっていう人なんです。
渡辺:あーあ。ふんふん。
有坂:なので、『シェルブールの雨傘』って、もうほんとにそのベルナール・エヴァンっていう人の才能に支えられているといってもいいぐらい美術が素敵なんですけど、もうゴダールはその前に才能を見抜いて、彼を使っていたので、そんなところにもぜひ注目して、観てもらえたらと思います。
渡辺:なるほどね。あの部屋の中とかすごい印象的だもんね。
有坂:あれね、びっくりだよね。
渡辺:これはちょっとぜひ、なんかインテリアとかに興味のある人も絶対好きだと。
有坂:まあ、そういう特集の雑誌とかにもね、出てくるよね。
渡辺:うん、なるほど。そう来ましたか。まあ、やっぱりね、この辺の時代のやつはね。ちょっと選びたくなるっていうのは。じゃあ。僕は、次ちょっと変えてこれにしよう。
渡辺セレクト4.『ロスト・イン・パリ』
監督/ドミニク・アベル, フィオナ・ゴードン,2016年,フランス・ベルギー,83分
有坂:ああー。
渡辺:2016年なので、わりと新しい作品です。で、これがすごい変わった映画で、お話で言うと、わりとシンプルなんですけど、カナダに住んでる主人公がいて、パリに住むおばさんから「老人ホームに入れられちゃうから助けて」って連絡があって、じゃあ、おばさんを助けなきゃって、パリに向かった女性のお話です。すごいドタバタ喜劇で、ビジュアルもすごいおしゃれで、服装の色だったりとか、そういったところもすごくカラフルでポップな作品です。で、おばさんを探すんだけど、おばさんは見つからないし、自分はセーヌ川に落っこっちゃって全部荷物をなくしちゃうみたいな、それで、なぜかホームレスにつきまとわれるっていう。ホームレスが自分のこと好きになっちゃって、どこにでもついてくるみたいな、そういう不思議な展開なんですけど、なんかこうパントマイムで演技してるような、すごくコミカルだし、なんて言うんだろうな、ジャック・タチの映画みたいな雰囲気なんですよね。
有坂:うんうん。
渡辺:それでおばさんを探しながら、でもお金ないし、ホームレスはついてくるしみたいな、そういう環境の中でパリのいろんなところに行って、いろんな人に会うんですけど、なんかこの映画に出てくるのは、どこか変わった人たち。で、そういう人たちとの交流を通して、何か大切なものを見つけていくという作品なんですけど。なので、そういう中で、すごく変わった人たちっていうのを、あたたかい目で見つめる、なんか視線のある優しい映画だなっていうふうにすごい感じていて、なので、そういうちょっとドタバタコメディで、不思議な展開でパリをさまようっていう作品ではあるんですけど、そういうちょっとあったかい気持ちになれるような作品です。で、わりとパリのいいところを巡ったりするというところがあるので、これもパリを探索するような雰囲気になれる素敵な作品となっております。あんまりメジャーな作品じゃないから、知ってるい人は、あまりいないかもしれないですけど——
有坂:そうだね。
渡辺:けっこうね、冒頭のシーンがめちゃくちゃ印象的で、冒頭はカナダなんでパリじゃないんですけど、急に——
有坂:突風が吹く(笑)
渡辺:そう、突風が吹いて扉がバーンと開いて吹雪がバーっと家の中に入ってくるっていうシーンなんですけど、なんか女性が「あわわわ……」みたいに、吹き飛ばされそうになるシーンがあって、これはもう観ないとちょっとわからないんですけど、説明はちょっとうまくできないんですけども、そこからぐっと心を掴まれる。なんか、絵の作り方がすごい独特で、キャッチーですごい面白いんですよね。そこからもうこの映画は間違いないだろうし、信頼できるだろうと思わせてくれる展開なんですけど。ほんとにね、ポップですごい面白い作品ですね。
有坂:パリの魅力はかなり詰まっているよね。久々にこういうパリの街自体が魅力的な映画がきたなっていう1本で、確か、その年のベスト10に入れました。観てほしいね。
渡辺:そうなんです。結構新しい作品なんで、いろんなところで、観られるんじゃないかな、と思います。
有坂:はい、じゃあ、僕の4本目。順也この『ロスト・イン・パリ』をドタバタ喜劇って言ったよね?
渡辺:言いましたよ。
有坂:じゃあ、僕の4本目もドタバタ喜劇で!
有坂セレクト4.『地下鉄のザジ』
監督/ルイ・マル,1960年,フランス,93分
渡辺:ああ、そうだよね。
有坂:ドタバタ喜劇でしょ!
有坂:まあ、これはですね、ザジっていう10歳の女の子が主人公なんですけど、おかっぱ頭で可愛らしいザジのポスターとかね、見たことあるよっていう方もいるかと思います。で、これはあのストーリー的には、ほんとにもうあってないようなものというか、地下鉄好きのですね、ザジ。もう地方から出てきて「パリのメトロに乗るのが楽しみだな」と思って出てきたものの、なんとストライキ中で地下鉄に乗れないっていう。で、もう怒ったザジはですね、1人であずけられた親戚だったかな、その人から逃げ出して一人でパリの街を大冒険するっていう映画です。で、その中でいろんな出会いがあったり、エッフェル塔を、ぐるぐるぐるぐる……。「あれどうやって撮影したんだろう?」っていうぐらい、エッフェル塔の魅力的な映画っていわれたら、ダントツで『地下鉄のザジ』ってあげたくなるぐらい、エッフェル塔もそうだし、あとパッサージュっていうね。商店街というか、パッサージュもすごくこの映画の魅力的な舞台の1つになっていたりするので、観てもらいたいなと思う1作です。
渡辺:うんうん。
有坂:で、なんかね、この映画って、この100%ORANGEが書いた、DVDのジャケットも、やっぱりすごく可愛らしくて。……あっこれ実写です。そうだよね。「これアニメーションですか?」ってコメントがありましたけど、これはその映画のイメージで日本の100%ORANGEというイラストレーターが描いたDVDジャケットだと思うんですけど、すごくキュートでポップで、実際映画もそのイメージどおり、ではあるんですよ。ただ、そのザジがちょっとふざけたり、知らないおじさんから追いかけられたりっていう、逃げたりみたいな。そういうときのなんだろう、早回しにしたりとか、そういうちょっと映像的な遊び心が、もう満ち溢れすぎていて、なんかちょっと怖い。
渡辺:(笑)
有坂:観ていて、ちょっと恐怖を感じるぐらい、やりすぎなぐらい、映像で遊ぶっていうことも追求してる1本なんですね。なので、観た後に「なんかイメージと違った」っていう人も結構いる。確かに絵は可愛いんだけど、でも、2回目観ると、もうそういうものだと思って観ると、やっぱ、その可愛らしさの方がもっと入ってくるから。1回目で何かこう得体の知れない恐怖を感じた方も大丈夫なので、ぜひ2回目も観てみると、この映画のまた魅力の奥深さが見えてくるかなと思います。
渡辺:キノ・イグルーでもね、けっこう上映したりね。
有坂:クラスカでやったね。屋上で。エッフェル塔のシーンとかやっぱり屋上で上映すると、効果的だよね。
渡辺:ザジが10歳ぐらいの女の子なんだよね。
有坂:そうそう10歳。
渡辺:で、こう歯が絶妙に無くて、可愛いんですよ。
有坂:そうだね。なんか、あれだけなんかアイコン的な主人公っていうのもね、最近の映画だとあんまりないね。主人公の名前だもんね、ザジって。
渡辺:そう。
有坂:でも、ほんと彼女の魅力が支えていることは間違いないけど、彼女の魅力に頼らずに監督も頑張って世界観をつくった、そんな1本になってます。ぜひ観てください。
渡辺:そうきましたか。よし! いよいよ。
有坂:最後はね、かぶらない自信あるよ。ほんとに5本目は。
渡辺:ほんとに? そうですかー。
有坂:これがかぶったら、ちょっとこれビールかけるから!
渡辺:(笑)。なるほど、じゃあこれ行こう。
有坂:え! ちょっと待って。
渡辺:(笑)。これ行きます。えっとですね。ちょっと昔の映画です。
渡辺セレクト5.『フレンチ・カンカン』
監督/ジャン・ルノワール,1954年,フランス,102分
有坂:ああ!
渡辺:1954年の作品になります。これね、来るかなと思ってたんだけど。
有坂:忘れてた。
渡辺:うそ(笑)。
有坂:完全に忘れてた(笑)。
渡辺:これは、ほんとにキノ・イグルーでも何回も上映している作品です。で、どういうお話かというと、昔の文明堂のカステラのCMで、猫が足を上げて踊っているっていうですね、知らない人も多いかもしれないですけど、そういうのがあったんですけど(笑)。お話としてはですね、ムーラン・ルージュ、パリのムーラン・ルージュの誕生のお話となっています。で、主人公はジャン・ギャバンなんですけど、彼は興行師なんですね、で、興行師で一旦破産するんですけど、また次の新しいエンターテインメントをつくろうということで、いろんな芸人だったりとか、踊り子だったりを集めて、もう本当に当時、どこにもないような、エンターテインメントの劇場をつくるということを目指していく話になります。で、その過程で踊り子の子と恋に落ちて、でもジャン・ギャバンは恋多き男なんで、いろいろすったもんだがあったりするんですけど、オープンにこぎつけるという話になってます。
有坂:うんうん。
渡辺:で、この映画は先ほどいったヌーヴェル・ヴァーグのひと時代前になるので、完全にセットなんですね。
有坂:セットでつくられた映画だね。
渡辺:だから、パリの街中っていうのが描かれるんですけど、もう完全にセットなんですよね。それはまあ観てわかるんだけど、やっぱりヌーヴェル・ヴァーグの時代の思いっきりロケの生のパリを観てからだと、それは完全につくられた世界ではあるんですけど……。
有坂:「うそでしょ?」っていうぐらいのセット感(笑)。
渡辺:(笑)。でも、やっぱり当時の衣装だったりとか、髪型だったりとか、街の様子だったりとかっていうのは、そのまま再現されているわけなので、そういう意味でのパリというのは描かれてます。それで、1954年の映画なんですけど、舞台となってるのはもっと前ですね。1880年なので、もうちょっと前ですね。だから、服装とかも全然もっとフリフリのなんかね。ヒラヒラのドレスを着たようなマダムがいたりとか、そういうのはひと時代前ではあるんですけど、その時代のファッションだったりとかも楽しめるし、家の中とかも、ほんとにアパルトマンの様子とかも、当時の時代が観られたりして、そういったところも見どころだったりします。あとは、やっぱりショーをやる話なので、歌だったりとか、芸人さんの芸だったりとか、そういうのも面白いし、ほんとにラストのね、カンカン、本当にカンカンの踊りをするところが、ほんとに圧巻なんですよね。
有坂:いやぁ、あれはほんとに……。
渡辺:最後に、この大団円を持ってきて終わるっていうね。そしてムーランルージュが映ってみたいな。
有坂:言っちゃった? 今ラストを(笑)。
渡辺:(笑)
有坂:最後15分ぐらい、もう、なんとかオープンにこぎつけて、いよいよショーが、初日のショーが始まりますっていうところから、ラストまでが15分ぐらいあるんです。
渡辺:まあまあるんだよね。
有坂:いろいろすったもんだあった踊り子たちが、そういうのも全部吹き飛ばして、出てきて、ステージで踊るんですよ。1曲終わって、観ているこっちは終わったかなと思ったら、2曲目が始まって、3曲目始まって、途中からもうそのダンスに熱狂した観客も一緒に踊り始めて。
渡辺:そう、そうなんですよ。
有坂:もうね、画面中に映っている、何十人、何百人の人がみんな踊ってるっていう状況になるんですよ。
渡辺:客席とステージだったのが、その境界線がなくなるんだよね。
有坂:で、そのさっき言ったように、もうバリバリセットをつくって、もうなんだろう、「作り込みました」みたいな世界から、もう画面中の人がみんな踊っていることになると、もうね踊ってる人って、一応役者として演技で踊っているんですけど、やっぱりあれだけ体を動かすと、演技を超えちゃうんですよ。そういうなんか、人間のパワーとかエネルギーがもう画面中に満ちあふれ過ぎちゃう。しかもそれがね、15分続くんだよね。もう途中で幸せすぎて、涙が止まらなくなるんですよ。で、キノ・イグルーで何度か上映したときに、上映後に僕はそのステージで簡単な映画の解説を毎回するんですけど、フレンチ・カンカンが終わった後って、泣いているんですよ。
渡辺:(笑)
有坂:で、この時代の映画ってエンドロールがないんです。終わった瞬間、ステージに出なきゃいけなくて、ほんとにまだね涙が流れているうちに、喋んなきゃいけないけど、やっぱり喋れないから、お客さんにちょっと待ってもらってから喋るっていう。で、これ、みんな大好き西島秀俊さんが、大好きな1本。
渡辺:あ、そうなんだ!
有坂:泣ける映画といったら、迷わず、『フレンチ・カンカン』を挙げるって。ニシジいわく「フレンチ・カンカンが好きじゃない人とは仲良くなれない」らしい。ということで、西島ファンも必見の一本です。
渡辺:それを忘れてたって、どういうことですか(笑)。
有坂:なんだろう、多分、パリの印象があんまりないんだよね。ムーラン・ルージュはそうなんだけど、やっぱり、あのセットで作られたパリの風景はちょっと(笑)。
渡辺:パリじゃなかった?
有坂:パリじゃなかったね。でも、紹介してもらってよかった。もうぜひ観てもらいたい1本です。はい、じゃあ、僕の5本目、ラストは、1973年の映画です。
有坂セレクト5.『ママと娼婦』
監督/ジャン・ユスターシュ,1973年,フランス,220分
渡辺:ああ! ジャン・ユスターシュ。
有坂:はい、これ超マニアックな映画なんですけど、これね3時間40分あります。で、3時間40分もありながら、この映画のストーリーって、男1人、女2人の、これも三角関係の話なんですけど、その関係性が変わって誰かが幸せになるとか、そういう話ではなくて、なんかね、何にももう無気力に生きているジャン=ピエール・レオ演じる男の人が、まあ、いつもカフェに入り浸っていて、そこで知り合った年上の女性と、なぜかまた別な形で知り合った若い看護婦の人と謎の同棲を始めて、無気力にだらだら、だらだら、だらだら、もうああでもない、こうでもないっていう議論を交わして、生活している姿を切り取った3時間40分。
渡辺:(笑)。こんなパッケージなんだね、今。
有坂:そう。しかも、モノクロ映画で16ミリフィルムで撮っているから、なんかもうね、なんだろ、やっぱモノクロだと眠くなるし、淡々とした映画は苦手って人が多いと思うんですけど、そういう人にとっては三重苦みたいな映画なんですけど……
渡辺:(笑)。
有坂:ただこれも、観てもらわないとわかんない。
渡辺:(Filmarksの)スコアめっちゃ高いね。
有坂:これもね、伝説的な傑作って呼ばれている映画なんですけど、そんな内容なのに面白いんですよ。観れちゃうし、何が面白いのかっていうのは、観た人みんなやっぱりね、言葉にするのが難しい。「これがやっぱり映画の面白さなんだな」としか言いようがないようなタイプの作品です。
渡辺:うんうん。
有坂:これは70年代が舞台で、その70年代のカフェ、出てくるのは「カフェ・ド・フロール」とか、「カフェ・ドゥマゴ」とか、もういわゆるフランスのカフェだよね。テラス席もあるようなオープンカフェに、この主演のジャン=ピエール・レオっていうのは毎日入り浸ってるんですよ。で、僕はあの90年代後半に、東京にもカフェブームっていうのが来て、今これだけね、カフェだらけの世の中になりましたけど、それ以前で日本にあんまりカフェがない時ってね。映画の中でフランスのカフェを観るのが本当に好きで、そういう人間にとっては、この『ママと娼婦』っていうのは特別な1本で、ほんとにね、カフェでだらだら過ごしてくれる姿を撮ってくれている。なんか、その後ろに映っている人だったりとか、出てくるそのコーヒーだったり、そのカフェの空気感とか、そういったものが長い時間堪能できる1本として『ママと娼婦』っていうのは、個人的にグッとくる作品でした。
渡辺:うんうんうん。
有坂:カフェ・ド・フロール、カフェ・ドゥマゴっていうところに基本入り浸っているんですけど、たまの贅沢で行くお店がラ・クーポールっていうパリでも有名なところで、そういう形でパリジャンたちは、カフェを使い分けているんだなっていう、カフェ文化みたいなのも理解できて、すごく個人的にはいろいろ学ぶことの多かった作品でもあるんですね。で、僕、パリに行ったときにちょうど上映されていて。
渡辺:へえー!
有坂:パリの劇場で。なんか、リバイバルされていて、観に行ったんですよ。でも、日本で1回観ていたから内容は理解できていたので、フランスだと、日本語字幕は当然ないから、僕はフランス語まったくわからないんですけど、3時間40分体験したいと思って。
渡辺:シネマテークとかじゃなくて?
有坂:シネマテークじゃなくて、どっかの映画館。普通の映画館で、サン=ジェルマン=デ=プレの映画館だったかな。で、観たらなんか全然コメディとかじゃないのに、結構笑うシーンとかがあるんだよ。なんで、笑ったのかいまだにわからないんですけど、僕の中では、その主演のジャン=ピエール・レオっていう人が、もう今はもっとおじさんなんですよ。おじいさんみたいな、あの人がテレビで面白いおじいさんみたいな位置付けに今なっていて……。
渡辺:それ想像で?
渡辺:そう、僕の想像でね、で、その若き頃の姿を見た今のパリジャンたちが、
渡辺:ギャップがあって面白いみたいな?
有坂:いや、「今と一緒じゃん!」みたいな。じゃないかと思っています。
渡辺:(笑)
有坂:でも、なんか、そうやって楽しみ方が、日本人とフランス人で全然違うんだなっていうのも、体験してよかったし、もう僕はその映画を観た後、カフェ・ドゥマゴとかに行こうと、もう、その映画の余韻の中でコーヒーを飲むのがすごい楽しくて、それもセットで楽しめたという意味でも、特別な一本です。
渡辺:なるほどね、でも、パリに行ったらカフェ・ドゥマゴとか行くもんね。
有坂:行くよね。
渡辺:カフェ・ド・フロールとかね。
有坂:そうそう、もうマストだよね。
渡辺:行ったな俺も。
有坂:ちなみに、最後に『ママと娼婦』っていう不思議なタイトルなんですけど、これは、「男にとって必要なのは恋人でも愛人でもなく、母親と娼婦である」とよく言われているそうです。で、その言葉をそのまま映画化したと言われています。
渡辺:ふーん、なるほど。
有坂:そんな3時間40分のモノクロ映画を、最後5本目に紹介しました。
渡辺:なんかね、今ちょっと聞いていて思い出したのが、その、キノ・イグルー前夜、キノ・イグルーをまだ僕らが結成する前に、実はそういうカフェに入り浸っていたっていうのがあって、それが今は無き原宿のオーバカナル(AUX BACCHANALES)って。今は銀座とか……
有坂:原宿でも再オープンしたよ。
渡辺:ええ! そうなの?
有坂:駅直結で。
渡辺:いつ?
有坂:2年前ぐらい。
渡辺:そうなんだ、あったっけ? 原宿の今でいうと竹下通り抜けて、ユニバーサルミュージックのすごい今おっきいビルが立ってるんですけど、そこがオーバカナルだったんですよね。で、オーバカナルっていうのは、もうフランスカフェでね。
有坂:店員さんも「ドゥ・キャフェ・シルヴプレ」とかフランス語で言っててね。
渡辺:そう、しかも、ほら、キャッシュオンだったじゃん。まとめて後でお会計とかじゃなくて、もう都度会計なんですよ、店員さんに。っていうスタイルとか、通りに向かって椅子が向いているとか、そのスタイルとかもね、ほんと忠実にパリ仕様というか。当時はすごい珍しかったんですけど。
有坂:席数がすごい多いから、なんか何時間いても罪悪感がないんだよね。ほんとコーヒー一杯で粘っている人とかもいるし、普通になんかあれだよね、キョンキョンがいたり、芸能人とかも、もう別に変装するわけでもなく、普通にいられるようなオープンな空気があって、そうだね、だから20年前ぐらいだね。
渡辺:そうそう。それでなんかこう映画の話をする流れで盛り上がって。
有坂:どんだけ憧れているんだよ! 恥ずかしい限りですよ(笑)。
渡辺:(笑)。そう、それをちょっと思い出しました。
有坂:そうなんですよ、なのでそのね、今はなき、そういったカフェ文化とかを知れる。やっぱりフランス映画って、基本的にファンタジーとかあんまりなくて、日常ベースのものが多いじゃん。なので、やっぱりその時代、時代のライフスタイルとか、生活習慣とかがなんかすごく垣間見られるのも面白いところかなと思うので、ぜひ掘り下げて、気になる時代のフランス映画を観るっていうのも面白いかなと思いますね。
渡辺:今日だけでも、また10本出たんで、ちょっと気になったものはぜひチェックしてもらえると嬉しいです。
──
有坂:終わっちゃったね。念願のパリ企画ね。なんか話しておきたいことある、パリについて?
渡辺:パリ、えっとなんだろう。でもなんか、僕もパリ行ったときに、結構やっぱり映画館が残っているなってのはすごいありました。結構、他の国とか行っても、わりとシネコンみたいなのしかなかったりとか、かかっている映画もハリウッド映画ばっかりだったりっていう国がすごい多い中で、わりとパリは、ちゃんと老舗の映画館みたいのが残っていて、普通に現地の映画をやってるイメージがありましたね。
有坂:そう、あのなんか、僕、人生で尊敬する人誰って言われたら、間違いなく一人上がってくるのが、フランスにある「シネマテーク・フランセーズ」っていうのがあるんです。国立の映画機関なんですけどで、そのシネマテークっていうのを立ち上げた人が、アンリ・ラングロワっていう変人で、その人はなんか映画を観るだけじゃなくて、当時だとフィルムを集める。個人的に集めるのも趣味で、で、だんだん映画の衣装とかいろんな脚本とか、そういうものを集めたくてしょうがないみたいな、ほんと手に負えないコレクターだったんですよ。で、自分のフィルムを使って上映するための小さい場所を借りて始めたのがシネマテークってところで、それがどんどん当時だとアメリカ映画とかが、パリでは全然観られない時に、でもラングロワが持っているフィルムでしかアメリカ映画が観られないとかで、どんどん、さっき紹介したゴダールとか、そういうまだ映画監督になる前の10代の彼らが、そのラングロワが上映してくれるアメリカ映画とかにどんどん影響を受けて、で、「今までとは違うフランス映画つくろうぜ」って、ヌーヴェル・ヴァーグっていう運動が起こったんです。
渡辺:うんうん。
有坂:なので、映画をつくらなくても、これだけ多くの人に影響を与えられる人がいるんだなってのが、結構衝撃的で。で、その人って、第2次世界大戦でパリが大変だったときに、ナチスが「フィルムを燃やせ」って言ってたんだね。だけど、それは遺産ですよね。もう例えば、チャップリンとかいろんな——まあチャップリンは現役でしたけど——映画が誕生して50年ぐらいのときに、今までのフィルムを全部燃やしちゃったら、後世に語り継げなくなっちゃう。「そんなことさせるか!」って言って、仲間と一緒に、ほんとにもう命懸けで地下にフィルムを隠して、なんとかそのフィルムを守り抜いた人なんですよ。そのおかげで観られている映画っていうのが、実はいっぱいある。で、後にチャップリンとかもほんとに、「ラングロワ、フィルムを守ってくれてありがとう」っていうことで、なんかすごい声明を出したとか。そういう熱い人がフランスにはいて、その人がアンリ・ラングロワという人です。
渡辺:昔、フィルムって消費するものだったんですよね。だから、映画館でも上映し終わったら捨てちゃっていたんですよね。
有坂:劣化しちゃうからね。
渡辺:そう、ジャンクしてたんですけど、あんまりその保存するっていう概念がなかったんですよね。でも、ラングロワはね、もう狂人的なコレクターだったから、もうその彼の思考と実際、フィルムを守るっていうことが、またまたま一致してたというか。で、そこからシネマテークとかが生まれたり、日本の今、国立アーカイブとか、そういうフィルムを保存して後世に残そうっていうのが、国立の機関として今、全世界にあるきっかけをつくったのがこのラングロワっていうね。実は、すごい人なんですよね。
有坂:すごい人なんですけど、なんかもういろんな本を読むにつけ、絶対に近くにいてほしくないなって(笑)。
渡辺:(笑)。友達にはなれないタイプだよね、多分ね。
有坂:だから、でも、そういうの見ると、例えば、自分の周りにそういう人がいても、自分の感覚が追いついていないだけで、歴史に残る人かもって思えるようになったから、そういった意味でもね。マーク・ザッカーバーグとかも、そうだもんね。
渡辺:ああ、そうだね。
有坂:大体変人だよね。まあ、そういうちょっと変人なんですけど、映画史に貢献した人もいますので。ちょっとすいません、マニアックな話になりましたが、よかったら調べてみてください。
渡辺:はい。あっという間でしたね。
──
有坂:はい、それで、この月刊手紙舎のキノ・イグルーの「ニューシネマ・ワンダーランド」は、毎回、いろんな都市を舞台にお送りしてきましたが、来月からちょっとテーマを変えて再スタートしたいと思います。
渡辺:ちょうど1周したということですね。
有坂:そうだね。その最後に、思い出深いパリを紹介したということです。ちょっとテーマの内容については、また改めてお知らせしたいなと思います。内容は、このドラフト会議形式で今後もやっていきたいと思いますので、ぜひ今後もお付き合いのほど、よろしくお願いします。はい、では、今月のキノ・イグルーの「ニューシネマ・ワンダーランド」はこれにて終了です。みなさん、遅い時間まで、どうもありがとうございました。おやすみなさい!
渡辺:おやすみなさい!!
──

選者:キノ・イグルー(Kino Iglu)
体験としての映画の楽しさを伝え続けている、有坂塁さんと渡辺順也さんによるユニット。東京を拠点に、もみじ市での「テントえいがかん」をはじめ全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館など様々な空間で、世界各国の映画を上映。その活動で、新しい“映画”と“人”との出会いを量産中。
Instagram
キノ・イグルーイベント(@kinoiglu2003)
有坂 塁(@kinoiglu)/渡辺順也(@kinoiglu_junyawatanabe)

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店