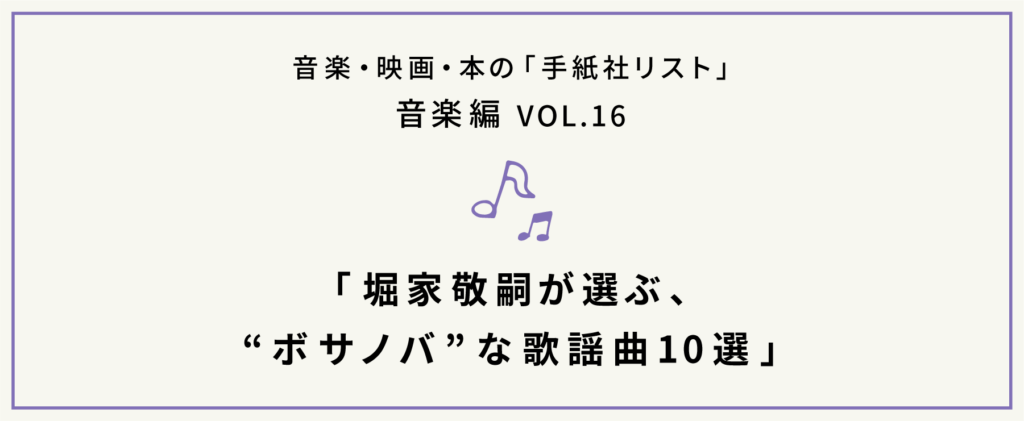
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。16回目となる音楽編のテーマは、ボサノバ。ボサノバの風が我が国の歌謡曲の歴史の中で、いつ、どのように吹いたのか? え? あの曲もボサノバの影響を受けていたなんて!
塩の! 太陽の! 南の! 歌謡曲の!
サンバ
ブラジルの西欧化は、1500年にポルトガルからの探検隊が上陸したことに端を発しています。そののち、この地に眠る資源を見込んで独占的な開発を狙う当時の国王の使命により、ブラジルには多くのポルトガル人や彼らが隷属させたアフロ系の人民が入植することになります。そしてこのときに、西欧式の文化に加え、アフリカ起源の文化もともに移植されたわけです。
こうした時代に人びとの精神を、その生活を律していたもの、それは、いうまでもなく信仰であり、ブラジルの地は、彼ら彼女らの信仰に深く根づいた祭祀の歓声や音楽が響くところとなります。そのうえ、ポルトガルを含むイベリア半島はヨーロッパ大陸でもっとも南西端に位置し、アフリカ大陸ときわめて接近していることから、かつてポルトガル側がアフリカ側に隷属していた時期もあるなど、相互的な影響関係のなかで他方の文化に対する寛容さの度合いも大きく、多様性が損なわれることがないまま、入植者たちの混合にともなって彼ら彼女らの文化も融合していきました(*1)。
そうしたなか、19世紀末には奴隷制度が廃止され、自由を獲得したアフロ系の住民たちは、職を求めて当時の首都だったリオ・デ・ジャネイロに集住する傾向にありました。このような共同体において、まずはダンスやパーティーのことを意味する言葉としてサンバが発生したものと指摘されています(*2)。やがて、こういったパーティーに出入りする楽器演奏者たちが、その都度セッションのかたちで奏で、醸成されていった音楽のありかたこそが、いま私たちにも親しい近代的なサンバであり、バイアーノが登記した〈Pelo Telefone〉(1916)がその嚆矢とされます(*3)。
サンバにとって音楽と踊りとが不可分であるのみならず、西方教会の文化圏でみられた謝肉祭がブラジルで独自に発展したカルナヴァルのパレードともまた密着しているのは、こうした理由によります(*4)。
ところで、これとほとんど同じころの北米大陸では、やはり奴隷として連行されてきたアフロ系の人民の音楽が、支配層のものだった西欧の音楽体系との接触により新しい大衆音楽のうねりを起こしつつありました。ジャズがそれです。ジャズの興隆は、音声の保存と再生を旨とする蓄音機や、音声の拡散と配信を旨とする無線放送といった、いわゆる音声メディアの技術革新とも歩調をあわせ、さらには、まさしく『ジャズ・シンガー』(1927)の名のもとに映画が有声化された事実にも背中を押されて、瞬くうちに世界中で共有されるところとなります。
ブラジルも例外ではありませんでした(*5)。サンバの演奏家たちをも魅了したジャズは、サンバのありようを少しずつ変容させていきます。とりわけジャズ式の歌曲の影響は、サンバ本来の強烈なリズムを和らげ、華麗なメロディや複雑なハーモニーを重視する風潮を導き、ディック・ファルネイによる〈Copacabana〉(1946)に代表されるサンバ・カンサォンへと結実します(*6)。
仮にこれが、サンバにジャズの要素を反映させた楽曲であるとすれば、のちに〈Rapaz de Bem〉(1961)を発表するジョニー・アルフなどはむしろ、ジャズにサンバの要素を反映させた演奏家であるかもしれません。
こうした先達の試行を追いながら、けれどそれらとは決定的に異なる新しさをもってサンバから派生した分節、それこそがボッサ・ノーヴァです。
ボッサ・ノーヴァ
ポルトガル語で[bossa]とは“瘤”や“傾向”、“素質”や“特性”を意味します。[nova]は“新しい”の謂であり、当初はこれらの語は、単にサンバの新しい潮流の指標として、ある学生グループのための演奏会における配布物に印刷され、また看板にチョーク書きされた小文字の惹句にすぎませんでした。ただしここでナラ・レオンははじめてマイクロフォンの前に立ち、カルリーニョス・リラがジョニー・アルフの〈Rapaz de Bem〉を披露して喝采を浴びたといいます(*7)。1958年のことです。
そこで小文字のまま綴られた、いわばある兆候としての[bossa nova]が、まぎれもないひとつの確定的な音楽表現としての[Bossa Nova]となるためには、アントニオ・カルロス・ジョビンとジョアン・ジルベルトが必要でした。
ジョビンがニュウトン・メンドンサと共作し、ジルベルトが歌唱した〈Desafinado〉(1958)の歌詞には、「bossa nova」の語句が登場します。なるほど、ここでもやはり、それらは小文字で綴りはじめられています。しかしながら、もはや問題は言葉ではありません。
これに先んじて、ジョビンが作曲した〈Chega de Saudade〉(1958)をめぐって、エリゼッチ・カルドーゾの録音のためにジルベルトが披露したヴィオラォン、すなわちギターの演奏こそが、ブラジルのみならず世界の大衆音楽の歴史を画し、この新しいサンバの潮流を小文字から大文字のそれへと、つまるところサンバの現代的な変奏をボッサ・ノーヴァへと飛躍させる大きな、けれど静かな律動となったのです。
ほどなく自らの歌声でもこの楽曲を吹き込むことになるジルベルトが、ヴィオラォンを抱えてこのとき披露した奏法は、のちに“バチーダ”と呼ばれるものです。従来のサンバでは複数の打楽器に配分されていたリズムを単純化したうえで、ヴィオラォンの低音弦側と高音弦側とに分担させて置換し、かわりにジャズにも通じるテンション音を多用した複雑なハーモニーを響かせることで、サンバの新しい次元を開闢してみせたのです(*8)。
加えて、あらためて彼の歌唱をもって発表された〈Chega de Saudade〉にあっては、自演するヴィオラォンのこうした斬新な奏法に合致し、それと溶解して一体となるような歌唱法をもジルベルトは提示しました。それは、豊富な声量と明瞭な発音に頼んで感情の機微を朗々と誇張し、その大袈裟な抑揚を感動的に歌いあげる仰々しくも重厚な歌唱ではなく、囁くように、語りかけるように穏やかに聴き手を包み込むべく、口腔よりもむしろ鼻腔を活かした発声によるものでした(*9)。
その意味において、慎ましくも抑制的な彼の歌唱は、旧来のサンバに期待された高揚や熱狂とは反対に、寛いだ、軽妙な、けれど冷めた理智性を印象づけることになります。そこでは音節のひとつずつがその都度ヴィオラォンの刻む諸弦の振動と調和して融合しながら、和音の響きを更新していきます。ヴィオラォンの演奏を自身の歌唱の相伴とするのではなく、これらが不可分のひとつの音響的な持続へと生成すること(*10)。そのためにこそ、ジルベルトは、声と音の発信を厳密に管理する修錬を蓄積してきたわけです(*11)。
その場にいあわせた誰もが思わず身体を揺さぶられ、踊りださずにはいられないようなサンバの強烈なリズムは、いわば扇情的な、もしくは煽動的な強迫でもありえます。サンバとは、要するにダンスのための音楽なのです。
ところで、ボッサ・ノーヴァは、まさしく研ぎ澄まされた耳をもって聴くための音楽として、憂鬱な知性に訴えかけます。当初から聴衆となった学生など有閑階級をはじめ、ブルジョワ層を中心に支持は相応に拡大していったものの、それでもなおボッサ・ノーヴァがブラジルの国民に全面的に支援されたわけではなかったとすれば、おそらくそれは、こうした観点と無縁ではないはずです。
ジャズへの還流
ジャズもまた、[swing]の語が的確に象るように、やはりダンスのための音楽として成熟していくなか、これに飽かない演奏者たちが互いの奔放な表現を味わいあう即興により音楽を自律させます。チャーリー・パーカーの〈Cool Blues〉(1947)にみられるそうした複雑さの緊張感に対して、今度は音数や楽曲の展開を抑制的に扱い洗練すべく、たとえばマイルス・デイヴィスが試行した1950年前後の音源などはのちに《Birth of the Cool》(1957)としてまとめられ、いまそれとして確認できるところです(*12)。ほどなくソニー・クラークの《Cool Struttin’》(1958)も発表されています。
このようにジャズの熱狂が次第に冷却の時代を迎えていったことも素地となって、大物の歌い手であるサラ・ヴォーンやナット・キング・コール、サミー・デイヴィスJr.らがブラジルを訪問し、現地で真正のボッサ・ノーヴァと接触しています(*13)。
さらにはジョビンが音楽に関与した映画作品『黒いオルフェ』(1959)によるアカデミー賞外国語映画賞の獲得も寄与し、ついにジャズの本場にまでボッサ・ノーヴァの響きは遡上します。事実、ルイス・ボンファが作曲したその主題歌〈Manhã de Carnaval〉は、たとえばデクスター・ゴードンが《Gettin’ Around》(1966)で演奏するなど、すでにジャズの標準曲となっています。
ブラジルの地にこの新しい潮流の探究に赴いたハービー・マンは、《Brazil, Bossa Nova & Blues》(1962)につづく《Do the Bossa Nova with Herbie Mann》(1962)ではジョビンとセルジオ・メンデスを迎え、クインシー・ジョーンズも《Big Band Bossa Nova》(1962)を録音しています。
しかしながら、ボッサ・ノーヴァの世界的な敷衍にもっとも貢献しただろう要因、それは、ブラジルでその魅力に囚われたチャーリー・バードとともに《Jazz Samba》(1962)に〈Desafinado〉や〈Samba de Uma Nota Só〉を収録したスタン・ゲッツが、ついにアントニオ・カルロス・ジョビンとジョアン・ジルベルトを招いて《Getz/Gilberto》(1963)を制作したことでしょう(*14)。
実際に、ここでジョアン・ジルベルトの妻だったアストラッドが歌唱を披瀝したジョビンの作曲による〈The Girl from Ipanema〉は、1990年のある調査では音楽の歴史において5番目に多く演奏された楽曲だと評価され、さらにこれ以外の楽曲をも含めた場合には、ジョビンの音楽は、ザ・ビートルズの作品群に次ぐ頻度で演奏されたものと位置づけられています(*15)。
やがてジョビンは、フランク・シナトラに請われて《Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim》(1967)で協働するまでに至ります。いまやボッサ・ノーヴァは、その源泉のひとつであるジャズへと還流し、そのありようを変容させうるひとつの力能となったのです。
こうした時期にアメリカのバークリー音楽学校に留学中だった渡辺貞夫は、当代のジャズの最先端でボッサ・ノーヴァを知る機会を持った日本人で最初の演奏家のひとりです。ゲイリー・マクファーランドが、公表してほどない《Soft Samba》(1965)のための全米ツアーに向けて結成したバンドに、渡辺は学生の身分のまま参加しています(*16)。
これが移民局に咎められるところとなり、ひとまず日本に帰国した彼の1966年以降の活躍のなかで、現地のジャズの息吹きとともにボッサ・ノーヴァをも積極的に演目に採用したことは、その日本での流通にきわめて肯定的に与しました(*17)。
日本上陸
なるほど、“翻訳ポップス”の最盛期だったころには、アメリカにおける大衆音楽の流行にいかにも敏く、すでに藤木孝の歌唱による〈ボサ・ノバでキッス〉(1962)が発売されています。これはポール・アンカの〈Eso beso〉(1962) のカヴァー盤であり、梓みちよも〈ボッサ・ノバでキッス〉(1963) として競作しています。彼女はまた、バリー・マンが作曲したイーディ・ゴーメの〈Blame It on the Bossa Nova〉(1963)をも、〈恋はボッサノバ〉(1963)と謳ってカヴァーします。金井克子が歌唱した〈恋はボサノバ〉(1963)はその競作です。
ジョー・ハーネルがボッサ・ノーヴァ調のインストゥルメンタル曲へと編成したことにより大ヒットした〈Fly Me to the Moon〉(1962)なども、中尾ミエが〈月夜にボサノバ〉(1963)の邦題のもと日本語で披露していますが、“和製ポップス”としては、狛林正一が作曲した小林旭の〈アキラでボサ・ノバ娘〉(1963)や鈴木庸一が作曲した谷ヒデコの〈東京ボッサノバ娘〉(1963)あたりが、ボッサ・ノーヴァに便乗したほぼ最初の事例かもしれません。
それでもなお、歌謡曲へのその本格的な導入は、やはり《Jazz & Bossa》(1966)や《Bossa Nova ’67》(1967) の渡辺貞夫に依拠する部分が多大です。 ユキとヒデが歌唱した〈白い波〉と〈長い夜〉、〈スノードルフィンサンバ〉と〈恋のスノー・ドルフィン〉のいずれも、渡辺が作曲に加え編曲まで施し、1967年に発表されています。〈ストリート・サンバ〉(1968) を泉田エミイに融通したのも彼でした。このシングル盤の片面に収録された〈キューピッヅ・ソング〉は、泉田による〈恋のスノー・ドルフィン〉のカヴァーです。
これらでは渡辺貞夫が自身のバンドを率いて演奏も担当していますが、サキソフォンよりはむしろ彼のフルートが活躍することが、のちに歌謡曲がボッサ・ノーヴァを援用するにあたって踏襲するひとつの雛型となったように思われます。
戦後ほどなく灰田勝彦の楽団に所属するなど、戦前からジャズやハワイアンといった洋楽に造詣が深く、またマンボを中心に演奏するアフロクバーノでは自らの歌唱をもって紅白歌合戦にも出場した浜口庫之助は、ボッサ・ノーヴァの理解をめぐって相応に本格的な作品を遺しています。
沢田駿吾のバンドを借りて吹き込まれた《DRIVING BOSSA NOVA》(1967)では、浜口本人が伊集加代子とユニゾンで口遊むスキャットを〈DRIVING LOVE〉に聴くことができます。渡辺貞夫の公演にも参加したクラウディア・ラロの歌声を採用し、ポルトガル語の響きを日本語に併置させた〈恋のカローラ〉(1968)は、その片面となる〈はだしのボサノバ〉とともに、ラテン音楽を歌謡曲になじませた彼の面目躍如といったところです。
ただし、ポール聖名子に提供した〈雨のピエロ〉(1961)を自身で歌唱した《MY SONG, MY VOICE》(1967)の音源は、原曲を著しく逸脱し、石原裕次郎の〈粋な別れ〉(1967)や守屋浩の〈月のエレジー〉(1961)などを含めボッサ・ノーヴァ調に変換されているとはいえ、すでに歌謡曲へと回収されつつあります。
ところで、ユキとヒデの解散後の出門英があらためて結成したヒデとロザンナでは、いったんボッサ・ノーヴァから遊離したものの、筒美京平の作曲による〈真夜中のボサ・ノバ〉(1969) で出門は再びボッサ・ノーヴァ調の音楽へと回帰します(*18)。
“ボサノバ”
筒美のこの楽曲は、渡辺貞夫が日本の大衆音楽に与した場合とは異なり、たとえば映画の主題歌として広く知られるフランシス・レイの〈Un Homme et une Femme〉(1966)などを経由した、いわば欧化されたボッサ・ノーヴァらしさの芳香を巧みに纏った歌謡曲であり、彼のそうした姿勢こそが歌謡曲の真髄であることは疑うべくもありません。事実、のちに〈初夏の香り〉(1975)を発表する久保田麻琴もまた、フランス映画を介したボッサ・ノーヴァの禍々しい妖しさに魅了されたといいます(*19)。
“翻訳ポップス”の女王だった弘田三枝子に筒美京平が提供した楽曲は傑作ぞろいです(*20)。これらのうち、「BLUE BOSSA NOVA」の英題を掲げる〈悲しみの足音〉(1967) は、彼がボッサ・ノーヴァを歌謡曲へと換骨奪胎しつつある過程のものでしょう。《BLUE LIGHT YOKOHAMA》(1969)に収録されたいしだあゆみの〈ひとりにしてね〉(1969) は、彼女の歌唱が筒美の楽曲を実際以上にボッサ・ノーヴァ的に奏でています。大橋巨泉に供与された〈こりゃまたみなさん百面相〉(1969) ですでにこれを自家薬籠中のものとしている筒美は、藤巻潤の歌唱に委ねられた〈ストックホルムの白い夜〉(1970)にあっては、その“ボサノバ”で「白夜」の「北のはて」を謳っています。
[bossa nova]が日本に着岸し、“ボサノバ”となって歌謡曲に投錨したのは、おそらくこのころのことです。
とはいえ、出門英から離れてアン真理子と改名したユキの〈悲しみは駆け足でやってくる〉(1969) や〈太陽は知らない〉(1970) に限らず、筒美京平の才覚に依拠しない歌謡曲がさしあたって試みるボッサ・ノーヴァの響きは、やはりいかにも貧しいものです。
https://www.youtube.com/watch?v=H-xSCy58oho
森田公一が在籍していた原トシハルとBアンドB7による〈二人で踊ろう〉(1967)では、ボッサ・ノーヴァに“ムード歌謡”と“グループ・サウンズ”の風味が施され、むしろ歌謡曲の手管を感じさせます。キリンジの〈嫉妬〉(2003)の着想源は、ことによるとこの近辺なのかもしれません。それでもやはり、水戸浩二が歌唱した〈涙のボサノバ〉(1968)ともなれば、もはや歌詞の言葉以外のどこにも「ボサノバ」を聴取することはおよそ不可能です。
中村泰士の作曲による天地八重の〈恋はジリジリ〉(1968)も、イントロから丁寧に構築してきたボッサ・ノーヴァ調を、サビへの突入にあたってにわかに放棄してしまいます。古谷充とザ・フレッシュメンの〈夜は流れる〉(1969)に至っては、そのジャケットに「ボサノバ歌謡の決定盤!」の文句が踊っています。
ヴィブラフォンやフルートの旋律がほどよく歌謡曲にボッサ・ノーヴァをつなぐ山内賢の〈君のサンバ〉(1970)のほか、すぎやまこういちがルートNO.1に提供した〈大学ノート・サンバ〉(1970)あたりは、ボッサ・ノーヴァがサンバの支流として発生した経緯を相応にうかがわせますが、橘モナの〈涙のサンバ〉(1973)には、ボッサ・ノーヴァはおろかサンバの律動さえ認めることは困難です。
サンバの名のもとにボッサ・ノーヴァを援用した楽曲としては、森山良子とズー・ニー・ヴーの競作となった〈雨あがりのサンバ〉(1968)がすでにありました。
しかしながら、寺尾聰の《二人の風船》(1970)に収録された〈風もない午後のサンバ〉を含めて、こうした傾向は、なんといっても森山と同じレーベルから長谷川きよしが発表した自作曲〈別れのサンバ〉(1969)のヒットを踏まえてのものでしょう。そのシングル盤のジャケットで「ソウル・フォーク・シンガー」とも形容された彼がサンバの名のもとにボッサ・ノーヴァを歌うとき、歌謡曲はそれらの可能なジャンルすべてを包摂する寛容な音楽として、これを“ボサノバ”とみなすのです。
この〈別れのサンバ〉を編曲したのは、森山の盤において〈雨あがりのサンバ〉の作曲と編曲を担当していた村井邦彦でした(*21)。
偏西風
村井邦彦が関与した“ボサノバ”には、ブラジルから東廻りの航路で大西洋を渡り、ユーラシア大陸に漂着したボッサ・ノーヴァが、フランスの映画音楽による洗練のフィルターをもって雑味を濾され、そこから抽出された上澄みの潔さを聴くことができます。
笠井紀美子に提供された〈たゞそれだけのこと〉(1968)は、川口まことに編曲を任せたこともあってか、どれほどか旧来の歌謡曲の湿気に侵蝕されています(*22)。笠井の歌唱も、ここでは逆に歌謡曲の側に加担しているように思われます。ところが、久美かおりの〈髪がゆれている〉(1969)にあっては、その歌声と男声との主旋律の共有、とりわけスキャットでなぞられるそれなどに、のちの村井邦彦におけるボッサ・ノーヴァの扱いかた、いわばその“ボサノバ”の方向性が示唆されるところとなります。
神谷重徳が編曲したザ・ハーフ・ブリードの〈白い風を見る日〉(1970)や渋谷毅が編曲した荻野達也とバニーズの〈金色のほほ〉(1970)は、これを“グループ・サウンズ”末期の迷走状態を突破するための糸口とみなしています。東海林修の編曲が歌謡曲に浸透するボッサ・ノーヴァの按配をきわめて適切に処遇している団次郎の〈霧の中の孤独〉(1970)の場合にさえ、そうした機運は認められます。
村井邦彦の“ボサノバ”は、トワ・エ・モアのデビュー曲となる〈或る日突然〉(1969)であれ、「ニュー・フォーク」の名義を借りた小谷充による編曲のなかにも反映されるものです。やがてそれは、安井かずみが自ら発表した唯一の音盤である《ZUZU》(1970)のために書きおろされ、クニ河内が編曲を施した〈わるいくせ〉を経由し、荒井由実の登場を待ってHI-FI SETに提供された〈スカイレストラン〉(1975)へと結実します(*23)。
なお、このころアルファミュージックを設立した彼は、東京とパリを頻繁に往来するなか、ルイス・ブニュエルが監督した『哀しみのトリスターナ』(1970)の音楽をクロード・デュラン名義で担当してもいます(*24)。
したがって、彼の試行が予感させた“ボサノバ”のありようとは、日本の大衆音楽の土着的な泥濘に抵抗し、歌謡曲がその束縛から浮揚する余地をわずかながら担保するような、記号的に消化ないし消費されたひとつの様式です。洋風にして洒脱な、それゆえある種の空疎で冷めた雰囲気をも脚色するそれは、虚構としての都市空間を音響のうちに表現しはじめます。
こうした風潮は、彼のほか、たとえば《浅丘ルリ子のすべて 心の裏窓》(1969)に収録された〈シャム猫を抱いて〉の三木たかしや、津川順の歌唱による〈私、夢を見るの〉(1970)の津田義彦、ジュリアンズとして〈目の中の海〉(1970)を吹き込んだ都倉俊一らにも共有されたにちがいありません。なお、ここでの津田や都倉の楽曲には、馬飼野俊一が編曲者として参加しています。
村井邦彦や安井かずみが出入りするサロンだった川添浩史のレストラン『キャンティ』には、その当時、彼らをはじめ多くの文化人や芸能関係者が常連として集っていました。ザ・スパイダースのかまやつひろしもそのひとりです。
必要な楽器を彼ひとりで演奏して自宅録音された《MONSIEUR》(1970)に所収の〈二十才の頃〉では、やはりその常連だったなかにし礼が安井と連名で作詞に参加しているのみならず、彼らの危うくも親密な歌声がかまやつ本人の歌唱に朴訥な花を添えます(*25)。彼らが顔をそろえた現場でほとんど即興的に作られたらしいこの楽曲には、「ショパン」やフランス象徴派の詩人たちの名前が引用されますが、ブラジル文化への言及は微塵もありません。
なかにし礼とかまやつひろしとの共作に前田憲男が編曲を施したペドロ&カプリシャスの〈夜のカーニバル〉(1971)は、まさに「カーニバル」そのものを題材としています。ここで細かく刻まれる「リズムにあわせて」大胆に採用されたフルートは、「今宵はお祭り 町中が」の表現のかたわらにあっては文字どおり祭囃子で神輿を煽る篠笛のように響きます。
α都市の憂鬱
そうした『キャンティ』の人脈のなかで培われた村井邦彦の、いかにも華麗で多彩なその履歴のすべてを考慮したとしても、なお日本の大衆音楽における彼の最大の貢献といえば、荒井由実を歌い手としてデビューさせたことに尽きるでしょう(*26)。
ザ・タイガースを脱退した加橋かつみの《1971 花》(1971)に数曲を書いた村井邦彦は、その録音に臨席した際に、そこに提供された荒井の作曲作品〈愛は突然に…〉を聴かされます。この調整室において、まず村井は、まだ高校生だった当時の荒井由実を、はじめてアルファミュージックが専属契約する詞曲の作家として勧誘しています(*27)。
単なる作家に甘んじることなく、ついにかまやつ・ひろしの音楽プロデュースにより〈返事はいらない〉(1972)でデビューした彼女は、今度は細野晴臣による音楽プロデュースのもと、キャラメル・ママの演奏を配して《HIKŌ-KI GUMO》(1973)を発表します。細野ら演奏陣とのやりとりにおいて楽曲のかたちを定め、精錬していく制作の仕方を村井が採択するなか、〈曇り空〉の収録にあたり荒井が参照したのがセルジオ・メンデス&ブラジル’66でした(*28)。ここで聴くことのできる男声は松任谷正隆のものです。
トワ・エ・モアが旭化成のために歌唱した村井邦彦によるCMソングを〈愛を育てる〉(1973)として採用したNOVOの横倉裕は、この年に〈白い森〉と〈この星の上で〉を公表したのち渡米し、やがて村井のアルファレコードからはYUTAKAの名義で《LOVE LIGHT》(1978)が発売されます。セルジオ・メンデスのもとカルロス・“ユタカ”・デル・ロザリオとして演奏を補助するなど、いまなお彼の活動はつづきます。
すでに“ボサノバ”へと昇華していた荒井由実の〈魔法の鏡〉(1974)の調子は、のちに早乙女愛の歌唱で実現する竜崎孝路の編曲による1976年の音盤にあっては、きわめて良質な歌謡曲へと還元されています。『キャンティ』界隈の知己である小林麻美に松任谷由実として提供した〈移りゆく心〉(1987)でも、後藤次利の編曲の彼方に“ボサノバ”が奏でられています。
いずれにしても、荒井由実の“ボサノバ”をなにより強く印象づけた楽曲、それこそは、〈あの日にかえりたい〉(1975)にほかなりません。女性が短調の響きをもって「暮れかかる都会の空」の憂鬱と哀愁を謳うここに、いわば都市式の“ボサノバ”の鋳型が成立します。事実、ほどなくヒットした丸山圭子の〈どうぞこのまま〉(1976)について、その影響を指摘することはいかにも容易です。
〈あの日にかえりたい〉の前奏でスキャットを披露した山本潤子のことは、村井邦彦との最初の遭遇の段階で紹介されていたといいます(*29)。かねてより村井が積極的に支援してきた赤い鳥を解散した山本が、細野晴臣による命名のもと、その元メンバーの一部と結成したHI-FI SETは、荒井が詞曲を担当した〈卒業写真〉(1975)を発売します。同様に荒井由実からの提供曲である〈冷たい雨〉(1976)などにも、稀薄ではあれ“ボサノバ”の律動は感じられます。
本来は〈あの日にかえりたい〉の旋律のために荒井が書いた歌詞が村井邦彦の作曲に委ねられた〈スカイレストラン〉(1975)が、“ボサノバ”の体裁をもってこの時期の東京のありようを音響的に象った真正の傑作であることに疑いはないでしょう(*30)。事実、発売からほどなくビルボードの週間チャートで1位を獲得したJ.コールの《2014 Forest Hills Drive》(2014)では、〈January 28th〉がこの楽曲をサンプリングしています。
しかし、これが滝沢洋一の作曲である〈メモランダム〉(1977)ともなれば、どれほどか様式に依存しすぎているきらいがあるかもしれません。
CIRCUSが歌唱した〈Mr.サマータイム〉(1978)もアルファレコードから発売されています。フランスの新しいシャンソンに竜真知子が訳詞をあてがい、前田憲男が“ボサノバ”に編曲したこの楽曲も、〈スカイレストラン〉の延長線上にあります。
風都市の幻影
荒井由実の才能をその演奏をもって開花させたキャラメル・ママは、はっぴいえんどの解散を受けて細野晴臣が鈴木茂を誘い、ここに松任谷正隆と林立夫が加わった演奏家集団です。《キャラメル ママ》(1975)を発表するまでにTin pan alleyへと改名した彼らは、鈴木茂が作曲した〈ソバカスのある少女〉を“ボサノバ”の体裁のもとこのアルバムに吹き込んでいます。やはりはっぴいえんどのメンバーだった松本隆が作詞したこの楽曲では、彼がデビュー盤《摩天楼のヒロイン》(1973)をプロデュースした南佳孝が客演し、鈴木と並んでその歌声を響かせます。
彼らの演奏を中心としつつも松任谷正隆を欠く体裁で、歌唱にいしだあゆみを招聘して制作された《Our Connection》(1977)は、収録曲の半分を細野晴臣が、もう半分を萩田光雄が作曲しています。ここで萩田が担当したうち〈六本木ララバイ〉と〈バレンタイン・デー〉、そして〈黄昏どき〉は、かつて筒美京平が彼女に提供した〈ひとりにしてね〉を思わせる“ボサノバ”です。実際に、〈六本木ララバイ〉の旋律については、萩田も自ら筒美の影響に言及しています(*31)。
こうしたTin pan alleyにおける活動の一方で、単独でもアルバム制作をつづけ、その声質によって制約を被る自身の歌唱との親和性をいずれボッサ・ノーヴァに見出したすえに、彼なりの“ボサノバ”をもってその音楽観光の集大成とする《HoSoNoVa》(2011)の細野晴臣が、まずは《TROPICAL DANDY》(1975)の完成に漕ぎ着けるためには、久保田麻琴との邂逅が必要でした。西洋と東洋の文化の坩堝としてハワイや沖縄の音楽を発見した久保田は、細野に以後の活動の着想を与えつつ、今度は彼をプロデューサーに迎えて夕焼け楽団の名義のもと《ハワイ・チャンプルー》(1975)を発表します。
細野がドラムスを叩き、ライ・クーダーも参加したここで聴くことのできる〈初夏の香り〉は、〈ソバカスのある少女〉とともに、村井邦彦や荒井由実による都市式の“ボサノバ”の鋳型ではなく、むしろ都市から海辺へと吹き抜け、都会からリゾートへと聴き手を誘うような、涙よりは汗が「しめらせ」た一陣の風に揺れる鼓膜のかたち、すなわちリゾート式の“ボサノバ”の鋳型となるにちがいありません。
CIRCUSに〈二人の帰り道〉(1977)を提供するなど、作曲家としてアルファレコードと契約していた南佳孝は、細野を除くTin pan alleyのメンバーを集めたうえで、坂本龍一が編曲した大胆なストリングスを配して、かつて彼が客演した楽曲を、「シティ・ミュージックの大物」を謳う独自の解釈のもと〈ソバカスのある少女〉(1977)として実現しました(*32)。やはり坂本の編曲による〈日付変更線〉(1978)についてもまた、松任谷由実を作詞に起用したにもかかわらず、のちの〈モンロー・ウォーク〉(1979)にまでつながる湿気った海辺の風にここで触れることは可能です。
松本隆の歌詞を介して都市へと戻り、「夏の雨」に「濡れ」る〈SCOTCH AND RAIN〉(1982)においてさえ、その楽曲は「何故か陽気」で、「好きなステップで踊る」ほどに爽快かつ開放的です。やがて《BLUE NUDE》(2002)をとおしてボッサ・ノーヴァへの共感を表明する南佳孝は、他方で《Bossa Alegre》(2006)では“ボサノバ”たることも甘受してみせます。
Tin pan alleyが緩やかに自然消滅していく過程で、鈴木茂もボッサ・ノーヴァに接近します。もともと浜口茂外也と同級生だった彼は、その父親である浜口庫之助とも親交があり、アントニオ・カルロス・ジョビンをよく聴いたこのころに、サンバなどラテン音楽のリズムの魅力を教えられたといいます(*33)。浜口茂外也もパーカッションで参加している〈LADY PINK PANTHER〉をはじめ、《LAGOON》(1976)はまぎれもなくその成果でしょう。
Sal+Sol+Sul+α
ブラジルの首都だったリオ・デ・ジャネイロの市街地で発生したボッサ・ノーヴァは、やがて州内ではあれ都心から隔たった海辺のリゾート地にも伝播し、ここに赴いて余暇を愉しむ演奏家たちによって楽曲の主題が取材されることになります(*34)。オス・カリオカスが最初に録音したホベルト・メネスカルの作曲による〈Rio〉(1962)の歌詞のなかで、ホナルド・ボスコリは、塩と太陽と南を謳う音楽へとボッサ・ノーヴァを仕立てました。
この限りにおいて、日本に漂着して歌謡曲との邂逅のもと“ボサノバ”へと変容する渦中で、それが都市から海辺へと、より具体的には東京から湘南へと舞台を変転させることは、いわば必然だったわけです。
実際に、松本隆は、「月曜からは憂鬱色の日々」が待つからこそ週末に「みんなTOKYOを逃げて行く」さまを、鈴木茂の〈《LAGOON》に収録された〈TOKYO・ハーバー・ライン〉の歌詞を借りて描出しています。「ラム」による湿度や「浅い眠りごと」にもかかわらず、仮に五十嵐浩晃の〈愛は風まかせ〉(1980)がそこに連鎖しうるとすれば、それは、この「まどろ」みが「空」の「光」った「午后」および「午後」のものであることによる以上に、ここで鈴木茂が編曲を担当しているせいなのかもしれません。
《14番目の月》(1976)における〈天気雨〉の荒井由実も「相模線」で「茅ヶ崎」まで南下し、南佳孝などは本人が茅ヶ崎に移り住んでいます。荒井や南が頼ったのは、茅ヶ崎に在住のまま音楽活動をしていたBREAD & BUTTERでした。彼らがアルファレコードに移籍して発表した最初のアルバム盤《Late Late Summer》(1979)には、細野晴臣と鈴木茂が連名で編曲者に登記された〈渚に行こう〉が収録されており、これは〈初夏の香り〉や〈ソバカスのある少女〉の系列に明確に位置づけられる楽曲です。
BREAD & BUTTERの楽曲にあっても、同じ岩沢二弓の作曲とはいえ〈Hotel Pacific〉(1981)の場合は、むしろ〈あの日にかえりたい〉の磁場に囚われずにはいないでしょう。
かつて茅ヶ崎の国道134号線沿いにランドマークとして存在した菊竹清訓の設計によるホテル建築で、もっぱら「雨」の雫が波紋を広げる「プールを見」ながら、「浜辺」のことはあくまでも「想い出」の耽溺するところと措定する呉田軽穂すなわち松任谷由実の歌詞は、都市の憂鬱と哀愁を抱えたまま海辺の街に訪問し、ここに逗留する過客の視点から綴られています。「僕」にとって、いま「海」とは単に「聞こえる」ものにちがいなく、その輪郭さえ「雨」の音に滲むそこでは、塩も太陽も南もいかにも不明瞭です。おそらくそれは、リゾートたることを拒否した都市の周縁の光景なのです。
それでもなお、歌謡曲と親和的であるのは、この憂鬱と哀愁の側です。要するに、荒井由実の〈あの日にかえりたい〉を原型として、歌謡曲が都市に“ボサノバ”を係留するうち、いつしかそれは憂鬱と哀愁による過度の湿気を帯びて希釈されてしまったわけです。
〈雨の日のひとりごと〉(1974)でデビューした八神純子は、萩田光雄が編曲した“ボサノバ”の中庸さを、〈思い出は美しすぎて〉(1978)をもってまさしく「思い出」の「美しさ」を象る響きへと応用します。豊島たづみが歌唱した〈おもいでは琥珀色〉(1977)でも、井上忠夫による旋律を〈あの日にかえりたい〉と〈どうぞこのまま〉の直系に配置する鍵は萩田の編曲のうちに存しています。なにより、彼女の“ボサノバ”には、文字どおり〈都会のゆううつ〉(1978)が自作曲として謳われます。
やはり萩田光雄が全曲の編曲を負担した久保田早紀の《夢がたり》(1979)では、彼女の歌声のほかナイロン弦のギターと単音のシンセサイザーのみで演じられる〈ギター弾きを見ませんか〉が、憂鬱よりは憂慮を、哀愁よりは郷愁を奏でます。これは、彼女が愛した「ファド」が“ボサノバ”に共鳴しているからです。のちに《サウダーデ》(1980)のために彼女とともにポルトガルを訪れた萩田は、現地でファドの演奏家たちとの即興的な録音を達成しています(*35)。
歌謡曲になる
「甘い夜」に「記憶をたど」りながら「最後のglass」を傾ける高橋ユキヒロの〈Sarabah!〉(1978)も、都市の憂鬱と哀愁からは逃れられないようです(*36)。「泣き疲れ」た「君」の「寝息」に、「酔った俺」と「白いシーツ」を「素肌に巻い」た「君」との「あの日」を想起する稲垣潤一の〈ロング・バージョン〉(1983)もまた、事情は変わりません。なるほど、その「都会の荒野」は「乾い」ているようです。とはいえ、それはあくまでも「窓の下」、相応の湿度をこの部屋に囲ったはずのガラスの向こう側のことにすぎません。
このような都市の憂鬱と哀愁を歌謡曲のなかで増幅すべく、“ムード歌謡”の独壇場である「雨」の「夜」の繁華街を舞台に設定し、いわば偽悪的に“ボサノバ”を騙ってみせるのは桑田佳祐です。中村雅俊に提供された〈恋人も濡れる街角〉(1982)は、都市とリゾート、東京と湘南のあいだを「YOKOHAMA」として異化しつつ、「時折雨の降る」その「街角」で「愛」に「迷」う「俺」の憂鬱と哀愁が“ボサノバ”の意匠をもって表明されます。
SOUTHERN ALL STARSによる《TINY BUBBLES》に収録され、「雨の降る夜」などには「思い出」の「あの頃がなつかしく」て「ひとしきり泣」かずにはいられない〈私はピアノ〉(1980)では、そんな「夜が怖いよな」ほど「情ない女」に、桑田は「サンバ」を聴かせています。
高田みずえがこれをカヴァーしたように、研ナオコにカヴァーされた〈夏をあきらめて〉(1982)の場合には、もはやボッサ・ノーヴァの調子は“ボサノバ”からほとんど捨象され、〈恋人も濡れる街角〉や〈私はピアノ〉との共振のなかでわずかな残滓が空耳のように拾いあげられるばかりです。不意の「雨」にあの「Pacific Hotel」に「かけこ」んだ「二人」が、「江の島が遠く」で「ボンヤリ寝てる」様子をうかがうここでもまた、件の「渚」で「思いきり 遊ぶはず」だった彼らは都市からの過客にちがいありません。
研ナオコが歌唱した〈ボサノバ〉(1981)の初源は、福島邦子の〈ボサノバ〉(1979)です。鈴木茂が編曲で支えたこの楽曲では、「昨日の夜」の「涙」は「夜更け」の「消えたネオン」とともに「思い出話」となってしまいます。
歌謡曲にとってかつて一領域として省みられたボッサ・ノーヴァは、いまや単なる様式としての“ボサノバ”よりもなおさら仔細な要素へと分解されたうえで、必要に応じて随時それらが参照されるような、したがって一聴しただけではボッサ・ノーヴァはおろか“ボサノバ”の影も捕捉しがたいような、ごく寡黙にして慎ましやかなありようを呈しています。要するに、歌謡曲のそこここに、それと知れず“ボサノバ”は潜在しているわけです。
もちろん、小野リサやnaomi & goroといったほとんど真正のボッサ・ノーヴァや、《PURISSIMA》(1988)での大貫妙子の〈Voce é Bossanova〉、二名敦子の《Play Room~戯れ》(1983)など、程度の差こそあれボッサ・ノーヴァに肉薄する試みはつづけられています。
それでもやはり、尾崎亜美による〈マイピュアレディ〉(1977)や門あさ美による〈ファッシネイション〉(1979)、麻倉未稀による〈ミスティ・トワイライト〉(1981)や〈黒いパンプス〉(1982)、Sugarによる〈ウェディング・ベル〉(1981)や竹内まりやによる〈夜景〉(1986)のごとく、これ見よがしの雄弁さで“ボサノバ”の衣裳を纏う楽曲の一方で、大橋純子〈たそがれマイ・ラブ〉(1978)や桑江知子の〈私のハートはストップモーション〉(1979)、松原みきの〈真夜中のドア〉(1979)やラジの〈ラジオと二人〉(1980)など、その“ボサノバ”らしさの消化の具合いに相違の認められるあたりにこそ、むしろ歌謡曲の本質は認められるはずです。
残り香
松山千春が〈もう一度〉(1980)を、かつてさだまさしとグレープを結成していた吉田政美が〈オレンジ・シティの朝〉(1980)を発表し、MALICE MIZERに〈au revoir~BOSSA~〉(1997)のあることが、歌謡曲をいかに豊かにしていることか。今井美樹が歌唱した〈PRIDE〉(1996)は、そうした歌謡曲のひとつの成熟です。
こうして歌謡曲に浸透した“ボサノバ”には、もはやボッサ・ノーヴァの要件は律儀には備わっていません。
「もうすぐ17歳」となることを強調する松本伊代の《サムシングI・Y・O》(1982)では、デビューほどない女性アイドルによる楽曲が、“シティ・ポップス”を援用する過程で“ボサノバ”と遭遇しています。そこに収録された〈或る夜の出来事〉は、〈センチメンタル・ジャーニー〉(1981)の途上にある「まだ 16」の少女の「恋」をも、「やさしく傷つけ」られる「哀しみだけでもいい」ものと措定し、いわばその「傷」をあらかじめ想い出の記録とするように、都市の憂鬱と哀愁の共有を彼女に唆しています。かろうじて爪先立ちで背伸びした彼女は、都市に棲む大人の「夜」のありようにどうにかその手が届く時機をえたわけです。
伊達歩の歌詞にそれを記述するいっさいの語がないにもかかわらず、早見優の《AND I LOVE YOU》(1982)における〈ハニーな昼下り〉がプールサイドを感じさせるとすれば、それは、「少しだけ オトナなんだ……」と謳うこのアルバムに収録されたほかの楽曲との関係性もさることながら、歌手デビューを控えて彼女が出演したCMからの影響によるところかもしれません。
写真機を広告する映像のなかで、競泳用の水着姿の彼女はプールサイドに佇んでいます。飛び込み台に腰かけた彼女の髪は濡れたまま、首にはゴーグルがかけられ、肩で息をするその視線は伏せられています。彼女のものと思しき水着姿の泳者が先行者にわずかに遅れてゴールに到着する短い映像が挿入されるなか、カメラは彼女に近づき、重く暗いその表情を大写しにします。一瞬、画面が白く転じるやいなや写真機のシャッターを切る音が聞こえるとともに、モノクロームによるその静止画が出現し、ほどなく画面は再び白へと溶明していきます。このあいだ、背景曲として荒井由実の〈あの日にかえりたい〉が流されています。
こうしてデビュー直前の早見優をあらかじめプールサイドに、さらには都市の憂鬱と哀愁に係留していたCMは、〈ハニーな昼下り〉のうちに回収されます。事実、この楽曲のサビの旋律は、〈あの日にかえりたい〉のそれときわめてよく類似しています。ただしそこでは符割りの前倒しをもって和音が組みなおされ、単なる模倣に終始することは巧妙に回避されます。基本的にはボッサ・ノーヴァの響きの奏でられないこの楽曲に、それでもなお“ボサノバ”が浸透しているとすれば、おそらくそれはこうした理由によります。
井上望の〈ルフラン〉(1979)から宮沢りえの〈心から好き〉(1992)に至るまで、女性アイドルが都市を舞台に歌唱する楽曲のそこかしこに、“ボサノバ”は憂鬱と哀愁の芳香を漂わせてやみません。他方で、菊池桃子の〈もう逢えないかもしれない〉(1985)には、杉山清貴&オメガトライブの〈君のハートはマリンブルー〉(1984)と均質の“ボサノバ”を聴くことができます。それは、都市からの過客が去ったのちリゾート地に居留せざるをえなかった側の、どれほどか都市の憂鬱と哀愁に馴致してしまった鼓膜のために、その残滓すなわち移り香として慰めに奏でられるものです。
カフェの家具
〈Summer Beanty 1990〉(1990)の THE FLIPPER’S GUITARや〈baby portable rock〉(1996)のpizzicato fiveら、いわゆる“渋谷系”の登場は、英仏をはじめとする洒脱な洋楽の現在形を消費するなか、必然的に“ボサノバ”に接近します。かの香織が発表した〈午前2時のエンジェル〉(1996)などもこの系譜にあるでしょう。
そうした“渋谷系”の騒動も落着した20世紀の末ごろに、東京や湘南、京都といった文化拠点の界隈で勃興し、流行をすぎていまや常態化したものと考えられる今日的なカフェ事情にあって、とりわけそれらの店舗で利用される背景曲にボッサ・ノーヴァが重宝されることとなりました。それは、これがコーヒー豆の主要な生産地としてのブラジル由来の寛ぎの音楽であること、および、その今日的な事情がパリを中心としたフランスから移入されたものであることに依拠したところでしょう(*37)。
このときボッサ・ノーヴァは、ブラジルからの潮流、その大きなうねりであるとともに、フランスを経由して濾過された洒脱な大衆音楽の上澄みの成分として、コーヒーの芳香をともなって波及したわけです。要するに、いち早く“渋谷系”が着目していたその洒脱さは、コーヒーの芳香と不可分の雰囲気となって、カフェの居心地を構成するひとつの家具たることを期待されたのです。
いまでいう環境音楽のように、気配を誇示することなく空間に浸透していく音楽のありようを“家具の音楽”として概念形成したのはエリック・サティでした(*38)。そして、カフェの外側の騒音を緩和するとともにその内側の静寂を満たすような、それでいてこれ自体がまろやかな寛ぎをその空間に提供するようなカフェの“家具の音楽”、たとえばそれがボッサ・ノーヴァなのです(*39)。
このころの日本で、本場のボッサ・ノーヴァの楽曲を登録した編集盤はいうまでもなく、私たちの耳に親しんだ歌謡曲などをボッサ・ノーヴァ調に編曲し、発声が穏やかであれば誰でもかまわない匿名の、ただし音程だけは確実な歌い手によるカヴァー盤が多種多様に発表されてきた実情は、この音楽の性質をよく反映しています。評判のカフェに同調する店舗のために、あるいはむしろ消費者の部屋などさまざまな空間の気質をカフェのような洒脱さへと転換するために、家具を導入しないまでも音楽にその機能を期待することは、対費用効果の観点からすれば相応に納得の及ぶ判断です。
ここでは音楽は、聴かれるものでないどころか、もはや聞かれるものですらありません。それは、まさしく聴かれないためにこそ存在します(*40)。ボッサ・ノーヴァについてさまざまな側面から指摘できる抑揚の稀薄さは、この音楽を、その演奏を、いわば白色雑音として拡散的に遍在せているにちがいないのです。
*1 クリス・マッガワン+ヒカルド・べサーニャ,『ブラジリアン・サウンド サンバ、ボサノヴァ、MPB―ブラジル音楽のすべて』, 武者小路実昭+雨海弘美/訳, シンコー・ミュージック, 2000, pp.15-20.
*2 同書, pp.32-33.
*3 同書, pp.33-36.
*4 同書, pp.31-32.
*5 エレーナ・ジョビン,『アントニオ・カルロス・ジョビン ボサノヴァを創った男』, 国安真奈/訳, 青土社, 1998, pp.83-84.
*6 ルイ・カストロ,『ボサノヴァの歴史』, 国安真奈/訳, 音楽之友社, 2001, pp.36-39.
*7 同書, pp.215-217.
*8 同書, p.149., p.158., p.161.およびp.178-179.
*9 同書, p.158.
*10 ジョビン, 前掲書, p.126.
*11 カストロ, 前掲書, pp.148-150.
*12 菊池成孔+大谷能生,『東京大学のアルバート・アイラー〜東大ジャズ講義録・歴史編』, メディア総合研究所, 2005, p.55.
*13 カストロ, 前掲書, p.288.およびp.337.
*14 ドナルド・L・マギン,『スタン・ゲッツ 音楽を生きる』, 村上春樹/訳, 新潮社, 2019, pp.301-331.
*15 カストロ, 前掲書, p.446.
*16 山下洋輔,「等身大の栄光」, ジョビン, 前掲書所収, pp.360-363.および西田浩,『秋吉敏子と渡辺貞夫』, 新潮社(新潮新書), 2019, pp.80-84.
*17 西田, 前掲書, pp.104-106.および岩浪洋三,『モダン・ジャズの世界』, 荒地出版社, 1969, pp.222-225.
*18 濱口英樹,『ヒットソングを創った男たち 歌謡曲黄金時代の仕掛人』, シンコーミュージック・エンタテイメント, 2018, pp.106-107.
*19 久保田麻琴,『世界の音を訪ねる』, 岩波書店(岩波新書), 2006, pp.120-124.
*20 濱口, 前掲書, pp.105-106.
*21 同書, pp.80-84.
*22 同書, p.73.
*23 島﨑今日子,『安井かずみがいた時代』, 集英社, 2013, pp.87-101.
*24 村井邦彦,『村井邦彦のLA日記』, リットーミュージック, 2018, p.201.
*25 ムッシュかまやつ,『ムッシュ!』, 日経BP, 2002, pp.124-126.
*26 濱口, 前掲書, p.85.
*27 吉田俊宏,「村井邦彦×松任谷由実「メイキング・オブ・モンパルナス1934」対談」(https://realsound.jp/2021/01/post-680285.html), 『Real Sound』所収, blueprint, 2021, p.2.
*28 松木直也,『アルファの伝説 音楽家村井邦彦の時代』, 河出書房新社, 2016, pp.131-140.および松任谷正隆,『僕の音楽キャリア全部話します』, 新潮社, 2016, pp.42-44.
*29 吉田, 前掲サイト, p.2.
*30 松木, 前掲書, pp.201-208.
*31 萩田光雄,『ヒット曲の料理人 編曲家萩田光雄の時代』, リットーミュージック, 2018, pp.48-49.
*32 君塚太,「南佳孝 INTERVIEW シンガーとソングライターの間で彷徨った日々」(https://www.kiokunokiroku.jp/post/minamiyoshitaka-2), 『記憶の記録LIBRALY』所収, 日本音楽制作者連盟, 2013.
*33 鈴木茂,『自伝 鈴木茂のワインディング・ロード はっぴいえんど、BAND WAGONそれから』, リットーミュージック, 2016, pp.197-201.およびpp.210-211.
*34 カストロ, 前掲書, pp.291-295.
*35 萩田, 前掲書, pp.54-55.およびpp.220-221.
*36 高橋幸宏,『心に訊く音楽、心に効く音楽 私的名曲ガイドブック』, PHP研究所(PHP新書), 2012, pp.129-133.およびpp.141-144.
*37 西村淑美,「記号としての「カフェ」」, 『フラット・カルチャー―現代日本の社会学』, 所収, 遠藤知巳/編, せりか書房, 2010, pp.54-61.
*38 アンヌ・レエ,『エリック・サティ』, 村松潔/訳, 白水社, 1985, pp.194-196.
*39 アスペクト編集部,『カフェの話』, アスペクト, 2000, 01.および02.
*40 秋山邦晴,『エリック・サティ覚え書』, 青土社, 1990, pp.488-495.
堀家教授による、私の「ボサノバ」10選リスト
1.〈恋はジリジリ〉天地八重(1968)
作詞・作曲/中村泰士
イントロのⅰmからAパートがⅴではじまり、以後、2小節ごとにこのⅴとⅰmとをコードが往来するにあたり、スネアはリムの響きもまじえて変型のソン・クラーベのリズムを呈しつつ、ナイロン弦のギターは、ボッサ・ノーヴァ調のリズムをフィンガリングではなくカッティングで刻む。ヴィブラフォンの音の揺らぎもここでの“ボサノバ”感に貢献しているが、これがBメロに突入するやいなや、にわかに楽曲は景気のいい“ビート歌謡”の律動に委ねられる。中村泰士の快作。
2.〈白い森〉NOVO(1973)
作詞/西川利行,作曲・編曲/横倉裕
エレクトリック・ピアノがかつてのヴィオラォンの役割りを負担し、ベース・ギターの太く重い音が歯切れよくこれにからんでグルーヴを生むなか、歌唱される旋律はいかにも爽やかである。この時代の楽曲とは容易には信じがたい音作りに驚きを禁じえない。
3.〈スカイレストラン〉HI-FI SET(1975)
作詞/荒井由実,作曲/村井邦彦,編曲/松任谷正隆
局地的ではあれ、どうやら北米でも確実に“シティ・ポップス”が評価されつつあることは、J.コールによるこの楽曲のサンプリングの事実をもって推測できる。とはいえ、そうした外圧とは無関係に、歌謡曲とボッサ・ノーヴァのあいだの距離を正確に捕捉し、さらには“シティ・ポップス”におけるボッサ・ノーヴァの貢献を厳密に理解するうえで、この楽曲の重要度はきわめて高い。いうまでもなくそれは、“ボサノバ”を概念形成することと同義である。そしてそれゆえに、これはその金字塔となる。
4.〈魔法の鏡〉早乙女愛(1976)
作詞・作曲/荒井由実,編曲/竜崎孝路
〈やさしさに包まれたなら〉のB面に収録されたシングル版にせよ、《MISSLIM》のB面に収録されたアルバム版にせよ、荒井由実自身の歌唱による原曲では可聴的だった“ボサノバ”が、早乙女愛のカヴァー版においては、これが私たちの鼓膜に直接的に触れるところはほとんど皆無である。それでもなお、竜崎孝路のフォーク調の編曲によるこの歌謡曲に“ボサノバ”を感じずにはいない。“シティ・ポップス”の延長線上にある松田聖子への提供楽曲についてではけっしてなく、アグネス・チャンの〈白いくつ下は似合わない〉から三木聖子の〈まちぶせ〉に至るまで、通俗的な歌謡曲を平然とものしてみせた若き荒井由実の類い稀な才覚をこそ、いま、私たちは正当に評価すべきであろう。
5.〈LADY PINK PANTHER〉鈴木茂(1976)
作詞/松本隆,作曲・編曲/鈴木茂
Tin pan alleyにおける〈ソバカスのある少女〉以来、浜口庫之助の薫陶も与ってその身体に浸透したボッサ・ノーヴァを、鈴木茂は自在に“ボサノバ”として奏でてみせる。《BAND WAGON》や《LAGOON》、《Caution!》や《TELESCOPE》など、単にスタジオ・ワークの巧みなギタリストの座に留まることなく鈴木が自ら楽曲を制作し、その歌声でこれらを発表していたことについては、やはりはっぴいえんどでの経験によるところが大きいものと考えられる。そしてこれらがなければ、とりわけ1980年代前半の歌謡曲における彼の活動の彩りは多くが喪失されていたにちがいなく、この意味でも、1970年代後半の彼のアルバム群とは、いわば僥倖なのである。
6.〈マイピュアレディ〉尾崎亜美(1977)
作詞・作曲/尾崎亜美,編曲/松任谷正隆
この囁くような歌いくち、軽やかで清々しく慎ましいそれは、ボッサ・ノーヴァ本来の歌唱のありかたへの率直な参照であると同時に、まさしく音楽に対する邪心なき純粋な態度の表出でもあるだろう。松任谷正隆の編曲もその意を的確に汲んで最良の仕事をこなす。
7.〈ファッシネイション〉門あさみ(1979)
作詞/岡田冨美子,作曲/門あさみ,編曲/戸塚修
この気怠さはなんたることか。都市の夜にあって憂鬱と哀愁に浸るわけでもなく、かといって昼下がりのリゾートの清涼な風が吹き抜けるわけでもなく、たとえば起きがけのいまだ覚醒しきらない意識が感じる身体そのものの重さのように、それとも少し粘度のある乳白色の微睡のように、その歌唱は「遠く近く」と両義的な「揺れ」を謳う。いずれ「揺」さぶられて「地球がなくなる」退廃のなかでも、なお気怠さばかりはそこに残るにちがいない。
8.〈ギター弾きを見ませんか〉久保田早紀(1979)
作詞/久保田早紀・山川啓介,作曲/久保田早紀,編曲/萩田光雄
デビュー当時から、ボッサ・ノーヴァの源流のひとつでもあろうポルトガルのファドに対する共感を隠そうともしなかった久保田早紀は、中近東をイメージづけた萩田光雄によるあの天才的な編曲よりもむしろ、《サウダーデ》におけるファド調のありようをもって〈異邦人〉を着想していたのかもしれない。いずれにしても、アメリカ経由のボッサ・ノーヴァともフランス経由のそれとも異なる“ボサノバ”の可塑性をこの楽曲は示唆している。
9.〈黒いパンプス〉麻倉未稀(1982)
作詞・作曲/いわさき ゆうこ,編曲/瀬尾一三
大野雄二の作曲によるデビュー曲〈ミスティ・トワイライト〉と、次のシングル盤として発表されたこの楽曲との聴感における均質性の度合いは、たとえば近藤真彦が歌唱した〈スニーカーぶる〜す〉と〈ブルージーンズ メモリー〉のあいだのそれに勝るとも劣らない。しかしながら、あるかなきかのその微細な差異のうちにこそ、歌謡曲を舞台として“ボサノバ”が“シティ・ポップス”へと変容していくその次第、つまるところその連続性はよく理解される。なお、この詞曲の作家は、堀ちえみに〈さよならの物語〉を提供した岩里祐穂の別名。
10.〈SCOTCH AND RAIN〉南佳孝(1982)
作詞/松本隆,作曲/南佳孝,編曲/LEON PENDARVIS, NICK DE CARO(管弦)
都市の住人が聴くにふさわしい音楽のありようを追求してきた南佳孝は、ボッサ・ノーヴァをそのためのひとつの方便としてしばしば援用する。この楽曲もその成果ではあるものの、ここではなにより管弦の展開がすばらしい。
番外_1.渡辺貞夫
最先端のジャズの本場からボッサ・ノーヴァの潮流をほとんど劣化なく持ち帰り、日本のジャズの現場のみならず歌謡曲にまでその知見を惜しみなく披露した功績はきわめて多大である。
番外_2.いしだあゆみ
筒美京平による〈ひとりにしてね〉や、《Our Connection》における萩田光雄によるその扱いを考慮すれば、彼女はいわば和製ジェーン・バーキンとでも形容されるべき存在感を示す。たとえばこれは、のちに1980年代には小林麻美などが、1990年代にはカヒミ・カリィなどが連なっていく系譜の端緒となる。
番外_3.八神純子
〈水色の雨〉で小道具に持ち込まれたサンバ・ホイッスルが八神純子のイメージをブラジル音楽に密接させたことは疑いない。萩田光雄が編曲した真のデビュー曲である〈雨の日のひとりごと〉以来、実質的なデビュー曲となった〈思い出は美しすぎて〉や〈想い出のスクリーン〉はもちろんのこと、当の〈水色の雨〉も相応に“ボサノバ”的である。他方で、そこには「雨」が降り、「思い出」や「想い出」に耽溺する彼女がいる。八神純子ほど徹底して都会の憂鬱と哀愁の“ボサノバ”に与したものはいまい。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





