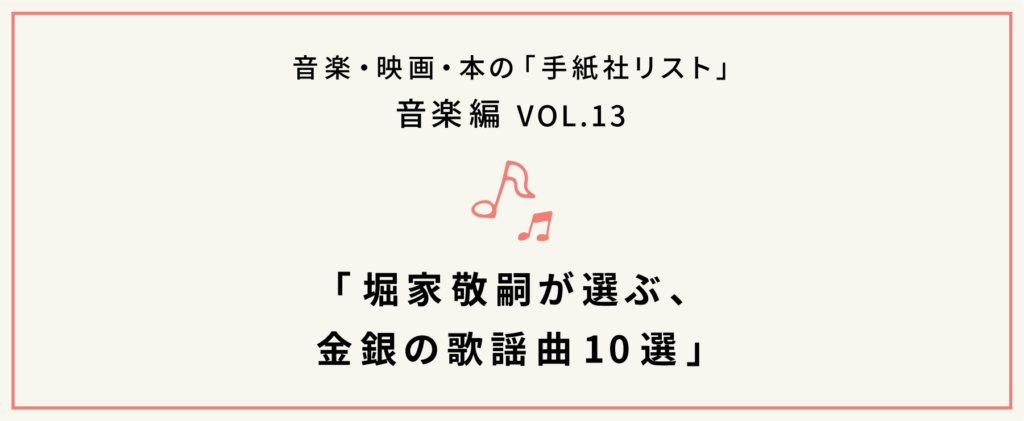
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。13回目となる音楽編のテーマは、金と銀。ゴールドとシルバー。この輝かしきキーワードは、我が国の歌の中で、どのような”装置”として使われてきたのか? さあ、堀家教授の講義、間も無く始まります!
あなたが落としたのは金の歌謡曲?それとも銀の歌謡曲?
金色と銀色
子どもたちにとって、金色と銀色は特別です。とはいえ、もちろんそれは、金本位制や銀本位制といった貨幣経済の根幹を基礎づけ、そこで基礎づけられる価値を、彼ら彼女らがそこに見込んでいるからではないはずです。なるほど、そうした価値が投影されたものと思しき五輪競技などにおける褒賞メダルへの憧憬については、彼ら彼女らが金色や銀色を特別視する理由のひとつとして考慮できるかもしれませんが、おそらく事態はより単純です。
金色と銀色が彼ら彼女らにとって特別でありうるのは、色絵具や色鉛筆、色紙といった、いわゆる図画工作のための画材や素材において、ほかの色彩とは明らかに異なる相貌を呈しているからです。
そもそも、金色や銀色は、ほかの色彩がそうであるように単純な色としての性質のみをもって成立する色覚的な状態ではありません。
たとえば銀色は白色に似ています。
事実、物質としての銀は、金属のなかでもっとも可視光線の反射率の高い物質であり、したがってこれが反射する光は白色に見えます(*1)。白色もまた、すべての可視光線を反射することでそのように見える色です。それでもやはり、銀色はあくまでも銀色であって、白色ではありません。それらの相違は、この反射における指向性の有無によって決定されます。
白は、その表面が光を乱反射し、拡散させるときにそれとして知覚される色です。ところが、銀における反射とは、光源の所在にもとづく光線の入射角度に呼応して、一定の方向にそれが反射されたものです。つまりこの反射光は指向的なのです。
このような指向性を備えた反射光のありようは、銀に限らず金属に特有の光沢をもたらし、いわゆる金属性の質感を視覚的に実現する要素となります。そしてすべての可視光線についてこの金属光沢をともなうとき、それは銀色となるのです。
一定の方向へと送り返され、特定の角度においてのみ煌めくこの白い輝き。もちろん、紫色から赤色に至るまで、銀の表面に射す光線の波長次第でそこに反映される色彩は変化し、磨き込まれたそれは一種の鏡面と化すでしょう。
他方で、金色が黄色に似ているのは、この反射が発生する可視光線の波長領域について、これを黄色く見せるような制約があるからです。
物質としての金は、銀のようにすべての可視光線を反射するわけではありません。それは紫色から青色あたりまでの短波長領域の光を吸収したうえで、黄色から赤色にかけての波長の長い光を選んで反射します(*2)。このため、有色金属とも形容される金の反射光は、いわゆる黄金色として表現されるのです。やはり反射に一定の指向性を備えたこの金属光沢こそが、金をそれとして輝かせる要因にほかなりません(*3)。
実際に、金や銀を個別の色彩として成立させるために、色絵具や色鉛筆では顔料に金属粉を混ぜ、金属光沢を発生させています。色紙では、基材となる紙のうえにアルミニウムの箔を貼り重ねてまず銀色の紙とし、この表面にあらためて橙色のインクを塗布することで金色の紙が製造されます。インクの塗布ではなくセロファンを貼付する場合や、最初からアルミニウムではなく真鍮の箔を基材の紙に貼付する場合もあるようです。
金属
金色と銀色のこうした性質を率直に提示してみせるのは、いうまでもなく金属の表面です。
とりわけ、腐食することのない金の未来永劫のものとも思われる不滅の輝きは、古今東西を問わず人類を魅了し、権力や財力を誇示する装身具の材料として重宝されてきました(*4)。それだけに、この錆なき輝きは、それにも増してえがたいなにごとかの貴重さ、それにかえてでも手中にしたいなにものかのありがたさを表現するための基準値として、しばしば歌謡曲の歌詞の言葉に援用されます。
石野真子が歌唱した〈ジュリーがライバル〉(1979)では、「あなたの胸」に「金色のペンダント」が「揺れてい」ます。「窓にもたれた」彼は、ここで「ジュリーのポスター」を「指ではじいて」みせるのだから、この「金色」が、彼が「撃ち落と」すべき「ライバル」としての「あいつ」、すなわち「ジュリー」こと沢田研二の眩いスター性に対抗する手段として機能していることは疑いありません。
しかもここで彼は、こちらに「背を向け」ていったんこれを隠しておきながら、「ジュリーのふりを」しつつ今度はこれ見よがしに「胸を張」ります。その胸に煌めく「金色のペンダント」の光沢が、「ジュリー」の発散する輝き、ただしあくまでも「ポスター」のそれと見比べておよそ遜色のないことは、結果的に主人公が「あなたの勝ち」と判定し、「あなたに決め」てしまうことからそれと知れます。
遠藤京子による〈Dear Mr.〉(1983)の主人公は、「金色の指輪」を「はず」して「ピアノの上に」置き、「二人の部屋」から「知らない街」へと「ちょっと出て」いきます。このとき指からはずされたこの宝飾品は、「あなた」との「重い過去」、その「熱い想い出」との「別れ」の決意を通告するものとなります。ここで彼女があえてそれを手放すことは、そうしてまでも状況の膠着を打破したいとする堅固な意志の切実さを表明するのです。
C-C-Bの〈2 Much, I Love U.〉(1987)は、「金色の指輪より大切なもの」は「嘘のない君の透明な瞳だけ」だと断じます。煌めく反射よりも濁りなき透過を尊重する「僕」にとっては、この「胸のドアの鍵」を「開けられる誰か」とは「世界中探しても一人しか」おらず、まさにそれは「君」のことである以上、そんな「君」にはきっと「金色の指輪」を与えても惜しくはないのでしょう。
ところで、下成佐登子が発表した〈金色のエアプレーン〉(1981)では、「ギリシャ」や「パリ」など欧州への渡航に「誘」われながら、「二人だけの旅」は「まだ早すぎる」からと断った「私」が、「ひとり」きり地上に残って「金色のエアプレーン」を「見送っ」ています。
この「金色」が、本来の機体の色なのか、それとも朝陽や夕陽など太陽の暖かさを反映したものなのか、にわかには判断がつきません。しかしながら、三浦徳子による歌詞では、「ギリシャ」のものではあれ「陽ざし」の介在が「あなた」を「見送った」件に先行して綴られる限りにおいて、聞き手の鼓膜があらかじめ陽光に染められてしまったとしても不思議はないでしょう。
このように「旅」立っていった「あなた」の行方には、文字どおり「Par Avion」による「葉書」や「テレフォン・コール」をもって「私」からの「愛」が伝えられ、むしろそうして「離れてるほどに 愛は見える」ところとなります。そしてそれだからこそ、「私」が「ひとり見送った」あの機体の輝きは、けっして冷ややかな銀色などではなく、あくまでも温もりある金色を呈していたにちがいないのです。
その証拠に、《EACH TIME》(1984)に収録された大滝詠一による〈銀色のジェット〉では、「君」は「この都会」を「捨て」て「滑走路から離陸して」いきます。「愛され過ぎたから愛せない」と、「迷って」いた「君」の最後の「答えを乗せて」、いま「銀色の機影」は「翔び立」っていくのです。
ここで地上に残された主人公は、「もうこれ以上」は「失うものなど」どこにも「無い」のだから、「雲間へと……消えてく」その「翼を……見送」りながら、ひとり「この都会で/生き続ける」よりほかありません。「……」とは、その涙の粒にして、「銀色の機影」を、その「翼」を覆い隠してしまう「雲」の粒子ともなります。「銀色」を滲ませ、その輝きを寒々と鈍らせるそれは、松本隆が描く冷めた別れの光景に似つかわしい重い質感を供給します。
さらに松本は、小泉今日子に提供した〈迷宮のアンドローラ〉(1984)でも、「銀のFlying Saucer」を「夜空」に「浮か」べています。
鍍金
金属の表面における金色や銀色の輝きは、その煌びやかさをもって、これを纏う実体の如何から視界を眩ませる効果もあります。それは一種の見栄や虚勢として、事物の輪郭を超過し、これを誇大に装う機能に与っているのです。
高橋優の歌唱による〈卒業〉(2012)では、「銀のメッキが剥がれ落ち」てしまったのちの「地金姿で尚も生く僕ら」について、「望みも絶たれ」て「絆も恥もぶら下げたまま」の、いわば剥きだしの裸形ではあれ、これこそが「新しい「今」」なのだと謳われています。それゆえこれは、同時に「過去から卒業のとき」ともなります。たとえどれほどそれが「鮮やかな想い出」であろうとも、彼らの「過去」の輝きは「銀のメッキ」に覆われた虚飾だったわけです。
クレイジーケンバンドが《Brown Metallic》のために吹き込んだ〈Midnight Cruiser〉(2004)において、「アメ車のヘッドライト」が「金色にみえた」とすれば、それはやはり「記憶」による鍍金が人工光の側に施された結果といえるでしょう。
人工光ではなく自然光、要するに太陽だけが、真正の金の輝きを担保します。逆にいえば、それが鍍金であるか否かは、文字どおり白日のもとに晒されるところとなります。
山口百恵の〈イミテイション・ゴールド〉(1977)は、「西陽の強い部屋」にあって、その「窓辺ではなしかけ」てくる「彼」の「焼けた素肌」に、「イミテイション・ゴールド」と同質の「若」さを感じたことをきっかけとして、この「今年の人」における「去年の人」との相違が列挙されます。なにしろひとたび「日が当れば」、「彼」らのありようは「影」も「色」も「違う」どころか、まさに「光が変わ」ってしまうことが率直に指摘され、「今年の人」の、あるいはむしろ「今年の人」との「愛」のにわかな模造ぶりに「私」は辟易せずにはいられません。
eastern youthの〈五月の空の下で〉(2007)についても、主人公の「メッキを剥」いで「五月の空の下」にその「地金を晒す」もの、それは、ほかでもない「午後」の「直射日光」の仕業です。金や銀に真性の金属光沢を担保するそれは、すなわち「メッキ」によるその擬態を露呈させ、告発する啓示でもあるのです。
いまやアルバム盤《地球の裏から風が吹く》にあっては、この「直射日光」のもと、「足に絡み付く」ほどに溶けつつあるらしい「アスファルト」もまた、まさに「足」の裏で「地平」から「剥がれ」ようとしている一種の「メッキ」にちがいありません。そしてついにこれが「高架」もろとも「剥がれ」落ちてしまえば、“地球の裏から風が吹”いてきたりもするのでしょう。
それだからこそ、こうして「狂い出した」世界の、宇宙の、自身をめぐる関係性の「歯車」が、すでに「加速を付けて廻」りはじめたところで、主人公はこれを「構わねえさ」と諦念で受け止めます。
あるいはそれは、「メッキ」が「剥がれ」た先に待つものへの期待や剥きだしの素地についての自信の呟きなのかもしれません。
事実、竹原ピストルの〈ギラギラなやつをまだ持ってる〉(2021)の場合には、「メッキ剥がれてもゴールド純金」であることが傲岸なまでに誇示されます。《STILL GOING ON》に収録されたこの楽曲で「Still Going On」と叫ぶ「オールドルーキー」の「俺」こと「竹原ピストル」は、「メッキ剥がれて」なお、「ギラギラなやつ」で「あんた」に「痛えくれえ真っ赤な余韻を残」すことへの自負に満ちています。ここで「オールドルーキー」と「ゴールド純金」とは、韻を踏んでその同一性を聴覚的にも強調されます。
ところが、松任谷由実の自負は、むしろ鍍金が鍍金であることの安っぽい輝き、底の浅く奥行きを欠いた薄っぺらなその金属光沢の禍々しさを、無垢の金属の塊が提示する重厚な存在性にはない固有の質感として味わいうる感性にこそ賭されています。
夢
日常の機微を鋭敏に嗅ぎわける彼女の研ぎ澄まされた感覚は、とりわけ《悲しいほどお天気》(1979)において、「いつかは」きっと「あなた」を「みかえすつもり」で「どこへ行くにも」きまって「着かざってた」はずが、「今日にかぎって」なぜか「安いサンダルをはいてた」ことへの悲嘆に暮れ、これをもって「あなた」との不意の遭遇と失望を言外に示唆する〈DESTINY〉のうちに、存分に発揮されるものです。
もともと《星屑の街で》(1981)の石川セリに提供された〈手のひらの東京タワー〉もまた、彼女のそうした感覚が的確に反映された楽曲であり、松任谷も自らこれを《昨晩お会いしましょう》(1981)に収録しています。
「愛したらなんでも 手に入る気がする」そこでは、「今は世界中が箱庭みたい」に「私」の意のままとなり、「東京タワー」さえが「私」からの「プレゼント」として「あなた」に手渡されます。「ガラスのエレベーター」の「ドアが開」いた先に広がる「東京」の「夕映え」の「パノラマ」、「遠いビル」も「ハイウェイ」も「港」もみな「煌いて」いる「パラダイス」のごとき光景のなか、これもろとも彼女が「手のひらに包ん」でいた「プレゼント」、それは、この光景から切り抜かれ、摘みあげられたような、「金色」に輝く「東京タワー」でした。
しかしながら、「本当は金色のエンピツ削り」にすぎないこの「プレゼント」を、「子供じみている」からといって「捨ててしまわない」ようにと「私」は忠告します。というのも、ここで彼女が「あなた」と共有しようとしているのは、貨幣経済を秩序づける貴金属としての金の価値などではなく、あくまでもあの色鉛筆や色絵具、色紙にあって特別な相貌を呈していたときと同じ「金色」の禍々しい質感、顔料に金属粉を混ぜたりアルミニウムの箔に橙色のインクで着色して造作されたような、鍍金による金属光沢の贋物性そのものだからです。
彼女は、鍍金が剥がれ、これが「東京タワー」の形状を模した単なる「エンピツ削り」と露呈してしまうことを懸念しているわけではありません。「煌い」た「パラダイス」のごとき「夕映え」の「東京」の「パノラマ」における眩い光景を「箱庭みたい」に所有する体験とともに、これと優劣なき味わいとして、鍍金された「金色」の安っぽくも幻惑的な輝きに動揺する感性を「あなた」に量り、そのうえで彼女は、「つぎはあなたの夢」を「私に下さい」と望みます。
「金色」の鍍金にもそれ固有の輝きの味わいがあって、それはけっして無垢の金塊の輝きを軽薄に再現するだけのものではないはずです。鍍金の安っぽさを、その安っぽさ自体においてこうして味わうことは、ある意味で優雅な戯れです。これに耽ることのできる感性ないし資質をもって、「私」は「世界」を自身の「箱庭」へと変容させます。いまや「東京タワー」はおろか「東京」も「世界」も彼女のものであり、そのありようをかたちづくる遊戯を「あなた」とともに享楽することが「私」の「夢」だったわけです。
色鉛筆や色絵具、色紙にあって特別な相貌を呈していたあの「金色」の禍々しさに瞳を輝かせる「子ども」のように、「あなた」と「私」だけにわかる仕方で「煌いて」くれる「世界」の味わいを生きること。
そうした「私」の「夢」とは、まったく「子どもじみている」にはちがいないでしょう。にもかかわらず、権力や財力におもねることも囚われることもない「子ども」の純粋さ、無邪気さをもってはじめて「夢」は「金色」に「煌いて」、その眩さをして無垢の金塊の輝きと拮抗し、これが秩序づける貨幣経済を前提とした既存の価値を転倒させ、膠着した社会の体系を転覆することができるのです。
事実、〈時をかける少女〉(1983)の原田知世は、「ゆうべの夢は金色」だったと歌います。そこでは「私」は、「幼い頃に遊んだ庭」を舞台に、「たたずむあなたのそばへ」と駆けていこうとしますが、その足は「もつれて」ままならず、「涙」に「濡」れた「枕」で彼女は「夢」から醒めます。
黄泉
このように「夢」を介して「私」は「時をかけ」、「過去も未来も星座も越え」、いまは「褪せた写真のあなたのかたわら」までも「飛んでいく」わけです。
そのとき「夢」は、「褪せた写真」のようなセピア色を基調に、ここに金属質の輝きを、煌めきを纏っています。現在のものである鮮明な色彩は、陽に灼け、風に晒されて次第に褪色してしまいます。やがて「過去」として構成要素の単位にまで関係性をほぐされ、個別的な細部を喪失しながら、一様に黄昏色の濃淡へと還元されていくなか、堆積した時間を貫いて構成要素を検索する「夢」において記憶は再構成され、ある統合的な磁力の入射角に適合した瞬間にそれは金属光沢を呈するのです。
この限りにおいて、それは現実に経験されたある確かな出来事の美しい想い出でさえありえません。それは、いまその瞬間ごとに「夢」として生きられつつある出来事そのものです。しかもそれは、腐食することのない無垢の金塊のように、死に瀕してなお「金色」に輝きつづける不滅の光です。「夢」が「金色」に輝くとき、それは、私たちが黄泉への扉に手をかけていることの兆しなのかもしれません。
〈時をかける少女〉にあって、「枕」を「濡ら」した「私」の「涙」とは、おそらく、その扉から漏出する輝きに染まった「金色の夢」の残滓、その名残りの煌めきにちがいないのです。
ただし、「夢」は、もはや小さな「金色のエンピツ削り」のようにこれを「手のひらに包」むわけにはいきません。その「金色」の源泉に駆けつけようにも、足は「もつれて もつれて」、けっしてこれに届くことはないでしょう。なぜならそれは、すでに失われてしまったものとして、まさにいま「夢」のかたちで生きられているからです。そしてこれは、まぎれもなく、すでに失われてしまったものだからこそ、いま「金色」に輝くのです。
松任谷由実は、原田知世に提供したこの〈時をかける少女〉を、松任谷正隆の編曲もほとんどそのままに自らの歌唱により《VOYAGER》(1983)に収録しているほか、歌詞に若干の変更を加えたうえでまったく異なる旋律をあてがい、〈時のカンツォーネ〉と題された《スユアの波》(1997)の収録曲としてあらためて発表しています。たとえば「ゆうべの夢は金色」の文言にも加筆され、「ゆうべの夢は金色の窓辺」の表現へと変化します。
こうした事情を知ってか知らずか、くるりの岸田繁が作曲した〈裸の王様〉(2005)において、湯川潮音の「私」は、「鉄格子の窓」の先に「金色の庭」を「見つけ」ています。この「鉄格子」を「蝶になっ」た「私の心」が「すり抜けていく」とき、そこには「あなたの見たもの」でも「私の思うもの」でもないなにかを「見つける」ことになると彼女の歌詞が綴られる以上、「夢の中のこと」かもしれないそこでは、主体性までも消滅し、もっぱら「金色」の輝きばかりが残されているはずです。
「なつかしい声」による「あのうたがきこえ」てくるのは、《僕と君の希求》(2021)をもって空気公団が発表した〈うたがきこえる〉でのことです。その「声」の主は「黄金色の中で手を振」っているといい、どうやらそれは、ここでも「夢の中に戻っ」たときの出来事のようです。そしてやはり、そこでも「なつかしい声」のもとにはけっして歩みの届かないまま、「夢の外へ戻って行」くように促されます。
斉藤由貴が歌唱した〈少女時代〉(1988)は、原由子の作詞と作曲により《PANT》に収められています。《MOTHER》(1991)では、原由子自身による歌唱を聴くこともできます。「落葉舞う校庭」で、「教室の片隅」で、さらにその「窓辺」で、「金色に輝い」ていたのは「少女達」です。またしても「庭」と「窓」とが、歌謡曲に「金色」の「輝」きを担保するわけです。
かつて主人公もそのなかのひとりだったはずの「少女達」は、いまや「誰」もが「大人にな」り、そうした光景も「想い出に変わって」しまいました。だからこそ、それらは「今も忘れ」られない「夢」もろとも、「少女達」を「金色に輝」かせるのです。とりわけ、「校庭」からの外光が射し込む「窓辺」では、屋内と屋外とを隔てる硝子やサッシの介在があたりに陽光を反射させながら、逆光のもと「少女達」の柔らかな輪郭が「金色に輝」きます。
流れる
「校庭」で、「教室」で、「窓辺」で、眩い「金色」の背景に輪郭を「輝」かせて浮きあがり、それゆえ個別的な相貌を次第に翳りのなかに埋没させながら、なお「少女達」は、「大人になっ」てしまった現在の彼女たちのありようとは異なる存在の仕方で「今」も息づいています。ここにもまた、あの不滅の光が注いでいるのです。
〈流れるものに〉(2012)の中村一義は、この「無限のように流れる黄金色」を、「街にいたって両目閉じりゃ、もう自然に」目蓋の裏の「全景を覆いつく」してしまう「田園」に喩えます。ただしベートーヴェンの交響曲との共鳴が企図された《対音楽》にあっては、「田園」とは、単に稲穂のなびく光景をめぐる記憶であるばかりか、「脳裏」に「流れ」る「音符」、「宇宙を流れる音」のことであり、しかもこの「宇宙」は「君」と「よく似」ています。
ここで「僕」は、「肌」の内側と外側とが互いを「鏡のように映」す関係であることに「ついに気付かされ」ます。さらに、互いに反映しあうがゆえに内側と外側とが自在に反転可能なそこでは、「君がいて僕がいる」ことが「世界」の「起点」となり、その限りにおいて「君」は「僕」であり「僕」は「君」でもあるのだから、「無限のように流れる黄金色」とは、原初にして終焉の「宇宙」の時間、すなわち永劫回帰としての「音」もしくは光のことにほかなりません。
ハナレグミの〈on & on〉(2021)では、「夕日」のもと「金色」に彩られた「高層ビル」の「街」が、「夢のよう」な「新世界」として屹立します。そのとき、「逢えない」はずの「君をすぐそばに感じ」た主人公は、「黄色いマーガレット」にも似た「君の笑顔」に「そっと降り注ぐ 歌でありたい」と願います。これまでに確立された人称性は「金色」の光に溶解し、「新世界」の「夢」を謳う無記名の「歌」として「君の笑顔」を揺らすとともに、この「響き」は「風になって」その「頬を撫で」ていくのです。
中村一義の場合であれ、ハナレグミの場合であれ、人格を規定していた輪郭は光の耀いに侵食され、融解したその存在性は可聴領域における周波となって、もはやあたり一面に流出しはじめています。
そして仮に、彼らの「音」や「歌」がひとたび「風の谷」に「流れ」、ここを吹き抜けようものなら、おそらくそれは「雲間から」そこに「射」し込む一閃の「光」と化して、「金色の花びら散らし」ながら「人」を「身体ごと宙に浮か」ばせ、たちまちここを「まばゆい草原」へと変容させるはずです。安田成美が歌唱した〈風の谷のナウシカ〉(1984)が映画作品の側から排除されたことは、まさしく詩人の、詩の、歌の潜勢力が可聴領域から可視領域へと波長の帯域を推移させ、「金色」に輝きはじめることを、映画の光が疎んだ結果なのかもしれません。
ハナレグミの楽曲を収録したアルバムが《発光帯》と題されている事実は、この懸念について いかにも示唆的です。
それどころか、甲斐バンドによる〈ビューティフルエネルギー〉(1980)は、「桟橋の上に」広がり「昇ってゆく」光の垂幕である「オーロラ」について、「もう二度とこの輝やきに」は「会えないかも しれないから」と、これを「金色」のうちに凝縮させます。ときに固体たる「爪」として結晶化し、ときに気体たる「声」として揮発化するなど、さまざまな状態への移行が許容された「金色」は、しかしそこでは、とりわけ液体たる「汗」のかたちで「流」れていくことがもっぱらです。
加えて、甲斐バンドは《黄金/GOLD》(1983)を発表し、ここからのちに〈GOLD〉をシングル盤に切りだします。「お前からでる目もくらむ光」が「すべて黄金に変」えてしまうここでも、「Body」はもちろん、「お前」の「声」も「汗」も「光って」います。とはいえ、その「輝きとひきかえに」して「いつか二人も」、つまるところその「命も愛も死んでいく」ものらしく、いずれ「すべて」は「あせた黄金になっちまう」と悲嘆されます。
水面
《黄金/GOLD》には、「黄金色に光る岸辺」と歌った〈シーズン〉(1983)も収録されています。それは「いちばん近い海」のものであり、「今から行ける海」の「波打ち際」のことです。「金色の汗を流」した果てに、いまや「黄金色に光る岸辺」が、「いちばん近い海」の「波打ち際」が「きらめく」のです。
《うつろひ》のさだまさしが歌唱した〈黄昏迄〉(1981)では、「黄昏」どきの「海」にあって「黄金色の波の上を帆影が」よぎっていきます。そうして夕暮れに傾斜した陽光は、現在を過去と等しく「黄金色」に輝かせてしまうはずだから、もはや「海を見下ろす丘の上」から望まれる「空と海の青と思い出とが一列に並ぶ」さまに、「僕の心が鴎になって舞い上が」ったかのように感じたところで不思議はないでしょう。
「空と海の青」を「黄金色」の輝きのうちに混交し、融合させる「黄昏」どきには、それゆえ、もとより「黄金色」であった「想い出」までが現在のそこかしこに滲んで浸透し、いずれ夜の闇に眠る夢と煌めくのです。
水は、光の入射角に応じてその表面を鏡面化させることで、にわかに金属光沢を装います。これが「黄昏」どきの陽光を反映するならば、それはまぎれもなく「黄金色」に輝きます。もちろん、朝焼けといえどもさほど事情は変わりません。
実際、「東の雲は紅く」染まり、「蒼く冷めたアスファルト」が現われつつも、「夜露」ばかりは「黄金色」と「輝いて」みせるのは、キリンジの〈朝焼けは雨のきざし〉(2008)でのことです。
山下達郎による〈ヘロン〉(1998)では、「金色」は「夜明け」の「空」のものです。ただしそれは、湿度の低く乾いた空気のもと、からりと晴れる澄んだ朝ではありません。あくまでもそれは、「イオン」が「沸き立」ち、これを「浴び」、やがて「朝もやの中」へと「溶ける」ような「柔らかな光」を纏う、いかにも湿気の充満した、そしてそれだからこそ青鷺の「鳴」き声がいとも容易に「雨を呼」んでしまうことを危惧せずにはいられないような、水の粒子を湛えながらかろうじて気体状を維持する輝きです。
この限りにおいて、〈朝焼けは雨のきざし〉の「夜露」が「黄金色」に「輝」く理由とは、単に「露」の表面が「朝焼け」の光景を反映する水鏡として機能しているからのみならず、これが夕べの、「夜」の夢を包摂した雫、いわば朝靄のうちに揮発していこうとしている夢の最後の一滴だからにちがいありません。
そうしたなか、〈ヘロン〉の青鷺の「鳴」き声が朝靄の垂幕を揺らすとあれば、ここに欠けていた紫色から青色あたりまでの短波長領域の光の振幅がその声の青さのもとにわかに補正され、明けた朝に銀色の「雨を呼」んでしまうことはもはや不可避です。「朝焼けのあとはいつも雨」だ「とは限っていない」にもかかわらず、そう「決めつけてしまいそう」になるほど、青鷺の一啼には「雨」の気配が、匂いが、色が宿っているのです。
いまや銀色の「雨」が降ろうとしています。
〈黄昏のビギン〉(1959) において「たそがれの街」を「濡」らしたのは、まさしく「銀色の雨」でした。そしてこれがほかならない「銀色」だったからこそ、この「街」の夕景はあくまでも黄昏ならぬ「たそがれ」に映ったのであり、「雨がやんで」のち「夕空晴れ」てなお、そこは「たそがれ」のまま「夜」の「星かげ」が「あなたの瞳」に迎えられます。
水原弘に加え、ちあきなおみによる歌唱でも知られたこの楽曲で、題名に明記された“黄昏”の語が歌詞にあってはこうして「たそがれ」と表記されている事実は、「ネックレス」の色味の印象を方向づける因子ともなります。「ブラウス」を「濡」らした「雨のしずく」の名残りのように、「こきざみ」で「ふるえ」る「胸元」のこの装身具からは、「きざ」まれる「ふるえ」の都度、まさに「銀色の雨」のものともみまがうばかりの冷ややかな金属質の閃光が放たれていたにちがいないのです。
不眠症
高田みずえが歌唱した〈花しぐれ〉(1978)において、それは「銀の細い糸」であり、アグネス・チャンが歌唱した〈雨の色〉(1978)においては今度はそれは「銀色の粒」となります。わけても松山千春の〈銀の雨〉(1977)にあっては、過去の「思い出」も未来の「夢」も、「いつの間にか 降り出し」てきた「銀の雨」にもれなく包まれてしまいます。
なるほど、ひとたびこれが「豪雨」を招き、いかにも地表に届く光量を激しく減衰させたその「どしゃぶり」のなかでは、銀色であるよりも光沢は著しく鈍まり、いわば「鉛色の粒」から織られた「毛布のよう」な重く暗い「雨」の塊としてふるまうことは、〈雨は毛布のように〉(2001)のキリンジが描写したとおりです。
それでもなお、これが氷点下のもと再結晶化して地上を覆う「雪」のものともなれば、「雨」だったころの「鉛」の鈍重さは濾過されて輝きばかりをその表面に凝縮し、たとえば〈案山子〉(1977)のさだまさしなどは、たちまちこれを「銀色の毛布」と形容してみせるはずです。
かつて〈時をかける少女〉において「金色」に彩られていた「ゆうべの夢」からつづくまどろみに耽溺したうえ、しとねに埋まろうとする身体を、こうした「鉛色」の「毛布」や「銀色の毛布」は厳しく処遇し、意識を冴えわたらせることがもっぱらです。甘美にして懐かしいあの「金色」、あの「夢」、ときに黄泉への経路となるあの眠りの、寂しくも心地いい温もり、安らかなあの暖かさは、それらの「毛布」に包まることによって実現されるどころか、そこからの覚醒がいっそう促されることになるわけです。
ここで冴えわたり、いよいよ覚醒していく意識が対峙せずにはいないもの、それは、あの「金色」の輝きが、どれほどそれに手を伸ばしてもけっして到達できない「夢」でしかありえない現実のありさま、そのさめざめとした明晰さにちがいありません。実際、ザ・ピーナッツの傑作〈恋のバカンス〉(1963)にあって、「金色に輝」いていた「熱い砂の上」の「バカンス」とは、あくまでも「夢見」られた「甘い恋」のことでした。
こうして、黄金色に染まることなくいつまでも「たそがれ」つづけるよりほかない〈黄昏のビギン〉のような、冷ややかな「銀色の雨」のもとでは、もはや誰もが幸福な「金色」の「夢」を求めて眠りに就こうにも寝つけないまま、いずれ不眠症とならずにはいられないでしょう。
小泉今日子による《Betty》(1984)に収録された〈バナナムーンで会いましょう〉の主人公は、そうした不眠のゆえか、「夏の浜辺」に「足をぬらしに来」ます。ここで「夜の月は細い三日月」を象り、だから「バナナムーン」とも喩えられています。けれどその語感が想起させる色彩に抗って、この眠れない「夜」には「浜辺」の砂もろともいっそう「足」を冷ますべく、寄せる「波さえ銀色」の光沢を反射することになるのです。
〈迷宮のアンドローラ〉にあっても、「銀河から」やってきた「銀のFlying Saucer」が「瑠璃色」の光跡を残して「夜空を駆けめぐる」さまを目撃し、これを「夢なの?」と自問した主人公は即座に「夢じゃない」と自答します。
光GENJIの〈パラダイス銀河〉(1988)における真の哀しみとは、したがって、「大人は見えない」という「夢の島」、つまるところ「子供達」だけに許された「パラダイス」として、彼ら彼女らが「ベッド」を「汽車」に変換して「風を切」って赴く行方が、なるほど睡眠に導かれた「夢」のなかにはちがいないものの、すでにあの黄金色ではない「銀河」と措定されることのうちに存しています。
「遊」び、「はしゃ」ぎ疲れた「子供達」の特権である熟睡。不眠を知らないはずの彼ら彼女らの無邪気で幸福な夜にとって、しかしいまや「夢」はもちろん、「愛」だろうと「心」だろうと「嘘」だろうと、そこから醒めることの喪失感に微熱で温もった名残りの涙が枕を濡らさずにはおかないような、あの甘美にして懐かしい翌朝のありようは、あらかじめ「銀」の光沢をもって禁じられてしまっているわけです。
銀河
あるいはむしろ、そのような「夢」として「さみしそう」な「その瞳」に映る「銀河」の瞬きとは、目蓋を閉じる暇も惜しんで眠った「子供達」ばかりに邂逅を許された、「止まらない」時間の最先端が次から次へと結晶化していく光景であるのかもしれません。
〈パラダイス銀河〉の「汽車」とは、まぎれもなくゴダイゴの〈銀河鉄道999〉(1979)が謳った「Galaxy Express」のことであり、したがって宮沢賢治による『銀河鉄道の夜』が参照されています。そしてこの限りにおいて、「銀河」とは、金色の輝きに浸る「やすらぎよりも」なお「素晴らしいもの」に「気づいてしまった」にちがいない「君」が、寝台を「Galaxy Express」に見立てた果てなき旅の途中で、宇宙のそこかしこに星として「置いて行」った「古い夢」の点滅です。
かねてより色鉛筆や色絵具、色紙などが呈していたような「金色」の鍍金の禍々しい光沢に、権力や財力におもねることも囚われることもない純粋さ、無邪気さを反映させて「煌い」た〈手のひらの東京タワー〉の、あのまったく「子どもじみ」た「夢」は、だが結局のところ〈パラダイス銀河〉の「子供達」のものではありえませんでした。ここではそれは、あくまでも「子どもじみ」た「大人」だからこそ「見」ることのできる、「子どもじみ」た「大人」のための「パラダイス」にすぎなかったのです。
*1 徳田昌則ほか,『構造、状態、磁性、資源からわかる金属の化学』, ナツメ社, 2012, pp.30-31.およびp.208.
*2 同書, pp.30-31.
*3 村上隆,『金・銀・銅の日本史』, 岩波書店(岩波新書), 2007, pp.20-25.
*4 同書, pp.12-13..
堀家教授による、私の「金と銀」10選リスト
1.〈黄昏のビギン〉水原弘(1959)
作詞/永六輔・中村八大,作曲・編曲/中村八大
〈黒い花びら〉につづくシングル盤〈黒い落葉〉のB面に収録。ちあきなおみの歌唱による盤の評価が高いが、水原の歌声や口笛とストリングスやトランペットとの対話がゆったりとしたリズムに絡んでステップを刻み、おおらかなグルーヴ感を生むこの盤の編曲も印象深い。へ長調からイ短調に転調したのち、平行調であるハ長調の響きのなかでたどられる「ぼやけてた」の旋律において、「や」の音程がブルー・ノートに相当するミ♭となり、黒い憂鬱さをきわだてる。
2.〈恋のバカンス〉ザ・ピーナッツ(1963)
作詞/岩谷時子,作曲・編曲/宮川泰
“翻訳ポップス”をとおして洋楽のエッセンスを習得しつつあった歌謡曲は、著作権の管理の厳格化のもと、いよいよ自前のポップスの確立を模索しはじめる。中村八大を中心にその尽力が結実するなか、いわゆる“和製ポップス”の本流たらんと切磋琢磨する多くの楽曲群にあって、〈恋のバカンス〉ばかりはむしろ、最初から日本語で歌詞があつらえられ、たまたま日本の音楽家によって作曲されたにすぎない“翻訳ポップス”であるかのようにふるまい、いまなおなんの違和も齟齬も感じさせるところがない。
3.〈ビューティフルエネルギー〉甲斐バンド(1980)
作詞/甲斐よしひろ,作曲/松藤英男,編曲/甲斐バンド・椎名和夫
甲斐バンド屈指の佳曲。なにより、歌唱が甲斐よしひろでなく作曲者の松藤英男であることが、このバンドの楽曲に特有の押しつけがましさを低減させ、その軽やかさが好ましい。音程がふらつこうとも声が裏返ろうとも、その歌声がなんら楽曲の価値を損なう理由とはならない。クリスタルキングにおける〈セシル〉とも共通する事情である。ジョン・ホールの〈Home at Last〉からの拝借加減も絶妙。
4.〈金色のエアプレーン〉下成佐登子(1981)
作詞/三浦徳子,作曲/下成佐登子,編曲/淡野保昌
松田聖子のシングル曲の歌詞として三浦徳子が最後に提供した〈夏の扉〉と同日発売の、同じ作詞家による良曲。ヤマハのポプコン出身でありながら、下成佐登子のこの楽曲は“シティ・ポップス”をきわめてわかりやすく衒いのない歌謡曲に翻案している。なお、彼女の配偶者はベーシストの亀田誠治である。
5.〈時をかける少女〉原田知世(1983)
作詞・作曲/松任谷由実,編曲/松任谷正隆
かつて、「ゆうべの夢は金色」という文句の凄みを正当に評価していたのは近田春夫である。したがって、〈時のカンツォーネ〉の企図は買うが、蛇足に該当する歌詞の改変はこの点を大きくスポイルしてしまう。松任谷自身による歌唱よりも、当の楽曲でデビューした原田知世の吹き込みにおける頼りなげな歌声のほうが、歌詞の繊細さを表現するにはやはりはるかに適切であろう。B面曲である〈ずっとそばに〉とあわせて、まぎれもない名盤。
6.〈迷宮のアンドローラ〉小泉今日子(1984)
作詞/松本隆,作曲/筒美京平,編曲/船山基紀
前作〈渚のハイカラ人魚〉でついにヒット・チャートの首位を獲得した小泉今日子が、〈まっ赤な女の子〉の筒美京平に加えて松本隆からの支援もえて、歌謡界における固有の存在性を確立した秀曲。『未知との遭遇』や『スターウォーズ』、ボイジャー計画などをきっかけに、とりわけ1986年のハレー彗星の地球への最接近に向けて、SF的な題材を歌詞に謳う歌謡曲がにわかに増加した当時、これもそうした機運に乗る楽曲のひとつとなった。
7.〈パラダイス銀河〉光GENJI(1988)
作詞・作曲/飛鳥涼,編曲/佐藤準
バブル経済と同期するように登場した半裸のローラースケート集団という異形の少年たちが、どれほど明るく装い、能天気にふるまおうとも、その無敵の勢いを駆って連発するヒット曲のいずれにも哀しみの響きが拭がたく纏われていたことは、いずれ到来するだろう陰惨な瞬間に対する単なる社会心理的な怯えのゆえばかりではないだろう。どこまでも光を追い求めずにはいられなかった彼らは、その歪な存在性に生来的な翳りを宿していたのである。
8.〈少女時代〉原由子(1991)
作詞・作曲/原由子,編曲/小林武史・桑田佳祐
いったん斉藤由貴に提供された楽曲だが、武部聡志の編曲によるそのヴァージョンは、いわば目傑作〈卒業〉の延長線上で奏でられたものであって、これを凌駕することはいかにも困難だった。それよりはむしろ、原由子のセルフ・カヴァー版のほうが楽曲の秀逸さを捕捉しやすいだろう。ただし、チャイム系や持続音系の音色の扱いはいかにも小林武史の編曲に定型的な常套句であり、いくぶんか辟易するところもある。パッヘルベルの〈カノン〉を思わせる弦による間奏は、桑田夫妻から山下達郎への目配せか。
9.〈ヘロン〉山下達郎(1998)
作詞・作曲・編曲/山下達郎
山下達郎にしては珍しく、歌謡曲の通俗的なキャッチーさを厭わない楽曲のうちのひとつ。ナイアガラ式の深いリヴァーブのもと、山下の歌声ははなから高音域で主旋律をたどる。それは音の靄を切り裂く青鷺の一啼の鋭利さそのものである。
10.〈裸の王様〉湯川潮音(2005)
作詞/湯川潮音,作曲/岸田繁,編曲/鈴木惣一郎
山下敦弘の監督による『リンダ リンダ リンダ』ではBase Ball Bear の関根史織やぺ・ドゥナとも共演した湯川潮音が、その出演の直後に発表した楽曲。大貫妙子の系譜を継ぐ歌声だが、いささか尖って聞こえる声質のかわりに、丸みをもたせた発音のもと子音を柔らかく、母音を深く響かせ、日本語の等時拍音的な性質が音声的な持続を区切り、切断してしまう懸念を回避する。子供ばんどのベーシストである湯川トーベンは父。
番外_1.キリンジ/KIRINJI
〈ニュータウン〉や〈朝焼けは雨のきざし〉、〈進水式〉や〈silver girl〉など、金銀財宝ザックザクのため番外とした。
自粛_1.〈金太の大冒険〉つボイノリオ(1975)
作詞・作曲/つボイノリオ,編曲/小池順一
Sugar Babeの《SONGS》にわずかに遅れて発表され、彼らとつボイはエレック・レコードにおいて同期となる。放送禁止歌のため自粛した。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





