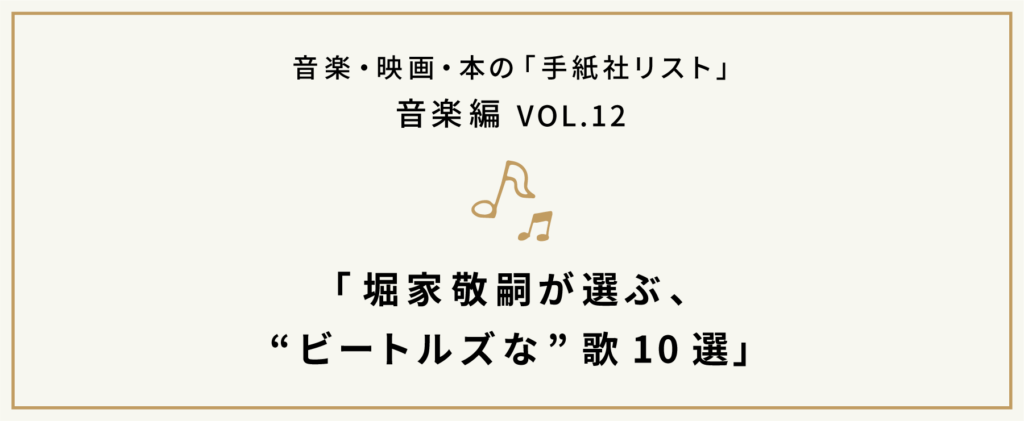
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。12回目となる音楽編のテーマは、なんとビートルズ。このFabulous Four(素晴らしき4人組)の登場以降、多くのアーティストが(ほとんどのアーティストが、と言ってもいいかも)その音楽性の影響を受けていますが、もちろん、それは日本のアーティストも然り。今回は、歌謡曲の中から、ビートルズを探してみます!
ビートルズを探せ!ヤァ!ヤァ!ヤァ!
〈SUKIYAKI〉
〈SUKIYAKI〉への改題のもと、〈上を向いて歩こう〉(1961)がイギリスでインストゥルメンタル作品として録音されたのは1962年のことでした。ケニー・ボール楽団によるディキシーランド調のこのカヴァー版は、翌年の早々には全英のチャートでトップ10に入っています。作曲した中村八大の才能の国際性を確信させたこの快打にあやかって、〈SUKIYAKI〉の表題は維持しつつ、しかし今度は坂本九が吹き込んだ原曲の音源をそのまま使用した盤が、ほどなくアメリカのキャピトル・レコードから発売されます。
たちまち全米のヒット・チャートを上昇したこの盤は、ついには『ビルボード』誌や『キャッシュ・ボックス』誌において、数週間連続してその首位に輝く快挙を達成することとなります。こうした経緯から、世界中でもっとも知られる歌謡曲ともなった〈上を向いて歩こう〉は、まさしくこの経緯のゆえに、ザ・ビートルズのアメリカへの登壇を妨げ、その成功を半年ほど遅延させる障壁として機能します。
ケニー・ボール楽団による〈SUKIYAKI〉が全英のチャートをにぎわしていたころ、〈Love Me Do〉(1962)でデビューしていたザ・ビートルズによる第2弾シングル〈Please Please Me〉(1963)が、これと競うようにチャートを急上昇していきました。EMI系列のレーベルの制作責任者として彼らを担当していたジョージ・マーティンは、やがて欧州に広まった彼らへの熱狂を新大陸にまで拡大すべく、縁のあったデイヴ・デクスター・ジュニアにザ・ビートルズのレコードのアメリカでの発売を打診します。
キャピトル・レコードのデイヴ・デクスター・ジュニアは、海外から新しい音楽を発掘する部門の責任者でした。しかしジャズに通じていた彼には、〈Love Me Do〉や〈Please Please Me〉につづき〈From Me to You〉(1963)もまたその嗜好にそぐわない不快な楽曲と映ります。アメリカの音楽市場には合致しないものと判断されたこれらの楽曲について、EMIとの業務提携によりキャピトル・レコードが優先的に保持していた販売権はここでいったん放棄され、ジョージ・マーティンはやむなく独立系のレーベルに〈Please Please Me〉と〈From Me to You〉の販売を委託するものの、売りあげは期待を損なうものでした(*1)。
かわりにデイヴ・デクスター・ジュニアが採用を決定し、キャピトル・レコードから発売され、英語以外の言語で歌われたものとしてアメリカで異例の大ヒットを記録した楽曲、それこそが、ほかならない〈SUKIYAKI〉こと〈上を向いて歩こう〉だったのです。キャピトル・レコードが東京芝浦電気レコード事業部と原盤供給契約を締結するにあたり1959年に来日経験もあった彼は、すでに《Rainy Night in Tokyo》(1961)で中村八大をアメリカに紹介してもいます(*2)。
水原弘の歌唱のもと、中村八大がはじめて作曲した楽曲のひとつである〈黒い花びら〉(1959)が第1回日本レコード大賞を受賞します。その余勢を駆って1960年に東京芝浦電気の部門から独立した東芝音楽工業は、渡辺プロダクションの原盤制作によりハナ肇とクレージーキャッツの〈スーダラ節〉を流通に乗せ、音楽産業の新しいありようを提示します。さらに、旧態依然とした体質のレコード会社ならば専属契約をもって自前の作曲家として囲っていただろう中村八大を、自由な立場に開いたかたちでその才能に賭けて支援しえたのも、新参であるにもかかわらず大企業に資本を担保された東芝音楽工業の境遇によるところでしょう(*3)。
それでもやはり、親企業である東京芝浦電気との不自由な関係性のなかで楽器や音響機器の販売なども背負わされた東芝音楽工業の業績は悪化し、その経営もたちまち危機に瀕していったといいます(*4)。そこで、いったんレコード事業のみに専念する体制を組織しなおしたうえで、けれどなお音楽に無頓着な人事を親会社から強いられ、東芝音楽工業はいっそうの苦境に陥ります。
〈抱きしめたい〉
苦境に喘ぐさなかの東芝音楽工業にとって、中村八大の作曲した〈上を向いて歩こう〉が、永六輔の日本語詞による坂本九の歌唱で録音された原盤のまま採用され、キャピトル・レコードの介入のもとアメリカで発売されたのみならず、世界的な規模でヒットしたことが、その収益を大きく改善する決定的な貢献となったことはいうまでもありません。
この時期、それまでアメリカの音楽市場には合致しないものと却下し、優先的に保持していた販売権さえ放棄するなど、ほとんど疎んでいたといっていいザ・ビートルズについて、キャピタル・レコードのデイヴ・デクスター・ジュニアは、ロンドンへの出張にあたりEMIで彼らの新曲として発表される予定だった楽曲を聴きます。そして一聴したこの〈I Want to Hold Your Hand〉(1963)をめぐり、彼は即座にアメリカでの販売を承諾します(*5)。ついに彼は、ここでザ・ビートルズのアメリカでの成功を確信したわけです。
ザ・クォリーメンから1960年にシルヴァー・ビートルズへと改名したジョン・レノンのバンドは、まもなくザ・ビートルズと称してドイツのハンブルクへ修業の旅にでかけます。そののち、彼らとマネージメント契約を結んだブライアン・エプスタインの野心的な慧眼と、ジョージ・マーティンによる音楽性の補完的な洗練が、彼らに対するイギリスでの、さらには欧州諸国での熱狂をやがて実現していきます。ザ・ビートルズが次にアメリカの巨大な市場を狙うのは当然でした。
ようやくデイヴ・デクスター・ジュニアが首肯したことで、1963年も残りわずかとなった11月末にイギリスで発売された〈I Want to Hold Your Hand〉が、年明けにはキャピトル・レコードのもとアメリカでも発売されることになりました。ところが、イギリスからの輸入盤が先行してアメリカのラジオで放送され、リクエストが急増するなどしたため、当初の発売日が前倒しされ、クリスマスを過ごしたばかりの新大陸に1963年のうちにキャピトル盤が登場します。
その大好評を皮切りに、1964年の2月には渡米のうえ、『エド・サリヴァン・ショー』への出演や屋内競技場およびカーネギー・ホールでの公演で間髪いれずに露出し、アメリカで顔を売ったザ・ビートルズは、その結果、『ビルボード』誌における4月4日の週のヒット・チャートで、上位から順に彼らの5枚のシングル盤が占拠するに至ります(*6)。前年の5月11日の週に〈SUKIYAKI〉が79位ではじめてチャートに入ってから、まだ1年も経過しないあいだの出来事でした。
ザ・ビートルズについて、イギリスの事情やアメリカの動向を現地の提携先から直接的に仕入れることのできた東芝音楽工業は、〈SUKIYAKI〉による快挙の余韻から醒める暇もなく、彼らを日本でデビューさせるための準備に着手します。株式を介した資本関係にあり、いわばEMIやキャピトル・レコードの日本での代理店だった東芝音楽工業が、当初は〈Please Please Me〉によるザ・ビートルズの日本解禁を計画していたところ、アメリカでの〈I Want to Hold Your Hand〉の急激な加熱ぶりに、臨時発売の体裁でこの楽曲を優先して発表する方針へと変更したことは、まさしくこの連携の賜物といえるでしょう(*7)。
ザ・ビートルズがアメリカに上陸したころ、日本では〈I Want to Hold Your Hand〉と〈Please Please Me〉がそれぞれ〈抱きしめたい〉と〈プリーズ・プリーズ・ミー〉の邦題であいついで発売され、東芝音楽工業の業績をさらに好転させる契機となります。
とりわけ、日本でのデビュー曲となる〈I Want to Hold Your Hand〉にあてがわれた〈抱きしめたい〉の邦題は、〈上を向いて歩こう〉が〈SUKIYAKI〉となってしまったことへの単なる意趣返しとするにはあまりにも秀逸です。ここには、とりわけ漣健児を中心として一連の“翻訳ポップス”において日本語が模索し、培われてきた、洋楽とのつきあいかたにかかわるひとつの様式の成熟が確認できます。
東京ビートルズ
〈抱きしめたい〉の臨時発売をもって日本でも正式にデビューしたザ・ビートルズですが、実情としては急遽の手配が届かず、結局のところ〈プリーズ・プリーズ・ミー〉のほうが先に各地のレコード店の店頭に並んでいたとの指摘もあります(*8)。
いずれにしても、このリヴァプール出身のバンドをめぐる日本におけるデビューのいきさつは、東芝音楽工業の立場上、アメリカにおける彼らへの熱狂と混乱について伝え聞くところを迅速に反映したものでした。ただし一般の聴衆にとっては、いまだ彼らの魅力を即座に味わいうるほどには日本は市場として未成熟だった一方で、東芝音楽工業の当事者に限らず英米の音楽事情にも敏感だった一部の業界関係者には、すでに彼らの評判が波及していたようです。
1964年の2月に展開されたこうした騒動は、新しいなにかの現われを示唆するものでした。その動揺のとにもかくにも鮮明なうちに、あるいはむしろ真の新規性が啓示されるまでに、未成熟の聴衆の鼓膜をかすめとらんとする怪しげな謀略の成立する余地が生じます。ザ・ビートルズによる真正の音響の到達にほとんど遅延なく、さらにはその浸透を待たず、日本ではこれをカヴァーする企画が早々に登場しています。東京ビートルズがそれです(*9)。
1964年の3月ににわかに結成されたこのグループは、4月下旬には〈抱きしめたい〉と〈プリーズ・プリーズ・ミー〉を抱きあわせたシングル盤をもってデビューします。これらはいずれも、ほかならない漣健児による日本語詞をあてがわれた“翻訳ポップス”であるとともに、管楽器が唸り、ときにクラベスの堅い音にラテンの情緒すら漂うジャズ編成のバンドに演奏を委ねた、いかにも前時代的なロカビリー調の吹き込みです(*10)。
英米の音楽事情にも敏感だった一部の業界関係者でさえ、ザ・ビートルズのアメリカにおける熱狂の正体については、作曲の能力に秀でた単なるロカビリーの一亜種とたかを括っていたふしがあります。もしくは、これまで“翻訳ポップス”なりの仕方で相応に対処してきたロカビリー的な要素それ以外のなにかを彼らの音楽から抽出できず、または聴こうとせず、結局のところその本質を捕捉しきれなかったあたりに、いわば認識論的な限界があったのかもしれません(*11)。
当事者だった漣健児こと草野昌一は、ザ・ビートルズの真価がもたらす潮流に乗れなかったことを悔やみ、これを契機に原盤制作ビジネスに着手します(*12)。
したがって、アメリカを熱狂させるさなかにあったザ・ビートルズの衝撃は、ここにはほとんど期待することができません。それどころか、これらの楽曲が日本語で歌唱されている事実に対する以上の困惑を、いま私たちは東京ビートルズに聴きます。というのも、いまだかつて耳にしたことのなかった新しさを追い、これに切迫するための機材や技量、なにより感覚が、イギリスやアメリカの最先端からはいかにも隔絶していた東京の現在を、その実際を、彼らの音源は如実に活写するものだからです。
リヴァプール出身のバンドがやがて日本にももたらすだろう衝撃、その新しさの意味の所在を音響そのもののうちに探究することなく、もっぱら海の向こうの熱狂に便乗する体裁でただ旋律ばかりを日本語でたどり、とりつくろうことに始終するならば、そこに象られる歌謡曲の輪郭はいよいよ卑屈なかたちに収束せざるをえないでしょう。
要するに、東京ビートルズは、あの〈あほ空〉(1928)以来、ジャズを頼りに歌謡曲が培ってきた“翻訳ポップス”の手法が通用する臨界点を露呈させたのです。そしておそらく、翻訳することの不可能な位相にこそザ・ビートルズの新しさの核心はあります。
エレキ
たとえばそれは、〈A Hard Day’s Night〉(1964)の冒頭で提示される、最初の不協和音の響きのことです。ジョージ・ハリスンのリッケンバッカー360/12とジョン・レノンのギブソンJ-160Eとが鳴らした和音を基調とするこの一撃は、単にFadd9だのG7sus4だのといったコード・ネームを賦し、もしくは音符で記譜するだけでは表現できません。それどころか、ザ・ビートルズ自身の演奏をもってしても同じものは再現できないはずです。にもかかわらず、当該の音盤を再生するごとにあの響きは反復を止めません。つまり複製技術によりその都度の出来が担保され、しかもそのことによってのみ経験可能なあの響きこそが、まさしく彼らの音楽の衝撃なのです(*13)。
もはや事態は、ひとり東京ビートルズのありように限定されるものではありません。どれほど緻密に、巧妙に模倣してみたところで、ザ・ビートルズの音楽は、ただ彼らだけが創造しうる出来事なのだから、いまや誰もが自らの音楽を創造することをもって以外にはザ・ビートルズの新しさに与することはできないわけです。
ところで、東芝音楽工業による〈抱きしめたい〉のジャケットでは、[演奏]でも[歌唱]でもなく「コーラス」の語をもってザ・ビートルズを紹介しています。
なるほど、楽曲に応じて歌唱の主導権をメンバーが分担する彼らの仕方は、それ自体が売り口上として誇示されるほど斬新なものだったのでしょう(*14)。とりわけ、ジョン・レノンとポール・マッカートニーの歌声は、ときにそのどちらが主旋律とも副旋律ともつかず複合的にからみあい、ある不可分な持続の塊として聴かれるものであることは確かです(*15)。
そのうえで、メンバーのあいだの不信や不仲が囁かれたバンドの最終期であっても、ジョージ・ハリスンを含めた3人がひとたび同じマイクを囲めば、彼らの歌声は、吹き込みに臨席した録音エンジニアが驚くほどの調和を響かせます(*16)。それらの極北が、《Abbey Road》(1969)に収録された〈Because〉の秀媚なコーラス・ワークであることに異論の余地はないでしょう(*17)。バンドとしてのザ・ビートルズの一体感は、つまるところ彼らの歌声の一体感に要約されていたのかもしれません。
こうした事情をみすかしたかのように、日本におけるエレキの時代の到来を牽引したのは、ザ・ビートルズに先んじて1965年の年始に来日公演を成功させたザ・ベンチャーズとジ・アストロノウツでした。ともにリヴァーブの深くかかった歪みのないエレクトリック・ギターの音を駆使するインストゥルメンタル・バンドであり、特にザ・ベンチャーズについては、東芝音楽工業との契約のもと、日本でのレコードの売りあげが急増し、ついにはザ・ビートルズのそれを凌駕するまでに爆発的なものとなります(*18)。
歌唱を、歌詞を、言葉を必要としない、楽器の演奏のみによる彼らの音楽の特性が、日本の聴衆にも音響そのものへの傾聴を促します。歌唱をきわだたせる単なる伴奏であることを放棄した彼らの演奏は、もはや歌声の欠落した不完全な歌謡曲ではありません。彼らの手もとのエレクトリック・ギターにおける弦の微かな振動は、いまやこれを電気的に増幅するアンプのスピーカー部分から発せられる響きの過剰にして余剰の肌理をもって、皮肉にも歌謡曲のありようを変容させることは不可避です。
実際に、当時の日本の聴衆が被った影響について、その体感をもとにザ・ビートルズよりもむしろザ・ベンチャーズからのものが甚大であったことを強調する言説は、けっして少なくありません(*19)。
大瀧詠一は、世界中がザ・ビートルズの天下だった時局になぜか日本でだけはザ・ベンチャーズの音楽が幅を利かせていた現実を、いわゆる“グループ・サウンズ”が前景化してくる時代の背景として重要視しています(*20)。
自作のラジオで最初に聞こえてきた楽曲がザ・ビートルズのものだったと述懐する鈴木茂でさえ、うまい歌い手がみあたらなくともバンドとして成立することや演奏の容易さなどから、ザ・ビートルズよりもザ・ベンチャーズに憧れたといいます(*21)。
矢沢永吉がザ・ビートルズを知ったのも、ザ・ベンチャーズの人気が圧倒的なさなかのことでした(*22)。
来日公演
ところが、ココナツ・バンクを主宰した伊藤銀次などは、ザ・ベンチャーズの大波に曝されつつもなお、彼らが歌わないことをもってまったく憧れるところがなかったとしてこれに抗い、エレクトリック・ギターを大音量でかき鳴らしながら歌うジョン・レノンの姿にザ・ビートルズの魅力を集約させます。あわせて彼は、エレクトリック・ギターに主旋律を歌わせたザ・ベンチャーズの音楽の単声的な性向に対して、ザ・ビートルズのそれが和声的であることを示唆してもいます(*23)。
ザ・ビートルズの歌唱がもたらす魅惑に囚われ、新たに歌い手を勧誘して結成されたファニーズも、本来はやはりザ・ベンチャーズに憧れて演奏活動を開始した学生集団でした。このときここに参加した沢田研二も、ザ・ビートルズの音楽の新鮮さに感動しつつ、けれどその緻密な組成が彼らの演奏の技量においては損なわれる懸念があったために、のちにザ・タイガースへと移行する彼らのグループではザ・ローリング・ストーンズの楽曲が演目の中心となったことを証言しています(*24)。
そしてついに1966年の6月末、ザ・ビートルズの日本公演が実現します。
RCサクセションのCHABOこと仲井戸麗市によれば、自身を熱狂させたザ・ビートルズの支持者は実のところ高校のクラスのなかでさえ数えるほどであって、ザ・ビートルズの日本公演における狂騒も、全国に拡散しているそうした少数が日本武道館へと局所的に参集した結果にすぎなかったといいます。したがって、彼らの衝撃はけっして日本中に共有されたわけではなかったようです(*25)。
ザ・ビートルズの4人が日本武道館に登壇するにあたって、彼らを歓迎するかたちでそろった日本のミュージシャンがその前座を務めました。ただしここでも、かつて東京ビートルズに覚えたものと同種の困惑が反芻されることになります。ザ・ドリフターズ、尾藤イサオ、内田裕也、望月浩、ブルー・ジーンズ、ジャッキー吉川とブルー・コメッツ。ここで彼らが披露したのは、リトル・リチャードやクリフ・リチャード、ジ・アニマルズやザ・ベンチャーズ経由のデューク・エリントンなど、基本的には英米の既成曲の演奏でした(*26)。
“翻訳ポップス”としてではなく、英語の歌詞をそのままシャウトする尾藤イサオの堂々たる姿勢には熱量が充満し、内田裕也の歌唱までが昂揚を隠そうともしません。加えて、彼らの伴奏も担当したジャッキー吉川とブルー・コメッツの技量は、〈If I Fell〉(1964)についてジョージ・ハリスンが自ら最低だったと失望してみせた当日のザ・ビートルズの演奏よりも、なお確かなものと誇れるところでしょう(*27)。
それでもやはり、困惑は残ります。のちの内田裕也が日本語に責任を押しつけるかたちで解消しようとしたもの、それがこの困惑だったのかもしれません。しかしながら、問題の所在はおそらくそこではないのです。実際に、インストゥルメンタルの楽曲におけるジャッキー吉川とブルー・コメッツの演奏からもそうした困惑が拭えないとすれば、それは、これが歌詞を綴る言語の問題ではないどころか、あわせて演奏の巧拙に依拠するものでもないことを意味するはずです(*28)。
ザ・ベンチャーズに加えてザ・ビートルズまでが来日し、日本武道館での公演が実現されたいま、海外の最先端の大衆音楽は、もはや日本人のミュージシャンたちによる翻訳を介した間接的な経験を待つまでもありません。日本にいながらにして手が届く、いわば実物による生演奏をもってこれを直接的に体験できる時代が到来したのです。
こうした観点からすれば、ザ・ビートルズの前座として披露された楽曲は、たとえそれが英語の歌詞で歌唱されようと、またどれほど巧みに演奏されようと、せいぜいが再現の精度の高い複製の域を超えることはないでしょう。仮に、たとえばここでザ・ビートルズによる衝撃をロックと呼ぶとして、このロックの輪郭を厳密にたどってみせたところで、そこにその本質としての新しさは屹立しようもないのです。
ロックと歌謡曲
そうしたなか、唯一、萩原哲晶の作曲による持ち歌〈君にしびれて〉(1966)を歌唱してみせた望月浩の場ちがいな清々しさは、困惑そのものをなんら糊塗することなく率直に露呈させ、これを観客に直視させる誠実なものでした。
だからこの困惑とは、おそらく、ロックの問題ではなく、あくまでも歌謡曲の問題にちがいありません。海外の最先端の大衆音楽を、海外に赴くまでもなく本人たちの演奏によって直接的に受容できる環境が日本でも成立しつつある以上、そこでは歌謡曲かロックかの排他的な二者択一は無効となるはずです(*29)。すなわち、純粋な、真正なロックを望む日本の聴衆は、いまや本場のロックのレコードを再生し、来日した本場の演者による実演を体験すればいいわけです(*30)。
したがって、日本の大衆音楽においては、ロックであるか否かが問題なのではなく、歌謡曲において、歌謡曲のなかで、歌謡曲をもっていかにロックになるかが問題なのです。単に責任を日本語に押しつけ、英語で歌唱されることをロックの要件と結論づけるだけではこの困惑への回答とならないことはもはや明らかでしょう。
とすれば、ザ・ビートルズの衝撃が歌謡曲のうちに組み込まれていく次第については、誰がどのようにザ・ビートルズの前座を務めたかという事実よりも、誰がなぜそれを務めなかったのかという事実を顧みることのうちに、その様相を省察できるかもしれません。
ザ・ベンチャーズの日本公演につづきザ・ビートルズの日本公演でも前座を務めることになったブルー・ジーンズからは、しかしその直前に、ふたりの主要人物が脱退しています。寺内タケシと加瀬邦彦です。
自ら牽引したブルー・ジーンズを病気を理由に脱退し、ほどなく個人事務所を設立する寺内タケシは、ベートーベンの〈運命〉をはじめ西洋の古典音楽をエレクトリック・ギターで奏でる独自の路線に、〈津軽じょんがら節〉をはじめ日本の民謡を演目として追加していきます(*31)。そうして彼は、歌謡曲とロックどころか、西洋の古典音楽も日本の民謡も、等しくその演奏のもと貴賎の予断を排し、エレクトリック・ギターの弦振動のうちに均質化してしまったわけです(*32)。
警備上の配慮から、前座を務める日本側のミュージシャンが自分たちの出番ののちにはただちに楽屋に戻され、ザ・ビートルズが登壇しているあいだは施錠のうえ彼らの演奏を鑑賞できないと知らされた加瀬邦彦は、これを逃せば再び彼らの生演奏を体験する機会はないものと怒りのあまりその場の椅子を蹴り、ブルー・ジーンズからの脱退を決意したといいます。前座として彼らと同じ舞台を踏む栄誉を諦め、客席から彼らの衝撃を目撃することを選んだのです。ザ・ビートルズに傾斜していた彼は、このころには、いままでの日本にはないポップな楽曲を自作自演すべく模索のさなかにありました(*33)。
そもそも、すでに1964年の東京オリンピックがらみの興行で、主催者が“リバプール・ビートルズ”を騙らせイギリスから招聘したザ・リヴァプール・ファイヴとの共演の際に、彼らに日本で最高峰のエレキ集団の演奏を誇示すべく自信満々の出番を終えて降壇したブルー・ジーンズの寺内と加瀬は、直後に交替で登壇した彼らが奏でた最初の響きを客席で耳にして、たちまち自信を喪失しています。このときのザ・リヴァプール・ファイヴの演目こそは、ほかならないザ・ビートルズの〈A Hard Day’s Night〉でした(*34)。
それまでに、同様の状況で体験してきたザ・ベンチャーズらの実演にも相応の驚きはあったものの、しかしこのときばかりは寺内も加瀬も、日本でほとんど無名のバンドによる借りものの楽曲の出音であるにもかかわらず、膝から崩れるほどの衝撃を受けたようです。まして本家のザ・ビートルズならばその衝撃はいかばかりともしれず、寺内はここで、歌唱をともなうことなく楽器演奏だけで聴かせるザ・ベンチャーズ流のエレキ集団の存在が、早くも時代遅れとなったことを悟っています(*35)。まだ見ぬザ・ビートルズへの加瀬の憧憬もここにはじまり、翌日からのザ・リヴァプール・ファイヴの客席には、その秘訣を探究すべくかまやつひろしらが出没しています。
“グループ・サウンズ”
これ以降、ザ・ビートルズの衝撃は、“グループ・サウンズ”が象られていくその周辺で歌謡曲への敷衍を試みられます。“グループ・サウンズ”の語が一般化するのは1967年の春先からとされますが、寺内タケシはこの語が自らの創発によるものと吹聴しています(*36)。
加瀬邦彦が歌ものとしてはじめて作曲し、安井かずみの歌詞により寺内タケシとブルー・ジーンズ名義で発表された〈ユア・ベィビー〉(1965)には、ザ・ベンチャーズの残響のなか浮揚するピーター&ゴードンの〈A World Without Love〉(1964)の幻影のうちに、ザ・ビートルズの衝撃がかいまみえます(*37)。
ザ・ビートルズの日本公演からわずか1ヶ月後には、自身の意向に適ったメンバーを率いる加瀬邦彦が、葉山マリーナのプールサイドに特設された舞台に招かれてこのグループで最初の演奏を披露しています。かつて加瀬にギターを教えた加山雄三の命名による、ザ・ワイルド・ワンズの登場です。ほどなく、〈ユア・ベイビー〉との両A面の体裁で彼らのデビュー盤〈想い出の渚〉(1966)も発表されます。
この楽曲で、「忘れはしないいつまでも」のフレーズを彩るコード進行Ⅱm−Ⅵ7−♭Ⅵ7−Ⅴ7における♭Ⅵの響きは、ザ・ビートルズにあってもとりわけポール・マッカートニーが好んで採用するものです。たとえば〈Hello, Goodbye〉(1967)ではⅠ/ⅠonⅦ −Ⅵm/ⅠonⅤ−Ⅳ/♭Ⅵ−Ⅰ、〈I Will〉(1968)では終盤のⅡm7/Ⅴ−♭Ⅵ−♭Ⅵ−Ⅰ、〈Oh! Darling〉(1969)ではサビのⅣ−♭Ⅵ−Ⅰ−Ⅰ7といった現われかたをします。
仮にここでジョン・レノンが参照された場合には、〈If I Fell〉や〈Nowhere Man〉(1965)、〈Across the Universe〉(1970)など、彼の楽曲でしばしばみられるように、♭Ⅵと平行調の関係にあるⅣmの響きが代入されていたかもしれません。とはいえ、これに先行する「小麦色した可愛いほほ」の旋律には、ジョン・レノンの歌唱を日本語に落とし込んだかのような節回しも認められます。
ザ・ベンチャーズやジ・アニマルズ、ザ・ビーチ・ボーイズらの来日公演で前座を務めた経歴のあるザ・スパイダースも、さすがにザ・ビートルズについてだけは本物の前で恥を曝したくないとして、田邊昭知やかまやつひろしらメンバーの合議によりその前座での出演を固辞しました(*38)。当日のかまやつは、前座で登壇した日本のグループによる演奏を客席で眺めながら、この判断が正当だったことを確信しています(*39)。熱狂に対するこの冷静な分別なくして、彼らが次代の日本の芸能界で中枢を占めることはなかったはずです。
なお、かつて在籍していたキャノン・ボールの解散にともない、かまやつひろしと加瀬邦彦はともにザ・スパイダースに加入しましたが、ブルー・ジーンズを結成した寺内タケシから勧誘された加瀬は、その数ヶ月後にザ・スパイダースから脱走のうえ寺内と合流しています。
田辺昭知とザ・スパイダースの名義による〈フリフリ〉(1965)は、単に“グループ・サウンズ”の発端とされるのみならず、これを日本のロックの嚆矢とする向きもあるところです(*40)。
ただし、頭打ちの、しかし4拍目だけは休止するスネア・ドラムと手拍子によるビートの強調が応援合戦の様相を呈するこの楽曲よりも、ザ・ビートルズからの直接的な影響は、同じ律動をリム・ショットに委ねた〈ノー・ノー・ボーイ〉(1966)に顕著です(*41)。「いってもいいかい」のフレーズには、〈Ticket to Ride〉(1965) における「She’s got a ticket to ride」の旋律をそのまま日本語で歌唱してみせたような、あの“翻訳ポップス”のごとき趣きさえ備わっています。
それでもなお、彼らの〈ヘイ・ボーイ〉(1966) や〈なんとなくなんとなく〉(1966) には、それぞれ〈Get Off of My Cloud〉(1965) や〈As Tears Go By〉(1965) の匂いが漂うなど、ザ・スパイダースにはむしろザ・ローリング・ストーンズとの共鳴を聴くべきかもしれません。なるほど、彼らが舞台でカヴァーしていた洋楽としては、ザ・ローリング・ストーンズよりもザ・ビートルズの楽曲のほうが演奏される機会が多かったとの指摘もあります(*42)。かまやつの作曲のもと自作自演を謳った彼らとしては、そこで参照された原典を自ら種明かしするわけにはいかないといった事情も邪推されます。
日本語とロック
沢田研二をはじめファニーズの面々も日本武道館の観客でした。
すぎやまこういちの作曲によるものとはいえ、ザ・タイガースとしての正式のデビュー曲となる〈僕のマリー〉(1967)は〈Michelle〉(1965) 、つづく〈シーサイド・バウンド〉(1967)は〈I Feel Fine〉(1964) 、〈シー・シー・シー〉(1968)は〈Twist and Shout〉(1963) 、加橋かつみの脱退を経て解散が既定路線となったころに、沢田研二の作曲により発表された〈素晴しい旅行〉(1970)ならば〈Day Tripper〉(1965) といった次第で、ザ・ビートルズの意匠は彼らの楽曲のそこここに組み込まれています。
にもかかわらず、このザ・タイガースの解散が象徴するように、ザ・ビートルズの衝撃が歌謡曲に十分に敷衍するのを待たず“グループ・サウンズ”の趨勢は窄んでしまいます。
その失調の理由のひとつには、“グループ・サウンズ”を騙る有象無象のグループの粗製濫造が挙げられます。それどころか、“グループ・サウンズ”の潮流に乗り遅れたあるレコード会社の邦楽部門のディレクターなどは、この趨勢が歌謡曲にこれ以上はびこり、日本の大衆音楽を席巻し尽くしてしまうことを懸念して、それを阻害し、この流行を人為的に終息させるべく、演奏力の酷い粗雑なグループをあえて市場に投入し、“グループ・サウンズ”の総体的な評価の低下を画策したともいいます。加えて、“グループ・サウンズ”の若者たち自身の奢りも作用しています(*43)。
また、〈ブルー・シャトウ〉(1967)で日本レコード大賞を受賞したのちのジャッキー吉川とブルー・コメッツが選択した方向性に典型的なように、さらにはザ・スパイダースの成功が〈フリフリ〉ではなく〈夕陽が泣いている〉(1967)によってもたらされた事実にみられるように、結局のところ、ロックの異物感を消化し吸収するには歌謡曲の聴き手がいまもって未熟だったことも、おそらくその理由となるでしょう。
旧態依然とした音楽産業の感度の鈍さとあいまって、“グループ・サウンズ”の志はザ・ビートルズの衝撃と土着的な磁場とのあいだで引き裂かれ、脱臼し、多様な形態や様式への分化と拡散を重ねて希薄化せずにはいられません(*44)。
歌謡曲において、歌謡曲のなかで、歌謡曲をもっていかにロックになるのか。その模索がザ・タイガースの解散によっていったん滞るころ、これと期をあわせるようにザ・ビートルズ自体も解散しています。
内田裕也とザ・フラワーズがFLOWER TRAVELLIN’ BANDへと再編され、《ANYWHERE》(1970)を発表したのも、またヴァレンタイン・ブルーがはっぴいえんどに改名して《はっぴいえんど》(1970)を世に問うたのも、まさしくそのときのことです。しかし彼らはむしろ、ザ・ビートルズの解散の先にあるロックの行方をすでにその音楽の射程に捉えていました。
“グループ・サウンズ”の終焉とともにザ・ビートルズの衝撃も霧散してしまうかに思われたなか、あくまでもそれに固執していたのは、ただの素人として日本武道館の公演を目撃した財津和夫が1970年に結成するチューリップです。その後にメンバーの大幅な変更を経て、漣健児こと草野昌一の新興音楽出版社が専属契約した最初の所属ミュージシャンとなり、1972年に東芝音楽工業からデビューする彼らの〈心の旅〉(1973)や〈夏色のおもいで〉(1973)は、ポール・マッカートニーによるザ・ビートルズ中期の傑作ポップスである〈Hello, Goodbye〉の面影を隠そうともしません(*45)。
なお、アグネス・チャンが歌唱した〈星に願いを〉(1974)は、これらチューリップの楽曲を介してザ・ビートルズにつながっています。
日本語のロック
他方で、これも1972年にデビューする矢沢永吉とジョニー大倉のCAROLは、ジョン・レノンを中心に初期のザ・ビートルズが耽溺していたロックン・ロールと歌謡曲のあいだで一定の折りあいをつけてみせます。
まだ自らがなにものとも知れない修業時代のザ・ビートルズの勢いとは、まさにロックン・ロールの勢いそのものであって、すなわちCAROLを踏み台に成りあがっていく矢沢永吉の姿勢それ自体でした。たとえば〈ファンキー・モンキー・ベイビー〉(1973)に認められるノリ、それは、もはやジャズのスウィング感でもファンクのグルーヴ感でもなく、あくまでもロックン・ロールのビート感の歌謡曲的な発動です。
矢沢と大倉の協働は、日本語の文言における語句を部分的に英語に置換したり、あるいは日本語を巻き舌で英語風に発音するなどの仕方で、不完全なかたちではあれ等時拍音の律動による束縛から歌詞を解放し、ロックン・ロールに吃る歌謡曲の摩擦を低減させます。
デビュー盤となった〈ルイジアンナ〉(1972)以来のこの体裁も、レコード会社からの最終的な要請に応じて、当初は英語で録音した歌詞を日本語に書き換えるにあたり採用された苦肉の策でした。このとき大倉は、矢沢の歌唱における発音を英語風に按配するために、歌詞の言葉を音韻へと分解したローマ字での表記を添付し、さらに節回しを矢沢に口伝したといいます(*46)。
熱狂もほどよく冷めたこのあたりで正当に歌謡曲に消化されはじめたザ・ビートルズの衝撃は、ようやくそこに溶け込み、その血肉となりつつあります。
いま私たちが東京ビートルズの音楽と対峙するにあたって困惑を覚えるのは、未知の出来事について、ことの本質を理解することなくその部分的な輪郭のみを抽出しながら、これを愚直になぞる描線のいびつさ、それを真剣にたどる姿勢のぎこちなさ、それらの滑稽なさまに悲哀を感じるとともに、そこにはほかならない私たち自身の姿が映り込んでしまっているからです(*47)。いうまでもなくそれは、必要な材料も技量も、知識も観点も満足に持たないまま、ありあわせのものでとにかく近代化を進め、西洋化に邁進してきた日本という国家の姿でもあります。
この意味からすれば、加藤和彦が率いたサディスティック・ミカ・バンドによる《黒船》(1974)はいかにも示唆的です。ザ・ビートルズの衝撃とは、明治維新以来ちょうどひとつの世紀を経た日本の大衆音楽に、日本語に、あるいはむしろ日本そのものにあらためて開放を迫る、いわば20世紀の黒船だったわけです。そして西洋近代の噂を耳にしつつ、まだ見ぬ黒船の衝撃に対抗すべくあらかじめ日本の側で練られた施策、それが東京ビートルズでした。
いびつにしてぎこちなく、滑稽にして貧相なその演奏に呆気にとられる私たち21世紀の聴衆は、しかしここで、単に明治維新がもたらしたひとつの世紀にわたる日本の近代のありように触れるのみならず、それが吹き込まれて以降の歌謡曲の半世紀をもそこに象ってるのです。
大瀧詠一は、東京ビートルズが背負ったこうした宿業を的確に看破し、歌謡曲に関与するひとりの表現者として、これが日本文化そのものの宿運でもあることを明確に自覚しています(*48)。
はっぴいえんどでの活動のさなか、彼が単独で発表したシングル盤〈空飛ぶくじら〉(1972)は、ザ・ビートルズの〈Your Mother Should Know〉(1967)の調子に全面的に覆われています。彼が音頭をとった《NIAGARA TRIANGLE VOL.2》(1982)において、杉真理が吹き込んだ〈Love Her〉および佐野元春が吹き込んだ〈Bye Bye C-Boy〉も、ともにこの楽曲に目配せしたものです。それどころか、杉の場合には、すでにMari & Red Stripesの名義による実質的なデビュー曲〈思い出の渦〉(1977)において、この楽曲への彼のより濃厚な頓着ぶりを示していました。
来生たかおやタケカワユキヒデなど、ザ・ビートルズの衝撃をその音楽のなかに抱えた日本のミュージシャンはいまなお多くいます。しかしながら、杉真理ほど率直にこれを自作曲のうちに語り、表現するものはいないでしょう。
やはり《NIAGARA TRIANGLE VOL.2》に収録された〈Nobody〉や〈ガールフレンド〉をはじめ、〈バカンスはいつも雨〉(1982)や〈あの娘は君のもの〉(1984)、〈Do You Feel Me〉(1987)といった楽曲群に加えて、彼が松尾清憲らとともに結成したBOXや、松尾のほか伊豆田洋之や元チューリップのメンバーらと結成したPiccadilly Circusでの活動にみられるように、彼の音楽にとってそれは、ほとんど自家薬籠中のものにちがいありません。
日本語もロック
桑田佳祐がSOUTHERN ALL STARS and ALL STARSの名義のもと発表した〈東京サリーちゃん〉(1990)の怪しさは、〈Sexy Sadie〉(1968)を起源に遡ることができるはずです。
矢沢永吉を支えるギタリストだった相沢行夫と木原敏雄によるNOBODYは、あわせて歌詞も提供したハウンド・ドッグの〈浮気な、パレット・キャット〉(1982)を端緒として、吉川晃司の〈モニカ〉(1984)やアン・ルイスの〈六本木心中〉(1984)、浅香唯が歌唱した〈セシル〉(1988)などの作曲者として知られます。ただし、堀ちえみに提供された〈涙色のエアポート〉(1984)よりもなお、彼ら自身による〈リバプールより愛をこめて〉(1982)にあっては、ザ・ビートルズの音楽が回顧の対象となる程度は顕著です。
杉真理や伊藤銀次がコーラスで参加した竹内まりやの〈マージービートで唄わせて〉(1984)や、かつて杉真理を発掘した平井夏美こと川原伸司が作曲に関与するThe Good-Byeの〈マージービートで抱きしめたい〉(1987)においても、ザ・ビートルズの意匠はいかにも回顧的に扱われています。
1985年から1987年にかけて、日産自動車のCMソングとして〈Here, There and Everywhere〉(1966)や〈Oh! Darling〉、〈You Never Give Me Your Money〉(1969)が採用され、お茶の間に流れました。ザ・ビートルズの全アルバムがいっせいにCD化され、まとめて発売されたのも1987年です。なお、予定されたウイングスでの日本公演がポール・マッカートニーの国外退去処分を理由に中止となってから10年後の1990年には、ソロ名義による彼の日本初公演が実現します。
つまるところ、日本武道館での演奏からほぼ20年を経て、ザ・ビートルズは、そうした新しいかたちのもとあらためて評価される機会をえたわけです。実際、ここでザ・ビートルズの音楽に触れた新しい聴き手は、ちょうどザ・ビートルズの熱狂とともに生まれた世代に重なります。このとき成人を迎える前後にあった彼らのなかに、すでにギターを手にしていたものや、さらにはこれを契機にギターを手にするものがいたことは当然です。
1964年の暮れに生まれた伊藤ゴローや高野寛をはじめ、1965年生まれの奥田民生や浜崎貴司、1966年生まれの斉藤和義やスガシカオ、吉井和哉、トータス松本、そして1967年生まれのYO-KINGや草野マサムネ、1968年の早生まれである寺岡呼人など、ザ・ビートルズの気配は彼らの音楽のそこここに察せられます。
なるほど、そのもっとも露骨な事例は、PUFFYに〈これが私の生きる道〉(1996)や〈MOTHER〉(1997)を提供し、自らも〈And I Love Car〉(2001)を発表している奥田民生にちがいありません。それでもなお、ボサ・ノヴァの響きを綴るギターの演奏を活動の基盤とする伊藤ゴローの音楽にあってさえ、たとえば〈Happiness〉(2010)にはそれが充溢しています。
そのうえで、いま、これらザ・ビートルズの熱狂とともに生まれた世代による音楽を聴いて育った次の世代が、もはやなんの衒いもなく自分たちの音楽のなかにザ・ビートルズの欠片を組み込むさまは、その響きが相応の仕方で消化され、吸収され、熟成したすえの、きわめて歌謡曲的な表現であるかもしれません。
すでに〈I’m In Love With You〉(2008)などTHE BAWDIESによる一連のロックン・ロールにおいては、かつてCAROLのジョニー大倉が腐心した日本語への対応をレコード会社から要請されることもなく、もれなく英語での歌唱が許容されます。
しかしこの世代にあって、おそらく他の誰のものより注目すべきは、毛皮のマリーズやドレスコーズを率いた志磨遼平の活動でしょう。そこには、フィル・スペクターやグラム・ロック、パンク・ロック、フレンチ・ポップスから“グループ・サウンズ”を含む歌謡曲などへの参照とともに、ザ・ビートルズの幻影が煌めくさまを確認することができます。
〈ちがいをみとめる〉
歌謡曲好みのコード進行のもと“アイドル歌謡”調に仕立てられたフレンチ・ポップス風の旋律や、それを囲むフィル・スペクター式の“音の壁”の効果に惑わされがちですが、ドレスコーズの〈ちがいをみとめる〉(2021)の冒頭でピアノが慎ましく奏でるⅤaugの響きを聴き逃すわけにはいきません。この開始の着想はまぎれもなく〈Oh! Darling〉から引用されたものです。
イ長調の〈Oh! Darling〉の場合には、これが主和音のAを導入するEaugの響きとしてただちに正当化され、その調性のうちに回収されます。このことを前提に、〈ちがいをみとめる〉の冒頭でもその響きが奏でられるならば、いまだ調性が確立されていない聴き手の鼓膜にこれがEaugとして届き、つづいてAの響きが導かれることへの期待が孕まれることは疑いないでしょう。
ところが実際には、これが導くのはAではなくFの響きであって、ここにようやく〈ちがいをみとめる〉の調性がへ長調であることが知れるとともに、今度は先のEaugの響きが主和音Fに対するⅤaugすなわちCaugとして遡行的に機能することになります。
これは、長3度の関係性にある3音を積んで成立するオーギュメント・コードの性質上、ある調におけるⅠaugとⅢaug、さらに♭Ⅵaugがまったく同じ構成音からなる響きを呈することを援用した、巧妙かつ知的な仕掛けです。つまり志磨遼平は、この性質のもと、楽曲の本来の調とは異なる〈Oh! Darling〉の調性をも〈ちがいをみとめる〉のうちに引用してみせたわけです。
洋の東西も品の貴賤もなく、あらゆる音楽を可能的に織り込みながら歌謡曲は持続してきました。そしておそらく、歌謡曲とは、その本性として変化することを止めないひとつの持続、ひとつの全体であるでしょう。たとえば筒美京平のような天命的な異能と器用さをもってして、その実現はもっとも高度の組み込みとして達成されもしたはずです。ドレスコーズの〈ちがいをみとめる〉もまた、そうした真性の歌謡曲のひとつの組み込みにほかなりません。
その宿業を背負うなか、適応のすべを練るにはいかにも即興的な対応を強いられたばかりに、ある種の奇態さだけが浮揚せざるをえなかったことは、いかにも東京ビートルズの音楽の不幸でした。いわばそこでは、もっぱら歌謡曲がロックたらんとあがく姿態の奇妙な響きのみが焦点化され、それがロックと響くことは困難です。
そうではなく、ロックに対して歌謡曲を歌謡曲たらしめる差異のかたちをそれと認めたうえで、これと真摯に向きあうことによって、歌謡曲において、歌謡曲のなかで、歌謡曲をもって、ロックになる瞬間がその持続のうちに招来されるにちがいありません。
ドレスコーズの〈ちがいをみとめる〉は、そうした仕方で歌謡曲の本質を謳歌する肯定的なまなざしのもと、東京ビートルズや“グループ・サウンズ”の楽曲をも輝かせる光源なのです。
*1 佐藤剛,『ウェルカム!ビートルズ 1966年の武道館公演を実現させたビジネスマンたち』, リットーミュージック, 2018, pp.73-79.およびpp.161-164.
*2 同書, pp.79-80.
*3 同書, pp.132-136.
*4 同書, pp.53-57.
*5 同書, pp.75-76.
*6 「Billboard Charts/The Hot 100/WEEK OF APRIL 4, 1964」(https://www.billboard.com/charts/hot-100/1964-04-04/), 『billboard』所収, Penske Media Corporation, 2022.
*7 佐藤, 前掲書, pp.170-190.
*8 大村亨,『「ビートルズと日本」熱狂の記録』, シンコーミュージック・エンタテイメント, 2016, pp.43-47.
*9 黒沢進,『日本ロック紀GS編 コンプリート』, シンコーミュージック・エンタテイメント, 2007, pp.5-6.
*10 大瀧詠一,『大瀧詠一 Writing & Talking』, 白夜書房, 2015, pp.693-695.
*11 北中正和,『ギターは日本の歌をどう変えたのか ギターのポピュラー音楽史』, 平凡社(平凡社新書), 2002, pp.167-173.
*12 濱口英樹,『ヒットソングを創った男たち 歌謡曲黄金時代の仕掛人』, シンコーミュージック・エンタテイメント, 2018, pp.17-18.
*13 ブラッド・トリンスキー+アラン・ディ・ペルナ,『エレクトリック・ギター革命史』, 石川千晶/訳, リットーミュージック, 2018, p.292.およびイアン・S・ポート,『フェンダー VS ギブソン 音楽の未来を変えた挑戦者たち』, 中川泉/訳, DU BOOKS, 2021, pp.317-327.
*14 きたやまおさむ,『ビートルズ』, 講談社(講談社現代新書), 1987, pp.45-49.
*15 トリンスキー+ペルナ, 前掲書, pp.259.
*16 ジェフ・エメリック+ハワード・マッセイ,『ザ・ビートルズ・サウンド 最後の真実』, 奥田祐士/訳, 白夜書房, 2006, p.386.
*17 同書, pp.455-458.
*18 佐藤, 前掲書, pp.230-235.
*19 稲増龍夫,『グループサウンズ文化論―なぜビートルズになれなかったのか』, 中央公論新社, 2017, p.84.およびpp.96-97.および濱口, 前掲書, p.165.
*20 大瀧, 前掲書, p.357.
*21 鈴木茂,『自伝 鈴木茂のワインディング・ロード はっぴいえんど、BAND WAGONそれから』, リットーミュージック, 2016, pp.32-45.
*22 矢沢永吉,『成りあがり How to be BIG』, 角川書店(角川文庫), 1980, p.56.
*23 伊藤銀次,『伊藤銀次 自伝 MY LIFE, POP LIFE』, シンコーミュージック・エンタテイメント, 2018, pp.28-33.
*24 磯前順一,『ザ・タイガース 世界はボクらを待っていた』, 集英社(集英社新書), 2013, pp.19-25.およびp.112.
*25 仲井戸麗市,『ロックの感受性 ビートルズ、ブルース、そして今』, 平凡社(平凡社新書), 2002, pp.31-33.
*26 大村, 前掲書, pp.310-311.
*27 トニー・バーロウ,『ビートルズ売り出し中! PRマンが見た4人の素顔』, 高見展ほか/訳, 河出書房新社, 2007, pp.281-282.
*28 磯前, 前掲書, pp.95-96.
*29 同書, pp.225-226.
*30 同書, pp.248.および加瀬邦彦,『ビートルズのおかげです』, 枻出版社, 2001, pp.111-114.
*31 寺内タケシ,『テケテケ伝』, 講談社, 2000, pp.52-55.
*32 マイケル・ボーダッシュ,『さよならアメリカ、さよならニッポン』, 奥田祐士/訳, 白夜書房, 2012, pp.185-192.
*33 加瀬, 前掲書, pp.8-19.
*34 同書, pp.29-36.
*35 寺内, 前掲書, pp.49-50.
*36 黒沢, 前掲書, p.14.および寺内, 前掲書, p.52.
*37 加瀬, 前掲書, pp.37-44.
*38 佐藤, 前掲書, p.321.
*39 ムッシュかまやつ,『ムッシュ!』, 日経BP社, 2002, pp.106-107.
*40 佐藤, 前掲書, p.389.および稲増, 前掲書, p.89.およびp.193.
*41 かまやつ, 前掲書, pp.88-89.
*42 稲増, 前掲書, p.22.
*43 黒沢進,『日本の60年代ロックのすべて COMPLETE』, ウルトラ・ヴァイヴ/シンコーミュージック・エンタテイメント, 2008, p.249.
*44 かまやつ, 前掲書, p.107.
*45 佐藤, 前掲書, pp.331-332.
*46 ジョニー大倉,『キャロル 夜明け前』, 主婦と生活社, 2003, pp.175-180.
*47 大瀧, 前掲書, pp.384-385.
*48 同書, pp.688-699.
堀家教授による、私の「ザ・ビートルズ的」10選リスト
1.〈ノー・ノー・ボーイ〉ザ・スパイダース(1966)
作詞/田辺昭知,作曲/かまやつひろし
〈Ticket to Ride〉における「She’s got a ticket to ride」のフレーズをなぞるような「いってもいいかい」の旋律につづいて、今度は〈I’ll Be Back〉の「I’m the one who want you」のフレーズを思わせる「イェイェイェイェ ベイビー」の旋律、さらにこの先のブリッジ部分では〈If I Fell〉につうじるエレキギターによる2連3拍くずれのリズムが施されるなど、ザ・ビートルズのイディオムが随所に嵌め込まれている佳曲。
2.〈空飛ぶくじら〉大瀧詠一(1972)
作詞/江戸門弾鉄,作曲・編曲/夛羅尾伴内
大瀧詠一が関与した作品のなかで、金沢明子が歌唱したカヴァー盤〈イエロー・サブマリン音頭〉を除きもっとも直接的にザ・ビートルズからの影響を表現した楽曲である。その全篇をとおして、無防備なまでに率直に〈Your Mother Should Know〉の響きが参照されている。やがて彼の主導する《NIAGARA TRIANGLE VOL.2》に参加する杉真理や佐野元春も、この響きに共振する〈Love Her〉や〈Bye Bye C-Boy〉をそこで提供しているが、とりわけ杉については、実質的なデビュー曲〈思い出の渦〉がやはりこれを明確に引用している。江戸門弾鉄は大瀧の単独によるプロジェクトに参加した際の松本隆の別名。
3.〈夏色のおもいで〉チューリップ(1973)
作詞/松本隆,作曲/財津和夫,編曲/川口真・チューリップ
松本隆の職業作詞家としての最初期の提供作品のひとつ。前作〈心の旅〉で歌唱を姫野達也に譲った財津和夫が、ここで歌詞までも他人に剥奪されることとなり屈辱的な思いをしたともいう。しかし、松本によるここでの歌詞が彼の業績のなかでも屈指の傑作であろうことは疑いない。一方で、財津による作曲は、〈心の旅〉につづき〈Hello, Goodbye〉への執心が顕著である。そして彼と松本とのこの協働が、のちに松田聖子の〈白いパラソル〉へとつながる。
4.〈涙のテディ・ボーイ〉CAROL(1974)
作詞・作曲/矢沢永吉,編曲/大野克夫
冒頭では「Ah」の歌いだしから〈Eleanor Rigby〉を存分に意識させながら、しかしストリングスをエレキギターのフレーズに置換するなど、ザ・ビートルズの場合のような重厚で深刻な響きは回避される。そののちも、〈Twist and Shout〉にも似たコーラス・ワークを採用し、また途中でベースを中心に〈Something〉のものを模したリズムのブリッジが挿入され、ついには〈She Loves You〉式のエンディングを迎えるなど、元ザ・スパイダースの大野克夫によるコラージュ的な編曲が冴える。なお、最初に発売されたシングル盤では作詞者は「矢沢永吉」となっているが、のちに再発売されたレコード盤のジャケットではこれを「大倉洋一」すなわちジョニー大倉とするクレジット表記もある。さらに、楽曲の題名さえ〈涙のテディー・ボーイ〉とするものもみられるなど、当時のフィリップスレコードによる場あたり的な対応は褒められたものではない。
5.〈気絶するほど悩ましい〉Char(1977)
作詞/阿久悠,作曲/梅垣達志,編曲/佐藤準
なにしろギターまでが泣くのだからもともと歌謡曲になじみやすい〈While My Guitar Gently Weeps〉は、イ短調からイ長調への転調など、構造ばかりか調性も変えられることなくほとんどそのまま歌謡曲に移植される。とりわけ、ともに転調後のサビで展開するA−C#m−F#m−C#mのコード進行は、ここで本来の歌謡曲らしさを遺憾なく発揮してみせるのだから、同時期に発表された原田真二による〈キャンディ〉における〈Michelle〉らしさよりもなお、この歌謡曲性が本格的なエレクトリック・ギター奏者であるCharの楽曲に採用されたことのほうが、よほど意義のある事実として指摘されるべきものと考えられる。
6.〈マドンナ〉杉真理&Red Stripes(1978)
作詞・作曲/杉真理,編曲/杉真理&Red Stripes
〈You’re Going to Lose That Girl〉をよりポップに、よりハードに換骨奪胎した、杉真理の初期の良曲。さまざまな洋楽の消化に努め、高感度のシティ・ポップス的な洗練への探究を印象づけるバンド名義時代の彼の作品のなかにあって、のちのソロ名義の作品群につながるザ・ビートルズに対する憧憬が隠しきれないぶん野暮な感触が、ここでは楽曲の力強さに加担している。《SWINGY》に収録。なお、これと類似した楽曲に、ALFEEによる〈恋人になりたい〉がある。
7.〈彼女はデリケート〉佐野元春(1982)
作詞・作曲・編曲/佐野元春
《NIAGARA TRIANGLE VOL.2》では杉真理による楽曲があまりも明瞭にザ・ビートルズの響きを反映しているがゆえに看過されがちだが、大瀧詠一が自ら告白しているように、このアルバムにはザ・ビートルズを中核としたいわゆるリヴァプール系の音楽が通奏低音として共有されている。佐野元春が担当した楽曲のなかでは、その終盤で〈Twist and Shout〉が導入され、彼の疾駆するビートのうちにザ・ビートルズの衝撃を消化し、吸収したさまを謳う〈彼女はデリケート〉がその典型であろう。沢田研二への提供曲の自身によるカヴァー版でもある。
8.〈愛しのロージー〉松尾清憲(1984)
作詞/秋元康・松尾清憲,作曲/松尾清憲,編曲/白井良明
ムーンライダーズのギタリストである白井良明によるシンセサイザーを多用した厚みある編曲は、ザ・ビートルズのフォロワーであるジェフ・リンのE.L.O.による電子仕掛けのポップなロックをも思わせる。もっと評価されていい秀曲。
9.〈東京サリーちゃん〉SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS(1990)
作詞・作曲/桑田佳祐,編曲/T.KOBAYASHI&K.KUWATA
《稲村ジェーン》に収録。音場のかたちそのものが〈Sexy Sadie〉を参照しているばかりか、歌詞さえももっぱら「Sexy」の語に吸引されて猥雑に綴られるなど、ザ・ビートルズへのここでの共鳴ぶりは、“グループ・サウンズ”における模索とは隔世の感がある。なお、KANがASKAを迎えて制作した〈予定どおりに偶然に〉のピアノによる前奏は、〈Sexy Sadie〉の輪郭をより明瞭に流用している。
10.〈ちがいをみとめる〉ドレスコーズ(2021)
作詞・作曲・編曲/志磨遼平
志磨遼平におけるザ・ビートルズのありようについては、この楽曲の最初にピアノで鳴らされるオーギュメント・コードの響きがすべてを物語っている。《バイエル》収録。
番外_1.〈ALGO〉伊豆田洋之(1989)
作詞/津島健太,作曲/伊豆田洋之,編曲/西本明
ザ・ビートルズというよりもポール・マッカートニーによる影響が顕著なため番外とした。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





