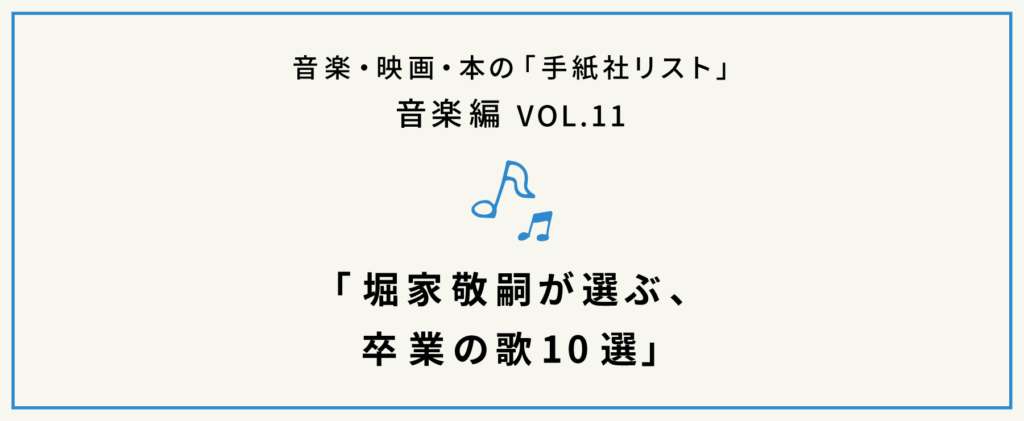
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。11回目となる音楽編のテーマは「卒業」。小学校、中学校、高校の卒業式で、涙ながらに歌ったあの曲。世代によっても、異なりそうです。そういえば、いつから卒業式で歌うようになったんでしょう? そんな話も飛び出すか? 堀家教授の講義、まもなく開講です!
歌謡曲とともに去りぬ
卒業式
「ちっちゃな頃から悪ガキ」だった「俺」が、「卒業式」に「何を卒業するのだろう」と問うてみたのは、チェッカーズのデビュー曲〈ギザギザハートの子守唄〉(1983) においてのことでした。「卒業式」なのだから、さしあたって彼は学校を「卒業」していくにはちがいないのでしょう。実際、彼はその「夢」を「机で削られ」たといいます。それでもなお、彼の「熱い心をしば」っていたかもしれないこの「机」に集約される学校からの「卒業」にあたって、自由を満喫し、解放感に浸る悦びを謳う気配は微塵もそこにうかがえません。
日本における卒業式の歴史は、いうまでもなく、西欧列強に倣って近代化を志す過程で導入された学校制度とともにはじまります。異国の脅威に開国を強いられた日本を近代国家たらしめんとする明治政府がなにより優先させて組織化したもの、それは、兵力すなわち軍隊であり、ここでは上意下達の指揮系統を有効に機能させるための規律的な秩序が求められました。
これにつづいて全国的に組織化された近代的な体系こそが、教育すなわち学校でした。教育とは、新しいなにごとかについて、これを知る師がそれを知らぬ徒に学修させることにほかなりません。そしてここで日本は、近代的な体系の導入をもって近代とはなにかを体得していくことにもなります。
ある組織に所属する構成員のあいだで秩序づけられた関係性を可視化し、それぞれの役割りにそったふるまいの次第を確認するためには、それ固有の儀式が必要です。卒業式とは、師の側が徒の側における学修の成果を承認する儀式であって、この承認こそが師を、学校を権威づける力能となるはずです。
記録に残る日本での最古の卒業式は、1876年の陸軍戸山学校が実施したものとされます(*1)。そこでは西洋式の楽隊が奏でる音楽の響くなか、西洋式の装束に身を整えた参加者たちが集い、よく学修をなしえた徒に銀時計を授与する表彰もあったといいます。学校と軍隊の交点として、あるいはむしろ学校から軍隊への移行の踏み台として、近代的な組織体系における規範を明示する儀式、それが卒業式だったわけです。
さらに1877年の歳末には、前身の諸教育機関を統合してこの年に開校したばかりの東京大学が卒業式を挙行しています。1879年に東京音楽学校の前身となる音楽取調掛が設置され、戦後の東京藝術大学音楽学部へとつながる礎となります。
1871年に施行された廃藩置県の翌年にはすでに「学制」が頒布され、ここに音楽教育としての「唱歌」の重要性が説かれたものの、教材や教員、指導法など、そもそも教育すべき西洋式の音楽に対する明治政府の知見はあまりにも貧弱でした(*2)。音楽取調掛は、その発足をもってようやく教科としての「唱歌」の具体化に着手し、最初の音楽教科書となる『小學唱歌集』3編を1882年から1884年のあいだに出版しています。とはいえ、そこに掲載された楽曲は、そのほとんどが欧米の民謡や讃美歌、歌曲など、既成の洋楽を収集し、これに日本語の歌詞をあつらえたものでした(*3)。
これらについては、単に歌詞における原語から日本語への文言の翻訳のみならず、文化の翻訳をも含んだ事象として、いわば広義の“翻訳唱歌”と理解することは可能でしょう(*4)。この「唱歌」を全国の教育現場に普及させる過程で、それは卒業式にも導入されることになります。東京師範学校などに掛員を派遣し、卒業式のための「唱歌」歌唱の指導や当日の演奏を担当させたほか、音楽取調掛で学修した学徒の卒業にあわせて彼らの成果を演奏や歌唱として発表させています(*5)。
唱歌
音楽取調掛の最初の御用掛に着任したのは、近代国家にふさわしい人材育成という観点から教育行政を実地で修得するために文部省より派遣され、アメリカに留学していた伊澤修二でした。1881年にはその掛長、1886年には文部省の編輯局長となって、翌年の東京音楽学校の創立を実現し、その初代校長に就任しています。
人格の形成にあたって幼児教育や初等教育における「唱歌」の重要性を把握していた彼が、しかし留学先となったアメリカの大学で唯一、その修業に難儀した科目、それは、ほかならない「唱歌」でした。なぜなら、それまでの日本における音楽の体系とは、7音から構成される西洋式の音階からすれば4音目と7音目に相当する[ファ]と[シ]の抜けた、いわば不完全なものだったからです。
彼にとって、西洋の音楽を修得することとは、なによりもまず西洋の音階を修得することでした。歌唱する行為をとおして彼が直面した近代的な文明のありようとは、すなわち西洋の音階の響きであり、あるいはむしろ、これこそが彼にとっての近代そのものだったわけです(*6)。
その響きは、従来の伝統的なものとはまったく異なる響きとして、西洋に由来する近代的な諸体系の新しさを、それゆえ明治政府が掲げる新しい国家の行方を、ここに国民として統合される民衆の新しいありかたを、音のかたちで表現しました(*7)。
伊澤修二を中心に編まれた『小學唱歌集』は、その3編を構成する91曲のうち半分以上はいまだ原曲がわかっていません(*8)。しかしながら、そのほとんどが外国の歌の旋律であることはまちがいないものと考えられます。
なぜなら、編纂した伊澤自身の経験が語るように、西洋の音階にのっとってそうした旋律を綴れる人材が当時の日本にはまだいなかっただろうからです。たとえば瀧廉太郎が作曲した〈花〉が発表されるのは、ようやく1900年になってのことであり、その翌年に彼はドイツへの留学に赴いています。
西洋式の「唱歌」について、文部省の趨勢もはじめは冷淡だったといいます。このため、伊澤らは儒教的な徳育を歌詞に謳い込んだ「唱歌」の選定に努め、国家の存立に寄与する音楽教育の意義を強調します。来賓が集う卒業式における「唱歌」の斉唱には、その貢献を披瀝する機能が期待されてもいました(*9)。さらに、そうした人前での「唱歌」の斉唱は、個人の属性を示す発音の偏りを一定の基準のもと均質化し、また大きく口を開いて発声することへの羞恥を払拭するなど、歌声を介して集団を統率し、近代的な組織の編成を基礎づける効用も認められます(*10)。
そうしたなか、当初から卒業式で歌われる機会の多かった「唱歌」が〈蛍の光〉でした(*11)。1883年の音楽取調掛の卒業式に相当する期末演奏会にて最終曲として披露された例をはじめ、1887年には皇后が臨席した華族女学校の卒業式で生徒全員がこれを斉唱しています(*12)。いずれも7月のことです。なお、卒業式ならずともすでに皇后は、1881年に東京女子師範学校に行啓した際に、まだ歌詞の定まっていない状態のこの「唱歌」を耳にしています(*13)。
また、1884年の東京師範学校では、小学師範科の「唱歌」の試験に〈蛍の光〉の独唱を課したとされます。教員養成の課程を修了したこれら中央の学校の卒業生たちこそが、卒業の儀式性を〈蛍の光〉とともに地方へと伝播させ、日本各地の子どもたちの師となってこれを普及させるメディアだったわけです(*14)。
〈蛍の光〉と〈仰げば尊し〉
〈螢〉の題名で『小學唱歌集』の初編に収録された〈蛍の光〉の歌詞は、音楽取調御用掛の伊澤修二が兼任で学校長を務めていた東京師範学校において和文と国史の教員だった稲垣千頴が、伊澤に請われ音楽取調掛員として作詞したものです(*15)。〈蛍の光〉は、スコットランドの伝承曲であり、讃美歌にも応用された〈Auld Lang Syne〉の旋律を採用した「唱歌」であることが知られています。実際、戦時の1943年には〈Auld Lang Syne〉が敵性楽曲とみなされたことから、〈蛍の光〉も演奏できなくなったといいます(*16)。
1949年には、戦後の新しい検定制度にのっとった最初の小学校5年生の音楽教科書に掲載されますが、このとき、稲垣千頴による歌詞のうち1番と2番のみが残され、3番と4番は削除されます。というのも、蛍雪に照らして書を読む日々を重ねてついに学び舎や在校生との別れの今朝を迎えた卒業生が、ともに幸福を願って歌う1番や2番の歌詞の調子とは明らかに異なり、その3番と4番では、まさに近代国家のかたちとして確定しつつあった国家の空間的な領域、要するに領有権を承認された国土の確保と維持のために勇ましく尽力すべきと謳われていたからです。
つまるところ、学び舎を出立するのも、在校生との別離も、さらには蛍雪に照らして書を読み学ぶ日々のすべてがまるごと、3番や4番の歌詞が謳う国家主義への献身的な奉仕を準備する愛国的な人民のありようだったわけです。
ところで、小学校においてそれまでは半年だった一等級の標準学修時間が1年の学年度となり、そのうえで4月の始業と3月の終業が全国的に統一されたのは、1892年のことでした。共通の学年歴にしたがって全国で一斉に実施される3月の卒業式は、式次第も定型化させながら、4月に開催される入学式とともに春の重要な学校行事として定着し、ここにこの季節をめぐる自然のさまざまが人びとの感傷を象る資格を獲得します(*17)。
同一の規律のもと、相応の歳月のあいだ一定の方向をめざして机を並べ、ともにすごした同級生たちは、そもそも成育段階のほとんど変わりない同じ年度の生まれであって、彼らは人格が形成されるこの過程で互いに共感しあい、その情緒をもわかちあう関係性を築きます。こうした情緒を、とりわけ別離という来たるべき状況ゆえにもっとも感傷的に共有する最後の儀式、それこそが卒業式なのです(*18)。
そのような場面にあって、いわゆる“ヨナ抜き”の5音によるペンタトニック・スケールで成立している〈蛍の光〉が歌われるとき、西洋の楽曲でありながらその旋律に吃ることなく斉唱できたことも、彼らが存分に感傷に浸り、涙を介して情緒をわかちあい、最後の共感を音声のうちに身体化することに有利であったかもしれません。
こうして国家の姿は隠蔽され、かわって学校での経験を想い出として整理する言葉が、卒業をめぐる「唱歌」の歌詞に綴られることになります。『小學唱歌集』の第3編に採録された〈あふげば尊し〉、すなわち〈仰げば尊し〉がこんにちの卒業式に至ってなお歌い継がれていることは、そうした事情と無縁ではないでしょう。
〈仰げば尊し〉は、久しく出典が不明でしたが、近年ようやくその原曲が同定されました。1871年ごろにアメリカで出版された歌集『The Song Echo』のための新作のひとつとして、〈Song for the Close of School〉の題名でここに記譜されたH.N.D.の名義による旋律が、〈仰げば尊し〉のそれと合致したのです(*19)。実際、『小學唱歌集』の編纂を統括した伊澤修二が、その第3編に着手するにあたりこの歌集を参照したことをうかがわせる資料ものちに確認されています(*20)。
原曲の題名が示唆するように、「We part today」からはじまるその英語詞は、「friends」や「Farewell」、「The school-room」、「When schoolmates say “Good bye”」など、ともに学び舎から巣立っていく級友たちとの惜別の表現に満ちており、あらかじめこれが卒業式のような場面で歌われることを想定して作られた楽曲であることの証左となります(*21)。ニューヨーク州の地方の名士だったティモシー・H.ブロズナンによるこの歌詞の趣旨は、逐語訳ではないものの、およそ〈仰げば尊し〉の日本詞にも反映されているところです。
桜
〈仰げば尊し〉の歌詞は、〈蛍の光〉の稲垣千頴とすれちがうかたちで音楽取調掛に異動してきた大槻文彦を含め、3人の掛員の合議により成立したものでした。
〈蛍の光〉が戦後の検定制度にのっとった最初の小学校5年生の音楽教科書に掲載されたとき、これと呼応するように小学校6年生の音楽教科書には〈仰げば尊し〉が掲載されています。この事実は、いうまでもなく、卒業式にあたり在校生が〈蛍の光〉を卒業生へのはなむけとし、卒業生が〈仰げば尊し〉を在校生への形見とすることで、この儀式における劇的な構成の定型化を勧奨するものです。
なにしろ〈仰げば尊し〉の3番の歌詞などは、〈蛍の光〉に倣って故事より[蛍]や[雪]の語を借り、その歌詞の文脈を組み込みながら綴られています。いわば送辞と答辞に相当する唱歌の斉唱のこうした応酬こそが、卒業式を感動的な行事に仕立てつつ、単にそれまでの学校生活のみならず卒業式そのものをこそ、涙まじりの感傷的な想い出とする誘因となるにちがいありません(*22)。
さて、「唱歌」に限らず、卒業や入学を契機とした別れや出会いの時期をめぐって歌唱される類いの楽曲について、昨今ではこれを“桜ソング”などと呼ぶ向きもあります(*23)。
しかしながら、[桜]の風情は〈蛍の光〉にも〈仰げば尊し〉にも詠われていません。おそらくこれは、『小學唱歌集』が出版され、これら「唱歌」が成立した当時には、まだ小学校における一等級の標準学修時間が1年の学年度となっておらず、卒業や入学の時期が[桜]のころに固定されていなかったからでしょう。つまり当時の卒業式において[桜]はその必要条件でも構成要素でもなく、それゆえ卒業を象徴する記号としてこれが機能しうるのはそれ以降のことです。
そればかりか、このころにはまだ、春先の校庭に[桜]の花が咲きほこっていたわけでは必ずしもないようです。
いま、日本の[桜]の8割ほどがソメイヨシノであるとされます(*24)。ソメイヨシノは自然交雑ないし人工交配により生まれた園芸品種であり、それとして同定されたのが1890年、正式に命名されるのはようやく1901年になってからのことです(*25)。ただし、1880年ごろには東京で流行し、こんにちもなお[桜]の名所として知られる上野公園や隅田川堤、さらには神田川堤への植樹が確認されています。とはいえ、やはり当初は本数もまばらなうえ若木であったはずです。
靖国神社の境内では、おそらくすでに生育していたものに加えて、1892年前後に520本あまりのまとまった植樹があったようです(*26)。ソメイヨシノは成長が早く、接木ないし挿木から10年もすればそれなりに花をつけ、20年後には爛漫と咲くことから、東京の各所で植樹された若木も、そのころには成木となって花吹雪を散らせていたにちがいありません。
地方では、廃藩にともない空隙化した城址が軍の駐屯地や警察署の用地として転用され、また官公庁舎や学校、公園もその近辺に設置されます。その環境造成にあたって、東京で流行し、活着がよく成長の早いソメイヨシノの特性が積極的に採用され、[桜]が公共空間の春を彩るものとして日本各地に伝播していきます(*27)。
とりわけ、1894年の日清戦争から1904年の日露戦争にかけて、各地で鎮魂のための公園や石碑の整備事業が推進されます(*28)。そうした需要の増大にソメイヨシノの特性は重宝し、この単一の品種のみによる集中的な植樹の結果として、[桜]が並木状に列植された景観が一般化していったものと考えられます。
ソメイヨシノは、種子から育成される実生ではなく、唯一の原木から採取された枝からの接木ないし挿木により増殖した品種であるため、すべての個体について開花の条件も花の色もほとんどちがいがありません。近隣の地域においてソメイヨシノはいっせいに咲き、またいっせいに散るわけです。並木状に列植されたこの[桜]の蕾がふくらみ、ひとたび開花の時期を迎えたとき、あたり一面はいっせいにこの花の色に染まっていき、そこから10日間ほどで今度はいっせいに花吹雪の舞う光景となるのです。
単に[桜]といえど、多くの品種が混合して植樹されていればこうはいきません。品種ごとに開花の時期がずれるからです。
散り行く花
いっせいに咲き、いっせいに散るソメイヨシノの群生に彩られる春のこうした景観が、しかもその成長の早さと活着の容易さ、および国土の開発にともなう公共空間の環境整備における需要のもと、日本各地にいっせいに広まったこと。これが、それまで[桜]に含蓄されてきた多義性をひとつの方向性へと収斂させる契機となります。
これ以降、[桜]のありようを日本人の精神性の表象として特権化し、ここに帝国主義的な忠信を反映させ美化するような比喩による喧伝が、国家の行方をめぐって軍国主義へと大きく舵をとっていきます(*29)。
たとえば『小學唱歌集』には、〈仰げば尊し〉の歌詞を担ったひとりでもある加部厳夫が作詞した〈霞か雲か〉がその第2編に収録されています。ここで「にほふ」その「花ざかり」を[霞]か[雲]か、それとも[雪]かとたとえられる[桜]は、眺望の輪郭を依然として曖昧にしたままでした(*30)。なお、加部はその眺望を[桜]のものと明言していませんが、同一の旋律のもと勝承夫により改変された1947年の歌詞では、この「花ざかり」は「桜」のものと特定されます。
幼稚園児のための本邦はじめての唱歌集として音楽取調掛が編纂し、1887年に出版された『幼穉園唱歌集』が収録した〈數へうた〉の歌詞には、すでに「二つとや。二つとなきみぞ。山櫻。山櫻。/ちりてもかをれや。/きみがため。きみがため」の表現が確認できます(*31)。ここで「山櫻」に要請された「きみがため」に「ちりてもかを」ることが、ソメイヨシノの拡散とともに、「かを」ることよりはむしろ「ちり」ゆくことを強調するかたちで全体主義に濫用されることになります。
志賀重昻が『日本風景論』を著したのは、まさに日清戦争が勃発した1894年のことです。ここで志賀は、その美しさを否定はしないものの、爛漫の[桜]の花が風雨に耐えずたちまち乱落し、泥にまみれてしまうあたりを理由に、日本の険しく厳しい風土にひとり晒されてなお常緑を誇る松の力強さこそが、[桜]の花よりなお国民の性質に適合するものと主張しています(*32)。
そこではまだ[桜]は、その散りぎわについて必ずしも潔さを強調されるものではなく、「きみがため」に「ちりてもかを」る軍国主義的な精神性を背負いきってはいなかったわけです。ただし、対称性に均衡を欠くことも厭わず、ここで志賀が、樹木としての[桜]ではなく、あくまでもその花について論じていることは重要です。
1943年には『風土』の和辻哲郎が、やはり[桜]の花のあわただしく華やかに咲きそろうにもかかわらず、この状態に執着することなく恬淡に散るその風情を、日本的な気質の象徴とみています(*33)。華やかな生の状態に執着せず散りゆくことの潔癖性は、[霞]や[雲]にもたとえられたその「花ざかり」ののどかさとともに、これを近代日本の大衆音楽における[桜]の語の心情的な含意とする指摘もあります(*34)。
散りゆく[桜]の花に人間の生命を重ね、その儚さの奥に死を透視する観点は、『古今和歌集』などにも認められます(*35)。それでもなお、国家のため、帝国の主君としての「きみがため」の死としてこれを美徳化する観点が軍国主義のものであることは疑いようもありません。なぜなら、西洋の軍制を採用するにあたりその軍服を模倣した海軍や陸軍では、徽章に[桜]の花を意匠化していたからです(*36)。このことは、国民皆兵の時代にあっては、民衆の誰もが一様に皇国のために咲き、散るべき[桜]の花であることを意味します。
そして日清戦争から日露戦争にかけて、このような価値観にもとづく軍歌が流行するのみならず、軍歌の旋律にみられる定型性が童謡や寮歌のうちにも応用されることにより、国家に対する文字どおり献身的な奉仕の準備を将来の兵士に促すのです(*37)。
櫻、さくら、SAKURA、サクラ
こうした場合、[桜]を涵養する風土こそが領土すなわち国家の領域としての国土であり、根幹たる[桜]の樹木は国家を構成する組織体系に相当するでしょう。さらにその枝先で小さく蕾を膨らませ、時期とみるや爛漫となり、いっせいに花びらを散らせる[桜]の花は、それぞれが国民ひとりひとりとなります。ソメイヨシノは、空間的な位相や時間的な位相に加え、精神的な位相についてもそうした集団的な連帯への同調を正当化し、いかにも整然とした全体主義的な美を演出するわけです。
敗戦にもとづくGHQによる国土の占領統治は、日本におけるこのような[桜]のありようを刷新します。軍国主義につながった封建的な諸体制が廃止ないし解体され、それらに担保されていた意味を削がれた[桜]は、なによりもまず季節の表象となります。
“開花宣言”や“桜前線”は、日本列島を北上していく春の訪れを可視化する装置です。[桜]については、1953年以来、気象庁が日本各地における開花と満開の日づけを観測のうえ記録しています。近隣の地域でいっせいに開き、いっせいに散るソメイヨシノが全国各地に植樹されていないことには、“開花宣言”も“桜前線”も風物詩たりえなかったにちがいありません。
戦火に荒廃した市街地の整備や開発に、成長が早く活着のいいソメイヨシノがまたしても重宝され、その並木が新設の学校の校庭や住宅地の街路を彩ることになります。土木建築を基軸に国土が改造された高度経済成長期には、この傾向はいっそう顕著となるところです(*38)。
それでもやはり、歌謡曲は[桜]を謳うことを躊躇します。かつて[桜]が背負った意味はいかにも深刻で、たとえアメリカ式の民主主義の軽やかな豊かさをもってしても、散る花の薄く淡い色に染みたその暗い影までは容易に払拭できようはずもなく、なにがしかの遠慮があったのかもしれません。
たとえば、藤山一郎と奈良光枝が歌唱した〈靑い山脈〉(1949)では、なるほど「若くあかるい歌聲」に誘われて「雪割櫻」の「花も咲」きます。ここで「雪割櫻」とされたツバキカンザクラは、早いところでは春も遠い寒中のころから残雪を割るように咲きはじめ、如月の寒気も手伝って散りにくく花期が長いのが特徴です。
https://www.youtube.com/watch?v=h4cMuqUdwpk
だからもはや国家のために散ることではなく、まだ「焼けあと」の残る戦後日本の荒廃のなか「夢を呼」び、希望の「鐘」を「鳴」らす「雪割櫻」たることこそが、「若いわれら」には期待されたわけです。いまは厳寒の冬を耐えながら、かつての「古い上衣」や「さみしい夢」は「雪崩」と「消」して、いつか新しい「バラ色」の社会を築くこと(*39)。とはいえ、ここで彼らに託されたもの、またしてもそれが、「靑い山脈」の「かがやく嶺」や「みどりの谷」といった国土のかたちで無批判的に表象されてしまうあたりに、西條八十の言葉の危うさはあります。
舟木一夫の歌唱による〈高校三年生〉(1963)は、終戦の年の新生児がちょうど高校3年生になるころに発表されました。つまり敗戦による新生日本の民主主義は、このころようやく高校3年生に成長したのです。東京オリンピックを控え、高度経済成長に裏づけられた国家や国民の自信や自覚は、戦後からの卒業への「日数」が「残り少ない」ことに「弾む声」からもうかがえます。ただしこれが響く校庭を覆うのは、あくまでも「ニレの木陰」です(*40)。
新しい世紀にはいるまでに福山雅治の〈桜坂〉(2000)が発売され、宇多田ヒカルは〈SAKURAドロップス〉(2002)を発表します。
さらに森山直太朗の〈さくら(独唱)〉(2003)がこれにつづきます。「刹那に散りゆく運命」だとか「いつか生まれ変わる瞬間を信じ」だとかいった表現が、かつて犠牲的な献身の強要が[桜]の散りぎわになぞらえて正当化されたことの悲愴な歴史を想起させるにもかかわらず、この楽曲は大ヒットします。
これを端緒に、ケツメイシが〈さくら〉(2005)を、コブクロが〈桜〉(2005)を、いきものがかりが〈SAKURA〉(2006)を発売します。それ以降も、たとえばAKB48は、実質的なデビュー曲となる〈桜の花びらたち〉(2006)をはじめ、〈10年桜〉(2009)や〈桜の栞〉(2010)、〈桜の木になろう〉(2011)などのシングル盤を発表していきました(*41)。YUIは〈CHE.R.RY〉(2007)を歌い、絢香による〈サクラ〉(2018)は配信限定で発表されています。
1985年
歌謡曲において[桜]の語をめぐる謹慎が解かれるには、だから軍国主義における錦の御旗にこれが織り込まれていった過程で費やされた時間と同じだけの歳月が必要だったのかもしれません。
もちろん、〈靑い山脈〉(1949)の「雪割櫻」にみられるように、20世紀後半の歌謡曲に[桜]の登場する機会は皆無ではないでしょう。
〈チェリーブラッサム〉(1981)は松田聖子によって歌唱されました。そのデビュー曲〈裸足の季節〉(1980)以来、彼女のシングル曲の作詞を担当してきた三浦徳子は、けれどかろうじて「胸に抱いた愛の花」と綴った以外には、そこに[桜]の語をめぐる言葉を差配することはありませんでした。
作詞家の座が松本隆に譲られたのち、〈制服〉(1982)が松田聖子にこの語を発声させています。「桜が枝に咲く頃には」と歌唱されるここでは、「セーラー服」を「着るのも」これで「最後」となる「卒業証書抱いた」日にあって、なお〈チェリーブラッサム〉すなわち[桜]の蕾の謂を踏襲するように、この「東京」とは「違う世界」で[桜]はまだ開花の適期を迎えていないことが示唆されます。
《Canary》に収録された〈Private School〉(1982)では、新人の英語教師に恋した「私」が、おそらくは「美人の教師」と彼とが「結婚するって聞いた」のも、やはり「卒業」の当日でした。しかしここにも[桜]の景観は認められません。
松本隆は、筒美京平が作曲した斉藤由貴の〈卒業〉(1985)に歌詞を提供しています。この楽曲が発表された前後には、尾崎豊や倉沢淳美、菊池桃子らが、それぞれ同名異曲の〈卒業〉をシングル盤として発売し、まさしくいっせいに卒業を謳ってみせます。
尾崎豊による〈卒業〉(1985)は、本人のものと思しき後ろ姿の人物が指先にかまえた角礫をいまにも投石せんとしている素振りの右肩を大きく捉え、陰陽を反転させて白黒のみの配色で印刷されたレコードのジャケット写真が印象的です。「夜の校舎」の「窓ガラス壊してまわ」るなど、歌詞に描かれた世界観と容易に重なるこの視覚的な意匠は、音楽産業のなかで彼がふるまうべき役柄やその立場を明確に指示します。
「ふらつき」、「逆らい」、「あがき」、「争い」、「強がって」、「怒り」、「闘い」…。青年の苦悩を露わとする尾崎のこうした言葉の羅列には、いかにも[桜]の情緒は不似合いなものでしょう。
倉沢淳美が歌唱した〈卒業〉(1985)では、なるほど「卒業」にあたって「薄紅の花片」が「校庭」に「舞い散」っていますが、それでも作詞の売野雅勇は、[桜]の語ばかりはその直接的な使用を回避しています。
斉藤由貴の場合にも[桜]の気配はみあたりません。けれどこの楽曲についてはかろうじて、かつて甲斐バンドでベースを担当し、脱退後にレコード会社に迎えられた担当ディレクターの長岡和弘が、母校の正門からの坂道に植樹された[桜]の並木を脳裏に描きつつその制作にのぞんでいたことを述懐しています(*42)。
菊池桃子の〈卒業〉(1985)においては、「春の陽射しこぼれ」るこの「少し眩しい並木道」について言及されています。とはいえ、どうやらこれは[桜]のものではなく、「ポプラ」の「緑の木々」のようです。ここでは秋元康によって、「あの人」が「都会」に「旅立っていく」時期がようやく「4月を過ぎて」からと設定されていることが、その主要な理由かもしれません。
彼らの以前に、沢田聖子もシングル盤として〈卒業〉(1982)を発表しています。「日付けをひとつ消したら」もう「あなたと別れの時」が「告げ」られてしまうにもかかわらず、この「卒業」の「季節のしるし」として提示されるのは[桜]ならぬ「雪どけの音」です。
3月
森昌子に提供された〈中学三年生〉(1973)では、「卒業して行」ってしまう「あのひと」を「蛍の光」で送りだそうにも「涙でつまって歌えない」という「私」は、「春」に「中学三年生」への進級が待っています。
松本伊代の〈Last Kissは頬にして〉(1986)の「私」は「女子大生」を「今夜でもう卒業」します。
歌謡曲が謳う卒業とは、それでもやはり高等学校の課程を修了した時機のものがほとんどです。おそらくそれは、この時機が青春期から成人期への移行の時期に相当することに加えて、これらの楽曲を収録した音盤の購入者たりうる聴き手の市場がその年代を中心に構成されるからでしょう。
いずれにしても、「中学三年生」や「女子大生」の彼女たちが別離をめぐる自らの心境を[桜]の語に反映させる余地はうかがえません。
1985年に発表された4曲の〈卒業〉などにもみられたように、こうした卒業における[桜]の語の欠落ないし空白は、単に戦時の不幸な記憶の参照を忌避するための配慮であるのみならず、卒業式の挙行の当日にはソメイヨシノの花は依然として小さな蕾のまま、咲く適期を測って身を潜めている状態にあるからにちがいありません。要するに、卒業を彩る象徴たるには、[桜]の語のありようは、精神的な位相においてばかりか時間的な位相においても、いわば現実とのあいだで齟齬を、ずれを、ずれを、もしくは吃りをきたすものだったわけです。
全国でももっとも[桜]の開花時期が早い都市のひとつが東京です(*43)。1953年から記録されているソメイヨシノについて、20世紀中の開花日の平均は3月28日あたりに算出されます。しかしこの期間でもっとも開花日が集中しているころあいをみれば、これよりもややうしろに重く、3月29日から4月3日のあいだの開花が48年のうち半分の24回を占めます。つまりいち早く開花の時期を迎える東京においてさえ、ソメイヨシノは卒業式にかなり遅れて咲くことになります。
ところが、21世紀にはいったいま、事態は大きく変容してきています。この21年間で平均の開花日は3月21日となり、しかもこの期間のうち半分の10回は3月20日から3月23日のあいだに開花しています。まさに福山雅治の〈桜坂〉以降、ほんの20年あまりのあいだに、[桜]はそれまでよりも10日ほど咲き急ぎ、だから散り急ぐことになってしまったのです。
いわゆる都市の温暖化の影響をここに指摘することも可能かもしれません。とにかく、21世紀を待っていたかのように、にわかに卒業式を彩りはじめた[桜]の花は、森山直太朗らによる21世紀の“桜ソング”の多産と無関係ではいられないでしょう。
なお、舟木一夫の〈高校三年生〉において「クラス仲間」だった「ぼくら」は、ともにすごした高校時代を含め成人するまでの5年間のうち、一度たりとも3月の東京に咲く[桜]の花を共有することはなかったはずです。また、斉藤由貴ら1985年の〈卒業〉群が参照しえた1984年の[桜]が開花したのは、観測史上でも最晩値となる4月11日のことでした。1985年も4月3日の開花と記録されますが、ただし1988年の4月2日を最後に東京では卯月を待たず[桜]の花が開き、目下のところ2014年と2020年、2021年の3月14日がその最早値となります。
東京
こうした文脈からすれば、「桜のつぼみ」の「春へとつづ」くところと歌ったレミオロメンの〈3月9日〉(2004)は、いかにも現実的な感覚にのっとった詞作です。川嶋あいによる〈旅立ちの日に…〉(2006)にあっては、「桜」は賢明にも「卒業の日」ではなく「4月の教室」に「舞」っています。
他方で、AKB48の雛型とみなされうるおニャン子クラブが発表した〈じゃあね〉(1986)では、「春」の「お別れ」と「旅立」ち、この「季節」の「SAYONARA」と「船出」を、「淡いピンクの桜」の「花びらもお祝いしてくれます」。ここでは「4月になれば」との表現が、これを3月の出来事とうかがわせます。1985年につづき1986年も4月3日に開花した東京の[桜]の実情を考慮する場合には、脳裏の貧弱なイメージに頼った根拠の希薄な風景を軽率になぞる秋元康の筆致は、およそ説得力のないものたらざるをえません。
渡辺美里による〈卒業〉(1991)も、[桜]のものと思われる「うす紅の 花びら」の「散る」なか、「耳元」を「春一番」が「吹きぬけ」ていく奇妙な「卒業」の歌です。
このように、20世紀における[桜]の語のありようは、卒業を彩る象徴たるには精神的な位相と時間的な位相において、現実とのあいだに齟齬をきたすものでした。
そのうえで、そこには空間的な位相におけるずれも招来されます。というのも、周知のように南北に長く気候の相違の甚大な日本列島の諸風土にあって、きわめて温暖な西南諸島を除いても“桜前線”は2ヶ月ほどかけてそこを北上していくからです。そうしたなか、[桜]が卒業の情緒を反映する象徴たるには、日本の春の訪れはあまりにも緩やかなのです。
その列島の各地をつなぐために、東海道新幹線の開業は1964年、1972年には岡山まで延伸された山陽新幹線が博多に到達するのは1975年です。1982年に盛岡まで開業していた東北新幹線が2002年にようやく全線の完成となるなど、いまなおその整備は途上にあります。1969年までに東京と名古屋のあいだで開通した高速道路についても事情は変わりません。
これら交通網の構築が多彩な気候の国土を覆っていくなか、1970年代には地方と都市のあいだの移動はいよいよ容易となり、東京への人口の流出と集中が加速します。高等学校を卒業することとは、それまで親もとで暮らした多数の18歳が、進学のためであるにせよ就職のためであるにせよ、いっせいに巣を離れ旅にでる時機でもあるわけです。
このころの歌謡曲は、卒業それ自体よりはむしろそうした旅立ちや別離をこそ焦点化してみせます。
はしだのりひことクライマックスが歌唱した〈花嫁〉(1971)などがその原型となります。ただしここで「花嫁」が「夜汽車」で「とついでゆく」先は「海辺の街」でした。
チューリップによる〈心の旅〉(1973)でも、「旅立つ僕」が「明日の今頃」に利用しているだろう「夜」の交通機関は「汽車」ですが、この車両の到着先は明示されません。
松本隆と筒美京平が太田裕美に提供した〈木綿のハンカチーフ〉(1975)は、その代表例だといえます。「東」の「都会」へと「旅立つ」ために「僕」は「列車」に乗ります。彼が向かう「はなやいだ街」や「ビル街」とは、おそらく東京の謂でしょう。
松本は、松田聖子の〈制服〉においても「四月からは都会に/行ってしまう」ことを「あなた」に課しています。歌詞の主人公には、すでに彼から「東京での住所」を記入した紙片が手渡されているものの、「雨に濡れ」てしまったその文字を判読することは困難であるかもしれません。
やがて松本隆は、またしても筒美京平と協働するなか、そうした設定を今日的に更新しつつ統合します。ほかでもない斉藤由貴の〈卒業〉でのことです。ここで「反対のホームに 立つ二人」を「時の電車がいま引き裂」き、それをもって「あなたの未来」は「東京で変わってく」ことになります。
青春の蹉跌
風の〈22才の別れ〉(1975)とイルカの〈なごり雪〉(1975)のいずれも、もとは1974年のアルバム盤《三階建の詩》に収録されていた伊勢正三の詞曲によるかぐや姫の楽曲でした。
「あなたの知らないところへ」と「嫁いで行く私にとって」は、「あなた」とともに生きた「17」歳からの「5年の月日」を「永すぎた春といえる」のだから、〈22才の別れ〉とはまぎれもなく「あなた」からの卒業を意味するものです。
あたかもそれを「ふざけすぎた季節」とみなしたかのように、「動き始めた汽車の窓に顔をつけ」る〈なごり雪〉の「君」は、「東京で見る雪」を「これが最後」と「つぶやき」、「ホーム」を「去っ」ていきます。[桜]吹雪ならぬ風花としての「落ちてはとける雪」のありようが、「なごり」そのものの脆く儚いさまを視覚化します。
さだまさしは、〈驛舎〉(1981)において〈なごり雪〉の「君」の行方を回収してみせます。「都会」を発った「列車のタラップ」から「ホーム」に「降り」て「驛舎」に「立」った「君」に、「改札口を抜け」るまでに「春」の訪れを告げたもの、それは、「僕」と「懐しい言葉」である「故郷訛りのアナウンス」、そして「時計をかすめて飛ぶ」、燕と思しき「季節の間ではぐれた小鳥」です。この「小鳥」が「なごり雪」の変奏であることはいうまでもありません。
アグネス・チャンの歌唱による〈アゲイン〉(1978)の「私」は、「よそゆきの都会」での生活に区切りをつけて「蒸気機関車」で「ふるさと」に戻ってきたひとりの女性、いわば〈なごり雪〉や〈驛舎〉の「君」の立場から、「あなた」との再会の場面を描写します。彼女の「暮らし」た「レンガの色の学生街」には、GAROの〈学生街の喫茶店〉(1972)との共鳴も聞こえてきます。
カナダのトロント大学への留学のため芸能活動を休止していたアグネス・チャンの、日本の芸能界に復帰して最初のシングル盤となるこの楽曲は、作詞を松本隆が、作曲を吉田拓郎が担当しています。松本による歌詞は、歌い手のこうした実情を念頭に、彼女の渡航を惜しみつつ「君を待つよ」と誓ったかつての聴き手たちに「あの日あなた言った約束は生きてるの」と問いかけ、「もう一度」だけ「振り出しに戻りたい」と請願します。
引退にあわせて発表されたキャンディーズの最後のシングル盤〈微笑がえし〉(1978)では、「あなた」と「別々」に「別れ」、「住みなれた部屋」から「引っ越し」ていく「私」の視点が、阿木燿子による言葉をもって提示されます。「春一番」が「ほこりの渦を踊らせ」るこの「部屋」は、〈アゲイン〉の「埃舞うふるさとの部屋」と通底します。加えて、アグネス・チャンの楽曲において「皮張りの旅行鞄」が相当した「青春のスーべニール」については、〈微笑がえし〉は、「迷子になっ」ていた「ハートのエース」を「青春の想い出そのもの」として指名しています。
もちろんそれは、単に「ハートのエース」それ自身であるのみならず、「春一番」にせよ「罠」にせよ、さらには「年下の人」にせよ「やさしい悪魔」にせよ「1 2 3」にせよ、これまでに彼女たちがシングル盤として発表してきた楽曲の数々を、あるいはそのすべてを示唆する指標です。それらのひとつひとつが、まぎれもなくひとひらの「なごり雪」となって現われ、消えていきます。
ここでもまた、歌詞の言葉は、本来はその外部にあるはずの歌い手の実情を聴き手に参照させる自己言及的な仕掛けを施し、〈アゲイン〉がこれを「あなた」すなわち聴き手との再会として演出したように、「あなた」すなわち聴き手との別離を脚色しているわけです。
中島みゆきから提供された〈春なのに〉(1983)において、柏原芳恵は「卒業だけが 理由でしょうか」と声にならないままに尋ねました。たとえば森田童子の〈僕たちの失敗〉(1976)にも確認できるように、1970年代の歌謡曲にみられるこうした光景にとっての別離とは、なるほど卒業だけが理由ではなかったにちがいありません。青春の蹉跌とするにふさわしいその光景にあっては、しかしあらゆる別離こそが卒業なのです。そしておそらく、春とは、別離をめぐるそうした青く若い傷の痛みの謂にほかならないのです。
写真
要するに、誰もが「春」だからこそこの「お別れ」を迎え、「涙がこぼれ」、「ため息」を「またひとつ」吐くことになったはずです。にもかかわらず、柏原芳恵の歌声が「春なのに」と繰り返すとき、この歌詞における「春」のありようは、その展開の方向性を逆相に配されます。
このような方向性の逆相は、そこに[桜]吹雪や風花が舞うのではなく、その等価物である「記念」の「ボタン」を「青い空」に向かって「捨て」ようとする行為に端的に表現されています。想い出の日々の象徴が、引力にしたがって天から地へと下降するのではなく、これに抗ってそれを地から天へと上昇させること。あわせて、それを保存するのではなく投棄してしまうこと。〈春なのに〉とは、「春」のありようを逆相に配することによって「流れる季節たち」の不可逆性を反転させようと試みる、時間の秩序に対する青春の革命的な闘争なのです。
〈春なのに〉の歌詞の言葉は、ただ時間を遡行することに充足するものではありません。それどころか、あくまでも時間それ自体を遡行させることを企てるものです。ここに中島みゆきの根源的な過激さがあります。とはいえ、青春の感傷が癒えるそのためには、時間が未来に向かって流れていく必要があることもまた、疑うべくもないところでしょう。
ならばせめて、想い出ばかりは時間の経過とともに色褪せてしまうことのないように、hi-fi setの〈卒業写真〉(1975)はこれを「皮の表紙」で固定し、「卒業写真」としてその紙面に定着させます。「人ごみに流され」ながら「変わってゆく私」の「青春そのもの」である「あなた」は、その「面影」を「卒業写真」に留めつづける限りにおいて、彼女の「青春」それ自身をも「そのまま」に保存しつづけることになります(*44)。
写真とは、時間の流れのなかから切りだした一定の瞬間の厚みを平面上に一瞬のうちに圧縮し、ここに凍結された空間の断片をもって、このままでいたいと願うささやかな欲望をまがりなりにも叶える装置です。
松田聖子の〈制服〉では、「セーラー服着るのも」これで「最後」となる歌詞の主人公が、そこに「卒業証書」を抱える時季を待たず、すでに在学中から「真っ赤な定期入れ」に「あなた」の「小さな写真」を「かくしてい」ました。倉沢淳美の〈卒業〉にあっても、「あなたはアルバムで」もっぱら「微笑うだけ」です。菊池桃子の〈卒業〉では「私」は、どうやら「4月になる」ごとに「卒業写真」を「めく」っているようです。
Dreams Come Trueは、〈未来予想図Ⅱ〉(1989)や〈笑顔の行方〉(1990)において「卒業」に言及しています。〈未来予想図Ⅱ〉の「私」は、「卒業してから もう3度目の春」になるというのに、「まだやんちゃ」だったころの「写真達」を収めた「アルバム」を、「あなた」と「時々2人で 開いてみ」ます。これと「同じ笑顔」が「あいかわらず そばにある」ことを確認するためです。それが「かわらぬ思い」の輪郭をなぞる一方で、〈笑顔の行方〉の「私」には、「卒業アルバム」で「無邪気に笑う私」とはもう「同じ笑顔はできな」いことが吐露されます。
ところで、中島みゆきが柏原芳恵の歌声を借りて「青い空」へと「捨て」ようとしていた〈春なのに〉の「ボタン」は、斉藤由貴の〈卒業〉においては、「下級生たちにねだられ」ながらも彼女たちから「逃げる」ことによって、かろうじて「あなた」の「制服の胸」に保持されつづけます。ただし、いずれ遠からずこれも、「制服」ごと「あなた」に置き去りにされずにはいないでしょう。
ここで「あなた」の「制服の胸のボタン」に対応するもの、それは、いうまでもなく歌詞の主人公の「セーラーの薄いスカーフ」です。これで「止まった時間を結びたい」と望むものの、それが「東京で変わってく」はずの「あなたの未来」を「縛」ることと理解してもいる彼女は、曖昧な状況のまま「過ぎる季節に流されて」いくことを覚悟しています。いわばそれは、超越性に対する一種の諦念かもしれません。そしてこの諦念のゆえに、「時の電車」に「引き裂」かれてなお、「二人」は時間の秩序に従順なのです。
ボタンとスカーフ
斉藤由貴の〈卒業〉における「スカーフ」は、太田裕美の〈木綿のハンカチーフ〉における「ハンカチーフ」の変奏です。「あなたの未来」を「縛」ろうにも、これら布きれはあまりに薄く、短いものです。それでもこれらの楽曲における歌詞の主人公にとって、「あなた」との別離に異を唱えるために用意できる道具立てとは、せいぜいのところこれら破れやすい布きればかりであって、したがって「セーラー」と「木綿」とはともに慎ましやかな純朴さの謂となります。
沢田聖子の〈卒業〉に歌われた、「ためらう心」を「入れ」た「箱」に「結んだ……リボン」もやはり、こうした布きれの系列にあります。しかもそれは「すぐにほど」かれてしまうのです。
いつまでも「胸」に「結」びつづけたい「スカーフ」の柔軟さに対して、いずれ「胸」から「離れて」いく「ボタン」の堅牢さは、柔らかさを旨とする衣服にあって明らかに異質です。その堅牢なぶん、「ボタン」は、制服をまとった日々の「想い出」を凝縮させて保守し、「時の電車」の行方から確実に区切ってみせるような、いわばひとつの「ホーム」として機能します。
この「ホーム」を「旅立」った〈木綿のハンカチーフ〉の「あなた」が次の「ホーム」となる「都会」で入手したもの、それが「見間違うような スーツ」であったことも、おそらく偶然ではありません。この「はなやいだ街」での新しい「制服」となる「スーツ」には、「星のダイヤ」や「海に眠る真珠」のように硬い「ボタン」がつけられているにちがいないのです。
〈ギザギザハートの子守唄〉の「俺」が「街を出ようと」して「つかま」り、「力まかせになぐられた」のも、やはり「駅のホーム」でのことです。堅牢な「ボタン」のような古い「街」に囚われて巣立つことを許されないまま、「仲間がバイクで死んだ」ときに彼ができた餞別といえば、「青春アバヨと泣」きながら硬い「ガードレールに」柔らかい「花」を「そえ」ることだけでした。
ここでなにが「俺」の「熱い心」を「しば」っていたのかについて、彼は明言していません。ただし、その「夢」は「机で削られて」しまったようです。「15で不良と呼ばれた」彼の未来を「削」るほどに堅固な「机」は、まさしくその硬質さゆえに、そこに「削」り込まれた痕跡に過去を保存しつづける機能を果たすところとなります。
倉沢淳美の〈卒業〉の「私」は、「あなたが座っていた机の傷」を「指で触れ」るうち、その「隅っこに掠れた文字」が「私の名前」を「刻」んだものだったことを知ります。この「机の傷は青春の忘れ物」として「誰もいない教室」に残されます。
斉藤由貴の〈卒業〉にあっては、「下級生たち」の前でかろうじて「ボタン」を保持した「あなた」も、「人気ない午後の教室」では「机にイニシャル」を「彫」ろうとします。これに歌詞の主人公は「やめて」と「つぶや」かずにはいられません。「セーラーの薄いスカーフ」をもって「止まった時間を結」ぶことすら「あなたの未来」を「縛」るものと遠慮する彼女にとって、もっぱら「心だけ」が「想い出を刻む」にふさわしい支持体なのです。
学校生活において、「机」すなわち座席の位置は重要です。座席の配置に応じてそこから見える景色はまったく異なり、これが想い出の輪郭を決定づける要因ともなりうるからです。
倉沢淳美の場合には、「私」は「斜め後ろの席」から「あなたをみてい」ました。斉藤由貴の場合には、「席順が変わ」るたびに「あなたの/隣の娘にさえ妬い」ていた主人公が、それでも「いたずらに髪をひっぱられ」て「怒ってる裏ではしゃいだ」ときには、おそらく「あなた」はすぐうしろの「席順」だったにちがいありません。
卒業
チェッカーズが〈ギザギザハートの子守唄〉で「卒業式」に「何を卒業するのだろう」と問うてみたように、〈卒業〉の尾崎豊もまた、「卒業して いったい何解ると言うのか」と問います(*45)。
「チャイムが鳴」れば「教室のいつもの席に座り」、「街ふらつ」くのも「放課後」であるような「俺」については、相応に「行儀よくまじめ」な気質と考えられ、事実、「卒業」にあたって彼は「想い出」ばかりは確かに「残る」ものと疑うところをみせません。
そんな「俺」が、チェッカーズから投じられた問いについては明瞭に回答します。「この支配からの 卒業」であり「闘いからの 卒業」だと彼はいうのです。
さらに彼は、それが「自分自身」からの「卒業」でもあるのに、いったい「何度」それを繰り返せば「本当の自分に たどりつけるだろう」と自問を重ねます。「人は誰も縛られ」、ひとつの「卒業」のあとにもまた次のなにかが「俺を縛りつけるだろう」から、「自由」さえも「仕組まれた」ものにすぎないところと彼は認識してもいます。
そうした醒めた意識をともないながら、なお「俺」は「夜の校舎 窓ガラス壊してまわ」るのです(*46)。なるほど、「校舎」は「この支配」の体現であって、それからの「卒業」とは、それとの「闘いからの 卒業」でもあります。しかしながら、この「闘い」の仕方はいかにも素朴にすぎます。彼が「本当の自分に たどりつ」こうとする限り、「この支配」のあとには次の「支配」が繰り返し訪れ、その都度、次の「自分自身」を求める彼もやはり、次の「闘い」へと組み込まれることは不可避だからです。
入れ子状のこの構造にあっては、「闘い」も「卒業」もたちまち相対化されてしまいます。ここでなすべきこと、それは、「信じられぬ大人との争い」などといった、すっかり手垢にまみれた反抗の仕草を呈することではなく、この構造そのものを失調させることでしょう。すなわちそれは、「本当の自分」という「幻」、その「支配からの卒業」を意味します。
どうやら「涙」は、絶対的な別離といっていい「本当の自分」からの「卒業」、つまり他の誰との別離の場合ともちがうこの真に「哀しい瞬間」のために「とってお」いたほうがよさそうです。
*1 有本真紀,『卒業式の歴史学』, 講談社, 2013, pp.24-26.
*2 佐藤慶治,『翻訳唱歌と国民形成 明治時代の小学校音楽教科書の研究』, 九州大学出版会, 2019, pp.57-60.
*3 櫻井雅人+ヘルマン・ゴチェフスキ+安田寛,『仰げば尊し―幻の原曲発見と『小学唱歌集』全軌跡』, 東京堂出版, 2015, pp.310-360.
*4 佐藤, 前掲書, pp.28-34.
*5 有本, 前掲書, pp.40-48.
*6 奥中康人,『国家と音楽 伊澤修二がめざした日本近代』, 春秋社, 2008, pp.127-151.
*7 櫻井ほか, 前掲書, pp.227-233.
*8 同書, p.v.
*9 有本,前掲書, pp.173-181.
*10 同書, pp.187-188.
*11 同書, pp.181.
*12 中西光雄,『「蛍の光」と稲垣千頴―国民的唱歌と作詞者の数奇な運命―』, ぎょうせい, 2012, p.81.
*13 同書, p.66.
*14 同書, p.86.
*15 同書, pp.28-31.
*16 同書, p.111.
*17 有本, 前掲書, pp.100-106.
*18 同書, pp.136-168.
*19 櫻井ほか, 前掲書, p.2-18.
*20 同書, p.305.
*21 同書, pp.30-32.
*22 有本, 前掲書, pp.199-213.
*23 中西, 前掲書, p.116.
*24 佐藤俊樹,『桜が創った「日本」』, 岩波書店(岩波新書), 2005, p.3.
*25 同書, p.14.およびp.50.
*26 同書, p.45.およびpp.88-90.
*27 同書, pp.119-122.および大貫恵美子,『人殺しの花―政治空間における象徴的コミュニケーションの不透明性』, 2020, p.67.
*28 佐藤, 前掲書,pp.100-103.
*29 大貫, 前掲書,pp.2-3.
*30 文部省,『小學唱歌集』第2編,『日本教科書体系 近代篇 第25巻 唱歌』所収, 海後宗臣/編, 講談社, 1965, p.20.
*31 文部省,『幼穉園唱歌集』,『日本教科書体系 近代篇 第25巻 唱歌』所収, p.58.および大貫, 前掲書, p.65.
*32 志賀重昻,『日本風景論』, 岩波書店(岩波文庫), 1995, pp.33-35.
*33 和辻哲郎,『風土―人間学的考察』, 岩波書店(岩波文庫), 1979, pp.202-203.
*34 見田宗介,『近代日本の心情の歴史』, 講談社(講談社学術文庫), 1978, p.224.
*35 大貫, 前掲書,p.48.
*36 同書,pp.63-64.
*37 同書,pp.65-66.
*38 佐藤, 前掲書,pp.160-163.
*39 村瀬学,『なぜ「丘」を歌う歌謡曲がたくさんつくられてきたのか 戦後歌謡と社会』, 春秋社, 2002, pp.14-21.
*40 同書,pp.101-106.
*41 西兼志,『アイドル/メディア論講義』, 東京大学出版会, 2017, pp.174-183.
*42 長岡和弘,「私の母校(2013.09.29)」(http://blog.jomon.biz/?month=201309), 『jomon 長岡和弘の日記』所収, JUGEM, 2013.
*43 気象庁大気海洋部観測整備計画課,「各種データ・資料/地球環境・気候/生物季節観測の情報」(https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html), 『国土交通省 気象庁』所収, 気象庁, 2022.
*44 村瀬, 前掲書,pp.152-159.
*45 見崎鉄,『盗んだバイクと壊れたガラス 尾崎豊の歌詞論』, アルファベータブックス, 2018, pp.81-82.
*46 同書, pp.113-118.
堀家教授による私の「卒業」10選リスト
1.〈恋のダイアル6700〉フィンガー5(1973)
作詞/阿久悠,作曲・編曲/井上忠夫
ファンキーなリズムにのせてこれだけ軽快に「卒業式」の語を謳ってみせた楽曲は、いまだかつて歌謡曲には例のないものである。〈個人授業〉や〈学園天国〉、〈上級生〉といった曲名は、そのまま歌詞の言葉が学校を舞台として綴られている事実を強調するものの、それが小学校のことであるように感じられるのは、おもに年少の弟妹ふたりの児童が歌唱しているからにほかならない。したがって、この楽曲においても「卒業式」は小学校でのものと理解されるところとなる。
2.〈青春時代〉森田公一とトップギャラン(1976)
作詞/阿久悠,作曲・編曲/森田公一
高度経済成長の終焉や学生運動の挫折による戦後日本の集合意識への懐疑は、団塊の世代を内向化させるとともに、今度はその誰もが個人的な苦悩を抱くことをもってひとつの集合を構成し、それをとおして集合意識を逆説的に更新する。戦争を知らない子どもたちが直面した、いかにも青くさいこの春の出来事は、しかし森田公一においては、苦悶への耽溺を自閉的に美化することなく率直に描かれ、虚飾のない爽やかさが好ましい。
3.〈微笑がえし〉キャンディーズ(1978)
作詞/阿木燿子,作曲・編曲/穂口雄右
1970年代後半の芸能界を席捲したピンク・レディーの台風は、先行する女性アイドルだったキャンディーズや山口百恵には解散商法や引退商法というかたちで引導を渡したうえで、ピンク・レディー自身も瞬くうちにその潜勢力をあらかた蕩尽し、1980年にはまったく別の光景が立ちあがるための平野が、余白が準備される。〈微笑がえし〉において「机本箱運び出された荷物のあと」の、がらんどうとなった「住みなれた部屋」とはそうしたものであり、「そこだけ若い」とされる「畳の色」は、まさしくこの「お引っ越し」が次代のアイドルのために席を空け、座を譲る卒業の謂にほかならないことを示している。寂しくもどこか清々しく、悲しくもなにか安堵を感じさせる〈微笑がえし〉では、だからこそ松原正樹のリード・ギターもいっそう切なく響く。
4.〈アゲイン〉アグネス・チャン(1978)
作詞/松本隆,作曲/吉田拓郎,編曲/松任谷正隆
人気絶頂のなか留学のため日本での芸能活動を休止し、その期間を終えて日本に戻ったアグネス・チャンの復帰第1作。そうした境遇にある彼女のための自己言及的な歌詞は、彼女の、そしてそれを支える人びとの、祈りにも似た請願である。起伏の激しい旋律は、たとえアグネス・チャンの歌声でなぞられようとも、滑らかさを欠きつつ弾む音程がいかにも吉田拓郎のものらしい。作家陣に松本隆や荒井由実、演奏にキャラメル・ママを起用するなど、“ニュー・ミュージック歌謡”とでもいうべき彼女の楽曲は、だから“シティ・ポップス歌謡”とでも形容されるべき松田聖子の音楽性の先駆としても、その意義を大いに再評価する必要があるだろう。ならば、抑制の効いた的確なエレキギターはここでも鈴木茂の演奏か。
5.〈驛舎〉さだまさし(1981)
作詞・作曲/さだまさし,編曲/服部克久
さだまさし自身がこの楽曲をイルカの〈なごり雪〉に対するアンサー・ソングとして着想していることの確証はない。それでもなお、ここにみられるものが、「東京」を「汽車」で発つ〈なごり雪〉の「君」が到着しえたひとつの可能性のかたちであることは疑いない。この楽曲が発表された当時、近田春夫が「明星」誌の付録の歌本における新曲紹介にあたり、好みではないものの商品としてよくできているところとこれを紹介していたことは、歌謡曲に対する近田の批評眼の信頼性を担保する挿話である。
6.〈制服〉松田聖子(1982)
作詞/松本隆,作曲/呉田軽穂,編曲/松任谷正隆
〈赤いスイートピー〉のB面に収録されながら、松田聖子の代表曲のひとつに数えられる佳曲。弦のピチカート奏法によるイントロは、シルヴィ・バルタンが歌唱した〈Cherchez l’Idole〉、すなわち〈アイドルを探せ〉におけるストリングスの印象的なフレーズを参照しているように思われる。それでもやはり、デビュー時には高等学校を卒業する年齢となっていたせいか、松田聖子に高校生の「制服」はそぐわない。
7.〈ともだちへ〉伊藤つかさ(1982)
作詞・作曲/矢野顕子,編曲/後藤次利
伊藤つかさの2ndアルバム《さよなら こんにちは》の最後を飾る楽曲。クラスの友だちの特徴を無秩序に列挙し、その誰もに「みんな 元気で」と願う矢野顕子ならではのきどらない詞曲は、ただ伊藤の脆く華奢な声をもって口先で話すように歌唱されるだけでも存分に感動的である。にもかかわらず、大村憲司と思しきリード・ギターに賭けた強引な転調の導入、そのうえでにわかに“テクノ歌謡”化するサビまで、これをピアノ伴奏による単なる名作バラードにはしておくまじと、後藤次利の奇抜にして大胆な音の差配が楽曲を活気づかせる。もちろん、後藤自身によるベースも、イントロからスラップやハーモニクスといった奏法で音の厚みに参画することを忘れない。なお、このリストではすでに“ニュー・ミュージック”の回の番外でこれに触れているが、ここでの選出が正当だろう。
8.〈微熱かナ〉伊藤麻衣子(1983)
作詞/売野雅勇,作曲/来生たかお,編曲/川村栄二
冨田靖子の〈オレンジ色の絵葉書〉や武田久美子の〈噂になってもいい〉などとともに、すでに女優活動を開始するかたわら吹き込まれたデビュー曲として、類似の曲調を採用し、いずれも1983年に発売されている。この流れは、すでに1981年の伊藤つかさや薬師丸ひろ子の歌手デビュー、さらには杉田かおるの成功をふまえたメディア・ミックス的な手法であるだろう。A−A’−B−C−Dの冗長な構成からなるこの楽曲のなかで、ここでもやはり同級生が特徴をとおして列挙されるものの、伊藤つかさの〈ともだちへ〉にみられた無作為的かつ属人的な列挙の過剰さにおける具体性は認められず、陳腐の型にはまった抽象に留まる。
9.〈グッドバイからはじめよう〉佐野元春(1983)
作詞・作曲・編曲/佐野元春
卒業証書を抱くわけでも薄紅の花びらが舞うわけでもなく、また校舎にも教室にも制服にも言及されないこの楽曲は、しかし3月5日に発売された事実をみても、別離一般を想定しながらも、なお卒業に焦点化して味わうことを許容するものだろう。ドラムスをはじめロック的な楽器の編成を排除し、ほとんどストリングスのみの緩やかな伴奏のなか、ときにハープのアルペジオがリズムを負担する。「どうして あなたは/そんなに 手を振るのだろう」のフレーズは、渡辺美里の〈卒業〉が参照し、「どうしてきみは/ずっと手を振るのでしょう」と歌われている。
10.〈卒業〉斉藤由貴(1985)
作詞/松本隆,作曲/筒美京平,編曲/武部聡
これこそが〈卒業〉である。レコード会社での担当ディレクターだった長岡和弘がラジオで紹介したものと思しき、作曲者である筒美京平によるデモ・テープや、武部聡による仮トラックに吹き込まれた彼女の最初の歌唱が、いまYouTubeで確認できる。ひとつの楽曲の生成論的な考察にとっても、こうした音源のパブリック・ドメイン化が望まれるところである。
番外_1.〈卒業写真〉hi-fi set(1975)
作詞・作曲/荒井由実,編曲/服部克久
誰もがすぐアルバム見がちなため番外とした。
番外_2.〈贈る言葉〉海援隊(1979)
作詞/武田鉄矢,作曲/千葉正臣,編曲/総領泰則
誰もがすぐモノマネしがちなため番外とした。
番外_3.〈さくら(独唱)〉森山直太朗(2003)
作詞/森山直太朗・御徒町凧,作曲/森山直太朗,編曲/中村タイチ
誰もがすぐカラオケしがちなため番外とした。
番外_4.〈旅立ちの日に…〉川嶋あい(2006)
作詞・作曲/Ai Kawashima,編曲/ Satoshi Takebe
徳さんがすぐ泣きがちなため番外とした。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





