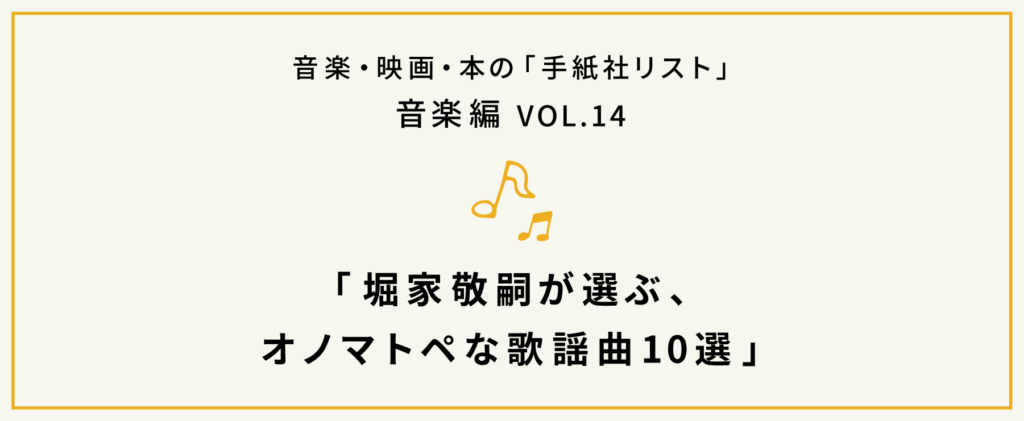
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。14回目となる音楽編のテーマは、オノマトペ。昭和から令和まで。オノマトペは歌謡曲になくてはならない“材料”だったんですね。今回の教授の講義のタイトルは、まさかの、歴史に残るあのギャグ。さあ、ハラホロヒレハレ(?)と、行ってみよう!
歌謡曲にガチョン!
オノマトペ
たとえば、と前置きしたうえで、海岸に迷いでてはじめて青い海をみた狩猟人が驚嘆のあまり叫んだ“う”の音声が、やがて意識をもって文節化される段階で言語としての一般性を獲得して[海(う)]という言葉となり、目の前の光景とともに海の概念をも抽出し、“う”の音声をもってこれを表現することが可能になったのだ、このように言葉のなりたちを説明してみせたのは吉本隆明です(*1)。
もちろんこの説明は、[海(う)]という言葉がすでに成立している段階を前提とした遡及的な仮説にすぎません。というのも、彼ら彼女ら狩猟人は、なにも青い海に対してばかり“う”と叫んだわけではないはずで、驚嘆の都度、その叫びがさまざまな局面でさまざまな事象に向けられていたことは容易に推察できます。つまりそこでは、“う”の指示対象は無数にありえたのだから、にもかかわらずなぜこの音声がことさら[海(う)]へと収斂していったのかについて、いっそうの説明が必要となります。
しかしこの点についての言及は、吉本にはありません。
それでもなお、この仮説は、日本語による表現について試行するひとりの詩人、もしくはそれを思考するひとりの文芸評論家としての吉本隆明の、言語のありかたをめぐる基本的な認識を示すものとして、相応に重要です。
ここで彼は、ひとつの国語が形成されるその原初的な段階において、言葉はオノマトペとして発生することを指摘しているわけです。オノマトペとは、擬音語および擬態語のことです。言語学では、さらにこれを擬声語や擬容語、擬情語といった細目で分割することもあります(*2)。
擬音語は、実際に耳に聞こえた音を模倣して擬似的に人声で表現する言葉であり、とりわけそれが生物の声を表現している場合には擬声語となります。擬態語とは、事物の状態や感情のありようを音に託して表現する言葉であり、特にこれが生物の様子を表現している場合には擬容語、さらに人間の胸中や心理を表現している場合には擬情語となります。
したがって、擬音語は聴覚的な感覚器官としての耳における経験の輪郭をなぞる言葉であり、擬態語は、聴覚以外の感覚器官としての眼による視覚、鼻による嗅覚、舌による味覚、肌による触覚をとおして知覚されたなにかが、いったん音に変換されたうえで言葉として定着したものだといえるでしょう(*3)。
日本語はオノマトペの豊富な言語であるとされます(*4)。換言すれば、オノマトペこそが日本語における表現の豊穣さを担保する肝要な因子であるとも考えられます(*5)。実際、日本に現存している最古の体系的な書物とされる『古事記』にあっても、すでにオノマトペは使用されています。「許々袁々呂々」などがそれですが、ここでは訓読みされることを懸念してあえて音読みするよう指示する注記もあり、“こをろこをろ”すなわちカラカラと音が鳴るさまが描写されています(*6)。
オノマトペとは、鼓膜に、あるいは脳裏に響いた音を、ひとつの言語を構成する一定の音素をもって表現することです。日本語におけるオノマトペの場合には、持続としてのそうした音響に対して、日本語を構成する音韻の組みあわせをとおして、できるだけもとの音響を近似的に再現できるように文節化が施されるわけです。
それゆえに、オノマトペはそもそも歌謡曲と親和性があるのです。
幼稚
新生児が最初に発する声は、例外なく泣き声です。泣くことのほか伝えるすべのなく、このためなにを欲して泣くのか大人には見当もつかなかったところが、やがて赤ん坊は喃語をもってその欲求と感情の対象を次第に文節化していき、ついには擬音語によって母を、食事を、自動車を、犬を、猫を表現するとともに、その概念を獲得します。
新生児の泣き声は、呼気が声帯を擦過するときの振動としておおむね喉もとから発せられ、ほとんど口唇が関与することはありません。けれど、授乳の機会を重ねてその口唇の動きが組織化されていく過程で原初的な喃語が実現され、さらに舌の動きもそれに与することで喃語はにわかに多彩なものとなり、それは音の世界を模倣しはじめます。そして歯が生えるころにはここにその硬い質感をも加担させて、それまで耳で吸収してきた日本語の音韻に馴致するように自らの声の響きを調整し、いずれ幼児は日本語による言葉を喋るようになるわけです(*7)。
口唇の単純な開閉にともなう口音と鼻音の連続的な交替や口唇を利用した破裂音の連鎖などがみられるオノマトペは、だからこそ幼稚に聞こえます。
ザ・スパイダースの〈バン・バン・バン〉(1967)の歌詞における「バンバン バババ ババババン」の表記や、Kuwata Band〈Ban BAN Ban〉(1986)の歌詞における「BAN BAN BAN」の表記については、なによりもまずこうした音そのものを指示対象とする擬音語であって、それぞれの楽曲にあってもっぱらその韻律に奉仕するものです。
前年にデューク・エイセスが発表した楽曲をザ・ドリフターズがカヴァーした〈いい湯だな〉(1967)では、もとの盤にはない“ba-ban-ba-ban-ban-ban”の囃子の律動が、いかにも遊興的な情趣をそこに付帯させます。
榊原郁恵が歌唱した〈Do It BANG BANG〉(1978)の場合は、そうした段階よりはいくぶんか成長がみられます。「BANG」の表記のなか「G」の刻印をもって、これが英語のオノマトペであることを強調しているからです。それは音の世界の単純に口唇的な再現たることに飽かず、ある種の文化的な蓄積を参照するものとなります。
松任谷由実による〈DANG DANG〉(1982)は、「弾丸をぶち込」む銃声として本来ならば日本語では[バン]、英語では[bang]と表記されるところを、これを「弾」の音読である“dan”に置換して「DAN」とし、さらに語尾に「G」を加えて英語のオノマトペを装います。これは、その愛称を自ら《Yuming brand》(1976)などと綴ってみせる彼女の体裁ぶりに通底する発想かもしれません。
しかもこれが「DANG DANG」と連鎖したうえで格助詞の「と」を付随させるとき、その発音は、次第に変化していくさまを形容する擬態語としての[だんだん]とも重複したうえで、つづいて「DANG DANG D-DANG」と吃るやいなや、銃弾を発射する拳銃の音を延長し、それを「ぶち込」まれた側が発するだろう音をも反映してみせます。つまりそれは、重層的で複合的なオノマトペなのです。 〈君に薔薇薔薇…という感じ〉(1982)において田原俊彦の「僕」は、「君の魅力に」完全に「感電して」しまったその「ハートは赤い薔薇」なのだと謳います。そして彼の「気持」は「すっかり薔薇薔薇」になってしまいます。「だから薔薇薔薇」、「とにかく薔薇薔薇」、「ほんとに薔薇薔薇」…。ついには「てんで薔薇薔薇」、「くずれて薔薇薔薇」といった具合いに瓦解し、崩落するその様子は、まぎれもなく「Fall in love」の語感に依拠した、擬音的にして擬態的な掛け言葉です。
滑稽
佐野元春のデビュー曲となった〈アンジェリーナ〉(1980)では、「ブルル……」と表記される歌唱で「エンジン」の「うな」りが再現されています。有声の破裂音「ブ」ののち、「ルル……」の箇所は巻いた舌で硬口蓋を連続的に高速で叩いているぶん高度な発音ですが、しかしこれは歌唱というよりも「エンジン」の「うな」りのものまねに近く、表現される対象とのこうした密着ぶりに関しては、言葉として機能する直前の擬音の状態にあるというべきかもしれません。
佐野はまた、大瀧詠一が企画し、杉真理とともに参加した《NIAGARA TRIANGLE VOL.2》(1982)に先行するシングル盤〈A面で恋をして〉(1981)の吹き込みをめぐって、「夜明けまでドライブ」のフレーズについても「ブ」の箇所で今度は口唇を連続的に高速で破裂させています。これもやはり、あらかじめ日本語に収まる“bu”の音韻であるよりはむしろ、そうして彼の口もとから発生する連続的な破裂音を「ブ」の側に嵌め込んだ響きにちがいなく、もはや擬音どころかそれ自体が「ブ」の文字を介してようやく文節化されるような、不断の音の持続そのものにほかならないでしょう。
言葉と効果音のいずれに着地するものか曖昧なまま発せられる佐野によるこれらの事例は、どれほどか児戯的であり、それゆえ歌謡曲にあっては滑稽にも響きます。
鶴岡雅義と東京ロマンチカによる〈ああ北海道には雪が降る〉(1974)では、“pa-payap-pa”だの“paya-pap-pap-pa”だのとでも表記されるべきバックコーラスの歌声が、主旋律の歌唱や楽器の演奏に呼応して組み込まれます。このとき、口唇を利用した彼らの破裂音は、それが世界の側と結託してオノマトペとなるための準備として、その偶発的な音の発生を規則化し、再現可能な身体性のかたちで管理していこうとする遊戯のようでもあります。堅苦しくスーツを着込んで生真面目そうに整列した大人の男たちがスタンドマイクを相手にそうして発揮する幼稚性も、歌謡曲の滑稽な側面となりえます。
家入レオの〈チョコレート〉(2014)において、「涙の数」と「チョコレート」のあいだを埋めるように歌われる“po-po-po”の音韻は、歌詞カードに記載されていません。「チョコレート」を予告する場合には“cho-cho-cho”とでも発音したほうが韻律としてなじむはずが、ここでは不可視の半濁点で「涙の数」を数えるように、柔らかい無声の破裂音の丸みが連鎖します。
それでもやはり、この音響的な持続は、なによりもまず鳩の鳴き声だの汽車の進行音だのを想起させる以上、これが旋律に乗せられるやいなや幼稚にして滑稽に聞こえてしまうことは不可避です。大瀧詠一の単独でのデビュー盤となった〈恋の汽車ポッポ〉(1971)などは、それを望むところとする真骨頂でしょう。
ニセレキシとして招聘されたU-zhaanのタブラーがレキシの謡いに同調する〈Takeda’ 2 feat. ニセレキシ〉(2015)では、「馬」の「パカパカ」という足音を基軸に、「アルパカ」の「可愛さ」へと転じた言及は、この「アルパカ」をも「パカパカ歩」かせたすえに、ついには「コパカバーナ」にまで到達します。レキシの声が馬の足音の擬音語を詠じるここで、それに呼応したニセレキシによるタブラーの打音はまさにその足音を再現してみせます。
この楽曲は、一聴したところ、なるほど「織田」と「武田」の「設楽原」での合戦に取材しているものの、実際にはその全篇が、人声による呪文的な韻律と原始的な楽器としてのタブラーの打音との同期とずれとが生みだす、人間と世界との音声を介した呪術的ないし土着宗教的な交感となって響きます。
したがって、そこでの言葉はすべからく原始の祈りのオノマトペとして鼓膜に晒されるものであり、このことは、擬音語としての「パカパカ」の件を排除した別テイクである〈Takeda’〉(2014)に漲る緊張感に顕著です。ただしこちらでは、「馬」の蹄のかわりに「恐竜」の「ツメ」をもって「カーッとや」られずにはいません。
クレイジー・キャッツ
日本の芸能もしくは大衆音楽の歴史において、現存するなかもっとも古いオノマトペの録音は、パリ万国博覧会の公演中に川上音二郎一座により吹き込まれたとされる〈オッペケペー節〉(1900)です(*8)。文明開化への盲信的な邁進にもとづくうわべばかりの西洋化を揶揄すべくそこに残された“オッペケペー”の響きは、いわば嘲笑まじりの諧謔心のオノマトペによる吐露となるはずです(*9)。
これは、社会や政治の風潮に対する批評性を、否定的な言辞をとおして批判的に提示するサディスティックな行為です。そうではなく、むしろ肯定的なかたちでそれに過剰なまでに同調し、このマゾヒスティックな従順さをもってその歪さを露呈させるとき、オノマトペは、幼稚で滑稽な本来のありようのまま、無邪気にも批評性を獲得します(*10)。
歌謡曲にあって、そうしたオノマトペの宿命をもっともよく理解し、これがもっとも効果的に展開されたのは、おそらく、ハナ肇とクレイジー・キャッツの周辺でのことにちがいありません。
青島幸男と萩原哲晶が彼らに提供する楽曲は、とりわけそれらを主題歌なり挿入歌に採用した映画作品のなかで、高度経済成長期の熾烈な上昇志向のもと立身出世にあくせくするクレイジーの面々のサラリーマンを傍目に、業務上の困難をでたらめにこなし、まんまと成功していく植木等の配役の脱力したのんきさを象ります。軋轢だらけの社会をストレスなく愉快に生き抜くそのC調なとぼけたイメージは、青島によるオノマトペや萩原による編曲をもって的確に描写されます。
〈スーダラ節〉(1961)の相伴に与って大映が製作した『スーダラ節 わかっちゃいるけどやめられねえ』(1962)につづいて、東宝が古澤憲吾の監督により『ニッポン無責任時代』(1962)を発表したことがその端緒となりました。
「ゴロ寝」や「すっからかんのカラカラ」はもちろん、特に「チョイト一杯」や「チョイとだまされた」の文句における擬態語は、いかにも軽率に響きます。そのうえで、どこまでも無責任な「ア ホレ」の掛け声を合図に、「スイスイ スーララッタ」ときて「スラスラスイスイスイ」とまとめられるフレーズは、渡世の荒波のはざまを水の抵抗の微塵も感じさせることなく軽妙に泳いでいくその処世のさまを、遺漏なく鮮やかに表現してみせます。
今度は「山」です。翌年に公開された『クレージー作戦 先手必勝』の主題歌となった〈ホンダラ行進曲〉(1963)では、「越しても越しても」波ならぬ「山」が植木等の行方を塞ぎます。もちろん、彼のかわりにたとえばハナ肇が「会っても会っても」、あるいは谷啓が「行っても行っても」、ついには彼らが束になって「やってもやっても」、結局のところ「この世は」ままなりません。「だからやらずに」、と彼らは「ホンダラダホイホイ」を斉唱するのです。
なるほど、たとえ植木等が体現した高度経済成長期のC調な軽薄さをもってしても「どうせこの世は」ままならぬものかもしれません。それでもなお、そうした諦念のなか、しかしそれ「だから」こそただひとり虚無に浸るのではなく、あくまでも「みんなで」いっしょに「ホンダラダホイホイ」と唱和するように、植木は私たちを促します。そしてこの題目の唱和を介して、彼らの、私たちの「この世」に対する執着は放擲され、世界との無頓着にして無責任な関係性のうちに平安な境地が訪れるわけです。
藤田敏雄が作詞し、宮川泰が作曲した〈ウンジャラゲ〉(1969)は、のちの志村けんらによるカヴァー盤で有名な楽曲です。そこでは「月曜日」から「日曜日」まで、「あけみちゃん」から「みえちゃん」まで、「サラリーマン」から「大学生」まで、すべてが「ウンジャラゲのハンジャラゲ」、「スイスイスイのモーリモリ」、「キンキラキンのギンギラギン」、「ランラ ランラ ラン」などといったオノマトぺにしたがって並置され、曜日や人名や職名など列記された名辞の属性は、繰り返されるその音響によってたちどころに奪取されてしまいます。
オノマトペの反復をもって世界を揺さぶり脱臼させる天才が植木等だとすれば、たったひとつの発声で世界をまるごと要約するオノマトペの天才、まぎれもなくそれは、〈愛してタムレ〉(1963)の最後を“ガチョン”で閉じ、〈あんた誰?〉(1964)の冒頭で“ビローン”と叫び、〈アイヤ・ハラホロ〉(1992)では「むひょー」と朗じる谷啓のことでしょう。
音としての動揺
谷啓による“ガチョン”は、日本全国に知られた彼の傑作ギャグです。ブラウン管のなかで彼がこれを提示するとき、“ガチョン”の発声にはいつもあの右手の所作がともないます。“ガチョン”の響きはこの所作と不可分のものであって、しかもその実現のあかつきには、これを撮影していたテレビカメラもズーム操作のインとアウトを小刻みに繰り返し、これに反応することが定型でした。
要するに、谷のあの右手の所作のみならずこのようなカメラの反応まで含めた一連の出来事、その持続を表現する擬態語こそが“ガチョン”なのです。そうして、宇宙に内在する持続につながれた赤い糸を手繰るように指先を窄め、空気もろとも世界を掌へと回収する谷のあの所作は、彼の仏像的な相貌をより説得力あるものとします(*11)。
“ガチョン”とは、だから私たちがなにかに心を捕獲された瞬間の動揺、その突然の衝撃を表現する擬態語なのかもしれません。そしてその都度、これに共振したオノマトペが私たちの心のどこかから聞こえてきます。
たとえば河合奈保子が歌唱した〈ヤング・ボーイ〉(1980)において「胸がキュンとなる」とき、まさしくそれは、この不意打ちににわかに収縮した「胸」に感じる繊細な痛み、締めつけられた心が鳴くその響きを聞いたものであり、Y.M.O.による〈君に、胸キュン。〉(1983)はこの現象を「胸キュン」として名詞化しています。
小泉今日子の〈渚のはいから人魚〉(1984)における「ズキンドキン」もやはり、収縮と膨張を繰り返す胸の鼓動、それに応じて身体を駆けめぐる血流の脈拍にともなう痛みを表現します。
相対性理論の〈LOVEずっきゅん〉(2007)の場合には、そうした痛みの起因となる一撃、いわば“ガチョン”の側の発射音をも「ずっきゅん」の語をもって包摂し、この「ラブ」が「わたし」からの一方向的な思い込みではなく、あくまでも「君」から放たれた射撃にもとづく双方向的なコミュニケーションにほかならないことを説諭します。既存のオノマトペを複合して新規の響きを創出し、もとの位相をずらして重層化していくその手練は、松任谷由実の〈DANG DANG〉を踏襲するものです。
やがて鼓動の昂りに高揚する胸は軽快な律動を刻みはじめ、弾む心は浮遊感で満たされていきます。〈妖精ポピンズ〉(1986)はポピンズの楽曲ですが、「合言葉」であり「夢のテレパシー」であり「愛の呪文」であるような「PiPiPaPiPo…」の文句は、編曲を担当した清水信之の差配により楽曲の全篇を支持する電子的な音質を象ってみせます。井上大輔が得意とする曲調に新鮮味を付加するそれは、「妖精」の非人間的な存在性に人造感を纏わせたうえで、「恋」を誘う「夏の日が近づく」ことへの高揚を軽やかに謳うのです。
松本伊代の〈TVの国からキラキラ〉(1982)もまた、恋する少女の世界観をオノマトペの列挙をもって提示します。「お花いっぱいフワフワ」、「見つめかえせばドキドキ」、「カンニングさえサラサラ」。しかしながら、「わたし」が「古い少女マンガの まるでヒロインみたい」に扱われるここではやはり、「夜空の星」も「わたしの瞳」も、「彼の瞳」も「街の景色」も、「彼の微笑み」や「ともだちの顔」や「先生の顔」や「黒板までも」、つまるところ「なにもかもが」、「恋の光でキラキラ」と煌めかずにはいません。
「見つめられたら」、「涙おちても」、「思い出にな」ろうとも、彼女の世界にあっては「なにもかもが」すべからく「キラキラ」すべきなのです。それゆえに彼女は訊ねます。「ねえ 君ってキラキラ」?そしておそらく、なにをおいても「キラキラ」しないことには、「あのひと」となって彼女の世界を共有する資格は「君」にはないでしょう。
伊藤と松本の楽曲の作詞が、それぞれ仲畑貴志や糸井重里ら、このころもっとも輝いていた文字表現の操り手たるコピーライターの筆によることは、これらの歌詞におけるオノマトペの頻出を担保する要素と考えられます。
《はっぴいえんど》
はっぴいえんどは、その活動期間のなかで3枚のアルバムを制作しています。11曲を収録し、俗に“ゆでめん”と呼ばれるデビュー盤《はっぴいえんど》(1970)をはじめ、12曲を収録した《風街ろまん》(1971)、9曲が収録された《HAPPY END》(1973)がそれです。
これらの楽曲を俯瞰してみれば、彼らがオノマトペを多用した事実は容易に捕捉できます。そしてその理由について考慮するとき、この事実は、彼らが概念形成していった歌謡曲における日本語のありようをめぐって、彼らの企図の理解に与する一定の観点を提供しうるにちがいありません。音の響きとともに、音の響きとしてあらんとする歌声は、あらゆる言葉をオノマトペの状態へと還元することを志向せずにはいないからです。
まず、《はっぴいえんど》では、松本隆の歌詞に大瀧詠一が曲をあてがった2曲目の〈かくれんぼ〉において、はっぴいえんどによる最初のオノマトペを聴くことができます。
その、「裡でそおっと滑り落す」のフレーズについては、しかし“そっと”ではなく、あくまでも「そおっと」と表記されていることに注目すべきでしょう。つまりこの表記は、「君」に悟られることなく「吐息のような嘘」を「一枚」、「私」がひっそり静かに「滑り落」としたさまの擬態語であるとともに、これを三つの音符で“そ-おっ-と”と歌唱する大瀧の声の抑揚を、書き言葉としての文字をもって文節化した擬音語でもあるでしょう。要するに、それは音の言葉であると同時に言葉の音でもあるわけです。
細野晴臣の作曲である3曲目の〈しんしんしん〉は、その題名からすでにオノマトペをもって綴られています。ただし松本による歌詞の言葉それ自体のうちには、周囲の雑音を吸収しながら降る「雪」の「都市に積」っていくいかにも静寂なさまは、まさしくこれが「黙りこくった雪」の景色であるがゆえか、たとえ無音を表現する擬音語であれ、音という音はそこに吸収されてしまい、細野の歌声で象られることはありません。
5曲目の〈敵 TANATOSを想起せよ!〉も、やはり松本と細野の詞曲です。ここでは、主人公が体験した「とても不可思義な夜」を、「うとうと」と居眠りでも「している隙」の、夢とも現ともつかない出来事としています。
8曲目の〈いらいら〉の詞曲は大瀧詠一によるものです。「時計の音が/気にな」って「眠れない」ばかりか、「苦し」さは「多過ぎ」て「息をすることも/できない」し、「街」でも「部屋」でも「何もいいことなんて/ない」。そうして堆積する否定辞「ない」は、しかしながら、この楽曲に充満した「いらいら」の原因ではなく、むしろ「いらいら」の響きをそのように充溢させるための口実です(*12)。
つづく《風街ろまん》では、その冒頭を飾る〈抱きしめたい〉から10曲目に相当する〈颱風〉まで、収録曲の半数以上でオノマトペの使用が確認できます。このため、基本的にはひらがな50音を羅列させた歌詞にすぎず、情景も状況も描写されない最終曲〈愛餓を〉においてさえ、「てとと」と吃る韻律などからオノマトペの感触が伝わってきます。
《風街ろまん》
松本の詞と大瀧の曲からなる〈抱きしめたい〉において、歌詞カードでは改行を介して「ゴオ/ゴオ/ゴオ」と再三にわたり繰り返される音の表記は、実際には多声で次第に重なりつつ歌唱され、左右に揺れる音効のなか言葉であるよりはむしろ音色として持続するとともに、「雪の銀河」たる「白い嚝地を切り裂」きながら「走」る「冬の機関車」の勢いに“go”と指示する声のようにも聞こえます。
単にはっぴいえんどのみならず、歌謡曲の歴史における傑作のひとつといって過言ではない3曲目の〈風をあつめて〉は、それゆえに、のちに松田聖子に提供された〈天国のキッス〉を実現する松本と細野の協働による初期の代表作です。「伽藍とした」の語は、ここでカタカナによる表記ではなく漢字によることで、伽藍堂の内部が広く天井の高く吹き抜けたさまを借りてその場所の空虚さを描写する語源を参照し、この構造物の具体的な形態をにわかに屹立させる擬態語であるとともに、大きな鈴の鳴らされる低い硬質の音響を声色で模倣した擬音語としても歌唱され、楽曲が生成するイメージをきわめて豊かなものとします。
同じ作詞者と作曲者による4曲目の〈暗闇坂むささび変化〉では、「ギラギラ光る目」のほか、「蝶々はひらひらひーら」や「蝙蝠はぱーたぱた」など、基本的に双眼や双翅、双翼といった視覚的に双対の状態の事物を強調するように「ギラ」や「ひら」、「ぱた」の音韻が重ねられます。
レコード盤ではB面の冒頭に配置され、通算で7曲目に相当する〈夏なんです〉からは、〈颱風〉に至るまで、連続するすべての楽曲でオノマトペが使用されています。
〈夏なんです〉も松本と細野が提供した楽曲です。「奴ら」が「地べたにペタンとしゃがみこ」んだここでは、「夏」のありさまが擬音語や擬態語によって表現されます。ひとまずそれは、「ギンギンギラギラ」と輝く「太陽」であり、「ホーシーツクツク」と鳴く「蝉の声」であり、「モンモンモコモコ」と湧く「入道雲」であり、そして「くるくる」と回される「日傘」でした。ただしこれらオノマトペは、季語として扱われる名詞群からただちに遊離し、それ自体で「夏」をかたちづくることになります。
〈花いちもんめ〉は、鈴木茂がはじめて作曲した楽曲です。松本隆による歌詞のもと、「巻き起こる/たつまき」で「街はぐらぐら」と揺れる一方で、「おしゃれな風」は「陽炎の街」に「花びらひらひら」と舞わせます。この「花びら」の「ひらひら」と舞うさまは、〈暗闇坂むささび変化〉における「蝶々」のたゆたうさまと等価であり、細野によるA面の楽曲をここに織り込んでみせます。
またしても松本と細野が組んだ〈あしたてんきになあれ〉では、「雨がしとしと」と降るなかを、「少女」の「微笑」が「雨」の雫のように「ぽつん」と爆ぜます。やがて「旧いフィルムのようなざぁざぁ雨」ともなれば、「少女」の「涙」は「雨」の粒のように「ぽつり」と堕ちます。そこで「黒雲」を「びゅうびゅう」と往来させただろう風は、けれどいまや「虹」に「雨」の滴としての濁点を運び去られ、「少女」の「ふけもしない口笛」を「ひゅうひゅう」と鳴らす息のうちに縮減されます。
〈颱風〉にあって、こうした「風」が「どんどんどんどんふいてくる」 とすれば、これはまぎれもなく「台風」の兆しです。宮沢賢治の『風の又三郎』を想起させるべくそれは「どどどどどっどー」と「みんな吹きとば」し、「地面にぴしぴしとびはね」ている「雨粒」ともども「そこら一面」を「ぐるぐるぐるぐる踊りまわ」ります。これほどまでの轟音のあまり、「街」の喧騒さえ「しーんと闇くな」ってそこに埋没せずにはいないでしょう。
《HAPPY END》
ところでこのとき、「窓の簾」は「洌たい風」をもって「ぐらぐらゆさぶ」られます。すでに〈花いちもんめ〉でも「巻き起こる/たつまき」で「街はぐらぐら」していたのだから、今度は大瀧の作詞によるこの楽曲がそこに組み込まれることになったとしても無理はないはずです。この限りにおいて、鈴木茂が作曲した〈花いちもんめ〉を舞台に、松本隆は、大瀧詠一が作曲した〈颱風〉の暴力性と細野晴臣が作曲した〈暗闇坂むささび変化〉の洒脱性とを、ほかでもないオノマトペをとおして対置させていたことになります(*13)。
《風街ろまん》からは、このバンドにおける人間関係の微妙な実際にもかかわらず、そうしたわずらわしさには還元されない彼らの感覚の共鳴が、言葉の音ないし音の言葉を介していまなお聞こえてきます(*14)。そしてそれゆえに、彼らの本領が発揮されたこのアルバム盤は、日本の大衆音楽の金字塔たりうるのです。
《HAPPY END》の場合にも、擬音語や擬態語のいっそうの使用が確認できます。
その冒頭に収録され、小坂忠の《HORO》(1975)が〈ふうらい坊〉としてカヴァーした〈風来坊〉の詞曲は、小坂の盟友である細野晴臣によるものです。ここでは「ふらり」と「ふら ふら」の連係が、単に「風来坊」の語をめぐる「ふ」音や「ら」音と音響的に韻を踏むばかりでなく、この語が意味する突発性や無頼性、不安定性と字義的にも韻を踏んでいます。そのうえで、「ふ」音の発声においては、その都度「風」が発生することになります。
つまるところ、細野の歌唱をもってここに不意に「風」が「来」たるのです。こうした観点からすれば、小坂の盤における「ふうらい坊」の表記は、細野の歌詞の言葉について音響的な韻律のみを強調しすぎるきらいがあります。
3曲目は、松本隆が鈴木茂の曲に歌詞を提供した〈明日あたりはきっと春〉です。そこで「ひっそりと」静まっている「冬化粧」の「砂糖菓子の街」は、のちに伊藤つかさが「雪」の「冬」に「まろやかなざわめき」のもと「ケーキのようなビル」が建つ「クリームの街」と謳った、佐伯健三による〈クリーム星人〉(1984)の歌詞の着想源かもしれません。その「空をゆっくりと渡ってゆ」きながら、「冬はだんだん遠くな」ります。穏やかに、緩やかに、時間は流れていくのです。
このアルバム盤のB面は、はっぴいえんどの名義で詞曲が作られ、彼らの最後の作品となった〈さよならアメリカ さよならニッポン〉を除き、すべての楽曲でオノマトペが使用されています。
松本と鈴木は、B面の端緒に相当する5曲目の〈さよなら通り3番地〉でも共演しています。〈明日あたりはきっと春〉にあって「冬化粧」の「白は流れ」たように、「知らない空が 」ここで「ぐるりとまわり」、あわせて「冬の絵の具」も「淋しく流れ」ていきます。「ぐるりとまわ」った「知らない空」とは、だから〈明日あたりはきっと春〉の「冬」が「ゆっくりと渡って」いったあの「空」のことにちがいなく、盤の両面を「ぐるりと」循環して、この両曲はひとつの運動へと生成するのです。
〈相合傘〉は細野の作品ですが、「どの路地もひっそり」しているのは松本の言葉の影響かもしれません。ただし「おてんと様ギンギラギン」の「あの町 この町」のなかでは、「ひっそり閑」が「すっからかん」と韻を踏み、また「ほおづき クチュ クチュ」と「ほおずりクスクス」の押韻はなお明瞭です。
〈田舎道〉およびこれにつづく〈外はいい天気〉は、ともに松本が供給した歌詞をもとに大瀧がほとんど即興で作曲した作品だといいます(*15)。
〈田舎道〉では、「向日葵ぼうぼう燃えている」、「おかみさんにこにこごあいさつ」、「太陽ざあざあ降りそそいで」のいずれのフレーズにも、主語+オノマトペ+述語の文章構造が共有されています。〈外はいい天気〉における「きみはひとりぽつん」の表現は、《風街ろまん》の〈あしたてんきになあれ〉を否応なく想起させ、その願いが叶って「今朝」に晴れの「ひかり」を迎えたところとみなすこともできます。
声と音のあいだ
はっぴいえんど解散後の活動拠点として設立した個人レーベルについて、大瀧詠一は、松本隆による歌詞の世界観をいったん否定してみることもその目的のひとつに掲げています(*16)。
そこでの試行のもと、自作として最初に発表された《Niagara Moon》(1975)は、メロディではなくリズムを基調とした楽曲づくりを標榜するものです。とりわけ、〈Cider’73〉では「ジンとくる」や「いきいき一息」、〈Cider’74〉では「キラキラ こぼれる」、〈Cider’75〉でも「どきどきどきどき」など、伊藤アキラが作詞した楽曲はCMソングとオノマトペの相性のよさをうかがわせます。
たとえばこれ以降も、そうした試行のほとんど最後の局面としてのちの《A LONG VACATION》(1981)の趣意を準備する〈青空のように〉(1977)には、大瀧自身の作詞により「ニコニコ顔」や「くるくる変わる」、「ぐるぐる回る」といった表現がみられます。
〈Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語〉(1981)は、このような経緯ののちあらためて歌詞を松本隆に委ねた《A LONG VACATION》の収録曲のなかで、唯一、大瀧詠一が自ら作詞した作品です。ここには「アツ アツ」や「グッと」、「ヒラリ」や「サラリ」といったオノマトペのほか、「イツ イツ」や「ドコドコ」のような不定称の代名詞が、「アツ アツ」との共振のなかでさもオノマトペであるかのようにふるまい、事実、大滝詠一による歌唱においては、「ドコドコ」は「恋人」である「2人」の「アツ アツ」の心拍または脈動にも聞こえてきます。
しかしながら、ここで重要なこと、それは、「Pap-pi-doo-bi-doo-ba」と表記された歌詞の言葉についてです。というのも、この楽曲にあって当該のフレーズを歌うのは、もはや大滝の声ではなくシンセサイザーの合成音だからです。
すでにここでは、人声がなにがしかの音や様子を擬似的に模するどころか、人工的な楽器の演奏音の側が人声をまねてその擬音を発しているわけです。楽器による擬声語、あるいはむしろ擬語音とでもいうべきこのフレーズは、単なる偶発的で一回的な、それゆえ一過性の演奏音ではなく、あくまでも「Pap-pi-doo-bi-doo-ba」と綴られる文字列をとおして再現されうる響きとして、この楽曲の聴き手の耳がその輪郭を人声でなぞって文節化できるように設計された音の持続であることは明白です。
この意味において、それは擬語音であるばかりか、まるで「ハナウタを歌うよに」、または「呪文でも となえるよに」、シンセサイザーが彼らなりの仕方で「Pap-pi-doo-bi-doo-ba」と「言」ってその響きを表現してみせた、まさにオノマトペの擬音語にちがいないでしょう。
音と声のあいだに言葉は出来し、声と音のあいだで言葉は消失します。この出来と消失の次第こそがオノマトペの響きなのです。
「泣かないぞ」と決意した〈泣かないぞェ〉(1995)の「私」が、これにつづけて鈴木蘭々の歌唱のもと「泣かないぞェ」と自らにいい聞かせる場合の「ェ」の彩りとは、まぎれもなくそうしたものです。胸中を音声に変換するにあたってはじめて発生し、この変換なしにはおそらく実現することのないその響きは、英語における[it]の韻律のごとく差配され、けれどいまだ日本語には不在の言葉として出来し、「私」の意気込みを彼女自身に向けて表明する個人的なオノマトペとなります。もはやそこでは、鈴木蘭々の名前もまたオノマトペ的に聞こえてくるかもしれません。
クラムボンの〈yet〉(2015)では、この題名に対して「やっと」の語が音響的な韻を踏んでいます。そしてそれによって字義的には逆相の韻が踏まれ、この語に先行する「あとから」の語がもたらす未然の感触を強調することにもなります。
しかしながら、ここではやはり「いっせーのーせ って 声 きこえる?」と記述されるフレーズが肝要でしょう。[一斉]から派生した間投詞ではあれ、すでにここでの「いっせーのーせ」とは、「苦しみ」や「悲しみ」の「傷の深さもわからないままで」こうして「のこされた 僕ら」に、それでもなおその「先の 先」にある「あたらしい未来」のためにともに生き「つづけ」ることを促すべく、どこからともなく「きこえ」てくる地鳴りにほかなりません。
ときに不吉に響くこの振動を聞きわける稀有の聴覚器官に恵まれ、たちどころにそれを自らの歌声で象ってみせる原田郁子の歌唱は、「のこされ」てしまったがゆえに「ここにいる 僕ら」の「今」にすくんだ足もとを、わずかであれ「未来」へと、「先の 先」へと投じさせるような、いわば勇気の発露として、それをオノマトペのかたちで出来させるものです。
*1 吉本隆明,『言語にとって美とはなにか』第Ⅰ巻, 勁草書房, 1965, p.23.およびpp.33-34.
*2 浜野祥子,『日本語のオノマトペ―音象徴と構造―』, くろしお出版, 2014, p.2.
*3 桜井順,『オノマトピア―擬音語大国にっぽん考』, 岩波書店(岩波現代文庫), 2010, p.222.
*4 田守育啓,『オノマトペ 擬音・擬態語をたのしむ』, 岩波書店, 2002, p.v.
*5 小野正弘,『オノマトペがあるから日本語は楽しい 擬音語・擬態語の豊かな世界』, 平凡社(平凡社新書), 2009, pp.7-12.
*6 同書, pp.140-164.および川田順造,『口頭伝承論 下』, 平凡社, 2001, pp.231-234.
*7 桜井, 前掲書, pp.223-234.
*8 永嶺重敏,『オッペケペー節と明治』, 文藝春秋(文春新書), 2018, pp.19-24.
*9 川田順造,『口頭伝承論 上』, 平凡社, 2001, pp.29-33.およびp.202.
*10 大瀧詠一,『大瀧詠一 Writing & Talking』, 白夜書房, 2015, pp.450-451.
*11 高田文夫,『笑うふたり―語る名人、聞く達人』, 中央公論社, 1988, p.164.およびアンリ・ベルクソン,『創造的進化』, 真方敬道/訳, 岩波書店(岩波文庫), 1979, p.32.
*12 大瀧, 前掲書, p.718.および大瀧詠一,『All About Niagara』, 白夜書房, 2001, p.361.
*13 大瀧,『Writing & Talking』, p.35.およびpp.787-788.
*14 門間雄介,『細野晴臣と彼らの時代』, 文藝春秋, 2020, pp.149-154.および田家秀樹,『風街とデラシネ 作詞家・松本隆の50年』, 角川書店, 2021, pp.63-65.
*15 田家, 前掲書, p.66.
*16 大瀧, 前掲書, p.103.
堀家教授による、私の「オノマトペ」10選リスト
1.〈愛して愛して愛しちゃったのよ〉和田弘とマヒナスターズ・田代美代子(1965)
作詞・作曲/浜口庫之助,編曲/寺岡真三
“ランランランラン”のコーラス・ワークとスティール・ギターの甘い音色なしには、この楽曲の魅力は半分にも満たされないだろう。スティール・ギターの無階調で滑らかな音程の上下は、“ランランランラン”が表現する心拍や脈動の歯ぎれいい高揚を、その昂りにもかかわらずきわめて切ないものに変える。原曲は、同じ浜口庫之助が作曲した〈黄色いさくらんぼ〉も歌った、スリー・キャッツの小沢桂子による〈愛しちゃったの〉。
2.〈涙の太陽〉安西マリア(1973)
作詞/湯川れい子,作曲/中島安敏,編曲/川口真
同曲でデビューしたエミー・ジャクソンの盤では英語詞だったところを、これを作詞した湯川れい子自身が日本語詞をあつらえて、今度は安西マリアのデビュー曲とした楽曲。“エレキ歌謡”真っ只中の原曲の編曲に対して、川口真は管楽器を多用し、しかもドラムスの音像とともにその重心はきわめて低い。重く鈍く激しく奏でられるブラスの音の質感は、まさしく「ギラギラ太陽」の輝くさまに聴覚的に同調するものである。
3.〈硝子坂〉木之内みどり(1977)
作詞/島武実,作曲/宇崎竜童,編曲/ラスト・ショウ,瀬尾一三
馬飼野康二が編曲し、高田みずえのデビュー曲として知られたこの楽曲は、だがそれ以前に木之内みどりのアルバム《硝子坂》の表題曲として発表されている。わずかに演歌調のこぶし回しが聞かれる高田の堂々と安定した歌唱よりも、やはり木之内の歌唱のほうが「キラキラ光る硝子坂」の脆い煌めきを表現するにはふさわしい。編曲においても、「キラキラ」の歌声を追って聞こえるディレイ効果や、その歌唱を促すように鳴らされるウィンド・チャイムの繊細な高音など、擬態語を演奏音へと変換する試みがこぞって木之内の存在性をなぞる。
4.〈情熱☆熱風☽せれなーで〉近藤真彦(1982)
作詞/伊達歩,作曲/筒美京平,編曲/大谷和夫
近藤真彦のシングル曲について、オノマトペを扱ったものとしてもっとも人口に膾炙したのは「ギンギラギンにさりげなく 」と謳った〈ギンギラギンにさりげなく〉であり、もしくは「Zig Zag Zag, Zig Zag Zig Zag一人きり 」と歌われた〈スニーカーぶる〜す〉であろう。それでもなお、ここでは伊達歩の名義で伊集院静が綴った「ハラハラ」「キラリ」「ドキドキ」「ドギマギ」「グサリ」などの擬態語が頻出し、また筒美京平の天才が遺憾なく発揮されたこの楽曲を推す。カルチャー・クラブの〈君は完璧さ(Do you really want to hurt me?)〉の剽窃にも聞こえがちだが、発売はこちらのほうが先である。
5.〈バージンブルー〉SALLY(1984)
作詞/さがらよしあき,作曲/鈴木キサブロー,編曲/鈴木キサブロー,大島ミチル
ストレイ・キャッツの登場を機に新しいロカビリーの波が日本にも到来し、チェッカーズの雛形となるが、同様の文脈のもとデビューしたSALLYは、しかしチェッカーズの人気に圧倒されてしまった。にもかかわらず、この時代にいくつもの佳曲を発表した鈴木キサブローによる〈バージンブルー〉は、チェッカーズのどの楽曲と並べても勝るとも劣らない秀作である。大島ミチルの活動最初期の関与作品。
6.〈抱いた腰がチャッチャッチャッ〉ビートたけし&たけし軍団(1984)
作詞/大津あきら,作曲/大沢誉志幸,編曲/井上鑑
映画監督としての北野武より以前に、声の限りにシャウトするこのビートたけしを知ることができた人生のどれほど幸運であったものか。
7.〈Ban BAN Ban〉Kuwata Band(1986)
作詞・作曲/桑田佳祐,編曲/KUWATA BAND
日本語のロックならぬ《NIPPON NO ROCK BAND》を標榜した桑田佳祐のプロジェクトによる最初のシングル曲。それゆえザ・スパイダースの〈バン・バン・バン〉を意識したところもあるにちがいないが、むしろロックなどという偏狭な範疇に収まらない歌謡曲の豊かさを感じさせる作品として、以降の桑田の音楽のありかたについて彼自身に再考を迫る契機ともなっただろう名曲。
8.〈泣かないぞェ〉鈴木蘭々(1995)
作詞/鈴木蘭々,森園真,作曲/筒美京平,編曲/田辺恵二
1990年代の筒美京平作品における最高傑作。R&Bのテイストを歌謡曲に浸透させた安室奈美恵に対して、鈴木蘭々の驚嘆すべき歌唱力のもと、この楽曲はファンクのテイストを歌謡曲に織り込む。「パリッと」「ぐぅーと」「ずーっと」といった擬態語にも増してここで耳に訴えるもの、それはまぎれもなく「ェ」の響きである。当初は記譜されていなかったこの音については、レコーディングに立ちあった筒美による現場での即興的な指示により実現したことを鈴木が証言している。萩田光雄が編曲を担当したストリングスとホーンは、この盤の活力に多大な貢献を呈する。
9.〈yet〉clammbon(2015)
作詞/原田郁子,作曲/ミト
ストリングスのアレンジに菅野よう子を迎え、ダイナミックにしてドラマティックな構成となった逸品。なにより、歌い終わった母音の名残りの、高域で丸まり、それでいて抜けのいい声の余韻が、ここでの原田郁子の歌唱の魅力である。かろうじて「バラバラ」の畳語が使用されているが、間投詞「いっせーのーせ」が無音の状態で胸中に響くとき、その潜在性を旋律に嵌めて表出させる彼女の歌声とは、この間投詞が用いられるべき状況を私たちに示唆するオノマトペとして機能するはずである。
10.〈Takeda’ 2 feat. ニセレキシ〉レキシ(2015)
作詞・作曲/池田貴史
池田貴史による謡声とU-zhaanによるタブラーの打音とは、この楽曲においては一心同体であって、それゆえ声と音とが不可分に密着して奏でられる。声は律動を語る音となり、音は抑揚を刻む声となる。それらはそれぞれの仕方で互いを反映しあって響き、それをもって大地の鼓動を表現するオノマトペとなる。
番外_1. クレイジー・キャッツ周辺
歌謡曲にあっては、クレイジー・キャッツはオノマトペのために、オノマトペはクレイジー・キャッツのために存在する。
番外_2. はっぴいえんど周辺
バンドとしてのはっぴいえんどをはじめ、作詞家となった松本隆などそのメンバーが個別に関与した楽曲においてさえ、そこでのオノマトペのありようを考慮するとき、彼らのバンドの試行したもののなんたるかが輪郭を明瞭にさせる。
番外_3. 女性アイドル“テクノ歌謡”周辺
コピーライターによる言葉とシンセサイザーによる音色と女性アイドルによる歌唱は、オノマトペをめぐってきわめて相性がいい。仲畑貴志と坂本龍一が詞曲を提供した伊藤つかさの〈恋はルンルン〉がその典型だが、松本伊代の〈TVの国からキラキラ〉は糸井重里が作詞し、スターボーの〈ハートブレイク太陽族〉は細野晴臣が作曲し、ポピンズの〈妖精ポピンズ〉は売野雅勇の歌詞で清水信之が編曲している。けっして安定しているわけではない歌声や巧みなわけではない歌唱、彼女たちの稚拙な表現力を逆手にとって、情景描写を拒絶するコピーライターの言葉とシンセサイザーの安っぽく人造的な合成音とが、まるで等身大のカラフルな玩具で構成されるようなポップな異世界を彼女たちのためにかたちづくってみせる。したがって、そこでは彼女たち自身もおもちゃのように弄ばれることは不可避である。いわばそれは、のちの初音ミクに代表されるような、不完全で不自然な合成音声を意のままに扱ってコンピュータの内部で実現される楽曲の制作様式をさきがける試みとして、いまなお以下のような問いを私たちに投げかけつづけている。すなわち、音とはなにか、声とはなにか、音楽とはなにか、言葉とはなにか、歌とは、歌謡曲とは、そしてアイドルとはいったいなにか。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店





