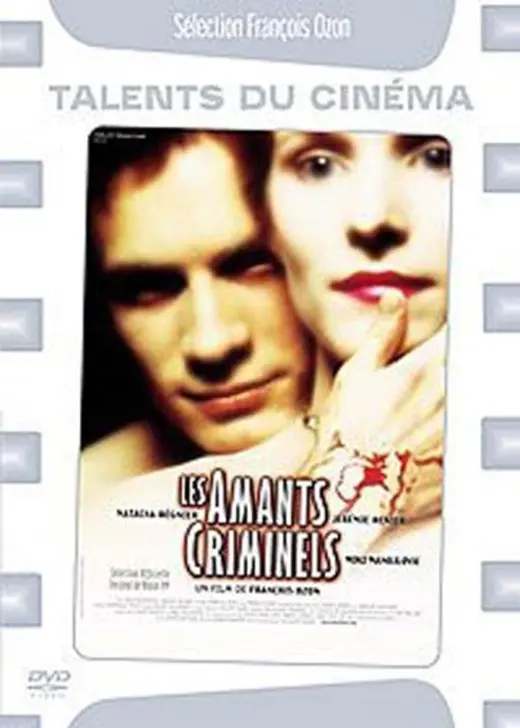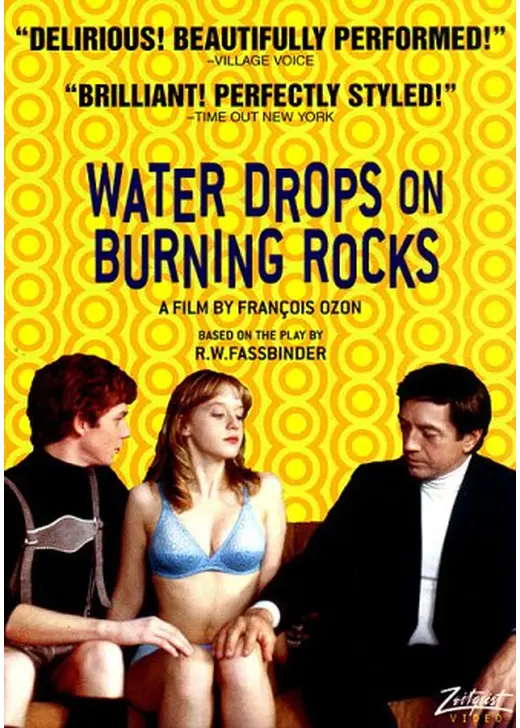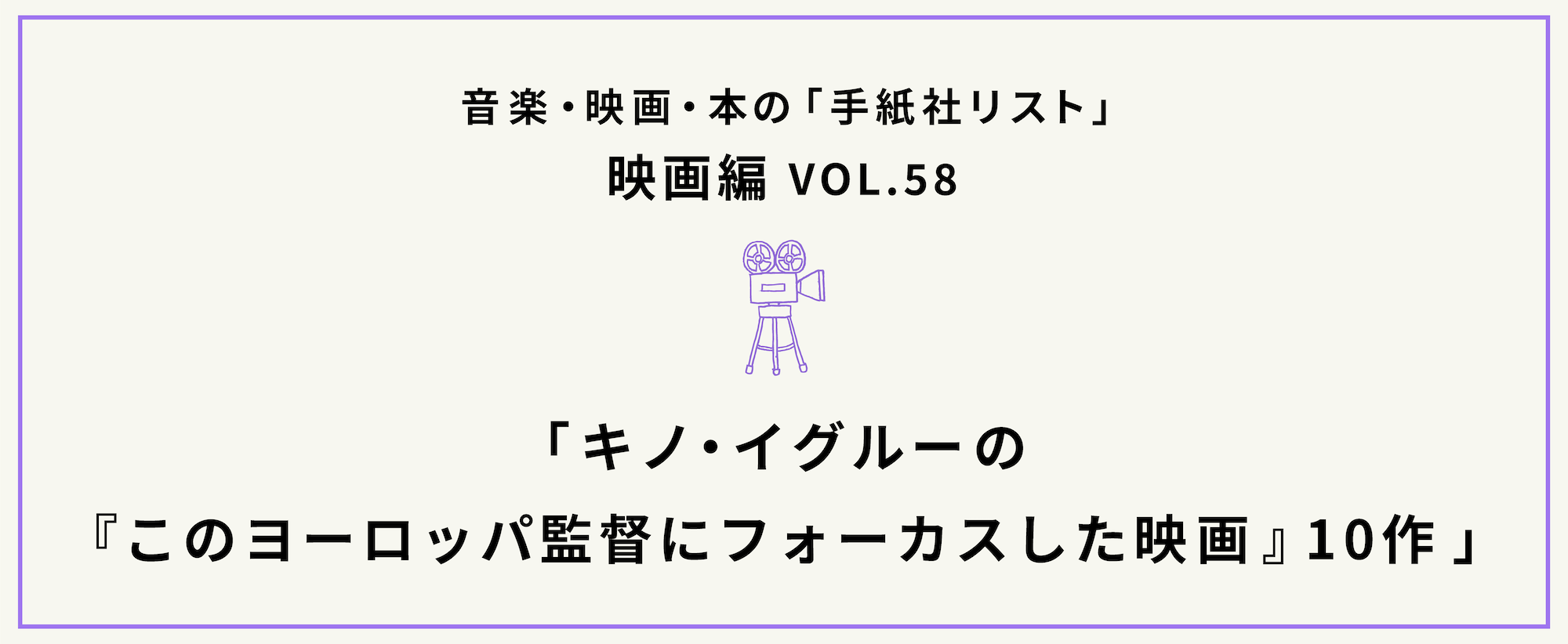
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。今回は「このヨーロッパ監督にフォーカスした映画」を切り口に、それぞれが一人の監督をピックアップし、おすすめの映画を5本ずつ紹介します。その“観るべき10本”を選ぶのは、マニアじゃなくても「映画ってなんて素晴らしいんだ!」な世界に導いてくれるキノ・イグルーの有坂塁さん(以下・有坂)と渡辺順也さん(以下・渡辺)。今月もお互い何を選んだか内緒にしたまま、5本ずつ交互に発表しました!
──
お時間の許す方は、ぜひ、このYouTubeから今回の10選を発表したキノ・イグルーのライブ「ニューシネマワンダーランド」をご視聴ください! このページは本編の内容から書き起こしています。
──
−−−乾杯のあと、恒例のジャンケンで先攻・後攻が決定。今月は渡辺さんが勝利し、先攻を選択。それでは、クラフトビールを片手に、大好きな映画について語り合う、幸せな1時間のスタートです。
有坂:今月のテーマは、「このヨーロッパ監督にフォーカスした映画」ということで、それぞれ推しのヨーロッパ監督を一人ずつピックアップして、これからおすすめを5本ずつ紹介していこうと思います。ちなみに、ピックアップした監督、順也は?
渡辺:僕は、クリストファー・ノーランです。イギリス。
有坂:ノーランはね、僕、最初、順也がノーランってた言ったとき、「いやいや、それアメリカ人だから」って思ったんだけど、実はね。
渡辺:そうイギリス人なんですよ。お母さんがアメリカ人っていうのがあるところではあるんですけど。
有坂:というノーランと、僕はフランスのフランソワ・オゾンという監督をピックアップしました。オゾンとノーランで、これから紹介したいと思います。
渡辺:じゃあ早速、僕の1本目からいきたいと思います。クリストファー・ノーランはご存知な方も多いとは思いますけど、今、現代の現役で巨匠感ある監督の、かなり代表格じゃないかなと。リアル主義で完璧主義というこの監督の1本目、まずは2000年の作品です。
──
渡辺セレクト1.『メメント』
監督/クリストファー・ノーラン,2000年,アメリカ,113分
有坂:うんうん、はい。
渡辺:この『メメント』、特徴的なのは、時間軸をめちゃくちゃいじっています。どんどん過去に遡っていく、そういう時間軸の編集というのが、特徴の作品になります。主人公は、妻が殺されてその犯人を追うというお話なんですけど、記憶障害のため、10分間しか記憶がもたないので、少し前のことを忘れてしまうので、それを自分の体にタトゥーを入れたりとかして、それで過去の何があったのかっていうのを遡っていくという、そういうサスペンスになるんですけど。もう本当にこれ低予算なんだけど、アイデア勝負で、時間軸を編集で見事にいじって見せ切るサスペンスというところなので、かなり初期から予算がなくても、本当にアイデアと、いい編集力とか、監督力があれば面白い作品つくれるんだというのを、見せ切ってくれた作品だなと思います。というので、まずノーラン1本目は『メメント』です。
有坂:これから順也がノーランのいろんな作品を紹介するから、具体的なタイトルは言えませんが、時間をいじることができるっていうのは、本当に映画の持っている特徴というか、映画の武器の一つだよね。現実世界では、時間は前にしか進まない中、映画の中では時間軸を解体するとか、逆再生するとか、時間をいじることでそれを表現として使える。それはやっぱり絵画とか写真でもできないことだから、そういう映画ならではの特徴にね、自覚的な監督だよね。
渡辺:かなり初期からそれをやっていたという感じですね。
有坂:これ、またガイ・ピアースだよね。主演。もうガッチリ体も絞って、タトゥーを体に刻み込んで、ビジュアル的にも面白い。ちなみに、あれ、順也はその時系列で紹介していく?
渡辺:時系列で。
有坂:僕も同じように時系列で紹介していこうと思います。では、フランソワ・オゾンの1作目は、96年の短編映画です。
有坂セレクト1.『サマードレス』
監督/フランソワ・オゾン,1996年,フランス,15分
渡辺:うーん!
有坂:まずフランソワ・オゾンという人なんですけども、彼は1967年生まれのパリジャンです。現役バリバリの監督で、最近だと去年公開された、『秋が来るとき』、その前は『私がやりました』、その前が『苦い涙』というように、1年に1本のペースで、いまだに新作が公開されている今や巨匠といってもいい、一人かなと思います。
そんなフランソワ・オゾンは、日本で最初に公開されたのが1998年。『ホームドラマ』という長編映画で初めて日本で紹介されて、そのタイミングで過去につくった短編ということで、この『サマードレス』も紹介されました。僕は、その98年のタイミングで、渋谷のユーロスペースでこれを観たんですけど、まあ、衝撃的でした。
フランソワ・オゾンっていうのは、パリ第一大学の映画コースを出て、その後、国立の映画学校フェミスっていう、もう言ってみたら超エリートなんですよ。アルノー・デプレシャンという人とか、90年代のフランス映画好きなら、誰もが知っている監督と同じようなキャリアを歩んでいるエリート中のエリート。
ただ、彼がつくる映画というのは、他の人のインテリとはちょっと毛色が違って、何が違うかというと、オゾンというのは、自分のセクシャルアイデンティティを、ゲイであるということを早々に公表している人なんですね。出てくる登場人物たちも、基本ゲイであるということが初期作は定番でした。
この『サマードレス』という短編は、定番設定である男のゲイのカップルが主人公の物語です。ただ、他の作品の暗いトーンと違って、これだけは底抜けに明るさもあるということで、特別な一本なんですけども、これはバカンスに行った男子カップルが、一人は言ってみたらチャラいタイプの男で、そのチャラいタイプの男に、嫌気がさしたもう一人の男の子が、そのバカンス先の別荘を出て行った先で、浜辺である女の人と出会うんです。
女の人と出会って、彼女が着ていたカラフルなワンピース、ドレスを見て心惹かれるものがあって、女性といい仲になる。っていうところから物語が進んでくるんですけど、言ってみても15分の短編なので、物語の展開っていうのは、ある程度想像できると思うんですけども。その15分の描き方、いわゆる三角関係と言ってもいいような3人の描き方が、例えば、そのダンスの動きで男の子の特徴を見せるとか、女性もののワンピースを男の子があることがきっかけで、着なきゃいけない。着たワンピースを、着ているその姿であったりとか15分の中でキャラクターをしっかり見せることができる。さらに音楽もいい。で、夏だし、自転車で走って浜辺を走っている疾走感とか、絵的にもすごく見ごたえもあるということで。本当に15分でこれだけの表現力があるっていうのは、ある意味、才能の塊みたいなものが『サマードレス』だったかなと思います。
当時、フランソワ・オゾンっていうのは“短編王”っていう異名があって、数々つくった短編が、軒並みいろんな海外の映画祭で賞を受賞するということで、あいつは一体誰なんだってことで、長編をつくる前から短編王という異名で話題を集めていた、そんな監督の短編の中でも傑作中の傑作が『サマードレス』です。
渡辺:なるほどね。オゾンは本当、初期は特にセクシャリティが前面に出ていた感じがあるよねね。
有坂:清々しいほどのね。そのセクシャルなシーンとか包み隠さず、堂々と。
渡辺:ちゃんと美しい男が出てくるみたいな。
有坂:そうだね。
渡辺:なるほどね。はい続けて、僕のノーラン2本目にいきたいと思います。僕の2本目は2008年の作品で、『ダークナイト』です。
渡辺セレクト2.『ダークナイト』
監督/クリストファー・ノーラン,2008年,アメリカ,152分
有坂:うんうん、そうね。
渡辺:これは、あのバットマンのシリーズになります。バットマンって、DCコミックのアメコミの代表作。本当にいろんな監督がバットマンを描いてきてるんですけど、この『ダークナイト』で、一気に異色になって、もうこれでノーランの知名度が、名声が一気に上がったという感じだと思います。今までアメコミって、わりとポップなイメージとかもあったんですけど、これは一気に本当にダークに、シリアスに、重厚に撮った作品になります。これの特徴が、特にジョーカーですね。ヒース・レジャー演じるジョーカーが、もう本当に狂気を帯びた悪役として、バットマンのジョーカーって、わりとなんかこうチャラいというか、そういうキャラクターが今まで多かったんですけど、これのね、ヒース・レジャーのもうちょっと狂気を帯びたようなジョーカーっていうのが本当にすごくて。これ撮影のエピソードで、ヒース・レジャーがすごすぎて周りの人がセリフ忘れちゃったっていうエピソードがあるほど、このときのジョーカーはすごかったというふうになります。ヒース・レジャーは、その後、亡くなってしまうんですけど、亡くなった後にアカデミー賞の助演男優賞を受賞するっていうですね。亡くなったのに獲ったっていう、そんなエピソードも残っています。ノーランのすごいところが、この人はCGとか使うのを嫌うんですよね。すごく本物主義で、実写主義なので、すごい巨大トレーラーがひっくり返るシーンとかがあるんですけど、そういうのを本当にそのままCGを使わずに爆破して、巨大トレーラーが本当にそのままひっくり返って爆発するみたいな。そういうのを力技で撮っているところが、このノーランの作家性の特徴でもあります。なので、こういうアメコミ撮っているのにCGを使わないとか、本当に役者の力とか、あのなんですかね、そういうCGになることでちょっとした違和感とか、そういうのが許せないらしくてですね。全部本物でやるっていう、そういう完璧主義者っていう作家性を表したのも、この『ダークナイト』じゃないかなと思います。
有坂:これはさ、特にそのバットマンシリーズっていう切り口でいうとさ、その前がティム・バートンだったじゃん。『バットマン』『バットマン リターンズ』で、ティム・バートンがマイケル・キートンをバットマンにして、ジョーカーをジャック・ニコルソン。それはティム・バートンらしいポップさもある、けどちょっと影もあるというキャラクターで、本当にもう描き切ったからこそ、その反動で、明るさゼロ。とにかく暗いアメコミものみたいな。
渡辺:ねぇ。
有坂:新基軸だったよね。
渡辺:本当に!
有坂:その手があったかと。
渡辺:ノーランをよく抜擢したなっていうね。
有坂:それも正直さ、ノーランがその『ダークナイト』をやるっていうニュースを見たときさ、なんか覚えていたんだけど、すごいショックだった。
渡辺:あ、そう。
有坂:そう。なんかもう、あのころの安易な自分。「ノーラン魂を売ったな」と。
渡辺:なるほど、「メジャーに行ったな」みたいな。
有坂:それを翻るぐらいの衝撃を受けたのが、この『ダークナイト』。だから余計に、この人、信頼できると思ってしまったのを、個人的にはすごい印象に残っている。
渡辺:これは本当に衝撃作なんで、ちょっと観てない人はね。
有坂:アメコミ苦手とかっていう人ほど、ぜひ観てほしい。
渡辺:本当にヒース・レジャーの演技が凄まじいので。
有坂:はい、じゃあ、そんな大作の後にふさわしくない、フランソワ・オゾンの2作目は、1999年の作品です。
有坂セレクト2.『クリミナル・ラヴァーズ』
監督/フランソワ・オゾン,1999年,フランス、日本,95分
渡辺:うーん!
有坂:これは、フランソワ・オゾンの長編第2作。『ホームドラマ』というタイトルのとおり、ある家族をブラックコメディとして描いたデビュー作があって、次、すごく毒々しいブラックユーモア満載なデビュー作の後、「次は何つくる? 」と思ったら、これは高校生カップルを主演にした作品でした。この高校生カップルが主演なんですけど、その女性のほうがいわゆるファム・ファタールというか、男を惑わすタイプ。“あざと女子”、あざとい系の女性で、男性にある方法の殺人をそそのかすんです。その女の子が大好きな男の子は、言われるがままに殺人をしてしまうという、同級生を殺害してしまう。で、その死体を埋めるために森に入った2人。でも、そこで森の奥に住む謎の巨大な男に捕らえられて……。これは、高校生っていう現代の設定ではあるんですけど、この映画のベースっていうのはグリム童話の『ヘンゼルとグレーテル』。それを現代版として置き換えた作品になっているんですけど、とにかくすごく不穏な状態がずっと続く。どんどんどんどん、なんだろうな、言葉にすればするほど観てもらえなくなっちゃうようなワードしか思いつかないんだけど(笑)、ある意味、フランソワ・オゾンの中にある黒い部分を現代映画として出しすぎると、ちょっとあまりにも生々しいから、『ヘンゼルとグレーテル』っていうものを下敷きにして、あくまでちょっとブラックなおとぎ話として描いている。ある意味フランソワ・オゾンは、自分の中のもやもやした黒い部分をこの映画で出し切ったんじゃないかなというぐらい、清々しいまでに残酷であり、エロティックであり、でも、こういう思春期特有の闇ってあるよねっていう、としか言いようがない作品です。僕はもう、この『クリミナル・ラヴァーズ』を観て、本当に一生ついていこうと思うくらい、個人的には胸をつかれました。特に、個人的な話なんですけど、僕は94年に映画に目覚めて、その5年後、この5年間で観た映画っていうのはハリウッド映画を中心に、映画はハリウッドだけではなくて、ヨーロッパとか日本の昭和の映画とか、いろいろあるという中で、各時代に名作がある。羨ましいな、あの時代に生まれたかったなって思う中で、ついに同時代の監督を見つけたんですよ。で、このすごく不謹慎な内容ではあるんだけど、それをどうしても作品にしたいという思いを、何かあの時代なりに感じることもできたし、それを恐れずに作品にできたこの人っていうのは、すごく信頼ができると思った、きっかけの一本です。なので、ただね、これ後々インタビュー読んだら、フランソワ・オゾンはキャリアの中での唯一の失敗作って言っている。「ズコ!」ってなって、それを読んで。でも、この感じって前もあったなって。それが、ウディ・アレン。僕、ウディ・アレンが大好きなんですけど、ウディ・アレンもキャリアの中での失敗作は、『マンハッタン』っていっている。だから、つくった本人の失敗作を僕は好きっていう傾向が強くて、でも、それはどっちも通じるものもあるから。なんかこう自分が崇めている人が失敗作って言ったからって、自分の評価を変える必要はない。今、観ても心打たれるものがある。相当やばいファンタジー映画です。
渡辺:なるほどね。オゾンも今やベテランだから、いろんなタイプの作品を撮っているけど、この初期は、すごいさらけ出してくる感じのね。痛々しいまでに、自分の闇とかを全部晒す作家性みたいな、そんなイメージだったからね。
有坂:そういう監督っているじゃない。一回、自分の中のそういう黒いものを出さないと、アーティストとしてじゃなくて、人間として、一人間として生きていけないタイプの監督っていて、それはもうやっぱり現実世界に居場所がないタイプの人。オゾンもそれに近いものを、『クリミナル・ラヴァーズ』を観てすごく感じました。
渡辺:初期作はそうだったよね。やべぇやつ出てきたなっていう(笑)。それがどんどん、ベテランになっていくと。なるほど。続けて、僕のノーラン3本目は、2014年の作品です。
渡辺セレクト3.『インターステラー』
監督/クリストファー・ノーラン,2014年,アメリカ、イギリス、カナダ,169分
有坂:うんうんうん。
渡辺:これは、ノーランを代表する名作だと思います。話としては、物理学者の主人公が、地球が危機に陥っているので、宇宙に旅立って解決策を持ち帰ろうとするというお話になっています。この辺からノーランが、物理学とか、科学とか、そっちの方にものすごい傾倒していく作品になっています。これも相対性理論とかを使って、ざっくり言うと、浦島太郎みたいな、宇宙空間をずっと行って帰ってくると、時間の経過がずっと地球にいるのと違うっていうですね。それをやっている作品になります。なので、宇宙に旅立った物理学者は大人で、娘がすごい小さい、幼い子どもだったんですけど、ようやく最後帰ってくるっていうときには、もう娘は自分と同じぐらいの大人になっているみたいな、そういう話だったりするんですけど。それをちゃんと相対性理論とかを使って、科学的にちゃんと科学者を監修に入れて、「物理学として理論上そういうことがある」ということを、SF映画として描いたという作品になっています。これ本当に、SF映画としてもすごく面白いし、父娘ものとしてもすごく面白い。ノーランを代表する作品にもなっているという感じです。これもノーランの本物志向とか、実写志向のエピソードでいうと、ものすごいトウモロコシ畑が出てくるんですね。500エーカーっていうとんでもないスペースのトウモロコシ畑が、CGでもわかんないのに、全部本当にトウモロコシを植えて実写で撮り切ったと。さらに、撮影後にトウモロコシ全部収穫して、販売して制作資金に当てたっていう(笑)、そんなエピソードまであるっていうですね。本当にどこまで本物志向なんだっていうことを表すエピソードもあるという、そんな『インターステラー』でした。
有坂:その映像、やっぱり覚えているもんね。だから、そこまで深くすり込まれるってことは、本物がゆえ。
渡辺:そう! あと、思い出したのが、エピソードでアン・ハサウェイも出ているんですけど、アン・ハサウェイが氷の、氷山の水に入っていくシーンがあるんですけど、そこで衣装が破れちゃったかなんかで、めちゃくちゃ冷たい氷水が入ってきて、低体温症にアン・ハサウェイがなったのに演技を続けたっていう、そんなアン・ハサウェイの女優魂みたいな。っていうのと同時に、ノーランの撮影が過酷っていう、本物にこだわるがゆえにね、氷水に本当に入るみたいな。そういう撮影をやる人なので。っていうエピソードもあったりします。
有坂:今の時代、ギリギリの撮影スタイル。
渡辺:現役でまだ撮っていますからね。
有坂:今回、1本ずつ紹介すればするほど、ノーランとスケール感の違いが。
渡辺:スケールは違うよね。
有坂:相対性理論というワードが出てくる。次、紹介する映画とか、すごいコンパクトな、小規模な名作にいきたいと思います。2000年の作品です。
有坂セレクト3.『焼け石に水』
監督/フランソワ・オゾン,2000年,フランス,90分
渡辺:なるほど。
有坂:これは、1970年代のドイツが舞台の作品なんですけど、原作があって、これは映画監督でもあるドイツのライナー・ヴェルナー・ファスビンダーという、彼自身もゲイであるってことを公表しているんですけど。オゾンが敬愛している監督がつくった戯曲が原作です。その未発表の戯曲を、オゾンが映画化したのが、この『焼け石に水』という作品です。
これはもうシンプルな映画で、4幕からなる室内劇。主人公は4人の男女。男2人、女2人の室内劇で、4章に分かれているという作品です。この4人の男女、中年男と恋人がいて、そこにまた2人が絡んできて、男と女という関係を超えて、男同士に恋心が芽生えたりみたいな形の、本当に言葉で説明しても面白さは何も伝わらないタイプの戯曲がベースの映画となっています。この映画は、フランソワ・オゾンの、さっき『クリミナル・ラヴァーズ』を紹介したときに、彼の中にある黒い部分を出し切ったと言いましたけども、やっぱり出し切ったんじゃないかなと思えたのは、この『焼け石に水』の中にも、もちろんダークな要素というのは多分に含まれてはいるんですね。ただ描き方があくまでもポップ。ちょっとミュージカル調なシーンもある、ということで、なんかね『クリミナル・ラヴァーズ』のときほどの切羽詰まっている感じがない。ちょっと余裕がある。映画としてどう面白く見せるかっていうところに、前作との違いが見て取れるかなと思います。そこにこそ、フランソワ・オゾンという監督のセンスが爆発しているのが、この『焼け石に水』かなと思います。この彼のセンスというのは、一つは70年代のドイツの設定なんですけど、この映画に出てくるインテリアは、基本的にはミッドセンチュリーのソファーとか、家具がたくさん出てきます。見た目的にめちゃくちゃオシャレ。さらに、そこで使われている音楽も、フランソワーズ・アルディとか、60年代、70年代に活躍したポップスターの曲が使われている。それを2000年の感覚で描く。わりと、一番最初に紹介した『サマードレス』もそうなんですけど、この映画にもすっごく印象に残るダンスシーンがある。予告編でも使われているので、ぜひ観てほしいなと思うんですけど、主人公の4人が、ある曲に乗せて、もう下手うま、下手下手なダンス、本当に素人が踊っているという設定のダンスを観せてくれるんですけど、そういうものを物語の中に入れることで、そのダンスシーンが物語にどう影響を与えるかというところで、すごくポップに見える表現だけど監督としてはチャレンジしているな、というところもこの映画の魅力の一つだなと思います。アパートの一室が舞台で、4人の男女の話なんですけど、やっぱり一つ屋根の下に人間が集まるといろんな葛藤だったりとか、いろんなトラブルが起こる。そういう誰もが共感できるようなところも、きちんと嘘偽りなく描いているので、何か人間関係にモヤモヤしている人にも、ぜひ観てほしいなと思う一作です。僕、個人的にリアルタイムでユーロスペースで観たときに、毎回映画のパンフレットを買うんですけど、これは、今の映画ファン。映画パンフレットファンにはぜひ観てほしい。この『焼け石に水』のパンフレットっていうのは、今をときめく大島依提亜さんの初の洋画作品なんです。この前に、『avec mon mari』っていう日本映画のパンフレットを手掛けて、初の洋画がこの『焼け石に水』。横長のパンフレットだったんですけど、
渡辺:持ってきてないの?
有坂:持ってきてないんだよー。そう、持ってくればよかった。パンフレットに、この映画のちょっと今このビジュアルは違うんですけど、ポスターとかでも使われている、すごく素敵なデザインのなんていうんだろう、ブランドロゴみたいな、説明が難しい。それを模したスカーフがパンフレットに入っていた。で、今でこそ大島依提亜さん知っていて、そういうギミックが好きな人ってわかっていれば、それもあるよねってわかるんだけど、当時のパンフレットって、そんなものがない中で、見た目のデザインもおしゃれなのに、変な厚みがあるなって思ったから、間からスカーフが出てくるっていう、それも含めてなかなかの衝撃でした。依提亜さんも、この映画には思い入れが強いんじゃないかなって思うので、パンフレット好きの方もぜひ!
渡辺:だいぶキャリア初期ってことだよね? 依提亜さんにしてもね。
有坂:2000年だからね。26年前。
渡辺:なるほど。これはでも本当、ダンスシーンがもうね。印象的だよね。あのなんとも言えないダンスシーン。まあ、でもあれだけ観ても、ちょっとなんかね、魅力を感じてしまう。
有坂:そう、ゴダールの『はなればなれに』をイメージしてやっているんだろうなと。
渡辺:そうなんだ。
有坂:横並びで。あっちは3人だったけど、こっちは4人で。人が踊っている姿って、なんであんなに魅力的なんだろうね。物語を超えた魅力があります。
渡辺:はいじゃあ、もう4作目ですね。ノーランの4作目にいきたいと思います。2020年の作品です。
渡辺セレクト4.『TENET テネット』
監督/クリストファー・ノーラン,2020年,アメリカ、イギリス,150分
有坂:うん、ふふふ。
渡辺:ノーラン、『インターステラー』の辺から、物理学とか科学とか、そっちのほうに傾倒していくんですけど、この『テネット』もかなりすごい作品になっていて、これも物理学の延長で、エントロピーっていう物理学上のエネルギーがあるんですけど、それを減少させていくっていうことは、イコール、時間を逆行するっていうのが、物理学上はそういった理論になるんですけど。現実で、我々が普段生きてる中で時間が逆行するってことはないので、ピンとはこないんですけど、数式とか物理学上はそういうことがあり得るっていう計算式があるんですけど。それをSF映画として、実写で表現したっていうのが、この『TENET テネット』になります。この大枠の話としては、スパイアクションです。なので、スパイアクションとしても普通に面白いんですけど、かなり高度な物理学の装置があるっていう設定になっているので、時間が過去から未来へっていうのが、普通に順行するっていうんですけど、そういう世界と逆に未来から過去へ逆行する、2つの時間軸が存在するっていうですね。これがもうノーランじゃないと思いつかないというか、とんでも設定というかですね。その中で順行する人と、逆行する人がアクションするみたいな(笑)。もうよくわからない。車を運転していると、反対側に急に転がり出す車がいたりとか、もうついていけないというか、頭が混乱しちゃうんですよね。普通に順行していると思ったら、逆行の世界に今度入り込んで、なので、さっきまで時間軸が過去から未来へ進んでいたのに、未来から過去の方へその主人公が入ると、さっきまでいたのが、また逆に見えるみたいな。そういう、本当に頭が混乱するような世界観でスパイアクションをやっていくっていうですね。本当に、これも実写主義のノーランのまたエピソードで面白いのが、順行している主人公の目線でいうと、逆行している人たちっていうのは逆に進んでいくんですね。それを撮影としてはガチで、役者たちが後ろ向きに歩いていたっていう(笑)。そういう力技というかですね。
有坂:そこが面白いんだよね。
渡辺:CGとかで逆回転させて、そこだけ再生していたとかじゃなくて、素直に後ろ向きに歩いていたみたいな(笑)。
有坂:なんかちょっと気持ち悪いんだよね。
渡辺:うん。っていうのを、本当にガチでやっていたっていうですね。それがすごいですね。これも大きいボーイングの旅客機があるんですけど、これを大爆破させるシーンがあって、IMAXで撮っているんですけど、これも本物のボーイングを大爆破させてっていう。もう飛行機のジャンボジェットを大爆破させるから、失敗できないシーン。とんでもない予算をかけて大爆発させるからね、「間違えましたー」とか、絶対許されない。そういうのを分かっていて観るとさらに面白い。あの大爆破、そんな2テイク、3テイク絶対できないので、これをちゃんと1テイクで撮るために、スタッフのどれだけの緊張感のもとやっているんだろうなみたいな。そういうところとかも感じさせる、面白さがあるっていう。あと、この主役がですね、デンゼル・ワシントンの息子っていうのも、特徴の作品になります。これね、本当になんかね、順行と逆行が分かりそうで分からないみたいなところがあるので、最初観てね、ちょっと分かんないなと思って、いっぱいなんか考察サイトとかそういうのをすっごいいっぱい見まくって、完全に理論武装できたと思って、2回目観に行って、「わかんねえって」っていうね(笑)。
有坂:(笑)
渡辺:もうちょっとね、ノーランの天才すぎる世界。これ分かる人いるのかなっていうぐらい、本当にね、いろんな人がこうじゃないかっていう考察とかをすごいしているんだけど、みんな本当に分かってんのかなって思うぐらい。
有坂:疑うぐらい。でも、やっぱりすごいのは、分かんなくても面白い。
渡辺:そうなのよ!
有坂:そこがやっぱ大事。
渡辺:それ! 本当に面白いんだよ。
有坂:映画の魅力の一つとして、そこもあったはずじゃない。分かんない映画は面白くないとか、認めないみたいな風潮がすごい強いけど、分かんないけど面白いってところに、いろんな可能性とか、未来があるわけで、それをこの規模感でつくり続けているノーランはね。
渡辺:本当にすごいですよ。
有坂:……はい、僕の4本目は2000年、さっきの『焼け石に水』と同じ2000年の作品です。
有坂セレクト4.『まぼろし』
監督/フランソワ・オゾン,2001年,フランス,95分
渡辺:ああー。
有坂:真逆でしょ?
渡辺:真逆ですね(笑)。
有坂:これは、散々挑発的な内容の映画をつくって、既成の価値観を揺さぶり続けたフランソワ・オゾン。ついに大人になりました。
渡辺:なりましたか(笑)。
有坂:としか本当に言いようのない、どっしりとした人間の生きる本質を見つめた名作中の名作となっています。映画自体はすごくシンプルで、主人公は50代の夫婦です。マリーとジャン。このマリーっていうのは、シャーロット・ランプリング。名女優シャーロット・ランプリングが演じています。いろんな酸いも甘いも経験した、25年の結婚生活がある夫婦が、夏にバカンスに行きます。その南仏の別荘でゆっくりして「ちょっと海でも行こうか」と言った2人。そのシャーロット・ランプリング演じるマリーは、ちょっと私は本読んでるから、海行ってきなということで、砂浜に残って本を読んでいたら、うとうと居眠りをしてしまいます。ふっと目を覚ましたら、いるはずの旦那さんがいない。どっかに行ったのかなと思って待っていても、帰ってこない。きっとどっか行っただけだから、先に帰っておこうと思って別荘に戻っても帰ってこない。いよいよ行方不明になったんじゃないかということで、物語が動き始めます。この映画の内容って、シンプルに言うとそれだけです。帰ってこない夫。それを待っている妻、っていう時間がずっと続いていきます。この映画の、要は自分が愛する人を失ってしまったと思いたいんだけど、失ったかどうかもわからない。いわゆる宙ぶらりんの状態に置かれてる人が、主人公なんですね。やっぱり大切な人を失うって、人間にとっての一番の恐怖じゃない? だけど、失った可能性が高いけど、その答えがわからないという状態が一番つらいんだな、ということを教えてくれたのが、この『まぼろし』でした。だから、ある意味、本当に希望がなくなってくると、いっそのこと亡くなってしまったことを受け入れた方が楽なんじゃないかとさえ思う。それぐらい深い話になってくるんですね。その喪失感を得ることもできない女性を、シャーロット・ランプリングが絶妙な。
渡辺:そうね。
有坂:あまり、セリフで語ることもできないような設定の中で、表情とか仕草で自分の悲しみを表現します。本当にこの人はこんなに素晴らしい女優だったんだけども、彼女は50代かな。54歳とかでこの映画に出ていて、20代でスターに駆け上がって、1回ちょっとね、キャリアが停滞して、『まぼろし』からまたキャリアを復活させていくことになるんですけども、この年代の女性のにしか表現のできないものを、もうギュギュッと詰め込んだ、本当にもう大人の女性とはこれっていう魅力に詰まった一作が、この『まぼろし』となってます。結局、今ちょっと言いましたけど、なんでいなくなったのか。実際海で溺れてしまったのか、それとも失踪してしまったのか、もしくは自殺してしまったのか、っていういろんなことがもやもや頭の中を駆け巡る。けど、長年連れ添った夫だから、夫に限ってこれはないよねって最初は思っていたけど、思っていた時間も長くなってくると、それさえも疑ってくる。やっぱり現実では絶対に起こってほしくない。それを、この映画を通して、本当に自分ごとのように感じられるっていう意味で、もっともっと多くの人にというか、次の世代にどんどん伝わってほしいなと思う映画ということで紹介しました。
渡辺:俺、でも一番好きだな、たぶん。オゾンで。
有坂:これ、オゾンが33歳のときに撮っている。もうさ70の人が撮る映画だよね。人生、何周もしたかのような。でも、それを彼は33歳という年齢で撮っていて、さらに最初に話しましたけど、彼は自分がゲイであるっていうアイデンティティで、ずっとつくり続けてきた人が、ついにそこを飛び出てつくった映画なんですよ。初めての映画。それが、こんなすごく深い死生観みたいなものを見つめる深い映画っていうところに、彼の内面世界を見せられたような気がして。
渡辺:この辺から、大女優を使うようになっていった。
有坂:そうなんだよね。
渡辺:今まで若い人を使ってきたけど、ここからけっこう往年の女優と仕事をするようになっていくっていう。
有坂:そういう女優さんからも、ぜひ出たいってオファーが来るぐらいの監督になっていく。そのきっかけにもなった一作かなと思います。
渡辺:なるほど。
有坂:これシネマライズだったよね。
渡辺:そうかもしれない。懐かしいね。はい、じゃあ、5本目ですね。僕のノーランの5本目、いきたいと思います。2023年の作品です。
渡辺セレクト5.『オッペンハイマー』
監督/クリストファー・ノーラン,2023年,アメリカ、イギリス,180分
有坂:うんうん。
渡辺:これは、本当にノーランが物理学とか科学とかっていうところに傾倒していった、理系でつくっていった作品づくりから、一気に今度は科学者を主人公にして、オッペンハイマーって実在する科学者の原爆をつくった人ですね。核開発をした科学者のオッペンハイマーの半生を描いた作品なんですけど。なので、一気にこの辺から科学とか物理の話じゃなくて、科学者の、科学者としたら、すごい成功を収めて実験を成功させた人なんですけど、それによってものすごい人の命を奪う兵器をつくってしまったという。そういう功罪の矛盾というかですね、科学者としては成功してるんだけど、人類としてはすごい脅威をつくってしまったっていう。そういうなんか、功績と罪みたいな、そういう矛盾に苛まれる科学者の葛藤みたいなものを描いた作品なので、今まで本当にSFで物理科学みたいなことをやってきたのに、今度は科学者の苦悩を描くというドラマをここでなったので、本当に一気に理系から文系に転換してきたっていう。また、ここでノーラン、次のステージに行ったなみたいなところの作品になります。これはつい最近の作品なので、いろいろ話題になったのが覚えていると思うんですけど、結局原爆をつくった原爆の父の話なので、ちょうど日本にとってはすごいデリケートな題材でもあるんですけど、アメリカで『バービー』っていう映画とちょうど同時期に、2つ大ヒットして、「バーベンハイマー」っていうファンアートなんですけど、この2つの作品をコラージュしてSNSで盛り上がるみたいな現象が起こったんですけど。たぶんアメリカ人の一映画ファンからしたら、別に原爆、そんなデリケートな話でもないぐらいな感じで、バービーのポップなやつと原爆のきのこ雲みたいなものを掛け合わせたファンアートをつくって、それがすごいミームとして盛り上がってたんですけど、ワーナーの公式サイトでいいねしちゃって、それがもう大炎上して、特に日本からしたら、アメリカのメジャースタジオが、そんな原爆をバービーとかの作品と揶揄したようなやつに、いいねしてんじゃねえよっていう。そういうので大問題になって、日本公開しないんじゃないかみたいな、っていうふうなところまでいった作品なんですよね。これはもうユニバーサルというアメリカのメジャースタジオが配給しているんですけど、これもエピソードがあって、それまでノーランってずっとワーナーっていうメジャースタジオで撮ってきたんですけど、『TENET テネット』のときにちょうどコロナ禍だったんですね。コロナ禍でワーナーとしては劇場公開せず、配信でやろうっていう決断をしたんですけど、ノーランが激怒して、ふざけんなと、俺の作品は映画館で観るやつなんだっていうので、ワーナーと大喧嘩してワーナーの反対を押し切って劇場公開したという経緯があって、そこでワーナーと大喧嘩して、ワーナーとは手を切って、こっからユニバーサルになったっていうやつなんですけど。ユニバーサルでもまたそういう問題が起こり、日本では公開が危ぶまれてたんですけど、なんとビターズ・エンドっていうですね、日本のミニシアターのインディーズの代表格みたいな配給会社が、なんとこの『オペンハイマー』を配給すると。リスクを承知で自分たちがやりますというので引き受けて、それで日本公開がかなったと。けっきょく日本でも興行としては大成功して、この作品がアカデミー賞で、なんと最多の7部門で受賞するということになりました。ノーランは、ずっと「無冠の帝王」と言われていて、これだけすごい監督なのに、ショーレースとは無縁だったんですけど、これで一気に監督賞も獲って、作品賞も獲って、主演男優賞も獲って、一気にですね、オスカー監督に名実ともになったという作品になっています。これもノーランの本物志向エピソードでいうと、実験で核爆発をするシーンがあるんですけど、それもCGを一切使わず、ちゃんと火薬とマグネシウムとか、ガソリンとかを使って爆破させて、その光をちゃんと映像に収めて、爆破シーンとしたというエピソードがあります。というね、もう本当に最後まで本物志向でやっているっていう。
有坂:最後までじゃない、まだ生きているから(笑)。
渡辺:そう、次の作品が発表されていて、それが『オデュッセイア』という作品で、ギリシャ神話のオデュッセイアをノーランが映画化するっていう。本当に物理、科学できて、科学者の話をやってきたら、一気に今度神話にいったっていう。どうなんだっていうね。もう科学とかそういうところじゃない、今度、たぶん精神性とか内面の方に入っていっているんだなっていう。オデュッセイアっていうのは、ある武将の戦争を行ってから帰還するまでの長い苦悩の10年みたいなところの話なので、本当にこの内面の精神性を描いていくんじゃないかなっていう。ノーラン、次、どこへ行くんだろうっていうのが楽しみな、本当に現代の巨匠という。
有坂:そうだね。
渡辺:どうなるんでしょうか。
有坂:『オッペンハイマー』のポスタービジュアル。僕は、あんまり映画を観る前って、ここに書いてあるキャッチコピーとか、このポスターに写ってる人の表情とかを読み取らないようにしている。本編をまず観てから、ちゃんと観ようと思って、あんまり知りたくないので。このイメージ、パッと観たときのイメージが、ずっと自分の中で、主人公がハリソン・フォードにしか見えない。『インディ・ジョーンズ』の。これちょっとイメージ的にどうなんだろうなって。
渡辺:なるほど(笑)。
有坂:どうでもいいですけど(笑)。
渡辺:じゃあ、ラスト。
有坂:最後の作品を。一見、真逆のノーランとフランソワ・オゾンでしたが、ここだけは唯一噛み合うんじゃないかという接点がある、というのを最後に紹介します。2004年の映画です。
有坂セレクト5.『ふたりの5つの分かれ路』
監督/フランソワ・オゾン,2004年,フランス,90分
渡辺:ああ!
有坂:これは、ある一組のカップルを描いた、ちょっと異色のラブストーリーです。このノーランとオゾンで唯一、ここが噛み合うんじゃないかなと僕が言ったそのポイントというのは、これは時間軸の話です。この『ふたりの5つの分かれ路』の一組のカップル、マリオンとジルという二人は、実はこの映画の冒頭、離婚調停から始まって、彼らがなんでそんなことになってしまったか、時間を逆行しながら描いていくという作品になっています。いかにもノーラン的な。
渡辺:いや、本当そうだよね。
有坂:それをフランソワ・オゾンの人間の内面を、特に黒い部分を見つめる視線とともに描いた、本当にバランスの良い、ある意味エンターテイメントっぽい要素もある、けど、人間の理屈ではどうにもならないような、人間の本能的な部分まで描ききった、個人的には大好きな作品になっています。このタイトルにある『ふたりの5つの分かれ路』、5つというのは、これは離婚から始まって、いさかいがあって、出産があって、結婚があって、そもそもの2人の出会いがある、という5つの瞬間を描いています。時間を遡っていくってことは、本当にもうバチバチの離婚しなきゃいけないぐらいのバチバチな2人の関係から始まって、だんだんだんだん幸せな時間に戻っていくわけです。これって誰かとお付き合いしたことがある人なら、誰もが経験したことがある。付き合って別れたことがある人なら。それを映画ならではの時間操作というテクニックを使って、表現したわけです。出会いの瞬間、そこから二人の未来が始まるという、一番美しい出会いの美しい瞬間。でも、それがこの映画のエンディングになるんですね。でも、もう彼らの終わりは分かっている状態で、それを観ると、もう幸せな二人の姿を観れば観るほど寂しい気持ちになる。本当になんかこう、自分の感情も分かりやすい起承転結のハリウッドのラブストーリーとはちょっと違う、心がグラグラ動いているけど、ちょっと冷静に考えると、「でもこの二人、あんなバチバチで離婚すんだよな」っていう複雑な気持ちになる。そこは、すごくいかにもアムールの国のフランス人らしい、この技術をこういう形で使うんだなというところに、フランソワ・オゾンらしさもありつつ、でも、そういったハリウッドのエンターテイメント映画が使う手法までも、貪欲に自分の作品に取り入れて新しい表現を見つけようというところで、彼の監督としての貪欲さを、改めて感じることのできた作品が、この『ふたりの5つの分かれ路』です。
ある意味、そういう意味では、人の内面に迫りながらも映画のその大枠フレームの部分は時間を逆行する面白さがあるから、そういう意味では観やすさはあるかなと思うので、ここを入り口にしてもいいかなと思います。
有坂:観られるのかな。U-NEXT?
渡辺:これはでも本当ね、時間軸をいじったラブストーリーとしては、初めてぐらいのやつじゃないかなっていう。
有坂:確かに。
渡辺:『マリッジ・ストーリー』っていうNetflixのノア・バームバック作品、スカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライバーのやつもまったく同じ内容なんですけど。
有坂:だいぶ先駆けている。
渡辺:別れるところから始まっていくみたいな。『花束みたいな恋をした』も、ちょっと違うけど、なんかちょっとそういういじり方をしているみたいなところでも、なんかそういうラブストーリーで、この時間軸をいじってくるみたいなのが増えてきた、きっかけかもしれないですね。でも、やっぱ初期作が好きだね。けっこう、この後ね、コメディとかすごいつくるじゃん、オゾン。
有坂:確かに。
渡辺:そういうね、ジャンルもやっているんだけど、やっぱり初期のちょっと毒のあるとこが、好きなんだなっていう。
有坂:そうなんだよ。僕も、最初はバランスよく、まだ現役なので、現代のものもと思ったんですけど、現代のも本当に面白い。観終わった後に満足度ってめちゃくちゃ高いんですけど、でも、やっぱり作品としては収まりが良すぎて、オゾンの映画を観たなっていう満足感とは違う。でも、それはたぶん原体験として、今日紹介した『サマードレス』とか、『クリミナル・ラヴァーズ』を食らっちゃってるから。求めるものがちょっと変わっちゃっている。
渡辺:なるほど。
有坂:でも、なおさら、現役の監督なので、あえて今、初期作。なかなか観るきっかけがなくて、配信でも取り扱いないんですけど、観てもらうと、これだけの監督が今この時代で映画つくってくれているってことの、ありがたみみたいなものを感じられていいかなと思うので、ぜひ機会があったら観てみてください。
──
渡辺:はい、じゃあ出揃いましたね。
有坂:ということで、じゃあ、最後に告知を。
渡辺:告知は、1月30日(金)から『トレインスポッティング』、リバイバルやるんですけど、それに合わせて、このリトルプレスをつくりまして、で、この出版記念ということで、下北沢のB&Bで出版記念トークイベントを、なんとこの2人で(笑)、やることになりました。なので、それはワンドリンク付き、さらにこのリトルプレス付きっていうですね、で、1800円かなというので、トークイベントをこの2人で行いますので、90年代映画とかね、そのときの90年代映画シーンみたいなところを、なんか話せたらいいなと思っております。
有坂:あれだよね、このリトルプレスがついてきてワンドリンクだから、実質トークはほぼ無料。
渡辺:そうですね。
有坂:無料限定30人という形の、チケット制のね。
渡辺:そうです。
有坂:オンラインでもあるか。
渡辺:そう、配信もあります。
有坂:僕のお知らせも、これしかないなと思うんですけど、今回、僕はこのリトルプレスの中で、そもそも僕ら中学の同級生でキノ・イグルーを始めて、順也がフィルマークスの会社に入社して、メインはフィルマークスの仕事。僕は、キノ・イグルーがメインでやっている中で、今、キノ・イグルーを始めて22年。今回、初めて、このリトルプレスに、初めて順也から仕事をもらいました。それが嬉しくて。酔っ払っている体でいいますけど、それがけっこう嬉しくて。特に嬉しかったのが、今回、90年代映画特集ということで、僕らはその時代を映画をたくさん共に観て育ってきて、彼はフィルマークスの中でそれを企画として表現していく中で、改めてその時代を振り返るときに、僕はもうあの時代のカルチャーを貪欲に、ここでは言えない、あるテクニックまで使って、バイトも休んであるテクニックまで使って、時間とお金を使ってあの時代を体験してきたという自負があるんですね。で、順也から今回、このジンでエッセイを書いてほしいと言われたときに、そのお題が、90年代の映画シーンについて書いてほしいだったんです。だから、『トレインスポッティング』とか、『ファーゴ』っていう作品評ではなくて、それはもう僕も、もし他の人にお願いしていたら、たぶんもうここの縁が切れてキノ・イグルーが解散していたと思います(笑)。
渡辺:危なかったね(笑)。
有坂:それぐらい自負もあるし、本当に楽しみながら90年代を過ごしていました。僕が体験した映画の90年代っていうエッセイを書いています。このトークイベントのときには、ここに書ききれなかったエピソードが実は山ほどあって、それはその日に話そうと思っているので、これはトークイベントでしか聞けないものなので、リアルでも配信でも大丈夫なので、ぜひそちらチェックいただけると嬉しいです。
──
有坂:ということで、今回はノーランとオゾンの作品を紹介しました。また、来月お会いしましょう! ということで、今月は以上です。皆さん遅い時間まで、ありがとうございましたー。
渡辺:ありがとうございました。おやすみなさい!!
──

選者:キノ・イグルー(Kino Iglu)
体験としての映画の楽しさを伝え続けている、有坂塁さんと渡辺順也さんによるユニット。東京を拠点に、もみじ市での「テントえいがかん」をはじめ全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館など様々な空間で、世界各国の映画を上映。その活動で、新しい“映画”と“人”との出会いを量産中。
Instagram
キノ・イグルーイベント(@kinoiglu2003)
有坂 塁(@kinoiglu)/渡辺順也(@kinoiglu_junyawatanabe)

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店