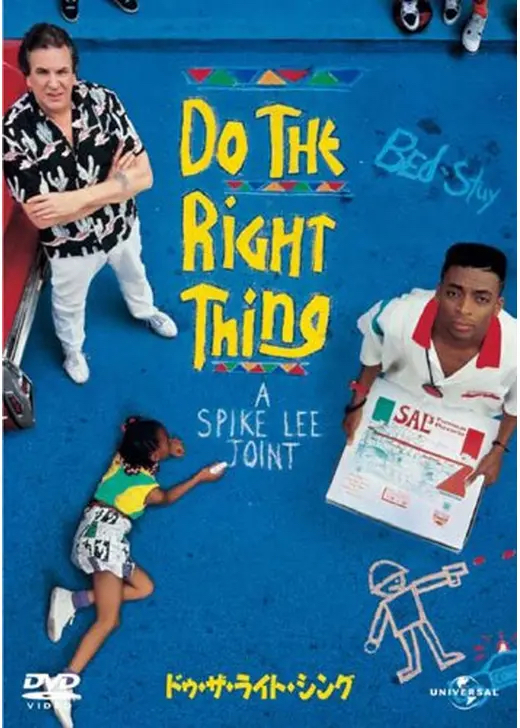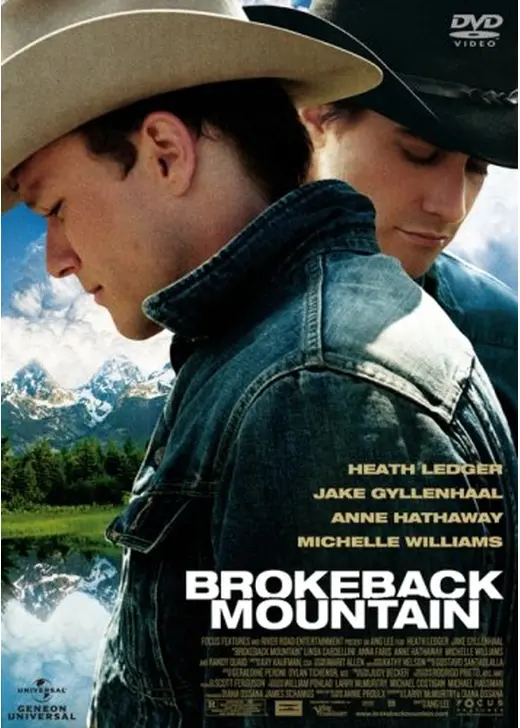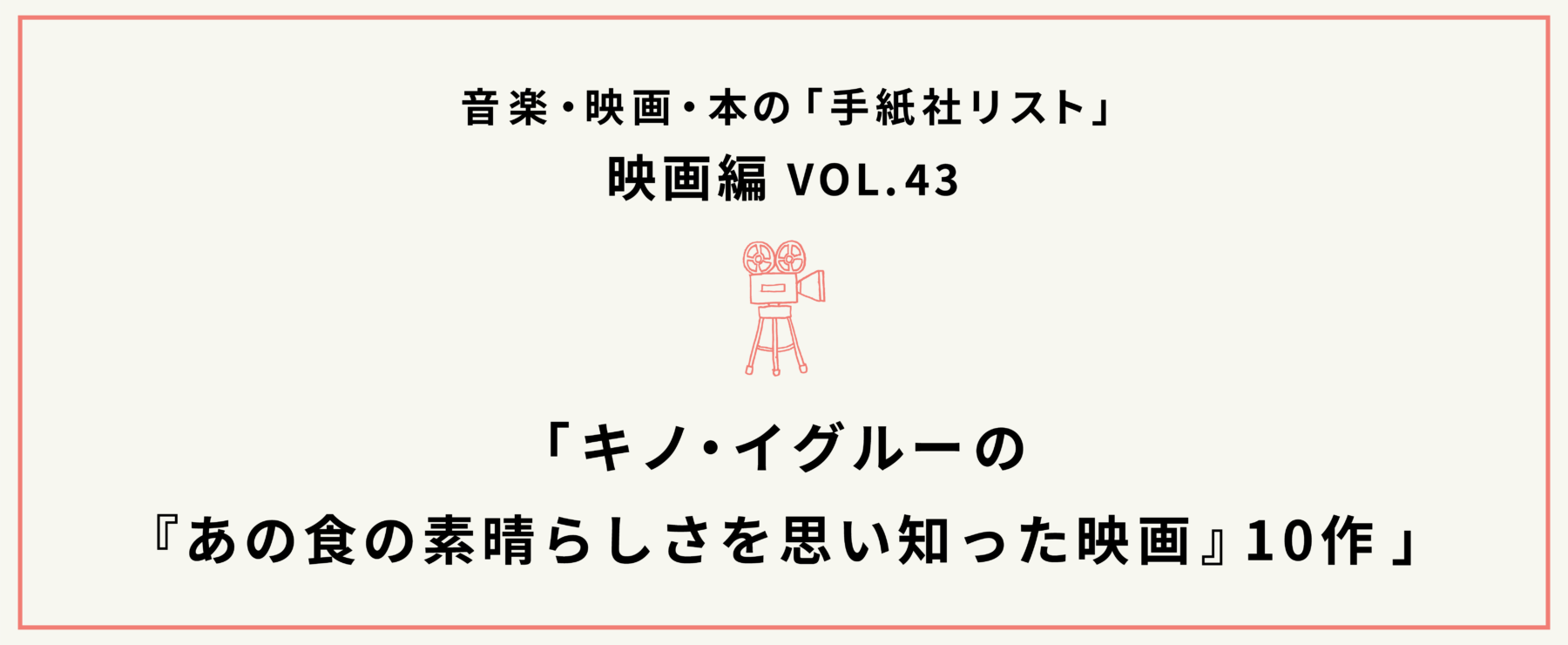
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。今回のテーマは、「あの食の素晴らしさを思い知った映画」です。その“観るべき10本”を選ぶのは、マニアじゃなくても「映画ってなんて素晴らしいんだ!」な世界に導いてくれるキノ・イグルーの有坂塁さん(以下・有坂)と渡辺順也さん(以下・渡辺)。今月もお互い何を選んだか内緒にしたまま、5本ずつ交互に発表しました! 相手がどんな作品を選んでくるのかお互いに予想しつつ、相手の選んだ映画を受けて紹介する作品を変えたりと、ライブ感も見どころのひとつです。
──
お時間の許す方は、ぜひ、このYouTubeから今回の10選を発表したキノ・イグルーのライブ「ニューシネマ・ワンダーランド」をご視聴ください! このページは本編の内容から書き起こしています。
──
−−−乾杯のあと、恒例のジャンケンで先攻・後攻が決定。今月も有坂さんが勝利し、後攻を選択。それでは、クラフトビールを片手に、大好きな映画について語り合う、幸せな1時間のスタートです。
──
渡辺セレクト1.『ホノカアボーイ』
監督/真田敦,2008年,日本,111分
有坂:うんうんうんうん。
渡辺:これは別の機会で塁が出していたと思うんだけど、また違う切り口で、この『ホノカアボーイ』っていうのは日本映画なんですけど、日本人の青年レオがですね、ハワイに旅をして、ひょんなことから現地で映画館で働くことになりました、というお話です。映画館に通っているうちに近所の偏屈ばあさんで有名なビーさんという人がいるんですけど、その人に気に入られて、「うちにご飯を食べに来なさい」というので通うことになって、自分探しの旅に出ていた青年と、偏屈で有名なおばあさんとの交流を描いたドラマです。なので、そこで2人の距離を縮めることになるきっかけというのが、料理だったりするんですけど、その中で出てくるビーさんがつくるロールキャベツ。ロールキャベツとマラサダと2つ出てくるんですけど、これがもうめちゃくちゃうまそうっていう。こういうやっぱり料理がキーワードになるような作品の映画のパンフレットって、だいたいレシピが後ろのほうに載っているのがあるんですけど、これも「ビーさんのロールキャベツ」っていう名前で、確か載っていたと思うんですよね、あと「マラサダ」と。この辺がすごい美味しそうな作品となっています。やっぱり物語のキーワードにもなっているし、マラサダとか、当時僕はあんまり分かってなかったんですけど、なんかドーナツみたいなやつですね。日系人の人たちの話なので、ビーさんも日本人女性で、倍賞千恵子さんが演じているというものです。あと、脚本がですね、高崎卓馬さんという、昨年『PERFECT DAYS』という役所広司さんの主演の作品ですね、ヴィム・ヴェンダース が監督をした。その脚本も手がけた高崎卓馬さんが脚本をしているというので、なんかこう、たまにしか映画をつくっていないんですけど、割とポイント、ポイントでけっこう気になる作品をやっていたりします。
有坂:広告の人だよね?
渡辺:そう、そうなんだよね。CMプランナー。
有坂:そっちで、すごい知っている。
渡辺:小説も書いたりとか、脚本も書いていたりとか、わりと多才な方ですね。という、『ホノカアボーイ』は、原作の本がめちゃくちゃ面白くて。
有坂:面白いよ〜。
渡辺:あのPORTERという、カバンのね、吉田カバンの社長の息子さんなんだよね。
有坂:そうそう。
渡辺:そのなんか、ハワイ滞在の体験を綴ったお話なんですが、まあそれがすごい面白い。で、映画化してっていうところなんですけど、まぁ、映画中では結構この料理がポイントになって出てくるというのがあるので、ぜひ気になったら観ていただけると嬉しいなと思います。
有坂:けっこう、配信でもあるね。マラサダといえば、ベスト・オブ・マラサダは、僕の中では悔しくて本当は言いたくないんですけど、手紙社でもおなじみの千葉県の「fato.」のマラサダがね、悔しいけど、今まで食べた中で一番おいしい! 悔しいというのは、その「fato.」の店主はですね、僕の高校のサッカー部の後輩なんです。で、あんなにあんなに味覚の無かった男が、こんなおいしいマラサダをつくるのかっていう、ちょっと本人に言うのが悔しくて悩んだんですけど、ちゃんと伝えましたが、食べたことがない方はぜひ! 千葉県の長生郡というところにある古民家カフェの「fato.」のマラサダ、ぜひ食べてみてください。
渡辺:そんなに味覚なかったんだ。
有坂:ひどかったよ。
渡辺:「お前に言われたくないよ」と思っているかもよ(笑)。
有坂:絶対、言われると思う。……はい、いいですか? じゃあ、僕の1本目にいきたいと思います。食べ物としては、トウモロコシのかき揚げです。2007年の日本映画になります。
有坂セレクト1.『歩いても 歩いても』
監督/是枝裕和,2007年,日本,114分
渡辺:んー、うんうんうん。
有坂:これは是枝裕和監督が2007年につくった、いわゆるホームドラマですね。個人的には、是枝作品の中ではダントツでベストな一本でもあるんですけど、この映画の中に出てくる「トウモロコシのかき揚げ」を紹介したいと思います。まず、物語自体は夏、この写真にも半袖を着ていますけども、夏のお盆の時期の話で、亡くなった、家族の中で亡くなった長男の命日にみんなが集まってきて、その中でいろいろと家族の団らんをしていく中で、いろいろな過去が浮かび上がってきたりするっていう、わかりやすい物語が進んでいくっていうよりは、関係性の中で物語が浮かび上がってくるっていう。是枝監督の真骨頂が発揮された映画かなと思います。この中で「トウモロコシのかき揚げ」というのは、とにかく調理するところ、トウモロコシを剥くところから始まって、丁寧にかき揚げをつくっていくというプロセスを、おいしそうに映像に残しているんですけども、おいしそうなだけじゃなくて、実はこのトウモロコシのかき揚げをつくるというのが、家族の思い出の一つでもあるんですよね。なので、命日に集まって、湿っぽくはない雰囲気の中で、樹木希林さんとYOUさんが冗談言い合って悪態ついたりとか、ちょっとユーモアもあるようなシーンの中で、でも、かき揚げをつくるというところで、ふと過去のことを思い出してちょっと寂しい気持ちになったり、その物語の一つのキーとなっている食べ物でもあったりします。この映画の中で、なんかトウモロコシは茹でたり焼いたりするよりも、揚げたほうが甘みが増すんですって。僕、トウモロコシのかき揚げって食べたことがなくて、それまで。で、この映画を観てから、もう食べたくてしょうがない。で、居酒屋とか行くと結構あるんだよね。それまで僕の中では、あんまり興味のない食べ物として選択肢に入ってきてなかったんですけど、まさにこの『歩いても 歩いても』を観てトウモロコシのかき揚げ食べたい! 出会いました。
で、食べたらうまい! と思って、そこからはメニューにあるたびに、毎回本当にたのんでいます。それぐらい、なんかこう本当にトウモロコシのかき揚げの素晴らしさを思い知った映画として。
渡辺:なるほど(笑)。
有坂:まず、1本目はこれしかないなということで、ここから始めたいと思います。
渡辺:そういえば、あったなっていう。
有坂:本当に? もう真っ先に出てくるぐらいのインパクトで。
渡辺:なるほど。
有坂:たぶん、だから食べるだけとかじゃなくて、あと、揚げ物ってさ、やっぱり映像映えするじゃない。映像、あと音。いい音なんだよね、揚げているときの。そこから、食べるときのサクっていう音とか、本当にあのしずる感っていうんですか。そういうものが本当に映像を通してちゃんと伝わってくるんだよね。
渡辺:映画としてのインパクトのほうが、大きかったかな。
有坂:本当に。めちゃくちゃいい映画だよ。
渡辺:そのYOUと樹木希林が台所でね、そうやって、こう一緒に楽しそうに料理をつくっているみたいなのがフリになっていてさ。その後、すごい、樹木希林の闇の部分を出してくる。
有坂:セリフがね。
渡辺:そっちのほうが、もうインパクトが強くって。
有坂:あの一瞬、ホラー映画だよね。
渡辺:うん。ちょっとなんか、そっちのほうが、インパクトが強くて。
有坂:でも、なんか、あそこのシーンがあるから、なんか信用できるなって。是枝さんは、やっぱりなんかそういう心の闇、闇と言ってしまえば闇だけど、人の本質があったりするじゃない。なんか、それを別に良いも悪いもなく、人の本質として表現している。
渡辺:そうね。
有坂:そういう意味で、ほんと特別な一本かなと。
渡辺:なるほど、日本映画で来ましたね。じゃあ、ちょっと海外に行きたいと思います。僕の2本目はですね、1989年のアメリカ映画です。
渡辺セレクト2.『ドゥ・ザ・ライト・シング』
監督/スパイク・リー,1989年,アメリカ,120分
有坂:あー、あー! わかった、そうそう、わかるよ。
渡辺:『ドゥ・ザ・ライト・シング』は、スパイク・リー監督の作品で、えっとかなり初期作ですね。監督、脚本、主演がスパイク・リー。スパイク・リーって、今はもうおじいちゃんですけど、このときは、すごいもう、やせこけた、少年ぐらい若さの……
有坂:B-BOY。
渡辺:B-BOYですね。本当に、舞台もニューヨークのブルックリンの黒人街の話なので、本当にそういう黒人カルチャーとかですね、ポップカルチャーが、前面に出た作品です。時代としても、90年代に入るタイミングだったりするので、そういうなんかヒップホップとかも出始めの頃ですね。そういう黒人カルチャーがフューチャーされ始めたとき感じで、どこで観たんだっけな、シネマライズとかだったかな、けっこうやっぱり90年代のミニシアターブームの。
有坂:シャンテ。
渡辺:シャンテか。その辺にまた新しい監督が出てきたっていうところの作品でした。これ、ストーリーとしては、ブルックリンで主人公がスパイク・リーなんですけど、ピザ屋でバイトをしていて、ピザの宅配をしているんですね、っていうのがこの映画のフードのところではあるんですけど、やっぱり当時ピザって、なんだろうな、イタリア料理でピザはあるっていうのと、アメリカのデリバリーのドミノ・ピザとかピザーラとか、そういうのも出てきてっていうタイミングで、あれってやっぱり今もそうですけど、丸の状態の1枚とか、2枚とかを買って宅配してもらうっていうやつなんですけど、この『ドゥ・ザ・ライト・シング』のスパイク・リーが宅配してるのって、ひと切れだけなんですよね。それが、一番衝撃的で、「アメリカって、こんなひと切れを宅配してくれるんだ!」っていう。あと、やっぱりでかい一枚、食べきれないっていうのがあるんですけど、ちょうどなんかこのワンピースだけ食べたいみたいなやつを宅配してくれるって、アメリカすごいなと思ったんですよね。っていうのが、本当にこの『ドゥ・ザ・ライト・シング』といえば、このワンピースのピザっていうのが、かなり印象として残ってる作品です。この作品自体もすごい面白くて、あとはブラック・ライブス・マターみたいな、今でも通じるメッセージとかがすごいあって、ブルックリンの下町なんで、いろいろアジア系とかもいるし、黒人も多くて、差別もあるみたいな、それをちょっとポップにユーモア交えて、ちょっとした言い合いから、暴動に発展していくみたいなっていうのをユーモラスに描いた作品です。そのきっかけを、スパイク・リーとかが思いっきりつくっているんですけど、それで、そのピザ屋も暴動に巻き込まれて、ぶっ壊されちゃうのに、「今日のバイト代をよこせ」みたいなことをスパイク・リーが堂々と言うみたいな、そういうちょっとね、どういう神経しているんだみたいな、面白さとかがあったりっていうのもあるし、まあ本当に音楽もすごくいいし、ビジュアルもポップでかっこいいし、それでいて今にも通じるメッセージがある作品だったりしますので、これもまだ観ていない方がいたら、ぜひチェックしてもらえればなと思います。
有坂:いや〜、名作だね。これはめちゃくちゃパンチの効いた。あれだよね、「なんかここ何十年かで一番暑い日なんだよね」っていう設定で、こうマンホールから水とかが吹き出ているみたいな。そのなんか真夏の灼熱のブロンクスも映像で観ると、本当にもう一生忘れないようなインパクトがあって、その中の日常なんだよね。
渡辺:そうだね。
有坂:大好き。だけど完全に忘れていた。
渡辺:あーそう、
有坂:でも、その『ドゥ・ザ・ライト・シング』を観るときにおすすめなのが、吉祥寺にあるトニーズピザで買ったピザを食べながら観るのがいいと思う。あそこってニューヨークスタイルのピザで、すごくもう結構おじいちゃんが本当に焼いてくれるんだけど、1枚から買えるの、ちゃんと。ワンピースで。
渡辺:そうなんだ。珍しいね。
有坂:絶対に、『ドゥ・ザ・ライト・シング』は観ているはず。この辺の情報はちょっとわかんないんだけど、ワンピースから買えるので。しかも、けっこう大きい。チーズもたっぷりで。なんかそれとともに観るのが、おすすめかなと思いました。順也らしいね。じゃあ、僕もアメリカ映画でいきたいと思います。食べ物としてはフレンチトースト。といえば、1979年の映画です。
有坂セレクト2.『クレイマー、クレイマー』
監督/ロバート・ベントン,1979年,アメリカ,105分
渡辺:はいはい、うん。
有坂:これは、ダスティン・ホフマンとメリル・ストリープが夫婦の、家族ものの映画なんですけど、もう仕事第一の、もうバリバリ仕事してますみたいなダスティン・ホフマンが、あるとき、その奥さんのメリル・ストリープに愛想を尽かされて、「もう私は妻とか母ではなく自分自身を見つけたい」と言って出ていってしまう。で、仕事しかしてなかったダスティン・ホフマンが、息子と2人暮らしになるんですよね、急に。まったく家事もしていなかったから、もうそういう日常からすべて、当たり前なんですけど、生活をしていくことから、子どもとの関係も生まれてっていうような物語になっています。で、この映画の、まあさっき僕が1本目に上げた映画が、あの『歩いても 歩いても』。で、そのかき揚げがおいししそうなだけじゃなくてって話しましたけど、『クレイマー、クレイマー』のフレンチトーストも、物語にちゃんとこうリンクしているんですね。というのは、この奥さんが出ていった後、息子と2人で最初にフレンチトーストをつくるんですけど、いかんせんダスティン・ホフマンは、まったく料理をしたことがない。でも、俺はできるって強がっている父なんですよ。実際、フレンチトーストをつくってみると、もうトーストは焦げちゃうし、もう熱々のフライパンを素手で握ってみたいな感じで、もうてんやわんやみたいな。そんな自分に腹立たしくてパパ切れる、みたいなシーンがあるんですね。息子は、恐怖と心細さで寂しそうみたいなシーンがまずあって、その後、物語が二転三転して、映画のクライマックスに、また息子と2人でフレンチトーストをつくるシーンがある。このときは、もう阿吽の呼吸で、息子と2人でフレンチトーストをつくるんですね。で、なんかパンを、卵をまずかき混ぜるところを息子がやって、それをお父さんに渡した後、息子は食パンを袋から取り出して、お父さんが最後かき混ぜたところにぽんって投げるの、で、そこの会話が一切ない中で、2人でフレンチトーストをつくる。で、作るシーンの最後で、息子がね、切なそうな顔をして、パパがもうそんな息子を観て、こうギュってハグをするんですよ。そうすると息子は泣いちゃうんです。なんで泣いちゃうんでしょうか。これはちょっと言うとネタバレになっちゃうので言えないんですけど、あの本当にフレンチトーストを通して、その親子の成長も見て取れる。あとは、そのコミュニケーションというところもフレンチトーストを介して行われるという意味で、おいしそうなだけではない食の使い方ということで、本当にこれは記念碑的な名作かなと、個人的には思っています。いろいろ調べてみると、これ、1979年の映画なんですけど、この映画を通してフレンチトーストのつくり方を、日本人は初めて知ったみたいな。
渡辺:そうだよね。
有坂:……って言われていて、リアルタイムの人ほど、この映画のフレンチトーストってインパクトが強いみたいです。あとは、作品的にも、これはもうその年のオスカーを総舐め。主要5部門を受賞している、本当に名作中の名作なので、ぜひフレンチトースト目線でもいいですし、そういう家族もの観たいなという方は、ぜひ観てほしいというより、マストな一本かなと思います。
渡辺:これも観られますね。配信で。これは、本当にフレンチストースといえばっていう作品で有名だし、映画としてもアカデミー賞とか獲っていて、名作という作品ですけど、
有坂:まだ、だからこれって、離婚とかが今ほど当たり前じゃない時代だったから、それが映画のテーマになっているっていう意味でも、今との時代の違いみたいなことも、たぶん観ると面白いかなと思います。
渡辺:フレンチトーストつくれないでしょ?
有坂:つくれない。つくったことない(笑)。たぶん、ダスティン・ホフマンと同じだと思う。ああって言って焦がしちゃう。
渡辺:フライパン握っちゃう。では、続けて3本目いきたいと思います。3本目は、2018年のアメリカ映画です。
渡辺セレクト3.『グリーンブック』
監督/ピーター・ファレリー,2018年,アメリカ,130分
有坂:うーんうんうんうん。
渡辺:これは割と最近の作品なので、観ている人も多いかもしれないですけど、内容としてはですね、舞台が1950年代ぐらいかな。ちょっとまだ昔、60年代か。黒人のピアニストがいるんですけども、彼が南部にツアーをしに行くことになって、その運転手に選ばれたのが、トニーという男なんですけど、彼はチンピラみたいな仕事をしていて、クラブの用心棒とか、そういうのをやっていた男で、気性の荒いタイプの男なんですけど。それが運転手としての報酬もいいということで引き受けるんですけど、なんで俺が黒人なんかの運転手をやらなきゃいけないんだって言いながらも、報酬がいいということで引き受けるんですね。彼は、もうゴリゴリの差別するタイプの人間で、ぶっきらぼうで喧嘩早いみたいな、そういうタイプなんですけど、その黒人のピアニストは、めちゃくちゃインテリで物腰柔らかくてジェントルマンで、という対照的な2人なんですけど。で、南部にツアーに行くんですけど、南部のほうが黒人差別ってすごいんですね。時代も時代なんで、なんで白人が黒人なんかの運転手をしているんだとか、あとはやっぱり黒人に対する言われのない差別とかっていうのを受けてるうちに、運転手のトニーはだんだんなんでそんなことで差別されなきゃいけないんだとか、なんで、そんなことで責められなきゃいけないんだとかっていうふうになっていくんですよね。2人の友情も芽生え出したりする中でツアーに行くので、差別を受ければ受けるほど2人の絆が強まっていくっていう、そういう感じのドラマとしてもめちゃくちゃ面白いし、メッセージ性もしっかりあるというタイプの作品です。南部を旅しているときに、ケンタッキー州に通りがかるんですね。そうすると、現地の黒人の人たちとも仲良くなって、黒人料理を振る舞われるんですけど、それがなんとチキン料理なんですね。やっぱりチキン料理は、南部の黒人の郷土料理らしくて、そこで味付けしてうまいっていうのが、ケンタッキーでは有名だったらしいんですね。そのフライドチキン、ケンタッキーフライドチキンが、そこですごく有名になったものなので、カーネル・サンダースが作る前から、現地のご当地グルメみたいな感じだったらしいんですよね。そこを描いているんですけど、この2人が買い食いして、ケンタッキーフライドチキンを頬張りながら車に乗っているっていう、それがもうめちゃくちゃおいしそうで、本当になんかこう、「これはうまい!」って言ってしゃぶった骨を車の外にポイポイ放りながら、車に乗りながら食べるっていう。あのフライドチキンが本当においしそうで、これを観た方はたぶん同じような気持ちになったと思うんですけど、僕も当時映画館出て、まっすぐケンタッキーフライドチキンに向かったっていうぐらい、もう本当に腹ペコのときに観ると、危険なタイプの作品です。
映画自体も感動的でめちゃくちゃいい。でも、ケンタッキーフライドチキン、すごく食べたくなるっていうですね、というのがこの作品です。これは、アカデミー賞も獲って、本当に作品としても有名で、これも結構、いろんなところで多分観られると思います。
有坂:アマプラとかU-NEXTとか、そうですね。
渡辺:いろいろ、やってますね。これ観ていない方は、本当に普通にちゃんと感動できる名作なので、ぜひ!
有坂:これは、やっぱさクラブの用心部を務めたトニー役がヴィゴ・モーテンセンっていうのがいいんだよね。
渡辺:そうね。
有坂:絶対、この本当、めちゃくちゃ差別しそうだなとか、自分の信念を変えなさそうだなみたいな強さがすごく出ている人だから、その人がだんだん心変わりしていくっていうところの説得力と感動。
渡辺:そうね、役者としてはね。でも、これはちょっと僕は、どうなのと思ったのは、イタリア人役なんですよ。イタリア人役なのに、デンマーク人のヴィゴ・モーテンセンがイタリア人としてやるっていうのは、どうなんだと思ったんですけど、ただ、それはちょっと一部言われてたこともあるんですけど、やっぱりヴィゴ・モーテンセンの演技力がすごすぎて、それすらも黙らせるっていうですね、っていうのはありましたけど、ちょっとそういう思うとこもある。
有坂:じゃあ、それで言うと、誰がいいんだろうね。誰かいる? イタリア系で、ちょっとやんちゃっぽい感じのね。若きアル・パチーノとかね。でも、探せば必ずいるはずだけど、ネームバリューも、実力も含めて。
渡辺:そうね。
有坂:わかりました。じゃあ、今の『グリーンブック』の設定が1962年って書いてあったね。ということで、僕は1963年の設定の映画をいきたいと思います。料理でいうと、豆料理です。
渡辺:んん?
有坂セレクト3.『ブロークバック・マウンテン』
監督/アン・リー,2005年,アメリカ,134分
渡辺:おー、ほほほほ。
有坂:これは、アカデミー賞にね、結局作品賞は獲れなかった。最有力と言われながら、その年、『クラッシュ』という映画が取って、オスカーの作品賞こそ逃したものの、その年の世界中の映画賞、特にヴェネチィア国際映画祭のグランプリ、金獅子賞を獲っているということでも、その年を代表する一本かなと思います。これはヒース・レジャーとジェイク・ギレンホール、2人のカウボーイが主人公で、2人の20年にわたる愛の行方を綴った物語となっています。60年代っていう時代設定、さっき、順也の『グリーンブック』の説明がありましたけど、やっぱりものすごく、まだ差別、いろんなことに対しての差別が、当たり前のように行われているような時代で、男の象徴みたいなカウボーイが、実は、同性愛者であるというか、同性愛に目覚める、っていうところを描いた物語になっています。なので、この時代設定の60年代では、およそつくれないような映画。そこから40年ぐらい経ったからこそ、改めてその時代のカウボーイとか、男性にも同性愛者はいたはずっていう視点で、これは映画になった作品となっています。この映画の料理は、豆料理ということで、見るからに高級でおいしそうな料理ではなくて、西部劇とかにもよく出てきますけど、いわゆる缶詰の豆をキャンプとかで直接火にかけて食べるみたいな、熱いって言いながらスプーンで食べる。そういうシーンがけっこう出てくるんですよ、『ブロークバック・マウンテン』で。もう食べる料理が本当に豆料理しかなくて、途中でヒース・レジャーが、「もう豆料理は嫌だ」って言うぐらい、そんなセリフがあるぐらい、繰り返し出てくる。あと、ちょっとこう映画のインパクトのあるシーンにも、豆料理っていうのは、ちょっと関連してくる、っていう意味で、すごく印象に残っている。あの場面、料理になっていて、いつか自分もこれは真似してみたいなと思いながら、まだできていない料理になっています。で、なんかこう、映画に感謝なんですけど、やっぱりこうハッピーエンドの映画がいいなーって人もいれば、同じぐらい切ない映画が好きなんですって人って多いよね。切なさが残るみたいな。そういった意味では、まあこの映画は、もうトップオブトップ、めちゃくちゃ切ない。それは時代のせいなのか。時代だけではなく、もちろんそれぞれ2人のパーソナリティも含めてのこの結末かなとは思うんですけども、やっぱりその時代に思いを馳せながら、こういうカウボーイに感情移入して、何かを考えるっていうのも、それは映画を観る醍醐味の一つかなと思うので、自分とはまったく違うタイプの人なら、なおさらこういう人の人生を追体験してほしいなと思う一作にもなっています。
ぜひ、観てほしいし、「ヒース・レジャーといえば、ジョーカーでしょう」と、『ダークナイト』、もちろんそれは間違いないんですけど、同じぐらい代表作として『ブロークバック・マウンテン』があり、あと、『恋のからさわぎ』っていうラブコメがあるという中で、ヒース・レジャーのすごさも感じられる1本となっています。
渡辺:監督がね、中国人なんですよね。
有坂:アン・リーね。
渡辺:なんか、そういうところもちょっと面白いですね。外国人の目から見て、やっぱりそのね、カウボーイっていう男の象徴みたいな。で、カウボーイだけに、南部でね。そういう差別意識の強い地域、時代でこれをやったっていう。なんかその辺もすごさもあるし、作品自体も本当に名作なんで、多分、この年のベスト10に入っている。
有坂:いや、もう余裕で作品賞でしょって思ったらね。9.11? なんだっけ、なんか大きな事件があって、世の中の空気が、そういう方向に引っ張られて『クラッシュ』に決まったっていう背景があるので、改めて作品として観ると、名作であることは間違いないかなと思う1本です。
渡辺:では、続けて、僕の4本目は、2017年のアメリカ映画をいきたいと思います。
渡辺セレクト4.『ファントム・スレッド』
監督/ポール・トーマス・アンダーソン,2017年,アメリカ,130分
有坂:ほう。
渡辺:この『ファントム・スレッド』……
有坂:食べ物?
渡辺:ピンときてないね。
有坂:うれしそう(笑)。
渡辺:しめしめ、全然料理映画じゃないので。『ファントム・スレッド』監督は、ポール・トーマス・アンダーソン。P・T・A、天才PTAの作品です。で、主演が天才ダニエル・デイ=ルイスですね。もう、役に打ち込みすぎるでおなじみのダニエル・デイ=ルイスなんですけど、お話はどういうのかというと、時代設定は1950年代のロンドンで、主人公のダニエル・デイ=ルイスは、ファッションデザイナーなんですね。当時は、オートクチュールといって仕立てるやつですね。その人用に服を仕立てるというので、お金持ち、セレブを相手にする高級洋服店のファッションデザイナーがダニエル・デイ=ルイスなんですけど。まぁ、時代の寵児みたいな人で、その人は日々忙しく暮らしているんですけれども、ある日、レストランに入ったときに、そこのウェイトレスに一目惚れをして、その子は本当にただの町娘ではあるんですけど、そんなトップクリエイターにスカウトされて、早速デートに行って、何をするかといったら、服の採寸をしだして、彼女のためにドレスをつくるみたいな、っていうところから始まるラブストーリーです。基本ベースはラブストーリーなんですね。でも、映像美がめちゃくちゃ綺麗で、50年代のクラシックな雰囲気と、とにかく洋服とか衣装が全部美しいんですね。車とかもすごいクラシックカーだったりとか、美術とかも素晴らしくて、音楽もジョニー・グリーンウッドで、ちょっとクラシック寄りな重厚な音楽だったりして、映画の世界観はバッチリかっこいいものになってるんですけど。この2人のラブストーリーが、愛の形がどういうふうに進んでいくか、みたいなところなんですけど、やっぱりトップクリエイターで大忙しなので、彼のペースで進んでいくんですけど、疲れすぎて疲弊して帰ってくる。そういう二人になったときだけ、彼女の方がちょっと優位に立てるというか、疲れ果てて疲弊したダニエル・デイ=ルイスは、少し彼女に従順になる、そういう関係性が生まれるんです。そうなったときに、彼女のほうに何か目覚めるものがあって、そのキーポイントに出てくるのが、なんと「キノコ料理」なんですね。あるとき、彼にキノコのソテーみたいな料理をつくるんですけど、それはそれですごいおいしそうなんですね。キノコ、おいしいんで、好きな方も多いと思うんですけど、それを食べた彼は苦しみだすんですね。それはなんと毒キノコで、毒キノコといっても、別に死に至るわけではなくて、嘔吐したり、ちょっと痺れたり、苦しそうになるんですけど、そうするとまた彼女を頼らざるを得ないというか、その彼女はそういうときにまたちょっと優位に立てる関係性になるんですね。なので、この二人の特殊な愛の形みたいなものが、そういう方向にシフトしていくんですけど、そのきっかけとなるのが、実はキノコ料理っていうですね。「キノコ料理、そんなふうに使う?」みたいな。なかなかこんな映画はないと思うんですけど、キノコがキーワードになるみたいな。でも、そのなんかこう毒殺するとかそういうものじゃなくて、愛の形の一つとして、それをアイテムに使ってくるっていう、ポール・トーマス・アンダーソンの変態さみたいなところがすごい現れているし、映画自体はめちゃくちゃ上品で、高級感あふれる感じのルックで、すごく重厚な感じで面白いですけど、このラブストーリーがまたちょっとそんな実は変態チックだったっていうですね。そういう面白さもあるのが、この『ファントム・スレッド』です。天才ポール・トーマス・アンダーソンの作品なので、面白さは本当に間違いないという作品です。
有坂:そうだったね。完全に忘れてた。
渡辺:実は、そうなんですよ。俺、もうこれ衝撃的だったから(笑)。
有坂:キノコ料理食べた?
渡辺:しばらく、キノコ料理が怖いみたいな(笑)、家でキノコ料理が出てきたら、怖いみたいな。
有坂:これ、あれだよね、ダニエル・デイ=ルイスって、役に没頭するでおなじみって最初に言ってたけど、役だけじゃなくて、基本的に自分がこれだって思ったものにのめり込む人で、役者辞めて靴職人やっていたんだよね。で、靴職人からの復活作がこの『ファントム・スレッド』で、デザイナー。なんか、ある意味、彼の人生もそこにかぶせながらの役っていうところも面白いなと思ったら、話がどんどん違う方にいく。
渡辺:これも役作りで、1年間デザイナーに修業していたらしい。
有坂:1年間すごいね。
渡辺:1年間ってすごいでしょ。で、本当に服をつくれるようになっちゃったらしい、っていうぐらいの役作りだから、やっぱりデザイナーの役やってて、服のパターンをつくっている姿とかやっているんですけど、それが本物にしか見えないんですよ。
有坂:そういうとこ大事だね。
渡辺:それが、本当にすごいですね。
有坂:なるほど、わかりました。じゃあ、僕の4本目は食べ物で言うとね、マカロンです。と言えば、2006年のアメリカ映画です。
有坂セレクト4.『マリー・アントワネット』
監督/ソフィア・コッポラ,2006年,アメリカ,123分
渡辺:うんうんうん。
有坂:これはソフィア・コッポラの作品で、大好きっていう人も多いと思います。同じぐらいアンチがいたと言われている映画でもあるんですけれども、これはタイトルそのまんま、マリー・アントワネットの生涯を映画化したものなんですけど、とにかくこの映画の何が衝撃だったって、いわゆる歴史絵巻みたいな大画ドラマ、いくらでも重厚につくれる、ちゃんと歴史を調べて、いろいろ間違いがないように調べて、重厚な映像でつくるのが、こういういわゆる歴史ものだったのが、ソフィア・コッポラは、全部そこを反転させて、マリー・アントワネットの青春映画にしちゃった。しかも、時代考証とか全部すっ飛ばして、もう着ている洋服のパステルカラーを基調にした洋服であったりとか、あと映画で流れる音楽が例えばザ・キュアーとかザ・ストロークスとかニュー・オーダーとか80年代のニューウェーブとかをこの映像に当てる。今の時代の感覚でつくり直した『マリー・アントワネット』という意味で、同時代の若い人たちからは圧倒的な支持を受けた。だけど、「歴史ものは、それじゃダメでしょ」っていう、アンチからはものすごい批判を受けたという意味でも、大きな話題を読んだ一作となっています。この映画の中で、とにかくマリー・アントワネットの青春っていうのは、恋をしたり、あとは物欲の塊だったので、とにかく買い物をする。家にすごく高級な布を持った人が来て、これが欲しい、あれが欲しいって言ったものが全部買える。甘いものも大好きで、ケーキも食べたい。その中で、マカロンが出てくる。なんか、ある意味こんな贅の極みみたいな、夢の生活をしてみたいなーっていうことをソフィア・コッポラはマリー・アントワネットって役を通してみんなに疑似体験させてあげるっていう意味でも、あの面白い一作かなと思います。で、まぁこれ、マカロンは、パリの老舗の「ラデュレ」のマカロンが使われているんですけど、実は、もともとこの衣装を担当した人って、ミレーナ・カノネロっていう『グランド・ブダペスト・ホテル』とかもやっている衣装デザイナーなんですよ。オスカーとかも、けっこう取っている女性なんですけど、彼女のこの映画をつくる上での衣装のヒント。カラーパレットと言って、ベースになる色彩設計をつくるときのヒントになったのが、ラデュレのマカロンなんですね。なので、マカロンタワーとかもビジュアルからおいしそうにも見えるんですけど、この映画全体の世界観をつくる上で、すごく重要なキーになった一つが、またマカロンだったりするということで、ぜひそんな目線でも観てほしいなと思います。あともう一個、『マリー・アントワネット』を観るときに、ちょっと注目してほしいのがクローゼットのシーン。靴はマノロ ブラニクの靴がいくつも並んでいて、どれも素敵だなっていう中に、ふとコンバースのスニーカーが置いてあります。水色だったかな? それは、マリー・アントワネットは履かないんですけど、クローゼットの中にポンとコンバースのスニーカーが置いてあります。その遊び心も含めて、ソフィア・コッポラのセンスが爆発した一作かなと思うので、ぜひ気になった方は観てみてください、……と言いながら、観られない。
渡辺:観られないんだ。
有坂:でも、いずれ配信で上がってくると思います。
渡辺:なるほどね。本当、そのときの今の解釈でやりましたっていう感じのソフィアらしい。
有坂:それまでのタブーだよね。そういうちゃんと時代を、背景を踏まえてつくらないといけないっていうところを、どんどん自分の感覚でつくり直したっていう。そうですね。
渡辺:そうだね、まあだけどね、そのときの若い一人の女の子っていう視点に共感させるとしたら、そういう今の感覚でっていうのは、それはもう何か新しいアプローチかなと。
有坂:そうそう、理にかなっているよね。
渡辺:あとは、そういう中でセレブの孤独みたいな、ソフィアらしい一貫したテーマが。
有坂:おなじみのね
渡辺:それがある作品でもあるかなと思います。じゃあ、ラストいきたいと思います。僕の5本目は、2022年の日本映画。
渡辺セレクト5.『土を喰らう十二ヵ月』
監督/中江裕司,2022年,日本,111分
有坂:ははぁ。
渡辺:これは沢田研二さん主演の作品で、これも最近の作品なので、観たことがある方いるかもしれないですけど、物語としては長野県の山奥というか、村に住んでいる沢田研二さんが主人公なんですけど、彼はもともとバリバリやっていたライターというか、作家さんなんですけど、今は田舎に引っ込んで畑仕事をしながら、たまに執筆をするっていう、そういうスローライフをしている主人公の男の人です。そこに、松たか子さん扮する編集者が東京から遊びに来て、彼女との交流をしていく四季を描いていくという作品です。原作がある作品なんですけど、これは本当にとにかく料理がいろいろ出てくる作品で、これの場合はもうなんかこの料理というよりかは、もうこの全般が、本当にこう土と暮らすとか、旬のものを旬なときに食べるみたいな、そういう四季折々の、本当に自然と密着した食っていうものを描いた作品なので、全般的に食を描いているし、おすすめしたい作品ですね。本当に松たか子さんが最初に訪れたときに、干し柿を干してあったやつとお茶を出すみたいな。ちょうど今それが旬な時期で、今あるものでもてなすとか、ちょっと大根を取ってくるって言って、庭から大根を取ってきて、それをふろふき大根にして、熱々のお出汁と一緒にホクホク食べる。そういうのがね、いちいち全部おいしそうなんですよね。
料理がその精進料理なんで、いわゆる、すごくつくり込んだというより、素材の良さをそのまま生かすみたいな、ちょっとした味付けで、旬のものをその都度、おいしくいただくっていう。それを四季を通してやるので、春夏秋冬っていう風に、その中で松たか子さんが通ってくる中の人と人の関係性だったりとか、なかなか実は前に進めていなかったことが、そういう人と人とのつながりで、一歩前に踏み出せるようになるみたいなお話もあるんですけど。でも、やっぱりこれは全編通してとにかく食がすごくおいしそうで、土と共に暮らすとか、そういう本当はこうじゃなきゃねっていう。やっぱり簡単に料理できてしまうとかではなくて、ちゃんと手間ひま、苦労があって、肉体労働したうえで食べる、いただく食事のおいしさみたいな。そういうのをひっくるめて、やっぱりこういう暮らしいいよねって思えるけど、なかなかね、都会の人はできないみたいな。そういう羨ましさも込めて楽しめる作品かなと思います。あと、沢田研二さん。もともと、本当は志村けんさんが役として決まっていたんですけど、亡くなってしまったので、急遽それも友情があったとか、男気で引き受けたみたいな、そんなエピソードもある作品です。
有坂:ちょっと、次の最後の映画、紹介しづらくなっています(笑)。まずいなぁ。こんな品のいい映画、真逆のもの用意していたんだけど、大丈夫かなぁ。
渡辺:(笑)。いっちゃってください。
有坂:ちょっと紹介する前に言いますけど。
渡辺:言い訳ですか(笑)。
有坂:この映画は、観ないでください。観ないほうがいいと思います。まあ100人見たら99人ぐらいがもう嫌悪感を示して、一人が熱狂するタイプのカルト映画です。食べ物で言うと、スパゲティミートソース、1997年のアメリカ映画です。
有坂セレクト5.『ガンモ』
監督/ハーモニー・コリン,1997年,アメリカ,89分
渡辺:なるほど(笑)。
有坂:これは、あのハーモニー・コリンという、まあ、その時代のもうアンファンテリブルって呼ばれた、いわゆる「恐るべき子どもたち」と言われた若き天才です。彼は、もともとスケーターで、あの『KIDS』っていう映画がありました。写真家のラリー・クラークが監督した。で、『KIDS』で脚本を務めたのが、ハーモニー・コリン。
彼は、まだ普通にストリートでスケーターとして活動している中で、ラリー・クラークと出会って、脚本を書いて、その中で脚本として表現したものはあったけど、自分が監督をつくるならまったく違うものにチャレンジするということでつくったのが、この『ガンモ』になっています。『KIDS』に関していうと、物語は一応、起承転結はあるんですけど、この『ガンモ』は、竜巻で街が大変なことになってしまった、オハイオ州だったかな、小さな田舎町で竜巻が直撃して、もう街とか屋根が飛んじゃっていたりっていうローカルな場所に暮らす人たちの、これはスケッチみたいな映画になっています。日常のコラージュみたいな構成でできた映画なので、起承転結な物語っていうのは、はっきり言ってないんですね。だけど、出てくる人たちが、みんな微妙にちょっと嫌な感じというか、なんだろうな、でも、本当にこういう人たちって生きているんだろうなって思ってしまう。だから嫌だって思っているこっちにも問題があるのかなって感じるぐらい、すごくリアリティがある人間ばっかりが登場する、やばい映画です。この映画に出てくるスパゲティミートソースは、本当にもう観た人みんな、もう衝撃を受けてしまうような場面で出てきます。それが主人公、このうさぎの耳をつけた、この少年が実家暮らしなんですけど、お風呂でスパゲティを食べるんですけど、その湯船がめちゃくちゃ汚くて、お湯も泥水みたいなお湯で、そこになんかこう海外の映画とかに出てくるホテルの朝食を食べる、ベッドで朝食を食べるテーブルみたいなものを置いて、そこで彼はそんな汚いところでこうスパゲティを食べるんですけど、食べながらお母さんが髪の毛を洗っているっていう、謎なシーンなんですよ。髪洗っているから泡が入っちゃうし、よくこんな汚いところで食べられるなって観てる人は思うんですけど、でも、本当に初めて観る光景。それは映画の中のワンシーンとして表現されているんですけど、最初に話したとおり、本当にこのローカルなところに行くと、こういうふうにスパゲティ食べてる人いるんじゃないかなって思ってしまうぐらいのリアリティのある場面になっています。決して美味しそうには見えないんですけど、ただスパゲティミントソースをまったく違う角度から考えることができた。何を隠そう僕の中でベスト1の食べ物なので、そういう意味でも真似はしたくないけど、ミントソース食べるたびに『ガンモ』のあのシーンを思い出して、いい映画だったなっていう気持ちになるのも、あのシーンの特別なところかなと思います。とにかくこの映画は映像もカオスだし、使われてる音楽も童謡みたいなものもあれば、デスメタルが使われてたりとか、本当に理解をしたくても理解できない、ありのままの世界を受け止めて何を感じるかっていう、けっこうアートフィルムな作品となっています。たぶん配信とかでは観られないとは思うんですけど、本当に90年代の渋谷シネマライズでヒットした話題になった作品なので、勇気のある方は機会があったら、ぜひ観てみてください、以上です。
渡辺:これは確かに、スパゲティ出てきたけど、全然おいしそうじゃないっていう(笑)。
有坂:そう、だから、これYoutubeにその場面だけ動画があったかな。予告でもちらっと写っているので、予告をまず観るといいかもね。
──
有坂:ということで10本出そろいました。皆さん作品、かぶったものあったかな?まあ、王道で言えば、『かもめ食堂』とかね、『バベットの晩餐会』とか、『シェフ』とかね、まあ、過去に別テーマで紹介しているものも多かったので。
渡辺:そうなんだよね。
有坂:その辺は、今回は外してお届けしました。
有坂:じゃあ、最後に何か知らせがあれば。
渡辺:毎度、そのフィルマークスのリバイバル上映をやっていて、今ちょうどですね、『ショーン・オブ・ザ・デッド』っていう作品をやっています。
有坂:いいじゃん!
渡辺:10月いっぱいまでなんで、もうすぐ終わっちゃうんですけど、やっておりますのでぜひ。もともと日本公開していなかった。
有坂:そうそうしてない。
渡辺:それを一旦、5年前ぐらいに上映があって、それ以来、再上映という形になります。初の4K版上映となっているので、ゾンビもののコメディなので。サイモン・ペッグですね。『ミッション:インポッシブル』とかに出ているんですけど、あのなんていうんですかね、観ているだけで癒されるタイプのコメディ映画によく出ている人が出ておりますので、ぜひ観てみてください。これですね。
有坂:エドガー・ライト。あのなんだっけ車の……。
渡辺:『ベイビー・ドライバー』。
有坂:そう、『ベイビー・ドライバー』の監督だね。出世作。
有坂:じゃあ、僕からはイベントは今後も続くんですけど、先月と同じで、11月3日のテアトル蒲田のイベント。ぜひ、これは去年も開催した、かつて映画館だった場所を1日だけ復活させて行う9時間の大イベントです。で、短編10本立て、ライブ、トークショー、あとはZINEのマーケット、スナックあすかなどなど、あのけっこう盛りだくさんな企画でお届けするんですけども、9時間の中でのタイムテーブルは一切ありません。で、何時に何やろうかなっていうのも、なるべく僕も考えないで、その場のフィーリングでお届けしようと思ってます。本当に一生に1回レベルの映画体験ができることは間違いないと思います。上映作品と、あとそのZINEマーケット。映画のZINEをつくってくれるのも、すごいね、素晴らしい人たちが。
渡辺:そうですね。イラストレーターとかね。
有坂:そう、イラストレーターだと、坂内拓さんとか、斎藤さんとか、あと朝野ペコさん、他にも元バンドのCHAIのベーシストだったユウキさんとか、あの本当に面白い人たちがこの日のために映画のZINEをつくってくれますね。本人が販売するということで、けっこういいイベントになると思います。
ゲストとか、あと上映作品。10本中6本は今日発表しました。なので、その辺はちょっとインスタで見ていただいて、チケットも絶賛発売中なので、ぜひ遊びに来てください。9時間楽しみましょう!
──
有坂:はい、ということで、大丈夫ですか。もう次回は11月。
渡辺:そうね、もう今年も早いですね。
有坂:これからいよいよ秋本番。秋もなく冬という噂もありますが、みなさん体調には気をつけて、また来月お会いできることを楽しみにしています。では、今月の「ニューシネマ・ワンダーランド」は以上となります。遅い時間までありがとうございました!
渡辺:ありがとうございました! おやすみなさい!!
──

選者:キノ・イグルー(Kino Iglu)
体験としての映画の楽しさを伝え続けている、有坂塁さんと渡辺順也さんによるユニット。東京を拠点に、もみじ市での「テントえいがかん」をはじめ全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館など様々な空間で、世界各国の映画を上映。その活動で、新しい“映画”と“人”との出会いを量産中。
Instagram
キノ・イグルーイベント(@kinoiglu2003)
有坂 塁(@kinoiglu)/渡辺順也(@kinoiglu_junyawatanabe)

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店