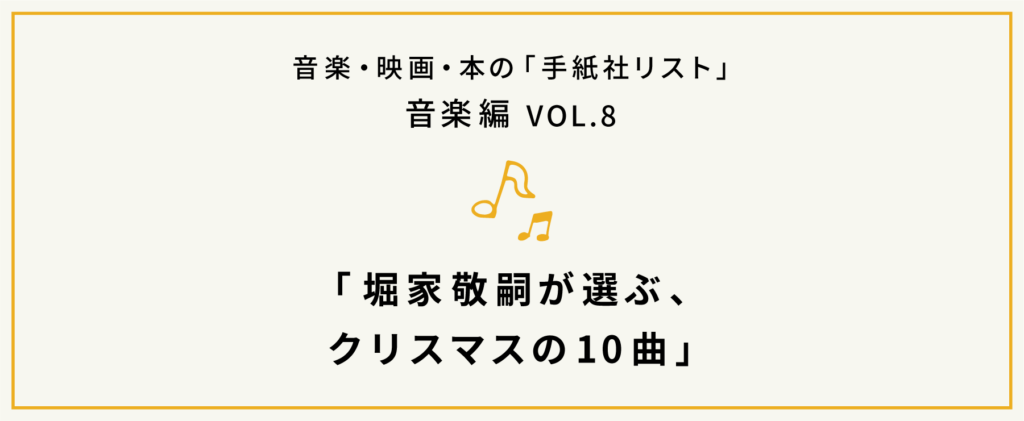
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。8回目となる音楽編のテーマは、「クリスマスとその周辺」。“聴くべき10曲”を選ぶのは、手紙社の部員たちに向けて毎月「歌謡曲の向こう側」という講義を行ってくれている、山口大学教授の堀家敬嗣さんです。自身もかつてバンドマンとして活動し、幅広いジャンルの音楽に精通する堀家教授の講義、さあ始まります!
聖なる夜の歌謡曲
[宗教行事]
日本においてクリスマスが祝福されたことを伝えるもっとも古い記録は、フランシスコ・ザビエルに領内での布教を許可した大内義隆の領地だったいまの山口市で、ザビエルの退去ののち1552年に催された降誕祭のものとされ、これをもって山口市はクリスマス発祥の地を謳ってもいます(*1)。そしてここでの歌ミサが、日本で披露された西洋の声楽として最古の記録でもあるようです(*2)。
要するに、日本が最初にそれらと遭遇した時点から、クリスマスと西洋式の音楽とはすでに密接な、ことによると相互補完的な関係にあったことになります。
それから450年以上の月日を経たこんにち、歌謡曲を代表するクリスマス・ソングを山下達郎による〈クリスマス・イブ〉(1983)と措定することに、おおむね異論はないでしょう。すでにある種のスタンダード・ナンバーと化したこの楽曲ですが、しかし当初はアルバム盤《Melodies》の最後を飾る収録曲として発表されたものでした。
日本の大衆音楽にあっては、クリスマスをめぐる楽曲をシングル曲として発売することを躊躇させる要因がいくつか考慮されます。
なによりもまず、それは宗教的な観点からの懸念でしょう。とりわけこの100年ほどのあいだに、ジャズをはじめさまざまな大衆音楽を西洋からほとんど時差なく輸入し、その消化と摂取を試みてきた歌謡曲は、けれど背景にある文化や社会をも理解したうえでこれらを採用してきたわけではありません。むしろ、日本の文化や社会に適合させるようにそれらを換骨奪胎するその手練手管にこそ、歌謡曲の矜持があったとさえいえます。
こうした矜持のもっとも先鋭的に実現された事例とは、おそらく大滝詠一の〈クリスマス音頭〉(1977)にちがいありません。アルバム盤を月めくりのカレンダーに見立てたうえで、ストリングスの編曲に山下達郎も参加したこの楽曲を各月に相当する12曲の最後に収録した《NIAGARA CALENDAR》は、ほかならないクリスマスの日に発表さました。
日本の人口における比率からすればけっして多くはないキリスト教徒を例外として、大勢を占める無節操にして寛容な歌謡曲の聴き手にとって、クリスマスとは、カレンダーの最後の紙面に設定された中身のない単なる催事です(*3)。音頭のリズムで笛に木魚や三味線にシャモジの打ち鳴らされ、おはやしが囃したてる演奏はもちろん、とりわけ大瀧詠一自身による歌詞の言葉は、その無節操な寛容さをよく表現しています(*4)。
「奇妙奇天裂」な「南蛮渡来」の「クリスマス」が、「何故かしらねど」日本に定着し、「商店街」も「ケーキ屋さん」も「テレビラジオ」も「夜のネオン街」も、全国を挙げて「晩から朝迄」これを祝います。それは「戦後変った」事情であって、「天下晴れて」ようやく「日本すみずみ」それを祝うことのできる状況となったのです。
とはいえ、その実態は「七面鳥食って飲んで騒」ぐ口実にすぎず、それどころか「カラ揚げ」であれ「カップうどん」であれ、「飲んで騒」げさえすれば、もはやなにを「食って」もかまわないわけです。こうした無節操な寛容さは、ほどなく「十二月はドサクサで 酒が飲めるぞ」と息巻くバラクーダの〈日本全国酒飲み音頭〉(1979)に要約されるものです(*5)。
ザビエルを援用しないまでも、幕末から明治初期にかけて日本に渡来した外国人に居留を認めた地域ではクリスマスの祝宴がもたれ、やがてキリスト教の解禁とともに日本人のなかにも少しずつそれは伝播していきます。たとえば、正岡子規が確立した俳句において、西洋からの外来語のなかでカタカナ表記によりはじめて季語として機能した言葉、それは、まさしく[クリスマス]の語でした(*6)。
明治の中期には、舶来の食料品などを扱う事業者として横浜で設立された明治屋が、洋菓子や洋酒といった舶来品の風味を宣伝する手段としてクリスマスに商機を見出し、また森永が洋菓子の製造を開始するなど、歳暮の時期に贈答の習慣のもと正当化される味覚的な贅沢の契機としてもそれは認知され、商戦として活発化していきます(*7)。
大正のころには児童向けの雑誌や少女雑誌の特集をとおしてその読者にクリスマスのイメージが流通し、その中核にはやはりサンタ・クロースがいました。さらに日本でもラジオ放送が開始された昭和の初期にかけては、クリスマスにあわせて特別番組が編成され、〈きよしこの夜〉など讃美歌が広く街に流れることになります(*8)。
[家庭行事]
それでもなお、これが西洋では主流の宗教を起源とする行事であることは、とりわけアメリカとの交戦に突入した困難のなかでは、クリスマスへの言及を容易ならざるものとせずにはいませんでした。
換言すれば、クリスマスは、封建主義的な家族制度のもとにではなく、物質主義的な豊かさをもって自由で民主的な思想の喧伝を達成するメディアとして、アメリカの進駐軍とともに日本の新しい家庭のもとに再びやってくるわけです。そこに宗教性は無用です。ここでの聖像とは、イエスでもマリアでもなく、敗戦国の貧しい子どもたちのために袋いっぱいの玩具を背負ったサンタ・クロースにちがいありません。
事実、たとえば終戦からほどなく、東京の駅頭に飾られるようになったクリスマス・ツリーについて、これを特定の宗教活動と批判する勢力に対して、運輸省は季節的な装飾のひとつとしてその宗教性を否定し、また小学校でクリスマスを催事化するにあたってその是非を問う声にも、東京都の教育庁は、これを宗教行為ではなく節分や七夕と同様の単なる季節的な行事とする通達で応じています(*9)。
戦後の出産ブームは団塊の世代を生み、特需景気がもたらした経済成長による都市部での生活基盤の安定は、土着的な文化や風土、さらには神式や仏式による宗教的な旧弊からの労働人口の流出に拍車をかけます。そうして頼る血縁の身近にいない核家族が郊外で維持しはじめた彼らだけの小規模な家庭では、親子の年間の奮闘をともに労うように、彼らのみで愉しむ慎ましやかなパーティーが用意されるわけです。
夕餉に母親が準備したチキンの唐揚げや仕事帰りの父親が購入してきた土産のケーキを囲んで親子の時間を満喫し、夢心地で就寝した聖夜の枕もとにプレゼントを貰う子どもたち。それが彼らへのご褒美であることはもちろん、そうした時間の共有や翌朝の枕もとを確認した彼らの笑顔こそは、ささやかな家庭の安寧を生きるよすがとする親たちへの贈りものにほかなりません。
不二家によるクリスマス・ケーキや、どこが発想したものともしれないブーツ型の容器に収まるお菓子の詰めあわせなどは、キリスト教に影響された文化には確認できない日本に独特の体裁であると指摘されてもいます(*10)。単に宗教的な由緒ばかりかクリスマスの雰囲気を構成する物質的な要素までが、その西洋的な風体を日本的に消化され、摂取されていったことになります。
これは、西洋の大衆音楽をめぐって歌謡曲が対処してきた仕方とほとんど均質です。そしてこのころに、石原裕次郎やハナ肇とクレイジー・キャッツ、坂本九やザ・ピーナッツなど当代を代表する綺羅星のごとき歌い手が、〈ホワイト・クリスマス〉や〈きよしこの夜〉、〈ジングル・ベル〉や〈サンタが町にやってくる〉、〈赤鼻のトナカイ〉といったクリスマスにまつわる歌曲を、日本語の翻訳詞のもとこぞって吹き込んでいました。
アルバム盤であれシングル盤であれ、いわば季節商品としての企画盤であったそれらは、クリスマスの雰囲気を煽り、これを愉しむことを促しながら、それ自身がクリスマスの贈りものとして、クリスマスの表象として、さらにはクリスマスそのものとして聴かれていたはずです。逆にいえば、冬に発売されるアルバム盤には、クリスマスを題材とした楽曲のひとつも収録しておくことがすなわち礼節なのかもしれません。
このように、ともすれば家庭的どころか所帯じみるほどの生活感がクリスマスには付随し、その限りにおいて、季節商品としての企画盤より以上の訴求効果をそこに期待することは困難だったわけです(*11)。
竹内まりやが歌唱した自作曲〈すてきなホリデイ〉(2001)は、「ママ」や「パパ」に加えて「犬や猫まで」、あるいは「テディベア」さえも、「クリスマスが今年もやって来る」この「すてきな季節」を「待ちきれ」ないようです。ただしここでのそれは、「心に住むサンタ」とともに「思い出」されるべき「幼い頃の夢」のことにちがいありません。「今年もやって来る」のは、もはや「サンタ」ではなく、あくまでも「クリスマス」なのです。
歌詞の言葉における「holidays」の表記とは明確に区別された題名における「ホリデイ」のカタカナ表記は、[holy day]の古語に由来する[holiday]の語に継がれた宗教的な語感を濾過することに貢献します。この楽曲もやはり、シングル盤として発売される以前に《Bon Appetit!》に収録された楽曲でしたが、このアルバム盤のプロデュースは山下達郎が担当しました。
[12月25日]
こうした観点からクリスマスを題材に扱ったシングル盤には、たとえば浜田雅功と槇原敬之による〈チキンライス〉(2004)があります。
「お祭り騒ぎ」で「にぎやか」な「クリスマス」の「今日」になっても、「親の顔色を気にし」たり「親に気を使っていた」ころの「あれだけ貧乏だった」自分の「昔話」を「語」るなか、作詞を担当した松本人志は、「家族」たちの「酸っぱい湯気が立ちこめる向こう」に「見えた笑顔」が「忘れられ」ません。
「今ならなんだって注文できる」にちがいない彼は、「赤坂プリンス」や「七面鳥」を試してみようとするものの、「やっぱり俺はチキンライスがいい」と結論します。「好き」勝手に「なんでもたの」んでみたそれらは、けれど「家族」の「笑顔」に、「俺」に固有の思い出につながっていないからです。そしていまこそ「俺」は、「チキンライス」が惹起する所帯じみた味わいに、とうに回復することのできない失われた時間の豊穣を、あの幸福の感覚を慈しむのです。
要するに、竹内まりやの〈すてきなホリデイ〉にせよ浜田雅功と槇原敬之の〈チキンライス〉にせよ、そこでクリスマスのものとして期待される光景とは、かつて子どものころに親と愉しくすごした、家庭の日常からすればわずかばかり贅沢な体験の思い出にほかなりません。換言すれば、それは大人へと成長した彼らからすでに喪失された過去であり、クリスマスとは、毎年の暮れにこうした思い出を彼らのもとに忘れることなく贈り届けてくれる符牒的な索引なのです。
家庭行事としてのクリスマスのありようは、このように過去の思い出として懐かしまれる場合にのみ積極的に謳われます。その所帯じみた気配は、あくまでも郷愁のなかを漂泊しつづけているわけです。
核家族のための、高度経済成長期における家庭のためのささやかで慎ましやかな愉しみとしてのクリスマスのこうした身分を、愛おしくも懐かしまれるべき過去の思い出へと変容させたのは、「となりのおしゃれなおねえさん」が「クリスマスの日」に「私に云った」言葉です。
松任谷由実のアルバム盤《SURF&SNOW》に収録された〈恋人がサンタクロース〉(1980)では、もう「私」は「サンタ」が「絵本だけのおはなし」なのだと悟っていました。彼女はすでに「サンタクロース」の正体を見透かしていたのです。
にもかかわらず、「となりのおしゃれなおねえさん」は、家庭のなかで消費されるものとは異なる新しいクリスマスの、新しい「本当」の「サンタクロース」の身分について、いつか「大人になれば」きっと「あなたもわかる」ことと示唆します。ここで「おねえさん」が「クリスマスの日」に「となり」から「私の家」に介入してきたことは、だから相応に重要です。
そしてついに「明日になれば」、「大人にな」った「私の家に来」る「サンタクロース」が、この「家」から、家族のもとから「遠い街へと」彼女を「つれて行」き、「恋人」と「私」とのふたりの時間がここからはじまることになります(*12)。
「恋人」と「サンタクロース」を接合する助詞を係助詞[は]とせず、格助詞[が]をもって「恋人がサンタクロース」と歌われたことのうちに、ここでのクリスマスのなんたるかが端的に表現されています。そうして所帯じみた家庭の気配は払拭され、クリスマスの意味が刷新されたとみて無理はないでしょう。
ところで、クリスマスにまつわる歌曲の吹き込まれたレコード盤が、季節商品としての企画盤のかたちで流通していたことは、日本の大衆音楽において、クリスマスをめぐる楽曲がシングル曲として発売されることを躊躇させる要因のひとつを、きわめて率直に吐露してもいます。それは、クリスマスが神の御子の降誕を祝福するものであり、つまりはその誕生日となる12月25日のための祝宴であるという事実です。
12月25日を越えて残ったクリスマス・ケーキが半額で叩き売られるように、仮にクリスマスに取材した場合には、そのシングル盤もまた、クリスマスの祝宴ののちにはたちまち叩き売られずにはいないのです。
[師走]
シングル盤として発表された稲垣潤一の〈クリスマスキャロルの頃には〉(1992)において、「クリスマスキャロル」の「流れる頃」まで先送りされた「君と僕」をめぐる問いは、どうあってもクリスマスの翌日にはその「答え」は導かれているはずです。
そうして「ラジオからのクリスマスソング」が聞かれるあたりから、「クリスマスまでに」どうにか「間に合うように」と「あなた」を「待っている」広瀬香美の〈DEAR…again〉(1996)に至っては、楽曲の効用はいかにも短いものです。
封建主義的な家族制度のもとにではなく、物質主義的な豊かさをもって自由で民主的な思想の喧伝を達成するメディアとして、進駐軍の旗頭に導かれ日本の新しい家庭へと再来したクリスマスは、団塊の世代の子どもたちの成長に同調して成熟していきます。やがて彼らが大人になるころには、それは消費社会における商業主義の雛型として市場を開拓し、需要を、欲望を喚起しながら、本来の宗教性はいったん脱色されたはずが、今度はある種の非精神的すなわち物神的な宗教性を獲得するまでに至ります。
2月14日のバレンタインデーが、10月31日のハロウィンが、そしてもちろん正月やひな祭り、端午の節句や七五三といった旧来の催事もやはりこの雛型を応用しながら、まんじりともせず商機をうかがっています。ハロウィンが終わり11月の声を聞くとともに、街角の陳列窓ではたとえば感謝祭などに秋波を送りつつも、機のないとみるやただちにクリスマスの装いへと鞍替えし、いっそうの消費を促す契機となります。
こうしたなか、クリスマスを題材に扱った歌謡曲などは、まぎれもなく季節商品なのであって、それ自身がクリスマスの贈りものとして、クリスマスの表象として、さらにはクリスマスそのものとして歓待される一方で、聖夜には賞味期限を、降誕日には消費期限を迎え、ここまであれほど聴き手を高揚させてきたその風味は、歳末の名のもとたちまち損なわれてしまうのです。要するに、歌謡曲がクリスマスを謳うことは、その商機をおのずと限定することにほかなりません。
その旬は短期間であり、単にアルバム盤を構成する楽曲のひとつとしてなら季節の彩りと効果的に聴かれうるでしょう。むしろ冬のアルバム盤には、クリスマスを題材とした楽曲のひとつも収録しておいたほうが気が利いているというものを、これをシングル盤として発表するとなると、いかにもそれは躊躇されるところです。この限りにおいて、歌謡曲は、もっぱらシングル盤については、その歌詞のなかで聖夜や降誕祭に直接的に言及することを回避する傾向に陥ったとしても不思議はありません。
〈夜空ノムコウ〉(1998)のシングル盤は、8cmCDの規格で発売されました。短冊型のパッケージにそった縦長のジャケットにおいて、大半を占める黒い夜空がメンバーの上半身像を画面の底辺に追いやったデザイン面の都合からか、「ノムコウ」の表記に共鳴させつつ、白抜きの文字による縦書きのカタカナで歌唱者名が「スマップ」と綴られています。
スガシカオが担当したこの楽曲の歌詞には、クリスマスをうかがわせる言葉は微塵もありません。そこではわずかに、「マドをそっと開けてみ」れば「冬の風のにおいがし」たり、「タメ息」が「少しだけ 白く残ってすぐ消え」るばかりです。
1月に発売されたこのシングル曲が冬の情緒に訴える傑作であることは疑いないところでしょう。それでもなお、この楽曲からは、「冬の風のにおい」のなかにクリスマスの雰囲気を嗅ぎとることができます。あるいはむしろ、この「冬の風のにおい」は、晩秋から早春までを覆って広がる「雲のない星空」にその粒子を遍在させているのかもしれません。
たとえば、この録音の冒頭で聞こえる雑踏の音のなかにナイロン弦のギターを招くように、バー・チャイムの緩やかなグリッサンド奏法による煌めきが重なるとき、そこには師走のにぎわいがもたらされます。
[聴覚的な語彙]
これもアルバム収録曲になりますが、吉田美奈子が発表した《LIGHT’N UP》の〈頬に夜の灯〉(1982)では、「灯ともし頃」に「街もはなや」ぐなか、そこで「擦れ違う人」たちもまた、「夜に飾られ」たクリスマスの電飾を思わせる「色とりどり」の「輝く灯に頬を染め」ずにはいません。そんな「夜の街」に、彼女は「一番好きなあなたの為」に「愛をおくろう」とします。
こうした歌詞の言葉を前提としつつ、とりわけサビのフレーズがいくたびとなく繰り返されるそのエンディングでは、やがてゴスペルを想起させるコーラスが主旋律に絡んで前景化し、消費社会の華やかな聖夜を、活気づく街の光景の高揚そのものを讃美する福音のように聞こえてきます。
松田聖子が〈恋人がサンタクロース〉をカヴァーしたのも、クリスマスのための企画アルバム《金色のリボン》(1982)でのことでした。他方で、すでに彼女が発表していた《風立ちぬ》には〈December Morning〉(1981)が収録されています。
ある12月の朝の「目覚め」からはじめるこの楽曲の歌詞において、松本隆は、クリスマスにまつわる記号をほとんどなにも提示していません。あえていえば、「風花」の「サラサラ」と「舞う」12月の「銀世界」に「スキー」で「シュプール」を描く「あなた」の「目印」として、「真っ赤なジャケット」を彼に着せることによって、その姿にサンタ・クロースの幻影を反映させ、〈恋人がサンタクロース〉における世界観への同調は認められるでしょう。
しかしながら、12月を謳ってなおクリスマスを象る語彙をまとわないそこには、聖夜へと傾斜する華やかな活気や騒々しい躍動性を感知することはできません。それどころか、この「目覚め」とは、そうした扇情的な強迫観念による抑圧から解放された静寂のもと浸透してくるような、夢とも現ともつかない輪郭の曖昧な体験です。
このことは、現実の空間のありようを覆って「銀世界」へと変換した「雪」が、あわせて音の反響をも吸収し、単に視覚からのみならず聴覚からも景色の気配が奪われてしまったときのあの所在ない感覚、「雪」に埋もれ閉ざされたことの諦念にも似た、身体の重みをはぐらかす脱力的な浮遊感と無縁ではないはずです。「真っ白な物語」とはそうした謂にちがいありません。
クリスマスの高揚をすごしたあとの疲弊のごとき無響空間におけるこの所在なき浮遊は、「サラサラ」と「舞」っている「風花」の不安定さそのものです。そしてそれゆえに、ここでの「目覚め」は、ひとつの年がまた暮れようとしていることのとりとめなき寂寞に親和的なのです。
〈December Morning〉に「舞」った「風花」は、あたり一面を「銀世界」として音響的な景観をも奪いました。この限りにおいて、仮に「雪」さえ積もらなければ、クリスマスを象る言語的な語彙が駆使されずとも、いわばクリスマスを象る聴覚的な語彙がここまで響いてきたかもしれません。
たとえば、ゴスペルを思わせた〈頬に夜の灯〉でのコーラスの採用などは、歌謡曲に対してきわめて直接的にクリスマスの装いをもたらします。
堀ちえみの冬のアルバム盤《雪のコンチェルト》で最後を飾る〈12月の祈り〉(1983)では、その冒頭でどこからともなく〈牧人ひつじを〉の合唱が聞こえてきます。そののち、ストリングスによる8小節の前奏に促されて歌唱をはじめた堀ちえみの歌声が、「樅の木と窓灯り」につづけて「教会の讃美歌」の語句を羅列し、いつのまにか「夕暮れ」た「12月の街」を描写するとき、いましがた聴いたばかりの〈牧人ひつじを〉が、あたかもこの「街」角の「教会」から漏出してきたもののように感じられます。
山下達郎の〈クリスマス・イブ〉についても、教会のオルガン奏者だったパッヘルベルの〈カノン〉をその間奏に引用し、しかもこれが彼ひとりの声で多重録音された無伴奏合唱のかたちで提示されたことは、現代の日本にクリスマスのありようを謳う讃美歌としてこの楽曲を規定するひとつの大きな要因となるでしょう。
細野晴臣や高橋幸宏、大貫妙子や伊藤銀次、ムーンライダーズらが参加した企画盤《WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS》のなかで、〈降誕節〉(1983)の名のもとに、戸川純は讃美歌〈荒野の果てに〉を味わい深くカヴァーしています。
[金色の煌めき]
つまるところ、クリスマスの雰囲気を、いわばクリスマスらしさを記号的に表現するいくつかの類いの音声があって、まさしくクリスマスを象る聴覚的な語彙として歌謡曲がそれらを援用する場合、そこではきわめて容易に、あるいはむしろきわめて安易に、クリスマスは音響をもって出来します。讃美歌や聖歌を含む教会音楽の響きは、日本では本来の宗教性はかなりの程度まで脱色され、希薄化しています。だからこそ、無節操にして寛容な歌謡曲の聴き手にとっては、かえってそれ自体がクリスマスの季節感を強調するものとなるのです。
単に声楽のみならず、オルガンの音からもそうした教会音楽の趣きは浸透してきます。〈クリスマス音頭〉の大瀧詠一は、その導入部で〈きよしこの夜〉を奏でる柔らかいオルガンの音に硬い靴音を重ね、扉が開く軋みとともにオルガンの音量を増大させることで、聴き手を教会の集いに招いてみせます。
再度の〈きよしこの夜〉の演奏が消えてこのアルバムの終了を打刻するのは除夜の鐘の鈍い音ですが、それはさておき、教会の鐘楼から街に降りてくる鐘の音、視認性の悪い吹雪のなかでも聴覚的に橇の通行を予告できるトナカイの首もとの鈴の音など、いわゆる金属質の鳴りものの鋭く煌びやかな響きは、クリスマスの雰囲気を容易に演出します。これを金色の煌めきといっていいかもしれません。竹内まりやの〈すてきなホリデイ〉などは、それが聞かれる典型でしょう。
「耳元」で「囁」くような音響処理を介して、讃美歌や聖歌ではなく自らの歌声こそが「天使の歌声」たらんと主張しながら、the brilliant greenによる〈angel song -イヴの鐘-〉(2000)の歌詞では、松田聖子の〈December Morning〉に「風花」と「舞」ったものを「天使」の「羽雪」に見立てつつ、「聖なる星の下」に「イヴの鐘」が、「天使の鐘が響」いて「X’masを告げる」とされています。
けれど実際には、この楽曲において聴覚的な語彙として確認できる音声とは、オルガンのそれがあるのみです。しかもこれも、発音のための大規模なパイプを備えた教会の楽器による響きとは異なり、ほとんど残響効果を排除され、「この耳元」で「囁」かれたように鼓膜に届きます。輪郭の鋭く歪んだエレクトリック・ギターの音色は、なるほど金属質ではあれ、クリスマスを祝うにはあまりにも鋭利で、鼓膜を切らんばかりに耳に刺さってきます。
その終盤では、ドラムスの独奏のあと、タンバリンの音色が3連のリズムを強調してきますが、ここにも当初はなかったはずの残響効果が施されるやいなや、吹雪のごときエレクトリック・ギターの歪みの過当さに埋没してしまいます。
〈牧人ひつじを〉を「教会の讃美歌」と聞いて開かれた堀ちえみの〈12月の祈り〉も、ただしこちらはいかにも教会に設置されているようなオルガンの響きをもって閉じられるとともに、鈴の音からはじまったアルバム盤《雪のコンチェルト》も終わります。
菊池桃子が「白いクリスマスイヴ」に「遠い教会の鐘の音」や「古いオルガンが聞こえる」と歌唱した〈雪にかいたLOVE LETTER〉(1984)は、まぎれもなくシングル盤として発売されたものです。しかし秋元康によるこうした歌詞の言葉を聴覚的になぞる音響は、ここではほとんど奏でられません。これについては、言語的な語彙に比して音響的な語彙がより直接的に鼓膜を刺激するために旬の鮮度に左右されやすく、それを編曲の林哲司が懸念した結果とも邪推できます。
稲垣潤一の〈クリスマスキャロルの頃には〉も同じく秋元康の作詞でした。ここでは「クリスマスキャロル」の「流れる頃」を先送りした設定もあってか、シンセサイザーの音色の選択にわずかに煌びやかさが意図されているものの、それでもやはりクリスマスを象る音響的な語彙というにはそれはあまりに貧しい響きです。
こうした事例を考慮するとき、dip in the poolがシングル盤として発表した〈Miracle Play・天使が降る夜〉(1987)の潔さは感動的でさえあります。
なによりもまず、ここには「メリークリスマス」と重ねて告げる言語的な語彙はもちろん、クリスマスを象る音響的な語彙がそれ以上に充満しています。鐘、鈴、オルガン、子どもの歌声…。その過剰さは、単にクリスマスを祝うためばかりか、ハープもティンパニーもヴァイオリンの弦をつまんで弾くピチカート奏法も、あわせてすべてが天上の調べのようにすら感じられます。
[肥大化する泡]
〈Miracle Play・天使が降る夜〉は、バブル経済の権化として、そのただなかに債務を背負わせてまでも若者に消費を煽ったあの“赤いカード”の丸井のCMに採用されました。それ自体があくまでも最適の季節商品たることに徹したうえで、季節をまるごと汲み尽くさんと謳うとき、拝金主義的な消費文化へのこの積極的な加担をもって、当の楽曲はいまなお蕩尽されない名曲となります。
なるほど、聖夜が明けて降誕祭をすごしたからには、その旬はたちどころに消失します。クリスマスの魔力は払底し、あとには新年の寿ぎが準備されるばかりです。
にもかかわらず、もう1年もしないうちに、クリスマスはまたやってきます。今年のカレンダーは残り1週間しかありません。でも来年のカレンダーの最後の月には、まちがいなく25日の印字があります。その次の年も、また次の年も、鈴や鐘の音色とともにきまってクリスマスはやってくるのです。そしてその都度、こうした季節商品の需要も確実に到来するわけです。
この繰り返しをもっていくつものクリスマス・ソングがスタンダード化してきたのであって、歌謡曲においてもついに山下達郎の〈クリスマス・イブ〉がそうした扱いを供されるに至ったのは、JR東海の新幹線のためのこの時期のキャンペーンCMが1988年にはじまり、毎年の恒例となってこの楽曲がそこに継続的に採用されたからにほかなりません。
家庭のものだったクリスマスを恋人たちのもとへと「つれて行」き、その身分を恋愛模様の現場へと転向させた松任谷由実の〈恋人がサンタクロース〉もまた、原田知世の主演による映画『私をスキーに連れてって』(1987)の挿入歌となることで、それまでは巧みに隠蔽してきた「本当」の欲望を露呈させます。
宮沢りえが起用された1988年の西武百貨店のポスターに「ほしいものが、ほしいわ」と謳ったコピーは、糸井重里のものでした。いままさに欲しいそれを手に入れたいという欲望と、そうした尋常な消費性向を超えて、欲しいものを入手し尽くしたうえでなお充足されない欲望が、さらに欲しいと思えるようななにかを欲すること、要するに欲望そのものを欲望すること。
いまやこうしたバブル経済のただなかでは、恋人たちの恋愛模様それ自身までが消費の、蕩尽の対象として照準されます(*13)。この限りにおいて、その「昔」、「私」の家庭の「クリスマス」に介入して「ウインクし」た「となりのおしゃれなおねえさん」とは、欲望の蕩尽を徹底的に肯定し、これを美徳とする肥大化した消費社会の謂にほかなりません。なるほど、そこでは「サンタクロース」は「プレゼントをかかえて」きますが、このとき彼が背負っていたのは、白い袋ではなく白い泡であり、すなわち「プレゼント」を仕立てるための債務だったわけです。
dip in the poolによる〈Miracle Play・天使が降る夜〉の潔さは、これがシングル盤として発表されたこと、にもかかわらずクリスマスを象る音響的な語彙が充満していること、そしてバブル経済のただなかで拝金主義的な消費文化への積極的な加担を微塵も躊躇しなかったことにあります。したがって、これを歌唱した甲田益也子こそは、「ウインクし」た「となりのおしゃれなおねえさん」の配役に真にふさわしい奇蹟劇の演者であり、その実体をうかがわせない存在性の空疎さとあいまって、まさしくバブルの申し子といえるかもしれません。
浪費が欲望を蕩尽し、ひいては欲望そのものが欲望されるような強迫観念の時代には、単なる季節商品の消費を促すばかりではたかがしれています。誰のものでもない季節のありようを、いわば季節それ自体を、まるでわがものと支配したかのように要約してみせ、これをまるごと「ほしいもの」と錯覚させること、その幻想を消費させること、それこそがバブル経済の泡たる所以です。
こうした状況にあっては、もはや誰もがクリスマスの消費だけに飽くはずもなく、たとえば杉真理の《LADIES&GENTLEMEN》に収録された〈クリスマスのウェディング〉(1989)では、ついに「イヴの日のWedding day」を迎えることになります。もちろんこの「X’masのWedding day」において、「X’mas」と「Wedding」の仲をとりもったのはまぎれもなく「教会」ですが、そこにキリスト教の教義が入り込む余地は残されていません。
[騙られたクリスマス]
クリスマスを題材とするシングル曲がヒットし、たとえば歳末どころか年が明けてなおこれをテレビのチャート番組で歌唱せざるをえないような事態は、歌い手にとっても聴き手にとってもそれこそ興醒めというものです。実際、幸か不幸かその余韻を新年まで繰り越し、初春の『ザ・ベストテン』でも〈雪にかいたLOVE LETTER〉を披露する機会を持ちあわせた菊池桃子は、本来なら台詞のように「……メリー クリスマス」と囁くべきフレーズを、そのときには「……ハッピーニューイヤー」に変換して寿いでみせました(*14)。
しかしながら、この事実は、クリスマスの旬をめぐる逸話であるというよりも、むしろ歌謡曲におけるシングル盤の旬をめぐる挿話であるように思われます。シングル盤の場合とは必ずしも一致しない流通原理のなか、必ずしも一致しない聴き手によって、必ずしも一致しない態度のもと消費されるアルバム盤とその楽曲においては、クリスマスの旬の短さは、場合によっては季節を彩る構成要素のひとつとして相対化され、効果的に聴かれうるだろうからです。冬に聴かれるアルバム盤では、クリスマスを謳う楽曲のひとつも収録しておいたほうが、その全体をとおした物語性の起伏を演出しやすくもなるわけです。
だからこそ、カレンダーがめくられ、旬を経過して売れ残ったケーキを値崩れさせていく均質な時間の冷徹さの外側で、〈頬に夜の灯〉が「時をそのまま」で「止められたら」と願うことも、〈クリスマスのウェディング〉では「教会の時計」が「今夜はStop」してしまうことも許されています。菊池桃子に新年を寿がせたシングル盤の流通原理は、ここでは機能しないか、またはその干渉の度合いを著しく低下させずにはいないのです。
いずれにしても、この時期を象徴する商材としてのクリスマスの通念は、歌謡曲の聴き手である私たちにも共有されています。そしてこのことは、聴き手の側にある種の先入観がかたちづくられるだろうことを意味します。
《夢ひとつ蜃気楼》に収録された松本伊代の〈赤いリボンのプレゼント〉(1983)は、「冬の海岸」が舞台です。ここで「わたし」は、「髪の乱れ」などを「気にする帰り道」に、「言葉に出来ない愛」の「つめこ」まれた「赤いリボンのプレゼント」を「あなた」に「あげた」くなります。
ところでこの「冬」の「プレゼント」は、その「リボン」の「赤」さとともに、クリスマスを祝うものとみえて、実際には歌詞の最後を括る語句に「Happy Birthday」と歌唱されることによって、聴き手の側が抱きえたクリスマスへの期待は裏切られます。しかもこれを「あなた」の誕生日ではなくあくまでも「Happy Birthday To Me」とするとき、ここでの「プレゼント」はすでに誕生日を祝うものでさえないのか、もしくは誕生日を迎えた「わたし」からその記念に「あなた」に贈るものとする趣旨なのか、事情はいよいよ混沌としてきます。
詞曲を担当した遠藤京子の意図はさておき、この「プレゼント」をクリスマスのものと偽装し、「Happy Birthday」を告げるまでわたしたちを欺きおおせた因子としては、歌詞の言葉のほか、Ⅰ−ⅤonⅦ−Ⅵm7−Ⅴ6と推移する山下達郎の〈クリスマス・イブ〉のAパートにおける冒頭の4小節のコード進行、すなわちパッヘルベルの〈カノン〉のそれと、この楽曲のAパートにおける冒頭の4小節のコード進行とがほとんど同一であり、しかも調性までが共通のイ長調を採用していることが関与しているかもしれません。
なお、このアルバムの最終曲として収録され、松本伊代の自作と謳う〈For You, Christmas〉(1983)では、「朝から」ひとり「ソワソワ」と逡巡のすえに、ついに「私」は「あなたと2人のクリスマス」に「ピンクのリボンのプレゼント」を渡そうと決心します。その「プレゼント」とは、ほかでもない「ピンクのリボンをつけた」この「私」、つまり「Iyo」本人のことです。
伊藤つかさの〈クリーム星人〉(1984)も、そのアルバム《OSUSUME》に収録された楽曲です。ここでは「雪」に覆われたものか、「白い車が走」っている「白い壁の街」は「クリームの街」にたとえられ、それは「クリームの冬がトロリ」と「とけるような甘い日」となります。「クリームの雲が フワリ」と浮かび、「クリームの雪が チラリ」と舞うそこは、もはや「地球」ではありません。
「ビル」を「ケーキ」に、「歩く人」を「キャンドル」に見立てながら、こうして〈クリーム星人〉となった「2人」が「手をつな」ぎ「火をともしてゆ」くこの「とけるような甘い日」も、クリスマスではなく「2人の誕生会」のこととされます。
[クリスマスの夏]
クリスマスを象る聴覚的な語彙があり、またクリスマスの風情をもたらすコード進行があるとして、それでは特定のリズムをもってクリスマスを想起させることは可能でしょうか。
おそらくそうしたリズムの存在を確言することは困難でしょう。クリスマスに限らず、冬の季節感をなにがしかのリズムに求めることは容易ではありません。
ところが、少なくとも夏に似合いのリズム、もしくは夏に聴きたいリズムならば、いくつかのものが該当するように思われます。たとえば、激しいサンバや気怠いボサノヴァ、軽やかなスカや憂鬱なレゲエなどがそれです。これらのリズムが夏を想起させるとすれば、きっとそれは、発祥の地となるブラジルやジャマイカの赤道に近い土地柄、その気候風土に因むものでしょう。
佐野元春の〈CHRISTMAS TIME IN BLUE 聖なる夜に口笛吹いて〉(1985)は、こうした臆見の意表をつくように、クリスマスを題材とした楽曲にレゲエのリズムを採用しました。クリスマスとレゲエのあいだの齟齬は、当たり前の時間が当たり前にすぎていくことの奇蹟に対する感謝と懐疑のあいだの齟齬を仄めかします。
事実、ジョン・レノンとオノ・ヨーコによる〈Happy Xmas (War Is Over)〉(1971)の姿勢に共感を示す一方で、ただし「War Is Over」を謳い「Let’s stop all the fight」と訴える素朴さからすればどれほどか冷笑的に、「平和な街」にであれ「闘ってる街」にであれ、「このままで」も「かまわない」からとにかく「メリー・クリスマス」を願う今夜とは、まさに「Christmas Time In Blue」たらざるをえません。
KUWATA BANDの名義による〈スキップ・ビート〉(1986)の「Rock Café」では、ほかでもない「Lennonが流れ」ていましたが、やはりKUWATA BANDの名義によりこれと同時に発表された〈MERRY X’MAS IN SUMMER〉(1986)もまた、レゲエのリズムにクリスマスの題材を委ねた楽曲でした。
冬にクリスマスを迎える北半球とは異なり、南半球ではクリスマスは夏に訪れます。年間を四季ではなく乾季と雨季とが構成するジャマイカなどでは、これをあえて冬だの夏だのと味わう気質すら成立しないはずです。
しかし〈MERRY X’MAS IN SUMMER〉では、レゲエのリズムを介することによって、むしろ季節の側がクリスマスへと浸透していきます。いわばそれは、夏のクリスマスではなく、クリスマスの夏です。それはクリスマスに、クリスマスのために到来した夏なのです。だからこそ、レゲエのリズムのもとではあっても、パッヘルベルの〈カノン〉のものと代替の可能なⅠ−Ⅲm7−Ⅵm7−Ⅲm7のコード進行が、ここでもAパートにおける冒頭の4小節で響いています。
ところで、桑田佳祐の詞曲によるものとしては、KUWATA BANDでの活動に限らずサザンオールスターズや桑田個人の名義でも、クリスマスを題材とする楽曲が多く発表されています。サザンオールスターズ初期のシングル盤〈シャ・ラ・ラ〉(1980)や、《世に万葉の花が咲くなり》に収録された〈CHRISTMAS TIME FOREVER〉(1992)、これとともに連続して丸井のCMに使用された〈クリスマス・ラブ (涙のあとには白い雪が降る)〉(1993)、そして〈白い恋人達〉(2001)などがそれです。
〈MERRY X’MAS IN SUMMER〉におけるⅠ−Ⅲm7−Ⅵm7−Ⅲm7のコード進行は、〈シャ・ラ・ラ〉でもⅠ−Ⅲm7−Ⅵm−Ⅵm7onⅤとして変奏されます。これが〈CHRISTMAS TIME FOREVER〉や〈クリスマス・ラブ (涙のあとには白い雪が降る)〉の場合には、4小節が2小節に圧縮され、Ⅰ/ⅤonⅦ−Ⅵm /Ⅵm7onⅤないしはⅠ/ⅠonⅦ−Ⅵm7 /ⅠonⅤとなって応用されます。〈白い恋人達〉も、Aパートの途中で1拍ごとに変化するコードの流れのうちにその響きを組み込んでいます。
それどころか、桑田佳祐は、これに類するコード進行をクリスマスを参照することなく多用し、その事例の枚挙には暇がありません(*15)。
〈Ya Ya あの時代を忘れない。〉(1982)や〈Bye Bye My Love (U are the one)〉(1985)をはじめ、〈BAN BAN BAN〉(1986)にせよ〈真夏の果実〉(1990)や〈涙のキッス〉(1992)にせよ、さらには〈TSUNAMI〉(2000)に至るまで、その代表作がいくつも、とりわけAパートの冒頭でⅠ−Ⅲm7−Ⅵm7−Ⅲm7の展開に基礎づけられ、これに準じるようなコード進行のなかで主旋律を相対化することになります。
いまや明らかなように、私たちはすでに40余年にわたり、日本の大衆音楽における桑田佳祐の業績の全体をとおして、冬といわず夏といわずそこにクリスマスを消費しつづけてきたにちがいないのです。
*1 日本のクリスマスは山口から実行委員会,「12月、山口はクリスマス市になる。」(http://www.xmas-city.jp/#), 山口商工会議所, 2020.
宗教統計調査」, 文化庁宗務課, 2020.
*2 クラウス・クラハト+克美・タテノクラハト,『クリスマス―どうやって日本に定着したか』, 角川書店, 1999, pp.16-19.
*3 「宗教統計調査」, 文化庁宗務課, 2020.
*4 大石始,『日本大音頭時代―「東京音頭」から始まる流行音楽のかたち』, 河出書房新社, 2015, pp.146-151.
*5 同書, pp.165-166.
*6 クラハト+タテノクラハト, 前掲書, pp.80-82.
*7 同書, pp.84-102.
*8 同書, pp.115-116.およびpp.133-134.
*9 同書, pp.176-182.
*10 同書, pp.188-190.
*11 ヴェルトナー・トゥースヴァルトナー,『「きよしこの夜」物語』, 大塚仁子/訳, アルファベータ, 2005, pp.173-175.
*12 酒井順子,『ユーミンの罪』, 講談社(講談社現代新書), 2013, pp.102-106.
*13 松任谷正隆,『僕の音楽キャリア全部話します』, 新潮社, 2016, pp.102-105.
*14 「アイドルが歌うクリスマスソングの先駆け(ザ・ベストテン「今月のスポットライト」第6回)」(https://www.uta-net.com/user/timemachine/best10/1511index.html), 『Uta-Net』所収, ページワン, 2015.
*15 スージー鈴木,『サザンオールスターズ 1978-1985』, 新潮社(新潮新書), 2017, p.249.
堀家教授による「私のクリスマス」10選
1.〈クリスマス音頭〉大滝詠一(1977)
作詞・作曲/大瀧詠一,編曲/多羅尾伴内
1枚のアルバムをカレンダーに見立てた《NIAGARA CALENDAR》に12月の曲として収録。ストリングスの編曲は山下達郎。日本の大衆歌謡におけるダンス・ミュージックとして音頭を評価した大瀧による、革新的な概念形成の一翼を担う楽曲。〈ナイアガラ音頭〉を端緒にここから《LET’S ONDO AGAIN》へと展開され、ついに金沢明子の〈イエロー・サブマリン音頭〉では萩原哲晶も招かれる。
2.〈安奈〉甲斐バンド(1979)
作詞・作曲/甲斐よしひろ,編曲/甲斐バンド
間奏におけるヴァイオリンの独奏部は、あがた森魚の〈赤色エレジー〉やかぐや姫の〈神田川〉、グレープの〈精霊流し〉などの系譜に連なり、また歌詞における「夜汽車」の語句はチューリップの〈心の旅〉を想起させる。こうした観点からすれば、1970年代の若者たちのメンタリティを表現した最後期の楽曲のひとつとして、その響きは四畳半フォークならぬ四畳半ロックとでも形容されるべきものだろう。北海道で生まれたあがたを除き、みな九州の出身であることも、この時代までの日本社会のありようやそこでのクリスマスの記号性と無関係ではいられない。
3.〈降誕節〉戸川純(1983)
作詞・作曲/不明,編曲/国本佳宏
高橋幸宏と高橋信之が兄弟で企画したクリスマスのためのオムニバス盤《WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS》に収録。戸川の歌唱における純粋を装った禍々しさ、作為を騙る無邪気さは、聴くものの鼓膜を麻痺的に蝕む。ゲルニカの活動休止期とあって、メンバーの上野耕路もここに自作曲〈Prelude et Choral〉で参加している。このほか越美晴や立花ハジメなど、¥ENレーベルのミュージシャンが中心となって吹き込まれたこの企画盤では、大貫妙子はまだしも伊藤銀次の名前と楽曲がいかにも異色に感じられる。なお、伊藤銀次の誕生日は12月24日である。編曲の国本佳宏は、この前年にはサザンオールスターズの仕事をサポートをしている。
4.〈12月の祈り〉堀ちえみ(1983)
作詞・作曲/伊藤薫,編曲/鷺巣詩郎
鈴の音からはじまるアルバム《雪のコンチェルト》所収。Aパートの冒頭からの4小節におけるコード進行は、パッヘルベルの〈カノン〉のそれとほぼ完全に合致する。A面の最終曲に〈夕暮れ気分〉を配置したこのアルバムにおいて、B面の最終曲となるここでもやはり「街」は「夕暮れ」ていく。
5.〈CHRISTMAS TIME IN BLUE 聖なる夜に口笛吹いて〉佐野元春(1985)
作詞・作曲・編曲/佐野元春
世界中に存在する個人の誰にも平等に訪れ、去っていくもの、それは、もはや「Christmas」ではなく「Time」、すなわち時間である。そして彼らが、私たちの一人ひとりがどのような状態や状況にあろうとも、それが等しく到来し、通過していくことの残酷さは、時間が宗教にとって絶対的な外部であることの謂となるだろう。
6.〈MERRY X’MAS IN SUMMER〉KUWATA BAND(1986)
作詞/桑田佳祐,作曲・編曲/KUWATA BAND
桑田佳祐の場合にはいかにも典型的なコード進行だが、しかし作曲者の名義として登録されているのはあくまでもKUWATA BANDである。ここで導入されたレゲエのリズムがこれほどまでに歌謡曲になじんで聞こえるのは、たとえばAパートにおいて、本来はこもった丸い音でベースが爪弾くべき16分音符のフレーズを硬く乾いたエレキギターが、エレキギターでカッティングされるべき2拍と4拍の裏打ちの和音をキーボードが、役割りを入れ替えながらそれぞれ演奏してみせる仕方で、このジャンルの真正さをポップに換骨奪胎しているからかもしれない。
7.〈Miracle Play・天使が降る夜〉dip in the pool(1987)
作詞/甲田益也子,作曲・編曲/木村達司
バブル経済の絶頂期に消費文化の極楽へと聴くものを誘った天上の調べのもと、演目はあくまでも泡に映る奇蹟劇である。
8.〈CHRISTMAS TIME FOREVER〉サザンオールスターズ(1992)
作詞・作曲/桑田佳祐,編曲/小林武史&サザンオールスターズ
クリスマスを象る聴覚的な語彙を多くまとった、桑田式の定型的な楽曲。桑田佳祐の作曲の流儀として、原由子のコーラスが響く余地を高音部に確保するためにサビで主旋律を必ずしも最高音に浮揚させず、むしろ遠慮して不自然なまでに高揚を抑圧する傾向にあった。しかし原の産休を発端とするKUWATA BANDでの経験において、彼女の歌声を欠いたサビの高音部に余白が生じたためか、これ以降はサビに向けて主旋律の起伏は次第に上昇し、ついにはサビにおいて最高音に到達するような滑らかな音符の配置を厭わなくなる。これが通俗的な歌謡曲化といっそうの大衆化を彼の楽曲に印象づける要因のうち決定的なもののひとつとも考えられるが、たとえばこの楽曲での桑田の歌唱における裏声の使用を考慮すれば、このことは容易に理解されるだろう。その裏声は、いわば原由子の歌声の機能的な代行にほかならない。
9.〈angel song -イヴの鐘-〉the brilliant green(2000)
作詞/川瀬智子,作曲/奥田俊作,編曲/the brilliant green
ソロ・プロジェクトに顕著だったようにヴォーカルの川瀬智子に焦点を奪われがちなこのユニットの魅力が、やはり〈There will be love there -愛のある場所-〉や〈冷たい花〉など、SAYAKAのデビュー曲に提供した〈ever since〉を含めメロディ・メイカーとしての奥田俊作の才覚にあることは確実である。にもかかわらず、いまだ彼が良質の歌謡曲の旋律を書ける作曲者として正当な評価を獲得できていないことは、残念ながらそれ自体がこんにちの歌謡曲の限界の証左であり衰退の理由となるにちがいない。この10年後に発表された〈LIKE YESTERDAY〉もクリスマス向けの佳曲。
10.〈Can’t Wait ’Til Christmas〉宇多田ヒカル(2010)
作詞・作曲・編曲/宇多田ヒカル
シンプルな符割りの奇を衒わないメロディは口遊みやすく、歌詞の言葉を直截的に聴き手に届けてくる。クリシェの響きをともなうサビの旋律の跳ねかたが藤井フミヤの〈TRUE LOVE〉を参照させるなど、すっかり歌謡曲に囚われてしまったものと思しき宇多田ヒカルが、ただしこの楽曲で唯一、「いいんです」のフレーズについては、なぜかここだけに“です・ます”調を採用する。それゆえ妙によそよそしく感じられるその語句では、撥音のための音符が設けられず「E in the soup」のようにはしょって分節化されることから、「I’m already 」だの「 loving you」といった一節よりもいっそう唐突に、歌謡曲からの反発的な逸脱を意識させずにはいない。職業作詞家ならば、これをたとえば「いいのに」とでもしたことだろう。
番外_1.〈恋人がサンタクロース〉松任谷由実(1980)
作詞・作曲/松任谷由実,編曲/松任谷正隆
クリスマスに対して日本の市民が抱いてきた意識を刷新し、日本の社会におけるその意味を大きく転向させた契機となる記念碑的な楽曲。《SURF&SNOW》所収。
番外_2.〈クリスマス・イブ〉山下達郎(1983)
作詞・作曲・編曲/山下達郎
季節商品でありながらその年限りでシーズンで消費し尽くされることなく、例年この季節を迎えるごとに繰り返し倉庫から持ちだされ、飾られる「クリスマス・トゥリー」のように、歌謡曲における時事性のありようをあらためて概念形成しなおした記念碑的な楽曲。《Melodies》所収。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店






