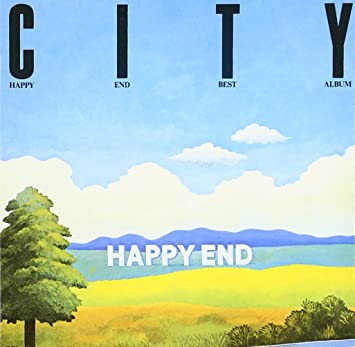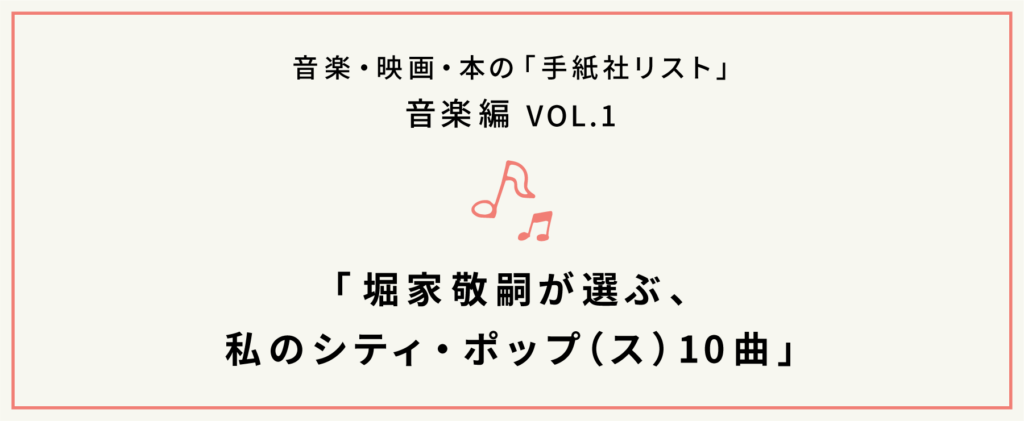
あなたの人生をきっと豊かにする手紙社リスト。5月号の音楽部門のテーマは、「シティ・ポップ(ス)」。“聴くべき10曲”を選ぶのは、手紙社の部員たちに向けて毎月「歌謡曲の向こう側」という講義を行ってくれている、山口大学教授の堀家敬嗣さんです。自身もかつてバンドマンとして活動し、幅広いジャンルの音楽に精通する堀家教授の講義、さあ始まります!
シティ・ポップとは何か?
“CITY POP/シティ・ポップ”
“シティ・ポップ”の語の響きを新鮮に感じる人たちがいます。その一方で、同窓会で旧友に再会したときのような、気恥ずかしくも懐かしい思いをそこに覚える人たちもいます。たとえば私がそうです。この、ほとんど40年にもなろうとするけっして短くない不在を隔てた再会は、互いの変貌に対する驚きをもたらすとともに、それでもなお、そこにかつての名残りをみつけた安堵で次第に満たされていきます。
Suchmosの成功によってこの語は再び日本のカルチャー・シーンの表層に浮揚しました。しかしそれに先んじて、韓国のDJにしてプロデューサーのNight Tempoが、1980年代前半を中心とした日本の大衆音楽をサンプリングし、またリミックスした作品を動画共有サイトYouTubeなどに発表したことから、その素材となった楽曲は世界に向けて“CITY POP”として紹介され、一部では熱狂的に支持されます。
誰であれ過去の音楽資源を素材として加工し、切り貼りすることが容易となったデジタル世代、そして誰であれそれを世界に向けて配信することが容易となったインターネット世代。こうした状況を前提に2010年ごろに実現したVaporwaveや、そこから派生したFuture Funkといった音楽文化の核心で、Night Tempoが素材として引用した楽曲には、かつてバブル期前夜の日本で“シティ・ポップス”と形容されていたものが多く含まれています。
かつての“シティ・ポップス”は、記憶のなかの相貌に素直には収まりきらない奇妙な郷愁とともに、“CITY POP”となり、さらにはこれを逆輸入するかたちで、いまや“シティ・ポップ”として響いてきます。
“シティ・ポップ”の語それ自体は、21世紀に入ってほどなく書籍のタイトルに用いられています(*1)。しかし、たとえば大貫妙子のアルバム《SUNSHOWER》や竹内まりやの〈PLASTIC LOVE〉、松原みきの〈真夜中のドア〉の再評価は、YouTubeの再生回数や外国語によるコメント数に大きく依存した話題であり、海外でこれらを発見した異国の眼ならぬ耳が、その今日的な価値を日本の聴衆にあらためて教えてくれたわけです。
“シティ・ミュージック”
はっぴいえんど界隈が“シティ・ポップス”の主要な源流であることを疑う余地はほとんどないでしょう。当時はっぴいえんどが所属していた音楽事務所「風都市」のネーミングは、はっぴいえんどのドラマーで作詞も担当していた松本隆のセンスの介入をうかがわせるものですが、さらにそのレコード原盤制作部門には「シティ・ミュージック」の名義が、ライブ・ブッキング部門には「ウィンド・コーポレーション」の名義が与えられています。
のちに松本自身が“風街”と呼ぶ彼の原風景、つまり高度経済成長期のただなかの1964年にオリンピック開催を控え、関連施設の建設や首都高速道路の整備にともない東京のかたちが大きく、急激に変容していくなかで、いかにもたやすく失われてしまったかつての首都の風景の幻、もしくは幻の風景、さしあたってここではそれが「風都市」とされたものと推察できます。
はっぴいえんどの公式の解散にあたり1973年に発表されたベスト・アルバムは、まさしく《CITY》の語を冠していますが、これに期をあわせて開催された解散ライブでもタイトルにこの語が共有されています。しかしそのライブは、単にこのバンドの功績を総括するのみならず、この時点でメンバーたちが各自で取り組んでいたさまざまな進行形のプロジェクトを紹介する、いわば新しい船出ともみなされるものでした。
ここで登壇したのは、細野晴臣と鈴木茂が参加し、のちにティン・パン・アレーとなるキャラメル・ママをはじめ、南佳孝や吉田美奈子、伊藤銀次や山下達郎、あるいは大貫妙子といった、都市的な音楽のありかたを模索するミュージシャンたちでした。ただし、はっぴいえんどを含め彼らの音楽は、歌謡曲やフォークに満たされた当時の聴衆を納得させるような大衆性を備えていなかったため、ただちには主流とならず、その市場規模は小さいままでした。
こうして彼らが模索してきた1970年代の、とりわけその後半の都市的な音楽が“シティ・ミュージック”であるとして、だからこれが“シティ・ポップス”となるには、尖ったその野心的な精神が希薄化するのは覚悟のうえで、彼らの試みの一滴が波紋を広げて大衆に届く必要がありました(*2)。
首都「TOKIO」
〈UFO〉による1978年の日本レコード大賞受賞を待っていたかのように、ピンク・レディー旋風が急速に衰えた一方で、1979年に竹内まりやの〈SEPTEMBER〉が、1980年には山下達郎の〈RIDE ON TIME〉がヒットします。さらに1981年には、松本隆の作詞による寺尾聰の〈ルビーの指環〉が爆発的なセールスを記録して日本レコード大賞を受賞し、また超ロング・セラーとなる大瀧詠一のアルバム《A LONG VACATION》が発表されるなど、かつての“シティ・ミュージック”はついに大衆の需要と合致するところとなり、この3年ほどの厚みのなかで“シティ・ポップス”化したものと考えられます。
それどころか、1980年代前半の日本の大衆音楽、つまり歌謡曲を含めた日本のポップ・ミュージックは、今度はその全体がこうした潮流にしたがって“シティ・ミュージック”化していきます。つまりバブル前夜の日本の大衆音楽とは、こういってよければ、多かれ少なかれ“シティ・ミュージック”的な様相を呈した“シティ・ポップス”であったわけです。
これにはおそらく、1980年に発売された〈TOKIO〉の歌詞で「欲しいなら何もかもその手にできるよA to Z」と謳われ、「奇跡をうみだすスーパー・シティー」と崇められた東京のかたちの肥大化と無縁ではないはずです。広告産業が煽る消費文化の象徴としての日本の首都は、ほかならない糸井重里によってここで「TOKIO」と表記され、またこれを沢田研二に「トキオ」と発音させています。のみならず、欲望のまま手に入れられる万物があらかじめ「A」から「Z」でラベリングされていることは、世界経済にとって日本の存在感がすでに無視できないものであることを示唆します。
〈TOKIO〉にわずかに先行して、細野晴臣の率いるYMOが1979年に発表した〈TECHNOPOLIS〉でも、ヴォコーダーで加工された「トキオ」のフレーズを冒頭から聴くことができます。シンセサイザーの電子音が近未来的な響きを編んで技術都市としての東京像を構築するこの楽曲は、1980年以降の日本の姿を予感させる“シティ・ミュージック”であるとともに、YMOの海外ツアーでの紹介をとおして“CITY POP”の先駆となり、その成功に箔づけられ逆輸入された“シティ・ポップ”のもっとも早い事例といえるかもしれません。
“シティ・ポップス”
“シティ・ポップス”のサウンドについては、テンション・コードの使用やリズム・ギターにおける16ビートのカッティング奏法、エレクトリック・ピアノによる音場の作りかたなど、さまざまな局面に関して、クロス・オーヴァーやフュージョン、あるいはA.O.R.やブラック・コンテンポラリーといった、1970年代後半に流行していた洋楽の影響がしばしば指摘されてきました(*3)。 ジャズやラテン、ロックやソウル/ファンクなど、既存の音楽ジャンルが越境しあい、交錯ないし融合していくなかで、“シティ・ミュージック”もそれらを取り込み、また歌謡曲も“シティ・ミュージック”を消化する過程でこれらになじんでいったわけです。“CITY POP”に対する昨今の世界的な評価もまた、こうした傾向に大きく動機づけられたものであるはずです。
既成のジャンルの垣根を越えて交錯し、融合する音楽は、まさしく巨大都市の様態そのものです。とはいえ、そうした交錯や融合は、あるカテゴリーの固有性を曖昧にします。逆にいえば、ジャンルを特徴づけるサウンド的な純正さの希薄化こそが、“シティ・ポップス”の特徴であるとも考えられます。“シティ・ポップス”の音とは、だから同時代の流行との関係のなかで相対的に実現されたものであって、そこに都市の響きを聴いてしまうことの恣意性には留意が必要です(*4)。
1980年代前半には日本の大衆音楽の全体を覆うまでに広がった“シティ・ミュージック”の一滴からの同心円状の波紋、それが“シティ・ポップス”であるとすれば、この語の定義としてもっとも腑に落ちるのは、結局のところ“シティ・ミュージック”をめぐる属人的なものでしょう。つまり、かつて「風都市」周辺に集ったミュージシャンたちの固有名を、1980年代前半についてもなお羅列してみることこそが、都市生活者による都市生活者のための局所的な音楽だった“シティ・ミュージック”が敷衍され、その一般化したありさまとなる“シティ・ポップス”の性質を端的に表現するための、おそらくはもっとも有効な手段です。
実際、寺尾聰や松田聖子、近藤真彦や薬師丸ひろ子をはじめ、売れっ子作詞家となった松本隆が歌詞を提供した歌い手たちの楽曲が当時のヒット・チャートにはひっきりなしにランク・インし、上位を独占することも珍しくありませんでした。大瀧詠一や山下達郎、細野晴臣や南佳孝らは、そうした楽曲の作曲者として招かれ、ついには“シティ・ミュージック”の一滴は、1982年が暮れるのを待たず〈冬のリヴィエラ〉によって演歌にまで波及するに至ります。
都市という主題
1980年代に入り日本の大衆音楽の全体に波及した“シティ・ミュージック”は、それがこの同心円状の波紋のために滴った最初の雫である限りにおいて、まさしく日本の大衆音楽の中心となったのです。そうした“シティ・ポップス”の構成要素にあって、都市とのつながりをもっとも率直に吐露するもの、おそらくそれは歌詞の言葉でしょう。
日本の大衆音楽の歌詞のなかに[都市]の語それ自体の字面を確認する機会は多くはありませんが、それは、この語が担ってしまう行政区分的な堅苦しさや冷淡さを忌避するためであるほか、空間的な概念であるにもかかわらず時間的な概念である[年/歳]と同音であり、聴覚的に区別しづらいこともその理由かもしれません。[都市]と[年/歳]とでは抑揚が異なるとはいえ、大衆音楽の歌詞にあっては語そのものよりも旋律の抑揚のほうが優先され、ときに[都市]の語が[年/歳]の抑揚で、また[年/歳]の語が[都市]の抑揚で歌われかねないからです。
そうした観点からも、「街のはずれ」から「防波堤ごしに緋色の帆を掲げた都市」を見るはっぴいえんどの〈風をあつめて〉(1971)は興味深い楽曲です。
「都市」の語それ自体の使用はともかく、日本の大衆音楽にとって都市という主題はさほど新鮮なものではありません。高度経済成長期の東京の変貌を待つまでもなく、さまざまな都市的な記号をもって歌詞はそれを表現してきました。
たとえば西條八十の歌詞による〈東京行進曲〉(1929)では、都市生活者は「ジャズで踊」り、「リキュルで更」け、「あけりゃダンサー」が泣き、「恋の丸ビル」あたりでは「ラッシュアワー」に巻き込まれます。そんな「広い東京」のなか、「あなた地下鉄」「私はバス」で、「いきな浅草」で「忍び逢」います。「シネマ」や「お茶」のあと、「いっそ小田急で逃げ」たくもなる「新宿」の彼らの頭上では、「月」が「デパートの屋根に出」ています。
ジャズやリキュールの流行を含め映画鑑賞や喫茶などの文化習慣や、地下鉄やバス、小田急といった交通手段、さらには丸ビルやデパートなど建築物に至るまで、当時の最先端の事物の列挙が、いまから一世紀前の東京がすでに消費社会であったことを教えてくれます。そしてその新しさは、「銀座の柳」や「武蔵野の月」など、「昔」と変わらない自然との対比のなかで強調されます。加えて、ラッシュアワーとは、東京が匿名者の密集する猥雑な都市となったことの表象です。これらが都市生活者にもたらした最新の行動様式を含め、絶えず変化していく街の風景こそが、東京を東京たらしめるものと謳われているわけです。
都市の主題
[都市]の語よりはむしろ[都会]の語を用いることが圧倒的に多い日本の大衆音楽の歌詞は、ときとしてこれを[まち]と読ませもします。したがって、日本語としては[都市]のほか[都会]や[街]の語が、[city]の訳語に充てられる資格を有しているものと考えられます。
けれど同じ[まち]の音韻を表記するにも、[町]の文字には構成部位として[田]の文字が組み込まれており、またやはり行政区分における市町村の序列にしたがえば、都市の内側にある一部分としてのより細かな集住の単位、もしくは都市の外側にある大部分としてのより鄙びた集住の単位とみなされることから、そこでは[city]の語感は著しく損なわれます。
井上陽水の〈傘がない〉(1973)は、「都会」を「新聞」や「テレビ」が表象する絵空事のように捉え、むしろ「僕」の「問題は今日の雨」のなか「君の町に行」くための「傘がない」ことだと主張します。ここでは「町」の語は、メディアをとおして創出された虚像としての「都会」との対置をとおして、「目の中に降」り「心に沁み」る「冷たい雨」によって身体が感覚できる等身大の空間の規模を象っています。
とはいえ、雨は都会にも降ります。それどころか、日本の大衆音楽にとって、雨こそは都会を、とりわけその夜を彩るもっとも魅力的な道具立てであるとさえいえます。
最先端の輝く都市に群れ集い、互いに見知るもののほとんどいないまま交錯する夥しい数の人びとは、夜の闇にまぎれてその匿名性の度合いをいよいよ高め、また電化された街の光は都市の横顔をなおさら煌びやかなものとします。高度経済成長期やバブル期はもちろん、いまなお日本の首都として東京は変化の最先端で自らを更新しつづけ、輝きつづけています。
交錯する誰であれ、匿名性のなかに埋没せずにはいない都市の夜に、彼らを誘うように怪しく煌めく人工光は、灰色に沈みがちな昼間の都会とはまったく異なる相貌のもと、都市生活者の誰もが焦がれる魅惑を放って止みません。ビルの窓灯りや街灯が規則的に並ぶなかを自動車の前照灯や尾灯が近づき、遠ざかり、店先のネオン管は毒気ある光をぎらつかせています。夜の闇を照らし立体化させるさまざまな人工光が、眠れぬ都市を息づかせ、活気づけます。
雨は、路面を濡らしてこれを鏡面に変え、夜の都市の輝きを反映し倍増させます。そのとき、すべての都市生活者は万華鏡を覗き込む視線を獲得するとともに、その万華鏡のなかに閉じ込められて瞬く都市の剥片でもあるわけです。
こうしたことから、夜の、とりわけ雨の光沢に覆われた夜の街の佇まいは、都市を謳う大衆音楽の歌詞に重用されていきます。逆にいえば、そこで謳われる都市像とは、雨の潤いによってその魅力を文字どおり水増しされた幻影なのです。
都市の夜の潤い
そのような光景は、松本隆がプロデュースし、ほとんどを作詞した南佳孝の1stアルバム《摩天楼のヒロイン》(1973)にもすでに認められます。
このタイトルが標榜するように、まさに〈東京行進曲〉に歌われたころの「シネマ」、つまり1930年代のワーナー・ブラザーズ製作のギャング映画やRKO製作のミュージカル映画などをイメージの源泉として、日本語によるその都市像の再構築がここでは試みられています。そしてジャズやレゲエをはじめ多彩な洋楽的素養をもって奏でられる音楽に若き南の艶やかな歌声が乗るとき、洋画というよりはむしろ同年代の小津安二郎の映画作品、たとえば『朗かに歩め』(1930)や『非常線の女』(1933)のようなバタくさい邦画をいま観るときのあの空間と時間の錯誤の感覚に、またしても私たちは囚われ、幻惑され、眩暈とともに陶酔します。
とりわけ〈夜霧のハイウェイ〉では、「踏みこむアクセル」に「飛び散る夜霧」によって「水銀灯が煌め」き、「オレンヂの星雲」となります。
伊藤銀次の〈こぬか雨〉(1977)では、フェンダー・ローズのエレクトリック・ピアノによる揺らぐ分散和音がイントロの音場を支配しています。これは、「街に今日も霧がふる」と歌われる、目視できないほど微細な蒸気が遍在した都市の夜の光景を音響的に表現するものと理解できます。「ヘッドライトがまたたく」この「くすんだアスファルトの海」には、やがて静かにホーン・セクションが浸透してきて、いずれ鬱陶しく足もとを濡らし、まとわりつきます。
杉真理&レッド・ストライプスによる〈青梅街道〉(1978)では、夜の都市の湿潤はより緊密に「二人」を囲う卑近なものとなります。「すれちがうヘッドライト」が「二人を照らしてく」のは、ほかならない東京の「夜の青梅街道」での出来事ですが、ただしそこでは湿気は、彼らの乗った自動車の前照灯が照らす車外の雨粒のものではなく、あくまでも他の自動車から照らされる彼らの車内に充溢する蒸気の結露したものです。というのも「あの娘は窓ガラスに誰かの名前書いては消してた」からです。
「青梅街道」の語句はこうした情景の現実感を担保する具体性を提示しますが、他方では本来[お/う/め/か/い/ど/う]の7音節で等時拍音的に区切らる日本語が、ここでは4つの音符に配分され、「おぅ/め/かぃ/どぅ」の4音節へと分節化しなおされることによって、実在の街道がわずかばかり地面から浮遊し、具体性の領土にあった現実感を揺さぶります。その限りにおいて、なるほどあれは、「きっと幻だった」のかもしれません。
歌謡曲
“シティ・ミュージック”の大衆化は、しばしばそれが視覚的な舞台設定に援用してきた[都市-夜-雨]という主題の系列を、ひとつの定型的な様式にまで昇華させます。“シティ・ポップス”の担い手として登場した稲垣潤一の製作陣は、彼のデビューを準備する段階で、その声質もあいまってあらかじめ都会・夜・雨をコンセプトに楽曲制作を方向づけていたといいます(*5)。
稲垣の1stアルバム《246:3AM》(1982)の表題は国道246号線の午前3時を意味しますが、それは、この盤に収録された楽曲が青山通りに喩えられる洒落た都心の夜を舞台に想定して作られていることの告白であると同時に、それらが聴かれるべき理想的な状況を示唆しています。また、ここに収録された彼のデビュー曲〈雨のリグレット〉では、「乾いた交換の声」の冷徹さを湿らせるように「しのび雨」が降ります。
要するに、すでにそこでは、[都市-夜-雨]という主題の系列は、“シティ・ミュージック”を大衆の需要に応じて生産するためのひとつの鋳型とみなされ、確実に機能していたわけです。 たとえそれが白夜であったとしても、すべての都市に夜は訪れます。しかし、ニュー・ヨークであれロサンゼルスであれ、あるいはロンドンであれ、“シティ・ミュージック”が追いかけた音楽の発信地のなかで、東京ほど降雨量が多く湿気った都市はありません。
“シティ・ポップス”とは、“シティ・ミュージック”の一滴が、そこに凝縮された野心的な精神の希薄化も疎まず郊外に向けて同心円状に拡散しながら、ついに大衆の鼓膜を振動させるに至った波紋のことでした。いいかえれば、それは“シティ・ミュージック”の揮発して都市の夜に満遍なく充溢する蒸気、聴き手の鼓膜にまといつくその湿気にほかなりません。
こうした湿潤さは、かつて“シティ・ミュージック”が軽蔑し、長らく敵視してきた歌謡曲のものでした。歌謡曲にはしばしば[泣き]のメロディが組み込まれます。聴衆を泣かせるメロディではなく、メロディ自体が泣くのです。 また、松本隆は、はっぴいえんどの試みが日本の大衆音楽からそのような水分を除湿することにあったものの、実際にはこれが大瀧詠一の声によって適度に保湿され、その潤いがいまなおはっぴいえんどの楽曲を枯らすことなく普遍化しているところと推察しています(*6)。とはいえ、彼の“風街”を体現する象徴的な逸話が霞町の消失であったことは、この作詞家が綴る言葉における飽和水蒸気量の指標となるはずです(*7)。
日本の大衆音楽にはいたるところ湿気がまとわりつきます。アメリカの西海岸のような乾いた空気にあっては音源から無媒介的に到達し、明瞭な輪郭を画す振動は、微細な水の粒子を高い密度で孕んだ東京の空気にあっては、遍在するそれら粒子との衝突を繰り返しつつ、いわば蒸気のフィルターに濾されてしっとりと潤い、輪郭を滲ませながら浸透してきます。
“シティ・ポップ(ス)”
東京では音楽は、望むと望まずとにかかわらず、あらかじめそうした湿気を帯びるエフェクターをその響きに介入させていることになります。特に高音の伝達について、遅延が生じるなど影響がみられがちだとの指摘もあります(*8)。
いずれにしても、“シティ・ミュージック”が払拭するにしきれなかった湿気を、“シティ・ポップス”はわかりやすい鋳型としてむしろ積極的に採用します。“シティ・ポップス”とは、だから歌謡曲化した“シティ・ミュージック”であるとも考えられます。風の伊勢正三やクラフトの濱田金吾など、フォーク系のシンガー・ソングライターがのちに“シティ・ポップス”へと移行していったのは、彼らの音楽が内包する湿気ゆえの親和性があったからかもしれません。
都市のただなかに滴った“シティ・ミュージック”の雫は、これが郊外に向けて都会的な性質の波紋を広げていく過程で、吸湿しながらその洗練された精神を希薄化していきます。仮に、大滝詠一の《A LONG VACATION》が“シティ・ポップス”であるとすれば、それは、海辺で愉しむリゾートが、こうした過程で都市生活者の行動様式に組み込まれていくからです。“シティ・ポップス”のアルバムのジャケットに海辺の景色が頻出するのも、おそらくこうした理由によります(*9)。
“シティ・ミュージック”の歌謡曲化とは、すなわち、湿気を帯び、それに浸されて“シティ・ミュージック”がふやけることです。大衆化し、湿気にふやけた“シティ・ミュージック”は、“シティ・ポップス”として1980年代の日本の大衆音楽を彩ります。
しかし、都市の大衆音楽どころか日本の大衆音楽、要するに“J-POP”へと泡のようにふやけすぎたそれが、21世紀に入りYouTubeをとおして“CITY POP”となって海外の聴衆に届くとき、そこではふたつの仕方で再除湿が施されることになります。ひとつは、Future Funkにおけるその受容にみられるように、ある種の懐古的なパロディとみなして湿気が撥ねられる仕方です。もうひとつは、かつて“シティ・ミュージック”が憧れ、本場ではすでに廃れてしまった洋楽の幻影を透かすような、乾いた輪郭の楽曲だけを選別する仕方です。
そうして再除湿され、“シティ・ポップス”は“シティ・ポップ”に生成します。そしてここで隠蔽された(ス)こそは、ほかならない東京の、日本の都市の湿潤なのです。
*1 木村ユタカ/監修,『ジャパニーズ・シティ・ポップ』, シンコーミュージック, 2002.
*2 「東京人 特集:シティ・ポップが生まれたまち」4月号, 都市出版, 2021, p.31.
*3 高護,『歌謡曲』, 岩波書店, 2011, p.181.
*4 村田健人,「シティ・ポップ卒論 ③「”都会的”をめぐる恣意性」」(https://note.com/kentomuratacom/n/n3cc571a5fedc), 2019.
*5 「昭和40年男 特集:俺たちシティポップ世代」2月号, クレタパブリッシング, 2014, p.30.
*6 「東京人」, p.20.
*7 松本隆, 『風のくわるてつと』, 立東舎(立東舎文庫), 2016, p.140.
*8 川瀬泰雄ほか,『ニッポンの編曲家』, DU BOOKS, 2016,p.145.
*9 モーリッツ・ソメ,「ポピュラー音楽のジャンル概念 における間メディア性と言説的構築― 『ジャパニーズ・シティ・ポップ』を事例に― 」,『阪大音楽学報』 16・17号合併号所収, 加藤賢/訳, 大阪大学音楽学研究室, 2020, pp.19-20.
堀家教授のシティ・ポップ(ス)10選
1.〈眠れぬ夜の小夜曲〉南佳孝(1973)
作詞/南佳孝(補作詞/松本隆),作曲/南佳孝,編曲/松本隆・矢野誠
収録されたほとんどの楽曲で作詞を担当し、うち数曲ではドラムも叩いている松本隆による初プロデュース作品にして南の1stアルバムとなる《摩天楼のヒロイン》所収。日本の大衆音楽にレゲエのリズムが導入されたきわめて初期の事例としても記憶されるべき、小気味よくも優しく美しいプロポーズ・ソング。前年に大ヒットし、フォークを大衆化した吉田拓郎の〈結婚しようよ〉との対照から、南における都市的な音楽の理想が浮き上がる。1930年代のWBのギャング映画やRKOのミュージカル映画をイメージ・ソースとして日本語に落とし込み、謳われる虚構の都市の物語にあって、この楽曲は、まさに1930年代の小津安二郎の映画のように、懐かしくも奇妙な空間的・時間的な錯誤への幻惑と眩暈を感じさせる。
2.〈ピンク・シャドウ〉ブレッド&バター(1974)
作詞・作曲/岩沢幸矢・岩沢二弓,編曲/岩沢二弓
加山雄三と桑田佳祐のあいだを埋めるように湘南サウンドを展開した兄弟デュオの、細野晴臣や鈴木茂らのサポートによる2ndアルバム《Barbecue》に所収。穏やかな茅ヶ崎の空気感に満ち、レイドバックやチル・アウトの語感にふさわしい彼らの音楽は、“シティ・ミュージック”というよりはむしろシティとリゾートの関係のなかで捕捉されるべき性格のものだが、その資質がもっとも都市に接近したこの楽曲の場合には、洗練され尽くさない垢抜けなさの適度なバランスが心地いい。山下達郎による忙しなくもより都会的な、ライブ収録のものとは信じがたいほどの完成度のカヴァー・ヴァージョンがある。筒美京平の作曲による1969年のデビュー盤のB面〈白いハイウェイ〉も、“シティ・ミュージック”にさきがけてむしろ高原リゾートの側に振れた名作。
3.〈雨は手のひらにいっぱい〉シュガー・ベイブ(1975)
作詞・作曲・編曲/山下達郎
単に“シティ・ポップス”のみならず日本の大衆音楽にとって記念碑的なシュガー・ベイブ唯一のアルバム《SONGS》所収。メンバーの上原裕と寺尾次郎がレコーディングに参加し、前年にヒットした山本コウタローとウィークエンドの〈岬めぐり〉では、「街に帰」ることを前提として旅先を走った「バス」が、ここでは「僕」を置いて「走り去」り、あたりを「行くあてもない街」に変える。天気雨のような山下達郎の乾いた「雨」を相応に湿らせているのは、プロデューサー大瀧詠一の提案による音の壁。ナイアガラ瀑布の「はね上がる」飛沫をまとって「街」は潤い、息づく。
4.〈中央フリーウェイ〉荒井由実(1976)
作詞・作曲/荒井由実,編曲/松任谷正隆
荒井由実名義による4枚目にして最後のアルバムとなる《14番目の月》に所収。フェンダー・ローズのエレピによる和音の揺らぎの2拍ごとの上昇からはじまるこの楽曲は、ここから松任谷正隆による彼女のプロデュースが開幕することの宣言となる。実在する地名を歌詞に織り込むことには、その楽曲の民謡的な土着歌謡化、いわゆるご当地ソング化の懸念がつきまとうが、ここでは「調布基地」を利用して「この道」を「滑走路」に見立てたうえで、そのバタくささを借りて中央自動車道を「中央フリーウェイ」と外連味なく変換するなど、彼女の鋭敏な言語感覚にもとづく巧みなイメージ操作がきわだつ。同じアルバムの収録曲〈天気雨〉においても、「ゴッデス」「茅ヶ崎」といった固有名詞の系列では、歌詞世界のリアリティと引き換えに楽曲が背負わずにはいない日常性の質があらかじめ入念に選別され、また都市の気配に呑み込まれ近隣の郊外が都会化していくなか、「相模線」の響きさえが「白いハウス」の語句をもって脱色される。
5.〈風になれるなら〉伊藤銀次(1977)
作詞/伊藤銀次・大貫妙子,作曲・編曲/伊藤銀次
短期間ながらシュガー・ベイブにも在籍し、松原みきのバック・バンドや佐野元春のプロデュースで活躍するなど、“シティ・ポップス”の主流を支えてきた伊藤の1st ソロ・アルバム《DEADLY DRIVE》所収。大瀧詠一・山下達郎とのユニットによる《ナイアガラ・トライアングル Vol.1》の経験を経て発表されたこのアルバムは、彼の音楽的な興味の雑多さをうかがわせるものだが、シングル・カットを前提にしたこの楽曲は冒頭のストリングスの重厚さにもかかわらず軽やかである。Aパートでは奇数拍のオモテで開かれていたハイハットがA’パートでは偶数拍のウラで開いて疾走感を演出し、空気のような大貫妙子の声の多層状の塊がまとわりつき、「風」になる。同じアルバムに収録された〈こぬか雨〉もまた必聴。
6.〈レイニー・ステイション〉鈴木茂(1978)
作詞/松本隆,作曲・編曲/鈴木茂
サウンド面でいえば、はっぴいえんどの4人のなかでもっとも“シティ・ミュージック”に近しかったのは鈴木茂だろう。個人名義では3rdアルバムとなる《Caution!》所収。日本屈指のギタリストとしてロックからフュージョンに至る潮流を探究する一方で、単なる奏者の位置に収まらず、キャッチーなメロディを作り、それをきわだたせるアレンジを施し、自らこれを歌唱するためのひとつの構成要素としてギターの音を有機的に組み立てる稀有な存在だからこそ、彼のディスコグラフィには名曲が多く、それらは山下達郎や小坂忠など、しばしば他の“シティ・ミュージック”の偉大な歌い手たちにもカヴァーされる。しかしそれら鈴木の代表曲とは異なり、この爽やかな楽曲の魅力は、“シティ・ミュージック”の一滴が大衆に波及する以前に、すでに彼なりの“シティ・ポップス”を象っていることにある。この楽曲にも角松敏生のカヴァー・ヴァージョンがあるが、そちらはいかにも空疎に響く。
7.〈青梅街道〉杉真理&レッド・ストライプス(1978) 作詞・作曲/杉真理,編曲/杉真理&レッド・ストライプス
のちに佐野元春とともに大瀧詠一の《ナイアガラ・トライアングル Vol.2》に参加することになる杉の、名実ともにソロ・デビューする以前のプロジェクトによる2ndアルバム《SWINGY》に所収。フェンダー・ローズのエレピによる揺らぐアルペジオがイントロの音場を支配し、目視できないほど微細な蒸気の充溢した都市の夜の光景を表現する試みは、伊藤銀次が「街に今日も霧がふる」と歌う〈こぬか雨〉にも共通する問題意識だが、そこではエレピも弾く坂本龍一のアレンジになるホーンが鬱陶しく足もとを浸してくるのに対して、ここではエレキギターの全面的な関与が「あの夜見た街」の輪郭を縁どり、バンド名義で発表された本作の意義を強調する。本来、日本語では「お/う/め/か/い/ど/う」の7音節で等時拍音的に区切らる「青梅街道」を、「おぅ/め/かぃ/どぅ」の4音節へと分節化しなおし、4つの音符に乗せることで、実在の街道はわずかばかり地面から浮遊し、「きっと幻だった」ものと嘯かれる。
8.〈蜃気楼の街〉大貫妙子(1980)
作詞・作曲/大貫妙子,編曲/加藤和彦
シュガー・ベイブ時代に《SONGS》に提供した同曲の、ソロによる4thアルバム《romantique》でのカヴァー・ヴァージョン。怯えつつも希望に満ちた、若さにひりひりする感覚の初出の録音とは異なり、加藤和彦によるボサ・ノヴァ調のアレンジが施されたここでは、いわば“シティ・ミュージック”の尖った姿勢が、いまなお「あての無い街」のかたちはつかめないながら、時代の支持による余裕とともに丸くポップになっていることが聴いてとれる。この両ヴァージョンのあいだにみられる相違こそが、おそらく“シティ・ミュージック”を“シティ・ポップス”から隔てるものであろうが、たとえばこれに先立つアルバム《MIGNONNE》に収録された〈あこがれ〉をはさみ、その前後に〈蜃気楼の街〉の両ヴァージョンを配置してみれば、「私」のみならず「街」それ自体が両ヴァージョンのあいだで成長しているようにも思えてくる。今回のリストでは大貫のソロ・ヴァージョンを挙げたが、個人的にはイントロのコーラスの4音目でのシンコペーションが刺さる初出のヴァージョンを推す。
9.〈雨のリグレット〉稲垣潤一(1982)
作詞/湯川れい子,作曲/松尾一彦,編曲/井上鑑
自作自演ではないにもかかわらず、“シティ・ポップス”を体現するもっとも典型的な歌い手のひとりと評価すべき稲垣のデビュー曲であり、その1stアルバム《246:3AM》に所収。午前3時の国道246号線、つまり深夜の青山通りを表題に掲げている事実が率直に示すように、彼の登場は“シティ・ポップス”の主題を明瞭に意識して企図されたものであった。とりわけその歌声は、都会の雨の夜に適合するウェットな質として制作サイドに価値づけられていたといい、筒美京平による〈夏のクラクション〉や大瀧詠一による〈バチェラー・ガール〉など、コンセプトの明確さと豪華な作曲陣の採用ゆえに佳曲も多い。だが、オフコースの松尾一彦が作曲し、井上鑑によって仕立てられたこのデビュー曲にこそ、大衆のものとなった“シティ・ポップス”のまろやかな真髄を聴くことができる。
10.〈頬に夜の灯〉吉田美奈子(1982)
作詞・作曲・編曲/吉田美奈子
エレキギターの軽やかなカッティングやミュートの効いた単音のリフ、エレピによる長音の和音、歯切れのいいベースと冷静なドラム、艶やかなホーンと抑制の利いたストリングスなど、演奏されるすべての音が、ここでは深さや太さよりも透明度をもってきわだつ吉田の繊細な声を煌めかせ、キャッチーなメロディを輝かせる。どこをとっても“シティ・ポップス”の本領といっていい傑作。《LIGHT’N UP》所収。
番外_1.〈或る夜の出来事〉松本伊代(1982)
作詞/康珍化,作曲/亀井登志夫,編曲/鷺巣詩郎
単に売れっ子の新人によるアイドル歌謡にまで“シティ・ポップス”が波及したのみならず、それが十分に熟成し、確実に消化されたことの証左として傾聴されるべき佳曲として、番外で紹介しておきたい。ボサ・ノヴァ調のおとなびたリズムに負けず、松本の歌声は夜に潤う都会的な気怠さを奏でてみせる。2ndアルバム《サムシングI•Y•O》所収。
番外_2.〈Endless Nights〉OFF COURSE(1985)
作詞/Randy Goodrum ,作曲/Kazumasa Oda,編曲/Peter Wolf & OFF COURSE
全曲が英語詞によるアルバム《Back Streets of Tokyo》所収。この楽曲も英語詞のため番外としたが、ヴォーカルを除き共通のトラックを使用している日本語詞ヴァージョンが〈たそがれ〉として発表されている。そこでは“シティ・ポップス”の印象が希薄な一方で、英語詞ヴァージョンではそれがむしろ濃密に漂う。テレビ出演を拒否し、メディアによる大衆化を徹底的に疎んだオフコースの音楽が、英語詞の採用によって自ら“CITY POP”になろうとしたせいかもしれない。しかしここでは東京は、「TOKIO」ではなくあくまでも「Tokyo」だ。一見それは海外の視点から省みられたバブル前夜の東京の裏通りであるかのようで、実のところすべての記憶が消失し、行き交う誰もが見知らぬ他人となり、なにもかも現実のこととは思えないような、いわば東京としてありえたもうひとつの可能的な光景である。このアルバムのジャケットに描かれた地図にも、大通りが国道246号線ならぬ「Route642」と記されており、ここで歌われる情景が東京に似た架空の都市のもの、もしくはもうひとつの東京の可能的なかたちであることを示唆している。

文:堀家敬嗣(山口大学国際総合科学部教授)
興味の中心は「湘南」。大学入学のため上京し、のちの手紙社社長と出会って35年。そのころから転々と「湘南」各地に居住。職に就き、いったん「湘南」を離れるも、なぜか手紙社設立と機を合わせるように、再び「湘南」に。以後、時代をさきどる二拠点生活に突入。いつもイメージの正体について思案中。

 手紙舎 つつじヶ丘本店
手紙舎 つつじヶ丘本店
 手紙舎 2nd STORY
手紙舎 2nd STORY
 TEGAMISHA BOOKSTORE
TEGAMISHA BOOKSTORE
 TEGAMISHA BREWERY
TEGAMISHA BREWERY
 手紙舎 文箱
手紙舎 文箱
 手紙舎前橋店
手紙舎前橋店
 手紙舎 台湾店
手紙舎 台湾店